04/18
新社会人向け書籍特集

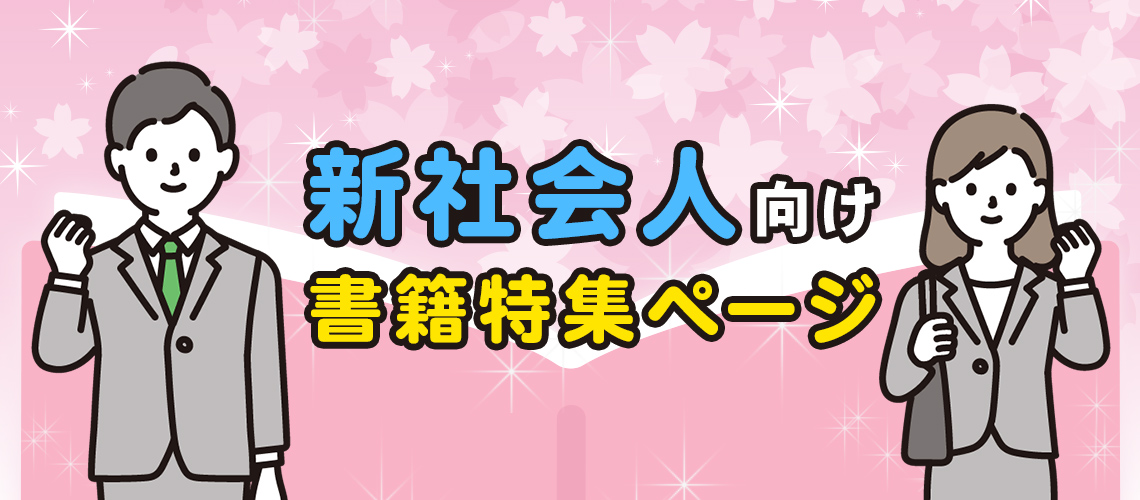
この春からの,新社会人・若手技術者のために,おすすめ書籍をリストアップいたしました。
カテゴリを選択してからカテゴリ下の書籍一覧を参照ください。
※各書名をクリックすると,目次や立ち読みページなど,詳細な情報がご覧いただけます。
- 共通(技術文章・プレゼンテーション・技術英語・特許関連など)
- 統計(クリギング・R・ベイズなど)
- 経営・管理工学(信頼性・リスク・安全・生産、品質管理・人間工学など)
- 電気電子工学(電力・通信・電子回路)
- 情報工学(セキュリティ・機械学習・データサイエンス・Julia・MATLAB・Python・基本情報など)
- マルチメディア(音響・信号処理・ゲーム・CG・映像・アニメーション・可視化・パターン認識・VRなど)
- モビリティ(サービス・自動運転・ドローン・モデルベース・電気鉄道など)
- ロボット
- 機械工学(塑性加工・腐食防食・CAE・振動・技術士・CFRTP・材料・設計など)
- 計量・計測・制御
- 土木・建築工学(モニタリング技術・建築形態の生成分析・空間経済分析・防災工学・多変量解析・コンクリート構造物設計)
- 環境・エネルギー工学(SDGs・サステイナブル・再生可能エネルギー・原子力・石油資源など)
- 化学工学(FRP・腐食防食・化学物質・分析化学など)
共通(技術文章・プレゼンテーション・技術英語・特許関連など)
- 詳細を見る
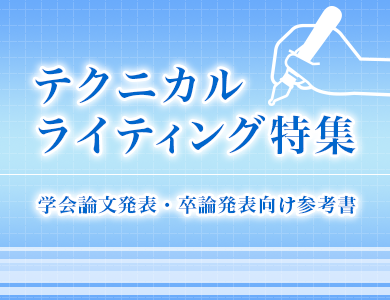
テクニカルライティング特集ページ
詳細を見る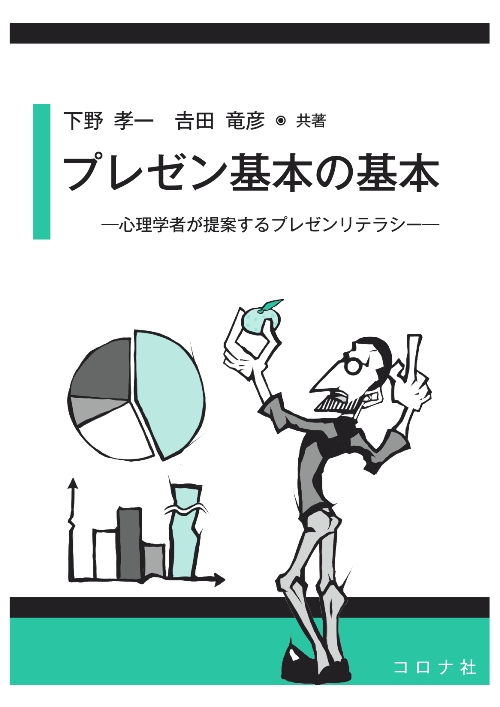
プレゼン基本の基本
詳細を見る
- 心理学者が提案するプレゼンリテラシー -プレゼンの効率的なやり方・具体的な事例に加えて,基本的な考え方:プレゼンリテラシーを解説する。心理学的背景に基づいて各プレゼン技術の「理由」を示すことにより,読者が良いプレゼンを行うための基礎をしっかり固める。
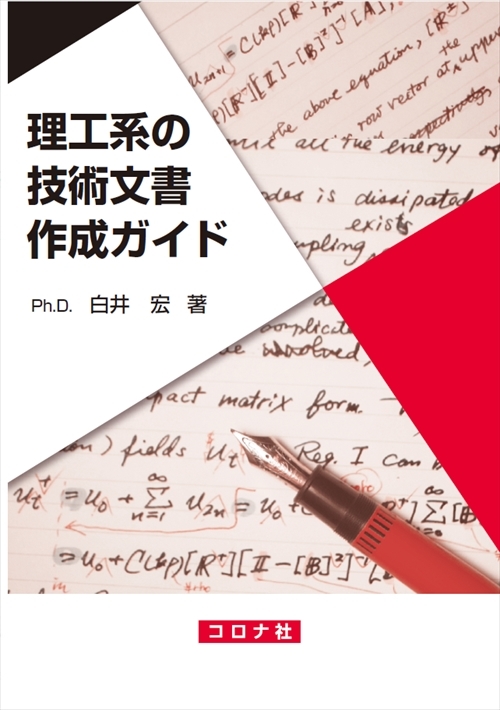
理工系の技術文書作成ガイド
詳細を見る誰が読んでも間違いなく同じ結論に達するためには,どのように技術文書をまとめればよいか。理工系の学生が悩む技術文書や技術論文,実験レポートの論理的な書きかたに,発表のしかたを含めて丁寧にまとめた。
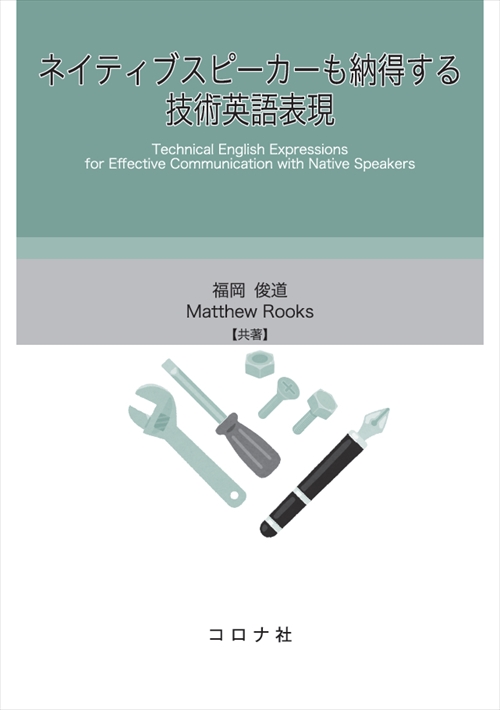
ネイティブスピーカーも納得する技術英語表現
詳細を見る本書では「英語表現の上達にはネイティブスピーカーの文章をまねるのが一番」との考えの下,初級~中級・上級レベルまでのさまざまな英語表現を含む例文を多数収録。今よりワンランク上の技術英語を書きたい方の支援ツールとなる。
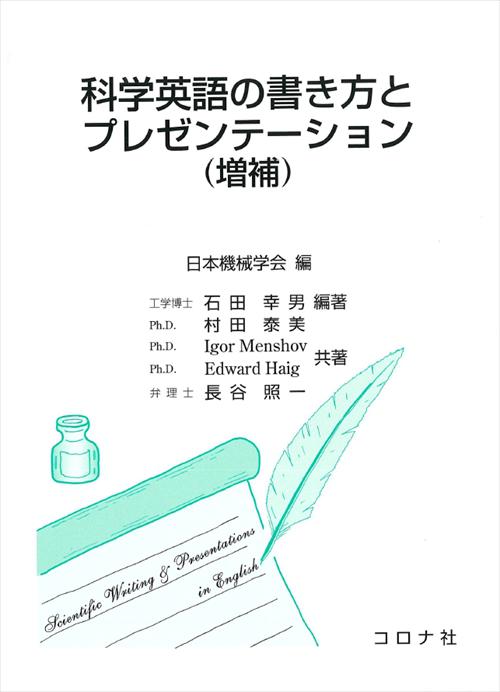
科学英語の書き方とプレゼンテーション (増補)
詳細を見る科学英語を用いて行うプレゼンテーションや論文等の書類作成の方法を,基礎から実践まで具体的な例を用いて平易に解説。増補にあたって,日本機械学会誌2017年1~12月号にかけて連載された「機械屋英語のあれこれ」を追記した。
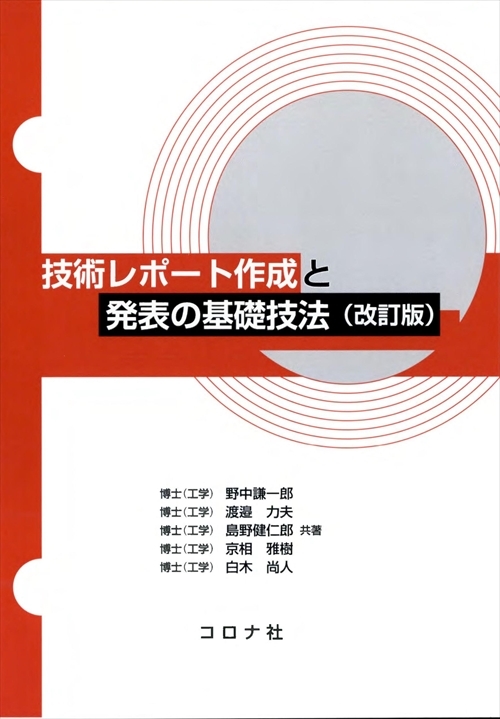
技術レポート作成と発表の基礎技法 (改訂版)
詳細を見るまず,データ処理の方法を説明し,続いて技術レポートの文体・構成・論理的な考察の方法を述べた。最後に,ルーブリック評価を導入したプレゼンテーションの方法をまとめた。単位や数量の表記はJIS Z 8000に準拠させた。
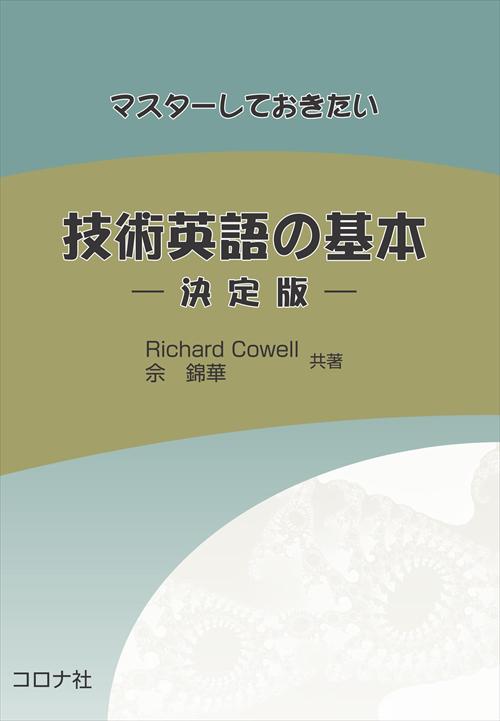
マスターしておきたい 技術英語の基本
詳細を見る
- 決定版 -本書は,従来の技術英語作文技法の成書とは違い,日本人が特に間違いやすい用語の使い方や構文,そして句読法の使い方を重要度の高い順に対比的に説明している。今回の決定版ではプレゼンテーションのノウハウについても解説した。
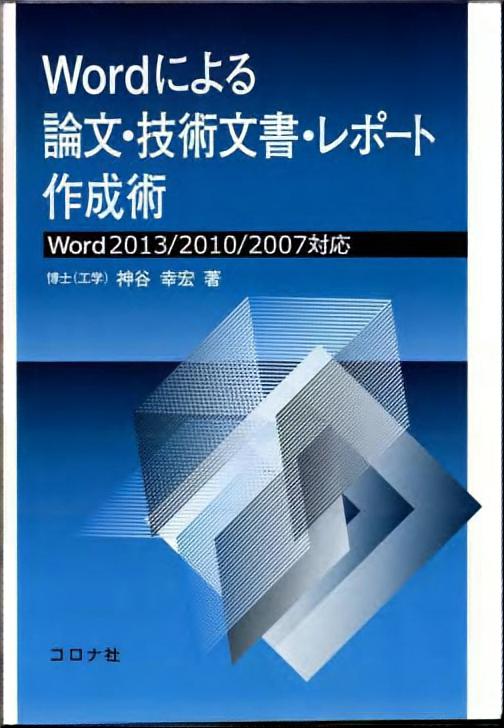
Wordによる論文・技術文書・レポート作成術
詳細を見る
- Word2013/2010/2007対応 -Wordを使うと,あらゆるタイプの文書を簡単に作成できる。本書では,単に辞書的にWordの機能を説明するのではなく,論文・技術文書等をわかりやすく,しかも美しく仕上げるためのプロセス上で,必要なWordの機能と操作を解説した。
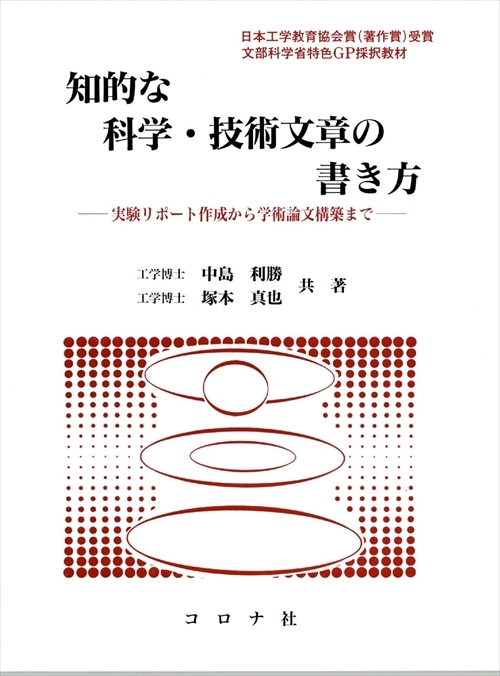
知的な科学・技術文章の書き方
詳細を見る
- 実験リポート作成から学術論文構築まで -理工系学生と若手の研究者・技術者を対象に,実験リポートと卒業論文のまとめ方,図表の描き方,プレゼンテーション原稿の作成法,校閲者への回答文の執筆要領,学術論文の構築手順などすべての科学・技術文章の書き方を知的に解説。
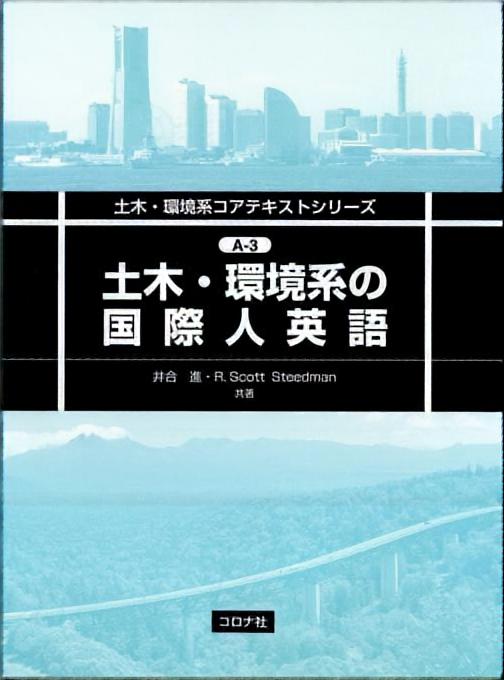
土木・環境系コアテキストシリーズA-3
詳細を見る
土木・環境系の国際人英語本書は,国際的なコミュニケーションの場で,国際人として英語を自然に「読み,書き,話し,聞く」方法を,実用例を交えてわかりやすく解説している。また例文に土木・環境系分野の英文を取り入れ,専門分野の英語学習を可能とした。
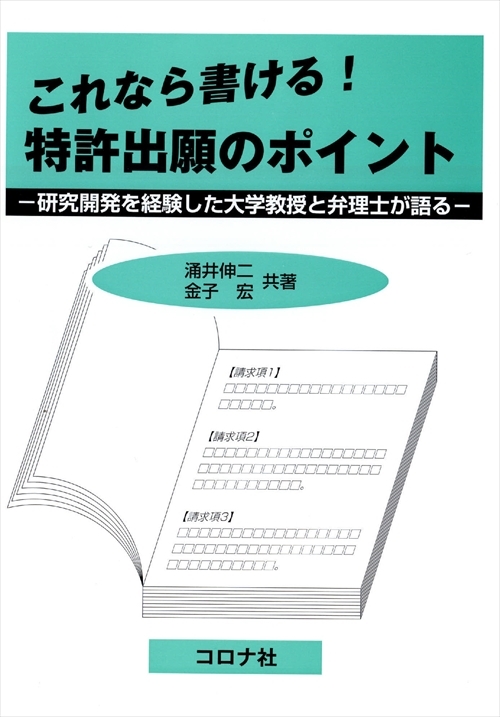
これなら書ける!特許出願のポイント
詳細を見る
- 研究開発を経験した大学教授と弁理士が語る -工学系学生や若い技術者が,はじめて特許出願書類を書こうとするときの導入書。それぞれに研究開発を経験し,実際に特許出願を行ってきた大学教授と弁理士が,互いの経験をもとに実践的な特許出願への取り組みをわかりやすく解説。
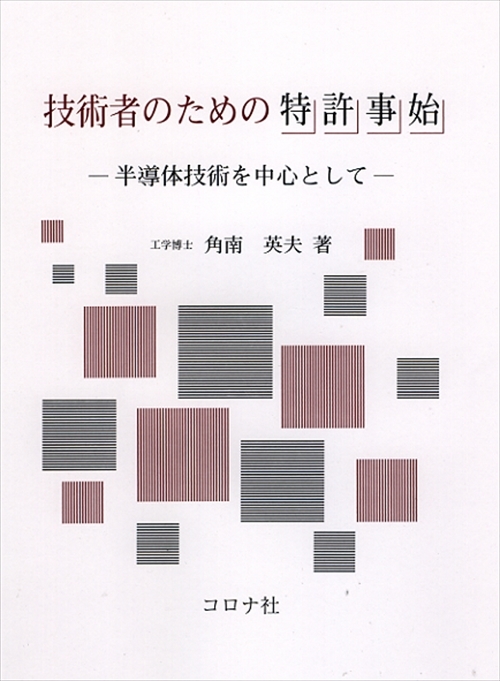
技術者のための特許事始
詳細を見る
- 半導体技術を中心として -従来の特許出願手引き書とは趣を異にした随筆風特許入門書である。日米で300以上の特許を出願している著者が,自身の成功・失敗をもとに,特許に対する誤解を解き,特許取得のための心構えやノウハウをつづる。発明ドリル付き。
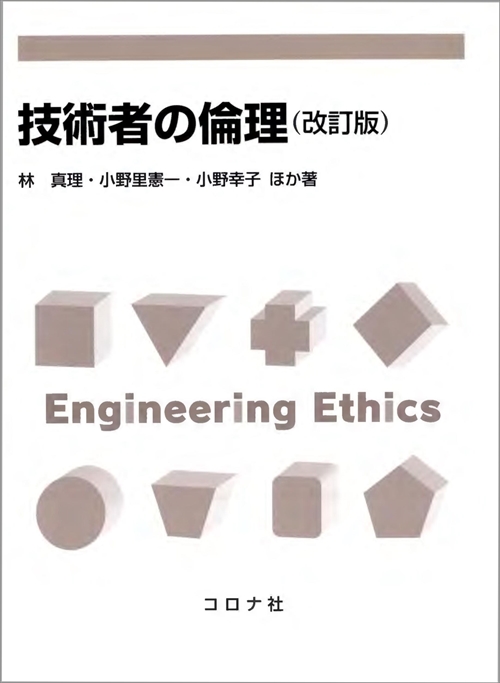
技術者の倫理 (改訂版)
詳細を見る倫理観はエンジニアとして身に付けていなければならない基本的な素養である。本書は倫理にかかわる問題について,基礎的・理論的なポイントと多くの事例を紹介した。改訂にあたり,法令や出来事に関する新しい事例も入れ替えた。
統計(クリギング・R・ベイズなど)

実験の計画と統計的データ解析
詳細を見る本書では実験の考え方,実験計画の立て方,統計的解析を基礎としたデータ解析法を学習する。また,測定における誤差や精度などの考え方に加え,測定結果の信頼性を表現するための不確かさの考え方とその表記方法についても説明した。
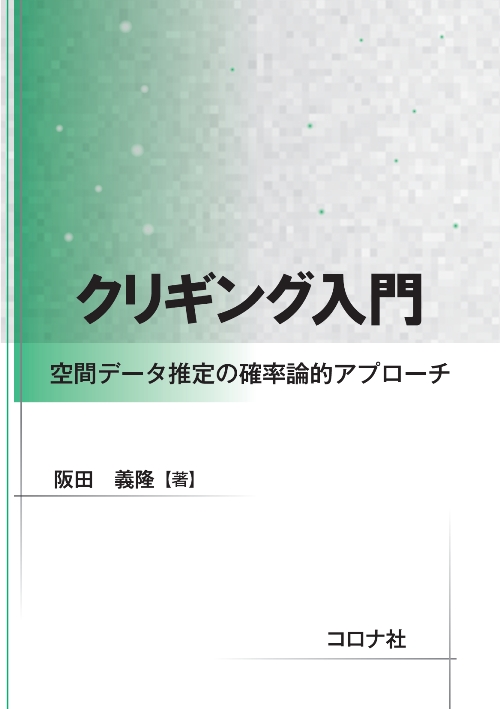
クリギング入門
詳細を見る
- 空間データ推定の確率論的アプローチ -本書は,空間データを分析する様々なソフトウェアに組み込まれているクリギングについて,読者が分析対象とする現象に応じた仮定や条件を自ら吟味,設定し,得られた結果の妥当性を判断できるように,その基礎から応用まで解説した。
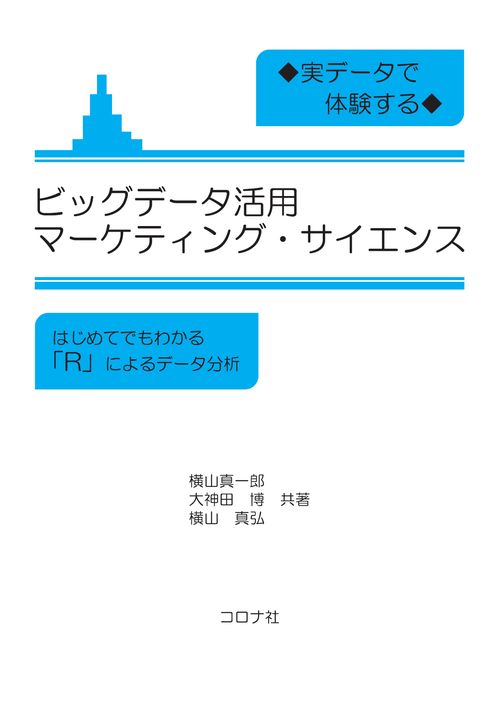
実データで体験する ビッグデータ活用マーケティング・サイエンス
詳細を見る
- はじめてでもわかる「R」によるデータ分析 -マーケティングとはどのような活動なのか,またその活動に必要で有効な分析にはどのような方法があるのかについて,基本的事項から,活用例に重点を置いて「R」を用いた詳細な分析まで,実際のビッグデータを用いて学習できる。
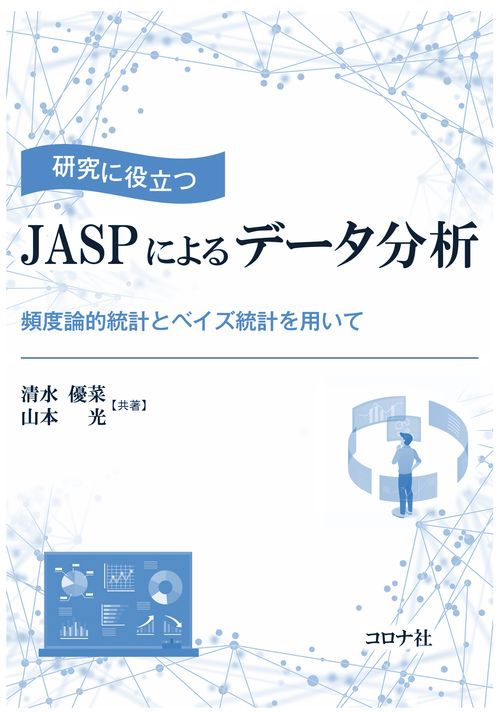
研究に役立つJASPによるデータ分析
詳細を見る
- 頻度論的統計とベイズ統計を用いて -Rのパッケージを利用した高性能なフリーソフトJASPを利用し,頻度論的統計とベイズ統計を比較しながらデータ分析の基礎を学ぶ。具体的なデータの収集・解析・論文に仕上げるための方法を,流れを追って学べるように記述。
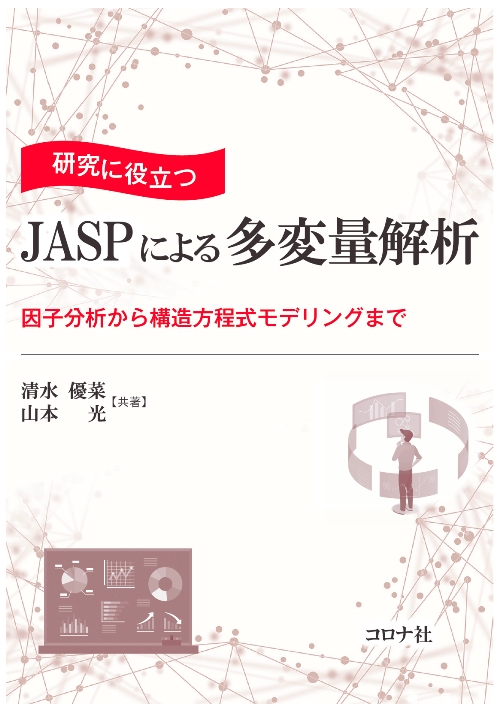
研究に役立つJASPによる多変量解析
詳細を見る
- 因子分析から構造方程式モデリングまで -Rのパッケージを利用した高性能なフリーソフトJASPを利用し,統計解析の要である多変量解析について学ぶ。データ解析を必要とする全ての人が活用できるように、分析方法・結果の解釈・報告例を丁寧に記述した。
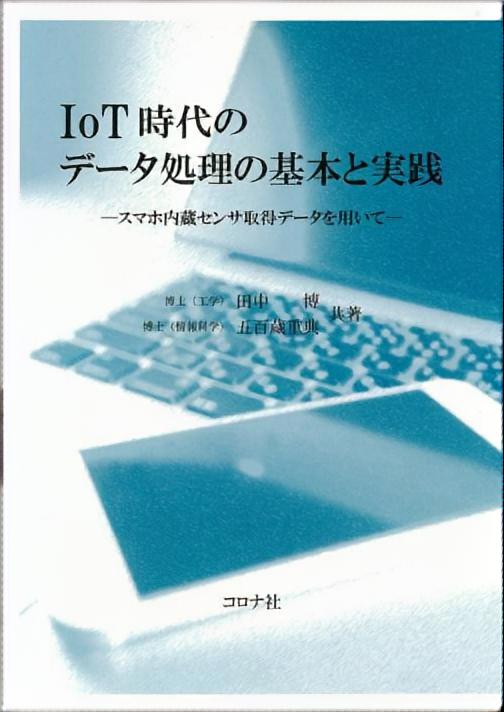
IoT時代のデータ処理の基本と実践
詳細を見る
- スマホ内蔵センサ取得データを用いて -本書では,これから統計解析,機械学習,信号処理を学ぶ学生が,IoTによる膨大なデータの解析や処理の前提となる知識やデータ処理の基本を身につけられる。スマホの加速度センサを例に,取得したデータ処理の方法も体験できる。
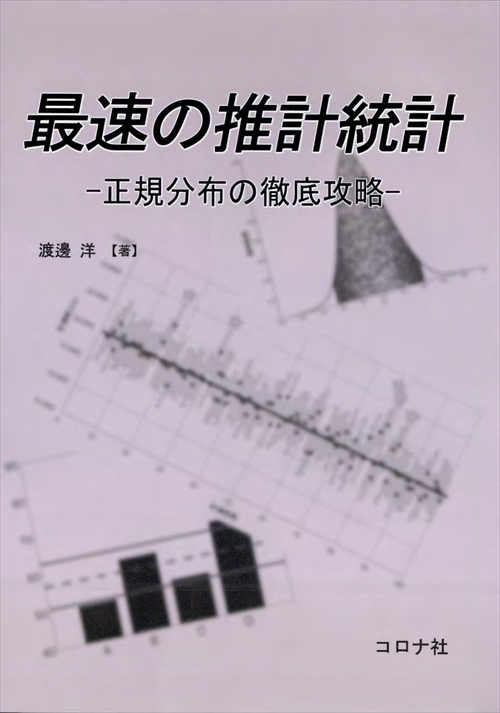
最速の推計統計
詳細を見る
- 正規分布の徹底攻略本書は推計統計学のキモの部分に最速で到達することを目的としている。すなわち,なぜ推計統計学といえば正規分布のグラフが登場するのか,その計算方法,使い道などについて,腹の底から理解することをひとまずのゴールとしている。
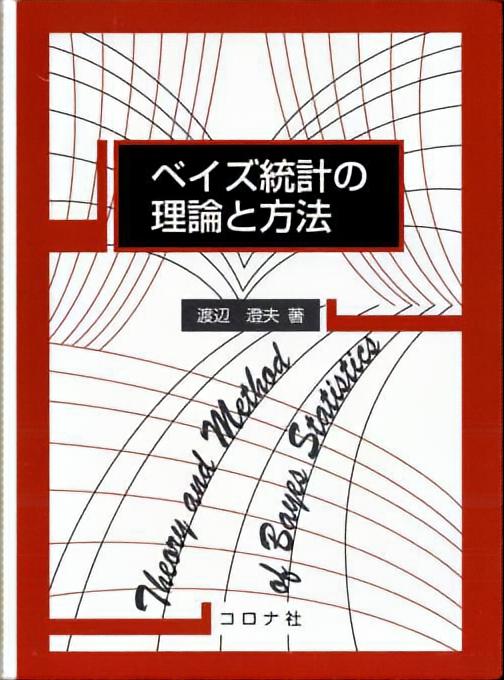
ベイズ統計の理論と方法
詳細を見るベイズ統計学に初めて出会う人が疑問に思うことを解説し,理論的な基礎を明らかにし,実用上で注意することを説明する。統計モデルとは何か,事前分布とは何か,ベイズ統計学ではどんな法則が成り立つか,などを学びたい人に最適。
経営・管理工学(信頼性・リスク・安全・生産、品質管理・人間工学など)
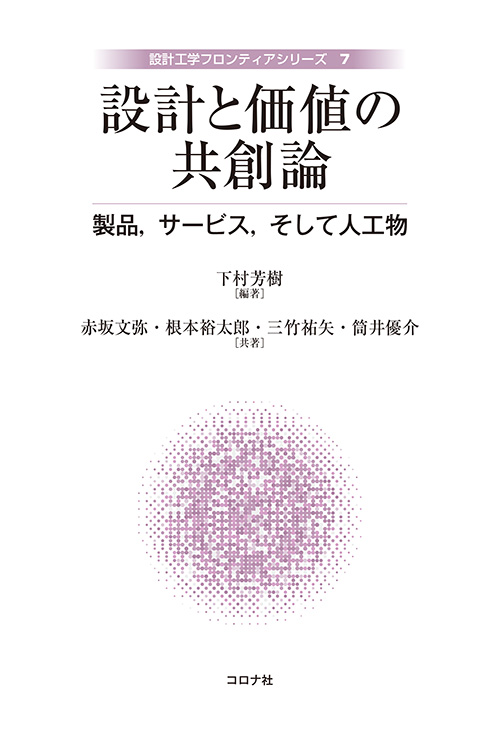
設計工学フロンティアシリーズ 7
詳細を見る
設計と価値の共創論
- 製品,サービス,そして人工物 -本書は,価値の概念を中心に据えつつ,科学・工学・設計の関係と,設計における人の思考の特徴を整理し,関連する既存の設計工学分野における最新の動向に広く言及することにより,理念的設計への架橋とすることを意識した。
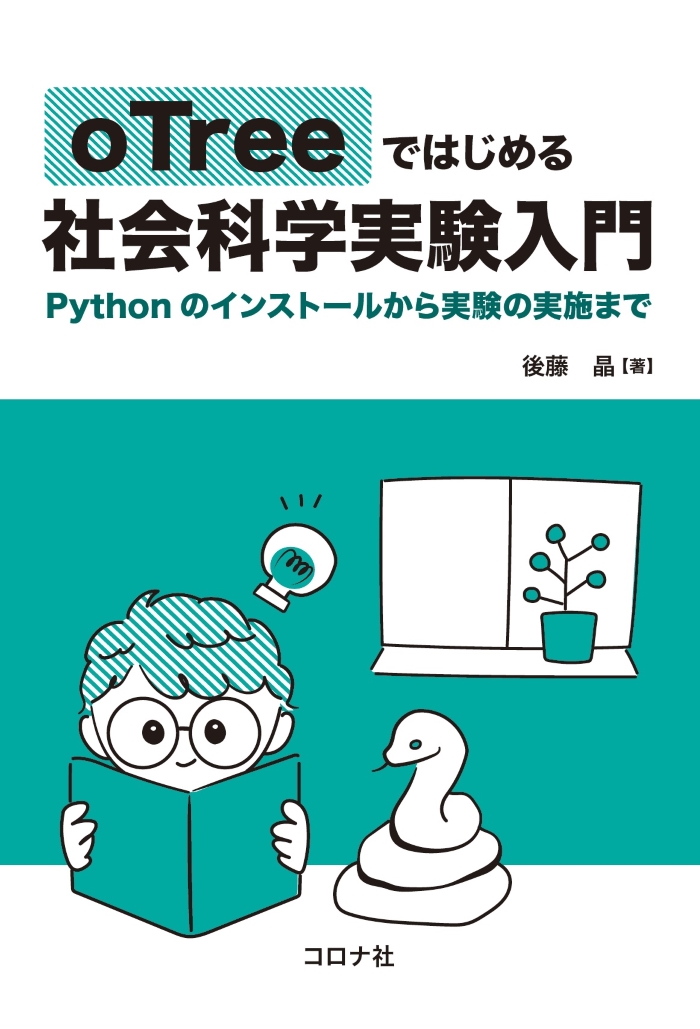
oTreeではじめる社会科学実験入門
詳細を見る
- Pythonのインストールから実験の実施まで -本書は,経済ゲーム実験などに用いられるoTreeというPythonで書かれたフレームワークを用い,社会科学におけるオンライン実験の方法と意義およびその課題,インストールからプログラミングまでを初学者向けに解説する。
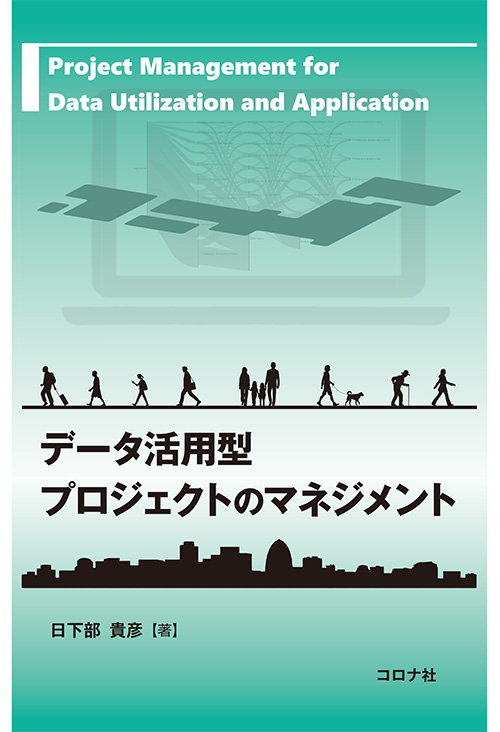
データ活用型プロジェクトのマネジメント
詳細を見る本書では,企業や大学の研究室においてビッグデータを分析・活用する際に必要となる実践的な知識をまとめた。円滑な業務遂行を成し遂げられるように,データサイエンティストだけではなくプロジェクトを統括する人も読者対象とした。
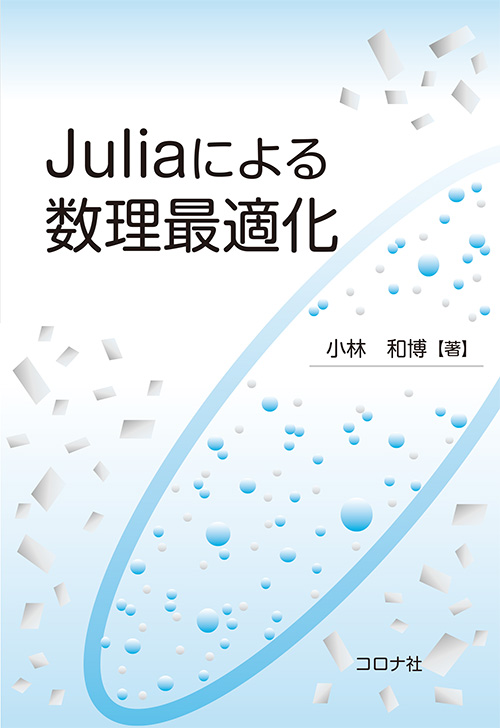
Juliaによる数理最適化
詳細を見る本書は,数理最適化自体の研究について扱っているのではなく,数理最適化に関するこれまでの研究成果とJuliaの既存パッケージを利用して,身近な問題を実際に解くことに興味のある方を読者対象としている。
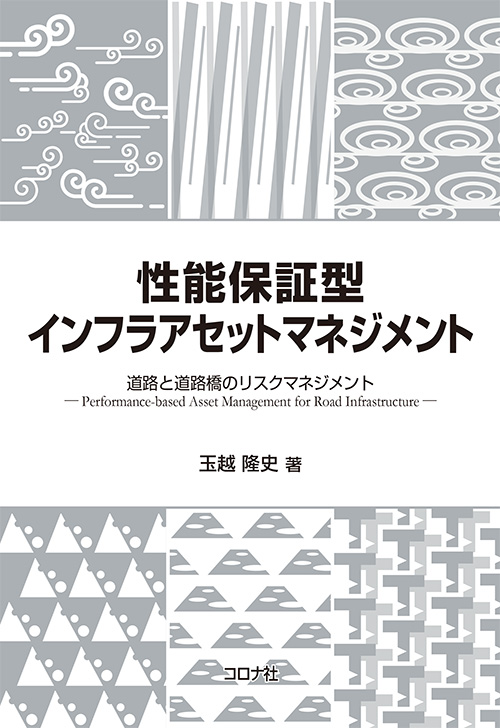
性能保証型インフラアセットマネジメント
詳細を見る
- 道路と道路橋のリスクマネジメント -インフラにおける性能保証とは,おもに構造物自体の性能を保証することと考えられてきたが,それはあくまで前提条件であり,道路ネットワークとしてのインフラの機能・役割等を保証することこそが,本当の意味での性能保証である。
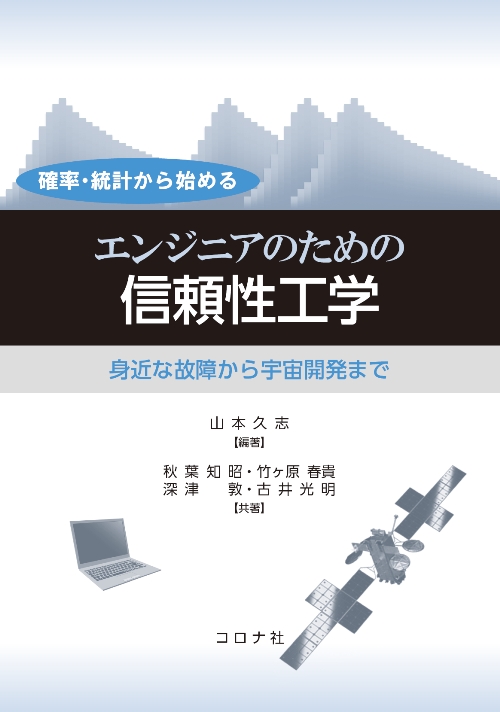
確率・統計から始める
詳細を見る
エンジニアのための信頼性工学
- 身近な故障から宇宙開発まで -累積分布関数の解説に始まり,故障データ解析に有用な統計手法,実際のシステム設計で重要な冗長化の方法,修理を伴うシステムの評価,信頼性設計や安全工学の考え方に加え,宇宙開発における安全・信頼性設計の事例まで幅広く紹介。

人間行動と組織行動
詳細を見る
- パフォーマンス向上の視点から -組織の中における人間の「行動」と,それによる結果「パフォーマンス」との関係を紐解く。自他の能力を客観的に把握する手順や最良の成果を発揮できる環境づくりの方策を解説。人的資源管理,経営,看護・福祉に携わる方に。
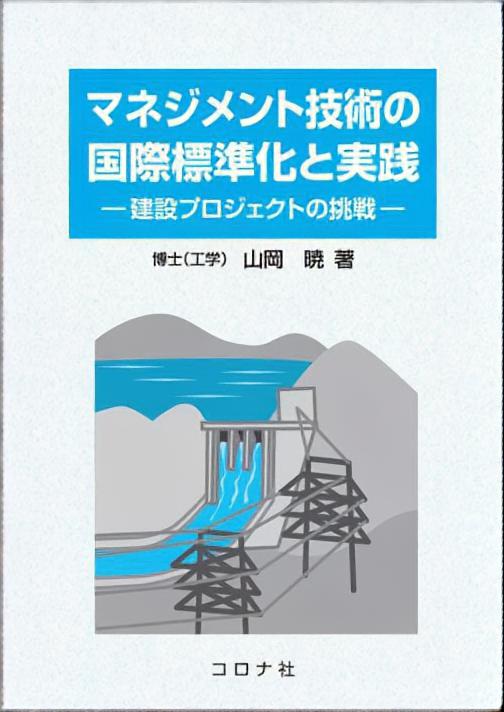
マネジメント技術の国際標準化と実践
詳細を見る
- 建設プロジェクトの挑戦 -本書では,「PMBOK®ガイド」を国際標準化されたプロジェクトマネジメントガイドとして,筆者の国内外におけるプロジェクトマネジメントの経験を踏まえ,国際標準化が進むマネジメント技術の知識体系や実践方法を解説した。
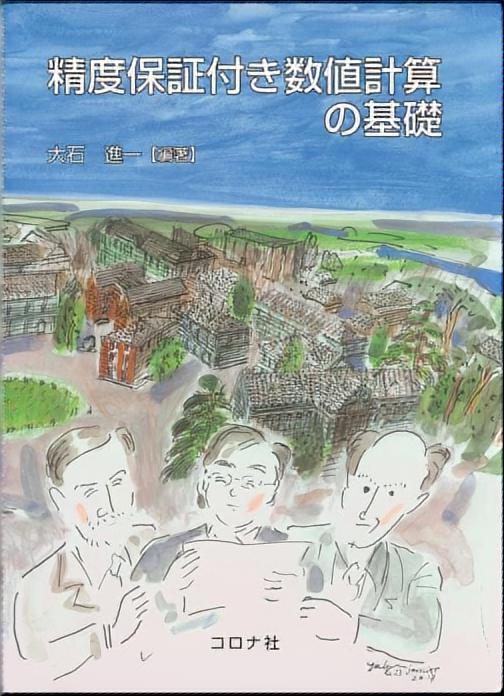
精度保証付き数値計算の基礎
詳細を見る数値計算の誤差を完全に把握する数値計算(「精度保証付き数値計算」)が重要となる局面は非常に多くなりつつある。本書は今までの成果をもとに,現在における精度保証付き数値計算の基礎となる事項を体系的にまとめたものである。
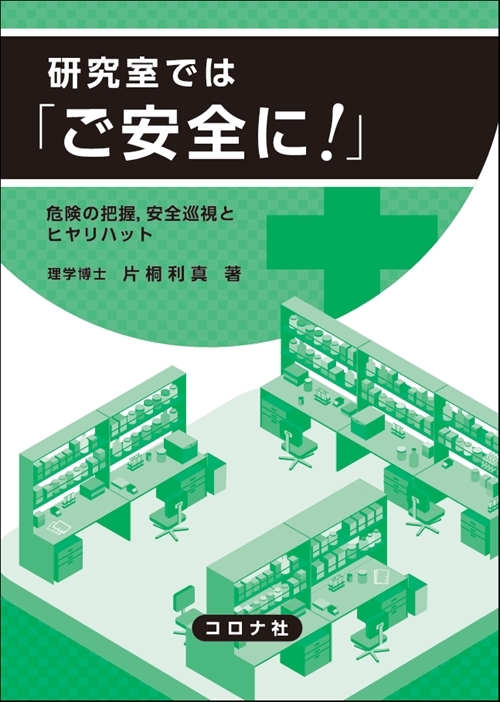
研究室では「ご安全に!」
詳細を見る
- 危険の把握,安全巡視とヒヤリハット -本書は,研究現場での安全推進や安全指導を担う人材(研究室のリーダーや将来の管理職)の育成を目的とし,基礎的な教養や心構えから危険要因の分析とその安全対策が立てられるところまでが身につくように実例を交えて解説している。
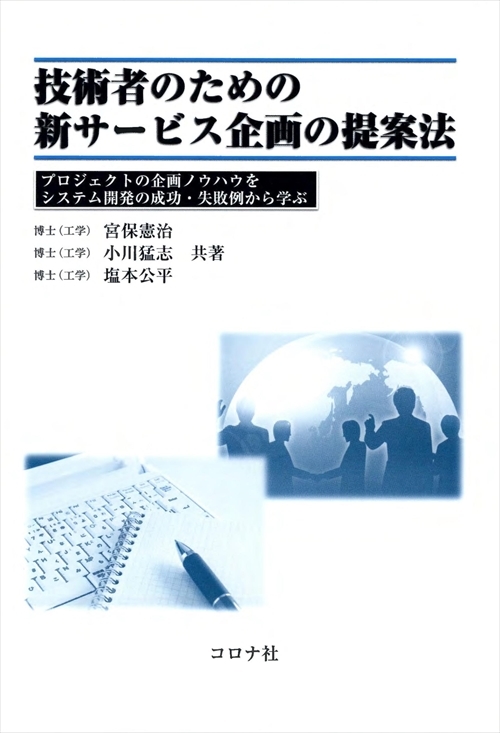
技術者のための新サービス企画の提案法
詳細を見る
- プロジェクトの企画ノウハウをシステム開発の成功・失敗例から学ぶ -ICT関連企業の若手技術者が,新サービスを提案するためのノウハウを学べる。そのために必要となる新しいネットワーク・ユビキタスサービスを取り上げ,安全性・信頼性に配慮したサービスやシステムの実現に必要な基礎技術も解説。
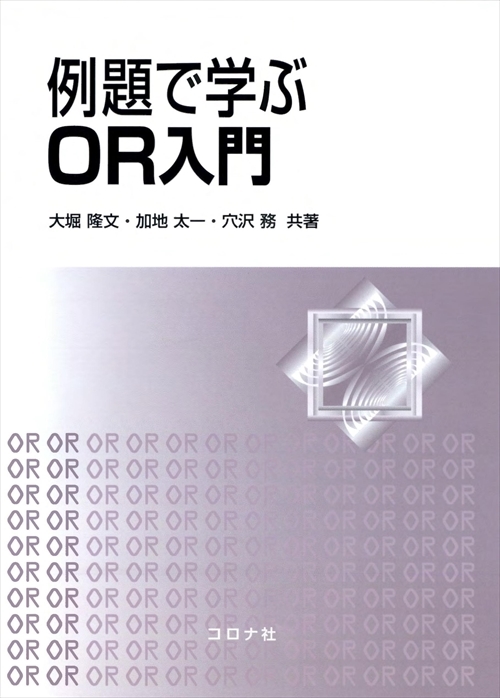
例題で学ぶ
詳細を見る
OR入門本書では,オペレーションズリサーチ(OR)をできるだけ数理表現を用いずに説明し,最小限の数学からなる身近な話題を例題・課題として,問題解決や意思決定,最適化の実現に必要なORの問題の本質を学べるようにした。
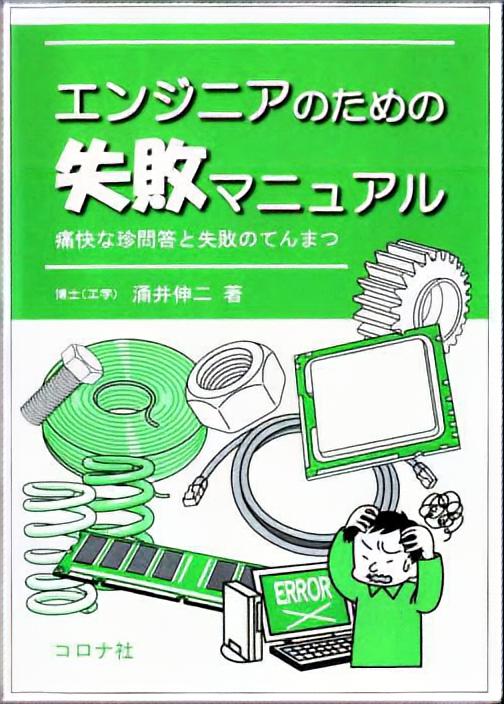
エンジニアのための失敗マニュアル
詳細を見る
- 痛快な珍問答と失敗のてんまつ -メカトロ機器開発の境界領域といえる振動のありかを探索し,解決策を提示・実証できる技術者育成を狙い,著者らが経験した機械振動のトラブルを挙げ,振動源の特定,性状の把握を踏まえ実現可能な解決策が発想できることを示す。
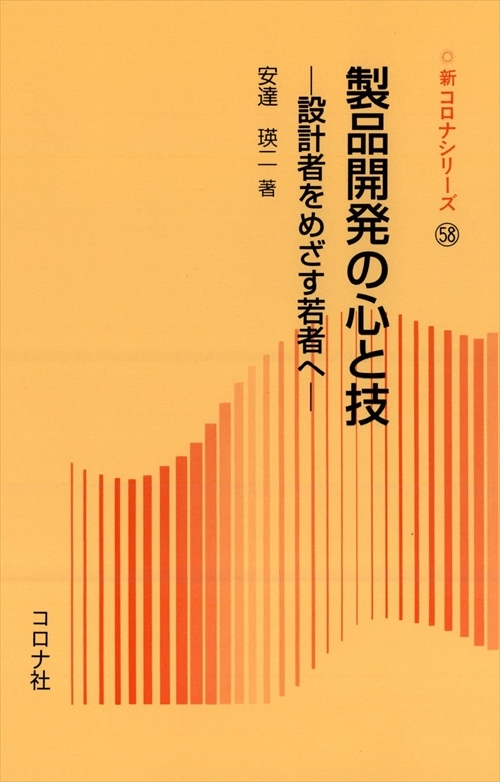
新コロナシリーズ 58
詳細を見る
製品開発の心と技
- 設計者をめざす若者へ -トヨタ自動車の元製品企画室主査である著者が,将来設計者をめざす若者へ向けて,製品開発の具体的なプロセスやノウハウ,設計者としての心のあり方を詳述した。実体験から語る,トヨタ自動車の開発システムも紹介。
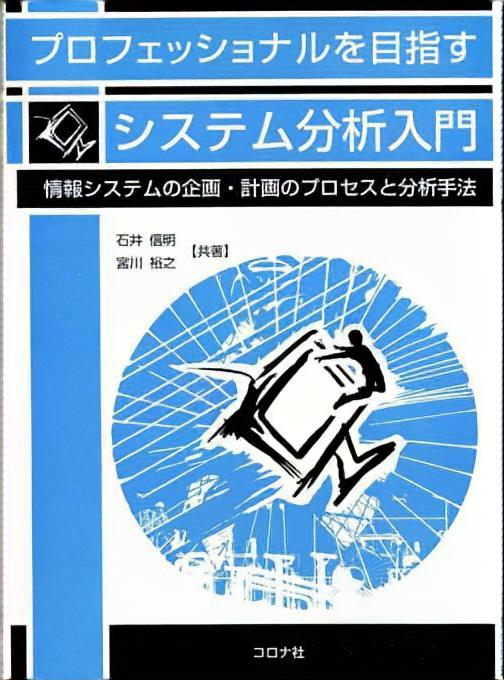
プロフェッショナルを目指す
詳細を見る
システム分析入門
- 情報システムの企画・計画のプロセスと分析手法 -学生または実務経験の少ない社会人が興味を持ちながらシステム分析を学習できるよう,システム分析技法を実際に適用する場面を想定しながら紹介。またシステム分析だけでなく,新たなシステムを創造する活動との関連も取り上げた。
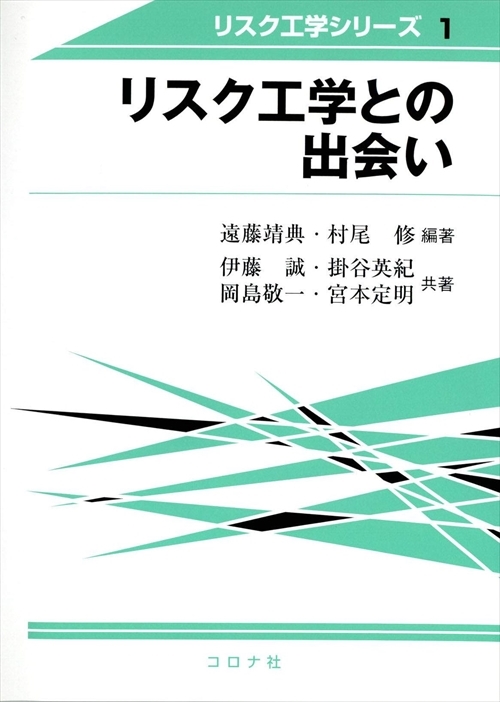
リスク工学シリーズ 1
詳細を見る
リスク工学との出会いこれまでケーススタディ的に扱われてきたリスクを工学的観点から再構築しようという試みが「リスク工学」である。本書はシリーズ第1巻として,リスク工学がいかに私たちに身近なものであるか,その全体像を物語風に平易に概説した。
電気電子工学(電力・通信・電子回路)
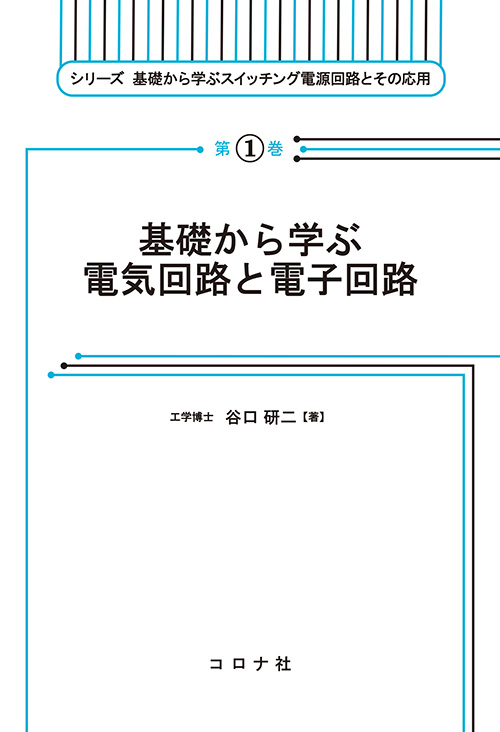
1.基礎から学ぶ電気回路と電子回路
詳細を見る受動素子だけで構成されている回路を電気回路,能動素子を含む回路を電子回路と区別し,前半では電気回路の基礎知識,後半では制御回路で使われている電子回路とオペアンプの内部構造の理解からそれを用いた回路の作り方を説明。
2.基礎から学ぶスイッチング電源の要素デバイス
詳細を見る
- パワー半導体デバイス,コンデンサ,インダクタ -電力変換回路(パワー段)で使用する電子部品(コンデンサ,コイル,半導体デバイス)の機能・性能・信頼性を扱い,パワー段においてスイッチ機能を果たす半導体デバイス,受動素子のコンデンサとコイル(トランス)を取り上げる。
3.基礎から学ぶ制御工学と基本コンバータ回路
詳細を見るコンバータの制御に多用されている古典制御について基礎的なレベルから説明し,各種コンバータの動作確認,伝達関数,動作の安定性,さらにスマホなどに搭載されているバッテリーに必須な技術であるリップルベース制御を解説した。
4.基礎から学ぶコンバータ回路におけるEMI対策
詳細を見る前半ではスイッチングによる電磁界ノイズ(EMI)の発生原因とその解決法を電磁気学の理論に基づいて説明する。後半では回路技術の視点から,コイルやトランスに関係する発熱要因とその解決法など,実践的な技術について説明する。

IEC 61850システム構成記述言語SCL
詳細を見る
- 電力システム設計者のための解説と記述例 -近年,電力システムにおいてデジタル化が進む中で,IEC 61850が注目を浴びている。本書では,IEC 61850のシステム構成記述言語であるSCLに特化した解説と規格動向を踏まえ,豊富な記述例をまとめた。

人工知能チップ回路入門
詳細を見るAIとニューラルネットワークによる情報処理専用の集積回路「人工知能チップ」について,原理から最新の開発例や動向までを追った入門書。AI処理の高速化・効率化・低電力化に必須のハードウェア技術を紹介する。
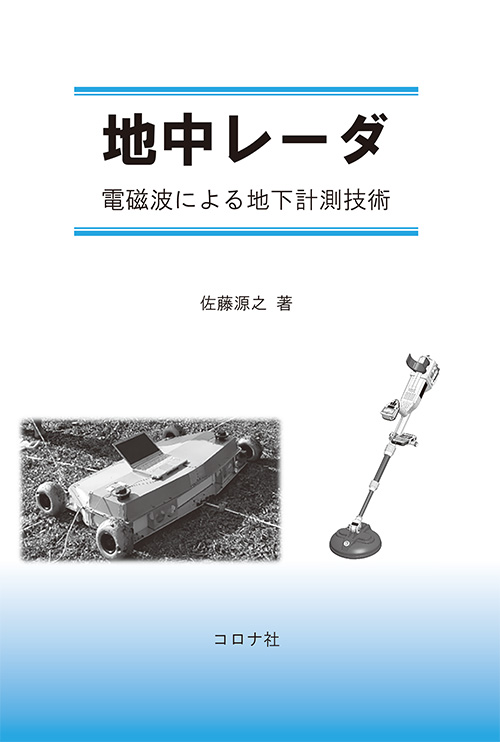
地中レーダ
詳細を見る
- 電磁波による地下計測技術 -電波の物理的な性質,媒質と電波の相互作用,レーダ計測装置と信号特性を理解するため,地中レーダに特有な技術を中心に解説した。地中レーダ技術が電波科学を基礎とする計測技術であることを理解してもらうことを目的とする。
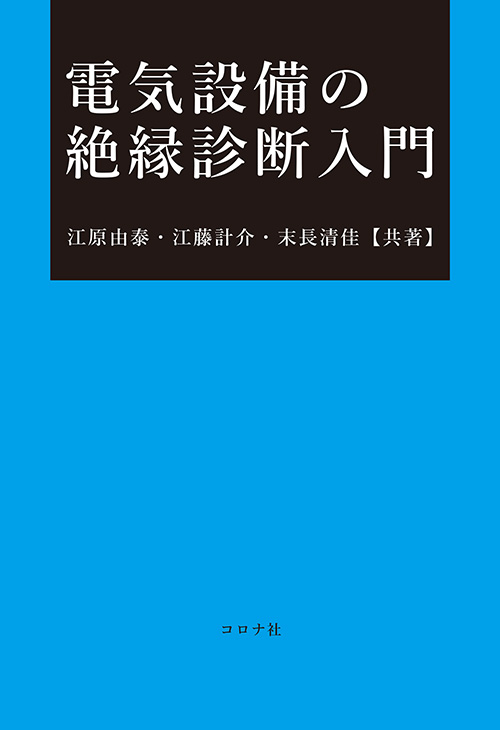
電気設備の絶縁診断入門
詳細を見る電気設備は目的により構造や適用される絶縁材料が異なる。それらは製造年代や電圧階級ごとに変遷を遂げ,絶縁設計も変更された。その絶縁診断の理解に必要な設備の構造や絶縁材料の特性,劣化メカニズムなどを体系的にまとめた。
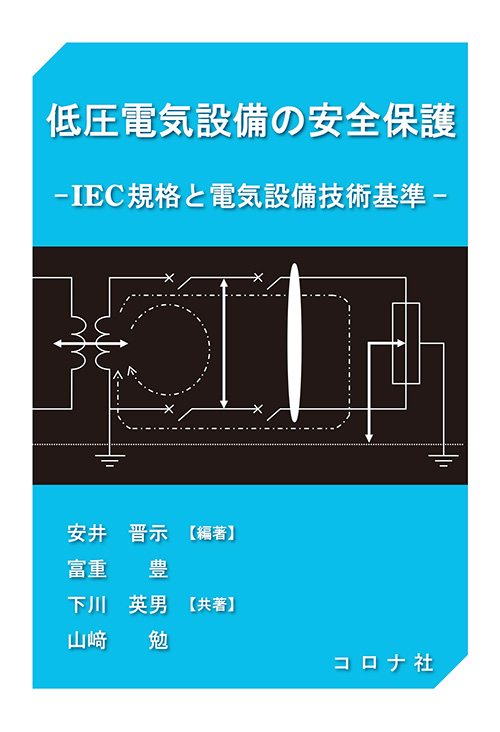
低圧電気設備の安全保護
詳細を見る
- IEC規格と電気設備技術基準 -低圧電気設備の安全保護,特に感電保護,過電流保護,過電圧保護について,国内の規格と海外のIEC規格の比較・解説をもとに,基本的な考え方や保護方法の選定・施工について理解する。実務で役立つ試算例,Web資料あり。
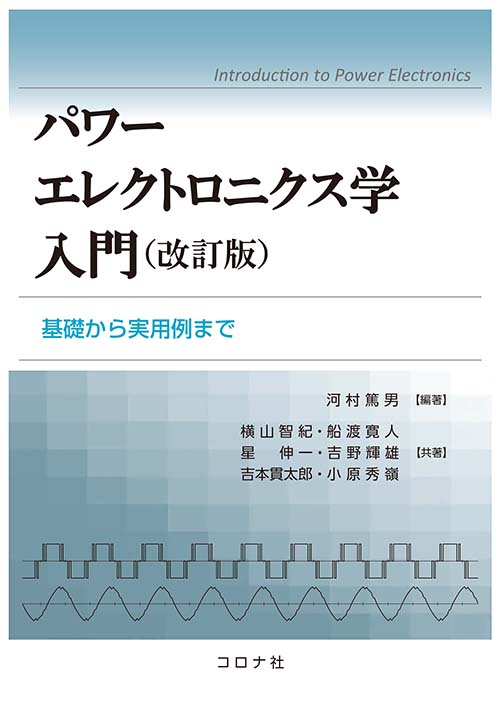
パワーエレクトロニクス学入門
詳細を見る
- (改訂版)- 基礎から実用例まで -初学者を念頭に,電力増幅の考え方から始まり,直流・直流変換,インバータ,整流器の順で解説し,豊富な実用例や応用技術についても紹介した。本改訂では実用化が広まるマルチレベル電力変換技術や電気自動車の技術動向を加筆した。
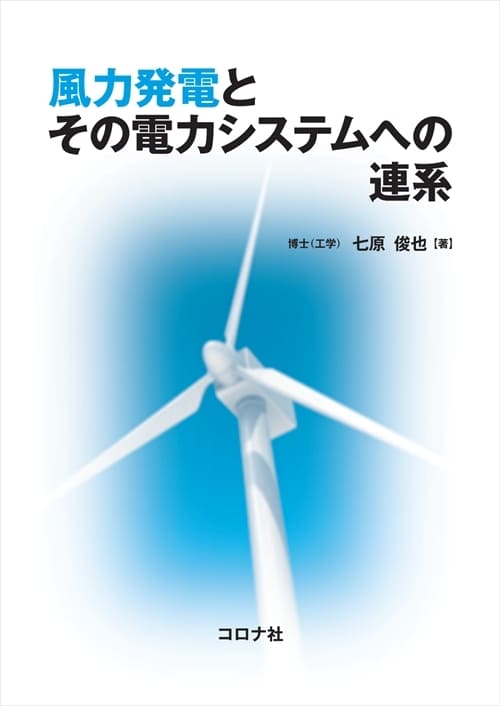
風力発電とその電力システムへの連系
詳細を見る本書は風力発電の概要とその電力システムへの影響を論ずるため,風という気象現象から,風力発電装置という機械装置,さらには電力システムまで多岐にわたる内容をそれぞれの初学者に理解してもらえるよう解説した。
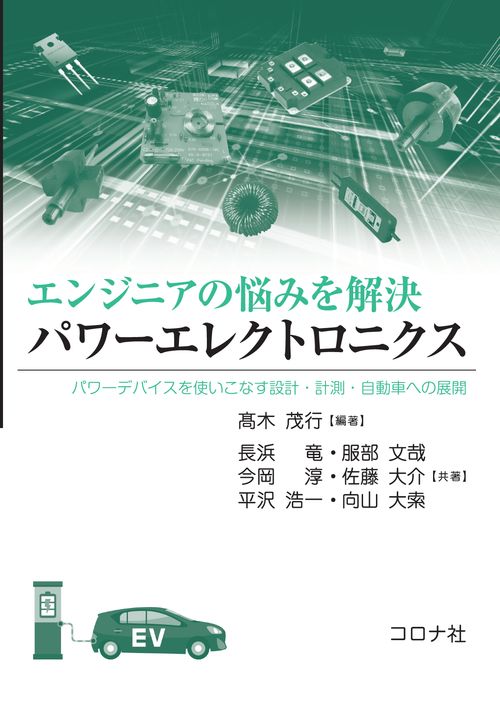
エンジニアの悩みを解決
詳細を見る
パワーエレクトロニクス
- パワーデバイスを使いこなす設計・計測・自動車への展開 -これまで専門分野が異なるため系統的な説明がなされてこなかったパワーデバイスと回路をつなぐ技術を中心に,パワエレ技術が集結する電気自動車,個人の持つノウハウに任されがちな測定技術等,パワエレに関する応用技術を解説する。
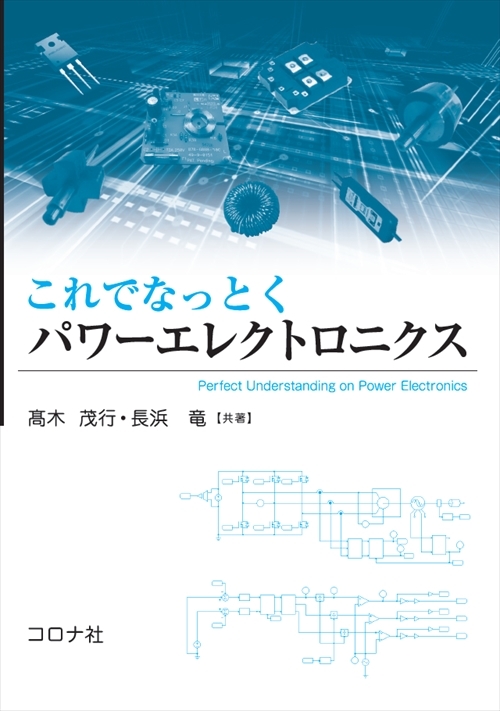
これでなっとく
詳細を見る
パワーエレクトロニクスパワーエレクトロニクスの回路系に始まり,モータ駆動と制御を関連付けて丁寧に解説した。高調波を考慮した電力測定技術や新型パワー素子,ベクトル制御についても紹介。学生はもちろん技術者にもお勧めしたい一冊。
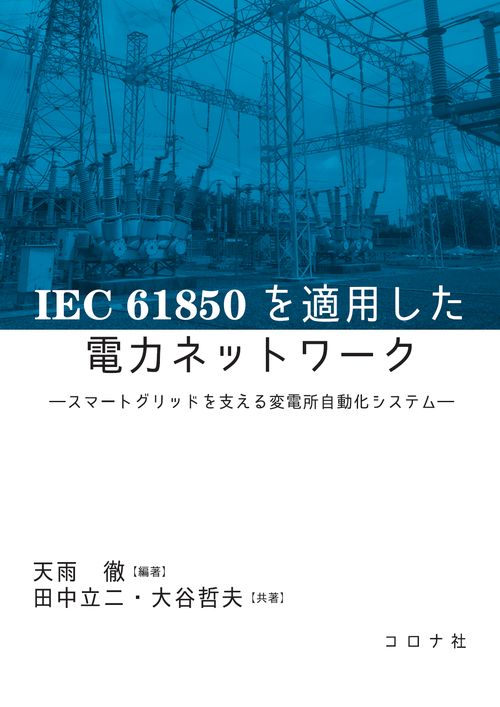
IEC 61850を適用した電力ネットワーク
詳細を見る
- スマートグリッドを支える変電所自動化システム -変電所自動化システムのための通信規格IEC 61850を理解するためその全容を網羅。必要項目と具体例を体系的にまとめた解説書。学生から専門技術者まで、変電所自動化システムをはじめスマートグリッドに携わる方必携の一冊。
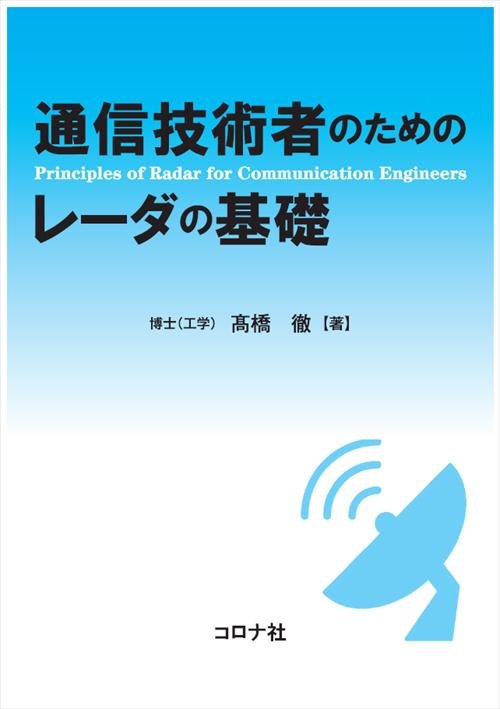
通信技術者のためのレーダの基礎
詳細を見る無線通信とレーダとの類似性の視点を取り入れながら,両者に共通のレンジ方程式,変復調方式,信号検出に特化し,それぞれに導入部として無線通信を専門とする人にとって馴染みのある内容を入れ,理論を解説した。
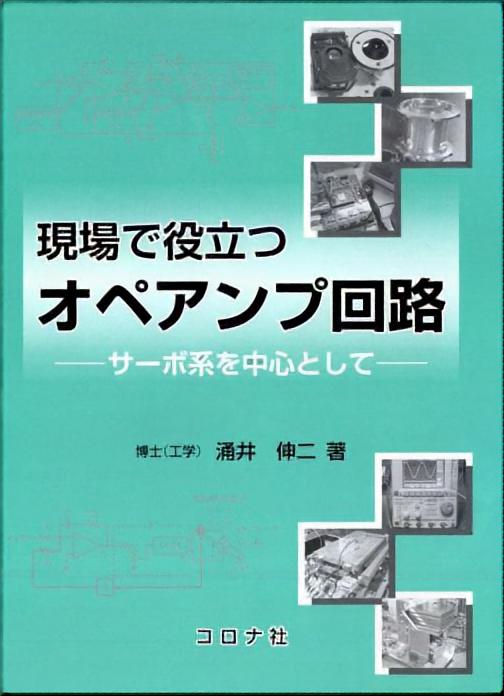
現場で役立つ
詳細を見る
オペアンプ回路
- オペアンプ回路 -本書では,サーボ系の構築という目的における一機能としてのオペアンプ回路という説明形式を採用。回路方程式を立式するための補助図面や実測の周波数応答を掲載し,この計測結果と数式との対応を詳細に説明し,理解の手助けとした。
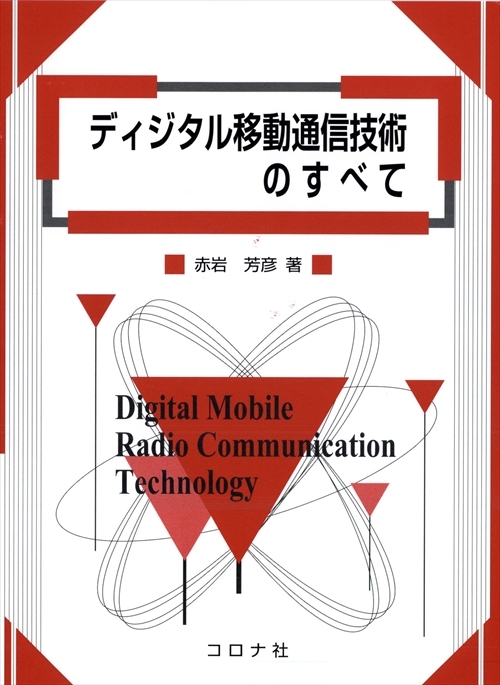
ディジタル移動通信技術のすべて
詳細を見るディジタル移動通信分野の開発・研究で世界的に有名な著者が,関連技術の初期の技術から最新技術までをその基礎と応用分野の全体像について,多くの数式や図表を用いて体系立てて詳説している。関連技術者・研究者にとっての必携書。
シリーズ:シリーズ 基礎から学ぶスイッチング電源回路とその応用
情報工学(セキュリティ・機械学習・データサイエンス・Julia・MATLAB・Python・基本情報など)
- 詳細を見る

プログラミング関連書籍
詳細を見る- 詳細を見る
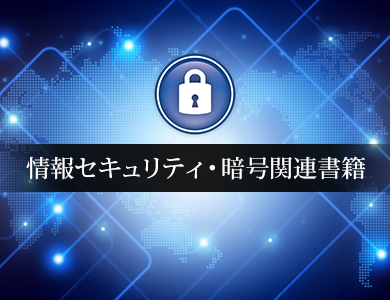
情報セキュリティ・暗号関連書籍
詳細を見る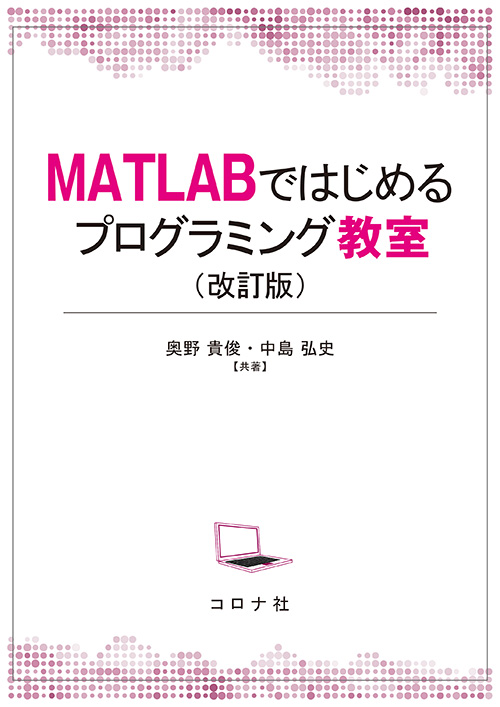
MATLABではじめるプログラミング教室
詳細を見る
(改訂版)初心者が手を動かして覚えることを念頭に,基本技術(数値計算,データの読み込み,分析,表示,加工,保存,GUIアプリケーション作成)を丁寧に解説。改訂版ではappdesigner利用のGUIアプリケーション作成を掲載。
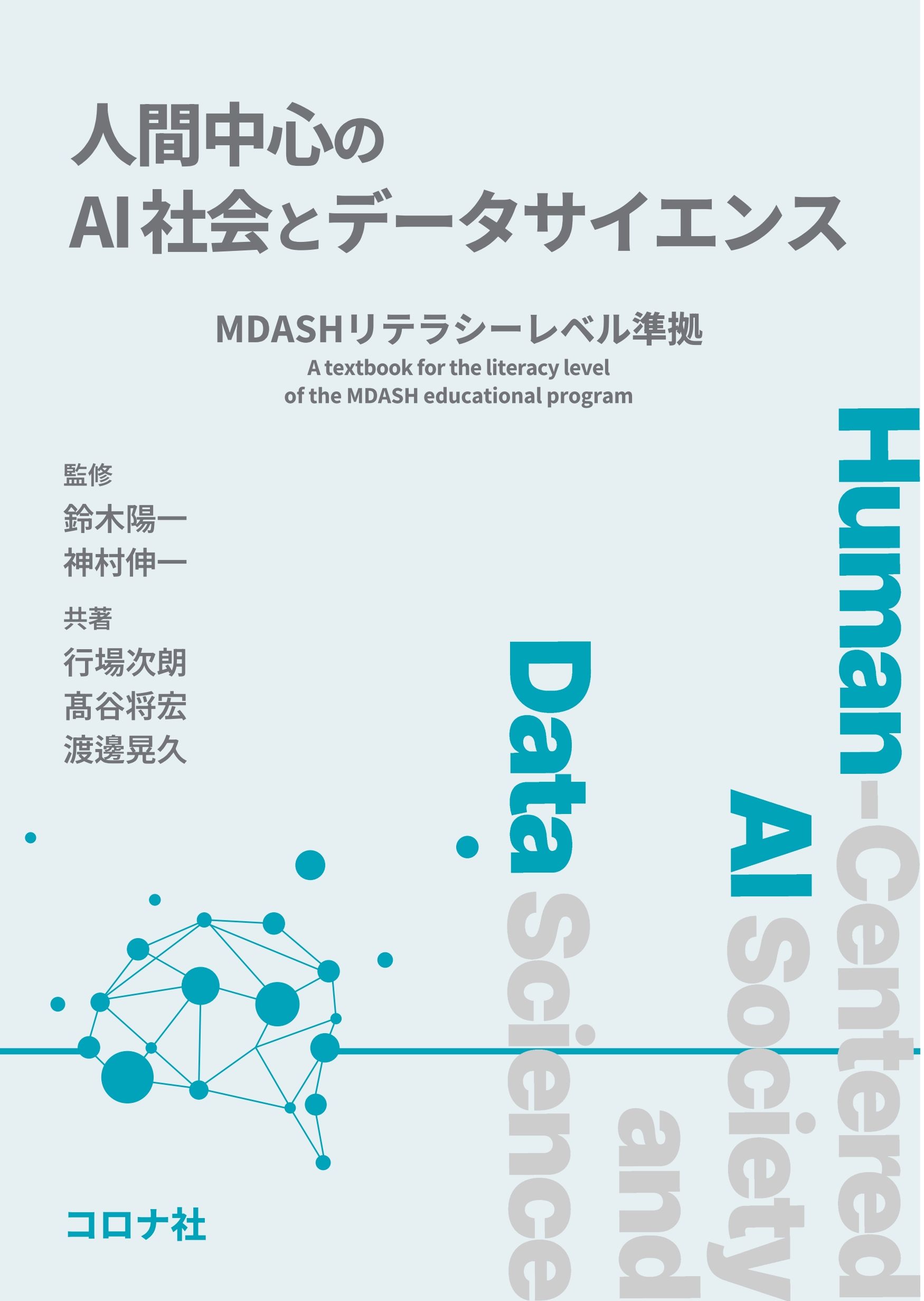
人間中心のAI社会とデータサイエンス
詳細を見る
MDASHリテラシーレベル準拠文部科学省MDASHのリテラシーレベルを満たす構成。AI やデータサイエンスの基礎や特性,課題について,人間中心の視点に立って,人類進化の背景や,人間の認知特性,持続的社会の発展,人間発達や教育など幅広い問題を解説。
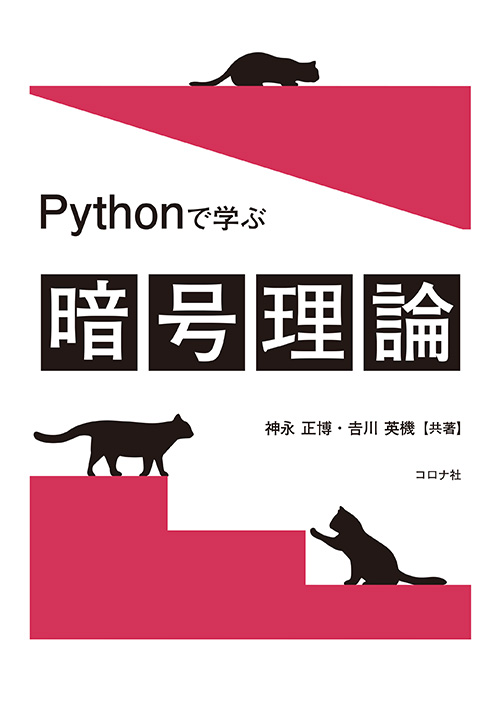
Pythonで学ぶ暗号理論
詳細を見る暗号理論の解説に加え,差分解読法・線形解読法,ハッシュ関数の解析,RSA 暗号に対する攻撃等を体験できる Python プログラムを提供。理論だけでは実感が湧きにくい暗号の仕組みを,プログラムを動かしながら学ぶ。
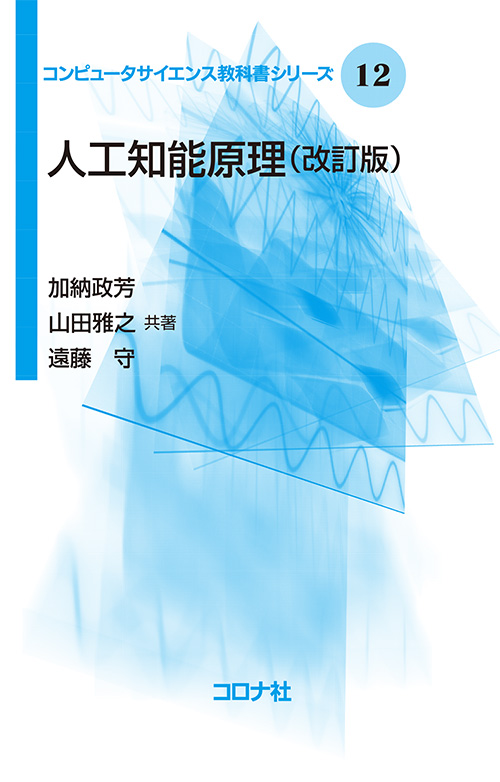
コンピュータサイエンス教科書シリーズ 12
詳細を見る
人工知能原理
(改訂版)本書では,人工知能アルゴリズムの中でも,探索,ゲーム,機械学習,知識表現・セマンティックWeb技術に焦点を絞り,それらを平易に解説した。改訂版では,サポートベクトルマシンとt-SNEの解説を追加した。
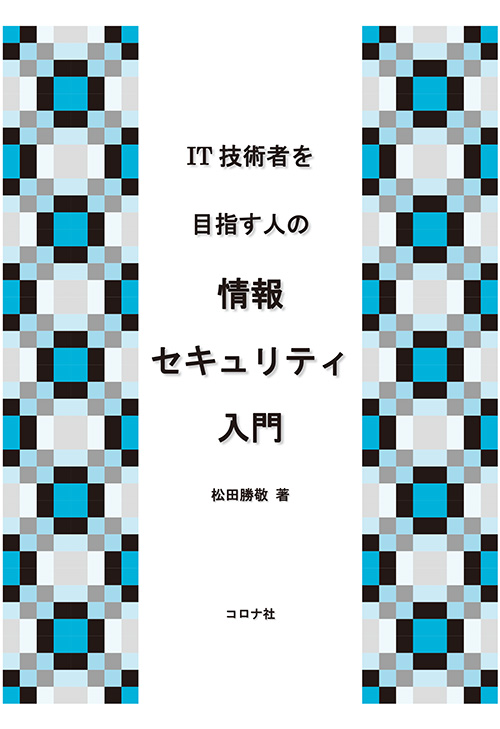
IT技術者を目指す人の
詳細を見る
情報セキュリティ入門IT業界で働いていると役に立つ情報セキュリティの入門書。IT技術者としてある程度仕組みまで理解しておいたほうがよいことは詳しく解説し,またどのように実務に関係してくるのか,見えやすくするように実例などを交えて解説。
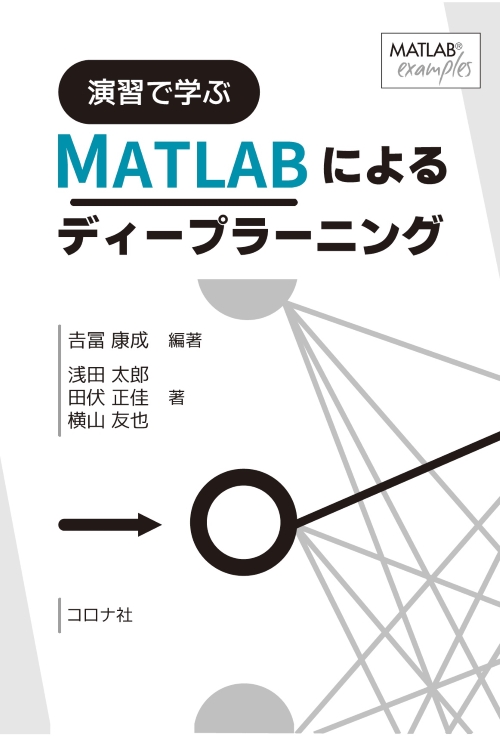
演習で学ぶMATLABによるディープラーニング
詳細を見る本著は,演習を通して実践的に学ぶ,MATLABによるディープラーニング入門書である。大学教養数学やプログラミングの経験があると理解しやすいが,その不足分を補う勉学意欲があれば,実践力が育まれるよう工夫して書いている。
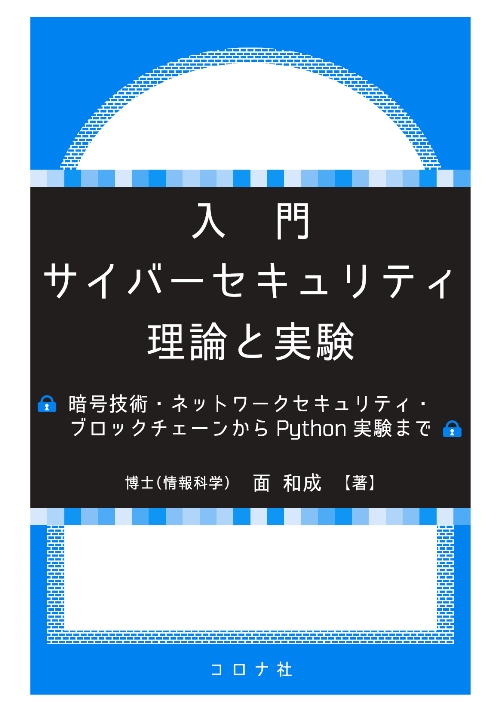
入門 サイバーセキュリティ 理論と実験
詳細を見る
- 暗号技術・ネットワークセキュリティ・ブロックチェーンからPython実験まで -暗号技術からネットワークセキュリティまで,広くサイバーセキュリティを扱う教科書。Python言語を用いたいくつかのセキュリティ実験を取り上げたことで,理論・応用・実装・実験の四つの観点から深く学ぶことができる。
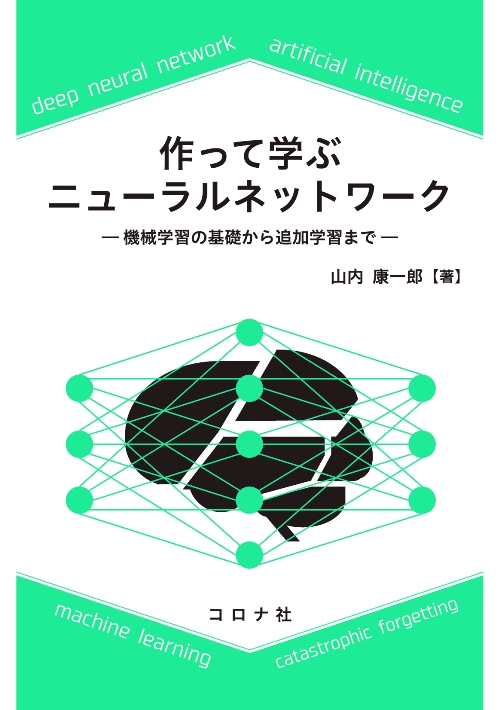
作って学ぶニューラルネットワーク
詳細を見る
- 機械学習の基礎から追加学習まで -Pythonによるプログラミングを行いつつ人工知能、機械学習の仕組みを学ぶ。新しい技術である「追加学習」のやさしい解説を通して、現在の機械学習が抱える問題点・限界を示し、読者により深い理解をもたらすことを目指す。
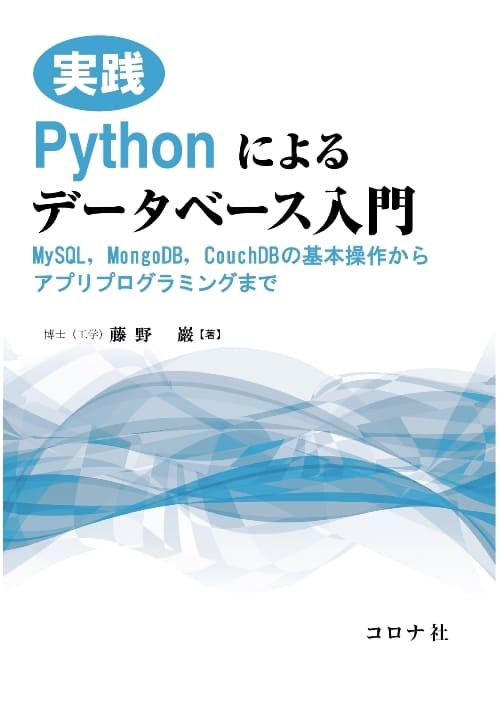
実践
詳細を見る
Pythonによるデータベース入門
- MySQL,MongoDB,CouchDBの基本操作からアプリプログラミングまで -基本理論は必要最小限に,実際の操作命令やデータベースプログラミングについては平易に解説。請求書データベースの設計,フライトデータ解析,Twitterストリーミングデータの収集と解析など,幅広い応用事例を示した。
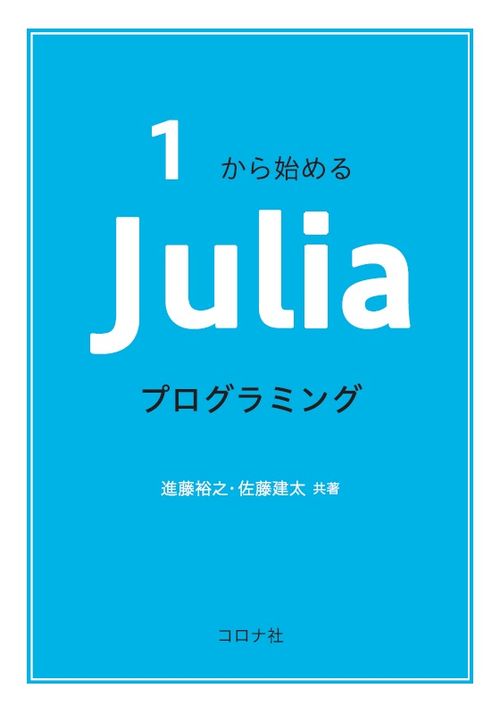
1から始める
詳細を見る
Juliaプログラミング「Pythonのように書けて,Cのように動く」新しいプログラミング言語Juliaの基本的な文法や使い方から,実践的な内容として,標準ライブラリには含まれない数値計算やデータの可視化などのパッケージの活用まで解説する。
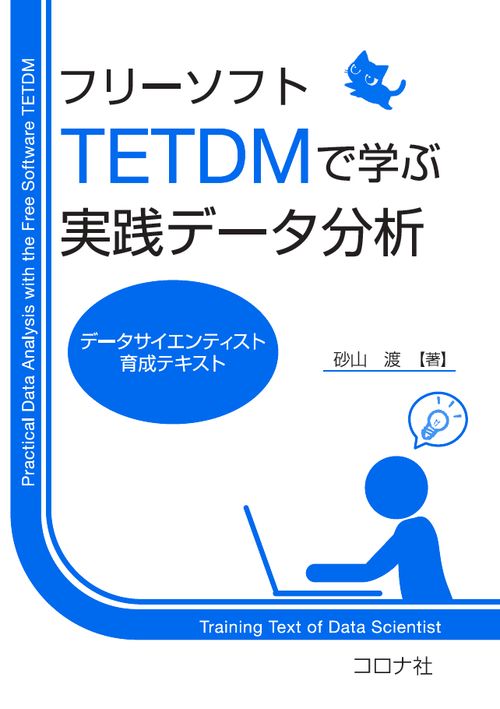
フリーソフトTETDMで学ぶ実践データ分析
詳細を見る
- データサイエンティスト育成テキスト -テキストデータから様々な情報を抽出・提示することによって意思決定をサポートするフリーソフトTETDMを用いて,データ分析の考え方から手順,そしてテキストマイニングの具体的な解析手法までを初学者でもわかるように解説。
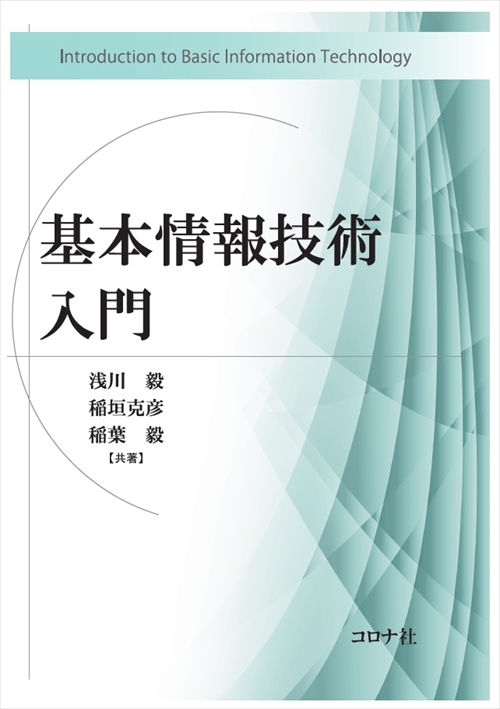
基本情報技術入門
詳細を見る情報技術全般の理解を深める入門書として,コンピュータ技術を核にハードウェアとソフトウェアの両方をバランスよく解説。「基本情報技術者試験」の多くの分野をカバーし,例題や章末問題には過去問を中心にその解法を掲載した。
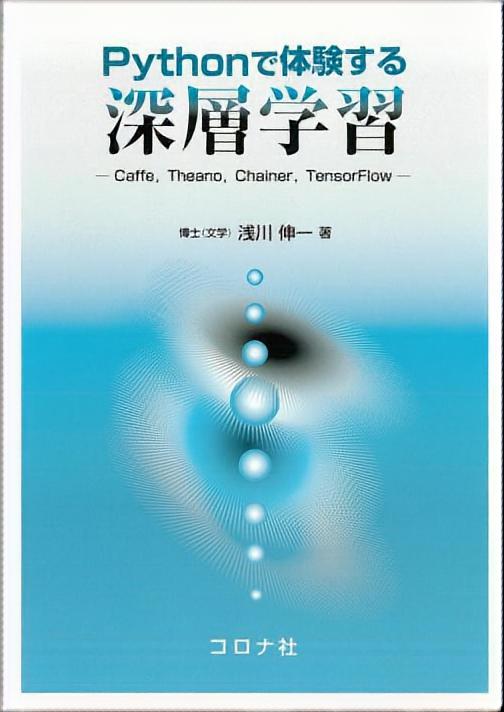
Pythonで体験する
詳細を見る
深層学習
- Caffe,Theano,Chainer,TensorFlow -ディジタル移動通信分野の開発・研究で世界的に有名な著者が,関連技術の初期の技術から最新技術までをその基礎と応用分野の全体像について,多くの数式や図表を用いて体系立てて詳説している。関連技術者・研究者にとっての必携書。
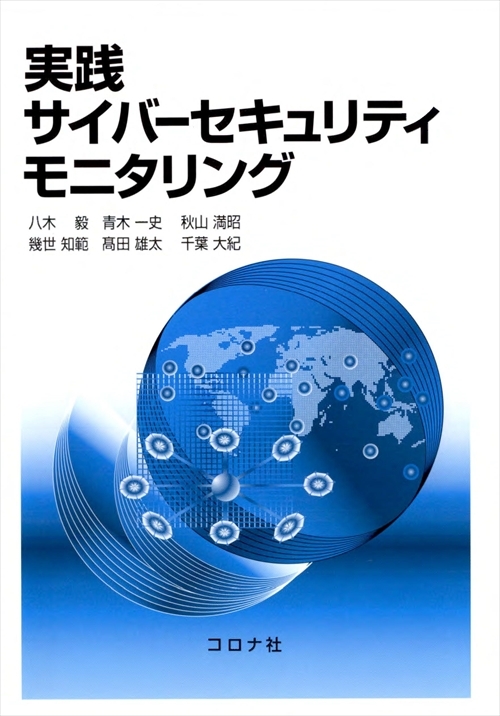
実践サイバーセキュリティモニタリング
詳細を見る本書では,マルウェア感染攻撃を中心に,攻撃を観測して解析する技術を演習を交えて解説した。本質的な検討方法や実践的な解析技術を学べるような構成とし,サイバー攻撃に対応するための実践力を身につけることができる。
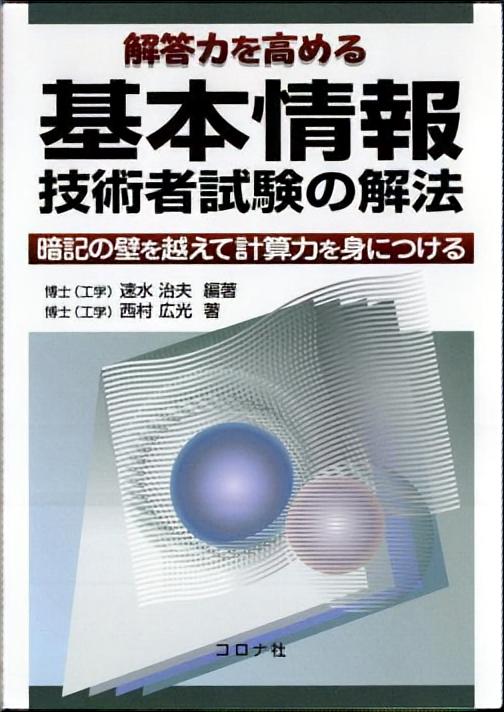
解答力を高める
詳細を見る
基本情報技術者試験の解法
- 暗記の壁を越えて計算力を身につける -資格取得には暗記で解くことができない計算問題を正しく理解して解けるかが大きく影響する。そこで,本書は暗記で足りる内容についてはまとめ程度とし,深い理解と応用力のある解法を習得することを目的としている。
マルチメディア(音響・信号処理・ゲーム・CG・映像・アニメーション・可視化・パターン認識・VRなど)
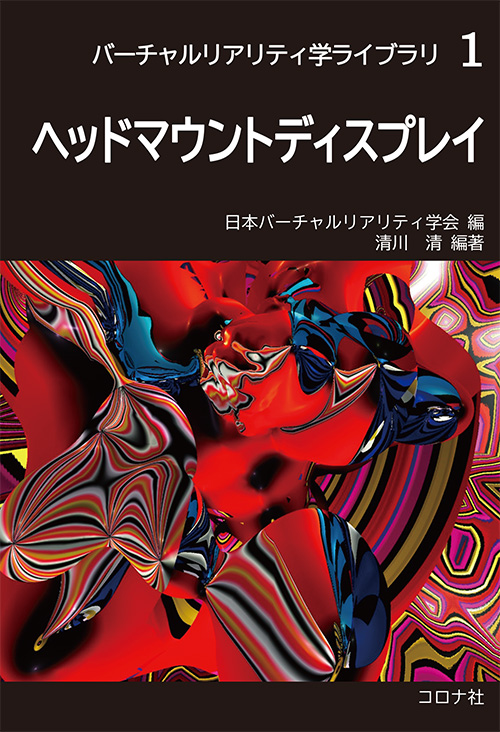
1.ヘッドマウントディスプレイ
詳細を見るヘッドマウントディスプレイは,VRやARを実現するための代表的なデバイスである。多種多様なHMDの違い,選択基準,性能や機能の進化,進化に伴う生活や社会の変化など,HMDを網羅的に取り上げた初めての書籍である。
2.神経刺激インタフェース
詳細を見るVRにおいて,感覚提示や感覚変容は非常に重要である。このような感覚を生じさせる仕組みが神経刺激インタフェースである。神経刺激には刺激するための目的がある。どのように研究されてきたのかを1冊で理解できるようまとめた。
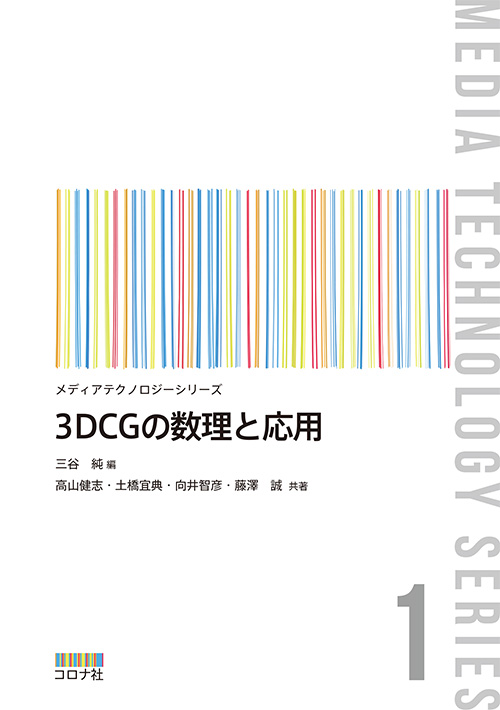
1.3DCGの数理と応用
詳細を見る3DCG技術を高度に使いこなし,さらに発展させるため,その基礎を支える技術を理解できるように,モデリング・レンダリング・キャラクタアニメーション・物理シミュレーションの4つの基礎要素に分け,それぞれ章ごとに解説した。
2.音楽情報処理
詳細を見る音楽情報処理に関する基礎的な解説に加え,音楽の創作(自動作曲,作曲支援・即興演奏支援,楽器演奏支援)から音楽の鑑賞(自動採譜,音楽鑑賞インタフェース)に関する具体的な研究事例を交えながら,その考え方や手法を紹介する。
3.可視化と科学・文化・社会
詳細を見る可視化という技術が実際どのように利用されているのかを科学・文化・社会という三つの分野に分け解説する。流体の可視化に始まり,有形文化財のディジタル保存,ソーシャルメディアデータの可視化など多岐にわたる実用例を掲載した。
4.ゲームグラフィックス表現技法
詳細を見るデジタルゲームのアーティストは,技術とアートを融合させた新たな表現を生み出す力が求められる。本書ではリアルタイムCGと映像表現手法の二つの側面からゲームグラフィックスがどのように表現されているか解説する。
5.シリアスゲーム
詳細を見る今後この分野の研究・開発に取り組む方々の共通基盤となる知見を提供する事に主眼を置き,シリアスゲームの成り立ちから展開,各分野の事例や新たな取組みを整理して論じるとともに,その意義や社会に起こした影響を解説。
6.デジタルファブリケーションとメディア
詳細を見る「デジタルファブリケーション」というデジタルデータをもとに制作を行う技術は製造からメディア,アートまで多岐にわたる領域で革新的な変化をもたらしている。本書では,その起源や技術,背景にある思想や今後の可能性を解説する。
7.コンピュータビジョン
詳細を見る
- デバイス・アルゴリズムとその応用 -メディアテクノロジーの発展において画像入出力デバイスとコンピュータビジョン技術は欠くことができない。本書では係る教科書において,これまで省略されることの多かった画像センサと人の一般生活環境への応用を詳述する。
8.サウンドデザイン
詳細を見る音のデザインは,視覚デザインに比べ,これまで裏方的な存在であった。本書では異なる分野で音を形作るサウンドデザインに携わる研究者らが,多面的かつ独自の専門性と視点に立ち,テクノロジーとしてのサウンドデザインを解説する。
9.音源分離・音声認識
詳細を見る人間は音を聞き分け,大事な音だけを理解する能力を持つ。技術の進歩に伴い,この能力をコンピュータで実現することが可能になりつつある。本書は音声に関わる多様な分野の研究者に向け,音声技術活用のノウハウを解説する。
10.音楽制作
詳細を見る
- プログラミング・数理・アート -AIの登場以前から用いられてきた音楽制作の技法にはじまり,プログラミングで音楽や音響を作り出す手法,作曲や音列の生成を数理の面から捉える分野,音を軸としたメディアアートなど,第一線で活躍の執筆陣が幅広く解説する。
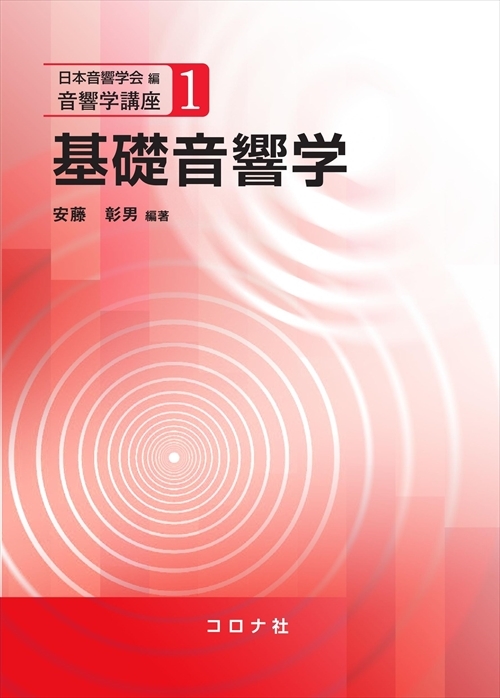
1.基礎音響学
詳細を見る物理学の一分野としての音響学の成立から現在に至る歴史について述べ,音の物理,聴覚に関する心理・生理について概説。さらに,計算機技術とともに発展した信号処理技術を解説した。最後に,音響学に関する数学を簡潔に紹介した。
2.電気音響
詳細を見る本書では,音響学における幅広い領域での根幹をなす技術について取り扱う。マイクロホンなどに用いられるトランスデューサの基本技術やその性能の計測技術,収音・再生技術,代表的な音響信号処理技術について概説している。
3.建築音響
詳細を見る音響物理の基礎事項のみならず,聴覚や聴覚心理の基礎に関わる内容や,建築物で利用される電気音響設備についても,建築音響学を学ぶうえで必要な範囲で網羅し,新しい研究成果も踏まえて,建築音響学として必須の事項を解説した。
4.騒音・振動
詳細を見る騒音・振動は,音響学の中でも広汎な学問分野を包含しており,現在もさらなる広がりを見せている。本書は大学院生および社会人向けの教科書として,大きく騒音,振動,低周波音の3分野に分け,それぞれ解説を行った。
5.聴覚
詳細を見る聴覚を環境音や音声から有益な情報を抽出する情報処理システムとみなし,おもに生理学・心理物理学的な立場から聴覚を理解できるように本書をまとめた。また、聴覚研究全体に通底する基本的な考え方や枠組みも理解できるようにした。
6.音声(上)
詳細を見る音声の教科書として利用できるように前半では,音声研究の歴史,基礎的な音声分析アルゴリズム,音声生成メカニズムとモデルなどについて詳細に述べた。また後半では,応用研究として音声合成,雑音除去について説明した。
7.音声(下)
詳細を見る上巻では音声の生成を取り扱ったのに対し,下巻では音声認識,話者認識,音声対話システムなどの音声の理解を取り扱う。Web検索や質問応答システム,対話型ロボットなどがその成果物である。これらとの関りで深層学習にもふれる。
8.超音波
詳細を見る超音波技術では,一般的な可聴域より大きな音圧の音波を扱うため,音波の非線形現象の発現が顕著である。本書は,超音波に特有のこの現象について理解を深め,次世代の超音波エレクトロニクスの発展に寄与することを目的としている。
9.音楽音響
詳細を見る本書は,学説的に固まった音楽音響の内容を5つの章に分けて記述した。楽器に関する音響学,音楽の心理学,音楽演奏の科学,情報処理技術を音楽分野に適用した音楽情報処理,そして音楽や音響技術と社会との関係である。
10.音響学の展開
詳細を見る本書では,音響学における新分野(熱音響,アコースティック・イメージング,音バリアフリー,音のデザイン,音響教育,生物音響)を紹介することで,音響学の諸分野を俯瞰する。音響学の広がりや多様性を感じることのできる一冊。
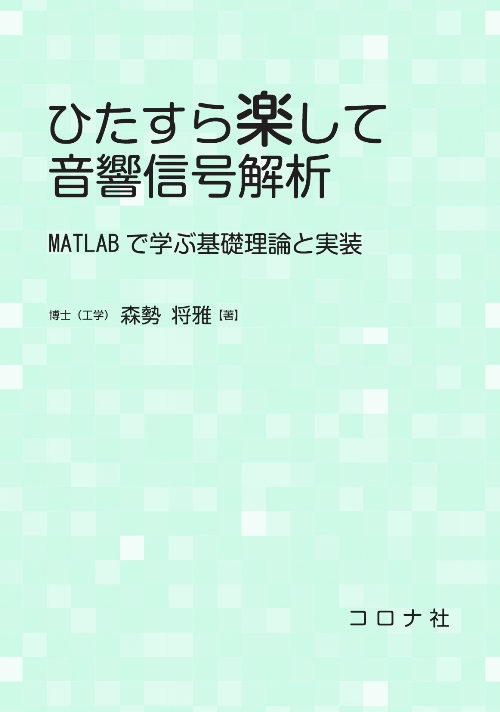
ひたすら楽して音響信号解析
詳細を見る
- MATLABで学ぶ基礎理論と実装 -本書では,1次元の信号処理の基本となる「フーリエ解析の数学的基礎」,「信号処理の原理と使い方」,「Pythonによる科学技術計算の基礎」について解説しており,専門的な信号処理を学ぶ土台となる知識を得ることができる。
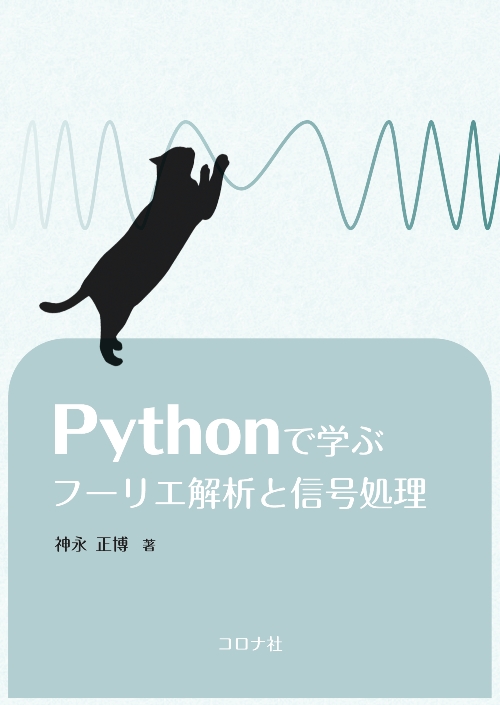
Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理
詳細を見る本著は,演習を通して実践的に学ぶ,MATLABによるディープラーニング入門書である。大学教養数学やプログラミングの経験があると理解しやすいが,その不足分を補う勉学意欲があれば,実践力が育まれるよう工夫して書いている。
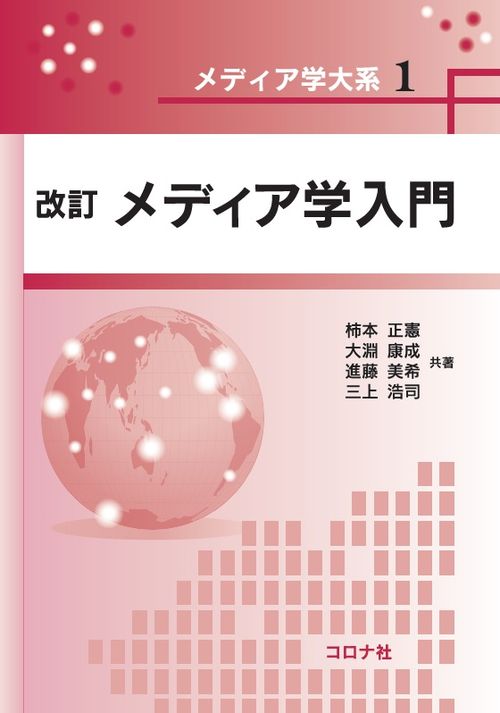
1.改訂 メディア学入門
詳細を見る本書では「メディア学」という枠を超えた学問領域を,その根底にあるディジタル技術を軸に,技術(理工系),コンテンツ(芸術系),社会(文系)の切り口で各分野の概要を解説。本改訂では分野ごとに章を細分化し構成を一新した。
2.CGとゲームの技術
詳細を見る本書は,ゲーム開発の歴史的経緯から現在のゲーム産業界の現状・企画・開発そしてリアルタイムCG技術まで,ゲーム開発に関わるさまざまな要素技術を総合的に学ぼうとする人を対象としたゲーム開発とCG技術のテキストである。
3.コンテンツクリエーション(改訂版)
詳細を見るアニメ,ゲーム,映像等のメディアコンテンツの産業構造と,シナリオライティング,キャラクターメイキング,演出等の具体的なコンテンツ制作技術を解説。本改訂では,各種制作支援システムを公開し,事例や実践的な解説を追加した。
4.マルチモーダルインタラクション
詳細を見る本書は,人が持つ視覚・聴覚など複数の感覚器を通して行われるコンピュータとのインタラクションコミュニケーションを可能にするための基礎理論と,それを支える要素技術についてわかりやすく解説している。
5.人とコンピュータの関わり
詳細を見るコンピュータは,人につねに関わるものとなり,その用途が生活のあらゆる局面に及ぶように拡大してきた。本書では,これまでのそうした変遷の内容を知り,人の意識や行動指針への影響を多様な視点から解説した。
6.教育メディア
詳細を見るICT(情報通信技術)の発展により,教育環境が大幅に変化し,新しい教育の枠組みが求められている。本書はICT教育のあり方から今後必要とされるICTを活用した教育方法までをわかりやすく解説している。
7.コミュニティメディア
詳細を見るインターネットの発展により,コミュニティは世界的な価値創造の場となっている。本書では,現代社会において重要な存在となったコミュニティの本質を,歴史をさかのぼって,多角的に解説するとともに,その可能性を検討する。
8.ICTビジネス
詳細を見る社会経済活動データを編集・分析する方法とプログラミング(AADL)を習得し,行政・企業の統計データを分析してシミュレーションに発展させる方法を学ぶ。社会学習ダイナミクスやトランザクションベース計測についても解説した。
9.ミュージックメディア
詳細を見る私たちの生活には音楽があふれている。音楽文化とメディアの関わりに加え,音楽産業がどのようなしくみになっているのか,さらには楽曲構成に関する基礎的な知識の解説とともにさまざまな音楽表現のあり方についてまとめた。
10.メディアICT(改訂版)
詳細を見るメディアサイエンスを支える基幹技術であるICTを整理し,情報科学とネットワークに関する基本的なリテラシーを身に付けるための内容を網羅。本改訂では情報をアップデートし新たに登場した様々なトピックを随所に盛り込んだ。
11.CGによるシミュレーションと可視化
詳細を見る本書はCGアニメーションにおいてダイナミックで写実的なシーンを生成するためのシミュレーション技術,およびその可視化技術について概説する。また,Houdini上でアルゴリズムを用いて図形形状をデザインする例も紹介した。
12.CG数理の基礎
詳細を見る本書は,CGの原理を理解するための基礎固めとなる技術に焦点をあて,広い範囲をカバーしながらもトピックは絞り込み,それぞれを深く掘り下げて解説した。初学者だけでなく,技術系・制作系クリエイターを志す方にも最適。
13.音声音響インタフェース実践
詳細を見る信号の基礎理論とその具体的応用,および信号処理を応用したインタフェースについて丁寧に解説し,実践を通して基礎理論の理解が深まるよう構成した。最近の音声認識や機械学習,最先端のディープラーニングについても紹介。
14.クリエイターのための 映像表現技法
詳細を見る様々な映画作品を例に演出,編集,撮影,特撮,CG,アニメーション,ライブイベント,美術デザイン,AR,VR等の技術を解説するとともに制作現場,脚本やプロデューサの仕事,市場拡大を続ける動画配信サービスについても紹介。
15.視聴覚メディア
詳細を見るよいメディアコミュニケーションとは,情報発信者の意図を受信者が正確にとらえることができる状態である。本書では,我々の視聴覚における認知的特徴をふまえ,伝えたい情報を正確かつ効果的に「魅せる」表現手法について解説する。
17.メディアのための物理- コンテンツ制作に使える理論と実践 -
詳細を見るメディアコンテンツの制作に携わる人が,前提として身に付けておくべき物理学の基礎をまとめた。物理学の知識を用いて,現実を表面的に観察し,背景にある理論に従って物や人を動かすことで制作物のクオリティを上げることができる。
18.メディアのためのアルゴリズム- 並べ替えから深層学習まで -
詳細を見るアルゴリズムの基本的な考え方から,さまざまな分野で使われる代表的なアルゴリズム(並べ替え,データ探索,経路探索,データの圧縮と展開,誤り検出・訂正,セキュリティ・暗号),人工知能や機械学習に関する内容まで丁寧に解説。

マルチメディアシステム概論
詳細を見る
- 基礎技術から実用システム,VR・XR まで -マルチメディア(文字,音声,音楽,画像,映像などの情報)を伝達・記録するシステムの重要な要素技術群の基礎を広くしっかりと習得できるよう意図し,アナログ技術からディジタル技術,インタフェースについて記述した。
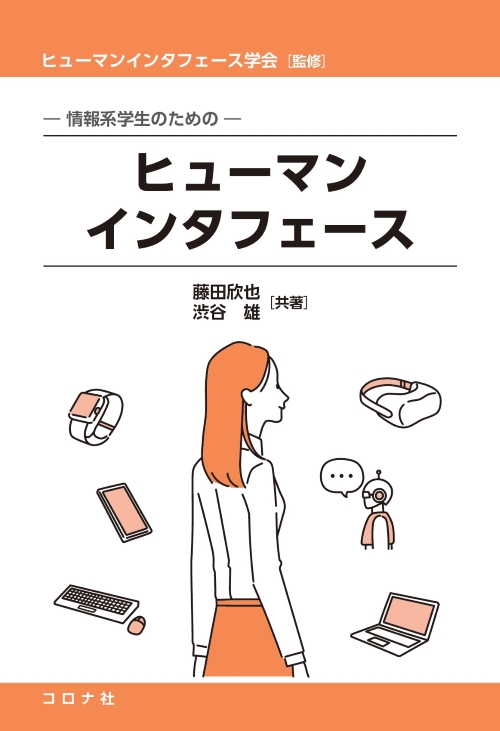
ヒューマンインタフェース
詳細を見るヒューマンインタフェース(HI)とは機械と人との接続部を意味する。本書ではHI の歴史や人と情報システムに関する基礎から始め,HI デザインの原則やデザインプロセスを学んだ後に,今後のHI を概観する構成としている。
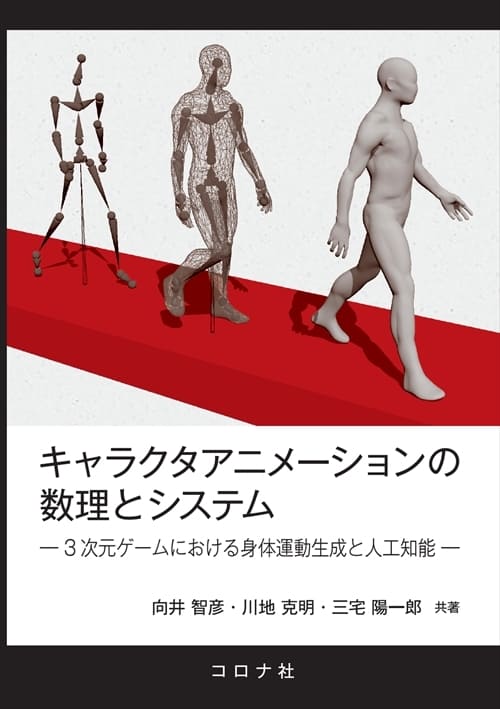
キャラクタアニメーションの数理とシステム
詳細を見る
- 3次元ゲームにおける身体運動生成と人工知能 -本書では,動的なキャラクタアニメーションを担うソフトウェアシステムに必要な技術要素とその構成方法について初めて学ぶ読者を対象に,インタラクティブな3次元CGの映像における,キャラクタの動きを生成する技術を解説した。
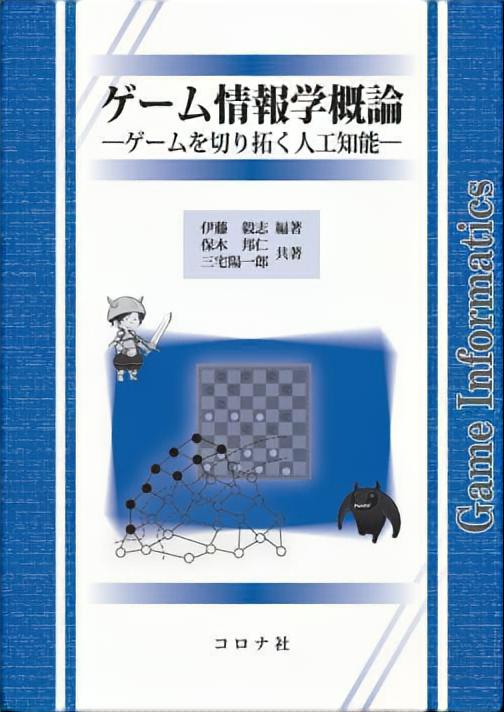
ゲーム情報学概論
詳細を見る
- ゲームを切り拓く人工知能 -ゲームは,古くから人工知能,認知科学の中心的な研究テーマとして扱われてきた。本書では,まずこの研究分野の基礎的な知識と歴史を押さえ,それを支える重要な理論について述べ,デジタルゲームの応用分野まで概観する。
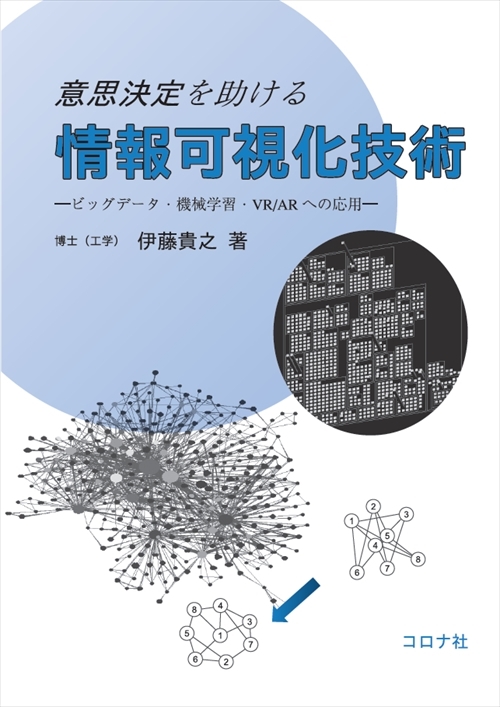
意思決定を助ける
詳細を見る
情報可視化技術
- ビッグデータ・機械学習・VR/ARへの応用 -情報可視化技術はCGやGUIによりデータの理解を助ける技術であり,あらゆる業務の意思決定や仮説検証を助けるツールである。本書は,情報可視化の基本からIT業界の各種技術分野への応用に至るまでを紹介する意欲作である。
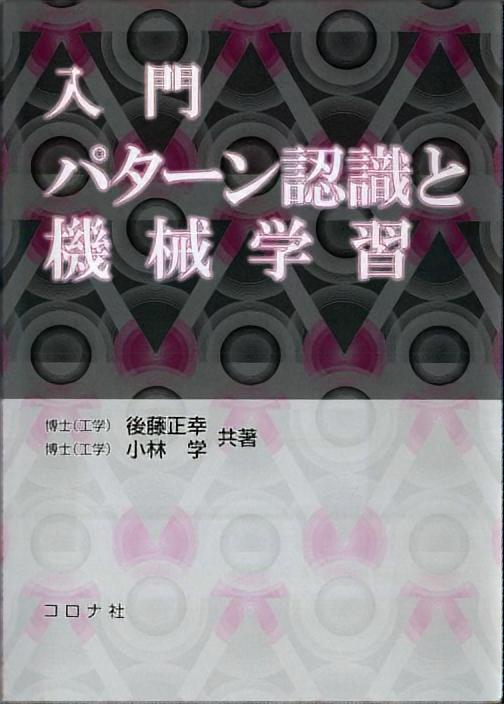
入門 パターン認識と機械学習
詳細を見る初学者が一通りのパターン認識と統計的学習の基礎について学ぶことができるよう,基礎的な内容に絞って記した。パターン認識の方法を実装し,実際のデータを分析し,手法を改良できるよう,WebでC言語プログラムを公開した。
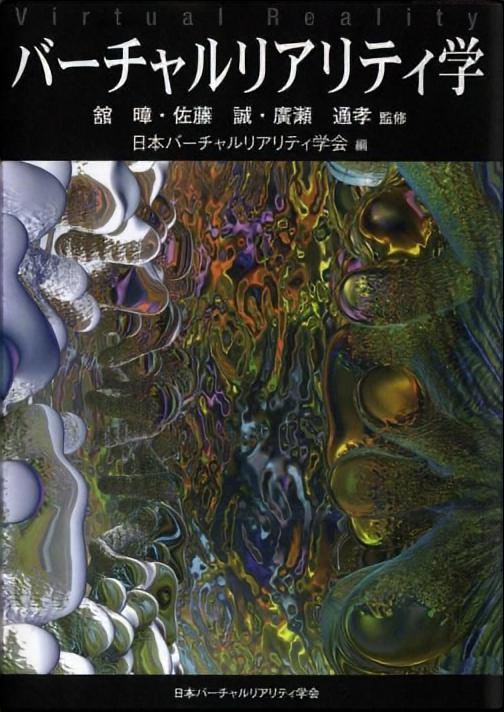
バーチャルリアリティ学
詳細を見る普遍性,一般性のある事柄を中心にまとめ,前半でVRの考え方,システムの原理,人間の認識と行動の仕組みなどの基礎を,後半で臨場感通信などの実世界と関連するVRの展開と,VRの社会との関連やその未来に関して学習できる。
シリーズ:バーチャルリアリティ学ライブラリ
シリーズ:メディアテクノロジーシリーズ
シリーズ:音響学講座
シリーズ:メディア学大系
モビリティ(サービス・自動運転・ドローン・モデルベース・電気鉄道など)
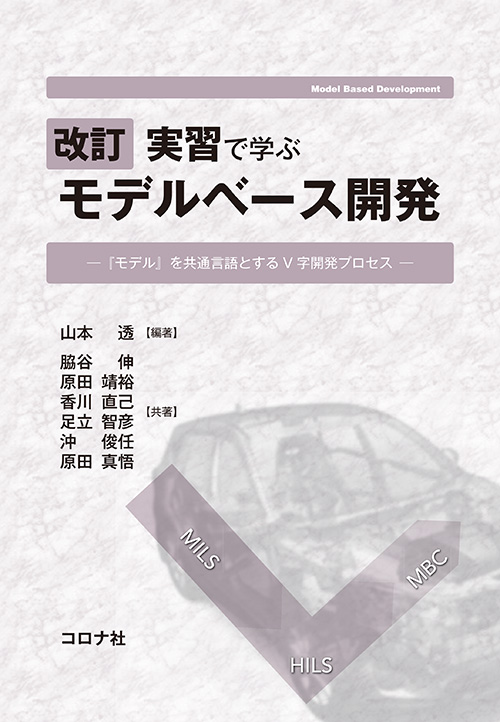
改訂 実習で学ぶ
詳細を見る
モデルベース開発- 「モデル」を共通言語とするV字開発プロセス -製品設計にシミュレーションモデルを用いるモデルベース開発(MBD)について,MATLABを用いて体験的に学習できる良書の改訂版。HILシミュレータなどもWebで提供し,今回の改訂ではスマートMBDについても紹介した。
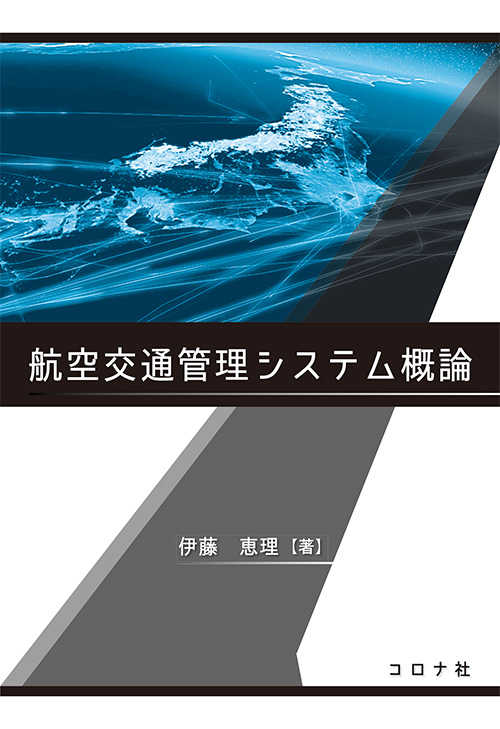
航空交通管理システム概論
詳細を見る航空交通管理の成り立ちと現状,システム設計と評価に関わる研究開発,社会実装に至るプロセスと課題を概観して論じる。さまざまな専門分野の読者を想定し,知識の有無に関わらず,航空交通管理分野の体系を学ぶことができる。
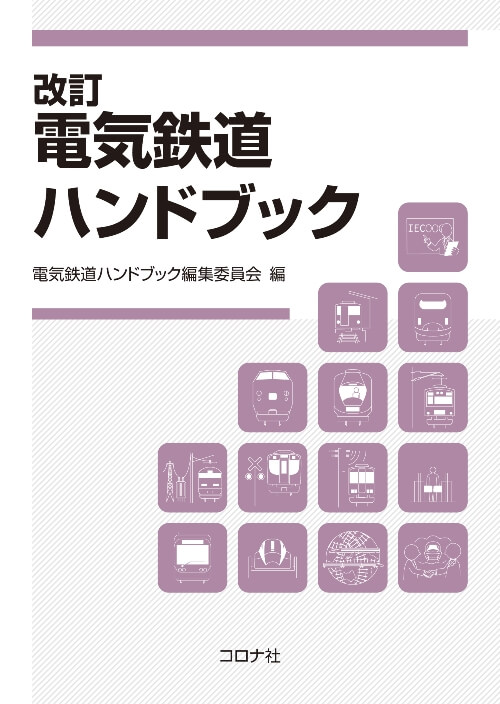
改訂
詳細を見る
電気鉄道ハンドブック電気鉄道の技術はもちろん,営業サービスや海外事情といった広範囲にわたる関連領域の内容も網羅した関係者必携のハンドブック。改訂にあたり,技術内容や規格類の更新をし,さらに日本の技術を海外展開するための知識を充実させた。
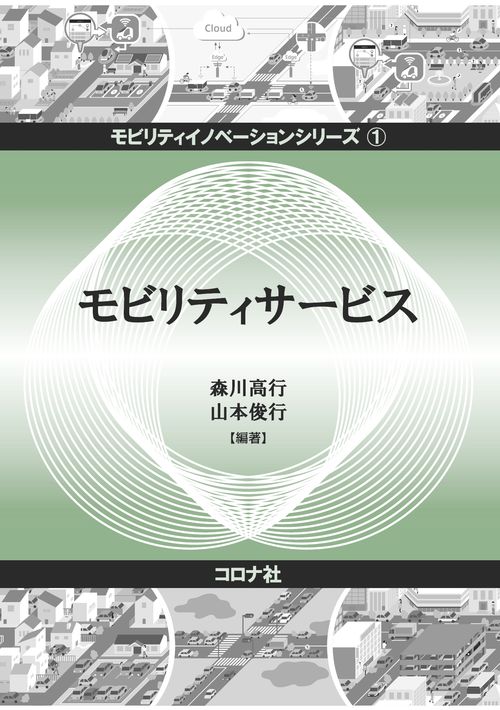
1.モビリティサービス
詳細を見る本書では,人間の活動における移動の意味を問いかけ,移動の歴史とその価値,交通サービスや自動車の歴史を解説した。また,今後,重要性が増してくるパーソナルモビリティビークルやモビリティのサービス化についても紹介した。
2.高齢社会における人と自動車
詳細を見る社会課題である高齢ドライバによる交通事故について,加齢変化による身体機能や認知機能,持病や服薬の運転への影響など個人差に関する研究動向と知見をまとめた。免許返納や運転制限による健康への影響や哲学的な側面も俯瞰した。
3.つながるクルマ
詳細を見る自動車が通信ネットワーク等により外部と情報をやりとりする(つながる)ことで,さまざまな付加価値がうまれる。本書では,つながるクルマのサービス,技術,システムを体系化して解説し,その現状と今後を俯瞰することを目指す。
4.車両の電動化とスマートグリッド
詳細を見る本書の前半(第I編)では,電動車両を復活に至らしめた最新の技術について解説した。本書の後半(第Ⅱ編)では,電動車両をエネルギーマネジメントに活用することを目的とした最新の研究について紹介した。
5.自動運転
詳細を見るカメラやセンサなどによる周辺環境や運転者の状況認識,それらをもとにした走行軌道の計画,計画に対して正確に走行するための制御という,自動運転の実現に必要な技術的要素だけでなく,それに伴う法制度についても解説した。
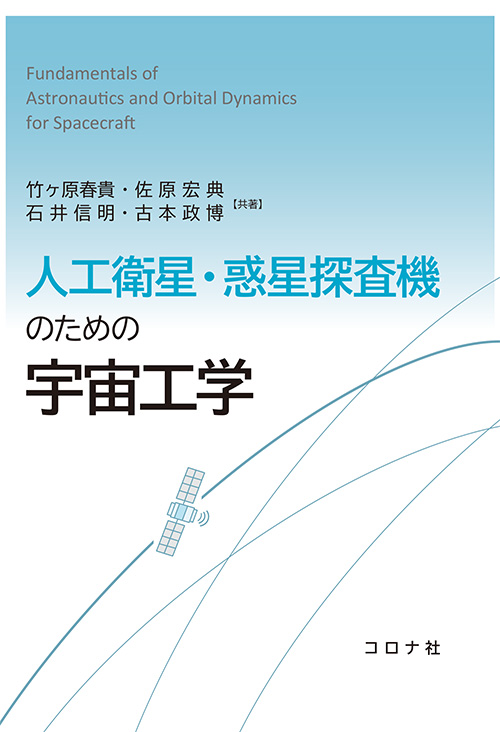
人工衛星・惑星探査機のための宇宙工学
詳細を見る天体運動の基礎から,気象衛星や観測衛星に代表される地球周回衛星や,惑星,衛星などを探査する宇宙探査機の地上からの打上げ,目標軌道への投入などを題材に,基礎となる数学・物理がどのように宇宙工学につながるのかを解説した。
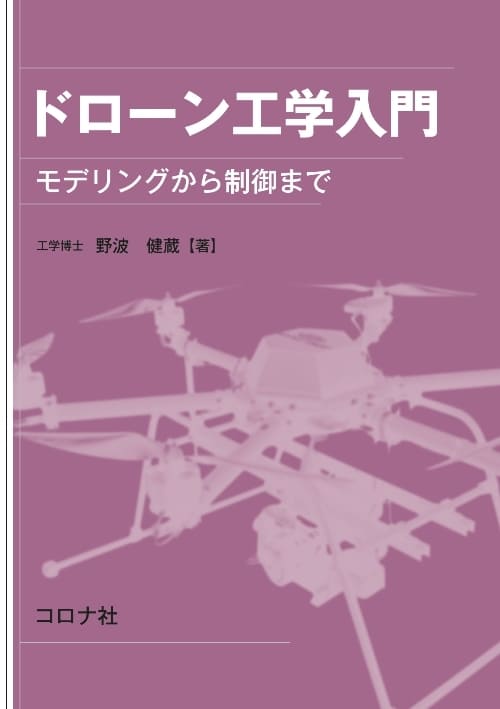
ドローン工学入門
詳細を見る
- モデリングから制御まで -ドローンの進化と利活用が急速に進んでいる。本書ではドローンを操るソフトウェアであるオートパイロットに代表される自律制御技術に注目し,第一線の著者が蓄積してきた技術を中心にヘリコプタやマルチコプタの制御までをまとめた。
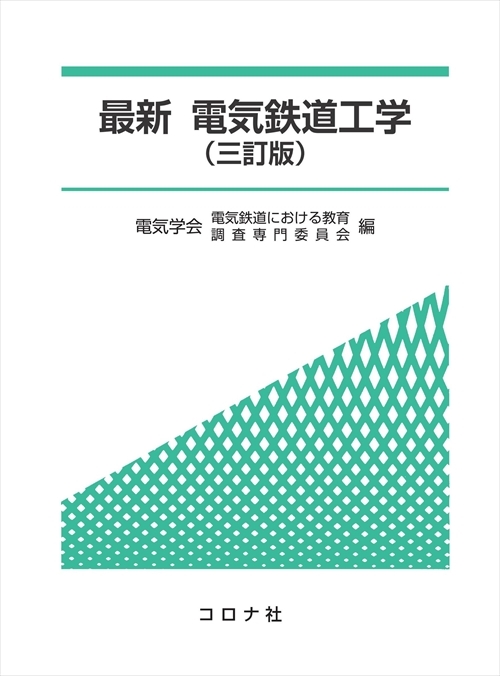
最新 電気鉄道工学
詳細を見る
(三訂版)わが国の電気鉄道は,エレクトロニクス等の技術進歩により一層の高速化と快適性・安全性向上が進んでいる。本書は,電気鉄道を支える技術全般を解説している。三訂版にあたり新しい技術と海外の鉄道技術について改訂を行った。
シリーズ:モビリティイノベーションシリーズ
ロボット
- 詳細を見る

ロボット工学ハンドブック(第3版)特集
詳細を見る- 詳細を見る
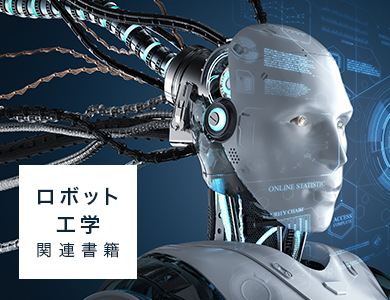
ロボット工学 関連書籍 特集ページ(2023年1月更新)
詳細を見る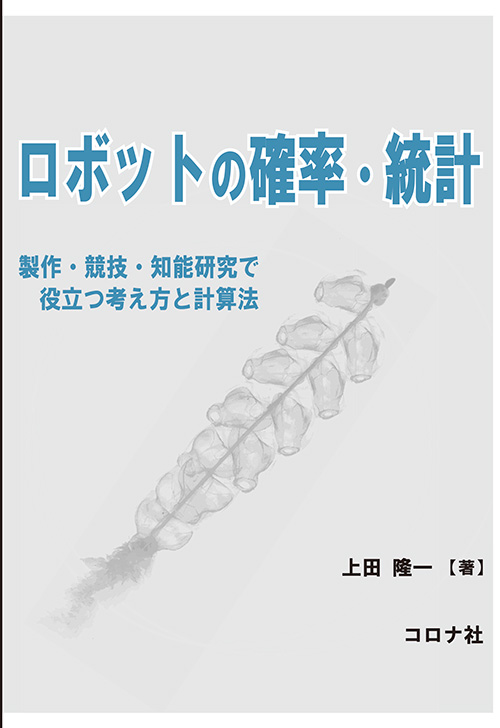
ロボットの確率・統計
詳細を見る
- 製作・競技・知能研究で役立つ考え方と計算法 -ロボティクスには広大な範囲の知識が必要とされます。本書では,ロボットの組立て,制御やセンサ処理のプログラミング,性能評価,ロボコンでの作戦など,ロボットだけに限定して,様々な確率・統計の知識を学ぶことが目的です。
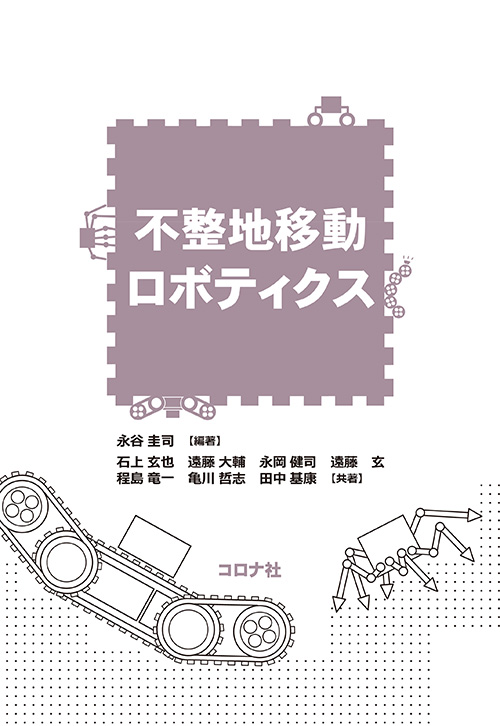
不整地移動ロボティクス
詳細を見る不整地移動ロボットを体系的に扱う書籍。各分野で定義がまちまちだった「不整地」の定義と分類を行い,不整地移動ロボットの代表的な移動形態である「車輪型/クローラ型」,「脚型」,「ヘビ型」の機構や力学,制御を広範に解説。
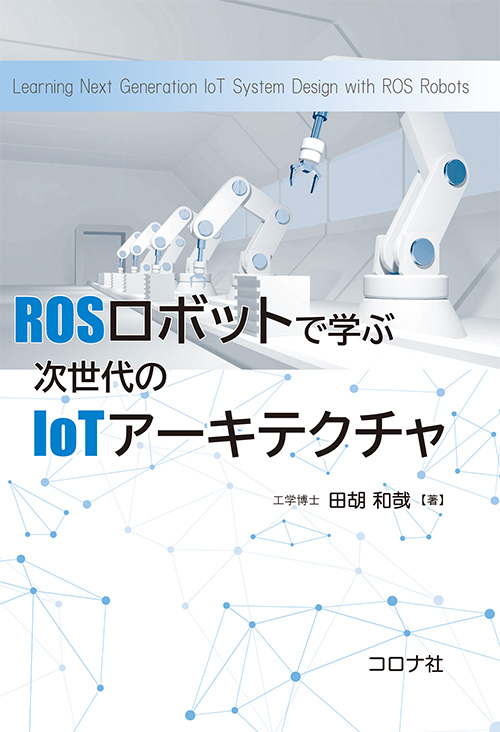
ROSロボットで学ぶ次世代のIoTアーキテクチャ
詳細を見るアーム付き自律移動ロボットを例にとり,その構成要素(ハードウェア,ナビゲーション機構,アーム制御機構,機械学習,システムアーキテクチャ)を原理に基づいて学ぶことで,IoT システムの全体像を理解できるよう解説した。
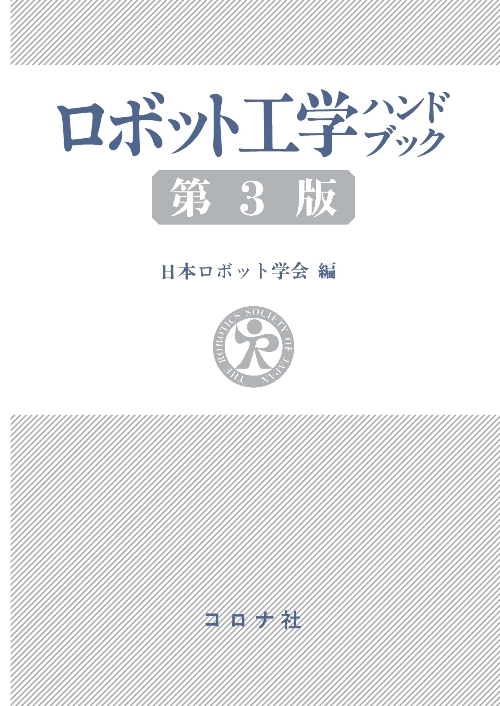
ロボット工学ハンドブック
詳細を見る
(第3版)Pythonによるプログラミングを行いつつ人工知能、機械学習の仕組みを学ぶ。新しい技術である「追加学習」のやさしい解説を通して、現在の機械学習が抱える問題点・限界を示し、読者により深い理解をもたらすことを目指す。
機械工学(塑性加工・腐食防食・CAE・振動・技術士・CFRTP・材料・設計など)
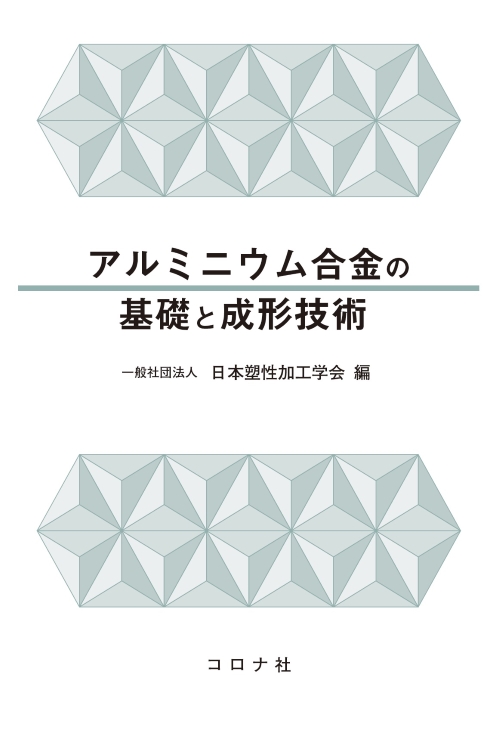
アルミニウム合金の基礎と成形技術
詳細を見るアルミニウムにかかわる機械系の技術者・研究者だけでなく,学生や新入社員など幅広い方々も読めるよう基礎から丁寧に,アルミニウムの特性,合金化,鋳造加工,圧延・板成形,押出し加工,接合,表面処理などの成形技術を紹介する。
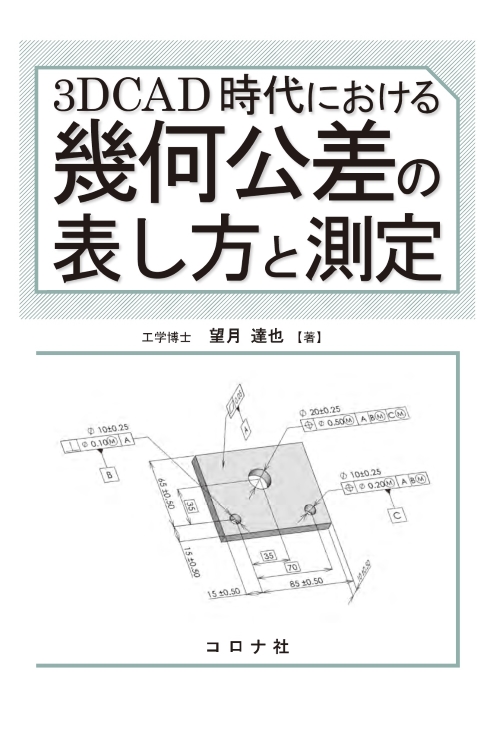
3DCAD時代における
詳細を見る
幾何公差の表し方と測定本書では,正確なものづくりに欠かせない機械製図における幾何公差の具体的な表し方と機械加工した部品の測定評価について丁寧に解説。さらに巻末には豊富な演習問題と詳細な解答・解説を掲載して理解度を深められるようにした。
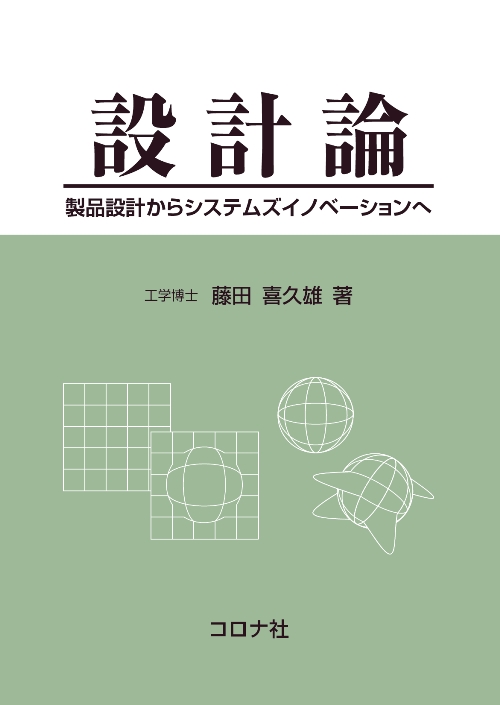
設計論
詳細を見る
- 製品設計からシステムズイノベーションへ -イノベーティブな製品・サービス・経験を生み出すための「設計工学」指南書。設計対象をシステムととらえ,いわゆる「設計学」や「デザイン学」の分野を横断し,汎用可能な知として議論の展開を行った。設計・デザインに携わる方必携!
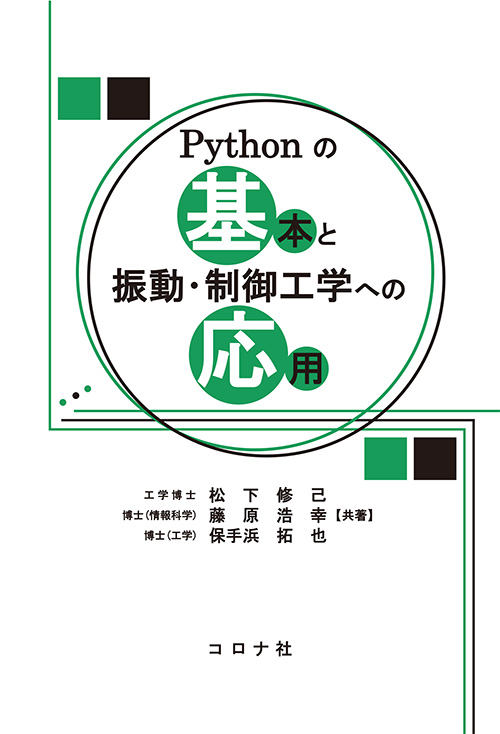
Pythonの基本と振動・制御工学への応用
詳細を見るビギナーのためにPythonのインストールから始め,簡単な四則演算,グラフ描画,ファイル入出力などを紹介し,微分方程式やラプラス変換,フーリエ変換,固有値問題なども解いていく。さらには振動工学,制御工学の問題も扱う。
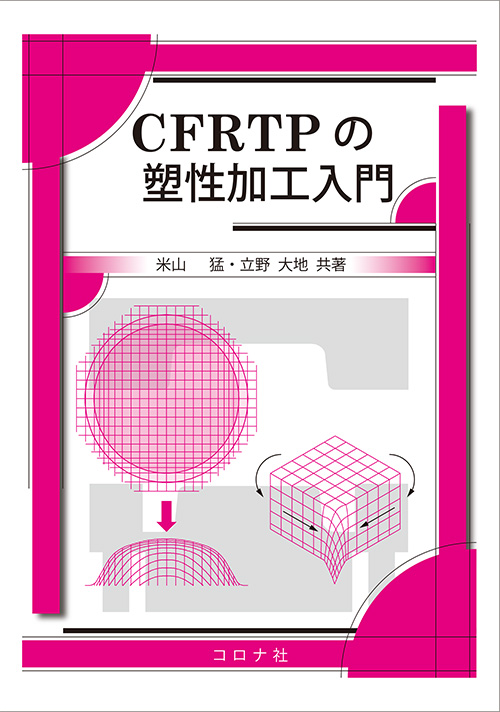
CFRTPの塑性加工入門
詳細を見るCFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂)は,軽量・高強度でリサイクルが可能な材料として,量産加工法の開発が期待されている。本書では塑性加工の手法を使って, CFRTPの量産加工を実現する方法について解説する。
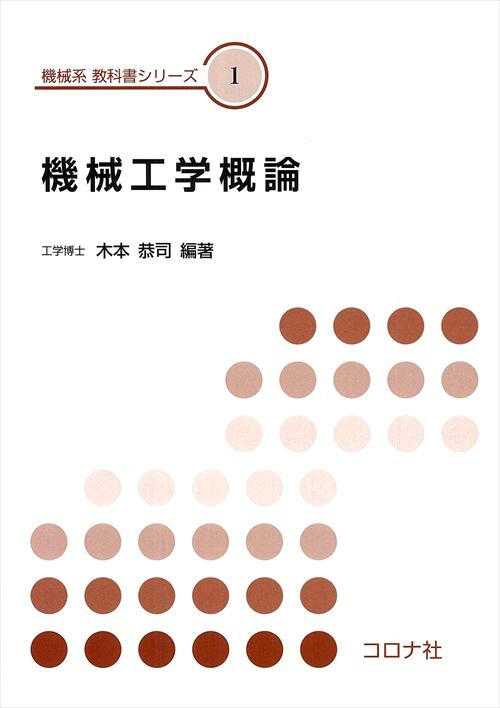
1.機械工学概論
詳細を見るまず,機械と人間とのかかわりについて概観し,つぎに機械工学の柱となる力学類(工業力学,材料力学,流体力学,熱力学)に触れる。さらに,機械材料,機械設計法,機械工作法,計測・制御,メカトロニクスの諸分野をまとめた。
2.機械系の電気工学
詳細を見る本書は,複雑な数学を用いずに図を使って電磁気現象を説明し,電気工学の基礎をわかりやすく解説した。豊富な例題により,電磁界の公式の使用方法を容易に理解することができる。また,自習のために,問に対する詳細な解答を付けた。
3.機械工作法(増補)
詳細を見る「ものの作り方」を知ってもらうために,機械工作法の主要な分野をわかりやすくまとめて解説した。鉄鋼など金属材料各種の加工法とプラスチック成形法を解説している。増補に際しては熱処理,材料学を付録として追加した。
4.機械設計法
詳細を見る本書は機械設計教育の中心である機械要素と材料の強さに関する内容を厳選し,必要最低限記述した。また,学習したらすぐに演習問題に取り組むことで本文への理解を深めるとともに,問題解決力を養えるよう配慮してある。
5.システム工学
詳細を見る本書は,機械・情報系学生のために,システム工学を工学基礎としてやさしく取らえ,記述した。特に遺伝的アルゴリズムやニューラルネットワークを最適化の視点から解説し,最近のシステム工学の研究・実用化についても述べた。
6.材料学(改訂版)
詳細を見る初めて材料学を学ぶ方向けに,金属,高分子,セラミックス,複合材料のそれぞれの分野を幅広く扱い,基礎的な知識を持ったうえで,専門的に深く追究すべきとの考えに基づいてまとめた。改訂版ではおもにJISの規格の更新を行った。
7.問題解決のためのCプログラミング
詳細を見るコンピュータの初心者が,その歴史からプログラミングの構造化やアルゴリズムとデータの処理を楽しく学べるようにまとめた。さらにグラフィックス,代数方程式や数値積分などの実際的な問題の解法を意識したプログラム例を示した。
8.計測工学(改訂版)新SI対応
詳細を見る情報の獲得と操作という視点を重視し,制御を目的とする計測技術を中心に,応用分野の広い基礎的な測定技術や原理をできるだけ体系的に解説した入門書。2019年のSI改訂に伴い基礎物理定数に基づく再定義に対応した。
9.機械系の工業英語
詳細を見る高校程度の英語から始め,英語学術論文の理解までを目指した高専・大学用英語学習教科書。通読することで,機械工学概論など工学全般の内容も学習できるようにした。各単元を見開き2頁とし,授業の際に活用しやすいよう配慮した。
10.機械系の電子回路
詳細を見る本書は,機械・メカトロニクス系の学生でこれから電子回路を学び始める方を対象としている。電子回路の基本的な考え方と半導体デバイスの特性から,電子回路を組み立てる手法が理解できるようにやさしく解説した。
11.工業熱力学
詳細を見る本書は,図やグラフを多用して,熱と仕事などの基礎概念や熱力学の法則,エントロピーおよび熱機関への応用などについてわかりやすく述べている。また,自習用としても使えるよう演習問題を数多く設け,詳しい解答をつけた。
12.数値計算法
詳細を見る数値解析法全般を平易に具体的に解説した入門書である。機械工学科の学生が利用しやすいよう機械工学分野の例題や問題をできるだけ多く取り入れるよう配慮した。主な手法に対してはFortranによるプログラムリストを示した。
13.熱エネルギー・環境保全の工学
詳細を見る本書では,エネルギーの資源・変換技術・環境保全の工学的役割について述べている。さらに,熱源を輸送,貯蔵に利用する冷熱技術,環境化学の立場からは環境保全対策についても述べている。
15.流体の力学
詳細を見る流体の力学を初めて学ぶ学生のための入門書として,わかりやすくかつ基本的な理論体系を崩さないように配慮した。各章ごとに何を学ぶのかを明確にし,章末には重要ポイントを示した。また,演習問題を設け,詳細な解答をつけている。
16.精密加工学
詳細を見る本書は,精密なものを作るということをテーマに,精密測定,精密工作法,工作機械の3分野の理論の基本的で実用的な部分をまとめたものである。誤差が生じる原因,工具のあり方,工作機械のあり方,加工用工具各論などを解説した。
17.工業力学(改訂版)
詳細を見る好評本の改訂版。改訂に際し,特に重ね合わせ法の基礎となる力やモーメントの置換え,機械要素の基礎である軸受の抵抗,また仮想仕事の原理および等価質量,等価ばねの概念などがより深く理解できるよう例題の内容と数量を強化した。
18.機械力学(増補)
詳細を見る本書は主に振動に関連する内容を取り入れた。振動を学ぶ目的の一つとして,機械や交通機関から発生する振動や地震における建物の振動などの解決がある。これらを踏まえ基礎的事項を中心に解説した。増補では章末問題を増やした。
19.材料力学(改訂版)
詳細を見る材料力学は,ものづくりの根幹を構成する基礎的科目であり,また安全性や信頼性といった領域とつながる学問である。今回の改訂ではモデルコアカリキュラムにも対応できる内容とし,学力が身につくよう演習問題も豊富に用意した。
20.熱機関工学
詳細を見る本書では基本的な事柄を重視し,ボイラ,蒸気タービン,内燃機関,原子力発電の各種形式,動作および構造についての必要事項を平易に記述した。また,自習できるように章末の演習問題についてはできるだけ詳しい解答例を巻末に載せた。
21.自動制御
詳細を見る制御工学は要素自身の表現法や総合するための方法など多岐にわたる学問であり,統合力を養うことが大切である。本書では制御系の設計につながる工夫として,多くの章で水位制御系を例に取り上げ,理解しやすくなるよう心掛けた。
22.ロボット工学
詳細を見るロボットの制御に必要な理論から実際の制御及びシミュレーションモデルの作成方法までを解説し,例題,演習問題を数多く掲載し,解答も詳しく記述した。また,実際に制御するために必要なプログラム例を示し,実践的な内容とした。
23.機構学
詳細を見る機構学の目的は,モータなどの動力源で生成した回転運動や直線運動を所望の運動に変化する仕掛を解析したり,作ることである。本書は初学者の数学レベルで理解できるよう例題と演習に重点を置いて平易に解説した。
24.流体機械工学
詳細を見る本書は流体機械に対する理論的アプローチを学習することをねらって書かれている。数式はできるだけ基本から解説することにより,説明に飛躍がないようにした。さらに,揚力の発生原理をできるだけ厳密に解説しているのが特徴である。
25.伝熱工学
詳細を見る本書では,伝熱工学の基礎が修得できるように,熱伝導,熱放射をはじめとするいろいろな熱伝達や,対流伝熱にかかわる物質輸送を扱っている。また演習問題と解答を充実させ,自学自習用の演習書としても活用できるよう工夫した。
26.材料強度学
詳細を見る本書は,金属材料を対象とし,静的強度,疲労,クリープなどを取り上げ,材料強度の基礎的事項や考え方を説明するとともに,材料強度学を学ぶうえで必要な破壊力学や信頼性工学的取扱いなどの基礎的事項を説明したものである。
27.生産工学- ものづくりマネジメント工学 -
詳細を見る生産管理,インダストリアル・マネジメント,コストを考えた改善技法などのものづくり技術を含んだ考え方と方法をわかりやすく説明した。
28.CAD/CAM
詳細を見るモノづくりとCAD/CAMの関係を中心に、3DプリンターによるモノづくりやCAD/CAMにおけるデータ管理とPDM/PLMまでの一連の流れを説明し、演習問題を付け設計・製図やモノづくりの授業で活用できるよう工夫した。
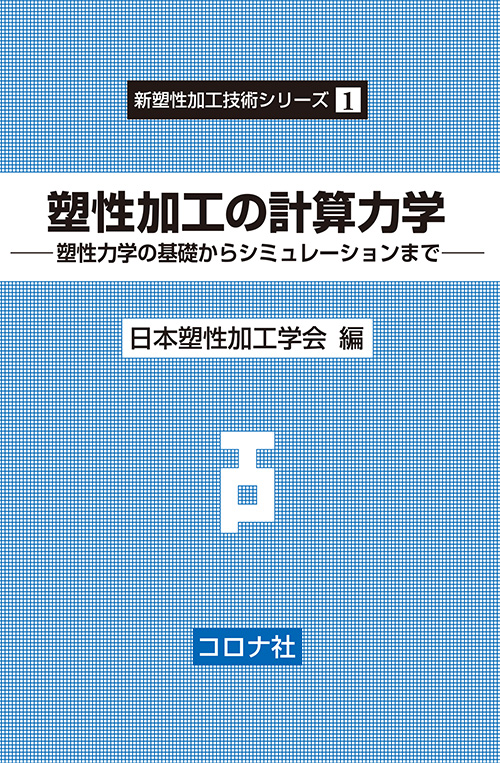
1.塑性加工の計算力学 - 塑性力学の基礎からシミュレーションまで -
詳細を見る初めに塑性加工の歴史と塑性力学の発展を俯瞰し,つぎに塑性理論から初等解法,そして数値解析,シミュレーション高度化に対応した実験手法,解析精度の検証と評価のための考え方(V&V)と順を追って理解が深められる構成とした。
2.金属材料 - 加工技術者のための金属学の基礎と応用 -
詳細を見る材料の基礎のほか,多様性のある鉄鋼材料を主に材料開発の動向や,塑性加工技術と材料技術の融合で生まれた組織材質予測技術とホットスタンピング技術についても解説。これからの塑性加工技術者に備えてほしい金属材料の知識を集約。
3.プロセス・トライボロジー - 塑性加工の摩擦・潤滑・摩耗のすべて -
詳細を見る摩擦・潤滑の基礎,および塑性加工における潤滑問題を平易に解説。工具と素材の表面テクスチャーが潤滑に及ぼす影響や熱間圧延における酸化膜の潤滑効果,振動・サーボプレスによる潤滑効果,ホットスタンピングなどについても解説。
4.せん断加工 - プレス切断加工の基礎と活用技術 -
詳細を見る好評だった「せん断加工」(塑性加工技術シリーズ)の内容を新たに見直し、高強度鋼板やマグネシウム合金などの新材料のせん断加工技術,進歩の著しいサーボプレス機械などの塑性加工機械の紹介やその活用技術に関する内容を加えた。
5.プラスチックの加工技術 - 材料・機械系技術者の必携版 -
詳細を見る「プラスチックの溶融・固相加工」(塑性加工技術シリーズ)にて紹介されていた内容を新技術やデータ等の更新の観点から全面的に見直し,さらに複合材料の成形やリサイクル技術に関する内容を加えた。
6.引抜き - 棒線から管までのすべて -
詳細を見る本書は,「引抜き」に関する理論,製造技術,材料,解析方法,機器・設備などを紹介・解説。旧版である「引抜き加工」(1990年,塑性加工技術シリーズ)刊行以降に得られた多くの新しい技術情報を盛り込んだ。
7.衝撃塑性加工 - 衝撃エネルギーを利用した高度成形技術 -
詳細を見る『高エネルギー速度加工』(塑性加工技術シリーズ)の内容を見直したものである。初めに加工の原理や特徴を述べ,爆発エネルギーを利用する加工法や放電成形,電磁成形,電磁接合,高速プレス装置についても事例と併せて解説した。
8.接合・複合 - ものづくりを革新する接合技術のすべて -
詳細を見る『接合』(塑性加工技術シリーズ)で紹介されていた基本技術について内容を見直し,実用上の点を考慮しながらアディティブマニュファクチャリングなど現在注目されている技術を追加した。それぞれの技術の適用例・応用例も紹介する。
9.鍛造 - 目指すは高機能ネットシェイプ -
詳細を見る鍛造技術は,高精度な形の創成から高機能な製品を創出するネットプロパティの領域を目指している。進歩する閉そく鍛造,分流法,温間,板鍛造等の実用例を紹介し、周辺技術のCAE,サーボプレス,環境対応型潤滑剤なども記述。
10.粉末成形 - 粉末加工による機能と形状のつくり込み -
詳細を見る粉末成形は優れた材料特性,粉末積層造形やポーラス金属のような三次元複雑形状のニアネットシェイプなどのコスト優位性からも注目される。本書では新しいホットプレス,セラミックス粉末,硬質材料の成形と作製,機能性材料なども加えた。
11.矯正加工 - 板・棒・線・形・管材矯正の基礎と応用 -
詳細を見る本書は,近年における形状に対する要求の厳格化や外見上現れない内部残留応力低減への要求,矯正が困難な高強度材への要求の高まりに際し,FEM解析等高精度な制御方法について最新の動向を可能な限り記述した。
12.回転成形 - 転造とスピニングの基礎と応用 -
詳細を見る転造やスピニングなどの回転成形は、簡単形状な工具を用い小荷重容量機械で成形でき、多品種少量生産に適する。本書では,近年,高強度材や難加工材の成形など、より効率的生産手段への展開が期待される回転成形について詳説した。
13.チューブフォーミング - 軽量化と高機能化の管材二次加工 -
詳細を見る管材の事務機器や自動車等構造部材としての利用の増加に伴い,複雑成形を可能にするチューブハイドロフォーミングを含め,近年複雑化,軽量化,高強度化が求められている管材の二次加工技術を普遍的な技術をふまえて体系化した。
14.板材のプレス成形- 曲げ・絞りの基礎と応用 -
詳細を見るプレス加工における曲げ加工と絞り加工について,基本から各種の加工法の原理・特徴,材料の変形メカニズム,型の設計,加工機械,板材料の選び方,またホットスタンピングやインクリメンタルフォーミングなど新しい技術も紹介した。
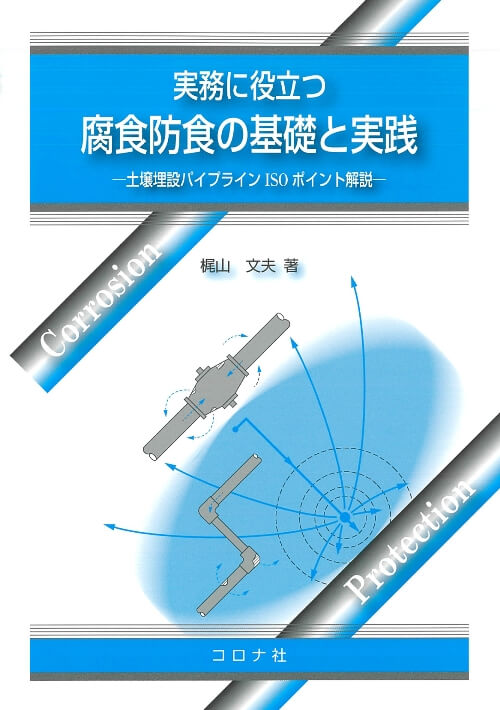
実務に役立つ
詳細を見る
腐食防食の基礎と実践
- 土壌埋設パイプラインISOポイント解説 -化学,電気化学,電気工学,土壌学,微生物学の広範な分野に跨る土壌に埋設されたパイプラインの腐食防食について,実務に役立つようその基礎と実践を解説。土壌埋設パイプラインに関するISO国際規格の解説も意識的に取り入れた。
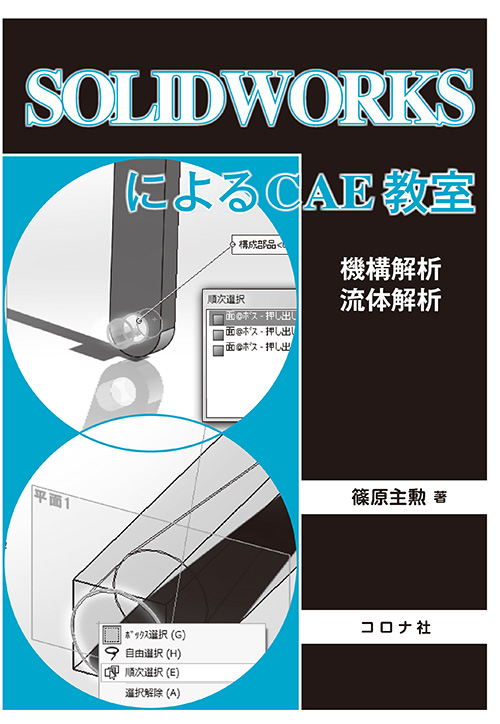
SOLIDWORKSによるCAE教室
詳細を見る
- 機構解析/流体解析 -「SOLIDWORKSによるCAE教室- 構造解析/振動解析/伝熱解析 -」の続編。さらに「機構解析/流体解析」をCAE解析により学習します。操作については基礎から記述していますので,本書から読み始めても大丈夫です。
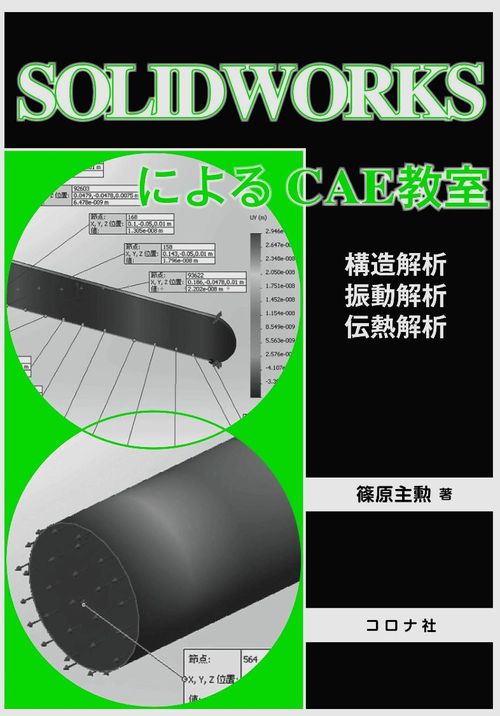
SOLIDWORKSによるCAE教室
詳細を見る
- 構造解析/振動解析/伝熱解析 -一般にCAEソフトは製品の改善や改良などに用います.本書では座学で勉強する理論(材料力学,機械力学(振動工学),流体力学,熱力学(伝熱工学)からなる4力)を理解するため,CAEによる解析を実施している点が特徴です。
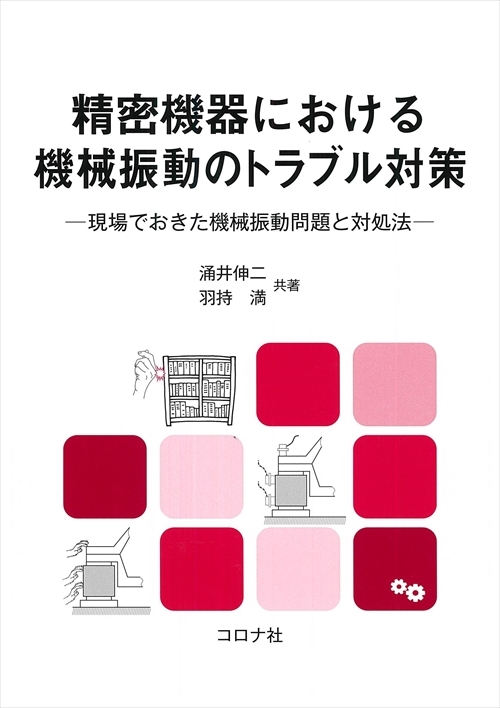
精密機器における機械振動のトラブル対策
詳細を見る
現場でおきた機械振動問題と対処法メカトロ機器開発の境界領域といえる振動のありかを探索し,解決策を提示・実証できる技術者育成を狙い,著者らが経験した機械振動のトラブルを挙げ,振動源の特定,性状の把握を踏まえ実現可能な解決策が発想できることを示す。
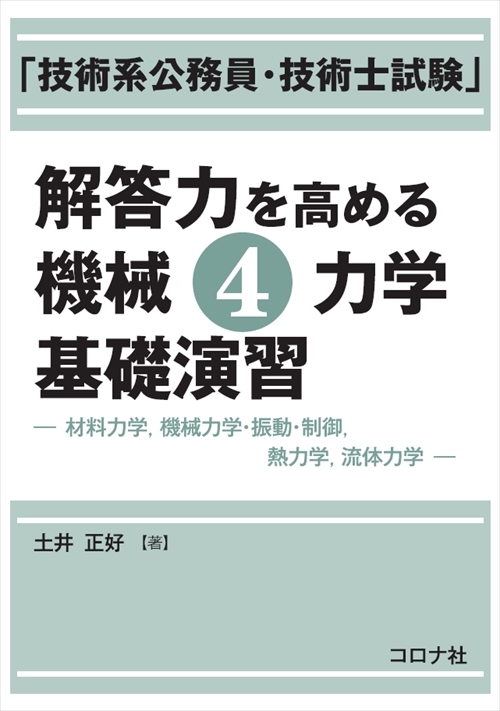
「技術系公務員・技術士試験」
詳細を見る
解答力を高める 機械4力学基礎演習
- 材料力学,機械力学・振動・制御,熱力学,流体力学 -本書は,機械系の「大卒技術系公務員」と「技術士資格」の合格対策本である。厳選した機械4力学(材料力学,機械力学・振動・制御,熱力学,流体力学)の過去問を解くことによって,機械工学全般の基礎知識を学べるように工夫した。
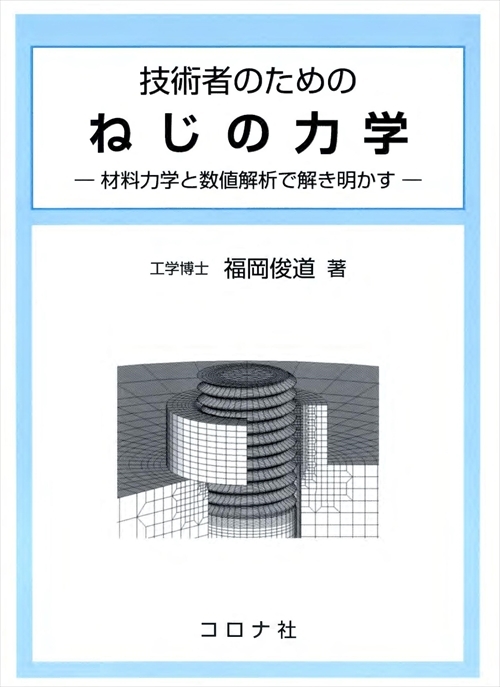
技術者のための
詳細を見る
ねじの力学
- 材料力学と数値解析で解き明かす -本書は,ねじの幾何学,締結部剛性,締め付け特性,静的強度と疲労強度,熱負荷に対する挙動,固有振動特性などを平易に解説し,材料力学と標準的なCAE手法による“壊れないねじ締結部設計”に必要な基礎知識の提供を目的とする。
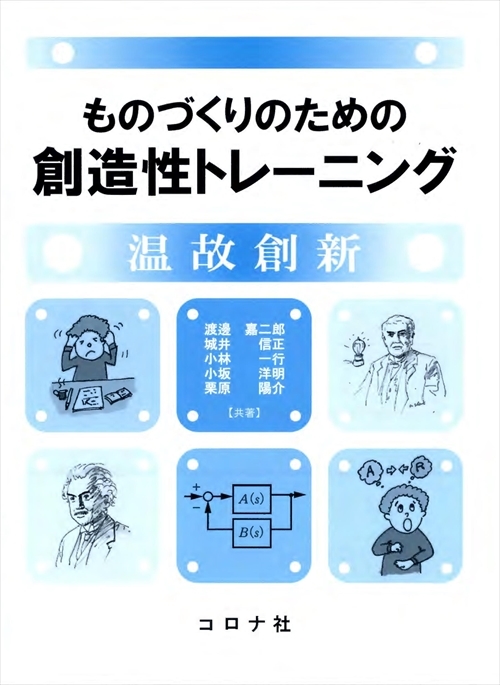
ものづくりのための創造性トレーニング
詳細を見る
- 温故創新 -本書は,ものづくりに生かすためのアイデア創生方法が誰にでも身につくよう,発想方法から実践的トレーニングまでをわかりやすく解説している。特に難しいとされる「既存デバイスから新製品を展開する」方法について焦点を当てた。
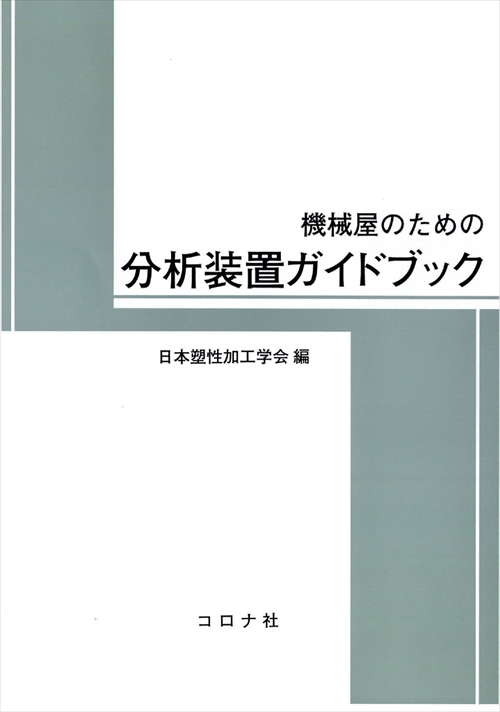
機械屋のための
詳細を見る
分析装置ガイドブック本書は,顕微鏡観察,元素分析,構造解析,各種物性計測などに関する分析装置についてあまり知識のない研究者・技術者が,どのような装置で何が測定・分析でき,どのようなデータが得られるかを手軽に手早く見つけ出すための案内書。
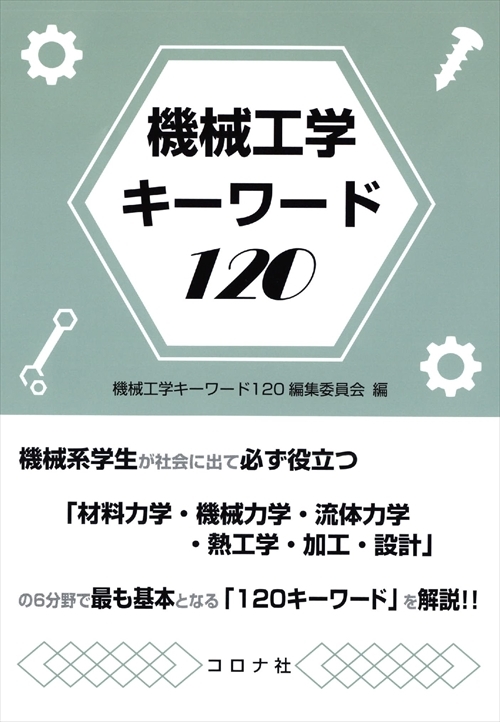
機械工学キーワード120
詳細を見る機械工学科を卒業し,これから社会に出ようとする学生が最小限の知識を効率よく得られるために,材料力学,機械力学,流体力学,熱工学,加工,設計の分野から,それぞれ基本となる語句を20選び,見開き2ページで説明した。
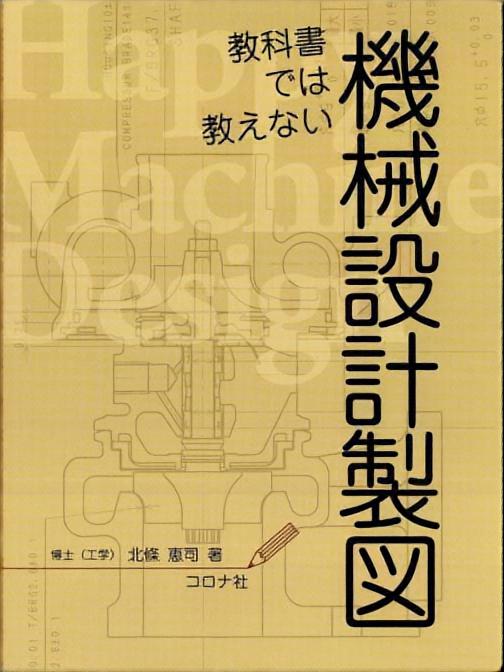
教科書では教えない機械設計製図
詳細を見る機械設計実務では「こんなときはどうするんだろう?」という教科書には載っていないような疑問にたびたび遭遇します。そんな疑問に,先人たちがどんな回答を出してきたのか,実務と教育に経験豊富な著者がやさしく丁寧に解説します。
シリーズ:機械系 教科書シリーズ
シリーズ:新塑性加工技術シリーズ
計量・計測・制御
- 詳細を見る
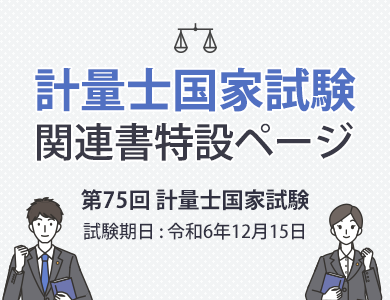
「計量士関連書籍」特設ページ
詳細を見る- 詳細を見る
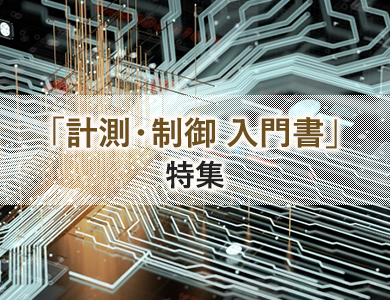
「計測・制御 入門書」特集
詳細を見る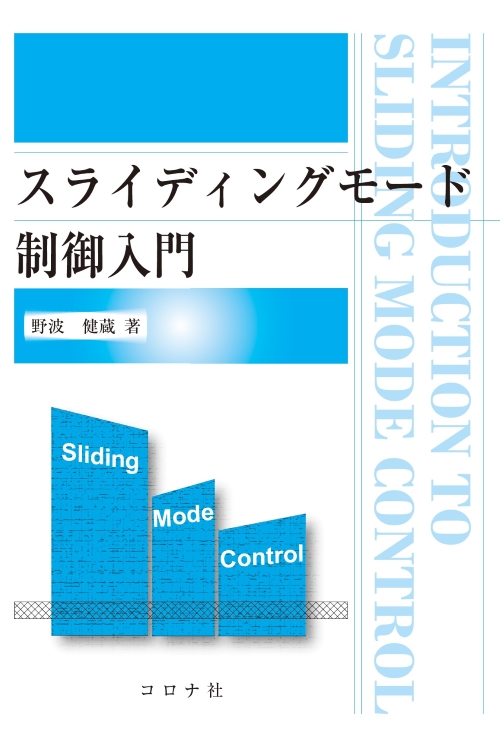
スライディングモード制御入門
詳細を見る本書は,ロングセラーとなった『スライディングモード制御-非線形ロバスト制御の設計理論』を大幅に刷新し,基本的な考え方や基本構造から解説し,きわめて実用的で有益な最近の設計法とその成果までをまとめた専門書である。
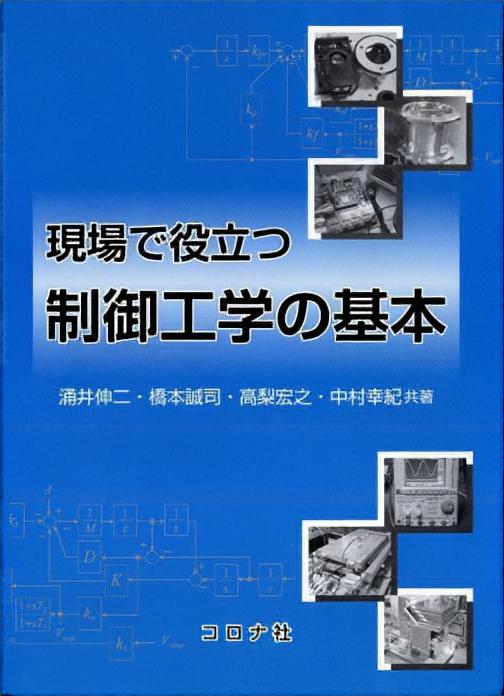
現場で役立つ
詳細を見る
制御工学の基本制御工学を講義している著者が感じる,学生の座学での知識習得の向上を目的に,制御工学の面白さや全体像の理解をはじめに行い,順次に数学的背景を理解していくという構成で執筆した意欲的内容。章末には演習問題と全解答を付けた。
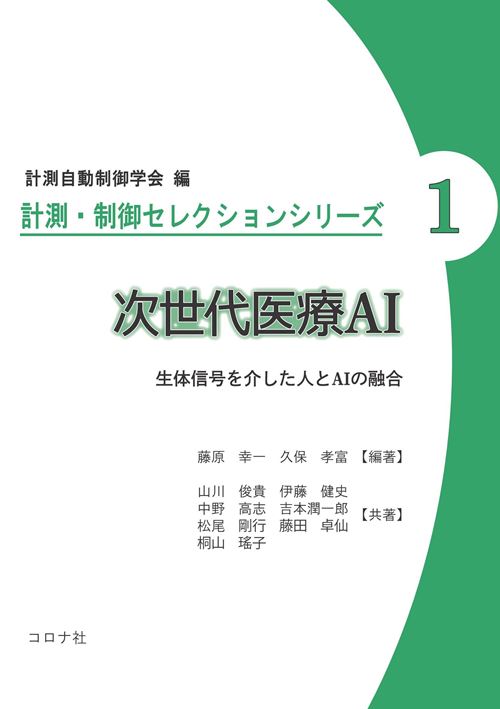
1.次世代医療AI
詳細を見る
- 生体信号を介した人とAIの融合 -医用画像(CTやMRI)以外,特に生体信号を用いたAI技術に焦点を当て,新たな医療AI開発の時代に備えるために必要な事柄を丁寧に解説した。さらに,医療AIに関わる法律や倫理,薬事についても解説を試みた。
2.外乱オブザーバ
詳細を見る物体を動かす際に生じる外乱(摩擦や重力など)を推定できれば,制御系の安定性や追従性を向上させることができる。本書では「外乱オブザーバ」の設計プロセスや応用方法,性質を体系的に記し,研究する人に役立つことを目的とした。。
3.量の理論とアナロジー
詳細を見る量の理論を系統立てるため,理論の出所を明らかにし,文献を適切に紹介した。数学的な厳密さよりも直観的な理解を重視し,量の理論に留まらず,横断型科学技術の基礎として,情報量や信号理論の構造,文学や生命学など多方面に言及。
4.電力系統のシステム制御工学
詳細を見る
- システム数理とMATLABシミュレーション -ネットワークシステムの解析と制御の観点から,多数の発電機,負荷,送電網等から構成される電力系統のモデリング,数値シミュレーション,制御系設計,数理解析の要点を解説する。MATLABシミュレーションのプログラムを掲載。
5.機械学習の可能性
詳細を見る機械学習の歴史や種類,基本的なアルゴリズムから,画像認識や文字認識,ゲーム理論,音声生成や制御,また応用例として医療や社会インフラ,外観検査,語学学習に至るまで網羅的に解説しており,開発環境についても言及している。
6.センサ技術の基礎と応用
詳細を見る千差万別ともいわれるセンサ技術を,その広い分野の中で,代表的ニーズがあると考えられる技術に対象を絞り,専門家でない人にもわかりやすいよう,基礎編と応用編にわけて解説している。
7.データ駆動制御入門
詳細を見るモデルベースドアプローチと異なり,データを直接用いて制御器を設計・更新・調整する方法はデータ駆動制御と呼ばれる。モデリングが困難な状況で操業データを有効に使いコストダウンを実現する方法論を整理・体系化した入門書。
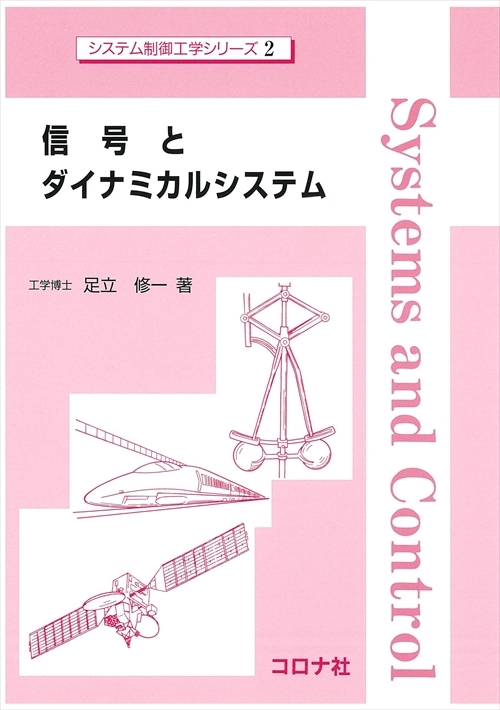
2.信号とダイナミカルシステム
詳細を見るシステム制御工学のための信号とダイナミカルシステムの入門書。フーリエ解析,ラプラス変換を導入し,伝達関数,周波数伝達関数,状態方程式を関係づけ,体系的に解説する。議論を,連続時間信号と連続時間システムに限定した。
3.フィードバック制御入門
詳細を見る本書では,システムの伝達関数表現に基づきながら,ロバスト制御を視野に入れた現代的な観点から記述し,豊富な図表と例題により,制御を専門としない多くの人々にも容易に理解できる「わかりやすい教科書」となるよう配慮した。
4.線形システム制御入門
詳細を見る本書は,状態空間法による線形制御系の解析・設計についての入門書である。状態空間モデルを用いて,対象が安定かどうか,いつ安定化できるか,センサがたりないが大丈夫か,安定化を適切に行う方法などについて平易に解説している。
6.システム制御工学演習
詳細を見るシステム制御工学シリーズの古典制御テキスト「フィードバック制御入門」および現代制御テキスト「線形システム制御入門」に対応した演習書として執筆した。共に用いることが最適であるが,本書のみで理解できるように配慮している。
7.システム制御のための数学(1)
詳細を見る
- 線形代数編 -本シリーズを学ぶ上で必要となる数学のための教本である。線形代数編と関数解析編の二つに大きく分け,本書はそのうち線形代数を解説する。本書は教科書であるが,制御工学のための数学を復習,自習したいと思う人にも適している。
8.システム制御のための数学(2)
詳細を見る
- 関数解析編 -本書は,システム制御を学ぶ人のために複素関数や関数解析の基本を解説している。また,システム制御から派生する例題や演習問題をなるべく多く含め、定理の証明,例題や演習問題の解答についてはなるべく省略せずに記述した。
9.多変数システム制御
詳細を見る制御対象の状態方程式表現に基づく制御系設計法の概要を,哲学から理論的成果および制御系設計例までという形でまとめた。定理・証明の方式をとらず,考え方を重視し,多変数システム制御の枠組みが容易につかめるようにした。
10.適応制御
詳細を見るモデル規範形適応制御系に関して,理想的な条件下での安定論から,現実的な不確定性のもとでのロバスト適応制御,離散時間形式の適応制御,非線形制御とも関連の深いバックステッピング法,逆最適性に基づく適応制御系まで解説した。
11.実践ロバスト制御
詳細を見る本書では,与えられた制御問題にいかにして答えを求めるかという実践的な側面から,H∞制御およびμ設計法について,これらの設計法をロバスト制御系設計のツールとして使いこなせるようにすることに主眼を置いて平易に解説した。
12.システム制御のための安定論
詳細を見る制御工学をより深く理解するための安定性に関する解説書。安定性に関する基礎理論を最近の主要結果まで含めて図や例を豊富に用いて平易に解説し,体系的に見通しよく理解し整理できるように配慮した。
13.スペースクラフトの制御
詳細を見る本書は人工衛星の姿勢制御について,力学と制御工学の二つの観点から系統的に述べた。スピン衛星の安定性,古典制御・現代制御による制御系の設計法,大形衛星のロバスト制御など,基礎から最先端の技術を,例題を示して解説した。
14.プロセス制御システム
詳細を見るプロセス制御の基礎から応用まで順に学べるようまとめてある。特に化学プロセスを具体的対象に,物理モデル構築の仕方をはじめ,プロセス制御の分野から提案された内部モデル制御やモデル予測制御の基礎的理論についても述べている。
15.状態推定の理論
詳細を見る連続時間線形システムの状態推定法への入門書である。確定的な方法としてオブザーバとH∞フィルタを,確率的な方法としてはカルマンフィルタを取り上げている。確率的な方法に関する章は確率システムへの入門として読むこともできる。
16.むだ時間・分布定数系の制御
詳細を見る制御対象のもつむだ時間,空間的に分布する制御量の振舞いなど制御性能を劣化させる恐れのある現象に注目し,入力むだ時間系を中心にスミス法,状態予測制御,熱系,振動系について例題・実験結果を交え効率よく学習できるよう解説。
17.システム動力学と振動制御
詳細を見る振動学と振動制御は不可分の表裏一体の関係にあり,先端科学技術を裏方から支えている基礎工学である。本書では,ラプラス変換法を解析法として用いながら,振動解析と振動制御を設計論の立場から一体的にとらえながら解説した。
18.非線形最適制御入門
詳細を見る最適制御およびモデル予測制御に関連する学生や技術・研究者の方に,最適化の基礎から数値解法に関する新しい話題を自己完結的かつ平易に解説した。関連の基本用語や重要な概念などは一通り理解できるように省略せず解説している。
19.線形システム解析
詳細を見る線形時不変有限時限の多入力多出力システムに対する理解を深め,制御系設計問題への準備として必要な概念を理解することを目的としている。行列操作論に偏らないよう,システムの振舞いに着目して諸性質を解説する。
20.ハイブリッドシステムの制御
詳細を見るハイブリッドシステムとは,離散値信号と連続値信号が混在した動的システムである。本書では,ハイブリッドシステム制御の基礎理論が直感的に理解できるように例を多くし,制御問題の設定方法・解法を効率よく習得できるようにした。
21.システム制御のための最適化理論
詳細を見る前半では,初めて最適化理論を学ぶ学生のために最適化の基礎理論を丁寧に解説。後半では,システム制御の最適化に直接関連する線形行列不等式,平方和最適化,確率的手法などについて,それらの意味も含めて理解できるよう解説した。
22.マルチエージェントシステムの制御
詳細を見る複数のエージェントの局所的な相互作用をもとに大域的な機能を発現するシステムをマルチエージェントシステム と呼ぶ。本書では,このシステムの制御理論を体系的にまとめ,基礎的な概念と研究成果を初学者向けに紹介している。
23.行列不等式アプローチによる制御系設計
詳細を見る線形時不変システムの安定性,受動性,有界実性などの性質を,凸最適化と関連する線形行列不等式(LMI)を軸に解説した。つぎに,これらの結果のシステム解析,ロバスト制御系設計などへの応用を概説した。
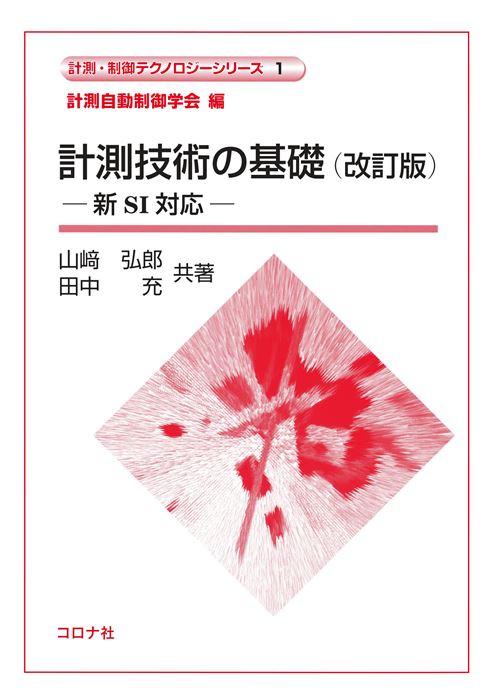
1.計測技術の基礎(改訂版)- 新SI対応 -
詳細を見る対象に関する不確かさを減らし,より明確な情報を得て,対象を正しく把握する計測技術の全体を記した。計測標準技術については,2019年のSI改訂に伴う基礎物理定数に基づいた再定義と,それによる測定精度の向上等を説明した。
3.センサの基本と実用回路
詳細を見る本書は,センサの種類,動作原理,電子回路を利用した実用例を取り上げ,センサに関する基礎知識の修得を目的として執筆した。また,マイコンを利用したセンサ情報の取得について触れ,より実践的な力が養成できるように配慮した。
4.計測のための統計
詳細を見る本書では,計測の基本概念から工学系全般に必要な確率・統計の数理的知識や測定値の不確かさ評価や改善に必要な知識,測定に関わる統計モデルと当てはめを解説。また,統計解析用プログラミング言語Rによるコーディング例も紹介。
5.産業応用計測技術
詳細を見る圧力,流量,化学成分,濃度などのプロセス物理量・化学量についてその計測技術の特徴や手法を解説し,後半では電気計測器における基本的な電気量の計測,高周波計測,半導体デバイス特性の計測技術について基礎的な要点を解説する。
6.量子力学的手法によるシステムと制御
詳細を見る主として想定する読者は,マクロの装置やプラントに係る技術者や研究者である。本書はマクロな世界をミクロの力学を使って解き明かす試みを提示する。その意味で本書は,量子力学ユーザーに新しい活用の用途を与えることにもなる。
7.フィードバック制御
詳細を見る本書は新しいスタイルの制御工学の入門書を目指した。最初に,状態空間での解析・設計法を説明して,初学者の理解を容易にする。その後で,応用上で重要であるロバスト性や2自由度制御なども含めて,周波数応答法を学ぶ。
9.システム同定
詳細を見るシステム同定の有用な結果を得るためには,対象とするモデルの選択,入出力データの取得,パラメータ推定手法の選定などを適切に行う必要がある。本書では,システム同定理論の基礎から最近の発展について解説した。
11.プロセス制御
詳細を見るプロセスオートメーションの基礎をなすプロセス制御の解説書。基本的技術からヒューマンインタフェース,エンジニアリング,生産管理,応用事例など,広い範囲をカバーした。各分野の専門家や実務者が多彩な見方で記述している。
13.ビークル
詳細を見る自動車,航空機,ヘリコプタ,ロケットおよび宇宙機の航法と運動,誘導,制御技術を述べ,これらの特徴とミッションを示し,運行(移動)を安全・正確に実行するための画像処理,移動体の位置認識および経路計画技術・手法を論じる。
15.信号処理入門
詳細を見るディジタル信号処理の基礎を理解し,先端的な信号処理技術も習得できるよう編集した。基礎の習得に必要な高度な理論についてわかりやすく記述した。学生や技術者がディジタル信号処理の基礎を学び,応用を目指すのに最適な教科書。
16.知識基盤社会のための人工知能入門
詳細を見る知識基盤社会では人工知能的な思考が大切である。起こる問題を記号でとらえ,命題・述語論理をベースに探索問題,ゲーム問題などを解決していく。論理プログラミング言語Prologを用い,知識プログラミングをわかりやすく解説した。
19.システム制御のための数学
詳細を見るシステム制御や広く工学を学ぶために必要な線形代数,複素関数とラプラス変換,状態ベクトル微分方程式等を中心とした数学的基礎事項を解説した教科書である。項目を絞ることで証明や説明を極力省略せず,参考書としても利用できる。
21.生体システム工学の基礎
詳細を見るシステムやモデルといった重要な概念を導入し,生体信号処理,生体システムの解析法の基礎について説明した。さらに,システムとしての生体について,数多くの具体例をあげ,最後に,生体モデルとシミュレーションについて述べた。
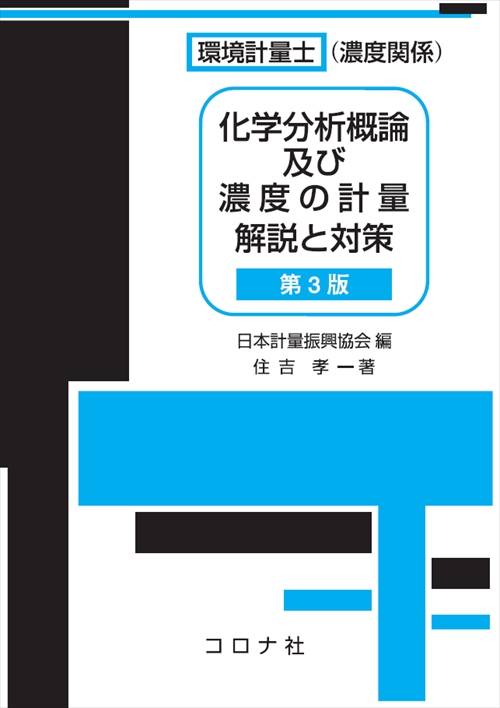
環境計量士(濃度関係)
詳細を見る
化学分析概論及び濃度の計量 解説と対策
(第3版)「化学分析概論及び濃度の計量」の過去問を、範囲別,体系別に分類整理し詳しい解説を加え,苦手科目の発見,克服に最適な構成とした。2009年の新版に関連法規やJISの改訂に伴う変更を追加し,平成28年度までの問題を掲載。
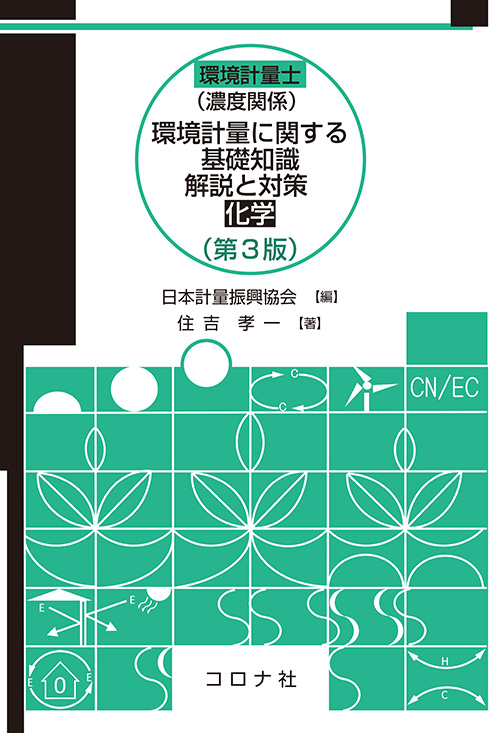
環境計量士(濃度関係)
詳細を見る
環境計量に関する基礎知識 解説と対策 (化学)
- (第3版) -環境計量士(濃度関係)国家試験の専門科目「環境計量に関する基礎知識(化学)」を分野ごとに体系的に解説。さらに平成24年度から令和4年度までのすべての問題(法規関係の出題を除く)を取り上げて詳細に解説。好評の第3版!
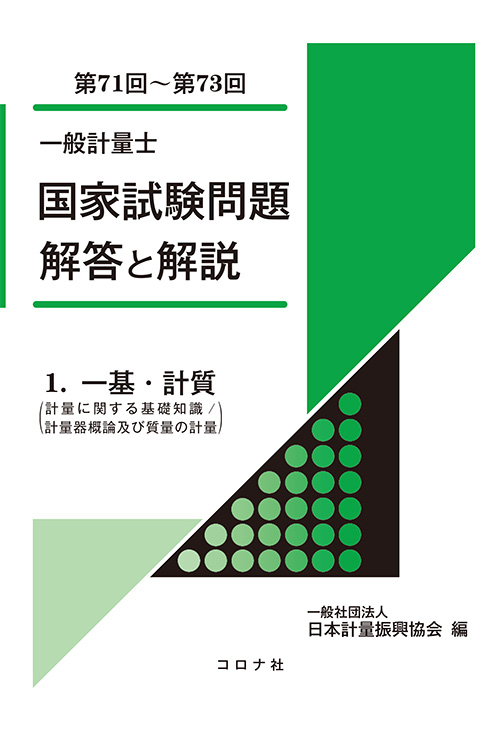
一般計量士
詳細を見る
国家試験問題 解答と解説
- 1.一基・計質(計量に関する基礎知識/計量器概論及び質量の計量)(第71回~第73回) -「一般計量士 国家試験」の専門科目である「計量に関する基礎知識」「計量器概論及び質量の計量」について第71回(令和2年12月実施)~第73回(令和4年12月実施)の全問題およびその解答,ならびに懇切丁寧な解説を掲載。
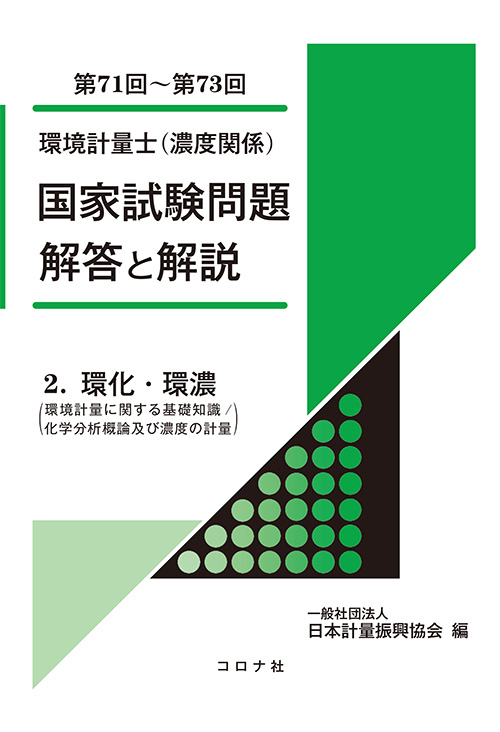
環境計量士(濃度関係)
詳細を見る
国家試験問題 解答と解説
- 2. 環化・環濃(環境計量に関する基礎知識/化学分析概論及び濃度の計量)(第71回~第73回) -「環境計量士(濃度関係)国家試験」の専門科目「環境計量に関する基礎知識(化学)」「化学分析概論及び濃度の計量」の第71回(令和2年12月)~第73回(令和4年12月)の全問題とその解答,ならびに懇切丁寧な解説を掲載。
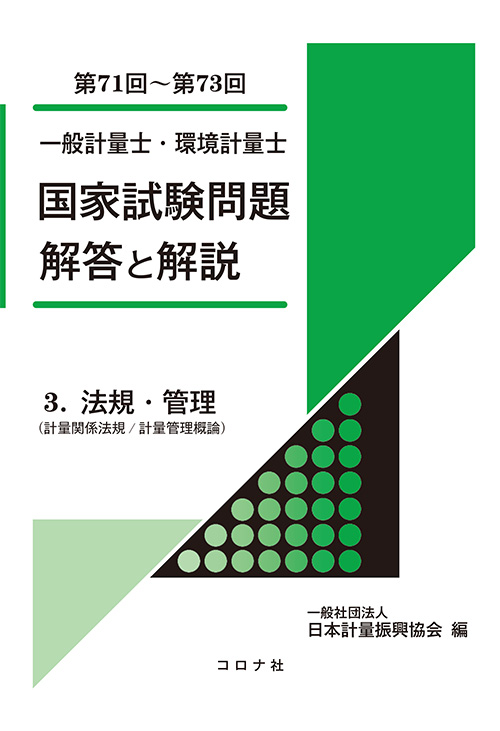
一般計量士・環境計量士
詳細を見る
国家試験問題 解答と解説
- 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)(第71回~第73回) -「一般計量士・環境計量士 国家試験」の共通科目である「計量関係法規」および「計量管理概論」について,第71回(令和2年12月実施)~第73回(令和4年12月実施)の全問題およびその解答,ならびに懇切丁寧な解説を掲載。
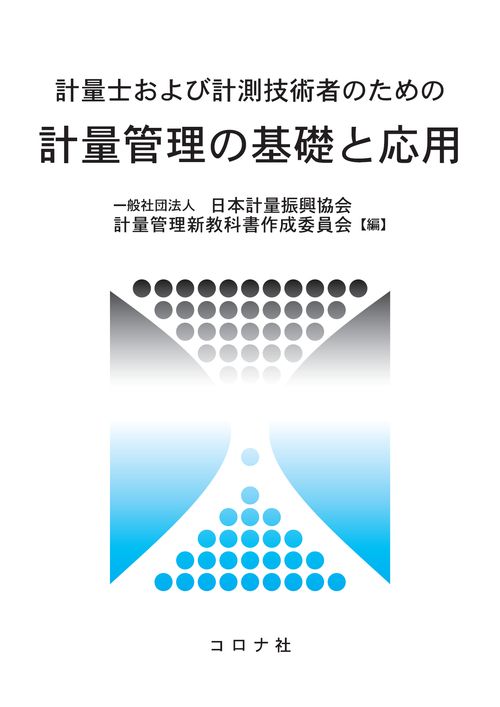
計量士および計測技術者のための
詳細を見る
計量管理の基礎と応用計量士国家試験科目「計量管理概論」を基礎から扱い,技術者がどうすれば信頼できる測定を行えるかを示す。SI基本単位定義の改訂,JIS Z 8103「計測用語」および計量行政審議会答申を踏まえた政省令改正にも対応。
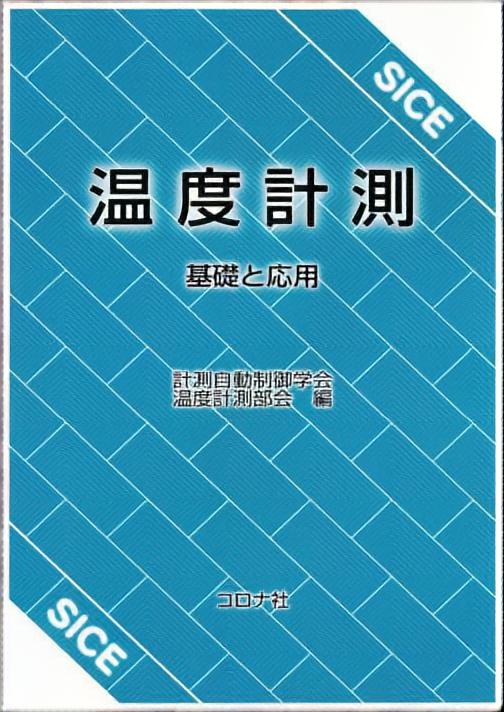
温度計測
詳細を見る
- 基礎と応用 -温度計測に携わる人々に有益な指針を提供することを目的としている。最新の知見を取り入れ,かつ入門者向けの部分を充実させた。また,不確かさ評価について独立した章を設け,温度計測に関連して評価方法に習熟できるようにした。
シリーズ:計測・制御セレクションシリーズ
シリーズ:システム制御工学シリーズ
シリーズ:計測・制御テクノロジーシリーズ
土木・建築工学(モニタリング技術・建築形態の生成分析・空間経済分析・防災工学・多変量解析・コンクリート構造物設計)
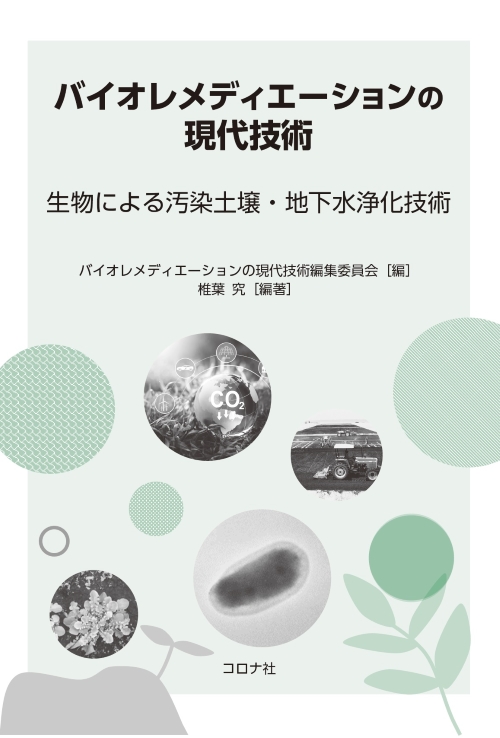
バイオレメディエーションの現代技術
詳細を見る
- 生物による汚染土壌・地下水浄化技術 -バイオレメディエーションとは,生物を利用して有害物質を分解・除去する技術を示す。本書では,この技術の背景・理論の説明に始まり,実例を交えた各技術の解説,浄化事業計画の書き方,統計資料に至るまでを解説している。
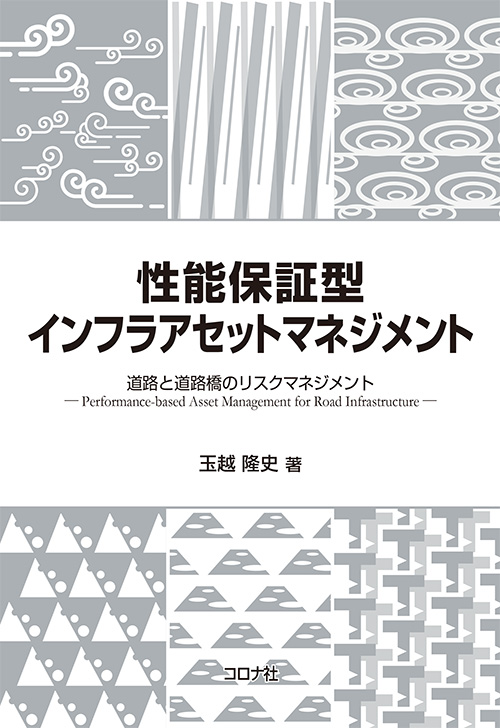
性能保証型インフラアセットマネジメント
詳細を見る
- 道路と道路橋のリスクマネジメント -インフラにおける性能保証とは,おもに構造物自体の性能を保証することと考えられてきたが,それはあくまで前提条件であり,道路ネットワークとしてのインフラの機能・役割等を保証することこそが,本当の意味での性能保証である。
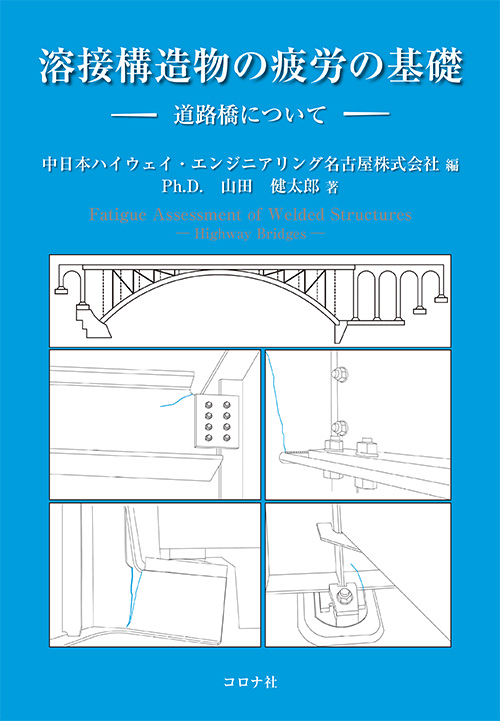
溶接構造物の疲労の基礎
詳細を見る
- 道路橋について -繰返し荷重を受ける鋼構造物では,しばしば疲労が問題となる。本書では,特に鋼道路橋の溶接継手を対象として,その基本的な疲労挙動を解説する。また,本書の内容は,鋼道路橋以外の溶接構造物に適用することも可能である。
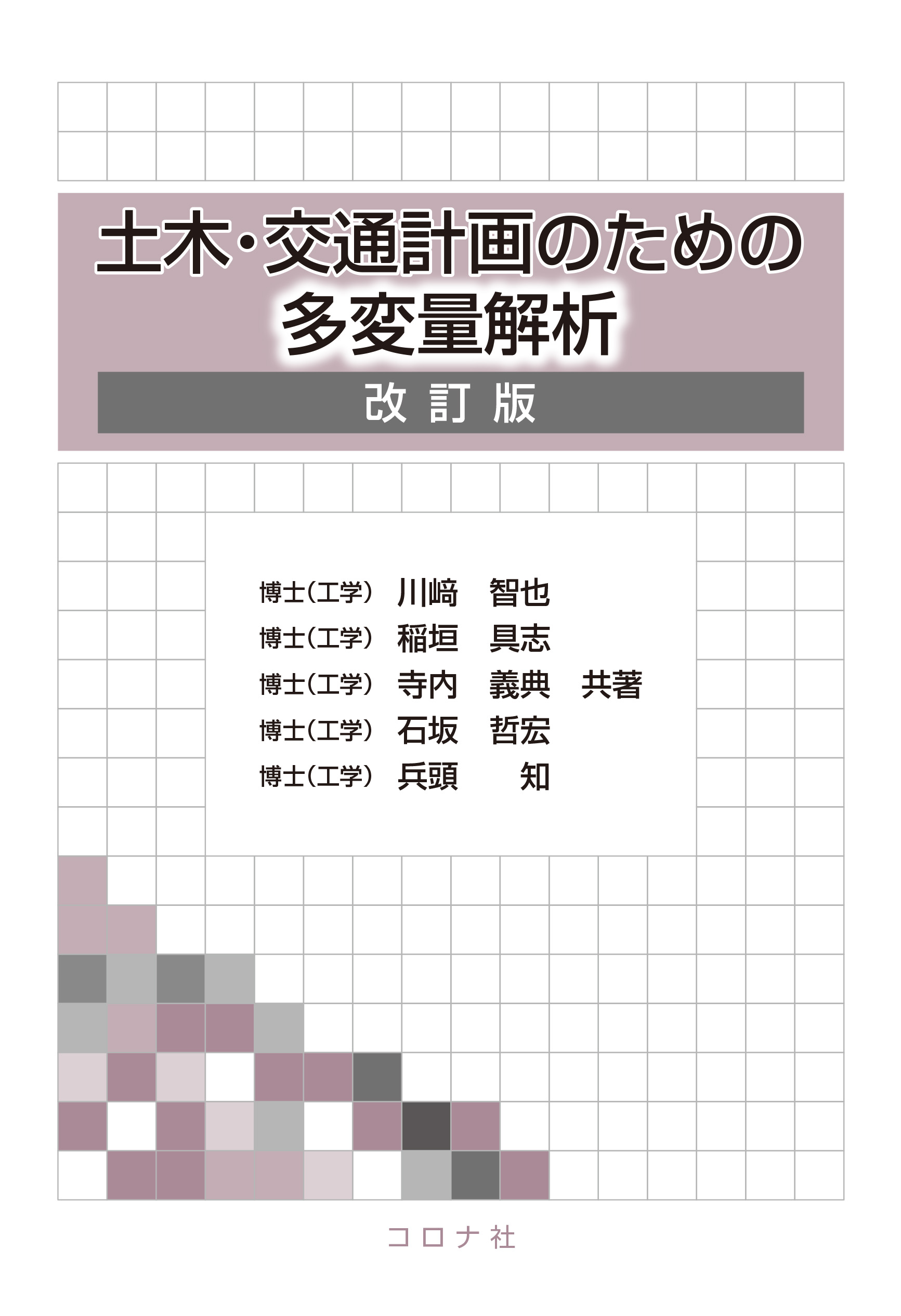
土木・交通計画のための多変量解析
詳細を見る
(改訂版)充実した解析手法の説明と,実際のデータを用いた豊富な例題・演習により,土木・交通計画で必須の分析手法である多変量解析の考え方・適用方法を身につける。改訂版では8章の因子分析の内容を再整理し,その説明を充実させた。
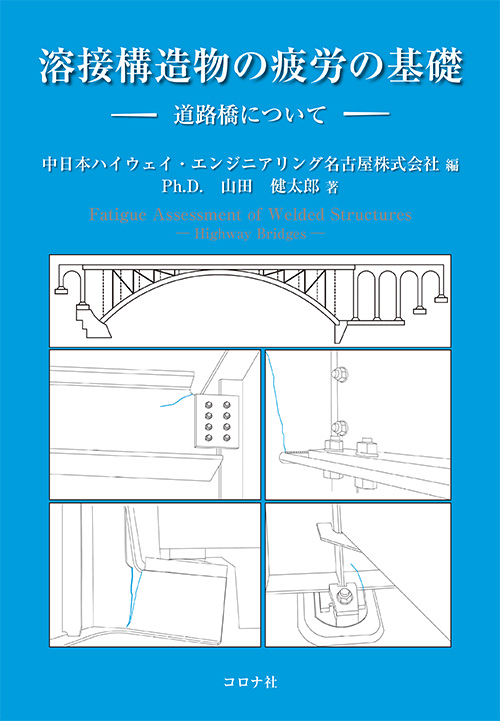
溶接構造物の疲労の基礎
詳細を見る
- 道路橋について -繰返し荷重を受ける鋼構造物では,しばしば疲労が問題となる。本書では,特に鋼道路橋の溶接継手を対象として,その基本的な疲労挙動を解説する。また,本書の内容は,鋼道路橋以外の溶接構造物に適用することも可能である。
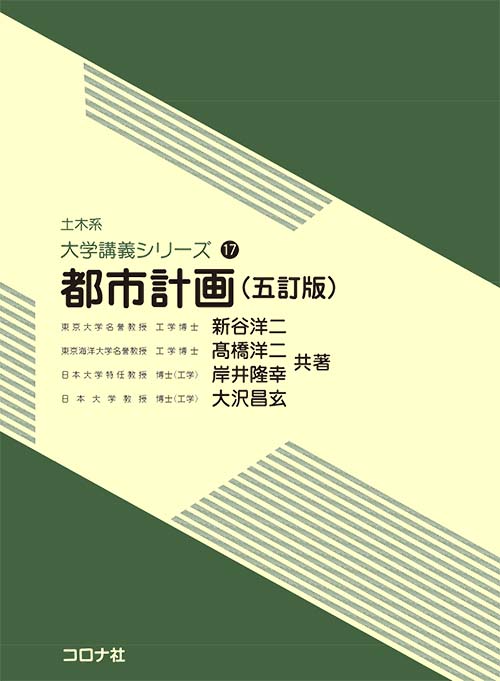
土木系 大学講義シリーズ 17
詳細を見る
都市計画
(五訂版)都市マスタープラン,土地利用計画,交通計画,都市施設設計を歴史的な背景含め体系的に整理した都市計画・国土計画の教科書。五訂版ではコンパクトシティ実現化に向けた立地適正化計画を含め,都市計画関連法制度の改正を反映した。
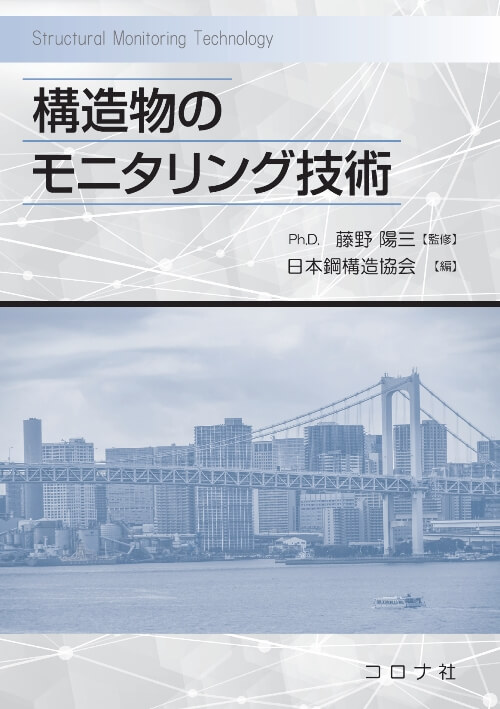
構造物のモニタリング技術
詳細を見るモニタリング技術の知識は,これまで個々の研究開発者への依存性が高くその習得に多数の研究論文を必要としてきた。本書は土木・建築分野と情報分野の知識を体系的にまとめ,各技術の到達点と課題を大まかに理解できるよう解説した。
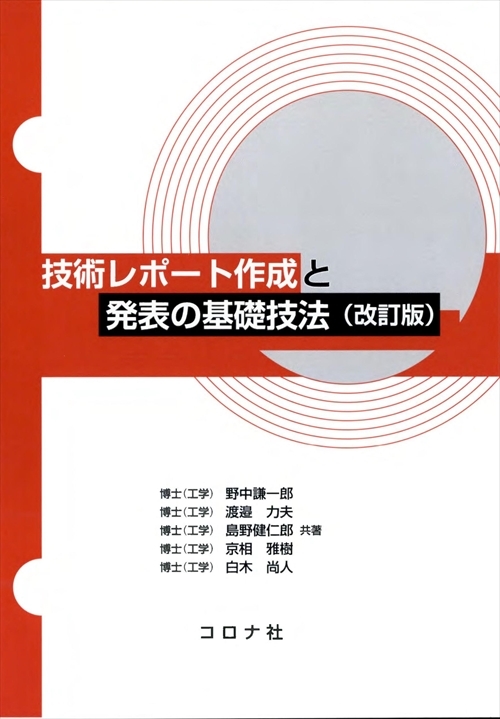
デザイン・コンピューティング入門
詳細を見る
- Pythonによる建築の形態と機能の生成・分析・最適化 -本書は,コンピュータによる建築形態の生成や分析を志す初学者が核となる基礎理論と計算手法をプログラミングしながら学べるように構成した。フリーのプログラミング環境を入手できる PythonとBlender を使用。
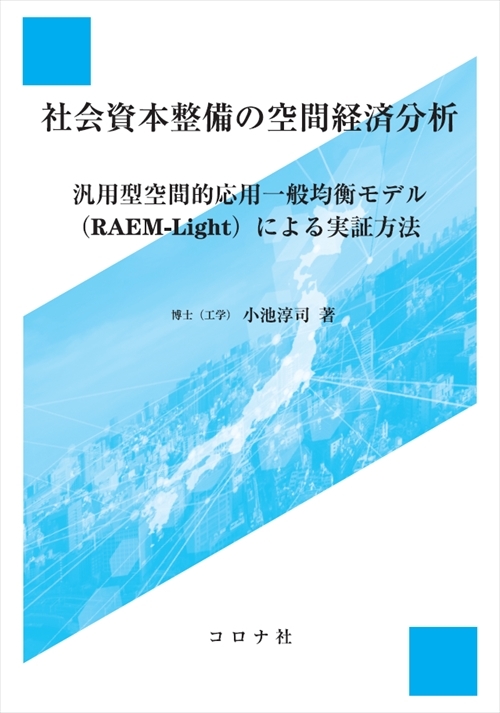
社会資本整備の空間経済分析
詳細を見る
- 汎用型空間的応用一般均衡モデル(RAEM-Light)による実証方法 -本書は,空間的応用一般均衡解析の内容を解説したテキストである。著者らが開発した汎用型空間的応用一般均衡モデル(RAEM-Light)を用いた実証分析を通じて,初学者から実務者までがこの手法を利用できるように解説した。
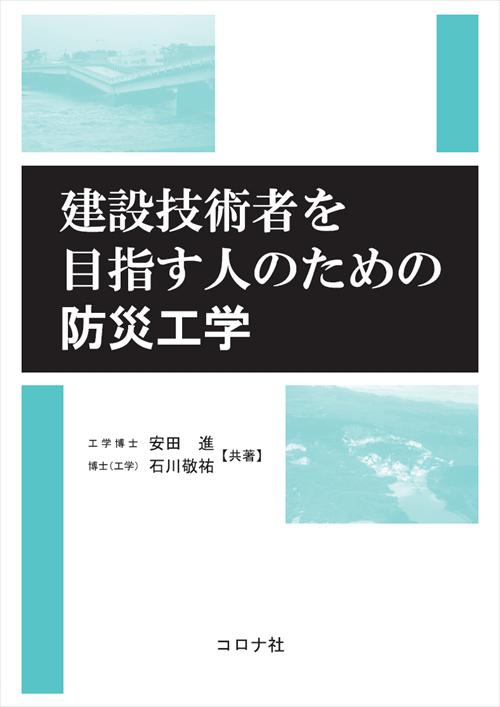
建設技術者を目指す人のための防災工学
詳細を見る建設技術者を目指す人が最低限必要な防災工学の知識を学べるよう,地域防災計画等でおもな災害対象の、地震災害、風水害、火山災害などの自然災害について,基礎的な知識から災害の予測・対策方法まで具体的な事例を交えて解説した。
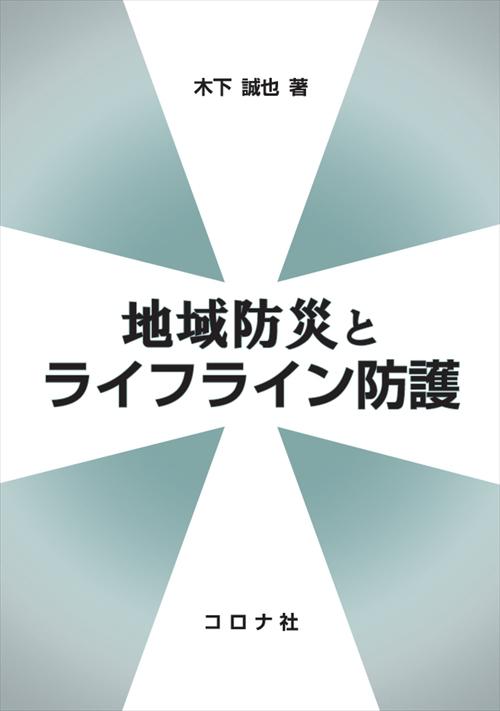
地域防災とライフライン防護
詳細を見る本書は,災害対策のための自治体や自主防災組織,企業,学校などの地域防災,および,社会経済への影響が大きい電気,通信,上下水道,道路などのライフライン防護について,具体的な現状と課題を解説した防災対策の教科書である。

自然災害の発生と法制度
詳細を見る国内外の様々な自然災害事例の発生状況を概観し,その特徴から今後の対策を論じた。また,過去の災害を踏まえて整備されてきた多種多様な法制度の歴史を学び,災害対策を検討するために必要な法制度の全体像も学べるようにした。
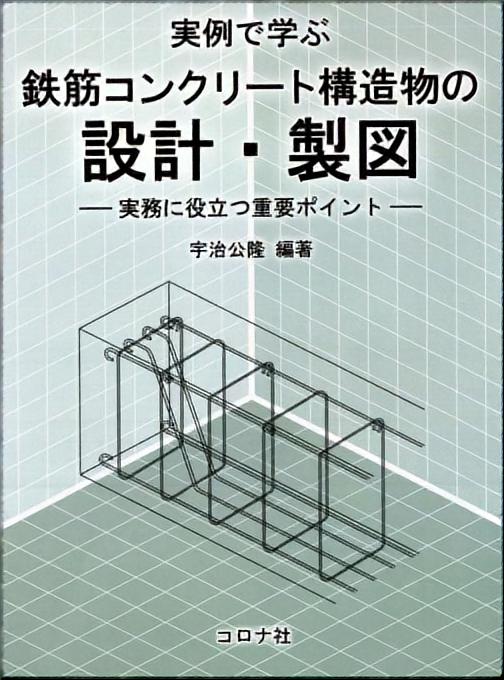
実例で学ぶ
詳細を見る
鉄筋コンクリート構造物の設計・製図
- 実務に役立つ重要ポイント -本書では,若手技術者やコンクリート構造物の設計を学ぶ学生が設計・製図を具体的に学べるよう配慮した。コンクリート構造に関する基礎知識に加え,代表的な土木構造物の例題を通して設計・製図の手順や重要ポイントを的確に解説。
環境・エネルギー工学(SDGs・サステイナブル・再生可能エネルギー・原子力・石油資源など)
- 詳細を見る
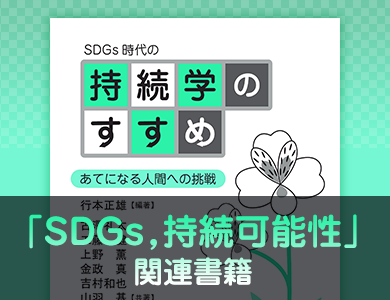
「SDGs,持続可能性」関連書籍
詳細を見る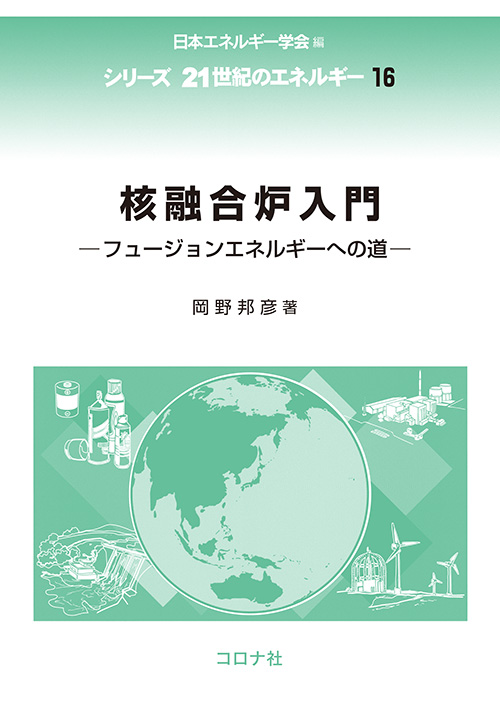
シリーズ 21世紀のエネルギー 16
詳細を見る
核融合炉入門
- フュージョンエネルギーへの道 -核融合炉開発の現状に至る経緯,実用化に近づきつつある最先端の研究をわかりやすく解説する。第1章だけで核融合炉の概要を把握できるよう構成し, 以降では内容を深め,範囲も広げ, 失敗の歴史や見えにくい事情にも言及した。
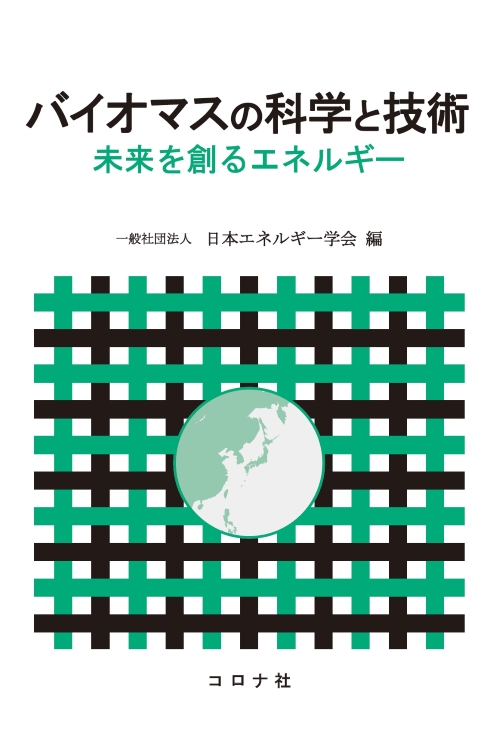
バイオマスの科学と技術
詳細を見る
- 未来を創るエネルギー -バイオマスを一通り学びたい学生,社会人,研究者向けに,各分野で取りこぼしがないよう項目を検討し,基礎事項から専門的な事項までを丁寧に解説した。また,記述の根拠となる文献を豊富に示し,必要に応じて参照できるようにした。
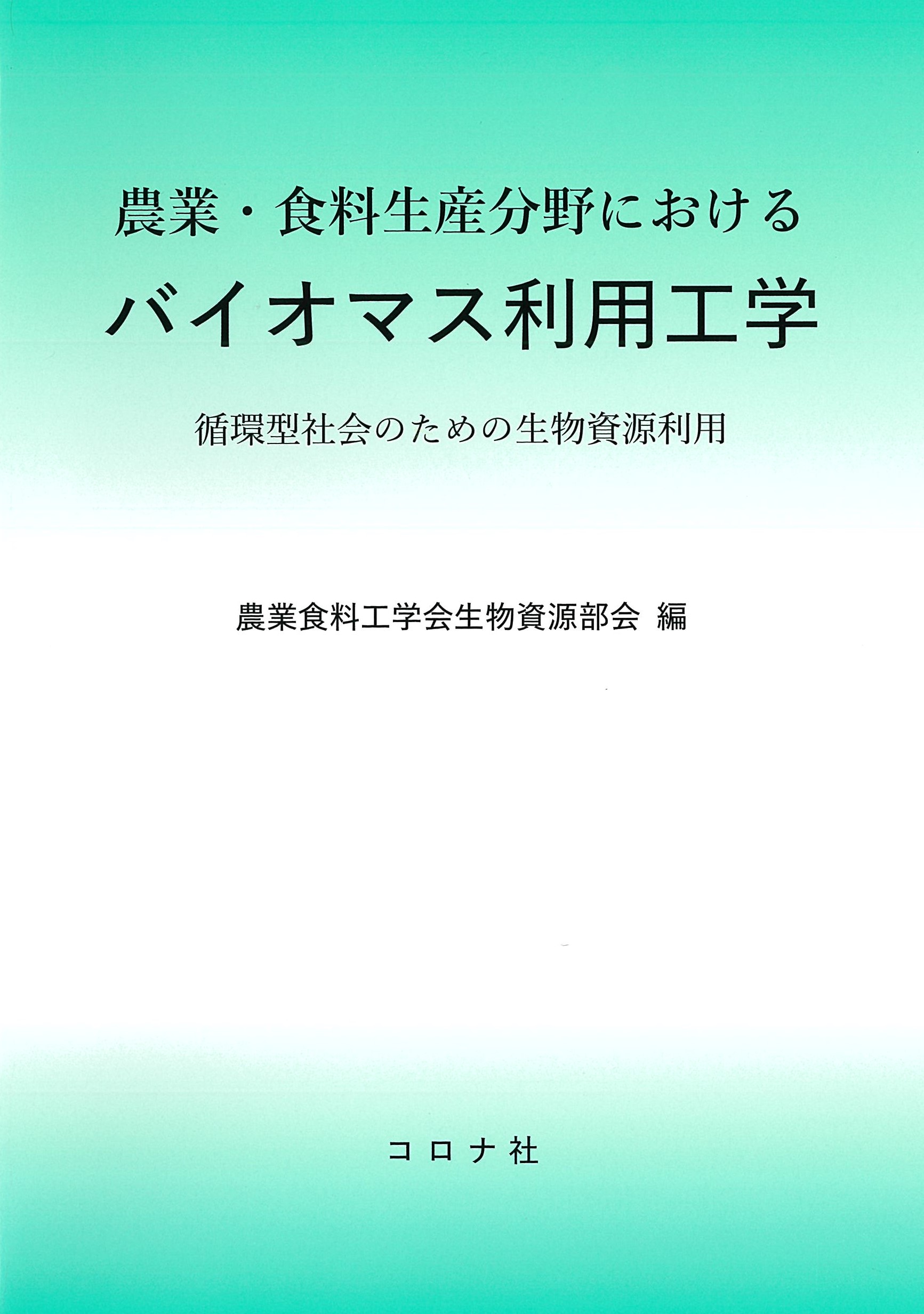
農業・食料生産分野における
詳細を見る
バイオマス利用工学
- 循環型社会のための生物資源利用 -バイオマス利用の基礎理論と,特にマテリアル利用とエネルギー利用のための実際の技術,生物資源の生産や収穫などに関わる機械作業や乾燥操作,食の安全,環境影響評価,SDGsとの関わりなど,社会実装に至る話題を取り上げた。
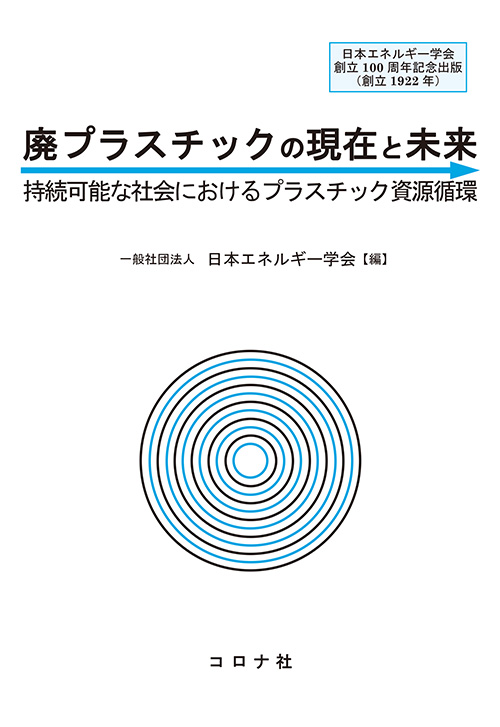
廃プラスチックの現在と未来
詳細を見る
- 持続可能な社会におけるプラスチック資源循環 -近年世界的に注目されている廃プラスチック問題について,国内外で具体的にどのような問題が生じているのか,またそれらに対してどのような取組みがなされているのかを資源循環社会,法制度,技術的な対応などの観点からまとめた。
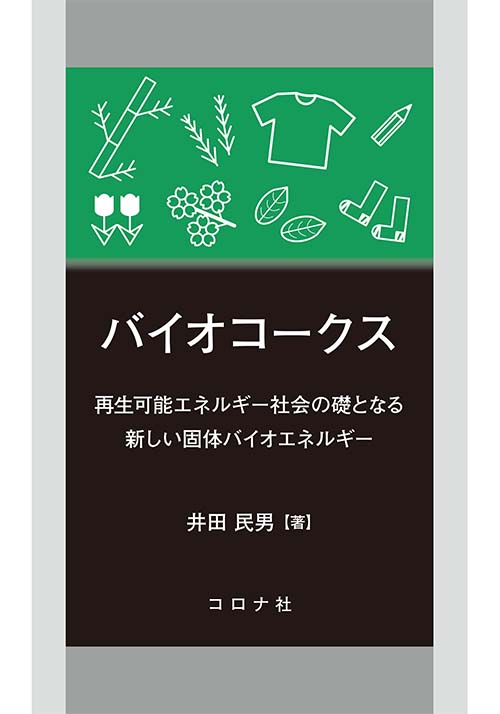
バイオコークス
詳細を見る
- 再生可能エネルギー社会の礎となる新しい固体バイオエネルギー -本書では木本系,草本系,農産系,厨芥系,果樹系バイオマス資源の特性を熱・物理学的観点から説明し,さらにバイオコークスの熱エネルギーとしての基本特性や循環型社会実現に向けたバイオコークス開発の意義などについて解説する。

SDGs時代の
詳細を見る
持続学のすすめ
- あてになる人間への挑戦 -持続可能な社会を構築していくには,自分の専門分野を深めるだけでなく,関連する学際研究,教養や文化も学ぶことが大切である。本書ではそのような多面的な考え方を身につけ,昨今の多様かつ複雑な社会問題を解決していく力を養う。
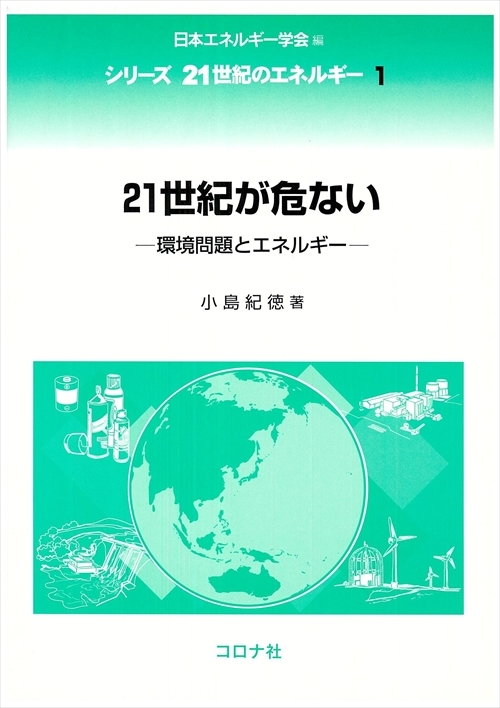
1.21世紀が危ない- 環境問題とエネルギー -
詳細を見る環境に優しいエネルギーの使い方とは,地球に優しい社会とは何かを考え直し,次世代に向けて新しい概念を取り入れた。これからの未来がどうなるか,悲観的でもなく,楽観的でもなく,冷静に今何をすべきかを考える内容である。
2.エネルギーと国の役割- 地球温暖化時代の税制を考える -
詳細を見る本書は,21世紀におけるわが国のエネルギー政策と国の役割について,税制面に焦点を当てながらその現状と問題点,および今後の課題について考えることを最大の狙いとし,一般の方々にも理解できるようにわかりやすく記述した。
3.風と太陽と海- さわやかな自然エネルギー -
詳細を見る本書ではエネルギーと環境問題を解決する可能性を明らかにするために,代表的な再生可能なエネルギーとして,太陽光・風・海洋・バイオマスを取り上げ,あらゆる角度から調査した。高校生以上に理解できるように書かれている。
4.物質文明を超えて- 資源・環境革命の21世紀 -
詳細を見る本書は大量生産─大量消費という物質文明の発展過程,物質文明がもたらした資源と環境の地球規模の問題について検討する。そして,資源・環境革命の必要性と,持続可能な社会へ向けての「物質文明を超える」方策を提言する。
5.Cの科学と技術- 炭素材料の不思議 -
詳細を見る炭素材料は多種多様な構造・性質をもつ。古くから利用されている炭素材料が,カーボンナノチューブなどの先端材料に変身し,今日注目を集めているが,本書は,なぜ多様に変身が可能なのかを易しく解説し,作り方や利用法を紹介した。
6.ごみゼロ社会は実現できるか(改訂版)
詳細を見る本書では,ごみの発生量や不法投棄量,海洋汚染の現状など,ごみに関する諸問題や,リサイクルに関する法律,行政・事業者・市民の取り組みなどを紹介している。また,ごみ発電,燃料化などごみ処理の技術や海外の事例も取り上げた。
7.太陽の恵みバイオマス- CO2を出さないこれからのエネルギー -
詳細を見る近年バイオマスエネルギーへの関心は高まってきているが,まだ十分に理解されているとはいえない状況である。そこで本書では,バイオマスエネルギーについて一般の方にもわかりやすく整理をし,理解を進めていただけるようまとめた。
8.石油資源の行方- 石油資源はあとどれくらいあるのか -
詳細を見る石油はいつどこでどのように作られ,あとどれくらいあるのだろうか。それに答えるべく,世界の新しい石油の発見も含め,地下に眠る石油資源についてその供給側面を技術的見地からわかりやすく紹介。21世紀の石油資源の行方を追う。
9.原子力の過去・現在・未来- 原子力の復権はあるか -
詳細を見る原子力は深遠な科学の世界から複雑な国際政治の領域にまで広がる巨大な複合システムである。本書の基本的な狙いは,今後原子力はどうなるのか,どうすべきかを読者に自分で考えていただくために必要な基礎知識を提供することである。
10.太陽熱発電・燃料化技術- 太陽熱から電力・燃料をつくる -
詳細を見る太陽エネルギーによる発電には,太陽光発電のほかに集光型太陽熱発電がある。また集光した太陽熱は,水素などの燃料製造にも利用することができる。本書ではこの集光型太陽熱発電とその熱を利用した燃料製造技術について解説する。
11.「エネルギー学」への招待- 持続可能な発展に向けて -
詳細を見る「エネルギー学」とは,エネルギー問題を総合的視点で捉え,工学や理学などの自然科学から,哲学・文化・政治・経済などの人文社会科学まで多くの分野を包括する新しい学術である。本書はその入門として,さまざまな視点を提示する。
12.21世紀の太陽光発電- テラワット・チャレンジ -
詳細を見る再生可能エネルギー,特に太陽光発電技術について広く学びたい方を対象に,太陽電池や太陽光発電システムなどの基礎から研究開発の現状,将来展望までをわかりやすく解説。エネルギー,化学系の大学学部や大学院の教科書にも最適。
13.森林バイオマスの恵み- 日本の森林の現状と再生 -
詳細を見る日本の森林運営を経済的に持続可能とするためのポイントとして,素材,副産物,エネルギー利用,法律等による補助の4項目について解説。日本の森林の将来を考える方,日本の森林バイオマスの有効利用に興味がある方にお勧めの一冊。
14.大容量キャパシタ- 電気を無駄なくためて賢く使う -
詳細を見る急速な充放電が可能で,繰り返しの充放電にも強いという特徴を持つ大容量キャパシタ。これからのスマートエネルギー社会を支える,この大容量キャパシタの仕組みや特徴,現在の使用例から今後の使われ方までをわかりやすく解説した。
15.エネルギーフローアプローチで見直す省エネ- エネルギーと賢く,仲良く,上手に付き合う -
詳細を見る従来から知られているさまざまな省エネの方法論をエネルギーフローからのアプローチという考え方で整理し,できるだけ具体例による説明をした。エネルギーフローに関連する参考例として,省エネ法やISO 50001の説明もした。
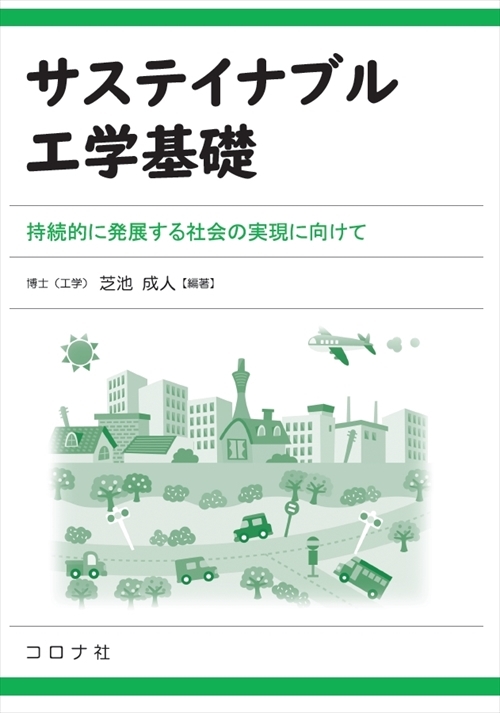
サステイナブル工学基礎
詳細を見る
- 持続的に発展する社会の実現に向けて -環境やエネルギー問題の概要と,その解決に向けた各分野における技術的課題や対策例を具体的に紹介。加えて,技術や製品の持続可能性を評価し,向上させる手段として,LCAや環境効率評価,各種指標,分析手法を丁寧に解説した。
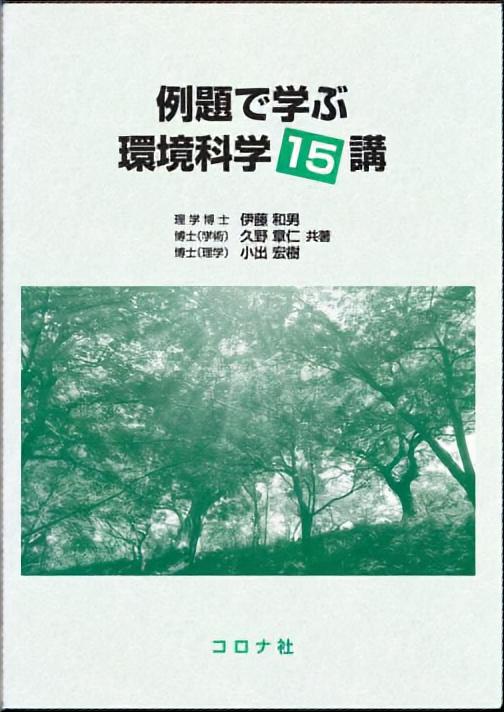
例題で学ぶ環境科学15講
詳細を見る例題を多く用意し,自分の手で問題を解くことにより,理解を深め,知識を十分定着させることを狙った。例題等には公的資格である,公害防止管理者試験の類似問題を選び,環境法規関連を重視し,資格試験に対応できるようにした。
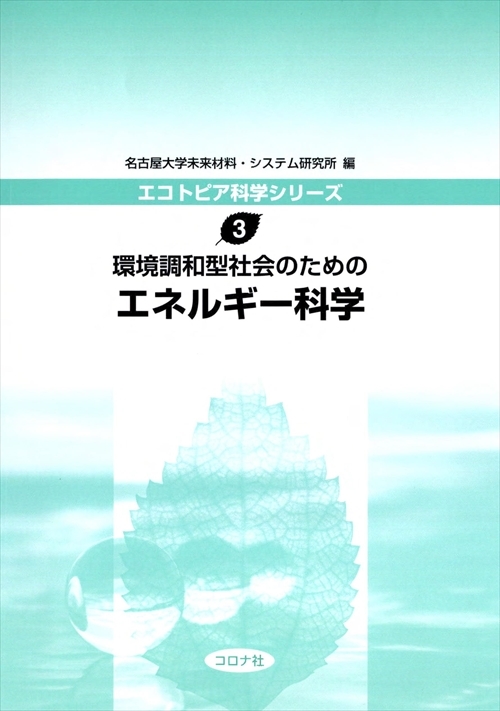
エコトピア科学シリーズ 3
詳細を見る
環境調和型社会のための
エネルギー科学新しい持続的エネルギー生産技術,新しいエネルギー変換技術,新しいエネルギー輸送・貯蔵・利用技術の3章構成。原理と特徴,開発の現状および今後の課題を,それぞれの専門家がこれまでの実績を踏まえて科学的な見地から解説した。
シリーズ:シリーズ 21世紀のエネルギー
化学工学(FRP・腐食防食・化学物質・分析化学など)
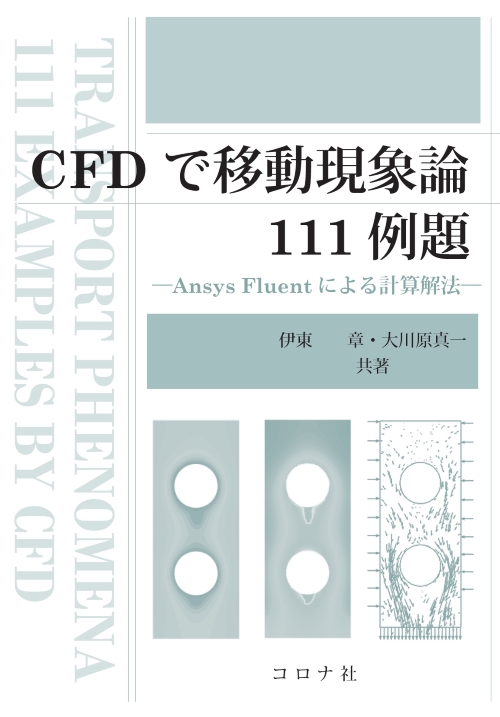
CFDで移動現象論111例題
詳細を見る
- Ansys Fluentによる計算解法 -化学系CFDのメジャーソフトAnsys Fluentによる,化学工学の主要科目である移動現象論に焦点を当てた解説本である。流れ,伝熱,物質移動の三つの観点から構成,特に解析解との比較という点に留意した内容である。
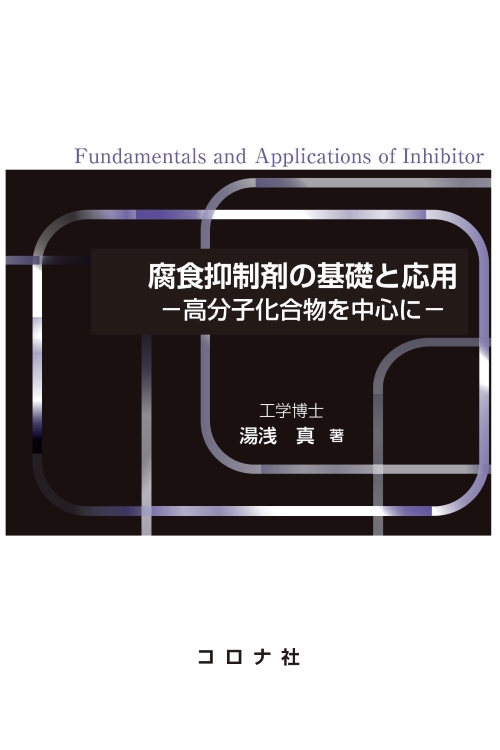
腐食抑制剤の基礎と応用
詳細を見る
- 高分子化合物を中心に -冷却水系,ボイラー系のような水誘導装置系で多く用いられている腐食抑制剤(腐食インヒビター)について,高分子化合物類を中心に,その作用機構も含めて解説する。また,環境問題の観点から水質と金属腐食の関係についても触れる。

Pythonで動かして始める量子化学計算
詳細を見る本書は,量子化学計算に関する初学者向けの入門書である。特に,PythonとPsi4を用いて量子化学計算の基本を学ぶことを目的としているが,計算ソフトに依存しない普遍的な概念を習得できるように心がけて執筆した。
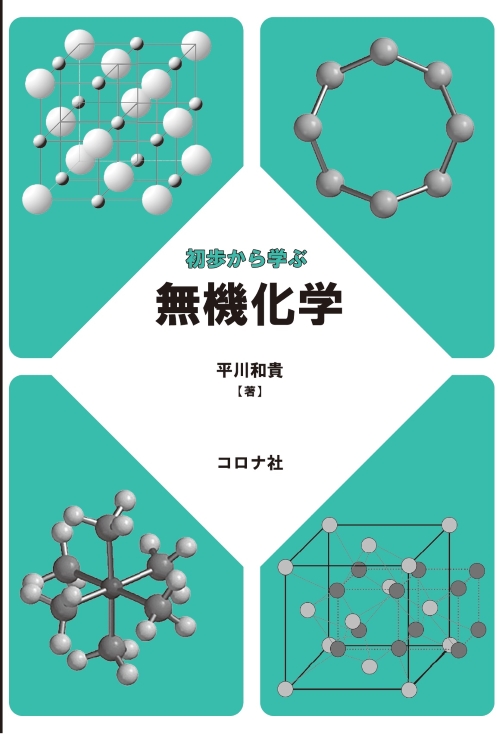
初歩から学ぶ無機化学
詳細を見る本「モノづくりのための学問」を志す人にとって,無機化学は本質的に重要な分野である。本書は,先人たちが開拓し,まとめあげた元素についての知識を「暗記」ではなく,「理解」することで学ぶことを目的としている。
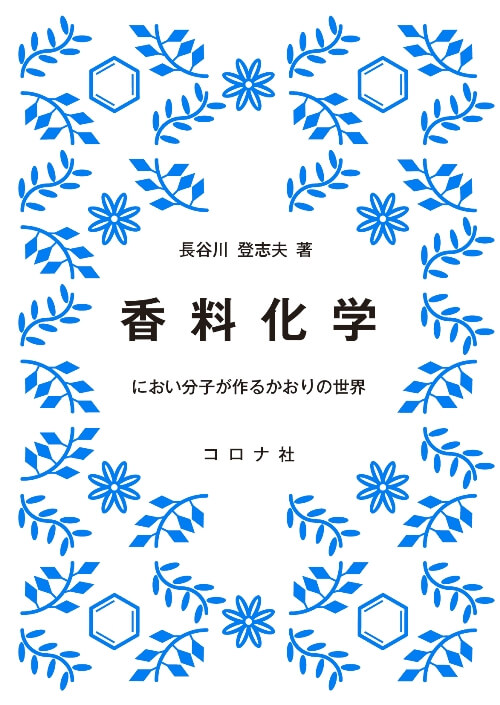
香料化学
詳細を見る
- におい分子が作るかおりの世界 -においを題材とした系統的な化学の教科書であり,基本的な有機化学をもとに人がにおいを感じる仕組みを説明する。また実際のにおい分析の様子や,分子の構造とにおいの関係などのテーマについて,著者の研究例をもとに解説する。
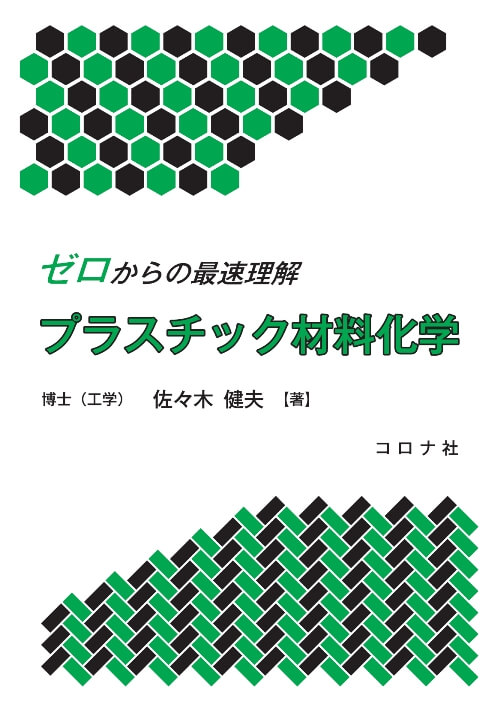
ゼロからの最速理解
詳細を見る
プラスチック材料化学プラスチックに携わる読者のための入門書。身の回りにある様々なプラスチック製品や繊維,フィルム,ペンキ,ゴムなどが具体的にどんな素材でできているのかを,その開発のエピソードなどを交えつつ,わかりやすく解説する。
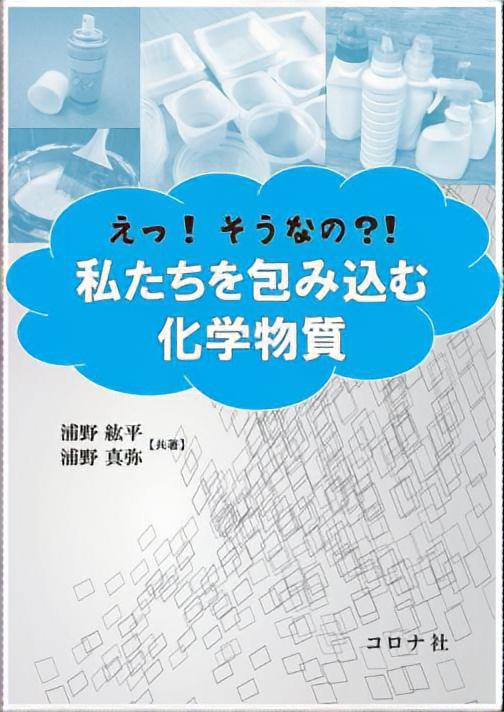
えっ! そうなの?!
詳細を見る
私たちを包み込む化学物質農薬,化学肥料,プラスチック,合成洗剤,家庭用の殺虫剤等の化学製品はずいぶん身近なものとなった。これらの貢献と化学物質による被害例を紹介するとともに,関連する法律の現状を解説し,化学物質と上手に付き合う方法を示す。
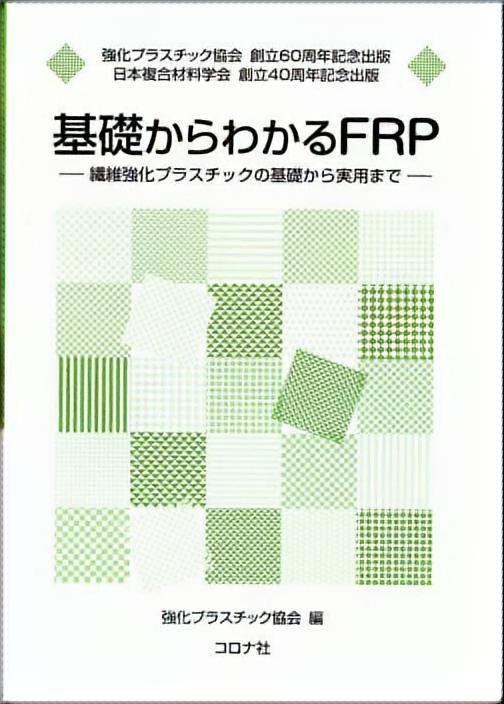
基礎からわかるFRP
詳細を見る
- 繊維強化プラスチックの基礎から実用まで -本書は,近年,軽量化や省エネ材料として脚光を浴び,自動車や航空機などの構造材料として適用が拡大しているFRP(繊維強化プラスチック)について,素材としての特色とその成形法に重点を置き実例を交えてやさしく解説している。
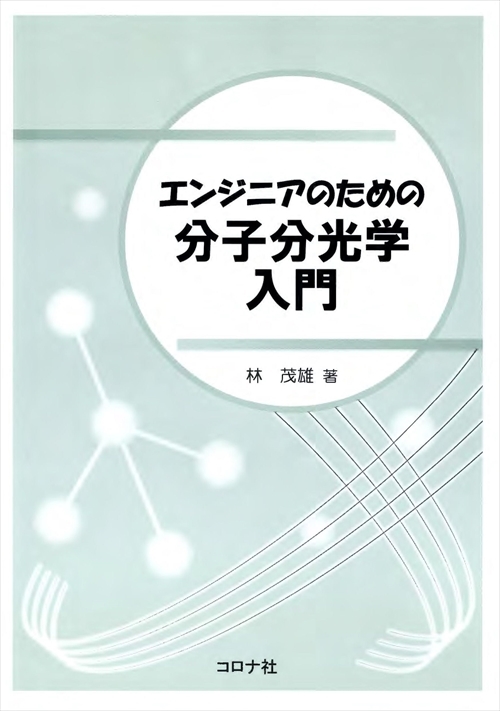
エンジニアのための
詳細を見る
分子分光学入門本書は,分子分光学をこれから学ぼうとしている学生や技術者の理解・アイディア創出の一助となるよう,天体からの分光や粒子線と磁気共鳴など幅広い対象をわかりやすく解説した。また身近な素材でできる分光実験も多数掲載した。
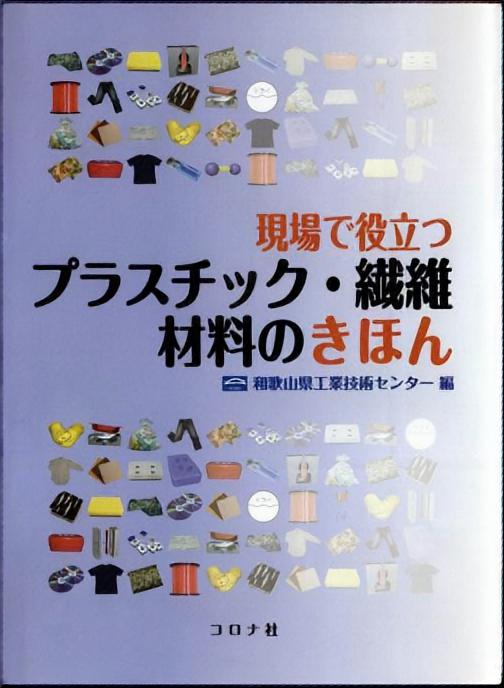
現場で役立つ
詳細を見る
プラスチック・繊維材料のきほん
- 4色刷 -プラスチック・繊維材料の特徴,用途,鑑別方法など,商品開発や商取引をするために必要不可欠な基礎知識を,営業や製造現場で参考書として使えることを原則に,図と写真を多用し,イメージで理解できるようにした。本文4色刷。










