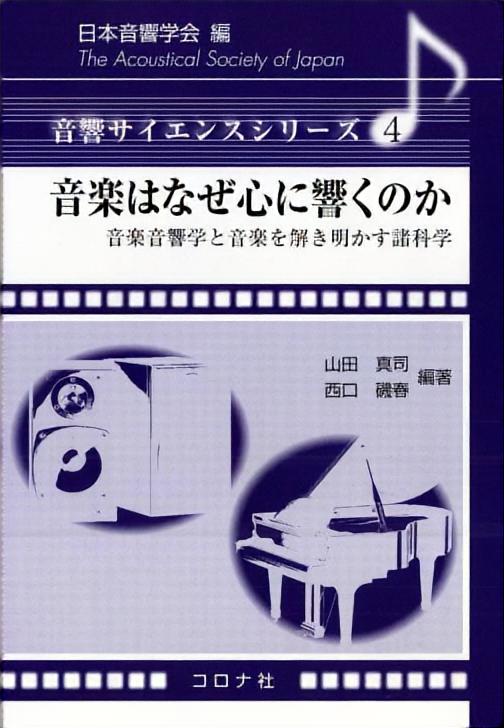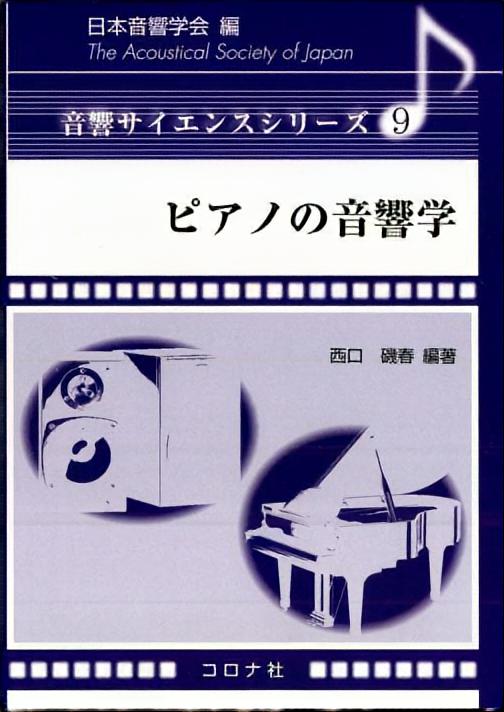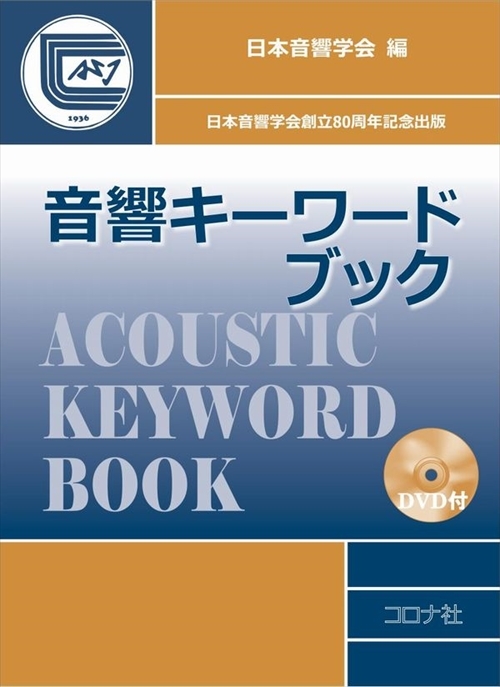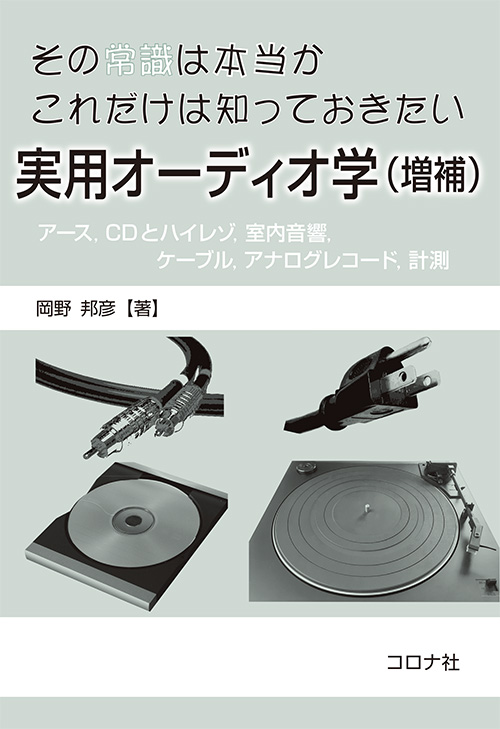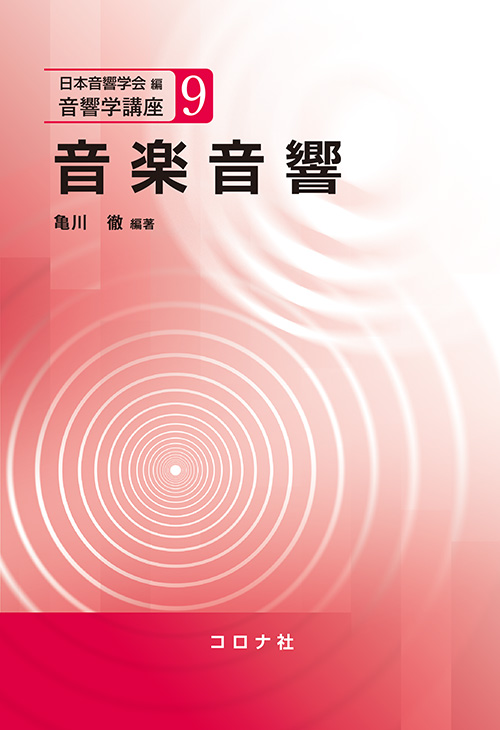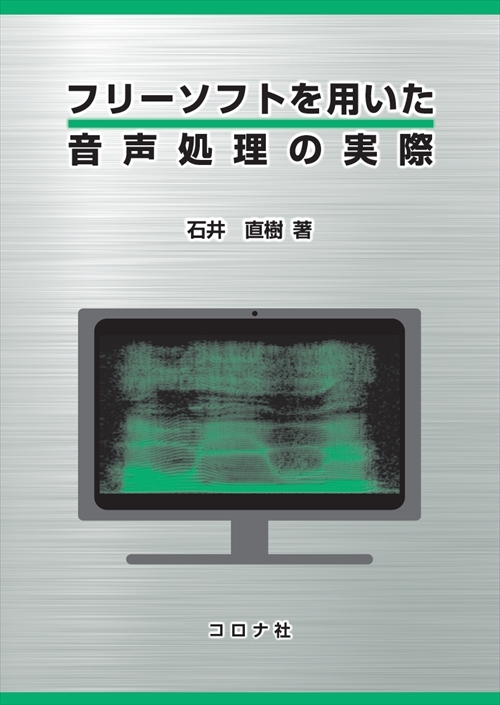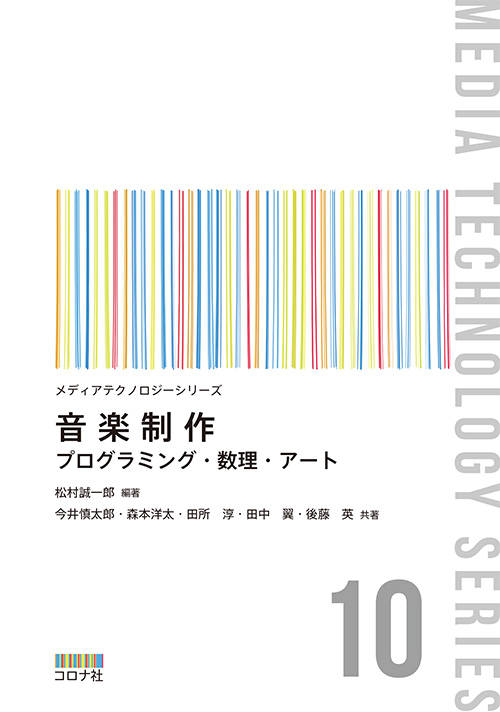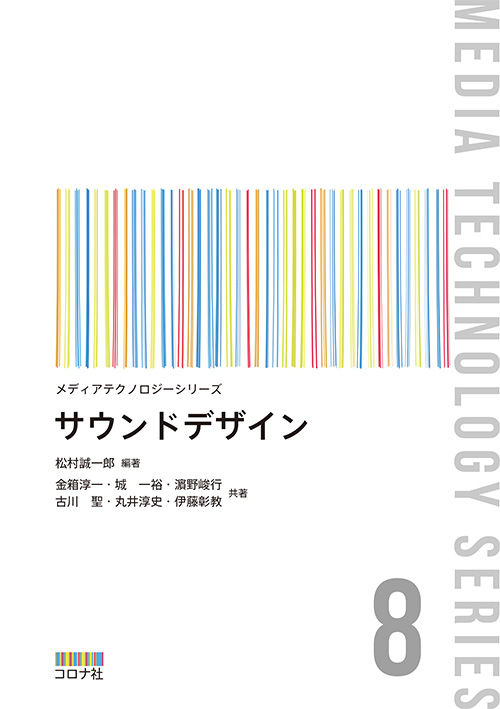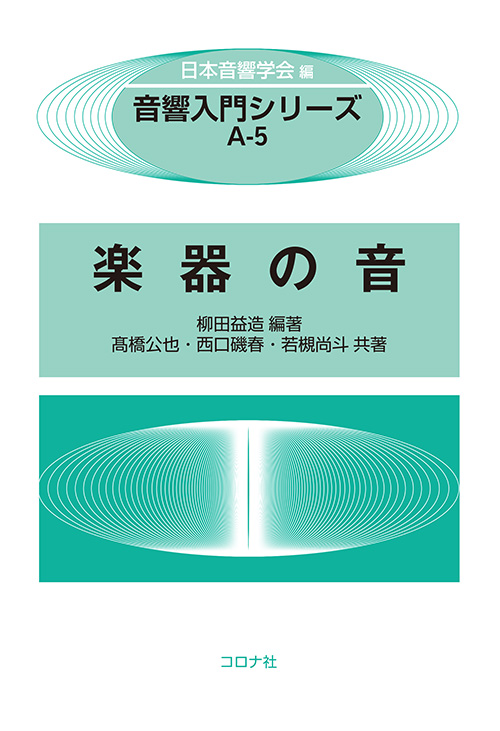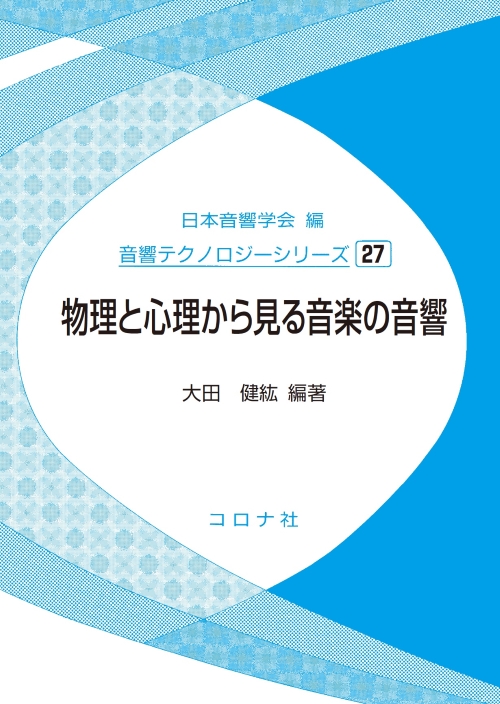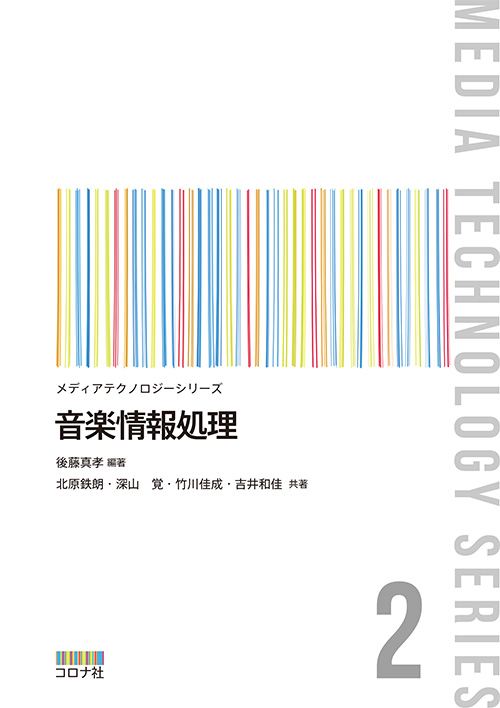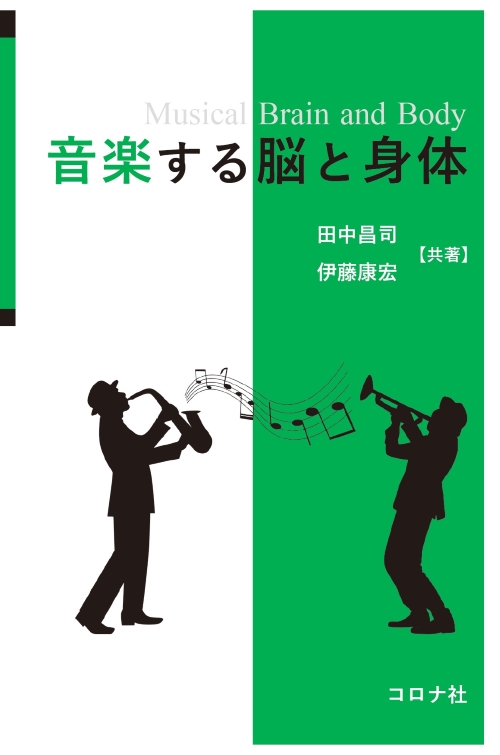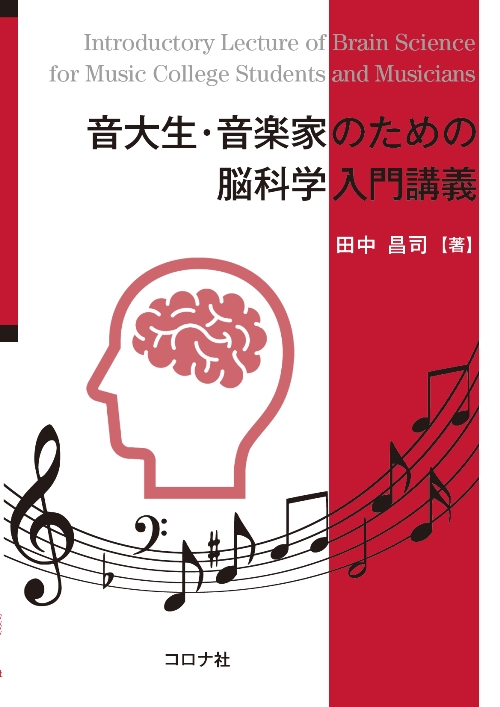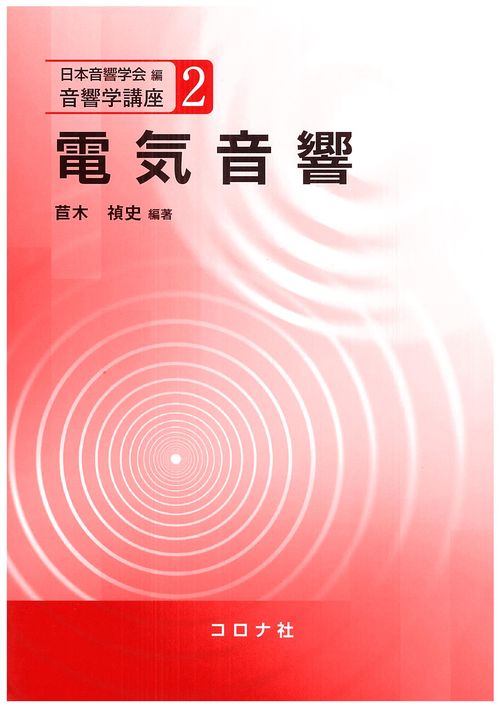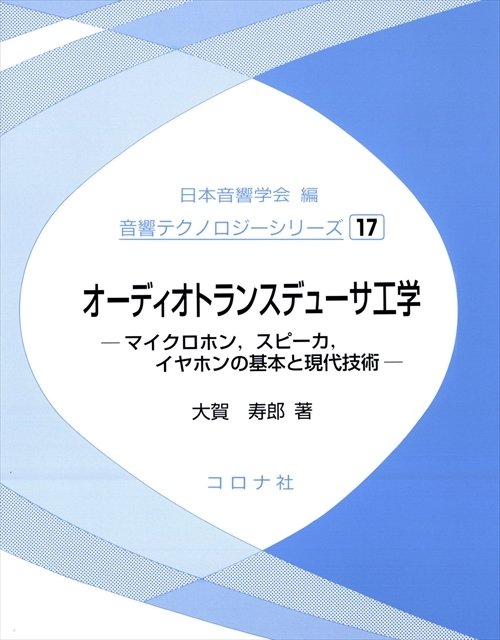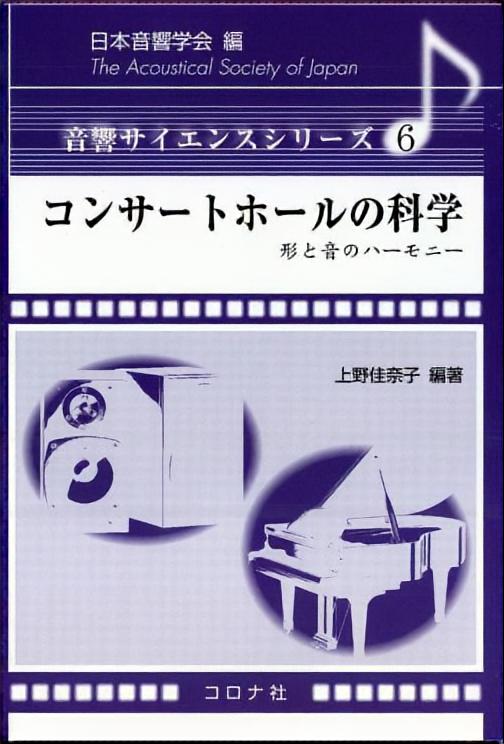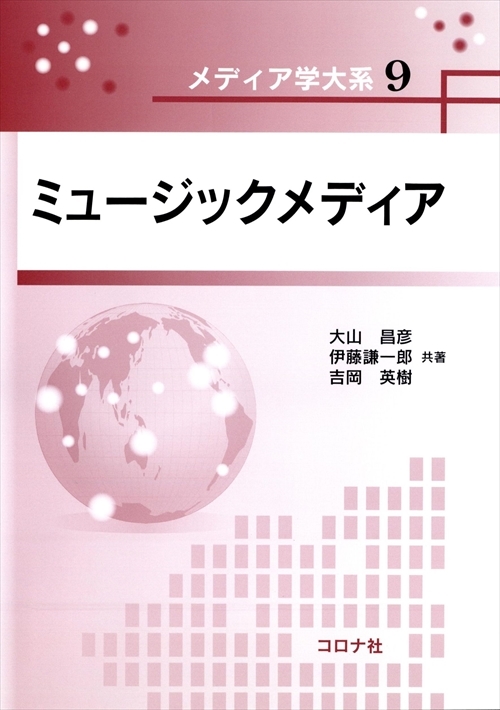
メディア学大系 9
ミュージックメディア
音楽文化とメディアの関わりに加え,音楽産業がどのようなしくみになっているのか,さまざまな音楽表現のあり方についてまとめた。
- 発行年月日
- 2016/09/26
- 判型
- A5
- ページ数
- 240ページ
- ISBN
- 978-4-339-02789-1
- 内容紹介
- 目次
- 広告掲載情報
【読者対象】
音楽に関心を持つ学生。特に音楽のコンテンツ制作や流通を学びたい学生。
【書籍の特徴】
「音楽が好き」「いつも聞いている」と思っている人に、自分の音楽生活がどのような歴史、技術、制度、そして表現方法を背景に成り立っているのかを分かりやすく伝えること、そこから改めて自分の音楽生活を振り返ることで、大学生として音楽とより楽しく、知的なつきあい方をしてもらえるようになって欲しいと思い本書を書きました。何気なく聴いて楽しんでいる音楽がどのような技術やアイデアで作られ、耳元まで届いているのか、その仕組みはどのようになっているのかをわかりやすく説明しています。
【各章について】
本巻は大きく分けて二つのパートから構成されています。 1章から4章までは音楽メディアの技術的変遷と音楽コミュニケーションの変化を説明しています。 1、2章では、楽譜から,音楽ファイルまで音楽メディアの変遷を説明しています。 3章では、音楽文化の中核である日本の音楽産業の現状を、その産業構造と制度とテクノロジーの変化を踏まえて概観しています。 4章では、音の物理的特性とそれが人の耳に届けられる基本的なプロセスを解説しています。
つづく5章から8章までは、音楽表現で不可欠な音楽理論を分かりやすく説明しています。 5章では、音を音楽にするための、音高の秩序のある規則性や 構成原理の歴史を解説しています。 6章以下では「音楽の三要素」をそれぞれ解説しています。 6章では、「リズム」の組織化の原理を人間の内面で心理的に生起する拍子感との関係から、7章では、「メロディ (メロディー)」をその形式や展 開に着目することから, 8章では、西洋音楽で高度に発展した「ハーモニー」 に注目し音楽の構成技法の根本的な思想と理論を解説しています。
【著者からのメッセージ】
私たちの日常生活では音楽があふれています。音楽を耳にしない日はないでしょう。耳にする音楽は誰かが作ったものですが、音楽を作った人、演奏している人はそこにはいません。音楽があふれる日常生活とは、時間と空間を共にしない誰かが作り出した音楽を、「メディア」の仲立によって経験したものである、と言っても過言ではないでしょう。これまで人は見えない誰かに向けて、どのようにメディアを使って音楽を作り伝えたのでしょうか。音楽のメディアの変容は、伝え方や音楽の価値をどのように変えたのでしょうか。そして私たちの音楽生活はどのように成立していったのでしょうか。この本を通じて、これまでの音楽経験では見えない部分を理解することで、ありふれた音楽生活をより有意義な経験にしてもらえることを願ってやみません。
1.音楽文化と楽譜
1.1 メディアと音楽文化
1.2 記譜法の発達
1.3 音楽の商業化と芸術化の進展
1.3.1 音楽の商業化とイデオロギーとしての芸術化
1.3.2 音楽作品の重要性とアーティストの神格化
1.4 音楽メディアの作品化と音楽著作権
1.4.1 音楽著作権の誕生
1.4.2 コピーライトとオーサーズライト
1.5 世界音楽経済システムの誕生
演習問題
2.音楽文化と音響技術
2.1 技術の社会的配分と世界音楽経済システムの強化
2.1.1 録音・再生・複製技術の社会的受容と再配分
2.1.2 音楽制作とテクノロジー
2.2 レコード作品における同一性の解体
2.2.1 DJイングの意義
2.2.2 ラップの商業化と世界音楽経済システムとのコンフリクト
2.2.3 マルチモーダル化する音楽
2.3 ディジタル化と世界音楽経済システムの動揺
2.3.1 ディジタル化による世界音楽経済システムの動揺
2.3.2 アーカイブとしてのインターネットと創作活動の活発化
2.3.3 世界音楽経済システムの危機?
2.3.4 ソーシャル化する音楽
2.4 音楽メディアと音楽文化のこれから
演習問題
3.音楽産業とメディア
3.1 レコード産業に関わる人々
3.1.1 音楽を作る人
3.1.2 音楽を売る人
3.1.3 音楽で儲かる人
3.1.4 メジャー以外の音楽活動
3.2 日本における音楽著作権管理
3.2.1 著作権管理事業とは
3.2.2 著作権使用料の分配方法
3.2.3 著作隣接権の管理
3.3 レコード産業とオーディオ産業
3.3.1 LPレコードの登場とオーディオ産業の始まり
3.3.2 CD発売とディジタル化が音楽産業に与えた影響
3.3.3 音楽ソフトの生産金額推移
3.4 電子楽器の変遷と音楽産業への影響
3.4.1 モジュラー・シンセサイザーの登場と普及
3.4.2 シンセサイザーのディジタル化
3.5 音楽制作環境の変化
3.5.1 マルチトラックレコーディング
3.5.2 MTRを活用したライブパフォーマンス
3.5.3 ディジタル録音の時代
3.5.4 コンピュータによる音楽制作
3.6 音楽産業とメディア
3.6.1 メディアの変遷と音楽産業
3.6.2 インターネットの普及と音楽産業への影響
演習問題
4.音
4.1 音の伝播
4.2 波形の表示
4.3 音の分類
4.4 音の属性と波形による表示
4.5 倍音
4.6 複合音と倍音構成
演習問題
5.楽音の組織化
5.1 音律
5.2 ピュタゴラス音律
5.3 純正律
5.4 中全音律
5.5 平均律
5.5.1 長所と短所
5.5.2 普及の背景
5.6 音階
5.6.1 長音階の構成
5.6.2 短音階の構成
5.7 旋法
演習問題
6.拍子・リズム
6.1 パルスと拍
6.2 拍子と拍節
6.2.1 定義と特徴
6.2.2 エネルギーの周期変化としての拍子
6.3 リズム
6.3.1 リズムの形成
6.3.2 「拍節的リズム」と「自由リズム」
6.4 拍節から逸脱するリズム
6.4.1 シンコペーション
6.4.2 拍節との関係性によるシンコペーションの生成と消失
6.4.3 シンコペーションとテンポ
6.4.4 そのほかのシンコペーション
6.4.5 ヘミオラ
6.5 複数のリズムの位相変化によって生じる現象
演習問題
7.メロディ
7.1 メロディが内包する要素
7.2 音の進行
7.2.1 反復と変化
7.2.2 音高線におけるコントラスト
7.3 動機(モティーフ)
7.3.1 動機と部分動機
7.3.2 動機の構成
7.3.3 動機の諸形態
7.4 楽節
7.4.1 小楽節
7.4.2 小楽節の諸形態と作例
7.4.3 大楽節
7.4.4 大楽節の諸形態と作例
7.4.5 実作品に見る大楽節の諸形態
7.4.6 大楽節の実際的な形態
7.4.7 大楽節と楽曲形式
7.5 メロディの展開
7.5.1 フレーズの変形
7.5.2 クライマックスの形成
演習問題
8.ハーモニー
8.1 和音と和声
8.2 和音の構成と和音表記法
8.2.1 三和音の基本形とその構成
8.2.2 三和音の転回形
8.2.3 三和音の表記法
8.2.4 七の和音の構成と表記法
8.3 和音の機能
8.3.1 和音と調の関係性
8.3.2 主要三和音における機能とカデンツ
8.3.3 各和音の機能と終止
8.4 メロディとハーモニーの関係
8.4.1 和声音と非和声音
8.4.2 非和声音の種類
演習問題
引用・参考文献
索引

-
掲載日:2024/10/01
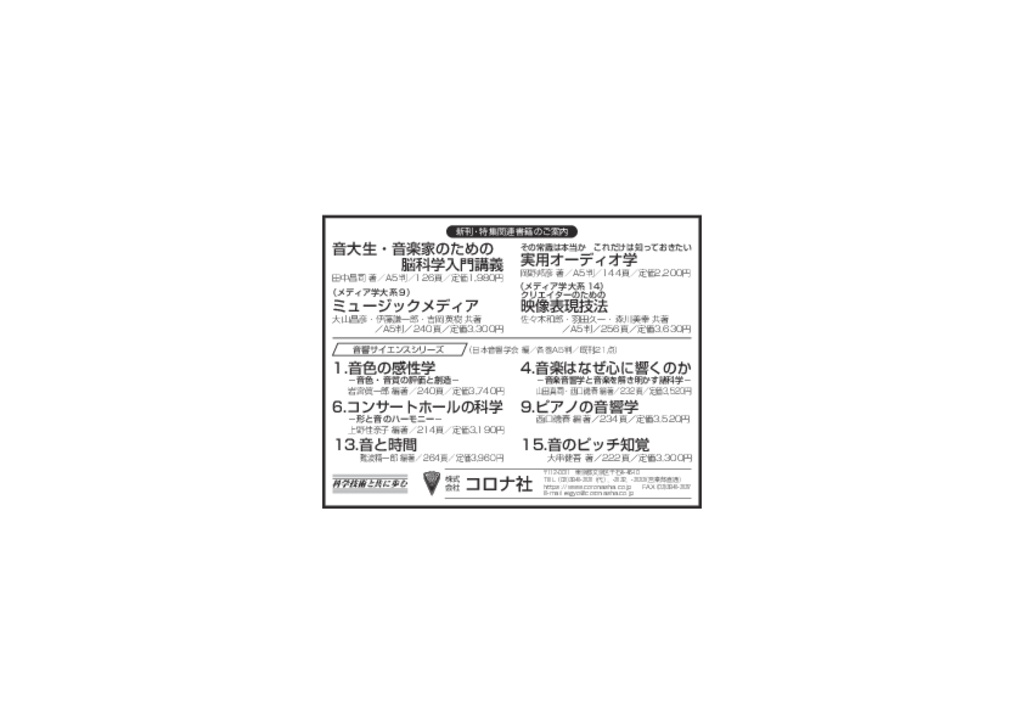
-
掲載日:2022/03/28

-
掲載日:2021/05/27
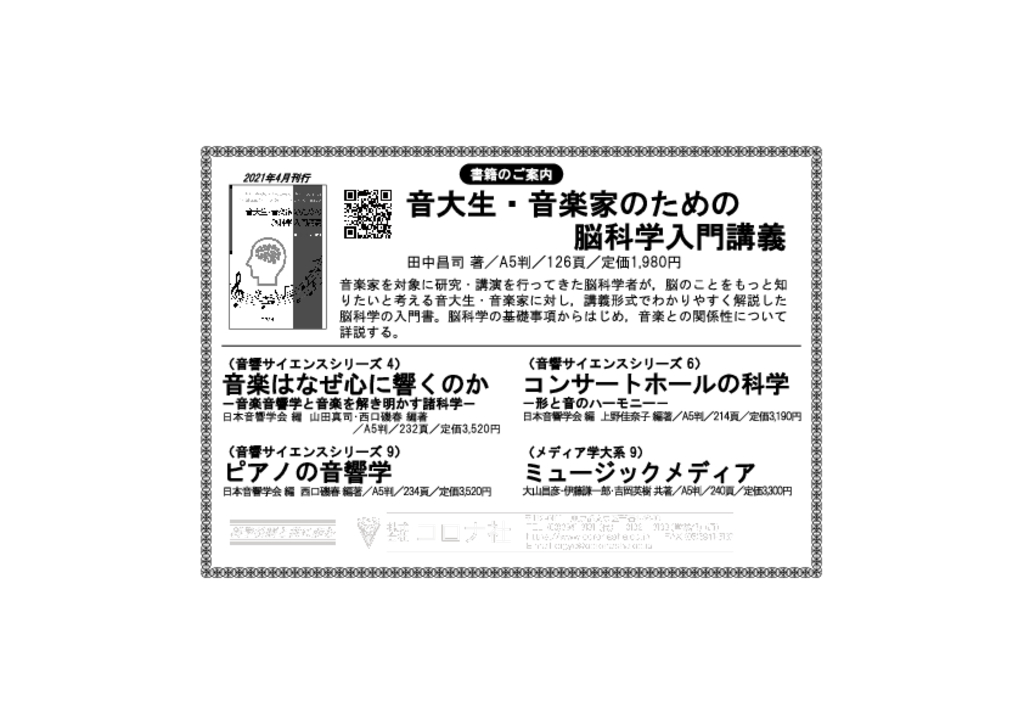
-
掲載日:2021/05/06