11/30
ロボット工学ハンドブック(第3版)特集

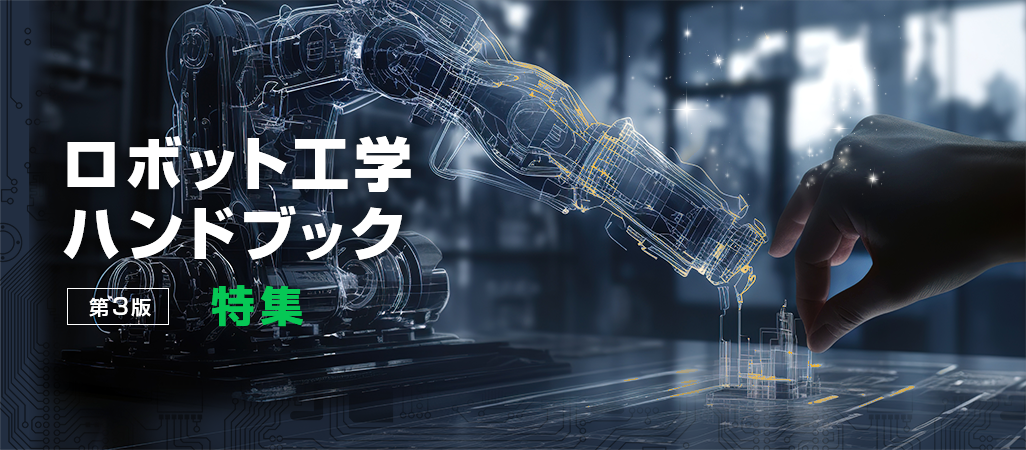
大型本『ロボット工学ハンドブック(第3版)』に関する書籍を集めました。
トピックごとにまとめてご紹介します。
今回は主に目次の「第Ⅳ編」の関連書をピックアップしました。
ヒューマンロボットインタラクション
人間の意図または意図のために生成した脳活動を脳計測によって読み取り,本人の意図を外部へ伝達する技術であるブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)のタスク・刺激と出力の関係(パラダイム)や信号処理を解説した。
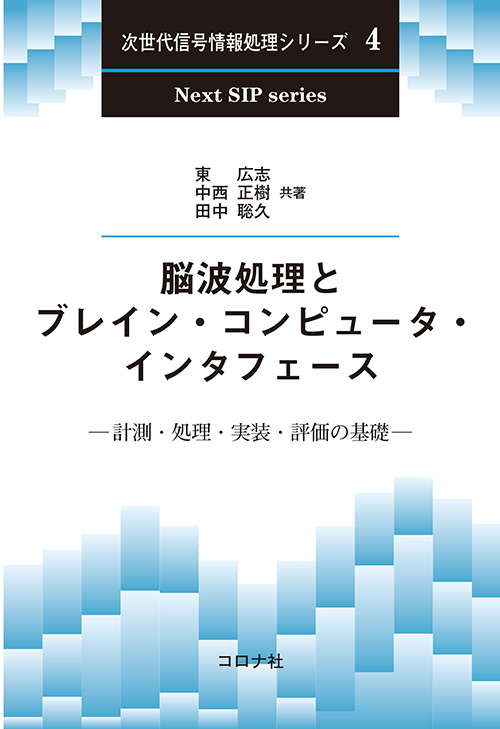
次世代信号情報処理シリーズ4
詳細を見る
脳波処理とブレイン・コンピュータ・インタフェース
- 計測・処理・実装・評価の基礎 -本書は,人が持つ視覚・聴覚など複数の感覚器を通して行われるコンピュータとのインタラクションコミュニケーションを可能にするための基礎理論と,それを支える要素技術についてわかりやすく解説している。
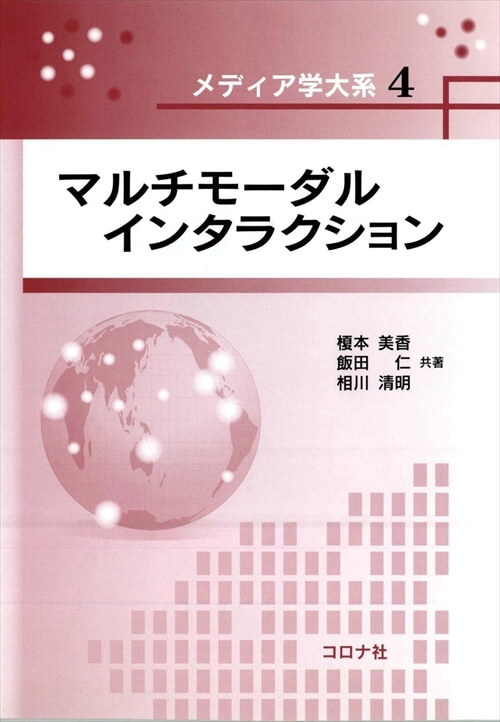
メディア学大系4
詳細を見る
マルチモーダルインタラクションコンピュータは,人につねに関わるものとなり,その用途が生活のあらゆる局面に及ぶように拡大してきた。本書では,これまでのそうした変遷の内容を知り,人の意識や行動指針への影響を多様な視点から解説した。
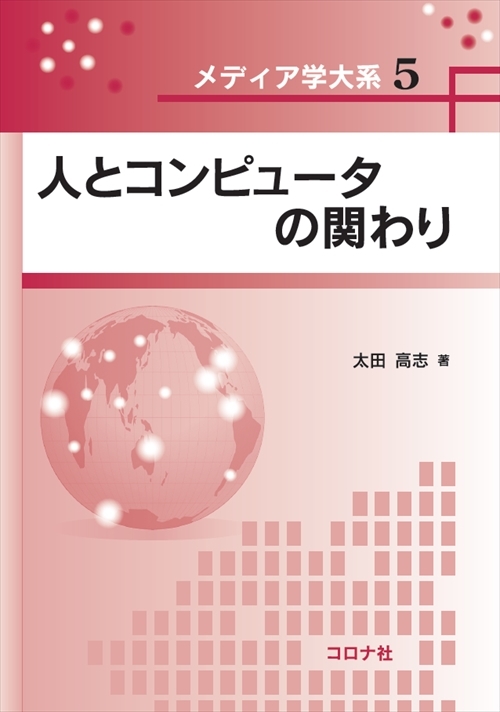
メディア学大系5
詳細を見る
人とコンピュータの関わりヒューマンインタフェースとは,モノと人間の境界部分のことである。本書は高専や大学,大学院の教科書として,人間の特性や心の働きについても知った上で,ヒューマンインタフェース開発の勉強をしてもらうために執筆した。
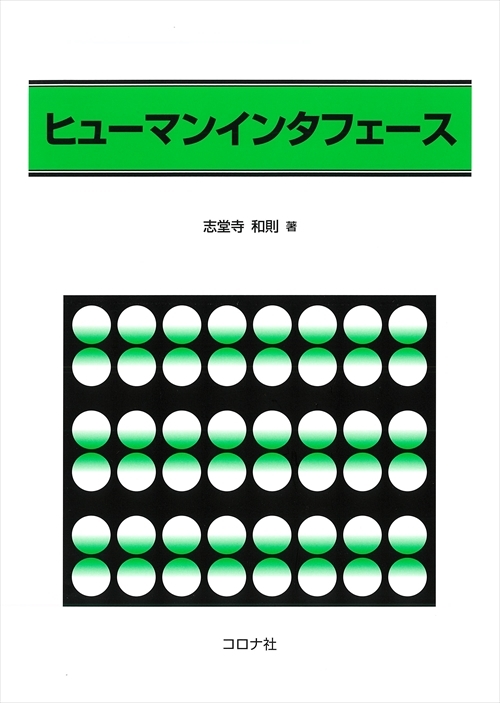
ヒューマンインタフェース
詳細を見るHCIやHIの初学者に向け,「人間に関すること」,「HCIの基礎知識」,「HCIの評価方法」について丁寧に説明している。実際に手を動かし,穴埋め欄に書き込むことで,効率的にHCIやHIについて学び,整理することができる。
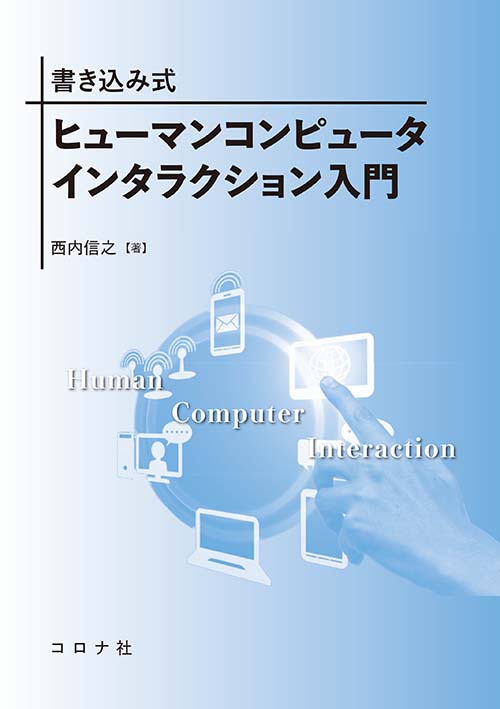
書き込み式
詳細を見る
ヒューマンコンピュータインタラクション入門安全で快適な機器を設計するためには,人間の特性に適合した人間中心設計が必要である。人間特性には多くの側面があるが,本書では特に人間中心設計の基となる感覚特性を解説するとともに,その計測および解析手法について説明する。
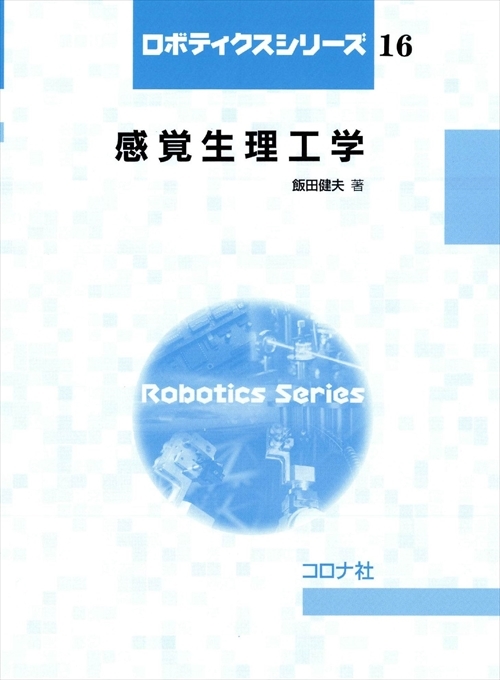
ロボティクスシリーズ16
詳細を見る
感覚生理工学本書は受動歩行ロボットを実際につくって動かすことを目指す。Part Ⅰで第一義的に「つくる」ことを目指す。また,Part Ⅱでは数理的な考察が展開できるように,受動歩行ロボットの力学についてもポイントを述べた。
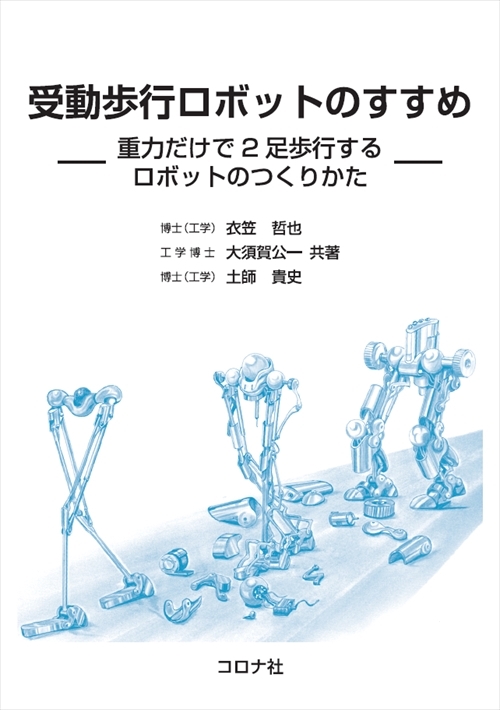
受動歩行ロボットのすすめ
詳細を見る
- 重力だけで2足歩行するロボットのつくりかた -本書は,文理系の大学生がはじめて脳科学および認知科学を学ぶ際の教科書を想定して執筆した。可能な限り図を多く掲載し,初学者でもわかりやすく,かつ教科書としての一定のレベルを保った専門的知識を提供する教科書となっている。
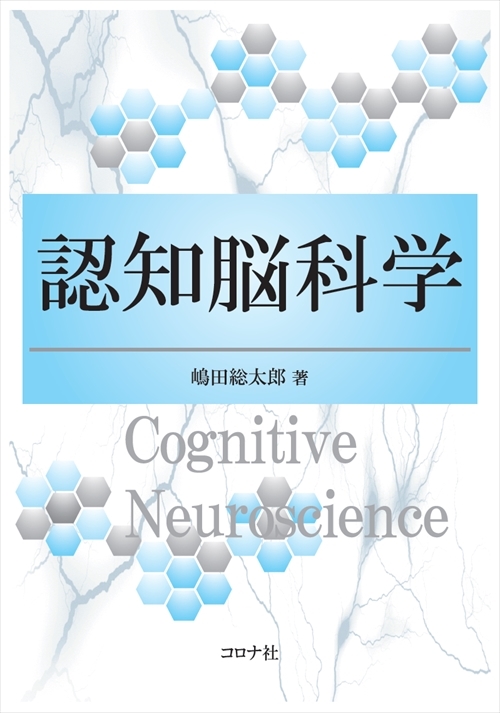
認知脳科学
詳細を見る
産業・サービス
旧版では主にロボットアーム(マニピュレータ)を対象とし運動学,静力学,動力学について解説したが,改訂版ではさらに独学を考え専門分野の研究で必要な基礎を充実させる話題や,知識や手法の実際の使用場面を考慮した説明を加筆。
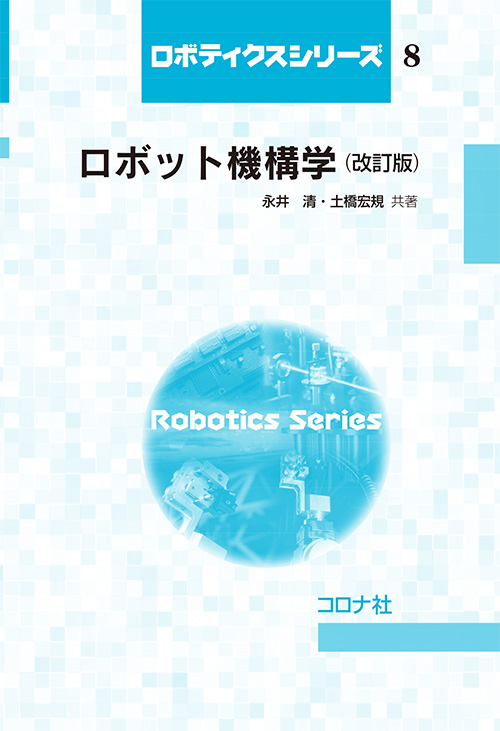
ロボティクスシリーズ8
詳細を見る
ロボット機構学(改訂版)ロボットの,人とのかかわりの深い存在への進化の要因である機械力学,電子,制御,情報,センサ,材料等の幅広い工学の進歩と連携について紹介する。パソコンによる表計算,行列計算,各種シミュレーションが取り入れられている。
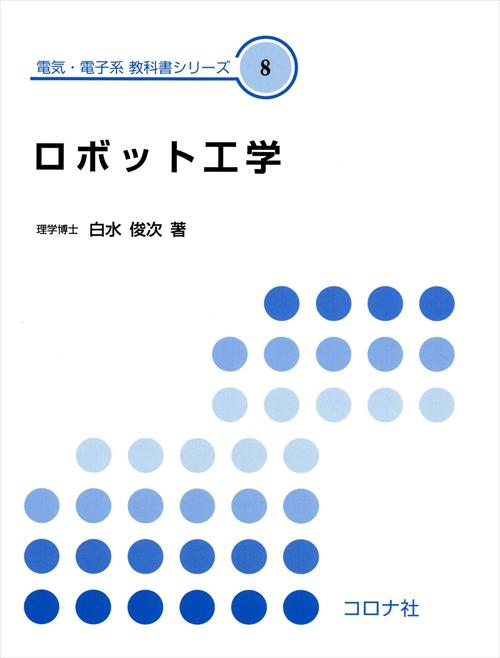
電気・電子系 教科書シリーズ8
詳細を見る
ロボット工学本書は,コンピュータビジョンすなわち計算機による視覚の数理と幾何を,非ユークリッド幾何をもとに基礎から最新理論までを平易に解説した。高度な内容も無理なく学べるよう,多くの図表を使い,直感的に理解しやすい構成とした。
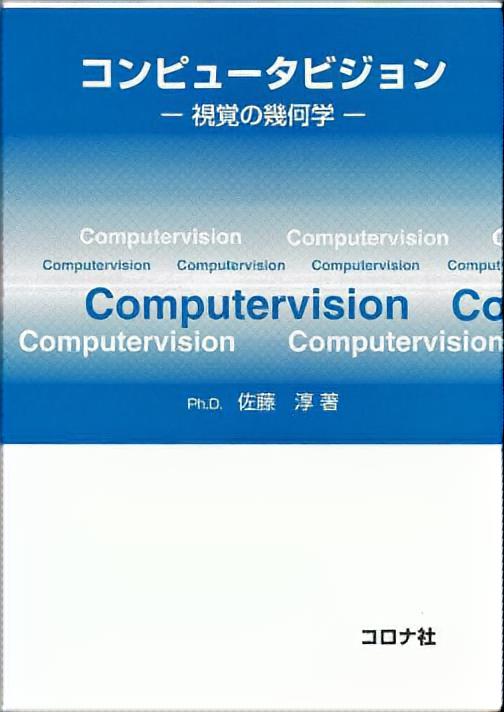
コンピュータビジョン
詳細を見る
- 視覚の幾何学 -急速な発展を続けながらも,わかりにくい印象を持たれがちなIoTについて,ロボット開発などを例に基礎から解説する。IoTの横断的な全体像を学ぶことを目指す。大学生,若手技術者におすすめの一冊。
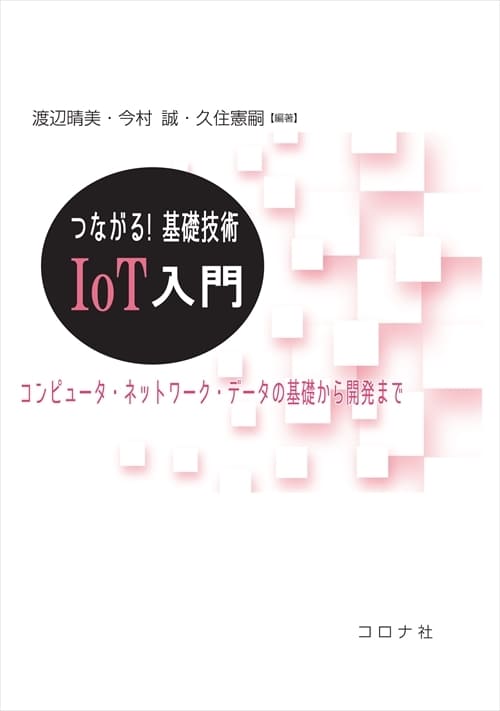
つながる! 基礎技術
詳細を見る
IoT入門
- コンピュータ・ネットワーク・データの基礎から開発まで -アーム付き自律移動ロボットを例にとり,その構成要素(ハードウェア,ナビゲーション機構,アーム制御機構,機械学習,システムアーキテクチャ)を原理に基づいて学ぶことで,IoT システムの全体像を理解できるよう解説した。
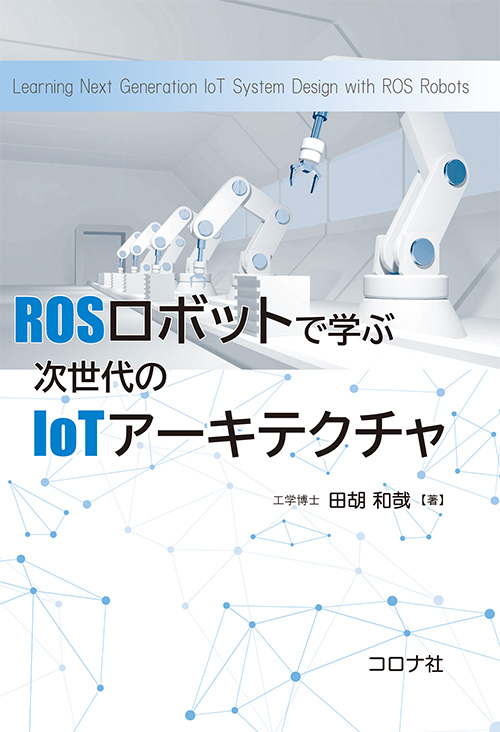
ROSロボットで学ぶ次世代のIoTアーキテクチャ
詳細を見る千差万別ともいわれるセンサ技術を,その広い分野の中で,代表的ニーズがあると考えられる技術に対象を絞り,専門家でない人にもわかりやすいよう,基礎編と応用編にわけて解説している。
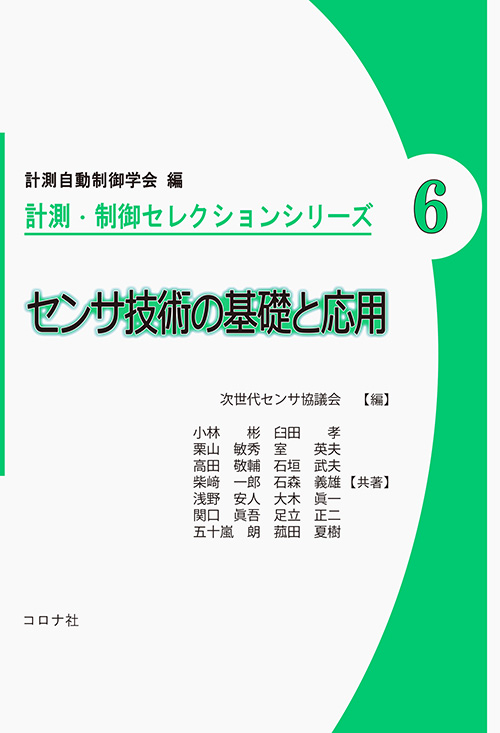
計測・制御セレクションシリーズ6
詳細を見る
センサ技術の基礎と応用ロボット・マニピュレータ(手)の計算機制御に関し,体系的・学問的な記述をした世界で最初の書物である。
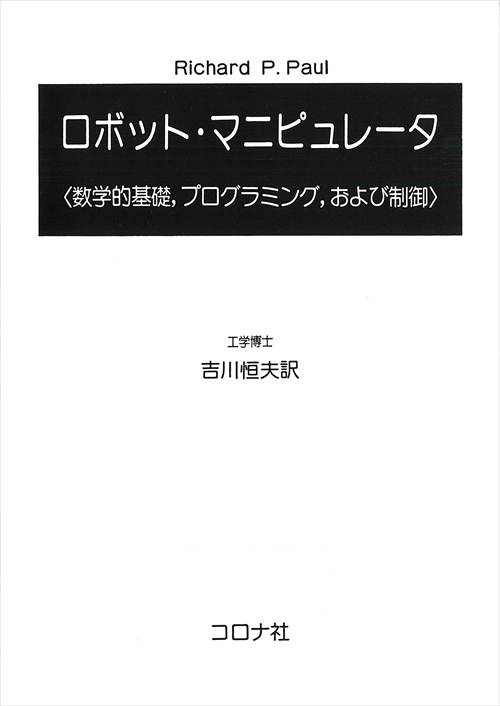
ロボット・マニピュレータ
詳細を見る
- 数学的基礎,プログラミング,および制御(ROBOT MANIPULATORS) -生産のシステム化に関わる現状の基礎技術を体系的にまとめるとともに,産業界の実用例も豊富に取り込んで,現場技術者の有用な情報を提供するだけでなく,システム化技術の今後の開発に対する基礎ともなるようわかりやすく述べた。
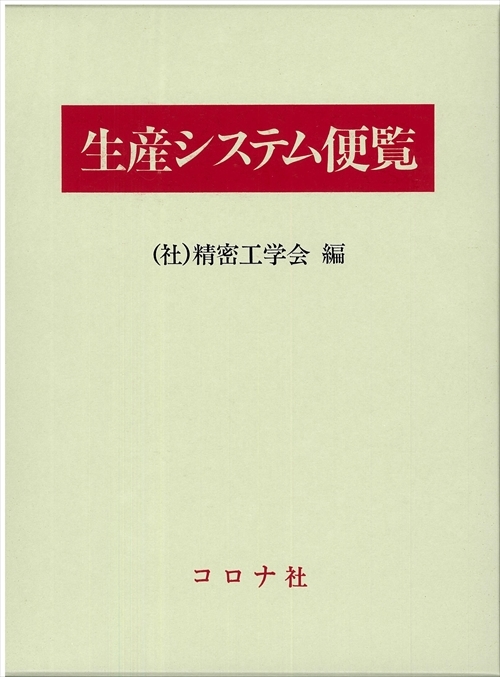
生産システム便覧
詳細を見るセンサの原理とその応用を学習する人に,メカトロニクス・ロボティクス分野で代表的なセンサを精選して記述した。また,システム全体の機能の実現のためのセンサの役割,およびセンサに求められる性能などを可能な限り記述した。
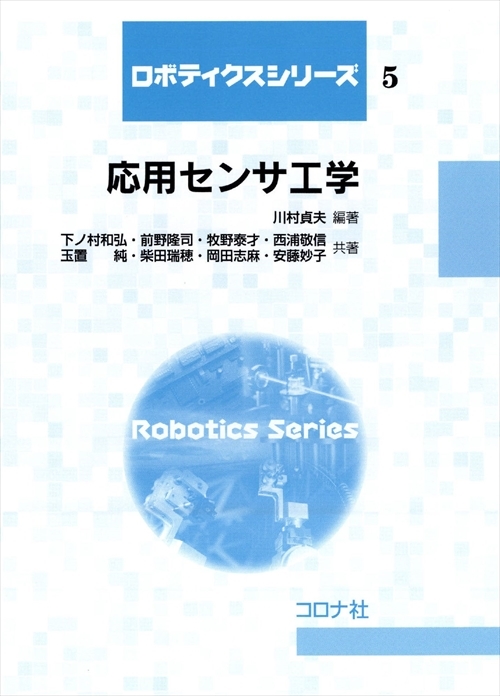
ロボティクスシリーズ5
詳細を見る
応用センサ工学本書では,ロボットが自ら環境を認識し,運動を計画し,環境や物体に触れながら作業するための科学的根拠をなるべく原点に立ち戻って講述する。後半では,ロボティクスと脳科学の観点から,身体運動の巧みさの源泉となる知能に迫る。
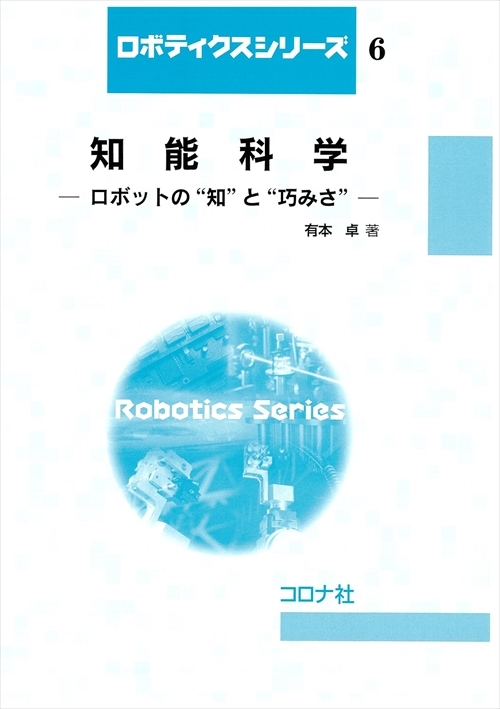
ロボティクスシリーズ6
詳細を見る
知能科学
- ロボットの“知”と“巧みさ” -本書では,機械システムの物理モデリングから数値シミュレーションの技法,制御系の安定解析法について述べ,さらに宇宙機と移動ロボットを具体例として取り上げてモデリングから制御系の設計までがどのようになされているかを示す。
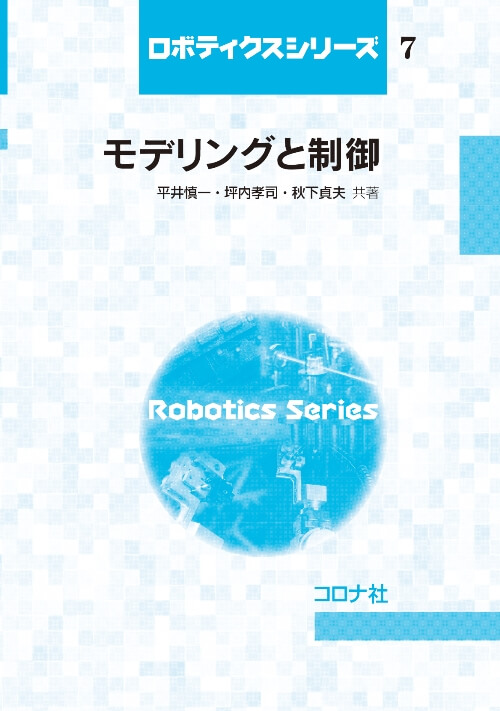
ロボティクスシリーズ7
詳細を見る
モデリングと制御オートメーションは,各種ハイテク技術を低価格で多くの人に提供し,国の富を増やす重要な技術である。本書は,生産工場で使われる基本的,先端的技術を体系的にまとめ,わかりやすく解説する。
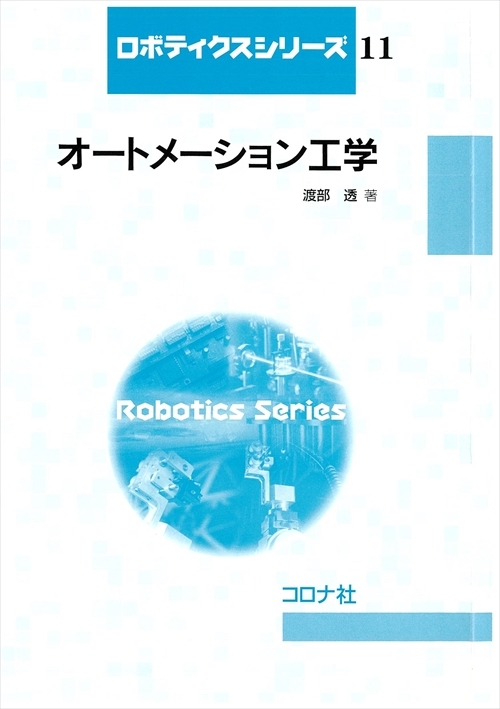
ロボティクスシリーズ11
詳細を見る
オートメーション工学メカトロニクス・ロボティクスの分野では,目的に応じてアクチュエータを適切に使い分ける必要がある。そこで本書では,種々のアクチュエータのメカニズムと基礎的動作原理,制御の視点でのモデリング,実際の応用例などを紹介する。
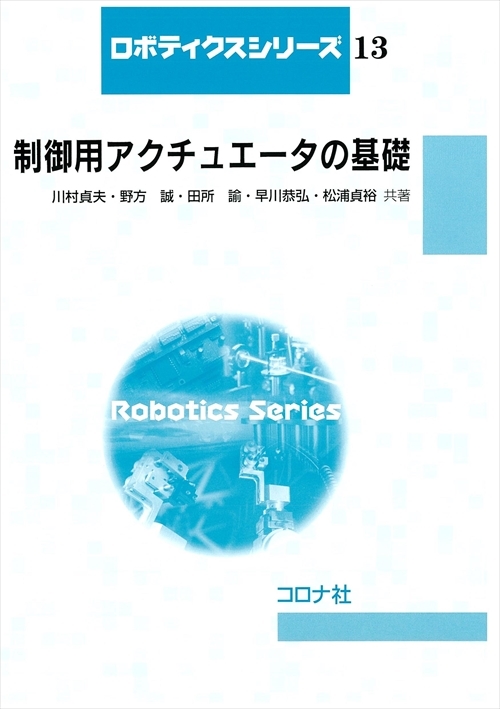
ロボティクスシリーズ13
詳細を見る
制御用アクチュエータの基礎人が手を用いて,ものをつかんだり,移動させたりする作業を総称してハンドリングという。ハンドリングでは物体と物体の相互作用が重要となる。そこで本書では工学的な立場から,ハンドリングにおける幾何学と力学の基礎を解説する。
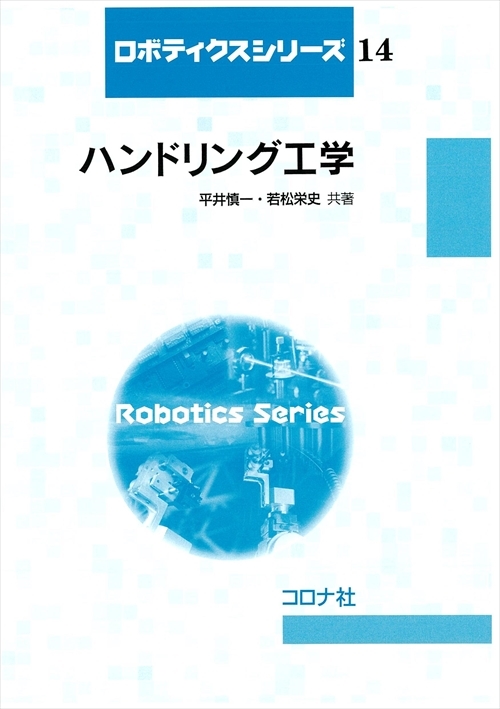
ロボティクスシリーズ14
詳細を見る
ハンドリング工学マシンビジョンとは,知能機械システムが外界の状況変化に適応した知的な動作制御をしたり,対象の認識・計測を行うための視覚情報処理技術である。本書は大学の1セメスタで扱える範囲の基本的で実用に即した技術を中心にまとめた。
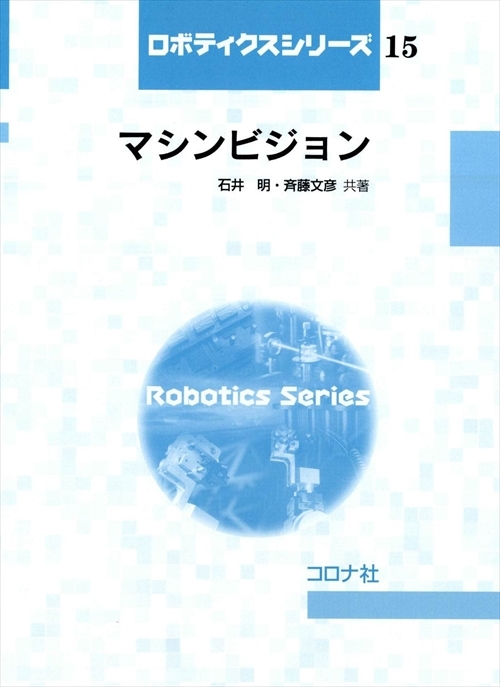
ロボティクスシリーズ15
詳細を見る
マシンビジョン
農業・災害
本書はSNIPによる独自のRTK基準局の開設により,読者が気軽に1周波数GNSS受信機を利用し,実務として運用することを目的としている。また実際の運用例として,測量や農業分野での利用についても詳しく紹介している。
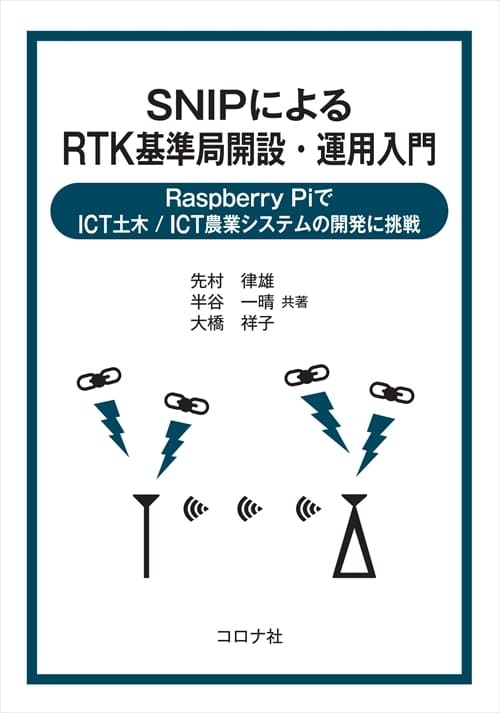
SNIPによるRTK基準局開設・運用入門
詳細を見る
- Raspberry PiでICT土木/ICT農業システムの開発に挑戦 -ドローンの進化と利活用が急速に進んでいる。本書ではドローンを操るソフトウェアであるオートパイロットに代表される自律制御技術に注目し,第一線の著者が蓄積してきた技術を中心にヘリコプタやマルチコプタの制御までをまとめた。
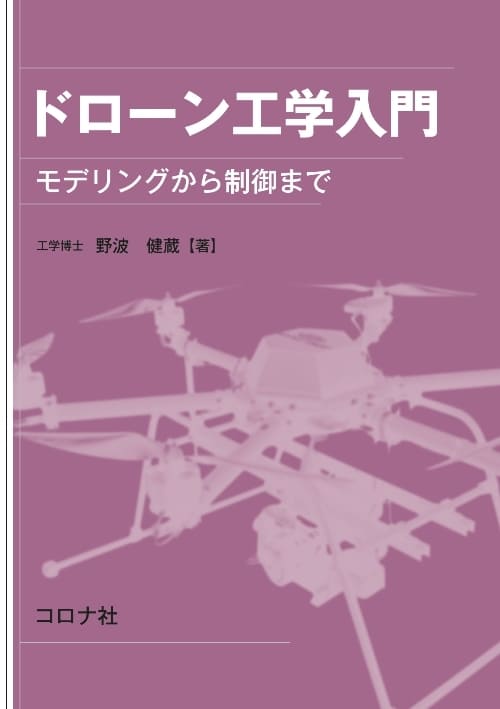
ドローン工学入門
詳細を見る
- モデリングから制御まで -ロボットや自動車が自動走行を行うために不可欠な「自己位置推定」について,その頑健性や信頼度などのさまざまな問題点に対して,枠組みを拡張,もしくは新しい手法を導入し,高性能化することで,それらの問題解決を目指した一冊。
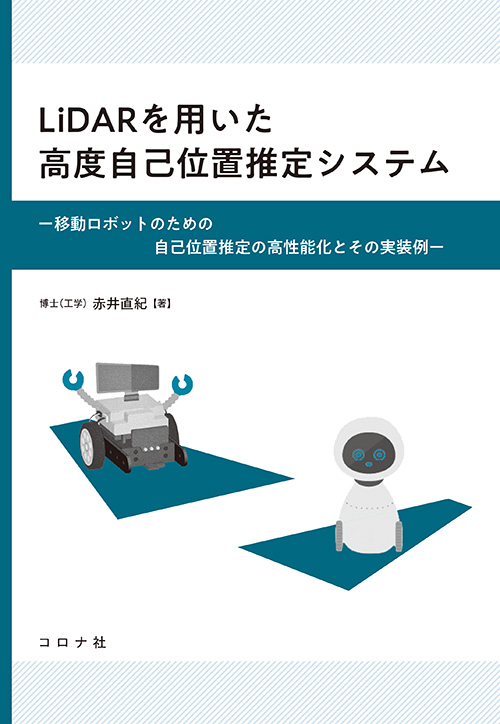
LiDARを用いた高度自己位置推定システム
詳細を見る
- 移動ロボットのための自己位置推定の高性能化とその実装例 -不整地移動ロボットを体系的に扱う書籍。各分野で定義がまちまちだった「不整地」の定義と分類を行い,不整地移動ロボットの代表的な移動形態である「車輪/クローラ型」,「脚型」,「ヘビ型」の機構や力学,制御を広範に解説する。
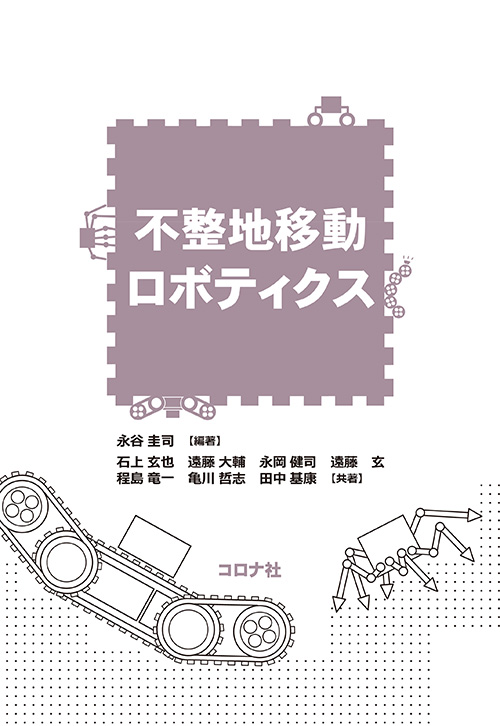
不整地移動ロボティクス
詳細を見る農業機械はもとよりセンシング技術や電子制御,自動化ならびにロボット化,ICTの活用さらには環境やエネルギー,ポストハーベスト技術に加えて食料生産・流通に係わる技術分野を体系的にまとめ直し,農業食料工学の知見に資する。
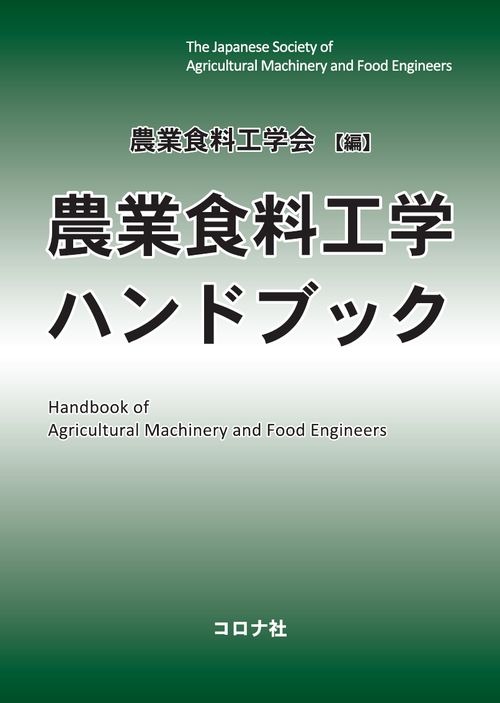
農業食料工学ハンドブック
詳細を見る複雑で多様な生物に情報を付加するためには生物の物性に基づいて精密に計測する技術が必要である。本書は迅速かつ非破壊で計測できる光と音を用いて,生物からいかにして目的の情報を計測するかという実験手法を中心に紹介する。
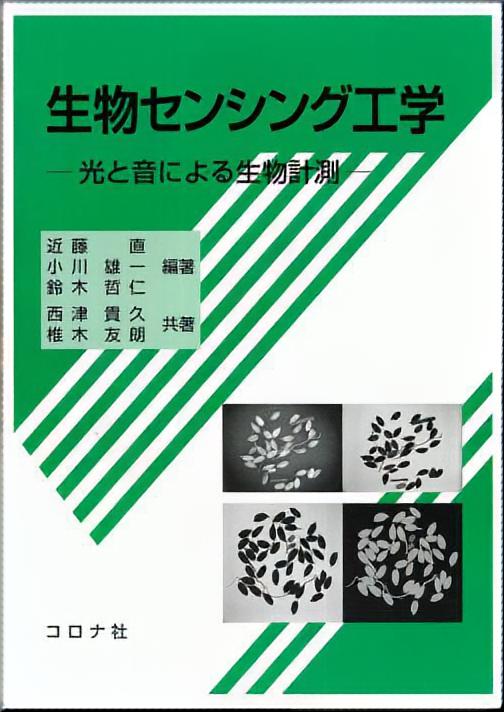
生物センシング工学
詳細を見る
- 光と音による生物計測 -
医療・福祉
本書は,基礎科学(神経科学・感覚の科学・音声科学など)をベースとした身体機能の補助代行技術から,バーチャルリアリティ・ロボティクスなどの先端技術を介護・リハビリテーションや高齢社会に生かす方法までを体系的に解説した。
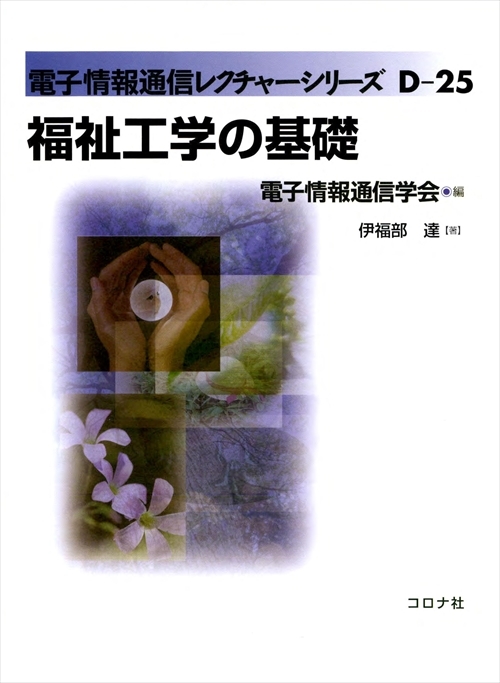
電子情報通信レクチャーシリーズD-25
詳細を見る
福祉工学の基礎本書では福祉機器について,なぜそれが使われているのか,どこが優れているのかを解説。工学だけでなく社会福祉や看護を学ぶ方にもわかりやすく記述。福祉機器の評価・選定のガイドブックあるいは機器開発の指針としても活用できる。
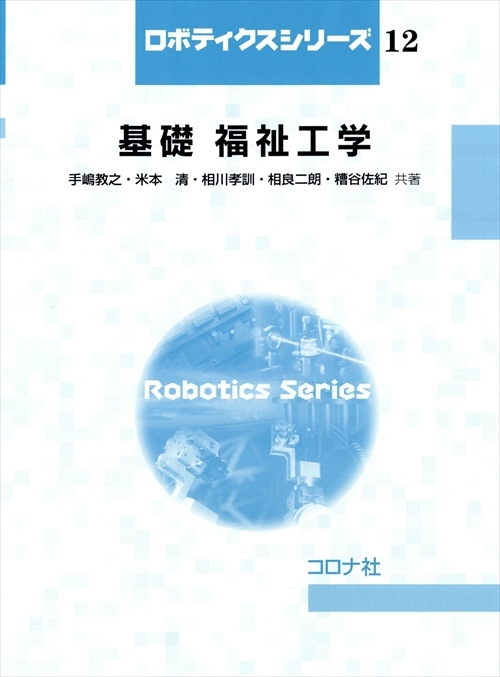
ロボティクスシリーズ12
詳細を見る
基礎 福祉工学バイオメカニクスとは力学,機械工学的に生物を理解する学問である。本書は人間の運動に的を絞り,ジョイントの構造,アクチュエータとしての筋,基本回路としての神経細胞,脳による運動制御方法などをロボティクスの立場から説明。
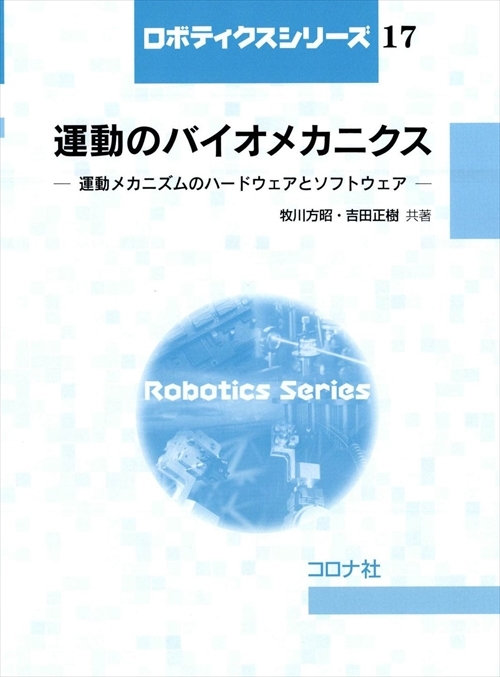
ロボティクスシリーズ17
詳細を見る
運動のバイオメカニクス
- 運動メカニズムのハードウェアとソフトウェア -はじめにロボットと身体で関連する運動の計測と解析について説明をし,その後,スポーツ科学・運動科学からのアプローチによる運動の巧みさおよびロボティクスからのアプローチによる運動の巧みについて事例を紹介した。
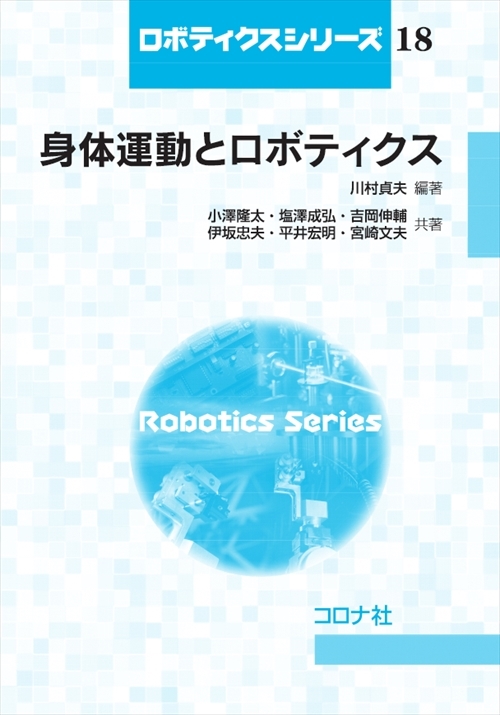
ロボティクスシリーズ18
詳細を見る
身体運動とロボティクス人間科学とは,人間を総合的にとらえ直そうという試みである。本書では,機器設計論に偏ることなく,人間科学という視点から福祉工学を俯瞰し,理工系だけでなく,医療・看護・福祉分野で必要とされる知識を解説した。
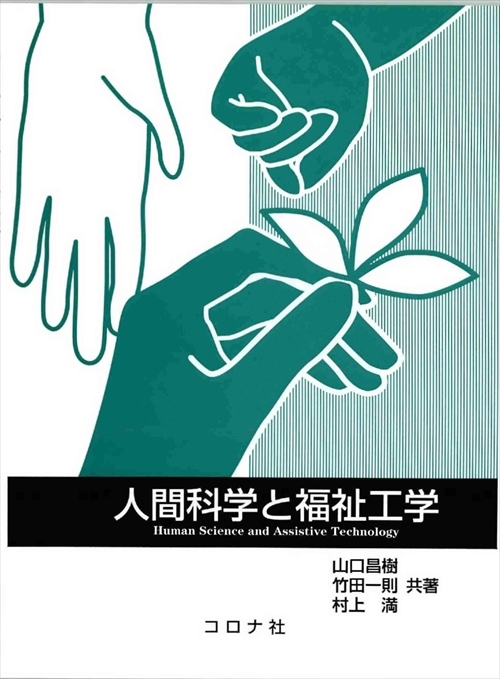
人間科学と福祉工学
詳細を見る生体や医療機器について機械工学の基礎とその応用までを学べる入門書。機械と比較しながら生体(人体)を工学的に解析し,生体と機械の共存・協調における問題点を考え,生体を解析するための機械工学の基礎を学べるよう解説した。
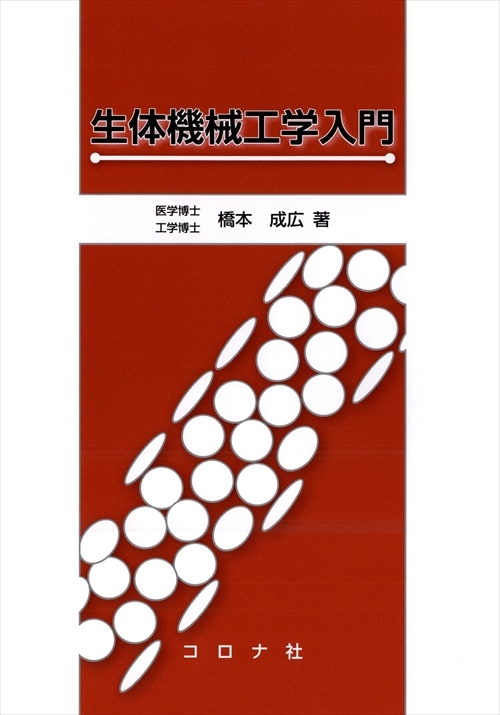
生体機械工学入門
詳細を見るこれからの高齢者と障害者を支えるのは,人材と福祉用具を基本とする生活支援技術である。本書は,高齢者と障害者の自立支援・介護支援に必要な基本的事項から関連する法律までを網羅した,生活支援技術の入門書・教科書である。
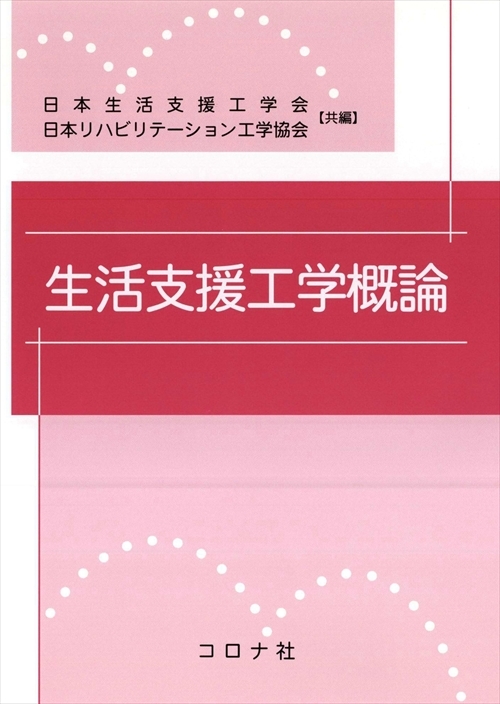
生活支援工学概論
詳細を見るヒト(人体)が持つ能力・機能について,基礎的な理解と正確な解釈を可能にするユニークな教科書。バイオメカニクス分野を学習する学生や医療,福祉などの分野において基礎研修を望む実務者・研究者の知識の整理に役立つ一冊。
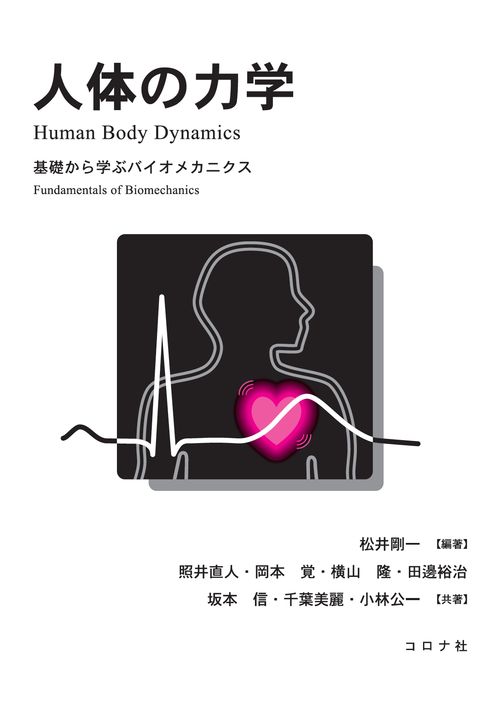
人体の力学
詳細を見る
- 基礎から学ぶバイオメカニクス -本書は,画像処理を初歩から学習しようとするさまざまな分野の人たちを対象として,画像処理技術を独自に利用できるよう,基本事項を平易に解説。アナログ処理がほぼディジタル処理に取ってかわるようになったことを受けて改訂した。
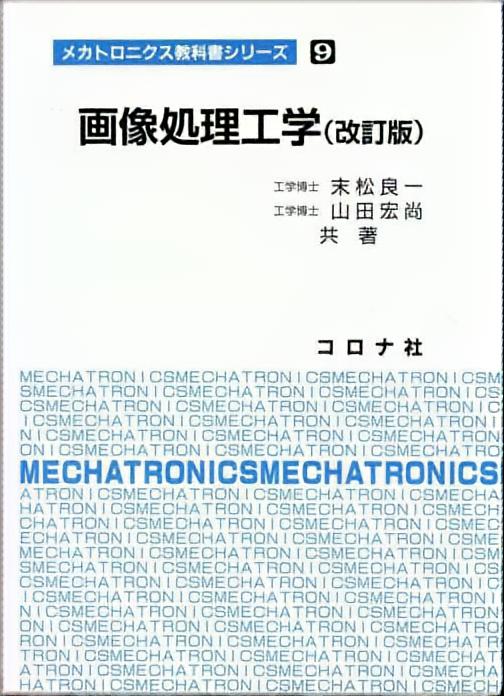
メカトロニクス教科書シリーズ9
詳細を見る
画像処理工学
(改訂版)画像処理で扱われる信号処理,画像処理手法,画像計測,グラフィックスに加えて,画像認識,機械学習,深層学習といった幅広い領域のトピックを入門的に扱いながら,バランスよく配分し,基礎事項を体系的に学べるように構成した。
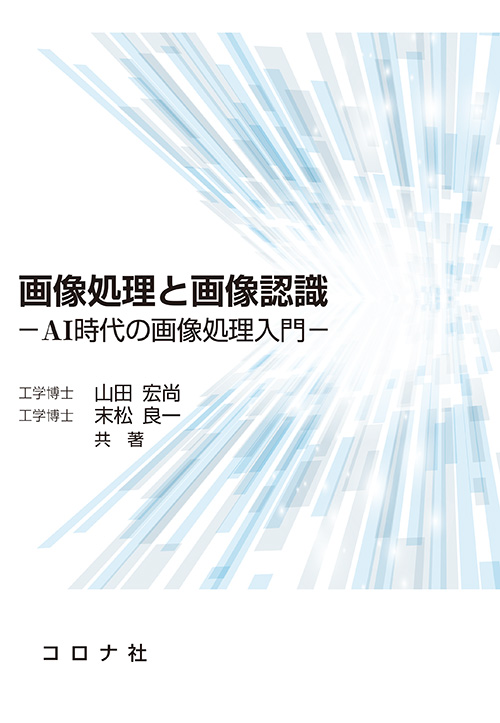
画像処理と画像認識
詳細を見る
- AI時代の画像処理入門 -行いたい画像処理に対して,どのような手法があるのかを見つけるのは意外に難しい。そこで,本書では処理を中心とした章立てを心掛けた。画像解析手法そのものが研究の対象でない分野では,本書に書かれた内容で研究に利用できる。
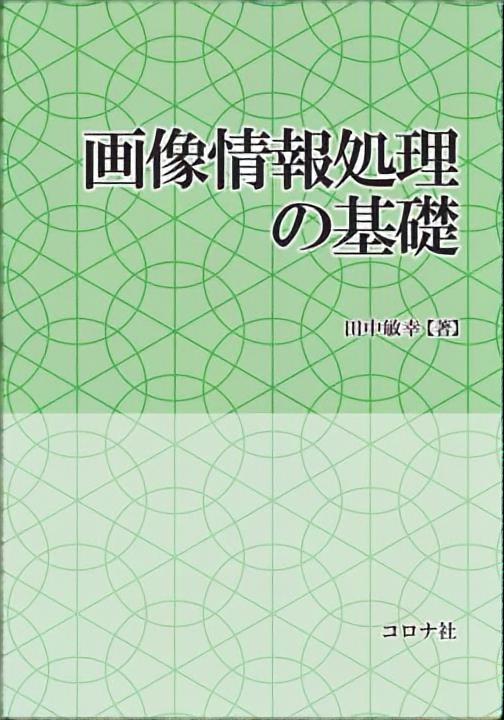
画像情報処理の基礎
詳細を見る
宇宙
ロケット・人工衛星の位置や速度は,電波を用いて測定される。逆にGPSのように衛星からの電波を用いて,自動車等の移動体に進路を示すことができる。本書は,これらの計測と航法システムについて基礎から応用例までを説明した。
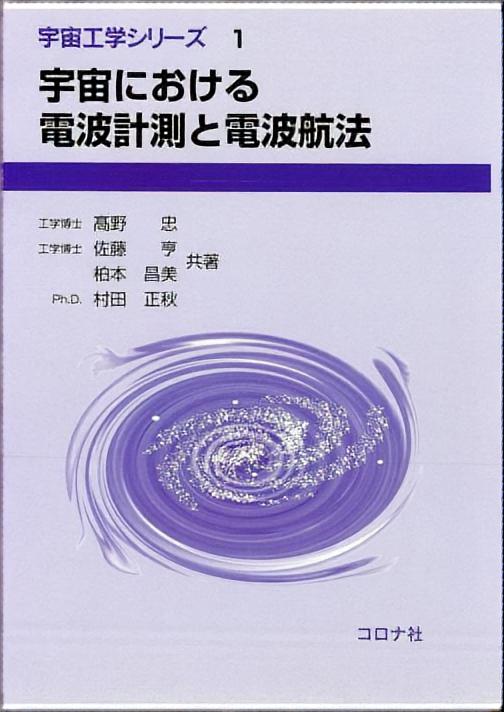
宇宙工学シリーズ1
詳細を見る
宇宙における電波計測と電波航法人工衛星と宇宙探査機の設計法について,具体的な多くの例題も紹介しながら,システム構成,構造設計,軌道設計,制御技術について解説。増補では新たに章を追加し,衛星のサブシステムや搭載機器の耐環境性のための検証試験も追加。
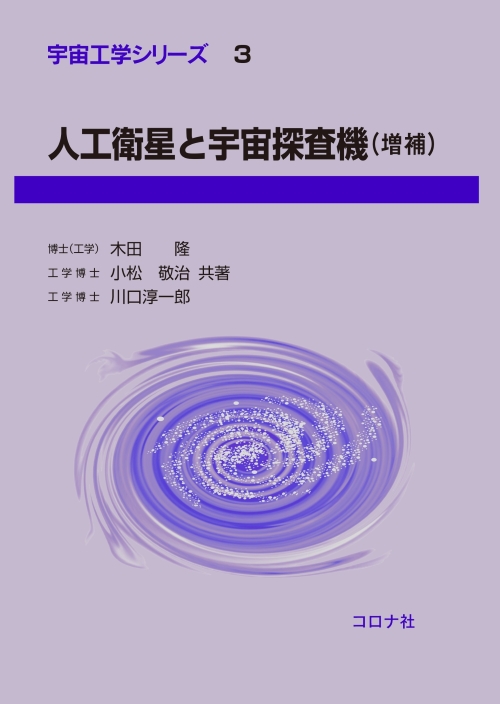
宇宙工学シリーズ3
詳細を見る
人工衛星と宇宙探査機
(増補)重要な利用課題となってきた宇宙環境について,おもに微小重力環境下での独特の現象,利用のための基礎技術および成果を,初心者から深く関わる研究者にも役立つよう記述した。生物と宇宙との関係についてもかなりの部分を割いている。
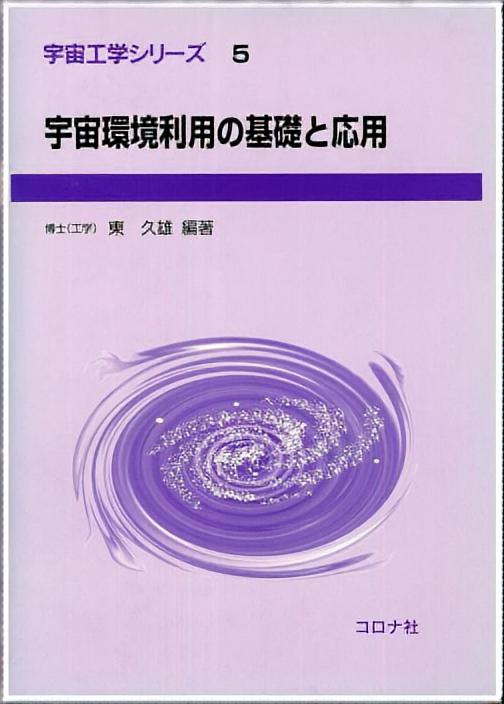
宇宙工学シリーズ5
詳細を見る
宇宙環境利用の基礎と応用科学観測や宇宙技術開発および気象観測に用いる成層圏気球と火星や金星などの大気に浮遊させる惑星気球を対象として扱い,気球の形状設計と方式,飛翔時の運動特性,放球・回収方法など気球工学全般を体系的に述べた本邦初の書。
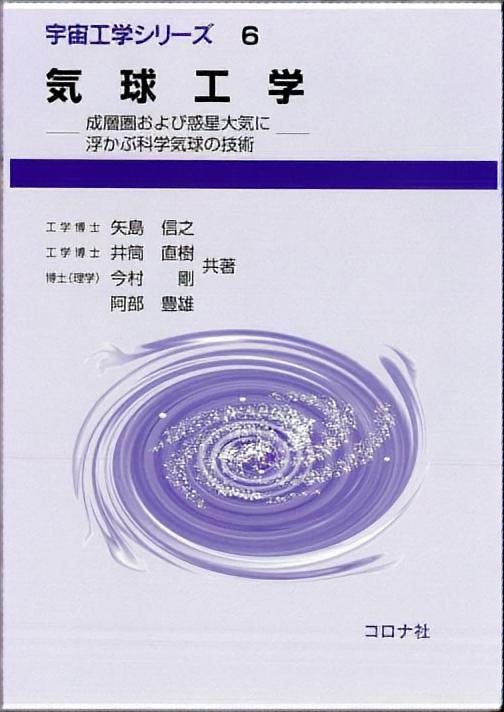
宇宙工学シリーズ6
詳細を見る
気球工学
- 成層圏および惑星大気に浮かぶ科学気球の技術 -国際宇宙ステーション(ISS)構想の歴史,開発の経緯,さまざまな支援技術,特にISSを構築するに至った動機,国際協力の動き,運用上の課題などの概要に,日本参加の経緯や実験モジュール「きぼう」についての解説を加えた。
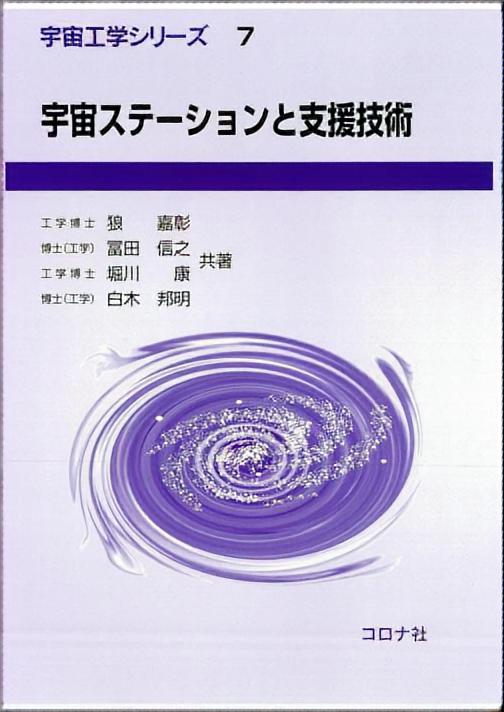
宇宙工学シリーズ7
詳細を見る
宇宙ステーションと支援技術地球環境のリモートセンシングは,生活に密接に関わる宇宙利用技術であり,多くの人工衛星が運用されている。本書は,光学および電波センサによるリモートセンシングの基礎から応用まで,新しい技術や成果も含めて解説している。
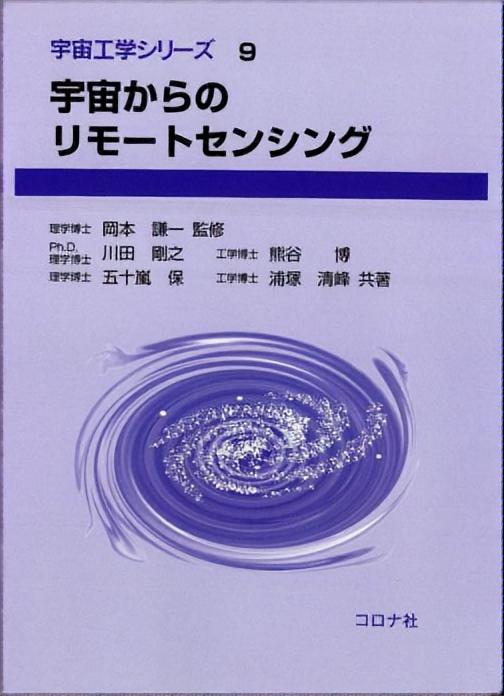
宇宙工学シリーズ9
詳細を見る
宇宙からのリモートセンシング自動車,航空機,ヘリコプタ,ロケットおよび宇宙機の航法と運動,誘導,制御技術を述べ,これらの特徴とミッションを示し,運行(移動)を安全・正確に実行するための画像処理,移動体の位置認識および経路計画技術・手法を論じる。
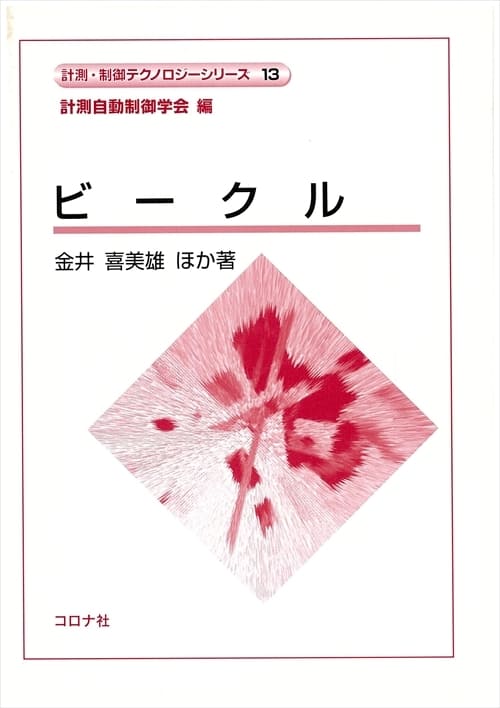
計測・制御テクノロジーシリーズ13
詳細を見る
ビークル本書では,機械システムの物理モデリングから数値シミュレーションの技法,制御系の安定解析法について述べ,さらに宇宙機と移動ロボットを具体例として取り上げてモデリングから制御系の設計までがどのようになされているかを示す。
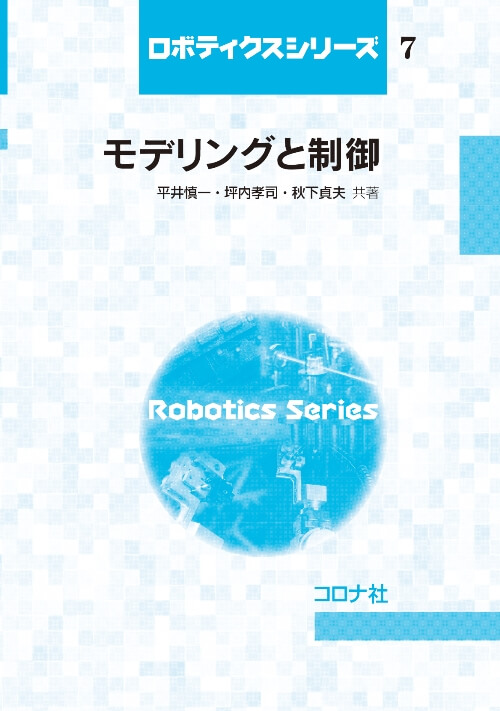
ロボティクスシリーズ7
詳細を見る
モデリングと制御本書は,人工衛星が描く軌道について,それに関する法則と現象発生までのプロセスを習得することを目的とし,初学者が理解できるよう,難解な数学解析を用いた言及は避け,多くの図面を用いたわかりやすい記述となっている。
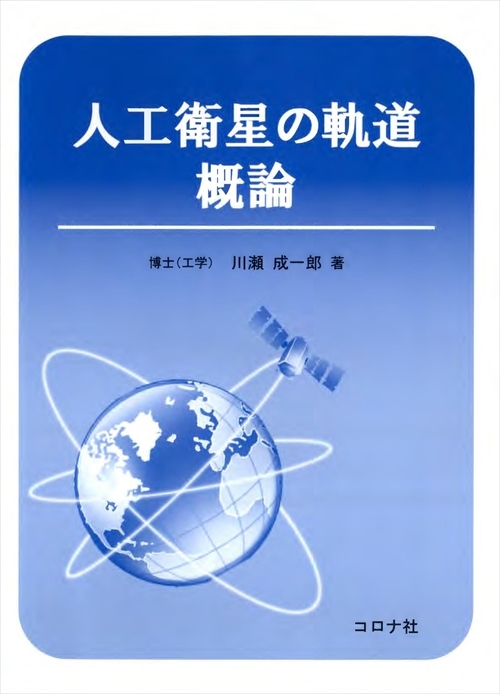
人工衛星の軌道 概論
詳細を見る









