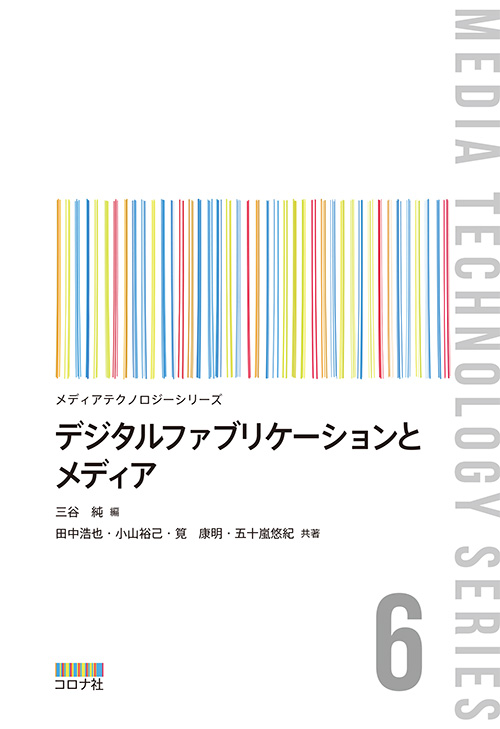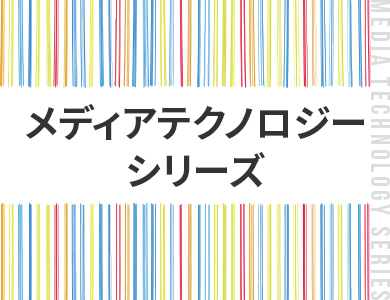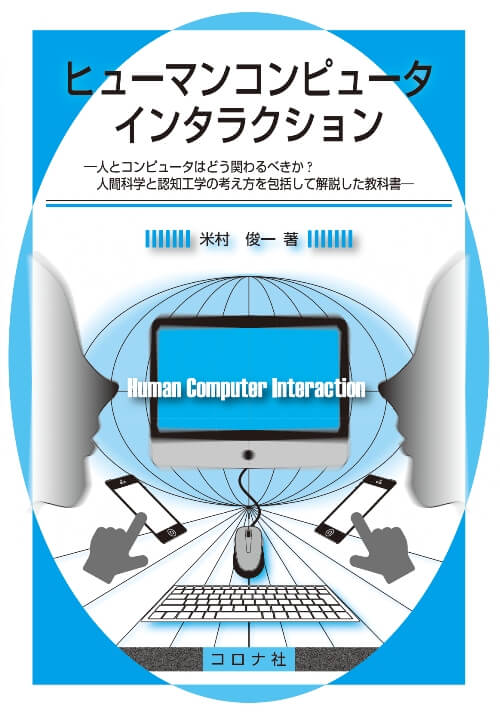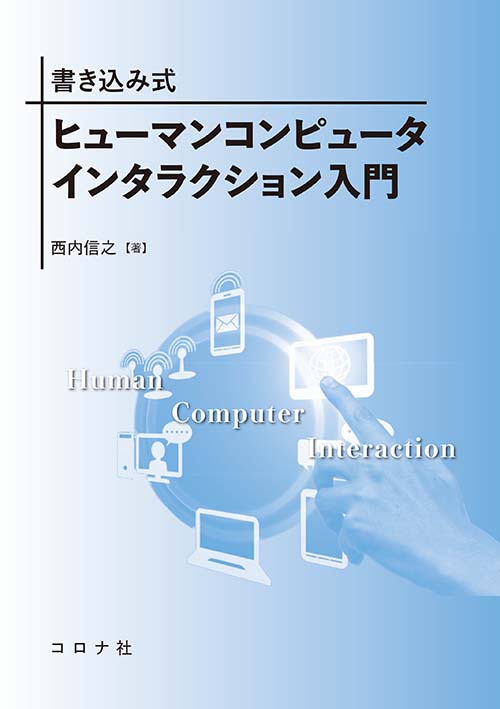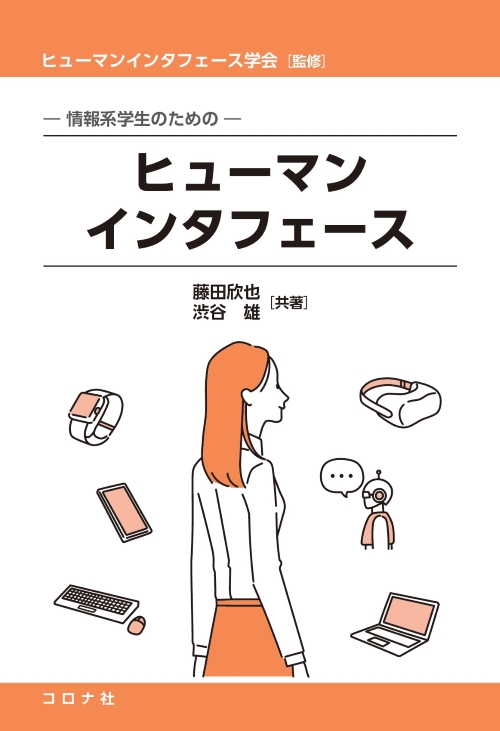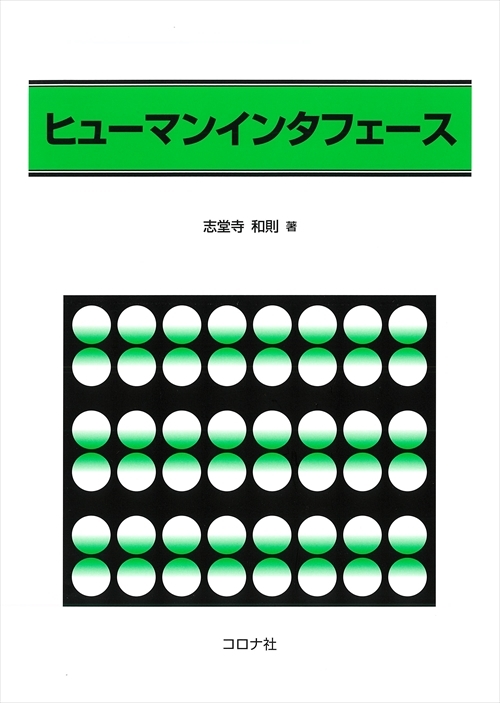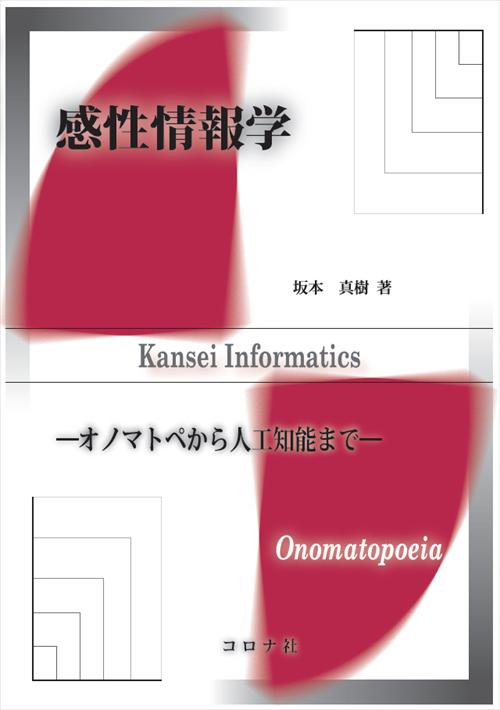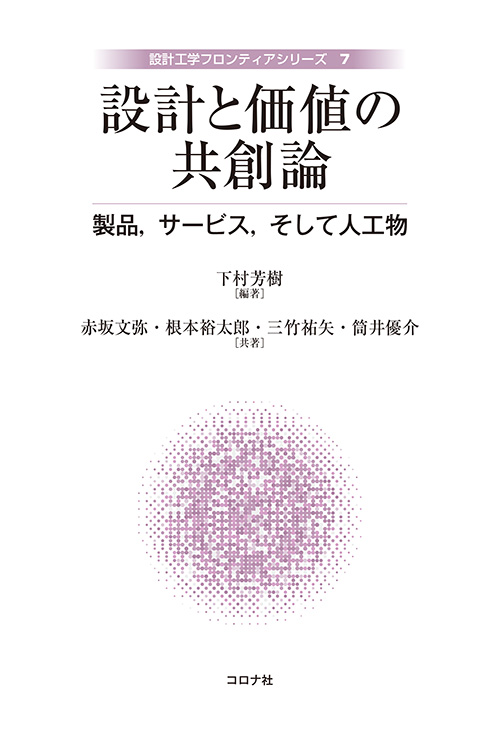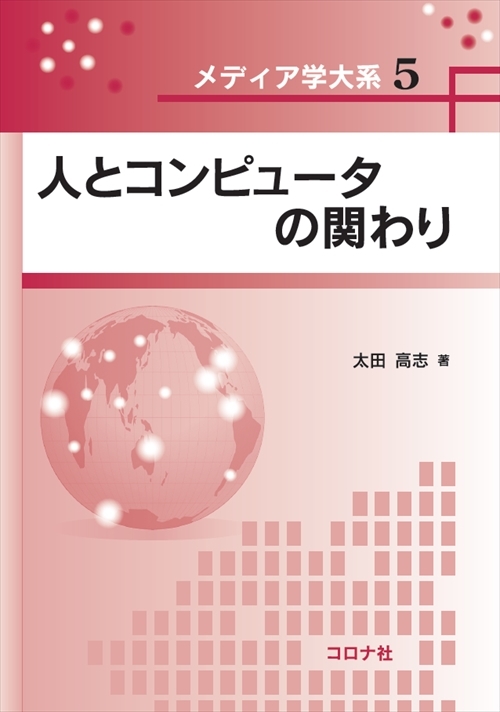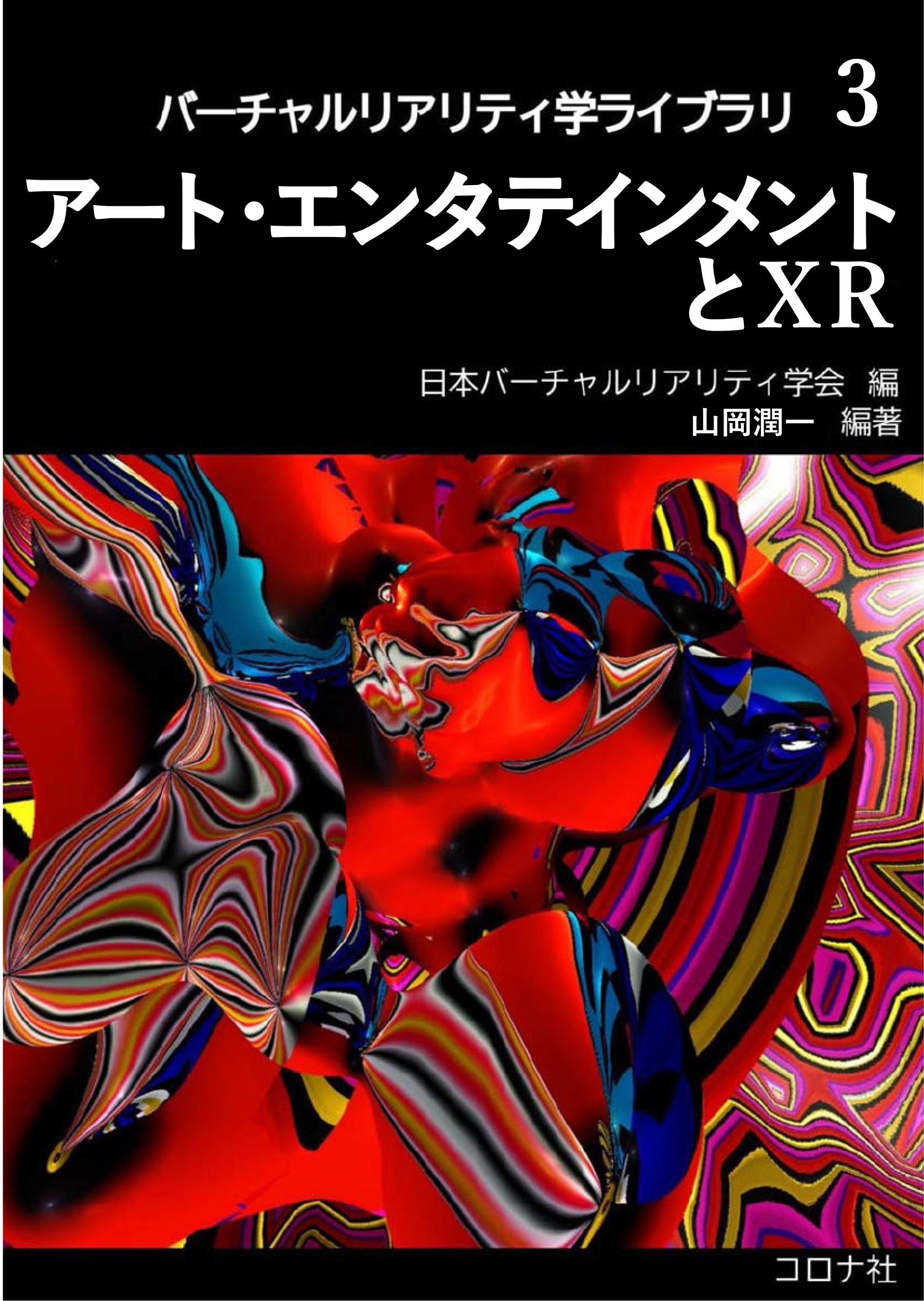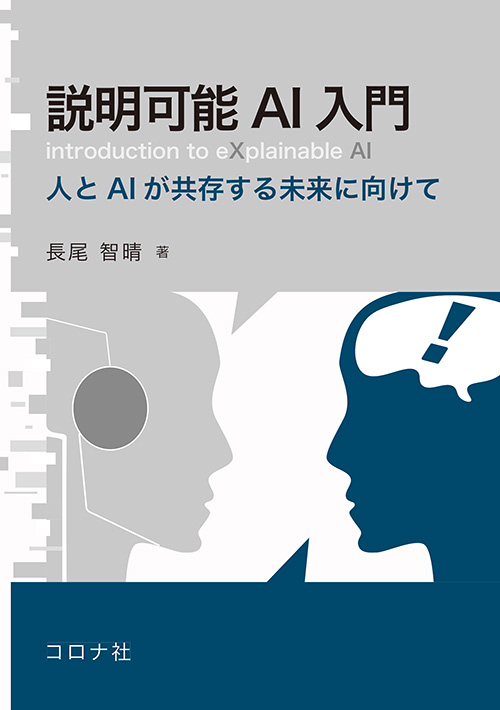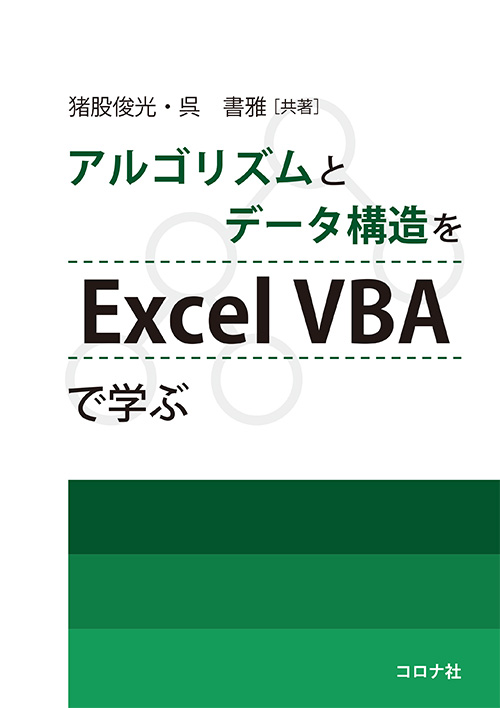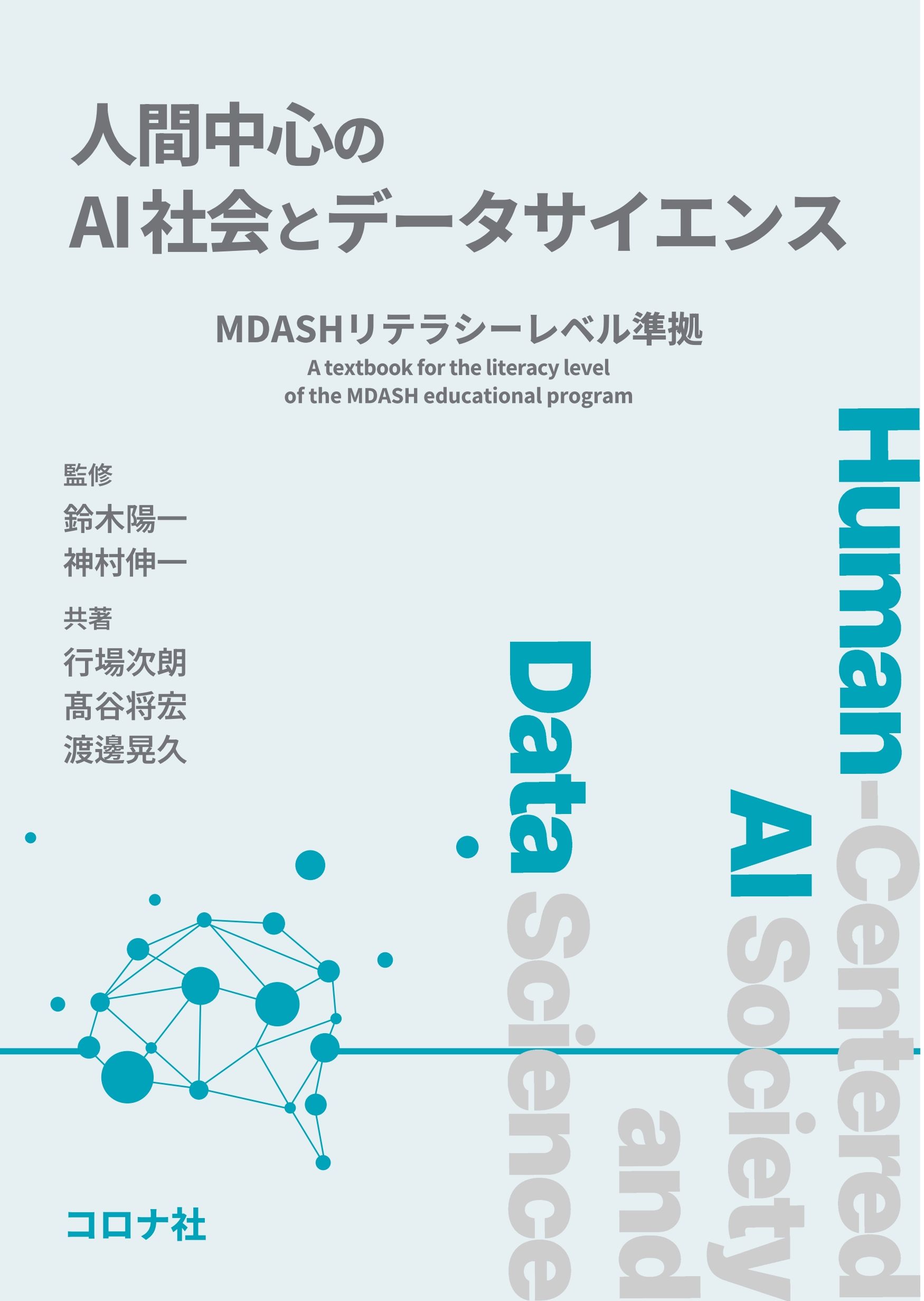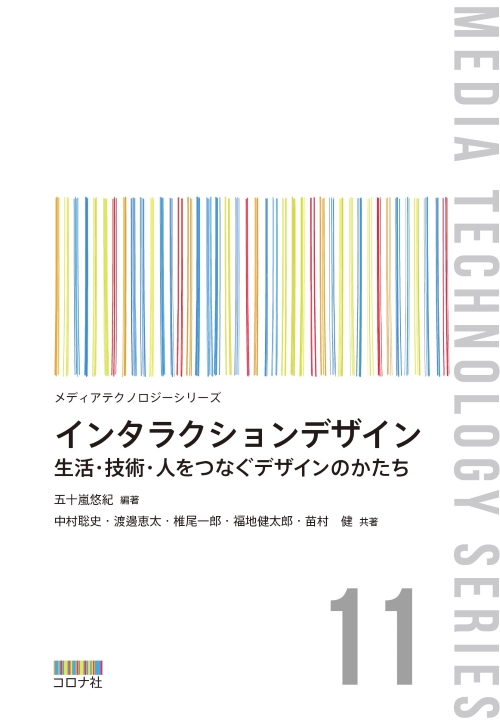
インタラクションデザイン - 生活・技術・人をつなぐデザインのかたち -
「使いやすさ」の当たり前を問い直し,発想を広げるヒントが満載の実践ガイド
- 発行年月日
- 2025/10/17
- 判型
- A5
- ページ数
- 216ページ
- ISBN
- 978-4-339-01381-8
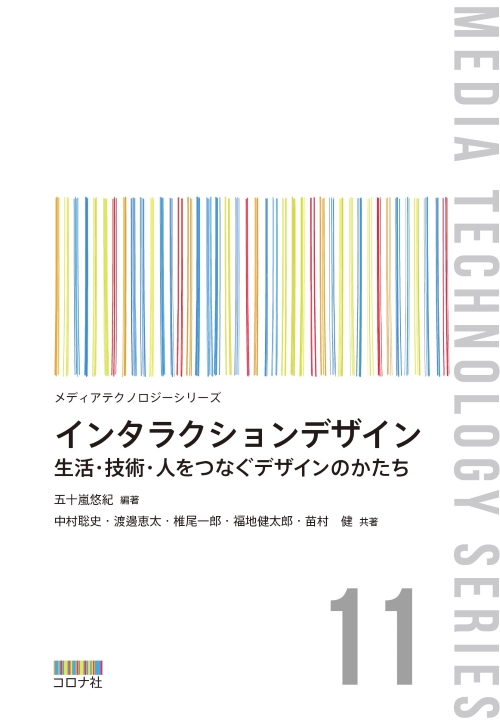
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
【読者対象】
・大学学部後半(3・4年生)でインタラクションデザインを学ぶ学生
・他分野からインタラクションデザインに興味を持った大学院生・社会人
・この分野に関心をもつ意欲ある高校生
・HCIや情報デザイン分野の教育者・研究者
【書籍の特徴】
本書は、インタラクションデザインの基礎を学んだ学生が実践や研究に踏み出すための“次の一冊”です。教科書では触れにくい、試行錯誤のプロセスや生活に根ざした実例を通して、「良いデザインとは何か」を多角的に考える機会を提供します。5名の執筆者がそれぞれ異なる視点から執筆しており、章ごとに分野の広がりと奥深さを実感できることでしょう。巻末の著者全員による対談では、インタラクションデザインの未来を見つめ、読者自身の関心や可能性を探る手がかりを提示します。
【各章について】
第1章では、インタラクションデザインの概要と関連キーワード、学会情報などを紹介し、本書全体の導入としての役割を果たします。第2章では、身近な“悪い”インタフェースの例から失敗に学び、「良いデザインとは何か」を考えます。第3章では、アイデアを試作するマインドセットとプロトタイピングの方法に焦点を当て、実践的なアプローチを紹介します。第4章は、生活の中にある課題を起点に、技術をどうデザインに取り入れるかを事例とともに解説。日常生活に根ざした視点からインタラクションを考えます。第5章では、不特定多数を対象にしたデザインの視点を提示し、空間的・社会的スケールの拡張について論じます。第6章では、「できる」だけでなく「したい」へと人の行動を促すデザインのあり方を、感情や行動変容の観点から探ります。最終の第7章では、執筆者全員による対談を通じて、インタラクションデザインの未来とその可能性を多角的に語り合い、読者が自身の視点でこの分野を考えるきっかけを提供します。
【著者からのメッセージ】
インタラクションデザインとは何か。それを一言で語ることは難しく、だからこそ私たちはこの本を書きました。本書では、生活・技術・人をつなぐデザインの「かたち」を、さまざまな事例とともに紹介しています。「なんとなく面白そう」「ちょっと気になる」そんな気持ちからでも構いません。失敗から学ぶこと、試しにつくってみること、生活のなかで見つける工夫…。そのすべてが、インタラクションデザインの大切な一部です。正解を求めるのではなく、たくさんの視点に触れながら、広く・深く考えるきっかけとしてこの本を手に取っていただけたら幸いです。
【キーワード】
インタラクションデザイン、HCI、ユーザインタフェース、プロトタイピング、ユーザビリティ、生活支援技術、社会実装、行動変容、創造的思考、人間中心設計
本書を手に取ってくださった方には「インタラクションデザインを学びたい」という人もいれば,「インタラクションデザインって何なのかイマイチよくわからない」という人もいるのではないでしょうか。インタラクションデザインの分野全体を俯瞰した書籍としては,『新しいヒューマンコンピュータインタラクションの教科書(玉城絵美著,講談社)』『ヒューマンコンピュータインタラクション入門(椎尾一郎著,サイエンス社)』『ヒューマンコンピュータインタラクション(米村俊一著,コロナ社)』などを読んでいただくことで,インタラクションデザインの本流を学ぶことができます。しかし,こういった教科書的な書籍では,枝葉の部分はそぎ落とされてしまうことが多くあります。
本書は,大学の学部で基礎科目を学んだあとを想定して,「インタラクションデザイン」にまつわる分野の具体的な研究事例を広く取り上げながら解説することで,インタラクションデザインをより理解していただくことを目指した書籍です。良いインタラクションデザインとはどのようなものか,それをためしにつくってみるにはどういった方法があるのか,どういったことがいま研究されているのかについて,具体的な事例を通してより理解していただけるのではないかと期待しています。
読者層としては,おもに学部3,4年生を想定していますが,この分野の大学といったアカデミアの場でどのような研究がされているのかを覗いてみたいという意欲のある高校生や,他分野で学んだけれどインタラクションデザインにも興味があるという大学院生や社会人にも興味を持っていただけるかもしれません。
本書の構成は,1章「インタラクションデザインって?」ではインタラクションデザイン分野について広く紹介したあと,本書を理解する上で必要なキーワードなどを紹介しつつ,学べることや関連学会の情報について簡潔にまとめてお伝えします。続く,2~6章ではこの分野を牽引する5名の研究者が具体的に解説します。2章「インタラクションデザインの失敗から学ぶ」では悪いインタフェースを理解することで良いインタフェースとは何かを考えてみることができます。3章「インタラクションデザインにおけるマインドセットとプロトタイピング」では思いついたもの・デザインをためしにつくってみるための方法を知ることができます。4章「生活志向のインタラクションデザイン」では私たちの生活に密着する場面を具体的に挙げながらどのように技術を導入できるのかの事例を知ることができます。5章「不特定多数を対象とするインタラクションデザイン」ではこれまでを踏まえて,人数や距離に着目したインタラクションに具体例を広げていきます。6章「「できる」から「したい」に導くインタラクションデザイン」ではデザインでどう人の行動を考えていけるかといった視点から具体例で学んでいくことができます。最後の7章では執筆者全員でここまでを踏まえた対談を行い,この分野の未来について考えてみました。答えに向かって最適化する分野ではないからこそ,広い視野でたくさんの試行錯誤をしていただくヒントになればと思います。本書が読者の皆さんにとって,いまを知り,未来を考えるきっかけになることを期待しています。
2025年8月
編著者 五十嵐悠紀
1.インタラクションデザインって?
1.1 インタラクションデザインとは
1.2 良いデザインにするためのユーザビリティ評価
1.3 アフォーダンス
1.4 プロトタイピングにはさまざまな方法がある
1.5 ユーザー中心設計
1.6 本書で学べること
1.7 最新情報はどこから得るといいの?
コラム:対象ユーザーを観察することでの気づき
2.インタラクションデザインの失敗から学ぶ
2.1 失敗は最高の先生
2.2 BADUIの事例とそこからの学び
2.3 BADUIとそのDIY
2.4 DXとBADUI
2.5 失敗からどのように学ぶか
2.6 生成AIは人と同じ間違いをする?
2.7 おわりに
3.インタラクションデザインにおけるマインドセットとプロトタイピング
3.1 「いいこと思いついた!みてみて~!」
3.2 エンジニアリングと科学とデザイン
3.3 インタラクションデザインの研究パターン
3.4 プロトタイピングというコミュニケーション
3.5 プロトタイピングの方法と考え方
3.6 代表的なプロトタイピング手法
3.6.1 試作実装
3.6.2 ビデオプロトタイピング
3.6.3 ペーパープロトタイピング
3.6.4 アクティングアウト
3.7 プロトタイピングを育む研究室環境づくり
3.8 アイデアを生み出す方法
3.9 研究室での活動事例とそのプロトタイピングフェーズ
3.10 おわりに
4.生活志向のインタラクションデザイン
4.1 ユビキタスコンピューティング
4.2 スマートホーム
4.3 生活空間を拡張する
4.4 生活に織り込むインタフェース
4.5 ユビキタスなデバイスの利用
4.6 遊びの未来
4.7 生活習慣の改善を応援
4.8 遠隔コミュニケーション
4.9 物探しの支援
4.10 導入と保守のインタフェース
4.11 おわりに
5.不特定多数を対象とするインタラクションデザイン
5.1 見過ごされるインタラクション
5.2 インタラクション可能性およびエンゲージメント
5.2.1 コアメカニクス
5.2.2 (主観的)インタラクション可能性
5.2.3 客観的インタラクション可能性
5.2.4 エンゲージメント
5.2.5 エンゲージメントの継続
5.3 距離に応じたインタラクションデザイン
5.3.1 近接学
5.3.2 近接学の応用
5.3.3 近接学に基づいた事例分析
5.4 時間軸から考えるインタラクションデザイン
5.4.1 期間の分類
5.4.2 時間軸に基づいた事例分析
5.5 展示設計のガイドライン
5.5.1 コアメカニクスの確立と洗練
5.5.2 空間的側面の考慮
5.5.3 時間的側面の考慮
5.6 おわりに
6.「できる」から「したい」に導くインタラクションデザイン
6.1 「できる」から「したい」を考える
6.2 書きたくなる:筆記音のフィードバック
6.3 伝えたくなる:ラジオ放送とグループワークでの実践
6.4 アンケートに答えたくなる:ミュージアムでの実践
6.5 おわりに
7.未来を考える
7.1 生活志向インタラクションの研究のはじまり
7.2 単機能を実現したスマートフォン
7.3 問題を探せるか,解決策を考えられるか
7.4 問題を与えられることを待っていてはいけない
7.5 アイデアを要素分解できるか
コラム:DIY精神が大事
7.6 アイデアが出せなければ,偉大なアイデアを真似てつくってみよう
7.7 スケールの大きいゴールの前に短期目標を据える
7.8 なぜ人が選挙に行くのかをインタラクションデザインで考える
7.9 発想を豊かにするためには現場に行け
7.10 自信を持って身近なことから考えてみよう
引用・参考文献
索引
読者モニターレビュー【 みた 様 (業界・専門分野:Web開発)】
総評として、学生から社会人まで幅広い世代が楽しみながら学べる本だと思いました。専門的なテーマを扱いつつも親しみある事例を多く取り上げ、段階的に理解が深まる構成になっていると思います。
1,2章はインタラクションデザインについてどういうものかを言葉や定義についての解説が主でした。良いUIや誤解の与えるBAD UIはどんなものかを解説する内容であり、とっかかりとしてよかったと思います。ただし、社会人や業務経験者には基礎的かもしれません。
3,4章は多くのインタラクションデザイン事例の紹介や、それに取り掛かるユーザーたちのマインドなどの紹介が主でした。
この章は自分にとって未知の事例が多く、「自分でも少し扱ってみようかな」と思える内容で読んでいてとても面白かったです。
5,6章はさらに学術的な深掘りがあり、どのようにユーザーに体験させていくかといったことが詳細に解説されている印象を受けました。
最後の7章は各章の著者らによる座談会。技術本には珍しく、未来志向で内容がまとまっており、読後に「何をどのように作るか」のマインドを自然と読者に意識づけさせてくれる構成になっています。読み終えた後に前向きな余韻が残り、好印象でした。
総じてこの本は、インタラクションデザインの基礎を学べると同時に、創造的なインスピレーションの両面を与えてくれる良書だと思います。
読者モニターレビュー【 bon 様 (業界・専門分野:Engineering in Medicine)】
本書は、教科書で見落とされがちな試行錯誤の手つきを前景化し、生活の現場からインタラクションデザインを捉え直す実践的ガイドである。第1章は当該分野の地図を端的に示し、専門外の読者にもその意義と射程を伝えつつ、以降の学びの足場を築く。
また、生成AIを用いて案内板やユーザーインターフェースの課題を抽出する取り組みも紹介される。AIは強力な補助となる一方、指摘の妥当性が揺らぐ局面も少なくないことを踏まえ、人が学び、経験に基づいて良し悪しを判断する重要性を説く。
さらに、問題発見の姿勢や要素分解、偉大なアイデアの模倣からの学び、現場重視の観点など、多視点から未来を考える契機が随所に散りばめられている。とりわけ次世代を担う読者にとって、自ら手を動かし思考を深めるための具体的なヒントが得られるだろう。
総じて、本書の強みは、生活・技術・人を結ぶ豊富な実例と、失敗、試作、評価を往還する実践の枠組みにある。分厚い理論体系を足すより、プロトタイピングを通じて目を養う姿勢を促す書籍であり、学習から実務への橋渡し役として心強い一冊である。
読者モニターレビュー【 松岡 大輔 様 (業界・専門分野:プログラマ)】
本書は、なぜ我々には本質的な新しさを作り出すことができないか、という根本的な問題意識に立脚しながら、いかにして新しさを見つけ、形にしていくかについて、丁寧に言語化した書籍である。インタラクションデザインというテーマはやや限定的な印象も受けるが、インタラクション、あるいはインタフェースというテーマ設定の背景には、デザイン思考がある。デザイン思考をより現実の方に引き寄せ、現実的な現象と人の界面を具体的に考えるということである。
本質的な新しさは、定義上、既存の知識の体系ではとらえられない。とりわけ既存の知識の体系の専門家であるほど、現実的な現象との界面で新しさの芽を見つけることが難しくなる。そのとき、学問的なアプローチになにができるか、という知的な誠実さが本書の根底にあり、そこに積極的な可能性を見ているのである。
したがって、本書は理論書ではないし、体系的な知識を提供するものでもない。本書は方法の書であり、本書から学ぶというよりは、本書で得た方法を現実に適用し、日々自ら新しさを発見していくという「営み」の必要性を説くものである。我々が知りうるのはせいぜい方法であり、あとは、具体的に現実的な人生を生きていく中で絶えず発見し続けるしかないのである。
そのようなアプローチを取る際に、本書が基本的な姿勢としているのが、失敗から学ぶということである。失敗とは、既存のデザインが機能不全を起こしている現象であり、まさにその理由を考え、解消することから、新しさが生まれる。
失敗は、基本的に、経験的にしか知られない。人が実際に対象を使ってみて初めてわかるのである。たとえば生成AIを使ってインタフェースの不備を洗い出す手法も検討されているが、執筆者の結論は現時点では否定的である。つまり、人が現象と接する界面において初めて、失敗は認識されるのであり、そこからしか新しさは生まれないだろうと考える。そして、失敗の経験を抽象化して分類することから、方法が生まれる。
問題は、むしろ、認識の面にある。自発的に新しいことを試みて失敗を肯定的に経験する心理を、教育課程で抑圧されることが多い。そのマインドセットから自己を解放する方法についても検討されている。そして、精神論ではなく具体的にプロトタイプを作り続けて考える、という実践的な姿勢も特徴だろう。
本書は、コンピュータ技術以降の情報科学の進展を踏まえて、現代的なメディア環境において具体的な事例を検討している。コンピュータの汎用性を、人とのインタラクションを通じて専用性へと最適化するという視点において、テクノロジーとメディアとデザインが交差しているところが、類書と比較した場合の特徴だろう。
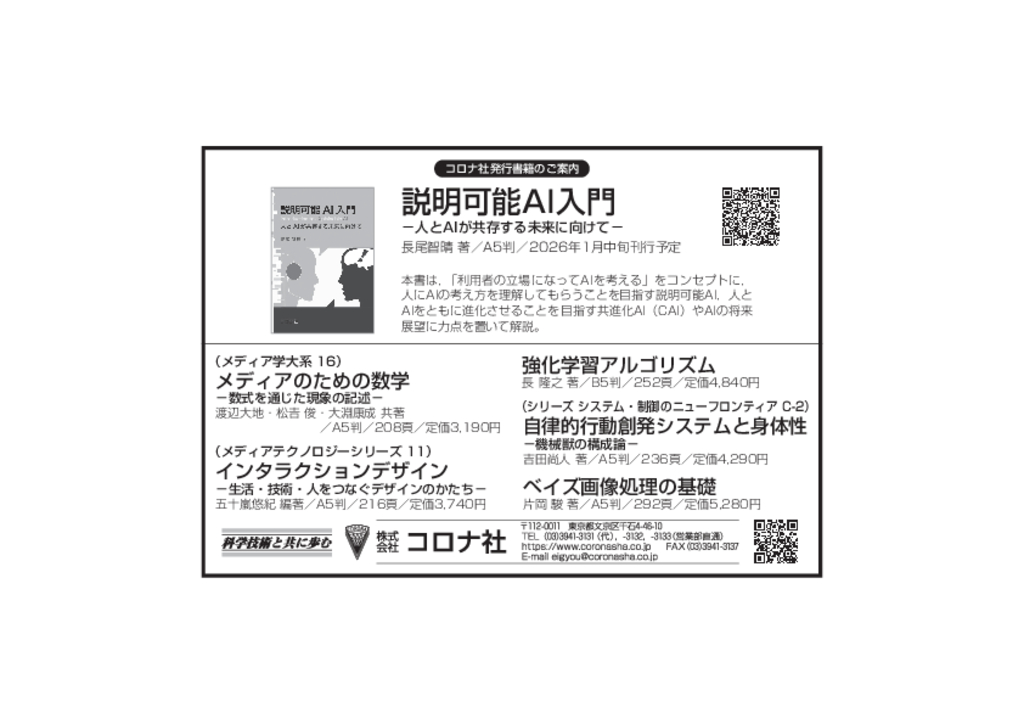
-
掲載日:2026/01/01
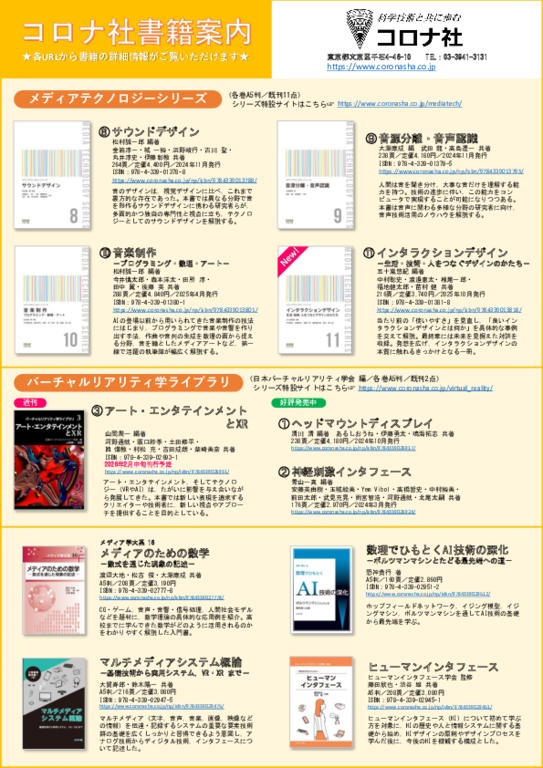
-
掲載日:2025/12/31
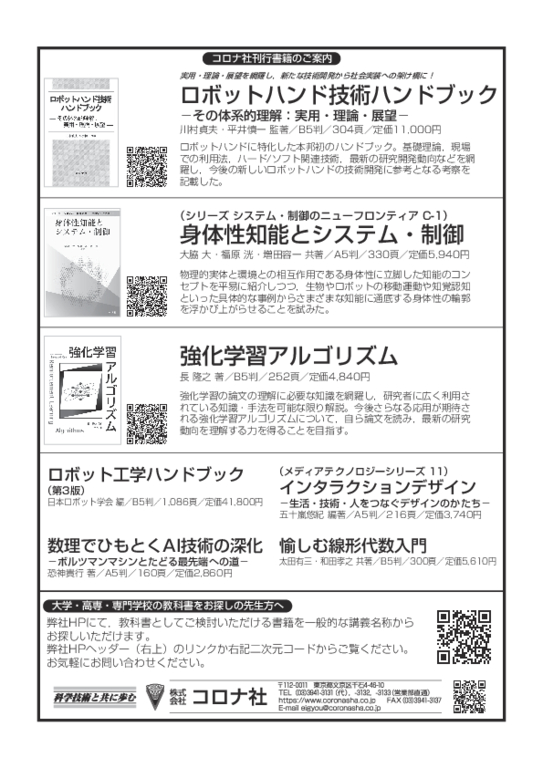
-
掲載日:2025/12/15
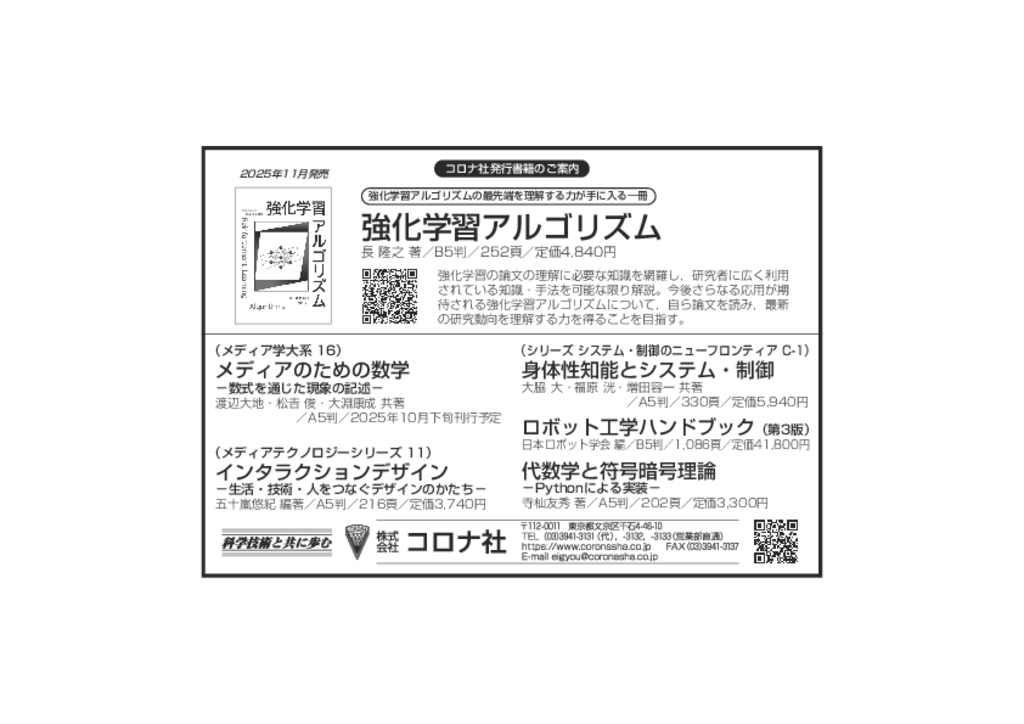
-
掲載日:2025/11/01
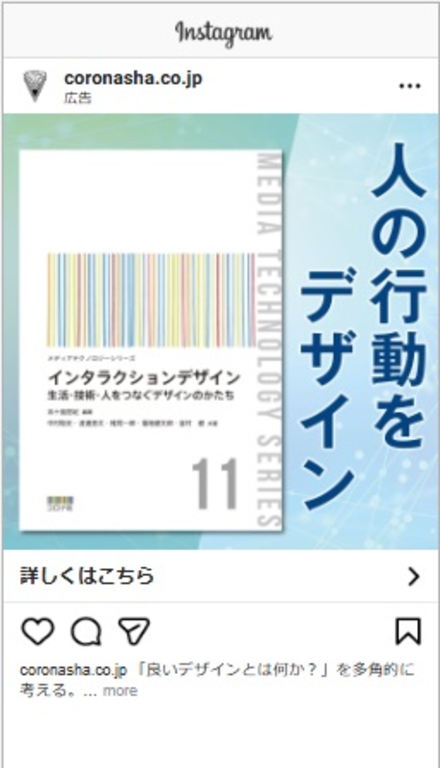
-
掲載日:2025/10/02
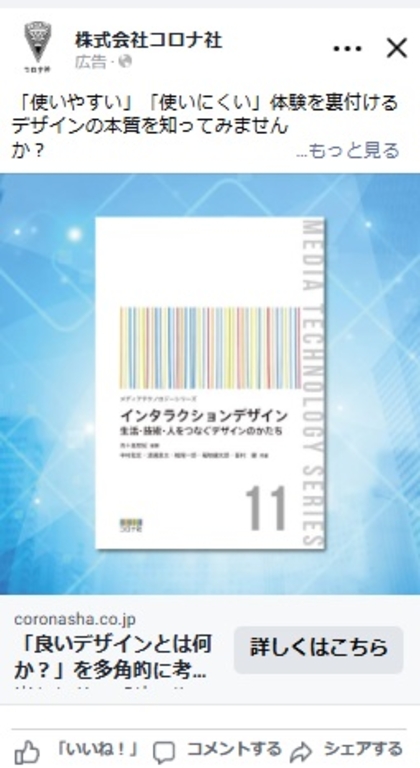
-
掲載日:2025/10/02
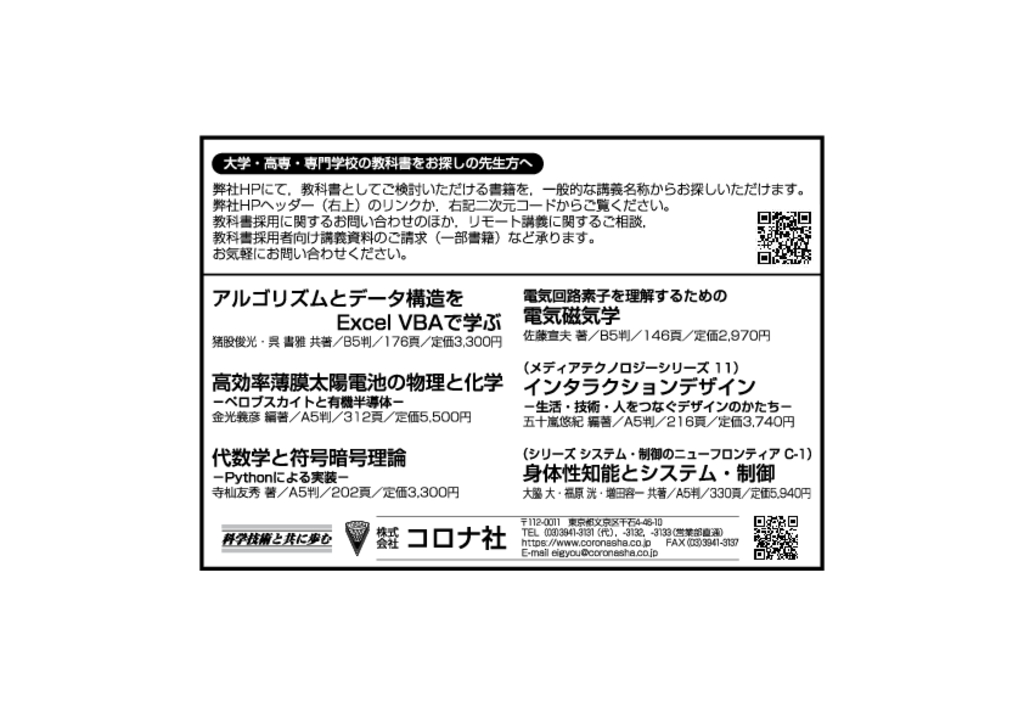
-
掲載日:2025/10/01
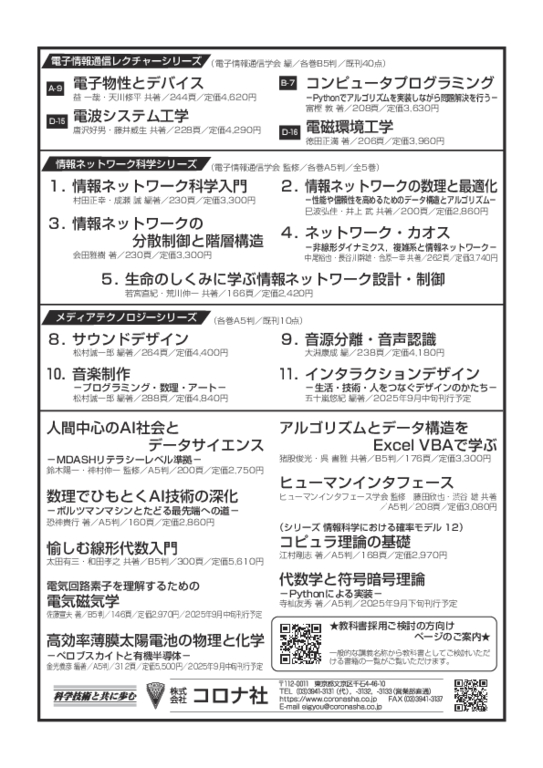
-
掲載日:2025/09/08

-
掲載日:2025/09/01
★特設サイトはこちらから★
各書籍の詳細情報や今後の刊行予定,関連書籍などがご覧いただけます。