レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
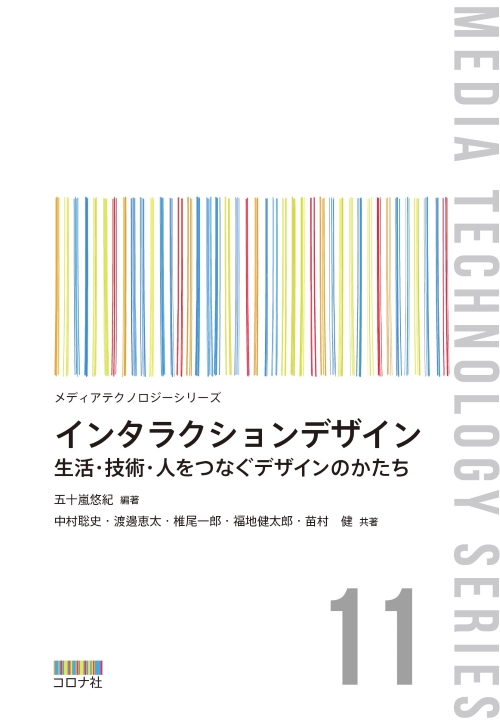
-
インタラクションデザイン - 生活・技術・人をつなぐデザインのかたち -
当たり前の「使いやすさ」を見直し,「良いインタラクションデザインとは何か」を具体的な事例を交えて解説。最終章には未来を見据えた対談を収録。発想を広げ,インタラクションデザインの本質に触れるきっかけとなる一冊。
- 発行年月日
- 2025/10/17
- 定価
- 3,740円(本体3,400円+税)
- ISBN
- 978-4-339-01381-8
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 みた 様 (業界・専門分野:Web開発)】
掲載日:2025/10/27
総評として、学生から社会人まで幅広い世代が楽しみながら学べる本だと思いました。専門的なテーマを扱いつつも親しみある事例を多く取り上げ、段階的に理解が深まる構成になっていると思います。
1,2章はインタラクションデザインについてどういうものかを言葉や定義についての解説が主でした。良いUIや誤解の与えるBAD UIはどんなものかを解説する内容であり、とっかかりとしてよかったと思います。ただし、社会人や業務経験者には基礎的かもしれません。
3,4章は多くのインタラクションデザイン事例の紹介や、それに取り掛かるユーザーたちのマインドなどの紹介が主でした。
この章は自分にとって未知の事例が多く、「自分でも少し扱ってみようかな」と思える内容で読んでいてとても面白かったです。
5,6章はさらに学術的な深掘りがあり、どのようにユーザーに体験させていくかといったことが詳細に解説されている印象を受けました。
最後の7章は各章の著者らによる座談会。技術本には珍しく、未来志向で内容がまとまっており、読後に「何をどのように作るか」のマインドを自然と読者に意識づけさせてくれる構成になっています。読み終えた後に前向きな余韻が残り、好印象でした。
総じてこの本は、インタラクションデザインの基礎を学べると同時に、創造的なインスピレーションの両面を与えてくれる良書だと思います。
-
読者モニターレビュー【 bon 様 (業界・専門分野:Engineering in Medicine)】
掲載日:2025/10/07
本書は、教科書で見落とされがちな試行錯誤の手つきを前景化し、生活の現場からインタラクションデザインを捉え直す実践的ガイドである。第1章は当該分野の地図を端的に示し、専門外の読者にもその意義と射程を伝えつつ、以降の学びの足場を築く。
また、生成AIを用いて案内板やユーザーインターフェースの課題を抽出する取り組みも紹介される。AIは強力な補助となる一方、指摘の妥当性が揺らぐ局面も少なくないことを踏まえ、人が学び、経験に基づいて良し悪しを判断する重要性を説く。
さらに、問題発見の姿勢や要素分解、偉大なアイデアの模倣からの学び、現場重視の観点など、多視点から未来を考える契機が随所に散りばめられている。とりわけ次世代を担う読者にとって、自ら手を動かし思考を深めるための具体的なヒントが得られるだろう。
総じて、本書の強みは、生活・技術・人を結ぶ豊富な実例と、失敗、試作、評価を往還する実践の枠組みにある。分厚い理論体系を足すより、プロトタイピングを通じて目を養う姿勢を促す書籍であり、学習から実務への橋渡し役として心強い一冊である。
-
読者モニターレビュー【 松岡 大輔 様 (業界・専門分野:プログラマ)】
掲載日:2025/10/06
本書は、なぜ我々には本質的な新しさを作り出すことができないか、という根本的な問題意識に立脚しながら、いかにして新しさを見つけ、形にしていくかについて、丁寧に言語化した書籍である。インタラクションデザインというテーマはやや限定的な印象も受けるが、インタラクション、あるいはインタフェースというテーマ設定の背景には、デザイン思考がある。デザイン思考をより現実の方に引き寄せ、現実的な現象と人の界面を具体的に考えるということである。
本質的な新しさは、定義上、既存の知識の体系ではとらえられない。とりわけ既存の知識の体系の専門家であるほど、現実的な現象との界面で新しさの芽を見つけることが難しくなる。そのとき、学問的なアプローチになにができるか、という知的な誠実さが本書の根底にあり、そこに積極的な可能性を見ているのである。
したがって、本書は理論書ではないし、体系的な知識を提供するものでもない。本書は方法の書であり、本書から学ぶというよりは、本書で得た方法を現実に適用し、日々自ら新しさを発見していくという「営み」の必要性を説くものである。我々が知りうるのはせいぜい方法であり、あとは、具体的に現実的な人生を生きていく中で絶えず発見し続けるしかないのである。
そのようなアプローチを取る際に、本書が基本的な姿勢としているのが、失敗から学ぶということである。失敗とは、既存のデザインが機能不全を起こしている現象であり、まさにその理由を考え、解消することから、新しさが生まれる。
失敗は、基本的に、経験的にしか知られない。人が実際に対象を使ってみて初めてわかるのである。たとえば生成AIを使ってインタフェースの不備を洗い出す手法も検討されているが、執筆者の結論は現時点では否定的である。つまり、人が現象と接する界面において初めて、失敗は認識されるのであり、そこからしか新しさは生まれないだろうと考える。そして、失敗の経験を抽象化して分類することから、方法が生まれる。
問題は、むしろ、認識の面にある。自発的に新しいことを試みて失敗を肯定的に経験する心理を、教育課程で抑圧されることが多い。そのマインドセットから自己を解放する方法についても検討されている。そして、精神論ではなく具体的にプロトタイプを作り続けて考える、という実践的な姿勢も特徴だろう。
本書は、コンピュータ技術以降の情報科学の進展を踏まえて、現代的なメディア環境において具体的な事例を検討している。コンピュータの汎用性を、人とのインタラクションを通じて専用性へと最適化するという視点において、テクノロジーとメディアとデザインが交差しているところが、類書と比較した場合の特徴だろう。









