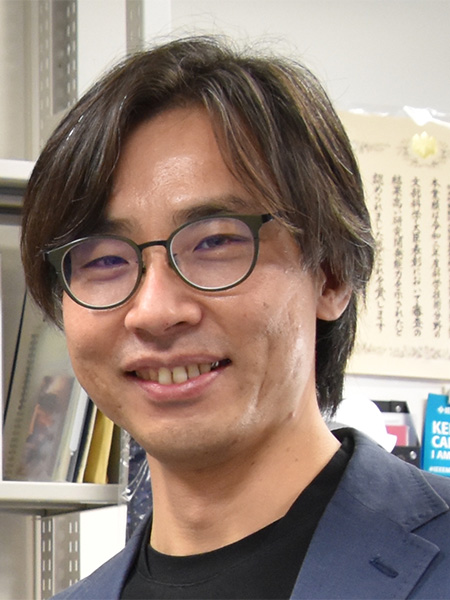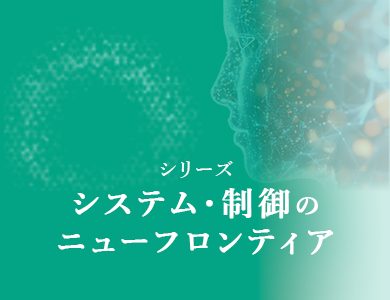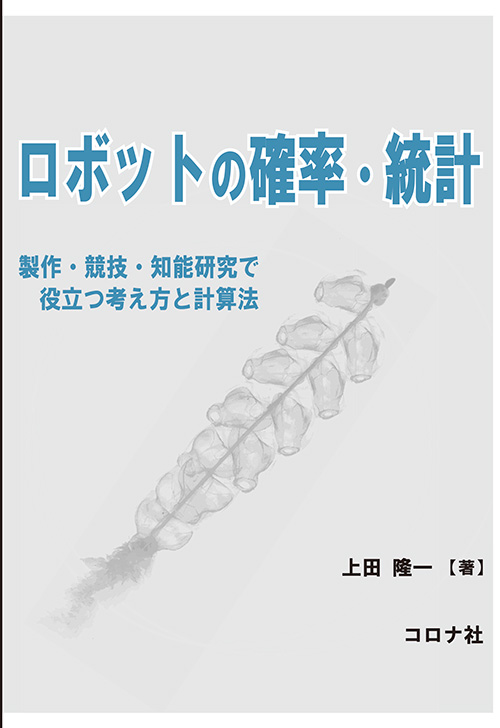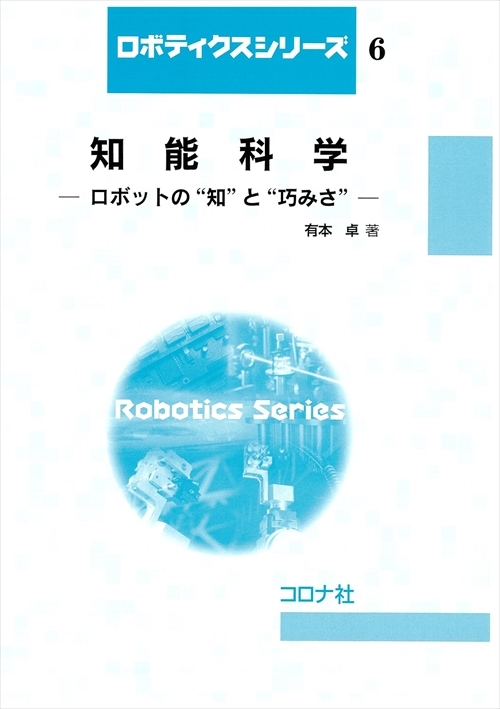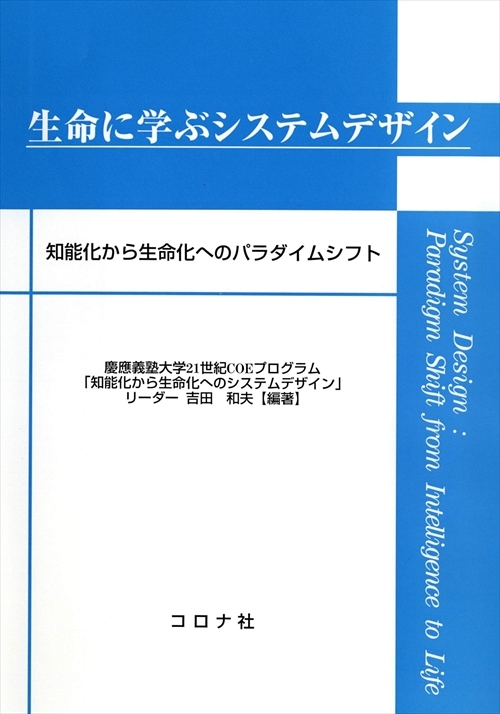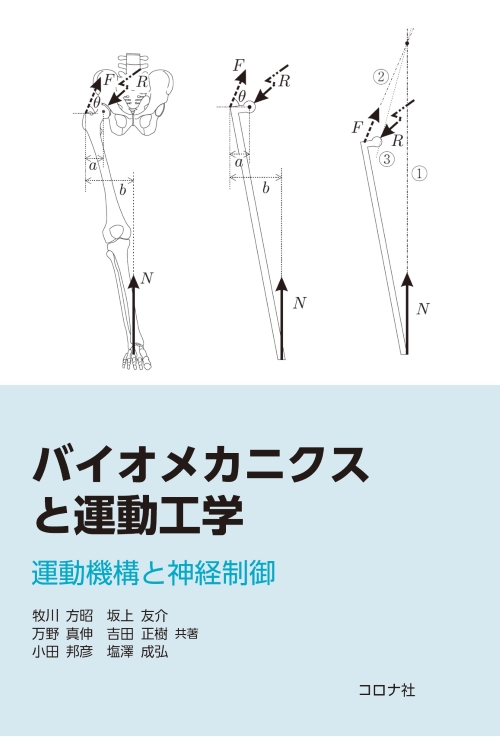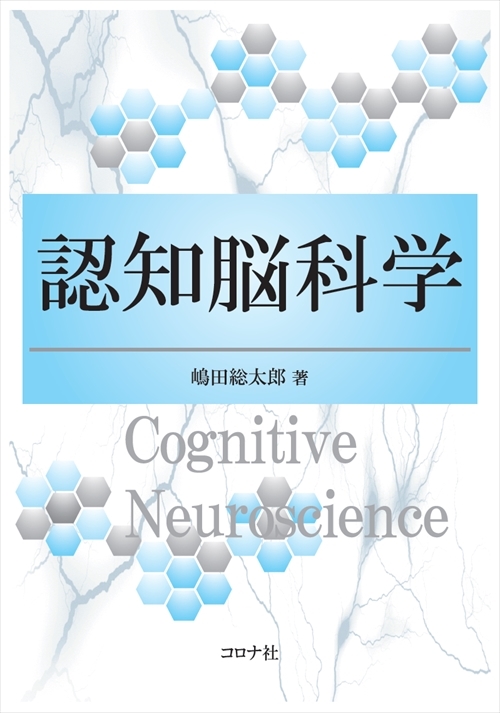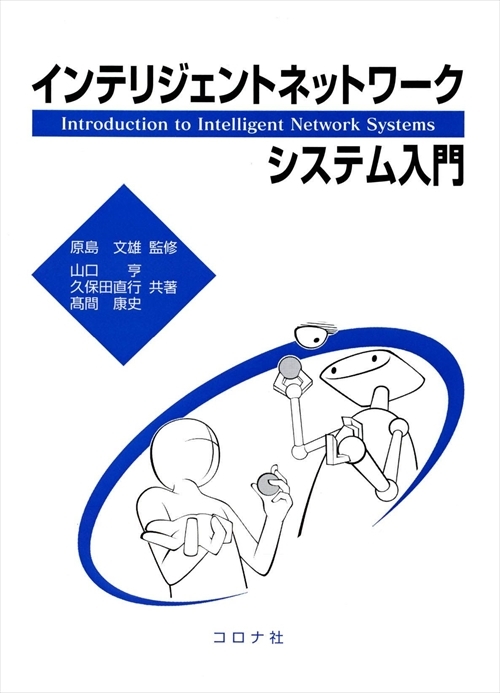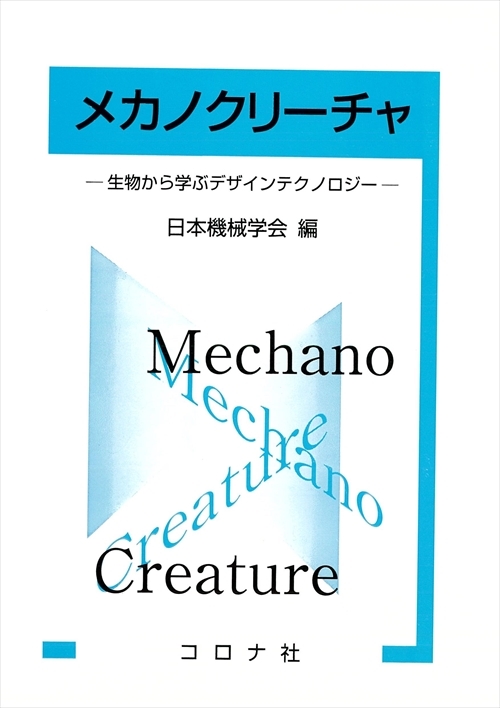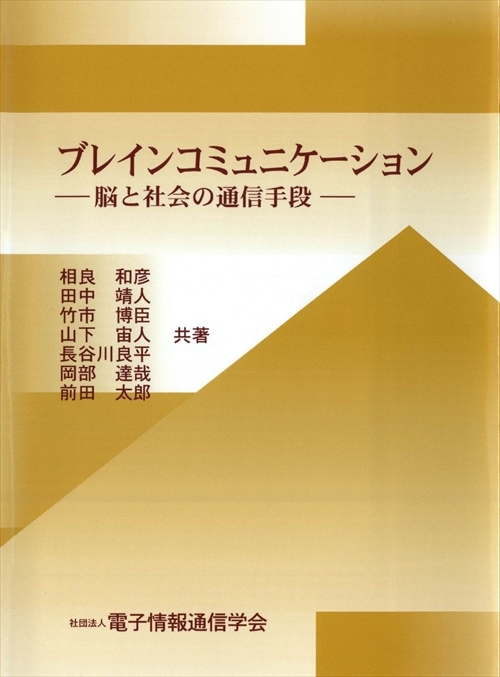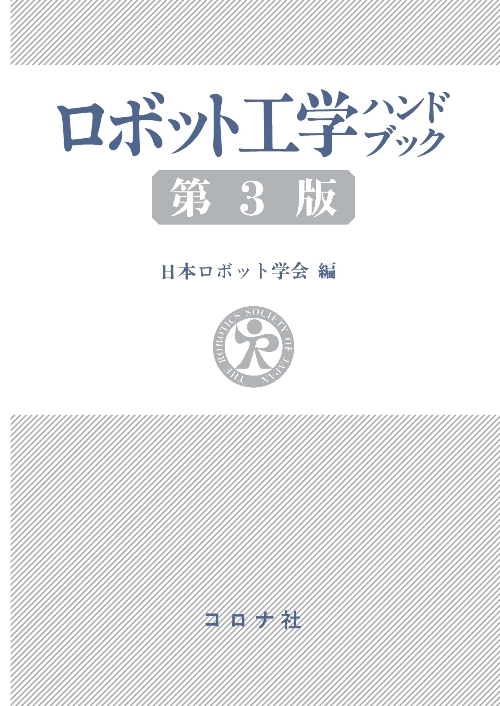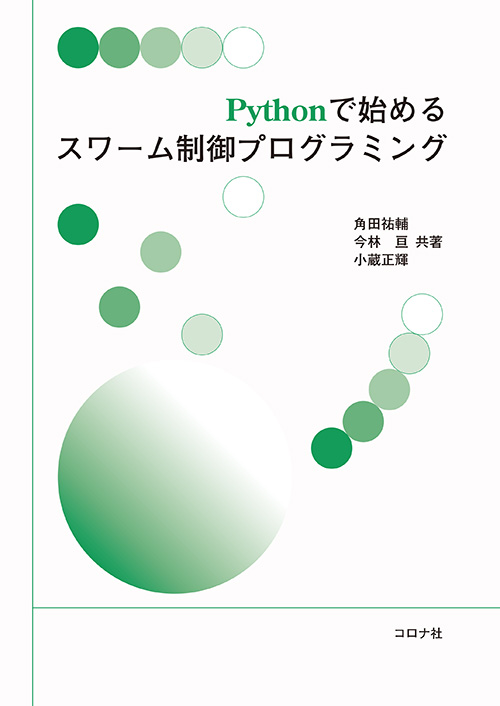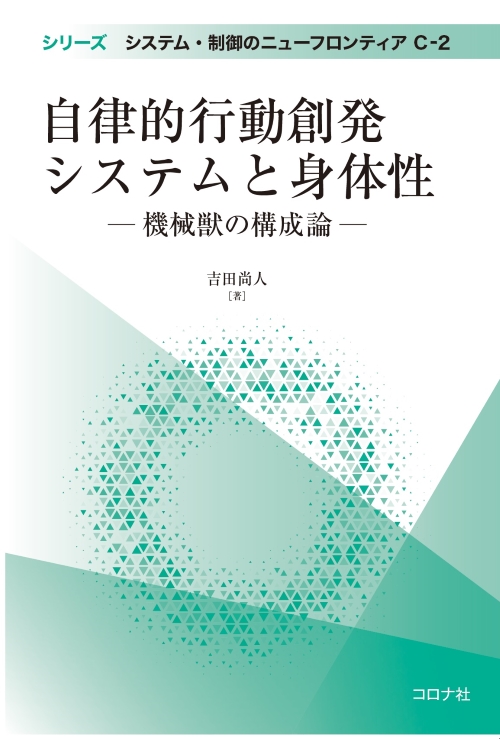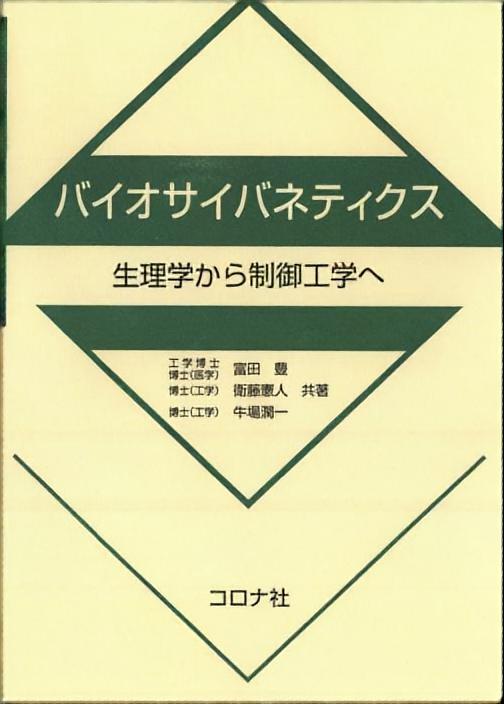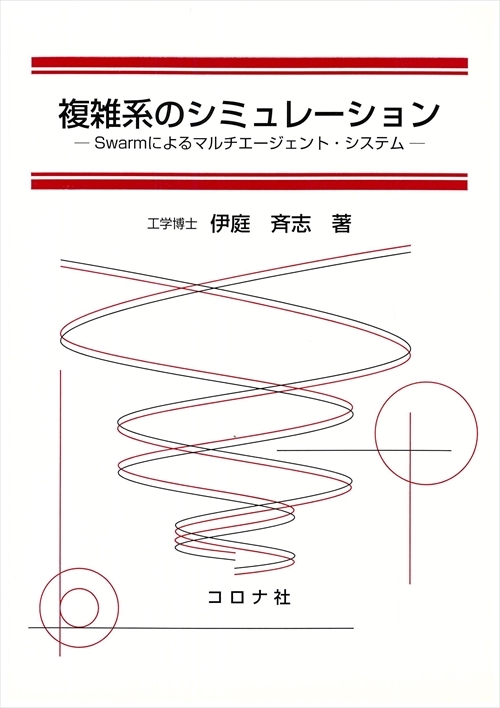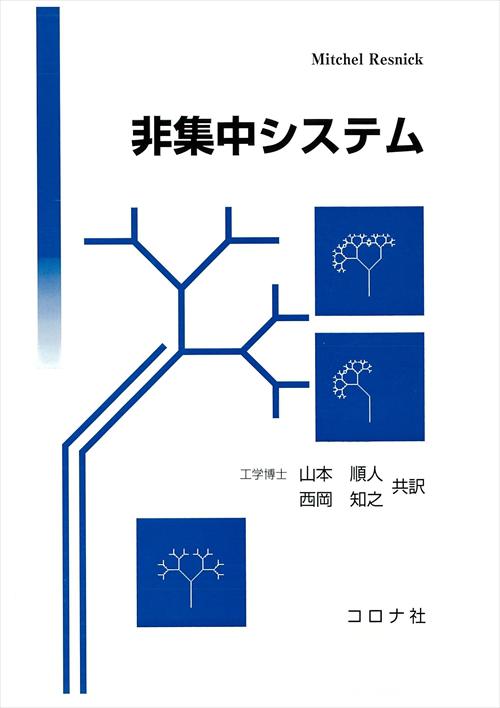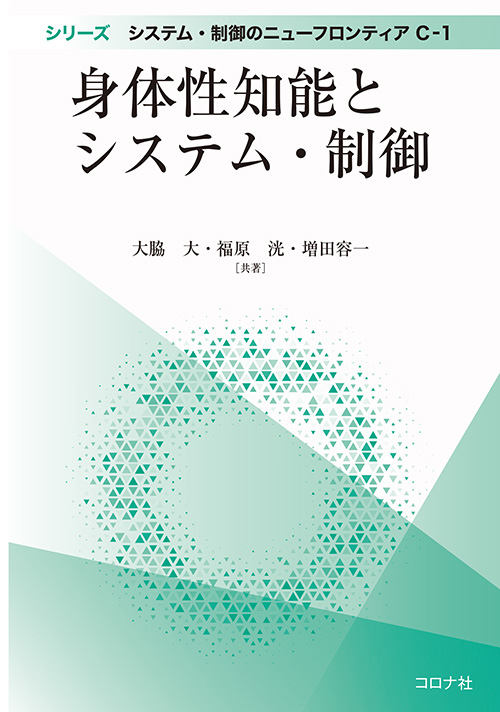
身体性知能とシステム・制御
身体性知能が個体の振る舞いのみならず,マルチスケールな現象にも通底することを示す。
- 発行年月日
- 2025/10/06
- 判型
- A5
- ページ数
- 330ページ
- ISBN
- 978-4-339-03401-1
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
【読者対象】
・本書は、工学系の大学院生・学部生、ロボット工学や制御工学、関連分野に関心を持つ研究者・技術者を幅広く対象としています。
・多様な事例を通じて「身体性」の概念を理解し、実践的に活用できる内容となっています。
・章ごとに完結した構成で、独学でも理解しやすく、関心のあるトピックから自由に読み進められます。
【書籍の特徴】
・『身体性知能とシステム・制御』は、「身体性」という視点から知能を再定義する新たな工学的パラダイムに基づく体系的な入門書です。
・「身体性知能(Embodied Intelligence)」の考え方を基盤に、制御工学やロボティクスと融合させることで、知能設計や運動制御にどのように応用できるかを具体例とともに解説します。
・シミュレーションコードをGitHubやWebアプリで公開し、理論(力学モデル・数理モデル)だけでなく、動作観察や実験を通じて「身体性知能」の本質を体感できる構成としています。
【各章について】
1章では、身体性に立脚した知能の概念・起源・歴史を踏まえ、本書の目的と全体像を示します。
2章では、「骨格」を基盤に創発する知能システムとして受動歩行現象を解説します。
3章では、「アクチュエータ」を基盤に創発する知能システムとして無脳ロボットの事例を紹介します。
4章では、「神経系」を基盤に創発する知能システムとして、Central Pattern Generator(CPG)による多脚ロボット制御を取り上げます。
5章では、「異なる身体部位の協調」に基づく全身協調運動の発現原理と設計法を解説します。
6章では、「個体間相互作用」に基づく群知能システムを紹介します。
7章では、2〜6章の事例を整理し、身体性に基づく設計・制御の要点をまとめます。
8章では、関連分野の最新トピックや今後の展望を示し、全体のまとめとします。
【著者からのメッセージ】
「知能とは何か?」という問いに対して、本書は従来の情報処理中心の枠組みを越え、「身体を介した環境との相互作用こそが知能をかたちづくる」という身体性知能(Embodied Intelligence)の視点から挑みます。本書では、受動歩行やアクチュエータ、多脚歩行制御、群ロボットなど、多様な実例を通して「身体性知能」の核心に迫ります。理論にとどまらず、シミュレーションコードや実験も豊富に紹介し、「読んで終わり」ではなく「試して体感できる」構成にこだわりました。新しい知能のかたちを探求したい学生・研究者・技術者の皆さんに、きっと新たな発見と刺激をお届けできると信じています。
【キーワード】
身体性、身体性知能、受動歩行、無脳ロボット、CPG、全身協調、群知能
知能とは何か?この問いに対し,「知能的な振る舞いを生み出すシステムには,主体の物理的実体と環境との相互作用,すなわち,身体性(embodiment)が不可欠である」とする概念が提唱されてから30年あまりが過ぎた。ビッグデータや機械学習の実用化などの技術革新を基盤とした第3次AIブーム,我々の生活様式を一変させた世界的パンデミックなど,時代が大きく変化しつつある昨今,予測不能的に絶え間なく変わり続ける実世界の複雑性に対応し,柔軟かつ適応的に振る舞う知能システムが未来の社会を支える科学技術の鍵となる。そのため,実世界との関わりから生じる知能やシステム・制御論の重要性は益々高まっている。身体性に基づくシステム・制御のアプローチは,従来の工学的なアプローチにみられるような,システムすべてを厳密にモデル化し統御するアプローチとはコンセプトが大きく異なる。そのため,初学者が身体性の持つ創発的で融通無礙な姿を納得を持って捉えることは容易ではなく,また,身体性の起源から,その歴史的経緯,さらには最新研究事例までを系統的に記述した解説書,専門書は少ない。そこで本書は,まず身体性に立脚した知能(embodied intelligence)の基本的なコンセプトを平易に紹介しつつ,生物やロボットの移動運動や知覚認知といった具体的な事例からさまざまな知能に通底する身体性の輪郭を浮かび上がらせることを試みる。そして,身体性に基づく知能のあり方が,個体の振る舞いのみならず,集団や群システムといったマルチスケールな現象にも通底することを示す。そして,身体性の観点から激動し続ける実世界におけるシステム・制御の未来像について展望する。
本書は,大学院講義の教科書,参考書を想定し,おもに工学系の大学院生を読者層として想定している。また,研究室に配属されたばかりの学生(学部4年生,大学院修士学生)や,ロボット工学,制御工学,その周辺分野に興味を持つ技術者,研究者も対象としている。本書の内容は,大学・大学院レベルの数学・物理の知識を持つ人が,できるだけ一人で読み進め,理解し,実践できるレベルに設定されている。一方で,環境との相互作用“力学(ダイナミクス)”に立脚する身体性の概念を理解する上で,力学,特に時間変化を伴う動力学の理解は必須であるため,前提知識となる。不安な読者は,力学に関する良書を片手に読み進めていただくことを推奨したい。特に,2章には,力学系を含む発展的な内容(リミットサイクル,ポアンカレ写像など)も含まれている。本書は,「身体性知能とシステム・制御」に関連するはじめての日本語の標準的な教科書や専門書を目指しており,身体性に基づくシステム設計,制御に関する事例の整理,体系化を試みた。
1章では,身体性に立脚した知能の概念と本書の目的をまとめた。知能の定義に関する議論から始め,身体性に基づく知能の「起源」,「歴史」的経緯について紹介し,その後,「本書の目的」を述べている(身体性に関連する必須「概念」,マイルストーンとなる研究「事例」および関連する国内外の「プロジェクト」を付録にまとめた)。2章から6章の構成として,身体性に基づく知能的システムを構成・設計する上で基盤となる「要素」を基準としている。具体的には,「骨格」を基盤として創発する知能としての受動歩行現象(2章),「アクチュエータ」を基盤として創発する知能システムとしての無脳ロボット(3章),「神経系」を基盤として創発する知能システムを構成するためのCentral Pattern Generator(CPG)に基づく制御(4章),「ヘテロな身体部位間の協調」を基盤として創発する知能としての全身協調運動の発現原理と設計(5章),「個体間相互作用」から創発する知能としての群知能システム(6章),という構成とした。
2章では,受動歩行と身体性についてまとめた。特に,本書の主たる話題である脚式ロコモーション(移動運動)の特徴と,脚式ロコモーションに着目する意義から説明した。そして,脚式ロコモーションにおいて,「身体性」の重要性を動機づける研究のパイオニアといえる受動歩行現象について紹介した。歩行現象の記述から始め,受動歩行現象をモデル化する支配方程式の導出について説明した。さらに,受動歩行現象の安定性解析の数理的アプローチと制御理論的解釈を説明した。また,力学系としてみた際の受動歩行現象の特性と,最新の研究事例を紹介した。本章には,受動歩行現象をモデル化したシミュレータをPythonでコードした資料(GitHub:https://github.com/daiowaki1229/python-passive-walker.git)およびWebアプリ(https://python-passive-walker.streamlit.app/)を公開している。シミュレー
ション上での実体験から,身体と環境の相互作用から発現する歩行現象を実感していただきたい。
3章では,ロボットや動物が複雑な環境で活動するために重要となるアクチュエータの特性と,それを活かす身体構造についてまとめた。特に,工学と動物の二つの観点から,身体性を能動的に活用するためのモータや筋肉の諸元について説明した。まず,工学の観点では,近年発展が著しいソフトアクチュエータやロボット用アクチュエータを紹介した。さらに,アクチュエータから発現する運動創発現象の例として無脳歩行現象を取り上げた。現象のモデル化,およびその安定性や分岐現象の解析事例を紹介し,2章で述べた力学系解析との具体的な接続を試みた。動物の観点では,生体筋特性の多様性と普遍性について説明した。さらに,読者の実践的な理解のために動物解剖の方法を紹介した。また,生体筋の筋特性をロボットへと実装するための方法として,Hillの三要素モデルの実機実装と,マッキベン型人工筋について紹介した。人工筋の製作法とその諸元を紹介し,生体筋の特性との類似性について議論した。
4章では,脚式移動ロボットにおける身体性に基づくシステム・制御設計の事例として,動物の神経系を模したCentral Pattern Generator(CPG)を規範とする制御手法についてまとめた。まず,四脚動物の歩行パターン生成を題材とし,脚協調制御を実現する神経基盤(CPG制御)について紹介した。そして,CPG制御の代表的な既存制御を紹介し,身体性に立脚したアプローチの要諦(設計指針)について説明した。さらに,状況依存的な脚協調制御を生み出すことを目的として提案された「手応え」制御の概念を紹介し,手応え制御を用いた研究事例を紹介した。手応え制御を実装した簡易的なホッピングロボットのシミュレーション事例として,GitHub(https://github.com/daiowaki1229/pyTegotaeCPG.git)およびWebアプリ(https://pytegotaecpg.streamlit.app/)を公開している。手応え制御から創発する身体性知能の実体験となれば幸いである。
5章では,動物が示す脚部のみならず体幹部を活用した運動様式を題材とし,脚式移動ロボットにおける脚部と体幹部という異質なサブシステム間の協調制御を扱った身体性システム・制御設計についてまとめた。まず,規範となるさまざまな動物の全身運動について概説し,異質な身体自由度の協調運動の協調様式のあり方についてまとめた。つぎに,動物の示す適応的な脚部・体幹部の協調運動の再現や発現機序の理解のために取り組んだ研究事例について紹介している。具体的には,身体の機械的な接続に着目したアプローチと,運動指令の制御的接続に着目したアプローチについてそれぞれの取り組みとアプローチの特徴をまとめている。全身のしなやかな振る舞いを生み出すためのサブシステムの“つなぎ方”"について,身体性システムの観点を広げていただきたい。
6章では,5章まで扱ってきた移動体システムの枠組みを移動体の集団システム,すなわち群れシステムへと広げて,身体性知能に基づくシステム・制御設計の事例をまとめた。本章では,非常に単純な系である自己駆動粒子の群れから出発し,徐々に身体性を追加した事例を説明することで,群れシステムにおいて身体性を考慮することの意義がわかりやすくなるように試みた。エージェント単体では議論できなかった群れシステムにおけるさまざまな相互作用様式を事例に,身体性知能に基づくシステム設計の視点を広げていただきたい。
7章では,2章から6章において紹介した,身体性知能に基づくシステム設計に関する事例を整理し,その体系化を試みた。これにより,身体性に基づくシステム設計・制御の重要なポイント,いわゆる「コツ・キモ」を明確化した。最後に,現在および未来の展望として,関連する最新分野や著者らの興味のあるトピックを五月雨式に枚挙し,まとめの節とした。これにより,身体性に基づくシステム・制御の現状と将来の方向性にについての知見が深まることを期待している。
本書では,読者らの身体性に関連する思考を促す試みとして,1~6章に章末問題を設けた。しかしながら,数学,物理などの専門科目と異なり,身体性に関連する研究領域には確立した解答がないのが現状である。そのため,解答例は付けていないが,必要があれば,著者らに問い合わせいただきたい。
本書が,読者の心に身体性に基づく知能とシステム・制御の深遠な理解と魅力を植え付けることを切に願う。本書の各章は,理論と実践の橋渡しを目指し,知識の深化とその応用への道を照らすことを意図して構成した。本書が,未来の破壊的革新を担う工学者や研究者の皆様に新たなインスピレーションを与え,知能システムの設計や制御技術の進化に貢献すること,を著者らは心に願い,この編集に(寝る間も惜しんで)奮励した。読者一人ひとりが本書から得た洞察を自らの研究や実務に活かし,新たな発見へとつなげることが,著者らにとって最大の喜びとなる。
2025年8月
著者一同
1.身体性に立脚した知能の概念と本書の目的
1.1 知能,身体性,身体性に立脚した知能とは?
1.1.1 知能とは?
1.1.2 身体性,身体性に立脚した知能とは?
1.2 身体性の起源と歴史的背景
1.3 本書の目的
章末問題
2.受動歩行と身体性
2.1 脚式ロコモーションの特徴と意義
2.1.1 脚式ロコモーションとは?
2.1.2 脚式ロコモーションと生物規範ロボティクス
2.1.3 脚式ロコモーションにおける受動歩行研究の位置づけ
2.2 受動歩行とは?
2.2.1 工学的意義
2.2.2 非線形力学現象としての受動歩行
2.2.3 受動歩行にみられる制御構造
2.2.4 受動走行,四脚受動歩行,多脚受動歩行
2.3 受動歩行のモデル化
2.3.1 歩行運動の力学
2.3.2 片脚支持期の運動方程式
2.3.3 両脚支持期の切り替え方程式
2.4 受動歩行のシミュレーション
2.4.1 定常歩行
2.4.2 分岐現象(環境適応性)
2.4.3 リミットサイクル歩行
2.4.4 身体特性の影響
2.4.5 吸引領域(初期値依存性)
2.5 受動歩行の安定性解析
2.6 受動歩行に内在する安定化構造
2.7 力学系としての受動歩行現象
2.8 演習:受動歩行モデルのシミュレーション
2.8.1 シミュレーションの概要
2.8.2 メインプログラムの構成
2.8.3 Streamlitを用いたWebアプリ
章末問題
3.アクチュエータ特性から生じる運動知能
3.1 ロボットの運動におけるアクチュエータの硬さと柔らかさ
3.1.1 アクチュエータのさまざまな柔らかさ
3.1.2 ロボットのアクチュエータ
3.1.3 脚ロボットのアクチュエータ
3.2 モータの電気的受動特性から生じる運動パターン
3.2.1 モータに備わる電気的受動特性
3.2.2 電気的受動特性が制御則になっている
3.2.3 電気的受動特性から生じる周期運動の安定化現象
3.2.4 1自由度跳躍ロボットのモデリング
3.2.5 バネ質点系における複数モータの同期および運動遷移現象
3.2.6 無脳ロボットにおける複数モータの同期および歩容遷移現象
3.3 動物の筋肉における柔らかさ
3.3.1 動物のサイズと柔らかさの関係
3.3.2 動物の多様な筋特性
3.3.3 筋肉の配置
3.3.4 動物解剖について
3.3.5 筋肉のモデルとロボットへの実装法
3.3.6 動物の筋肉と人工筋
3.3.7 人工筋の入手について
章末問題
4.脚式移動ロボットの身体性に基づく脚協調制御
4.1 多種多様な歩行パターンを発現する四脚哺乳動物
4.2 四脚動物の歩容生成を司る神経機構
4.3 生物規範型四脚ロボット
4.3.1 Raibertのホッピングロボット
4.3.2 Tekken(鉄犬)
4.3.3 位相リセット法
4.3.4 EPFLの四脚ロボット
4.4 身体性に基づく脚間協調制御
4.4.1 脚間協調制御の設計指針
4.4.2 身体を介した力学的相互作用を活用する脚間協調制御
4.4.3 Oscillexが示した歩容
4.5 「手応え」制御としての再解釈
4.5.1 「手応え」,「手応え」制御とは?
4.5.2 四脚ロボットの脚間協調制御の再解釈
4.6 六脚ロボットの手応え制御
4.7 二脚ロボットの手応え制御
4.8 「手応え」制御の設計方策
4.9 演習:「手応え」制御のシミュレーション
4.9.1 メインプログラム`pyTegotaeCPG_odeint.py'
4.9.2 力学モデル`SMDwPO.py'
4.9.3 アニメーション`video_pyTegotaeCPG.py'
4.9.4 Streamlitを用いたWebアプリ`streamlit_pyTegotaeCPG.py'
章末問題
5.全身協調運動にみるシステムのつなぎ方
5.1 脚の協調運動から全身の協調運動へ
5.2 動物の全身をめぐる動き
5.2.1 脊椎動物の全身運動
5.2.2 無脊椎動物の全身運動
5.3 機械的接続に着目したシステム設計
5.3.1 体幹の受動的屈曲による脚部・体幹部の協調運動の実現
5.3.2 機構的な連動による脚部・体幹部の協調運動の実現
5.4 制御的接続に着目したシステム設計
5.4.1 チーター様走行におけるフィードフォワード制御モデル
5.4.2 チーター様走行における反射の連鎖モデル
5.4.3 チーター様走行におけるセンサフィードバック制御モデル
5.4.4 サンショウウオ・ムカデ様の歩行・遊泳における運動遷移制御モデル
5.5 身体部位間の調和的協調運動を生み出すシステムのつなぎ方
5.5.1 動物にみる機械系・制御系の統合様式
5.5.2 身体部位の基本となる運動様式の設計
5.5.3 身体部位間の接続様式の設計
5.5.4 全身運動を引き出す条件づけの設計
章末問題
6.群れシステムと身体性,多様な相互作用のあり方
6.1 個体の動きから群れの動きへ
6.2 自己駆動粒子によって形成される群れシステム
6.2.1 Boid
6.2.2 群れシステムの柔軟な振る舞いを生み出すポイント
6.2.3 群れシステムにおける身体性とは?
6.3 情報伝達物質を活用した群れシステム
6.3.1 フェロモンを活用した餌場選択と確率的表現
6.3.2 フェロモンを活用した多様な蟻道パターンの形成
6.3.3 フェロモンを活用した構造物形成
6.3.4 情報伝達物質を介した相互作用の設計
6.4 自律個の身体的特徴を活用した群れシステム
6.4.1 エージェントの物理的接触と犠牲を活用した群れシステム
6.4.2 エージェントの身体の柔軟性を活用し環境を切り拓く群れシステム
6.4.3 選択的相互作用を可能とする身体と群れシステム
6.4.4 身体の物理的接触を介した相互作用の設計
6.5 群れシステムにおける身体性と相互作用の方向づけ
章末問題
7.身体性に基づくシステム・制御の将来展望
7.1 身体性に基づく知能システムの設計・制御の体系化
7.2 身体性に基づく知能システム設計の心得
7.3 将来展望
7.3.1 陰陽制御
7.3.2 環世界:生物からみた世界
7.3.3 弱いロボット
7.3.4 サイボーグ:生物の人工物化
7.3.5 さまざまな刺激-応答性の活用
7.3.6 大規模言語モデル(LLM)と身体性
8.1~7章の概要
付録
A.1 関連する必須の概念
A.1.1 一般化フレーム問題(generalized frame problem)
A.1.2 アフォーダンス(affordance)
A.1.3 創発(emergence)
A.1.4 自己組織化(self-organization)
A.1.5 オートポイエーシス(autopoiesis)
A.1.6 参照フレーム問題(The frame of reference problem)
A.1.7 サイモンの浜辺のアリ(Simon's beach ants)
A.1.8 包摂アーキテクチャ(subsumption architecture)
A.1.9 感覚運動協調(sensor-motor coordination)
A.1.10 構成論的手法(synthetic approach)
A.1.11 人間機械論(cybernetics)
A.1.12 身体性認知科学(embodied cognitive science)
A.1.13 人工生命(artificial life)
A.1.14 進化ロボティクス(evolutionary robotics)
A.1.15 生物規範ロボティクス(bio-inspired robotics)
A.1.16 モーフォロジカルコンピュテーション(morphological computation)
A.1.17 ソフトロボティクス(soft robotics)
A.1.18 ロボティクス規範生物学(robotics-inspired biology)
A.2 マイルストーンとなる研究事例
A.2.1 ブライテンベルク・ビークル(Braitenberg vehicles)
A.2.2 スイスロボット:掃除するDidabot
A.2.3 Brooksのロボット:Myrmix,Ghengis,Cog
A.2.4 受動歩行機械(passive dynamic walker)
A.2.5 群知能を示すBoidモデル(Boid model)
A.2.6 進化する仮想生物(evolving virtual creature)
A.2.7 モジュラーロボット(modular robots),群ロボット(swarm robots)
A.2.8 物理リザバー計算(physical reservoir computing)
A.3 関連する国内外の研究プロジェクト
A.3.1 自律分散システム(1990~1992年度)
A.3.2 創発システム(1995~1997年度)
A.3.3 移動知(2005~2009年度)
A.3.4 浅田共創知能システムプロジェクト(2005~2010年度)
A.3.5 Locomorph(2009~2013年)
A.3.6 OCTOPUS(2009~2013年)
A.3.7 身体性システム科学(2014~2018年度)
A.3.8 ソフトロボット学(2018~2022年度)
引用・参考文献
あとがき
謝辞
索引
読者モニターレビュー【 佐藤 希美 様 浜松未来総合専門学校 (業界・専門分野:ロボティクス,自律移動ロボット)】
この書籍は「知能は脳の中だけに存在する」という従来の考え方とは異なり,身体と環境の相互作用を含めた知能のあり方を示している.ロボットの歩行運動や群行動,力覚制御の設計に至るまで,身体構造や環境との相互作用が生み出す知能を数理モデルを通して論理的に掘り下げている.
特に「身体性」という概念は抽象的であり,初学者にはやや難解に感じられるかもしれない.しかし,本書の関連リンクには丁寧な説明が用意されている.概念のイメージが掴めない場合は,事前にそちらを確認することを強く勧めたい.
内容は大学から大学院レベルを想定しており,数式やシミュレーションを通して理論と実装の両面を学べる点が良い.各章の終わりには章末問題が充実しており,自分自身が理解をしているか確認する機会としても活用ができそうだ.
第2章の歩行現象のモデル化や第4章のホッピングロボットの手ごたえ制御シミュレーターなど,理論を実際の動きに落とし込むことが理解を深める助けとなるだろう.付録も充実しており,概念整理の面でも非常に有用である.
読者モニターレビュー【 あまさん 様 (業界・専門分野:制御工学)】
この書籍では、実在の動物の動作を制御工学的に解析し、その動作を模倣するロボットの実現方法について主に解説されています。
各章では、筋肉単位の局所的な動作の解析から始まり、全身の動作、さらには群れとしての行動まで幅広く取り上げられており、入門者でも大きな視野を得られる内容となっています。
ただし、数式の理解には制御工学や力学の基礎知識が前提となっているため、それらを身につけた上で読み進めるのが望ましいでしょう。
制御工学の一般的な視点では、ロボットは剛性を高めて外部からの影響をできる限り減らすことが重視されます。
しかし本書では、あえて剛性を低くすることで、環境からの影響を利用し、より少ない知能リソースで効率的に制御できるという興味深い知見を得ることができます。
読者モニターレビュー【 yk 様 (業界・専門分野:臨床医療, 神経科学)】
エージェントと環境の相互作用により知能的な振る舞いが創発するという考え方は、なるほど確かにそうだと思う反面、これだけではやや抽象的に過ぎる。それをどうやって定式化し検証し得るのだろうか、という疑問が真っ先に生じるのである。本書は歩行運動や群知能など具体的な問題に焦点を当て、その問いにいくつかの答えを与えてくれる。
特に印象的だったのが、純粋な力学現象として一様重力場のもとで斜面を“歩く”脚のモデル=受動歩行モデルである。運動方程式の導出からその数値積分に至るまで非常に丁寧な解説が与えられており、公開されている数値積分のpythonコードを用いて遊ぶことで身体性知能の一例を深く掘り下げることが出来る。目的の運動を得るためには初期値の微調整が必要であるという微妙な問題を実感することもできるだろう。付け加えるなら、受動歩行は力学の応用問題として非常に味わい深いものであり、物理学を専攻する学生にとっても一読する価値がある。
本書で扱われる身体性知能は、誤解を恐れずに言えば、脊髄反射により表現される類の知能なのであって、いわゆる脳の高次機能における知能とは言えない。個人的には、学習や他者とのコミュニケーションも含めた脳の高次機能を実現するロボットを作ろうと思ったときに本書の知見をどのように組み込めるだろうか、という点が気になった。中でも、本書では軽く触れるに留められているが、フリストンの自由エネルギー原理との接続がどう構成できるのか、興味あるところである。
以上は私が興味をかき立てられた事柄であるが、同様のことは全ての読者について言えるだろう。すなわち、読者は自身の専門によってそれぞれ思う所が出て来るはずであり、それは新しい研究の萌芽であり得る。本書はそれだけ多くの示唆を内包しているのであり、とりわけ境界領域に身を置く者にとって貴重な書籍であると思う。
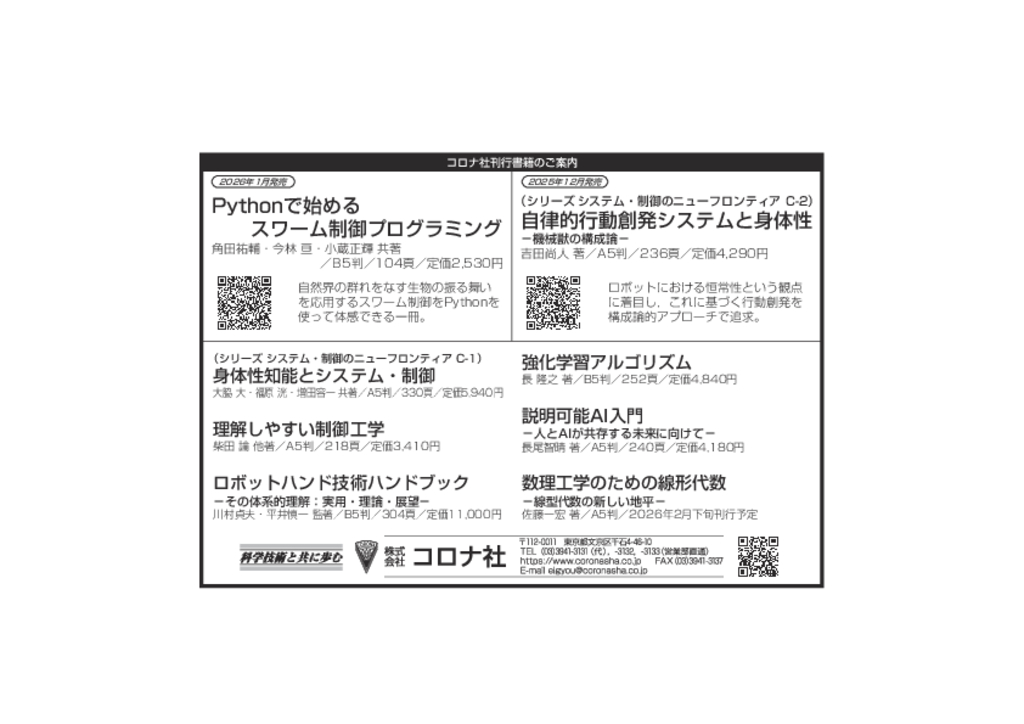
-
掲載日:2026/02/10

-
掲載日:2025/12/19
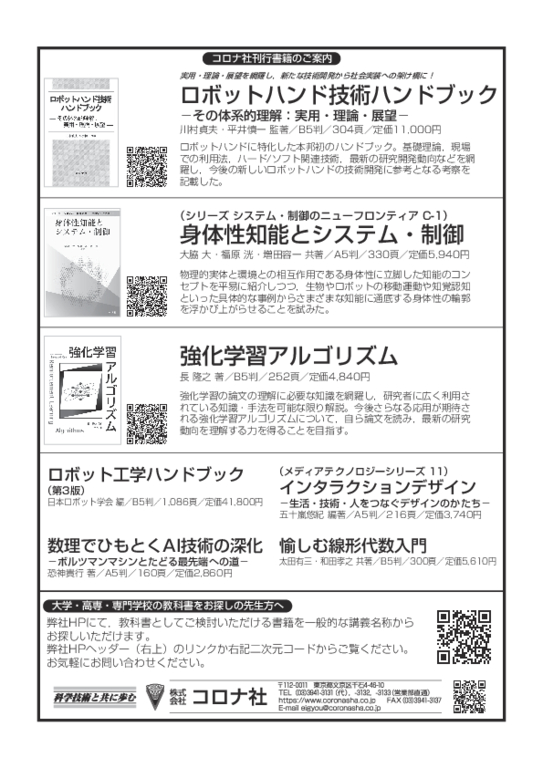
-
掲載日:2025/12/15
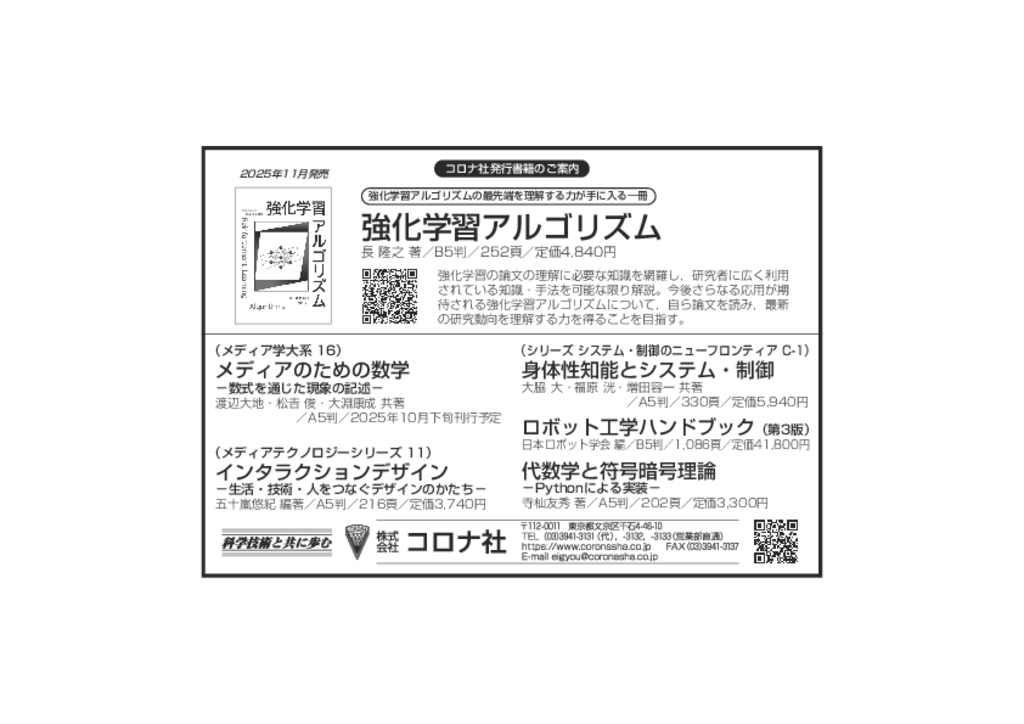
-
掲載日:2025/11/01
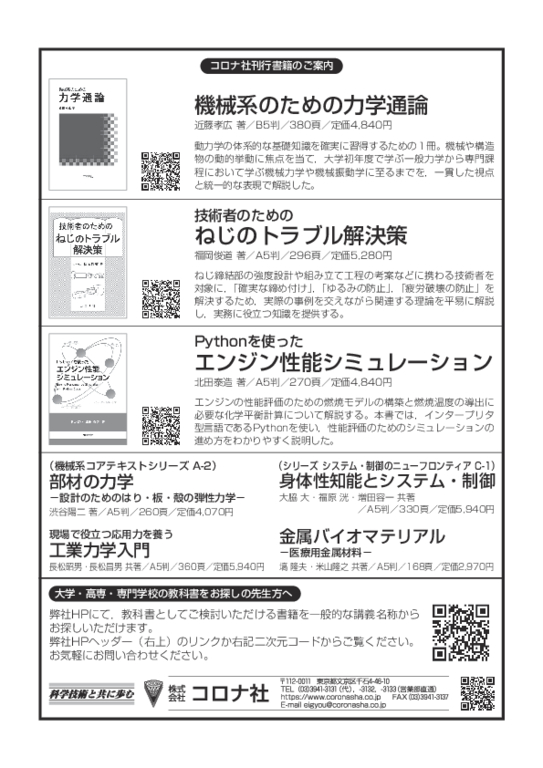
-
掲載日:2025/11/01
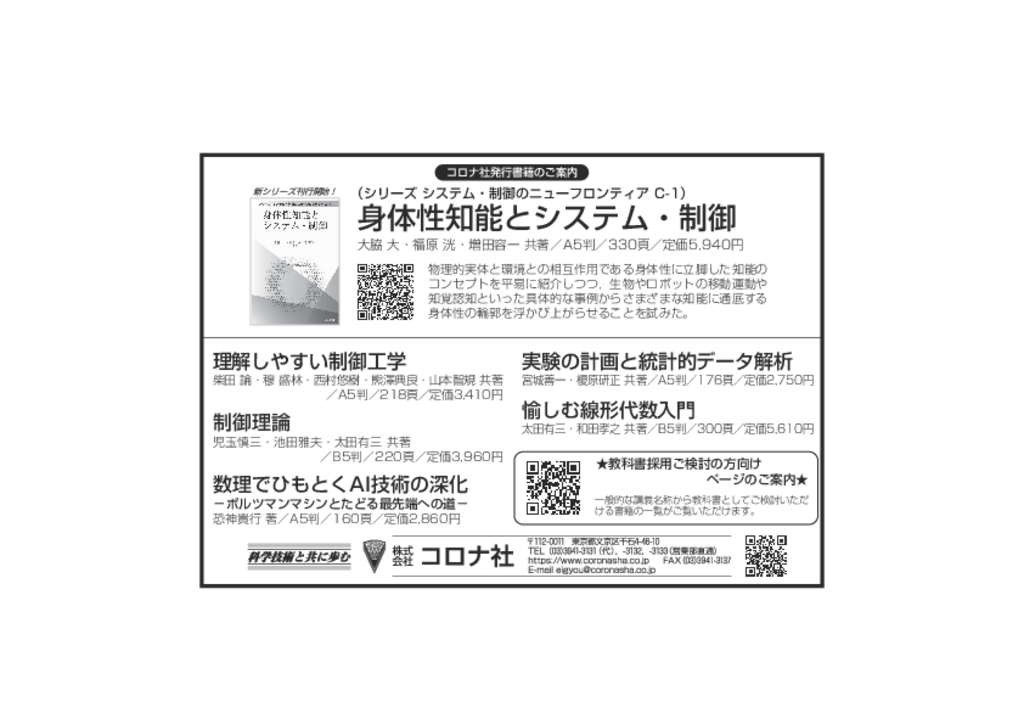
-
掲載日:2025/10/10
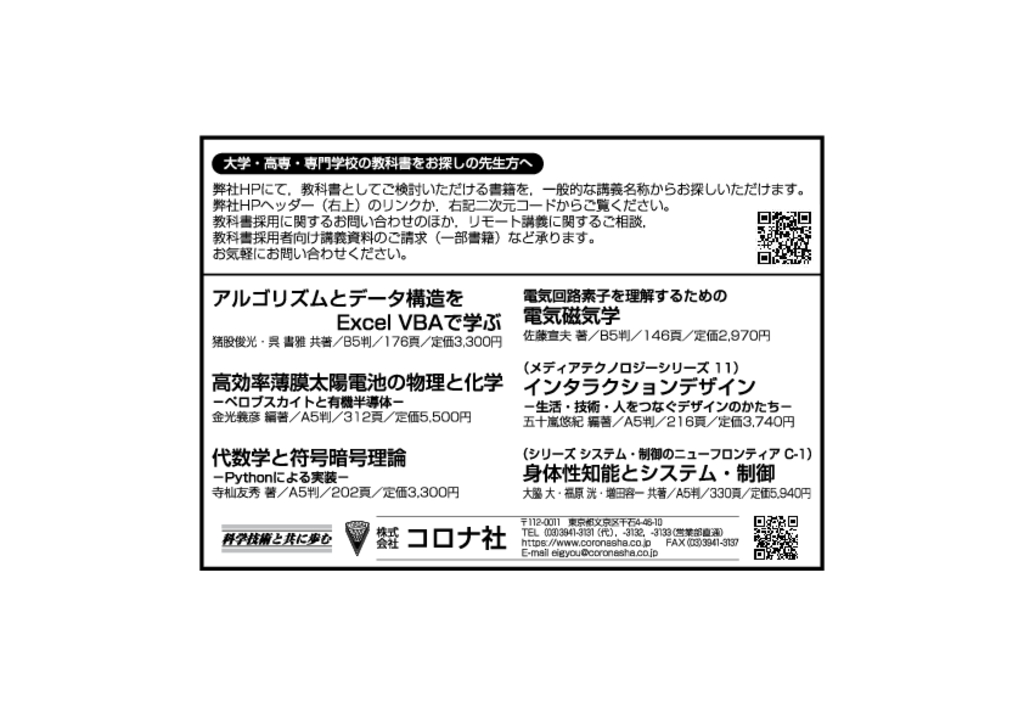
-
掲載日:2025/10/01
★特設サイトはこちらから★
各書籍の詳細情報や今後の刊行予定,関連書籍などがご覧いただけます。
関連資料(一般)
- Boidシミュレータ