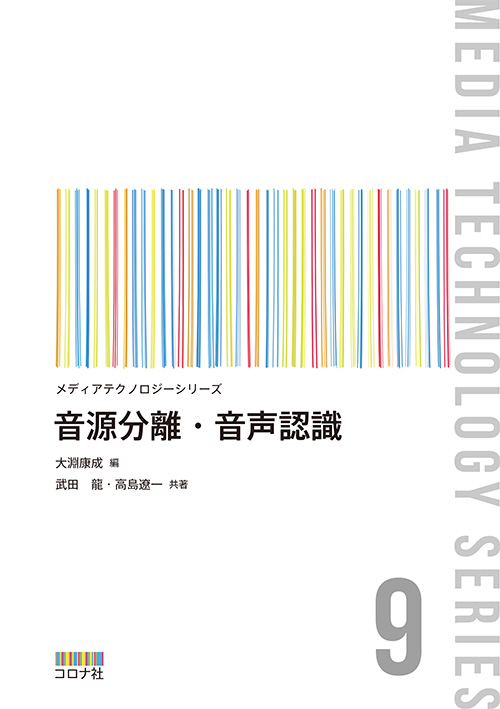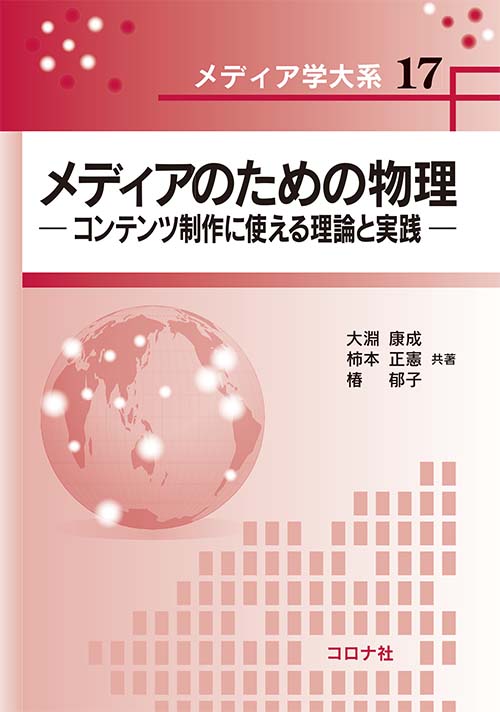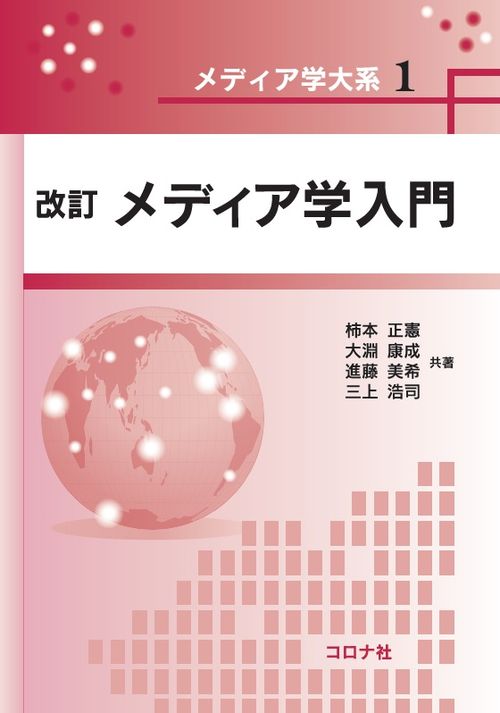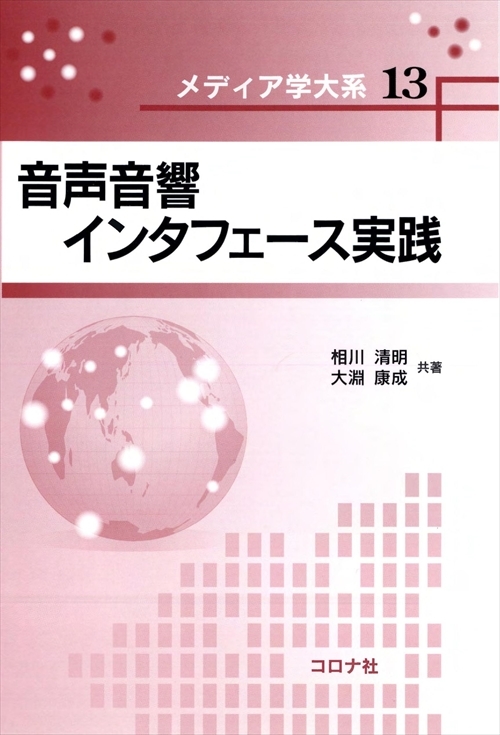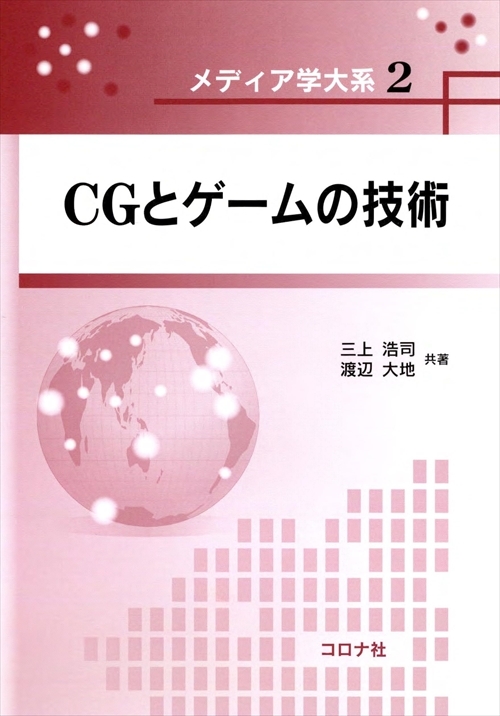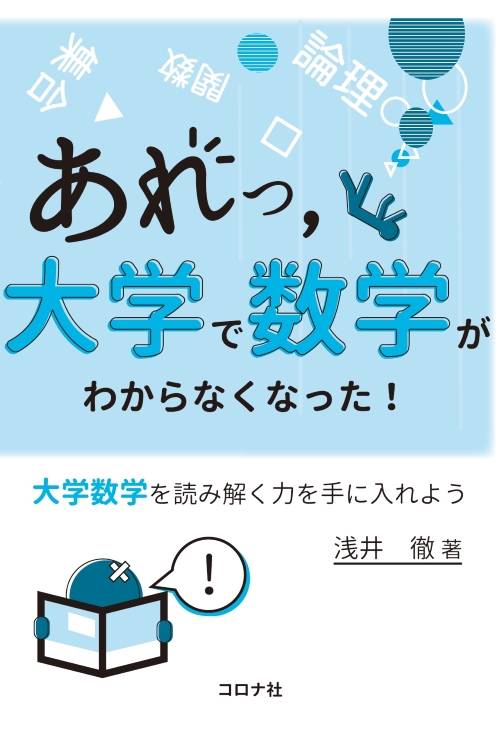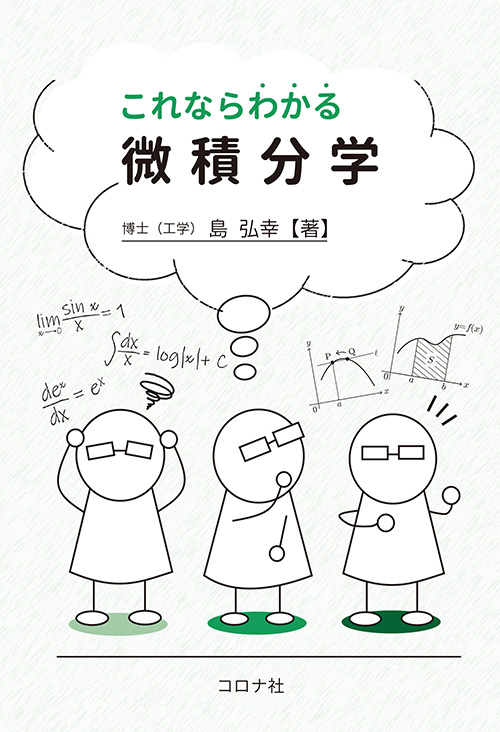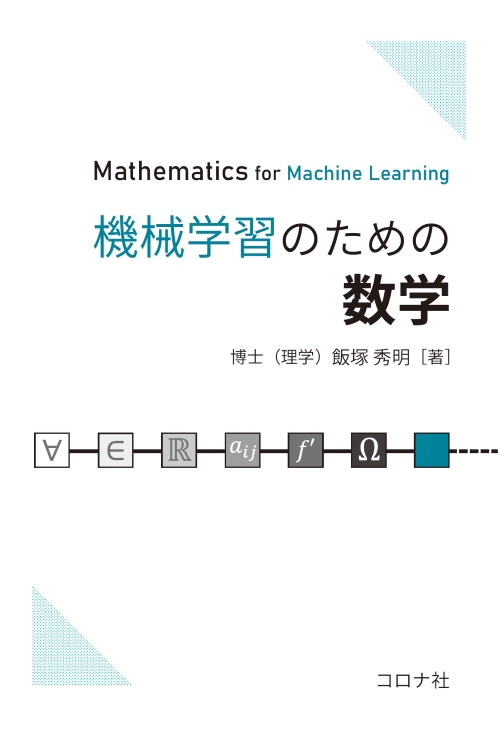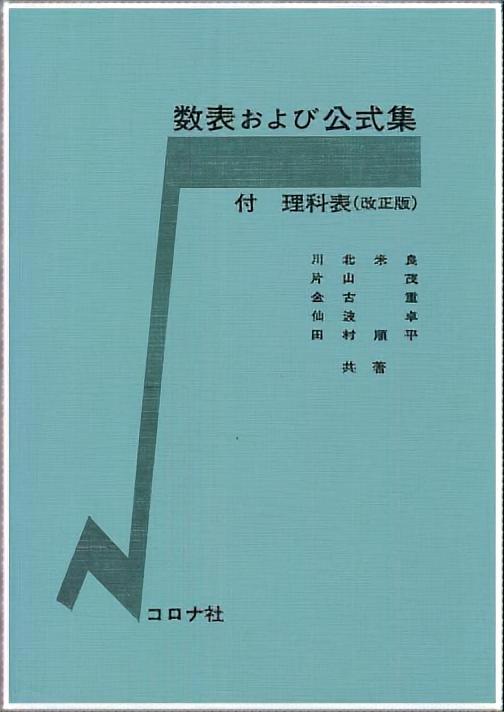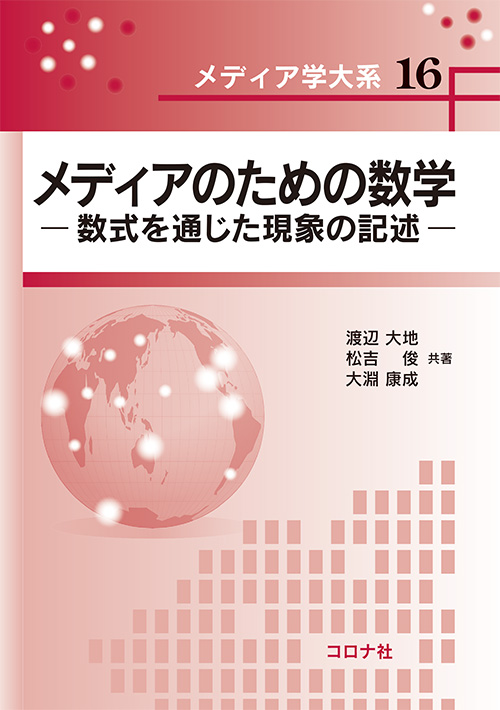
メディア学大系 16
メディアのための数学 - 数式を通じた現象の記述 -
CG・ゲーム,音声・音響・信号処理,人間社会モデル等の具体例を通して数学の魅力を解説
- 発行年月日
- 2025/11/28
- 判型
- A5
- ページ数
- 208ページ
- ISBN
- 978-4-339-02777-8
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
【読者対象】
さまざまなメディアに関する専門領域を学ぶ上で、基盤となる数学理論について網羅的に学習を進めたい学生。
【書籍の特徴】
映像、CG、ゲーム、音楽、音声など、様々なメディアを制作するためのアプリケーションが数多く存在しますが、従来のアプリケーションでは実現できない表現や、未解決問題の分析などを行うには、高度な処理が必要となります。その際重要となるのが、プログラミング技術と数学理論です。本書は、抽象的な数学理論が、様々なメディアに関する分野でいかに有用なものであるかについて、学生に理解してもらうことを目的として書かれたものです。
【各章について】
第1章では分野によらない共通項目を初学者向けに端的にまとめて紹介しています。集合と論理、数と式、関数、ベクトル、行列、微分積分、確率といった各単元をコンパクトにまとめて記載しています。
第2章は「CG・ゲームのための数学」と題して、主にベクトルや行列についての理論を学んでいきます。様々なメディア処理の中でも、3次元のグラフィックスは最も数学が活躍する分野の一つであり、その主役となるのがベクトルや行列を扱う「線形代数学」という分野です。
第3章は「音声音響信号処理のための数学」と題して、「フーリエ級数」という概念を中心に学んでいきます。音の正体は空気振動の波であるため、波を扱う数学としての三角関数が基本となり、その組み合わせを理論的に扱うフーリエ級数やフーリエ変換が不可欠です。第3章は、高度な音声音響処理の基盤となる数学理論をまとめたものです。
第4章は「人間社会モデルのための数学」と題し、グラフ理論を基本とした理論を学びます。グラフとは、複数の頂点と頂点同士を接続した辺による模式図であり、様々な問題解決に応用することができます。
【著者からのメッセージ】
日本の高校における数学教育カリキュラムの高度さは、世界的にトップレベルであると言われることがあります。その真偽については様々な議論がありますが、かなり高度な内容を扱うことに異論を唱える人は少ないでしょう。一方、高校までの数学教育では「どんなことに利用できるのか」についてはほとんど触れません。実は、本書の内容に高校数学の範疇もかなり含まれるのですが、これまで習ってきた数学理論が、どのような実践的な場面で必要となるのかを知ることで、数学が大変強力な武器であることを実感できることを願っております。
日本の高校における数学教育は,世界的に見てもトップレベルであると言われることがある。その真偽についてはさまざまな議論があるが,かなり高度な内容を扱うことに異論を唱える人は少ないであろう。しかしながらその一方で,高校までの数学教育では「どんなことに利用できるのか」についてはほとんど触れられないことが多い。
高校までの日本の教育制度は科目間での依存をできる限りなくすように設計されている。例えば,「物理」では微分積分の素養を必要としないように科目内容が設定されており,微分積分を履修していない生徒も物理を選択することが可能となっている。これにより,生徒は柔軟に履修教科を選択することができる一方で,複数科目に渡る共通の概念という存在を意識しないという副作用が生じてしまうという懸念がある。大学に入学し,さまざまな科目で実践的に数学を利用する場面があるが,これまで学習してきたさまざまな数学の素養が生かせないという学生は多い。本書は,抽象的な数学理論が,さまざまな分野でいかに有用なものであるかについて,学生に理解してもらうことを目的として書かれたものである。
1章では分野によらない共通項目を初学者向けに端的にまとめて紹介していく。数学での最も基本的な概念である「集合と論理」,さまざまな数の種類についてまとめた「数と式」,数学的な処理の中心をなす「関数」,図形や空間の処理に欠かせない「ベクトル」,現代の科学技術においてきわめて重要な存在である「行列」,関数の性質を扱う「微分積分」,統計処理の基礎となる「確率」といった各単元をコンパクトにまとめた。
2章は「CG・ゲームのための数学」と題して,おもにベクトルや行列についての理論を学んでいく。さまざまなメディア処理の中でも,3次元のグラフィックスは最も数学が活躍する分野の一つであり,その主役となるのがベクトルや行列を扱う「線形代数学」という分野である。線形代数学はきわめて有用な理論体系であるが,抽象性が高すぎて初学者にとって理解が困難な分野でもある。2章では,具体的な利用方法をつねに意識しながら学習を進めていくことで,その有用性を実感できることを期待して執筆を進めた。
3章は「音声音響信号処理のための数学」と題して,「フーリエ級数」という概念を中心に学んでいく。音の正体は空気振動の波であるため,波を扱う数学としての三角関数が基本となり,その組合せを理論的に扱うフーリエ級数やフーリエ変換が不可欠である。しかしながら,そのハードルは決して低いものではない。3章は,高度な音声音響処理の基盤となる数学理論をまとめたものである。
4章は「人間社会モデルのための数学」と題し,グラフ理論を基本とした理論を学ぶ。グラフとは,複数の頂点と頂点同士を接続した辺による模式図であり,さまざまな問題解決に応用することができる。高校数学まではほとんど扱われてこなかった内容であるが,さまざまな場面で問題解決に役立つものである。
本書を通じて,数学がいかに有用で重要なものであるかを読者が実感することを願っている。
2025年9月
著者を代表して渡辺大地
1.数学の基礎
1.1 集合と論理
1.1.1 集合
1.1.2 論理
1.2 数と式
1.2.1 自然数,整数,有理数,実数,複素数
1.2.2 複素平面
1.2.3 多項式
1.3 初等関数
1.3.1 関数
1.3.2 指数関数
1.3.3 対数関数
1.3.4 度数法と弧度法
1.3.5 三角関数
1.3.6 三角関数の加法定理
1.3.7 極形式
1.4 ベクトル
1.4.1 ベクトルの定義
1.4.2 ベクトルの演算
1.4.3 ベクトルの長さ
1.4.4 行ベクトルと列ベクトル
1.5 行列
1.5.1 行列の定義
1.5.2 行列とベクトルの積
1.5.3 行列と実数の積
1.5.4 行列同士の演算
1.5.5 行列の表記方法
1.5.6 各種演算の交換法則
1.5.7 単位行列と零行列
1.5.8 行列式と逆行列
1.5.9 行列と連立方程式
1.5.10 逆行列の利用
1.5.11 非正則行列の場合
1.5.12 行列の転置
1.6 微分と積分
1.6.1 微分
1.6.2 積分
1.7 確率
演習問題
2.CG・ゲームのための数学
2.1 ベクトルによる線分表現
2.1.1 点と座標系
2.1.2 位置ベクトルと方向ベクトル
2.1.3 直線と線分
2.1.4 直線の解析学的表現
2.1.5 ベクトルを用いた線分の表現
2.1.6 線分表現式の応用
2.1.7 線分同士の交点
2.2 ベクトル同士の掛け算
2.2.1 ベクトルの内積
2.2.2 内積演算の法則
2.2.3 ベクトルの前後関係と内積
2.2.4 ベクトルの外積
2.2.5 外積の正弦定理
2.2.6 外積演算の法則
2.2.7 ベクトルの左右関係と外積
2.3 領域内外判定
2.3.1 多角形(ポリゴン)と折れ線(ポリライン)
2.3.2 三角形内部の表現方法
2.3.3 一般的な三角形の領域表現
2.3.4 ベクトルの線形独立と線形従属
2.4 行列と線形変換
2.4.1 拡大・縮小変換
2.4.2 行列による回転移動
2.5 同次座標による線形変換の拡張
2.5.1 線形変換の限界とアフィン変換
2.5.2 同次座標
2.5.3 3行3列の行列
2.5.4 線形変換による平行移動
2.5.5 同次座標に対応した拡大縮小と回転
2.6 合成変換とその応用
2.6.1 二つの連立方程式と行列積
2.6.2 任意位置での図形回転
2.6.3 行列による任意位置図形回転
2.6.4 合成変換の利用
2.7 3次元空間での線形変換
2.7.1 4行4列行列
2.7.2 平行移動変換と拡大縮小変換
2.7.3 回転変換
2.7.4 回転変換の非可換性
演習問題
3.音声音響信号処理のための数学
3.1 単振動
3.2 フーリエ級数展開
3.2.1 奇関数・偶関数の積分
3.2.2 三角関数の直交性
3.2.3 フーリエ級数展開
3.3 複素形のフーリエ級数展開
3.3.1 テイラー展開
3.3.2 オイラーの公式
3.3.3 複素フーリエ級数と複素フーリエ係数
3.3.4 複素指数関数の微分と積分
3.3.5 複素フーリエ係数の計算例
3.4 フーリエ変換
3.4.1 フーリエ変換
3.4.2 フーリエ逆変換
3.5 スペクトログラム
3.5.1 スペクトル
3.5.2 スペクトログラム
演習問題
4.人間社会モデルのための数学
4.1 グラフとネットワーク
4.1.1 グラフ理論の成り立ちと表記法
4.1.2 さまざまなグラフ
4.1.3 グラフの周遊路と最短経路問題
4.1.4 ネットワークと最大フロー問題
4.2 線形関数で表される最適化
4.2.1 線形関数による表現
4.2.2 線形計画法
4.2.3 誤差最小化と最小二乗法
4.3 組合せ最適化
4.3.1 ナップザック問題
4.3.2 厳密解法と近似解法
4.3.3 巡回セールスマン問題
4.3.4 組合せ最適化問題のメタヒューリスティクス
4.4 ゲーム理論
4.4.1 ゲーム理論とは
4.4.2 囚人のジレンマ
4.4.3 ナッシュ均衡
4.4.4 混合戦略
演習問題
引用・参考文献
演習問題解答
索引
読者モニターレビュー【 N/M 様 (専門分野:総合情報学(情報科学))】
本書は,「メディア学大系シリーズ」(全19巻)の16巻目に位置する書籍である.本巻では,CGやゲーム制作,音声・音響信号処理など,メディアにおける現象を数式で表すために必要な数学的な知識についての記述がなされている.
まず,私自身,数学が[まえがき]にも記述されている『どんなことに利用できるのか』という部分が,まさしく重要だと感じた.その上,私自身,どちらかといえば数学(数式での記述および読み解き)に苦手意識があった.
本書は,2章では,ベクトル,行列を扱う線形代数学,3章では,微分積分(解析学),4章ではグラフ理論・ゲーム理論などの数学及び,その他の分野についての記述がなされている.
1章,4章,2章・・・の順で拝読させていただいたが,1章では,分野を限定せず数学概論といった内容で簡潔にまとめられている.
2章では,CG・ゲーム制作を行う際に必要となる線形代数についての記述がなされている.例えば,ベクトルの内積は,光線が面に当たるかどうかの判定や物体同士の衝突判定など,ゲームでお馴染みの物理現象の裏側はこのように実装されていたのか,という新たな発見が得られて大変興味深かった.
4章では,私自身,本書と同じコロナ社から発行されている『情報科学のための離散数学』(Ref: https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339023299/)を学生時代に教科書として指定されていたこともあり,既知の内容も多く,復習として拝読させていただいた.
我々が暮らす日常生活(人間社会)に数学が役に立っているモデルの例として,グラフ理論,ゲーム理論などが取り上げられている.グラフ理論の始まりの「オイラー小道」(一筆書きの問題,オイラー路の問題)は上記に挙げた書籍でも紹介されており,改めて興味深い内容だった.
他にも,学生時代に理解に苦労した,線形計画法,最大流問題などについて,改めて考えるきっかけにもなった.
それに加えて,ゲーム理論では,囚人のジレンマ問題が一般教養として論理学で紹介されていた記憶がある以外は,全く知らなかった分野・理論であったため,こちらも興味深かった(「ゲーム理論」という名前から,本書にも記述されているように,当初はゲーム制作に必要な各種理論なのかと最初は思っていた・・・).古典的なゲームのじゃんけん(グリコじゃんけん)での利得・混合戦略,経済活動でのナッシュ均衡の概念など,日常生活に直結するような例が挙げられており,身近に感じ取ることができるだろうと思われる.
最後に,本書で数学的なものの見方(数式)に慣れた後に,次の17巻目に位置づけられている書籍『メディアのための物理 - コンテンツ制作に使える理論と実践 -』(Ref: https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339027983/)が,物理現象を数式で表すメディアのための物理学が扱われているようで,内容的にも連続性があり良いように思われる.私自身,物理学も「数学の延長で難解な数式が多く難しい」という印象しかないが,本書をきっかけに拝読しようかと検討している次第である.
読者モニターレビュー【 松岡 大輔 様(業界・専門分野:プログラマ)】
ひとつの典型的な光景として、勉強に疲れた中高生が「数学なんてなんの役に立つんだよ」と嘆いて教科書を投げ出すというものがある。それは日本の教育制度では科目間での依存をできる限りなくすように設計されているためであるという。あえてなんの役に立つかわからないような形で教えているのである。それに対して、本書は「数学がどんなことに利用できるか」という観点から書かれている。数学の抽象性と現象の具体性を結びつけることで、数学の導入としての新しい切り口を提示しているといえるだろう。
具体的には、2章で線形代数、特に線形変換とグラフィック表現の関係が説明され、3章でフーリエ級数展開やフーリエ変換と音声音響信号処理の関係が解説される。視覚と聴覚という代表的な二つの感覚的現象を数学によってどのように記述するか、さらにいえば、数学的にそのような現象をどのように生成するか、という観点から、基礎的な理論が丁寧に説明されている。
個人的な関心に引き寄せると、私はプログラミングによってグラフィックや音響を生成するジェネラティブアートというジャンルに関心がある。昨今ずいぶん環境が整備されて使いやすくなっているが、その反面、ツールやライブラリで背景の数理は隠蔽されていることも多い。より多様で自由な表現のために数理の理解は欠かせないのだが、基礎となる数学をわかりやすく教える文献はあまりないと思う。こういったジャンルに適用できる数学への導入としても、本書は面白い位置づけになるのではないかと思う。
そして、本書の野心は、グラフィック表現と音声音響信号処理にとどまらず、広く社会現象一般を数学を通して記述し、理解するというアプローチに踏み込む4章だろう。ここには本書が連なる「メディア学体系」シリーズの広範な視野と射程が表れている。数学による現象のモデル化とは、数学を媒介・手段とした人間と現象との間の知的コミュニケーションであり、これこそまさに本書の依拠する「メディア」の定義である。
実際のグラフィック表現や音声音響信号処理では、現象と数学の間に、ツールやプログラミングなどの層が介在して、それらの層がユーザーインタフェースを形作っていることも多いだろうけれども、原理原則に立ち返ると、線形代数やフーリエ変換と現象の間には直接の対応関係がある。そこに目を向ける視点を醸成して、さらなるメディアの数理の探求に向かう導入として、本書は興味深い立ち位置にあるといえるのではないだろうか。
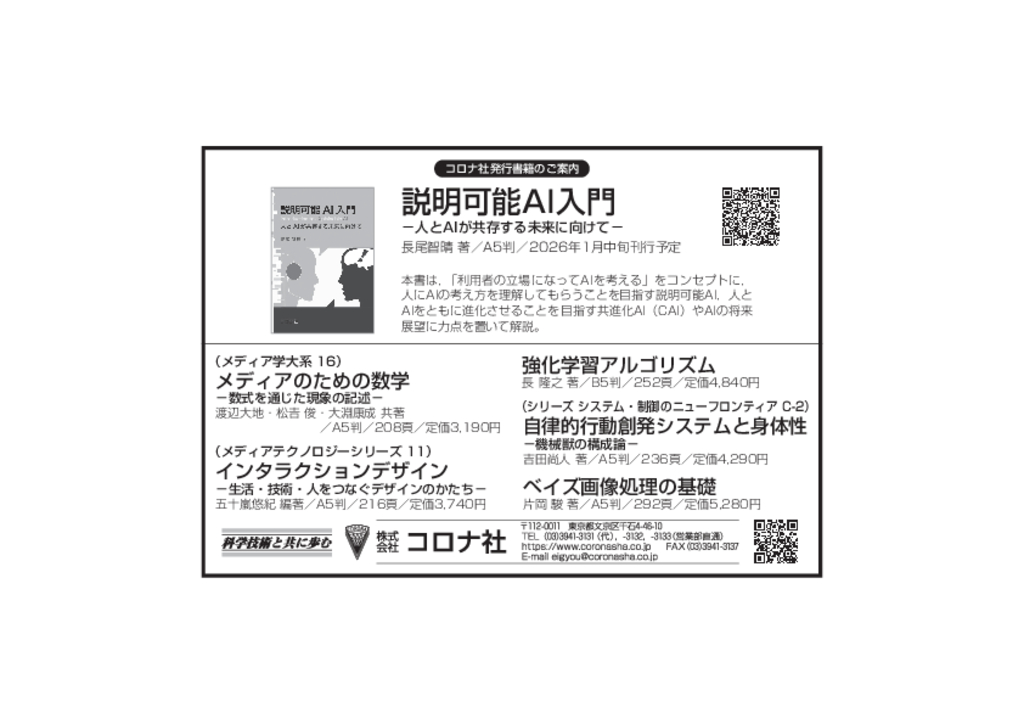
-
掲載日:2026/01/01
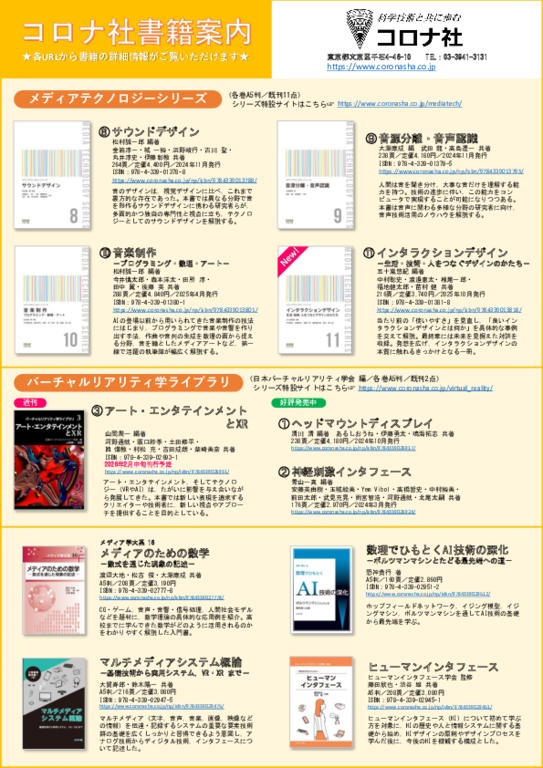
-
掲載日:2025/12/31
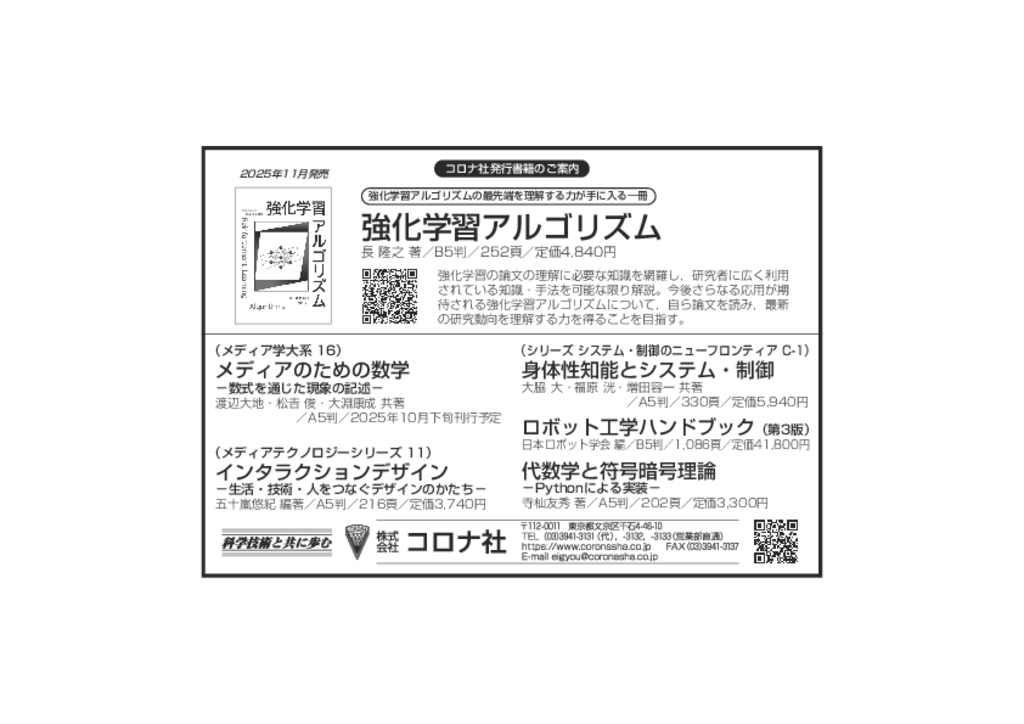
-
掲載日:2025/11/01