レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
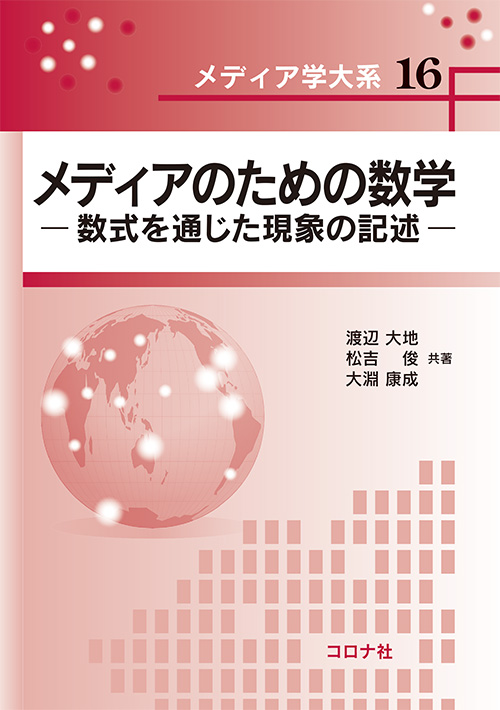
-
メディア学大系 16
CG・ゲーム,音声・音響・信号処理,人間社会モデルなどを題材に,数学理論の具体的な応用例を紹介。高校までに学んできた数学がどのように活用されるのかをわかりやすく解説した入門書。数学の実用性と魅力を再発見できる1冊。
- 発行年月日
- 2025/11/28
- 定価
- 3,190円(本体2,900円+税)
- ISBN
- 978-4-339-02777-8
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 N/M 様 (専門分野:総合情報学(情報科学))】
掲載日:2025/12/02
本書は,「メディア学大系シリーズ」(全19巻)の16巻目に位置する書籍である.本巻では,CGやゲーム制作,音声・音響信号処理など,メディアにおける現象を数式で表すために必要な数学的な知識についての記述がなされている.
まず,私自身,数学が[まえがき]にも記述されている『どんなことに利用できるのか』という部分が,まさしく重要だと感じた.その上,私自身,どちらかといえば数学(数式での記述および読み解き)に苦手意識があった.
本書は,2章では,ベクトル,行列を扱う線形代数学,3章では,微分積分(解析学),4章ではグラフ理論・ゲーム理論などの数学及び,その他の分野についての記述がなされている.
1章,4章,2章・・・の順で拝読させていただいたが,1章では,分野を限定せず数学概論といった内容で簡潔にまとめられている.
2章では,CG・ゲーム制作を行う際に必要となる線形代数についての記述がなされている.例えば,ベクトルの内積は,光線が面に当たるかどうかの判定や物体同士の衝突判定など,ゲームでお馴染みの物理現象の裏側はこのように実装されていたのか,という新たな発見が得られて大変興味深かった.
4章では,私自身,本書と同じコロナ社から発行されている『情報科学のための離散数学』(Ref: https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339023299/)を学生時代に教科書として指定されていたこともあり,既知の内容も多く,復習として拝読させていただいた.
我々が暮らす日常生活(人間社会)に数学が役に立っているモデルの例として,グラフ理論,ゲーム理論などが取り上げられている.グラフ理論の始まりの「オイラー小道」(一筆書きの問題,オイラー路の問題)は上記に挙げた書籍でも紹介されており,改めて興味深い内容だった.
他にも,学生時代に理解に苦労した,線形計画法,最大流問題などについて,改めて考えるきっかけにもなった.
それに加えて,ゲーム理論では,囚人のジレンマ問題が一般教養として論理学で紹介されていた記憶がある以外は,全く知らなかった分野・理論であったため,こちらも興味深かった(「ゲーム理論」という名前から,本書にも記述されているように,当初はゲーム制作に必要な各種理論なのかと最初は思っていた・・・).古典的なゲームのじゃんけん(グリコじゃんけん)での利得・混合戦略,経済活動でのナッシュ均衡の概念など,日常生活に直結するような例が挙げられており,身近に感じ取ることができるだろうと思われる.
最後に,本書で数学的なものの見方(数式)に慣れた後に,次の17巻目に位置づけられている書籍『メディアのための物理 - コンテンツ制作に使える理論と実践 -』(Ref: https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339027983/)が,物理現象を数式で表すメディアのための物理学が扱われているようで,内容的にも連続性があり良いように思われる.私自身,物理学も「数学の延長で難解な数式が多く難しい」という印象しかないが,本書をきっかけに拝読しようかと検討している次第である.
-
読者モニターレビュー【 松岡 大輔 様(業界・専門分野:プログラマ)】
掲載日:2025/11/25
ひとつの典型的な光景として、勉強に疲れた中高生が「数学なんてなんの役に立つんだよ」と嘆いて教科書を投げ出すというものがある。それは日本の教育制度では科目間での依存をできる限りなくすように設計されているためであるという。あえてなんの役に立つかわからないような形で教えているのである。それに対して、本書は「数学がどんなことに利用できるか」という観点から書かれている。数学の抽象性と現象の具体性を結びつけることで、数学の導入としての新しい切り口を提示しているといえるだろう。
具体的には、2章で線形代数、特に線形変換とグラフィック表現の関係が説明され、3章でフーリエ級数展開やフーリエ変換と音声音響信号処理の関係が解説される。視覚と聴覚という代表的な二つの感覚的現象を数学によってどのように記述するか、さらにいえば、数学的にそのような現象をどのように生成するか、という観点から、基礎的な理論が丁寧に説明されている。
個人的な関心に引き寄せると、私はプログラミングによってグラフィックや音響を生成するジェネラティブアートというジャンルに関心がある。昨今ずいぶん環境が整備されて使いやすくなっているが、その反面、ツールやライブラリで背景の数理は隠蔽されていることも多い。より多様で自由な表現のために数理の理解は欠かせないのだが、基礎となる数学をわかりやすく教える文献はあまりないと思う。こういったジャンルに適用できる数学への導入としても、本書は面白い位置づけになるのではないかと思う。
そして、本書の野心は、グラフィック表現と音声音響信号処理にとどまらず、広く社会現象一般を数学を通して記述し、理解するというアプローチに踏み込む4章だろう。ここには本書が連なる「メディア学体系」シリーズの広範な視野と射程が表れている。数学による現象のモデル化とは、数学を媒介・手段とした人間と現象との間の知的コミュニケーションであり、これこそまさに本書の依拠する「メディア」の定義である。
実際のグラフィック表現や音声音響信号処理では、現象と数学の間に、ツールやプログラミングなどの層が介在して、それらの層がユーザーインタフェースを形作っていることも多いだろうけれども、原理原則に立ち返ると、線形代数やフーリエ変換と現象の間には直接の対応関係がある。そこに目を向ける視点を醸成して、さらなるメディアの数理の探求に向かう導入として、本書は興味深い立ち位置にあるといえるのではないだろうか。









