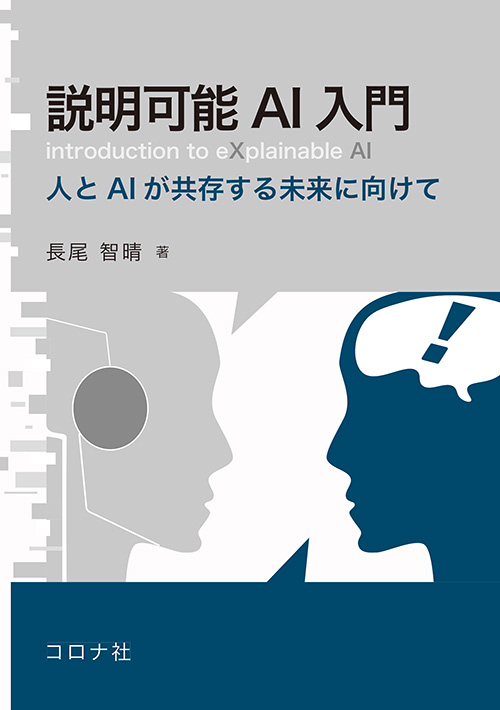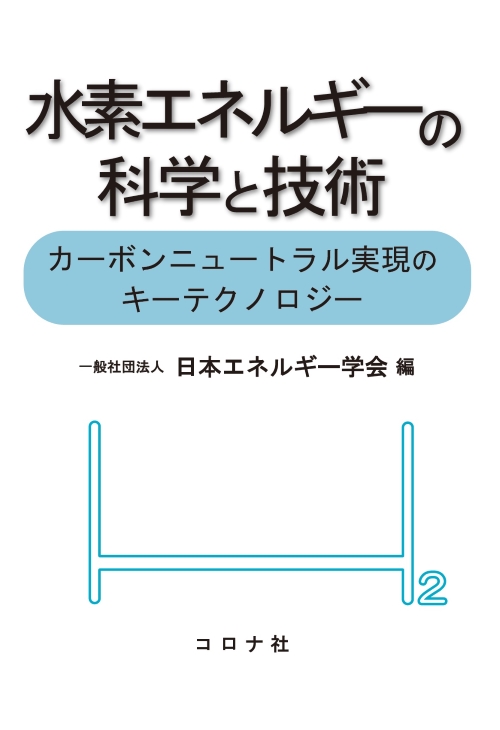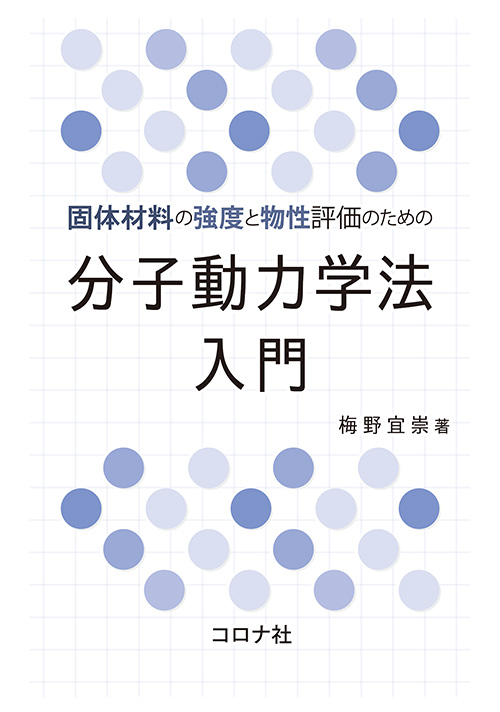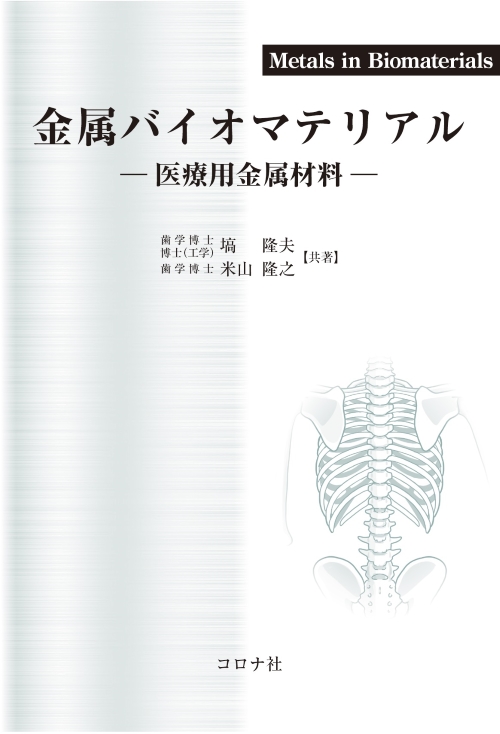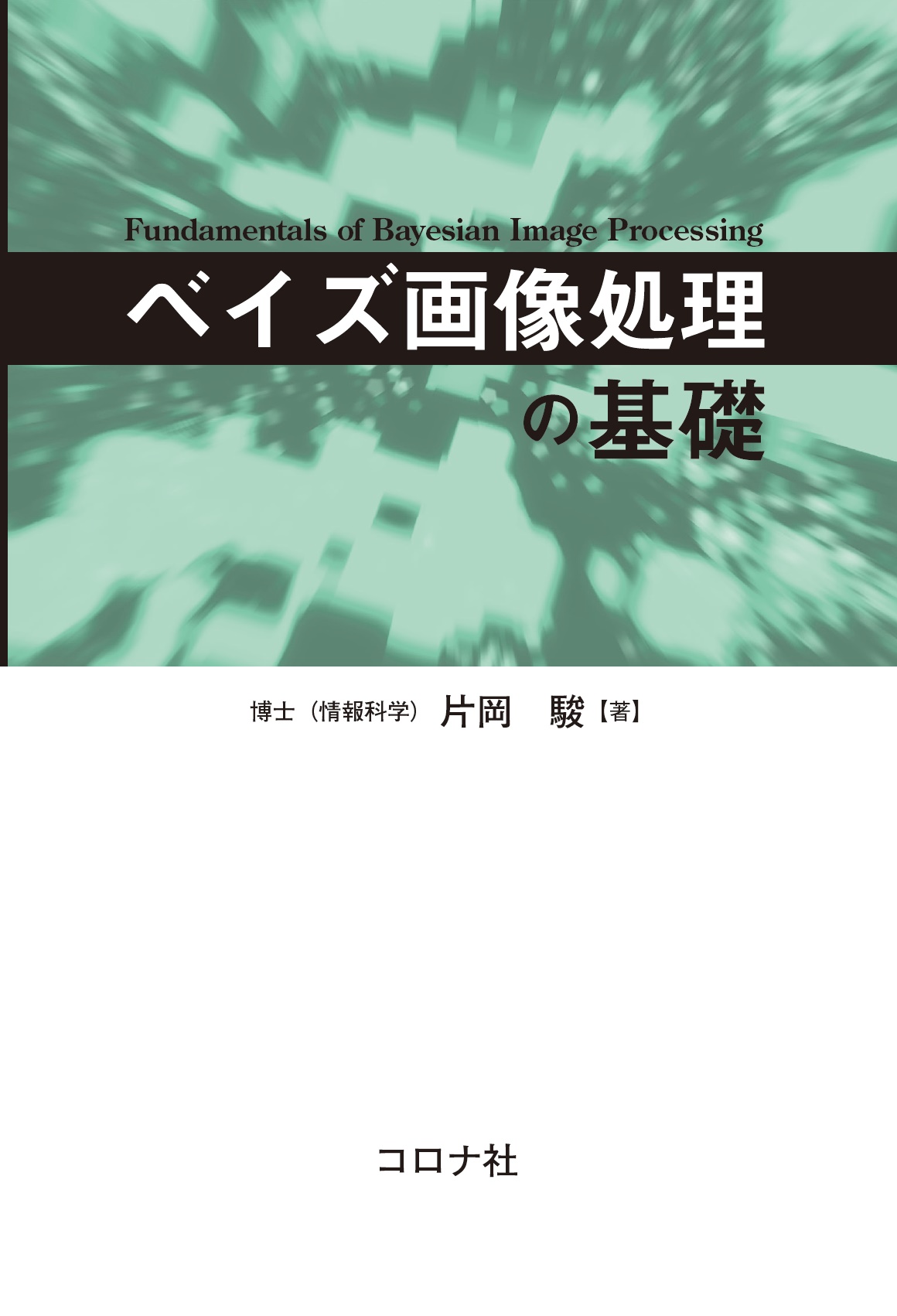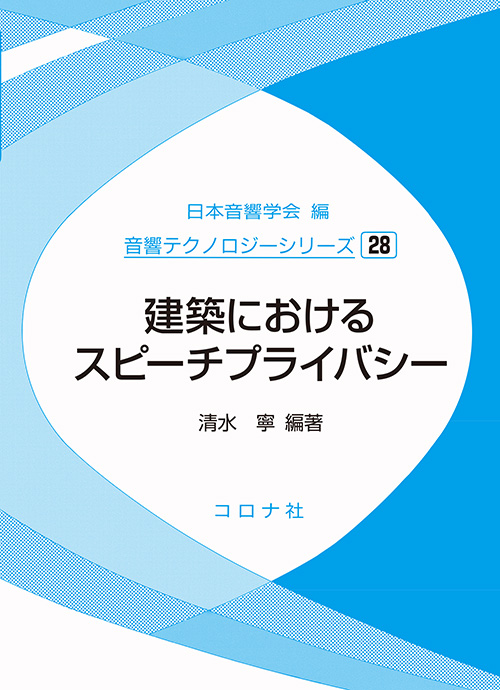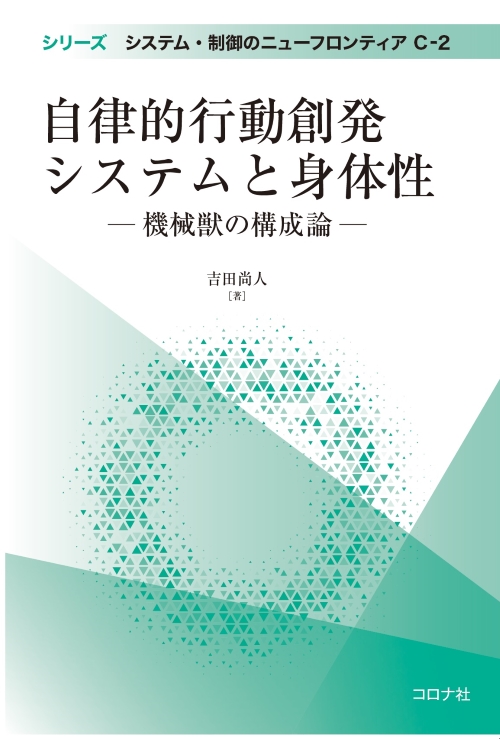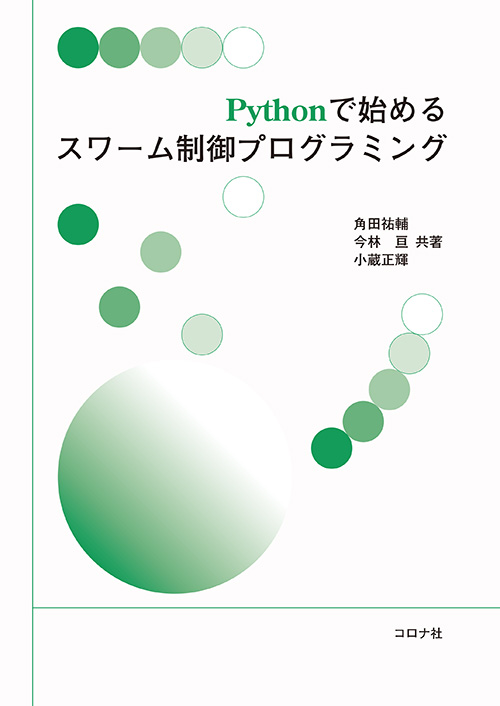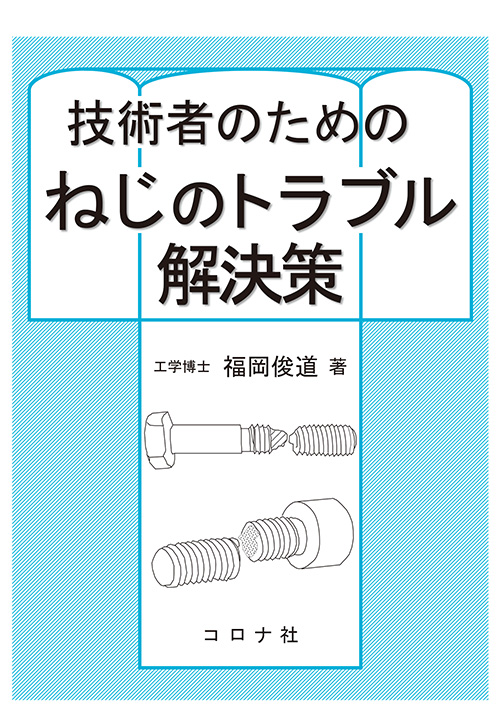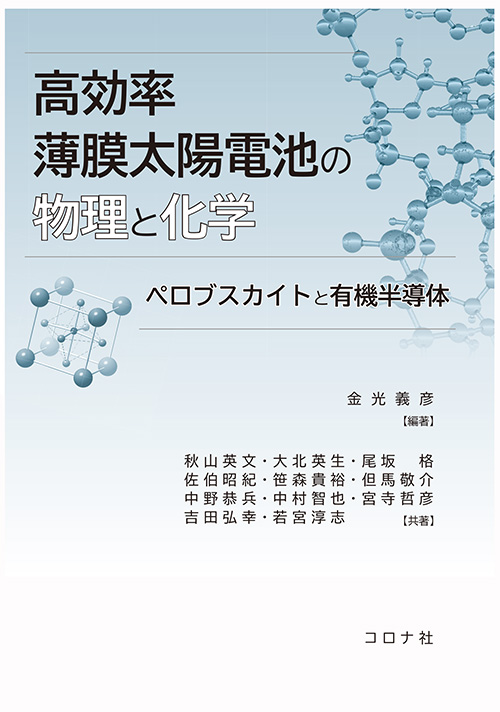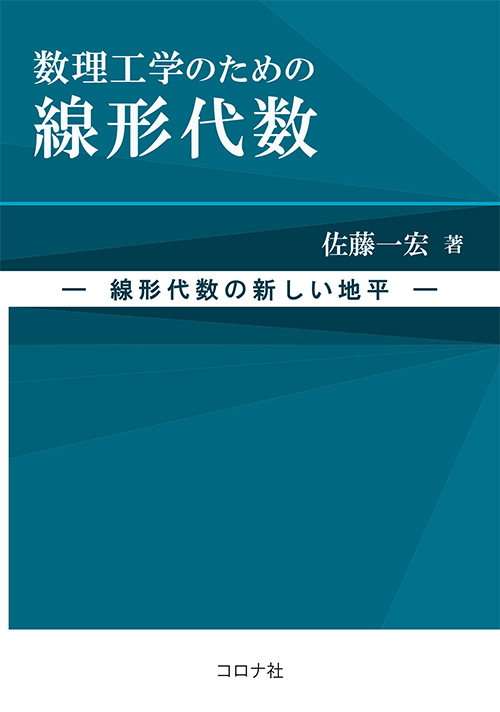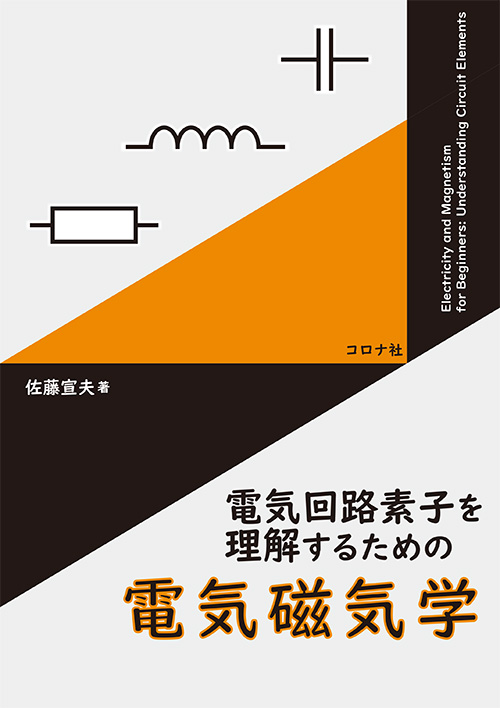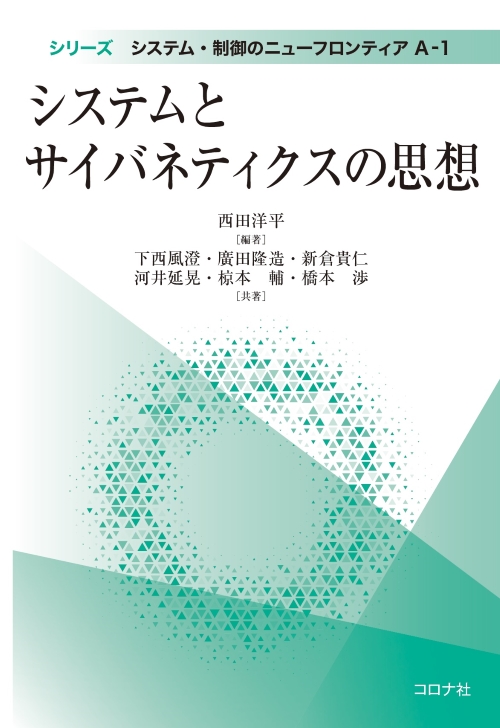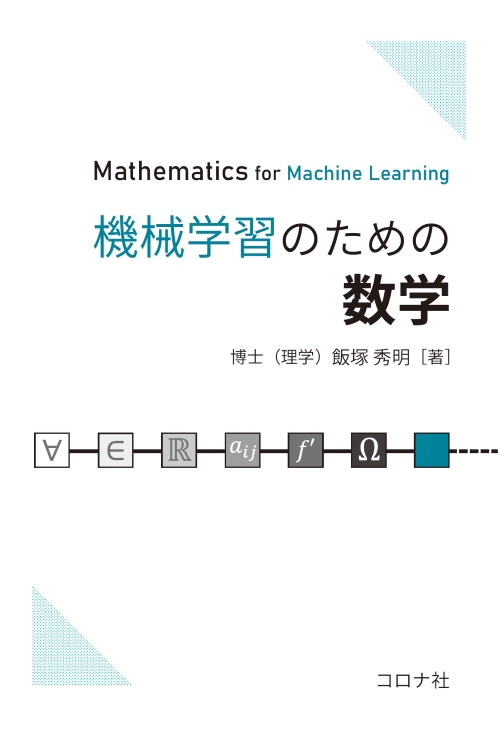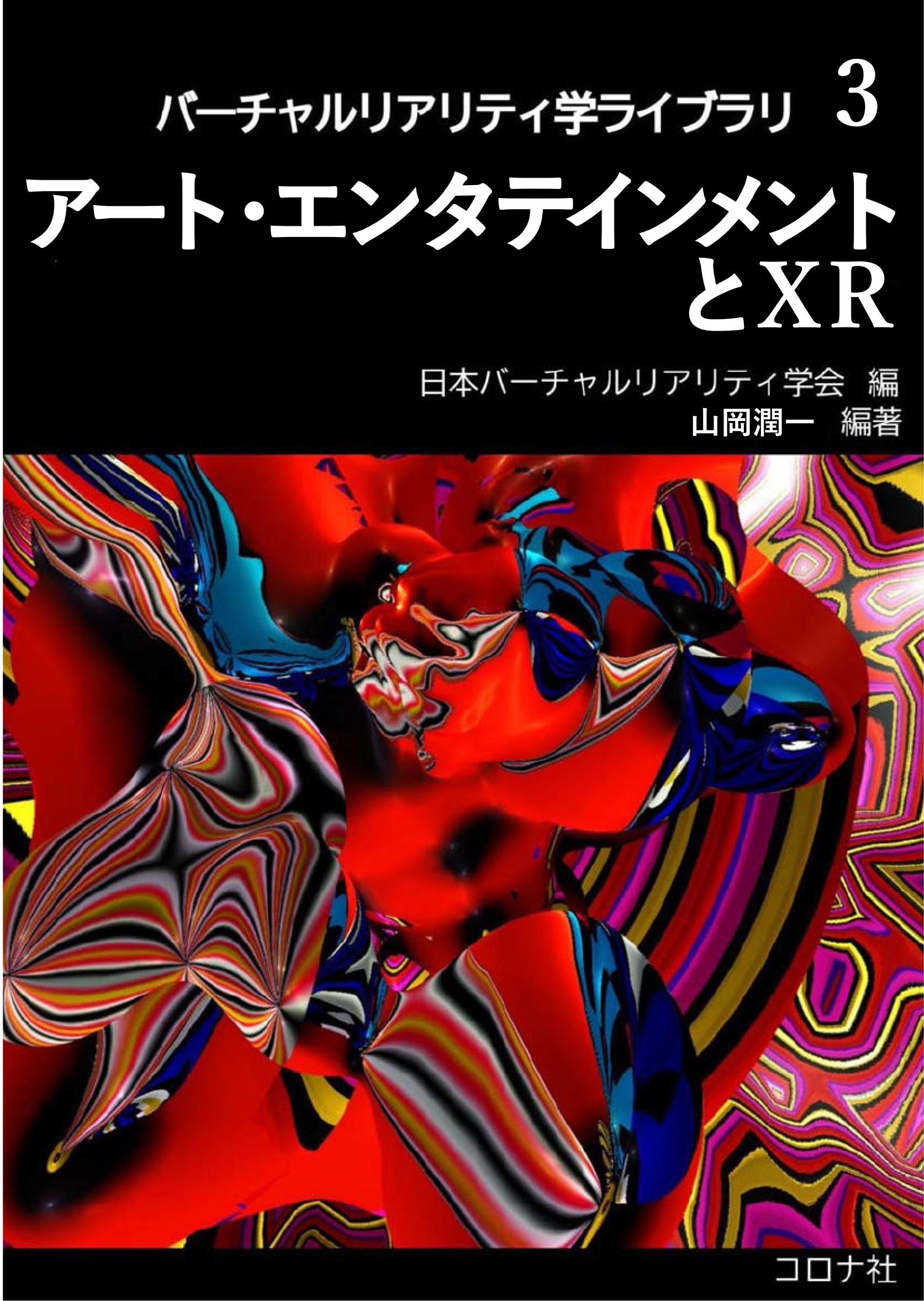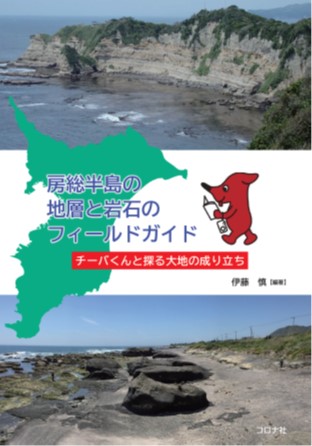書店様向け
書店様向け情報ご案内ページです。
書店様向けレビュー
生産加工・工作機械学
本書は、機械工学における主要学問分野の一つである、機械工作法・生産加工学のうちで、大量高速高能率生産、多品種少量(高品質)生産、試作や機械部品・機械要素の修理修復など一点モノの製作、あるいは他の生産技術である塑性加工(鍛造)や射出成形・鋳造などにおいて必須である金型の製作のいずれでもコアな技術であるという点で、最も重要な生産技術(除去加工)である切削加工を中心として、その周辺技術としての(切削型)工作機械、CAM、生産システム、研削研磨についても扱われている一冊になります。ふた昔前くらいまでは主にコンピュータの性能や価格、使いにくさの問題から、実験的な切削加工に関する研究開発とコンピュータを駆使した(CAD/CAE/)CAM・シミュレーション技術に関する研究開発との分断が大きかったようですが、近年のコンピュータの爆発的な高性能化と低価格化による普及、社会全体のコンピュータリテラシー向上もあって1研究室・研究チーム(あるいは個人)レベルで実験とシミュレーションそれぞれのアプローチを突き合わせることが可能になってきたようですが、そんな現代的な事情が反映された機械工作法・生産加工学のテキストといえそうです。
機械工作法・生産加工学についての科目は、機械工学がメカトロやVR技術などにも裾野を広げ続けている中にあって、ふた昔前よりかはどこの大学・高専等教育研究機関でも減らされている傾向にあるらしいですが、その中でも半期2セメスター四半期4ターム程度は機械工作法・生産加工学関連科目を設けられ得るとして、本書を主に用いる講義科目の前に、出来れば難しい数学や物理学の素養を必ずしも前提としない知識としての機械工作法・生産加工学に関する科目として、例えば「機械工作法(増補)(機械系 教科書シリーズ 3)」(平井 三友・和田 任弘・塚本 晃久 著、コロナ社)や「はじめての生産加工学1 基本加工技術編」(帯川 利之・笹原 弘之 編著、講談社)などを主なテキストとして用いた科目が事前に半期1セメスターあるいは四半期2タームくらいの時間で開講されていると、本書で網羅できていない溶接(あるいはその現在進行形の発展形である積層造形(Additive Manufacturing,AM)技術)、鋳造、鍛造(塑性加工)、射出成形などをカバーできて良いかもしれません。
上述の事情や、機械力学(振動学)、伝熱(工)学、制御工学といった他の機械系主要科目を事前に学んでおいた方が理解がスムーズな箇所が少なくない、という意味では、本書は学部3年次学生向けの授業用テキストを主な使途として編纂されたとのことですが、本書ベースの講義を開講するとしたら3年次後期(第2セメスター、第3・4ターム)くらいが妥当かなとは思います。そのような事情もあるので、無理に学部での講義で本書レベルの内容を教授しようとせず、大学院博士前期(修士)課程の生産加工・工作機械学特論とでも言えそうな授業科目用テキストとしても通用し得ると思います。その場合は必ずしも機械系学科出身者だけでなく、振動・波動論や制御工学くらいは学部で習得している可能性のある電気電子系・情報系・化学工学系あるいは(理論系はともかく)実験系では実験装置の設計製作運用に当たって高度に工学の素養が求められる理学系などの学生に門戸を広げても良さそうです。
あとは各章末の演習問題や例題では、十数年くらい前のものですが過去の院試(おそらく修士課程)の過去問ベースの問題が幾つも挙げられているので、いわゆる院試(修士課程だけでなく博士課程でも)対策でも有用な可能性があります(もっとも、近年の院試は数学+機械系専門科目(いわゆる4力(材料力学・熱力学・機械力学(振動学)・流体力学)+制御工学の中から幾つか選択)+英語の外部試験スコア(TOEICなど)提出+口頭試問、といった具合に筆記試験の(専門科目)選択の幅が狭まっている大学も少なくないと聞くので、機械工作法・生産加工学に準ずる科目で院試を受けられる大学院はあまり多くないかもしれませんが)。
本書で事実上扱われていない放電加工、レーザー加工、AM技術などについては「はじめての生産加工学2 応用加工技術編」(帯川 利之・笹原 弘之 編著、講談社)などで言及があるので、もし各生産技術についてより網羅的な講義が求められる場合にはそちらを副読本・参考図書に加えても良いかもしれません。
説明可能AI入門 - 人とAIが共存する未来に向けて -
本書籍は、非常に分かりやすく丁寧に書かれておりました。
私個人のおすすめとしては、AIをこれから仕事に使う方への導入本として非常に最適だと思います。
本書籍は多彩なイラストで、分かりやすく記載されています。内容も浅くなく実用的な考え方が記載されており、「AIにはどういうものがあって、それぞれどう作られており、どういったものが得意で課題を持ち合わせているか」という内容がしっかり書かれていると思います。
私自身なんとなくAIが分かるレベルでしたが、本書籍で単語や考え方を学ばせて頂き、非常に有意義な書籍だと思います。
水素エネルギーの科学と技術 - カーボンニュートラル実現のキーテクノロジー -
水素そのものの特性に始まり、製造・分離プロセス、貯蔵・輸送方式、利用技術と一連の流れがつながって理解できます。各技術に対してエネルギーを軸とした定量的な議論がなされており、設計や評価の観点で「どこを見るべきか」が参考になりました。他の書籍と比べて引用・参考文献が多く、記載事項の詳細調査がしやすいのも特徴です。個人的に水素を取り巻く話題は多い一方で、情報が分散していて全体像をつかみにくい印象を受けていました。そんな中、約250ページの中に網羅的にまとめられており、専門外の方の入門にも、専門家の整理にも役立つ書籍です。
説明可能AI入門 - 人とAIが共存する未来に向けて -
AIをツールとして用いる学生や,特に社会人にとっては,深層回路などの学習器がどのような処理をしたのか,を知ることは非常に重要であろう.本書では,AIの判断根拠などを示す手法である説明可能AI(XAI)や人とAIを共に進化させる共進化AI(CAI)について述べられており,これらの内容に関して知見を広めたいと考えている人たちに是非推薦したい一冊である.また,まえがきに記述のある通り,AIの説明性を理解すると同時に,AIの入門書としても適している書籍である.数式よりも,図などを用いた説明に重点が置かれており,内容も理解しやすいと思われる.XAIについて知りたい人のみならず,AIに関して知りたいと思う人にもお勧めしたい一冊である.
本書の大きな特徴は次の二点である.一つ目の特徴は,理解を深めやすい章構成である.まず第一章では,人工知能の概要から説明が始まる.複雑な数式を用いることなく,パーセプトロンから近年のトレンドとなっている手法までのアプローチの変遷や,AIの課題などが述べられる.その後,従来の機械学習手法やAIに関する説明を経てXAIなどの内容が始まるため,理解を深めることができる.本書を通して読むことで,AIなど機械学習の内容から,XAIの考え方,実用面や今後の展望まで広い知見を得られるであろう.二点目は,生成AIや大規模言語モデルなど,近年のトレンドとなっている内容にまで触れられている点である.生成AIなどは現在開発途上であるが,本書では説明性の観点から,それら手法の注意点が述べられている.他にも,アクティブラーニングなど様々な手法に関して触れられている.これらの内容を取り扱う第四部を読むことで,最近のトレンドである内容に関する知見を深めつつ,説明性という重要な要素を把握できると考えられる.
固体材料の強度と物性評価のための 分子動力学法入門
金属や半導体を含む多様な固体材料を対象に、分子動力学法(MD)を基礎から応用まで体系的に解説しており、大学の入門教材としても社会人のリスキリング教材としても適している。
特に、半導体結晶材料の強度評価や欠陥・破壊挙動の捉え方など、実務の課題に直結しやすい観点で整理されている点が有用である。
さらに、Pythonを用いたシミュレーション例が掲載されているため、理論理解に留まらず手を動かしながら学習を進められ、再現性の高い学びにつながる。
加えて、量子力学と併せて学ぶことで、原子間相互作用や材料物性の背景理解が深まり、より立体的に内容を吸収できると考える。
金属バイオマテリアル - 医療用金属材料 -
本書では医療に使用する金属材料を用途毎に細かい解説を加えて解説しており、医学・歯学系および材料工学系の学生のどちらにもとっても非常に有益なわかりやすい教科書である。特に序盤で臨床応用例と課題が具体的に提示されているため、その後の章で展開されている材料や機能別の特性の説明が頭に入りやすくなっている。人体と接触して使われるという観点から、金属の腐食に限定せず、疲労や摩耗、トライボロジーといった幅広い使用環境で何が起こるかについての整理もしっかりとされている。毒性評価や金属アレルギー、生体適合性に関する記述では、チタンが硬組織である骨と結合しやすいため、時間が経過し過ぎると取り外すのが難しくなるなど、興味を引くトピックスが多く盛り込まれている。生体適合性を高めるための表面処理・表面形態制御では、ナノメートルサイズの周期的微細構造の研究が今後のトレンドとのことであり、未来技術の方向性についても知ることができた。
最後に、本書の大きな特徴の一つに金属材料の機械的性質と腐食を簡潔にまとめた付録を挙げることができる。30頁にわたる付録の中に金属材料学のエッセンスが凝縮されており、金属材料を短時間で学べる点でも有益であろう。
ベイズ画像処理の基礎
本書は確率モデルがどのように活用されている技術なのかを知りたい人におすすめできる。
1章では、画像処理で使われる手法とそれに必要な数学の知識がわかりやすく説明されており、大学で習った画像処理の復習にぴったりだった。特に数値最適化法の説明では、理論の説明に加えてアルゴリズムの紹介もされているため、深い理解につながった。
7章では、グラフ表現を用いた具体例が出てきて、確率伝搬法の計算がどのように進むのかがよくわかった。付録には導出過程も掲載されているのも便利でよい。
題名にあるベイズ画像処理は8章で登場する。ここまでに必要となる予備知識は、線形代数、微分積分、統計学といった基礎的な数学だ。確率モデルの前提知識となる最尤法などの統計的推定に関する知識があると、さらに読みやすいだろう。すでに情報理論を学んだ人にとっては、グラフ理論を通して新たな視点から見直す際にも役立つ一冊だと感じた。
説明可能AI入門 - 人とAIが共存する未来に向けて -
世の中の多くの人は、「銀行のATMがどのようなしくみで動いているのか」を理解しなくても、引き出したい金額(入力)と出てきた現金(出力)が合っていれば特に困りません。しかし銀行員の立場で考えると話が変わってきます。銀行員にとってはお金の出入りが1円でもずれてしまったら大問題ですから、ATMが「どのような処理をしているのか」「正当な手続きを経て処理が行われているのか」が明確に確認できないと困ってしまいます。
これと同じような図式が、人工知能の世界でも起こっています。世の中の多くの人は「与えた入力に対して、それらしい出力が得られれば良い」と思うかもしれませんが、「なぜその出力に至ったのか」がわからないと困ってしまう人がいるという事です(例えば人工知能がレントゲン写真を見て「ここが悪いから切除すべき」と診断したとしても、なぜその診断に至ったのかという根拠がわからなければ、医師は手術をためらうでしょう)。
本書は、判断過程が人間に理解できる人工知能(説明可能AI)を構築するためのノウハウが集められた本です。現在流行しているディープニューラルネットワーク(DNN)は強力な性能で目覚ましい成果を挙げている反面、原理上どうしても内部の挙動がブラックボックスになりがちです。そのためこの本はまず、DNNだけではない様々な人工知能アルゴリズムについて概要を解説した後「(DNNではない)中身の分かりやすい人工知能アルゴリズムが使えないか検討する」「性能を保ったままできるだけ構造のシンプルなアルゴリズムを構築する」「どうしてもDNNが必要な時に、ブラックボックスを紐解くためのツールを使う」という流れで説明可能AIを構築する手法を解説してくれます。説明可能AIに関心がある人だけでなく、人工知能をチューンアップして軽量高速にしたい人にも役立つ内容がたくさん含まれている本です。
また大きな特徴として、それぞれのアルゴリズムを説明する図が素晴らしく良くできています。言葉だけではわかりにくい処理のイメージを、的確な図でわかりやすくしめしてくれています。
注意点として、本書は様々なノウハウを網羅的に紹介している分、各アルゴリズムの詳細については深入りしていません。ある種のカタログとして本書で概要をいったんつかみ、さらに詳しい内容が必要な時は参考文献を追って学んでいくという使い方が良いでしょう。
建築におけるスピーチプライバシー
本書は、プライバシー空間における音響設計を建築設計の中核的テーマとして捉え、理論、評価指標、設計手法を高いレベルで統合した、非常に完成度の高い専門書だと感じました。
近年、オフィスのオープンプラン化や医療施設、金融機関などにおいて、会話内容の秘匿性や心理的安心感が強く求められる一方で、「声がどの程度聞こえるべきか」「どこまで聞こえない状態を目指すのか」といった判断は、設計者の経験や感覚に委ねられてきた側面が大きいと思います。
本書は、その曖昧さを国際規格に基づく客観的な評価軸によって整理し、建築設計における合理的な判断へと導いてくれる点に大きな価値があります。
ISO 3382-3によるオープンプランオフィスの音響評価、ASTM E1130-16に示されるスピーチプライバシーの測定概念、ASTM E2638-10による遮蔽性能の評価方法、さらにISO 22351-1に基づく音声了解度および不明瞭性の考え方が体系的に整理されており、単なる規格解説にとどまらず、それらを設計者がどのように実際の設計に落とし込み、設計判断に活かすべきかという実務的視点で書かれている点が印象的でした。
また、ABCDルール(A:吸音、B:遮断、C:マスキング、D:話者との距離)を軸とした設計指針は、吸音、遮音、天井や内装構成、距離やレイアウトといった建築的操作がスピーチプライバシーの確保にどのように寄与するのかを分かりやすく示しており、建築計画の初期段階から音響を統合的に扱うための有効な思考フレームになっています。
材料選定や間仕切り計画、設備計画を検討する際の判断根拠が明確になり、設計意図を施主や関係者に説明する際の説得力が高まる点も、実務者にとって大きな利点です。一方で、作業妨害感や音声情報漏洩に対する主観的印象は、純粋な音響性能だけでなく、利用者の心理状態、業務内容、人間関係、空間の視覚的要素など、音響以外の主観的要因とも密接に関係していることも事実です。そのため、現行の評価指標だけでは、主観印象のすべてを包含するには限界があると感じました。
今後は、本書で示された音響評価の枠組みを基盤としつつ、日常生活における室内音環境をより総合的に捉える評価手法や、建築設計と人間の認知・心理を結びつけた研究がさらに進展されることを期待いたします。
自律的行動創発システムと身体性 - 機械獣の構成論 -
本書のタイトルを見てAIBOやASIMOのようなロボットについての書籍かな、と思った方もいらっしゃるのではないだろうか。
私もそのような期待を抱き拝読させていただいたが、内容は期待以上のものだった。
本書では特定の目的やタスクを持たない機械獣を作ることを目指し、強化学習に恒常性の概念を加えた手法を展開している。
近年、深層強化学習やLLMの発展が目覚ましく、関連する書籍も多いが、その多くが特定のタスクを達成するためのものであると感じている。
そのためAIBOのように友達ロボットとも言えるようなタスクには、どう適応すれば良いのかイメージが湧かない。
そのような方は、本書を読むことで上のようなロボットへのアプローチの一端が開けるのではないかと思う。
本書は8章で構成されており、前半3章が自律型ロボット/強化学習の基礎事項、後半5章が恒常性を組み込んだ強化学習と機械獣の構成について記述されている。
深層学習や強化学習に詳しくなくても理解できるように記述されているが、事前に学習しておいた方が、4章以降のハイライト部分の理解がはかどると感じる。
4章5章で恒常性を強化学習に適用するための報酬・アーキテクチャが丁寧に説明されており、タスク・目的を特定しないための方法論が理解できる。
5章までの準備基に6,7,8章で機械獣が論じられる。
ここはぜひ読んで体感して欲しいので詳しい内容は述べないが、ロボットに強化学習を適用するための工夫が盛りだくさんで、研究・開発どちらの技術者にも参考になる部分が多い。
本書全体を通して、"なぜこの手法を用いるか"と"妥当性はあるか"が論理立てて説明されており、非常に理解しやすい構成となっている。
私のようにAIBOみたいなロボットに興味がある人だけでなく、強化学習の応用に興味がある方、人工知能系の基礎研究に従事している方など、
幅広い方にお勧めしたい。
自律的行動創発システムと身体性 - 機械獣の構成論 -
システム・制御系の本ということもあり、ロボットを構成する要素の中でも、画像認識やモータ制御について詳細に書かれている。機械獣を扱っている本ため、動物の思考パターンを例として、感覚を受容してから行動に至るまでのプロセスを詳細に描かれている。扱う数式の量は、他のロボット工学系と比較して少なめで、概念の説明などが多い。実際のシミュレーション結果がグラフや写真として載っていて、分かりやすい。深層学習に関する説明はコンパクトにまとめられているため、深層学習に関して詳細に書かれている本と合わせて読むと、より理解が深まる。
Pythonで始めるスワーム制御プログラミング
マルチエージェントシステムや自律分散制御、群知能の応用に興味があり、実装まで踏み込んで学びたい方におすすめの一冊である。
魚や鳥の群れ、蟻の行列など、自然界にはマルチエージェントシステムの典型例が数多く見られる。そして、こうした自然界のマルチエージェントシステムをアナロジーとして、工学分野へ応用する研究が盛んに行われている。最適化の分野では粒子群最適化(PSO)アルゴリズム、ロボット工学の分野ではドローンの群制御などがその代表例である。また、交通工学、電力工学、通信工学といった、自律分散制御の必要性が高まっている分野においても、マルチエージェントシステムの活用が検討されている。
本書は、自然界のマルチエージェントシステムの中でも、羊の群れを誘導する牧羊犬モデルに焦点を当て、その理論と実装について丁寧に解説している。
マルチエージェントシステムを道具として活用したい人にはぜひ読んでほしいと思える、どの工学分野にも応用が利く内容である。
ベイズ画像処理の基礎
本書は,マルコフ確率場 (Markov Random Field; MRF) と呼ばれるグラフィカルモデルの一種を用いた,ベイズ画像処理の基礎についての解説がなされている.
まず私自身,数学的な数式を読み解くことに苦手意識があるため,本書の数式が意味するところの深い理解はできていないように個人的には感じる.そのため,本レビュでは概略的に気になる点を中心に記述させていただく.
1章では,本書の守備範囲である画像処理 (Image Processing) についての概略が記載されており,これらの分野をすでに知っている方への復習という意味合いでの解説がなされている.
2章〜7章では,ベイズ画像処理の専門分野に入る前に前提として必要な知識についての解説がなされている.具体的には,2章ではグラフ理論,3章では数値最適化法(数値解析やオペレーションズ・リサーチ等の分野で扱う手法),4章〜7章では確率・統計の分野より,必要な前提知識についての詳細な解説がなされている.
8章〜11章では,本書のメインテーマであるベイズ画像処理に焦点が当てられ,数学的な理論を基にした詳細な解説がなされている.
ただ,まえがきにもある通り,『時間的問題や分量的な問題により,本書では画像処理の問題としてノイズ除去問題しか扱うことができなかった.ベイズ的扱いについても,半ベイズ的な扱いにとどめ,完全なベイズ的扱いまでを紹介するには至らなかった.マルコフ確率場に基づく画像処理の方法はさまざまな画像処理問題に応用されている.その他の画像処理問題への応用については,巻末の引用・参考文献にその一部を挙げている.』とある.
個人的な希望としては,今回紹介しきれなかったその他の画像処理の問題についても,ぜひ続刊にて詳細な解説がなされることを願っている.本書が『ベイズ画像処理の基礎』という名称であるので,『ベイズ画像処理の応用』のような名称で,兄弟書・姉妹書が出版されることを期待したい.
最後に,学生時代に離散数学の分野でグラフ理論を学んだことがあるが,その理論がベイズ画像処理の分野においても活用されている点について,本書を拝読し驚きと発見があった.数式を完全に追いきれずとも,このように既知の知識と最先端の技術が結びつく面白さを実感できたことが,個人的な一番の収穫であった.
技術者のための ねじのトラブル解決策
本書はねじのトラブルの原因となるゆるみや疲労破壊について著者の過去の経験や技術相談の事例を基に書かれた書籍です。本書の構成はねじの基礎的な事項から始まり、ねじのトラブル原因についての説明へと段階的に移行するようになっていることや、技術者目線に立った文章の書き方や多くの図表をを用いた説明をしているため、機械設計や材料力学の基礎的な知見があれば無理なく読み進めることができます。また、本書で私自身が最もよいと思った内容は第5章から第6章の内容であり、この章ではねじのゆるみと疲労破壊について体系的にまとめられており、その内容や参考文献は設計や不具合発生時の要因分析を行う際に役に立つ情報源になると思います。そのため、機械製品の設計や生産技術に関わる技術者や将来的に設計業務を志す技術者・学生などの幅広い層の読者におすすめする書籍です。
自律的行動創発システムと身体性 - 機械獣の構成論 -
通常のロボットから、生命系の模倣のロボットへ興味を持たれた方や、逆に生命系から無機系での実装としてのロボットへ興味を持たれた方など、既存の単一学術領域から学際領域へのシフトを始めようと思っている方の最初の一冊にオススメで、おおまかなフレームワークや、重要なキーワードを網羅的にチェックできて、次に自分にとって、どの分野・情報が必要になるのかを明らかにしてくれるという点でも、非常に役立つ一冊です。
また、網羅的・大系的な理解をしてから実装することを好むタイプの人よりも、「必要最小限の知識」から【まずは動かしてみたい】、というタイプの人に、特にオススメの一冊です。
非常に多分野に渡る学術融合的な領域を扱う書籍なので、その点がわかるように、まず【はじめに】【用語集】から記述が始まっているのが、ありがたいです。
また、【機械獣】という文字のニュアンスからは人工生命を連想しやすく、倫理的な問題と不可分性があるシビアな領域かと反射的に思いがちですが、本書の対象は、あくまでもホメオスタシスを中心とした構成論的アプローチでの自律型ロボット(オートマタ)に限定されているので、その心配もなく読める点も良いと思います。
ベイズ画像処理の基礎
私の読んだ感想を一文にすると、いい本で難しい本でした。
本書の読書層としては、専門の方、これから専門としていく方に特化して書かれた本だと思います。
ノイズ除去に対するベイズ画像処理および関連の知識について、幅広く且つ、例も混じえて分かりやすく書かれています。
専門の方が、本棚に並べておく1冊としてとてもいい本だと思います。
私は知識の幅を広げるために読んだ読者でして、私のような方がお読みになる時は、1章、5章と8章以降を読んでいただいて、再度1から読むと目的と基礎知識ツールが頭に入りやすいと思うのでオススメです。
自律的行動創発システムと身体性 - 機械獣の構成論 -
本書は身体が環境との相互作用によりもたらされる多様な運動形態を力学やシステム・制御工学に基いて学び、さらに「知能」の意味を見つめ直すことができる良書である。アクチュエータのない受動歩行に始まり、アクチュエータをもつ生体模倣ロボット、四脚ロボット、脚部と体幹部を有するロボット、群れ行動するロボット、などの具体事例が豊富な図・写真で紹介されている。これらが織りなす身体と環境の相互作用によって生み出される「知能」的な行動は複雑なものであるが、本書の丁寧な解説により理解できる。この身体性に基づく知能システムの設計・制御の体系化の指針が与えられ、将来的には大規模言語モデルと身体性との相互作用が重要な役割を持つことが示唆されている。演習問題ではPythonプログラムやWebアプリを参照することにより、可視化された身体性知能の実体験も可能である。約500件にわたる幅広い引用文献は、より深い理解への道案内にもなっている。
ベイズ画像処理の基礎
本書は確率モデルに基づく画像処理の数理的基礎を扱っている。本書における画像処理とは、画像に数値的な計算操作を施して必要な情報を作り出す手続きである。そこでなぜ確率モデルが必要かというと、不確実性が存在するからである。たとえばノイズや類似物体の存在といった不確実性が存在する画像から必要な情報を抽出する際に、確率モデルを用いることで、不確実性を数理的に取り扱うことができる。
さらに、本書のタイトルであるベイズ画像処理とは、上記のような画像処理をベイズ推定の枠組みで考えるということである。つまり、画像処理が与えられた画像から知りたい情報を抽出することであるとすると、それは与えられた画像から知りたい情報を事後分布に基づいて推定することに相当する。
本書は技術的なことよりむしろ数理的な基礎に多くの記述を割いており、大学初年度程度の微積分と線形代数の知識を前提にした初歩的な数学から始めて、段階的に必要な数学を学んでいく構成になっている。ゴールは不確実性のもとでの画像処理の数理である。8章以降、ノイズ除去を事例にしながら、二値画像処理から始めて、8ビット画像、そして最終的に確率変数の実現値を離散値から実数全体に拡張したモデルを提示している。
画像処理という工学的なテーマを扱いながらも、どちらかというと数学書としての面白さの側面もある。たとえば個人的に読んでいて面白かったのは6章である。5章までに学んできた内容をもとに、ここで大きく展開して、確率分布の無向グラフ表現を導入する。つまり、無向グラフの頂点集合と確率分布の確率変数を同一視することで、確率分布をグラフ構造を用いて視覚的に表す、確率的グラフィカルモデルである。そして、マルコフ性の議論を介してイジングモデルが導入される。さらに、マルコフ確率場が無向グラフによる確率分布の表現であるのに対して、確率分布を有向グラフで表現したものがベイジアンネットワークである、という形で展開していく。このあたりの展開の堅実さとすばやさがとても面白かった。
そして、このグラフ理論と画像処理の実装を結ぶのがKL情報量である。これを介してモデルを用いた近似計算を行い、パラメータを収束させるアルゴリズムが、本書で提示されている方法論である。
もちろん、数理の解説自体が目的ではない。本書の目的は数理によるモデル化と計算法である。それを確率分布の無向グラフ表現を軸にした簡潔な数理で、ポイントを絞りながら段階的に構成している。そして、その一連の議論を大学初年度程度の数学知識を前提にして順次的に説き起こしているというあたりが、類書に対する特徴であり、本書の教育書としての姿勢であるだろう。
技術者のための ねじのトラブル解決策
本書は、ねじの基礎的な内容から実務で直面するトラブル対策まで幅広く網羅されており、設計者にとって実用性の高い一冊だと感じました。各章では、図やグラフに加え、FEM解析結果も多用されており、文章だけでは理解しにくい現象も直感的に把握できます。特にグラフは多水準で整理されており、各因子の影響度合いが視覚的に分かりやすい点が印象的でした。全体を通して、著者の長年にわたる研究に基づく知見が随所に感じられ、理論的な裏付けを重視する技術者にとって有益な内容だと思います。
高効率薄膜太陽電池の物理と化学 - ペロブスカイトと有機半導体 -
本書は、薄膜太陽電池の高効率化を支える物理・化学の基盤を体系的に整理し、材料科学・デバイス物理・プロセス技術を横断的に理解できる構成となっている。光吸収、キャリア輸送、界面準位、欠陥生成といった物理現象に加え、成膜プロセス、組成制御、結晶性改善など化学的アプローチが丁寧に解説されており、企業技術者が量産プロセス改善や新材料導入を検討する際の実務的な判断軸を得られる。特に界面制御や欠陥低減のメカニズムは、歩留まり向上や信頼性確保に直結する知見として価値が高い。また、ペロブスカイト、有機薄膜材料系の特徴・課題・成熟度が比較されており、「どの技術領域に投資すべきか」「どの材料系が将来の競争力を左右するか」を見極めるための視点が提供されている。また、基礎物性からデバイス構造、製造プロセスまで一貫して俯瞰できるため、研究テーマの優先順位付けや技術ロードマップ策定にも活用しやすい。研究と量産の断絶を埋めるヒントも多く、企業の中長期R&D戦略を支える実務的なリファレンスとしても有用な一冊である。
お問い合わせ先
書籍に関するお問い合わせやご相談は、以下まで、お気軽にお問い合わせください。
- コロナ社 営業部
- TEL:03-3941-3133
- FAX:03-3941-3137
- 休業日を除く、平日の9時~17時