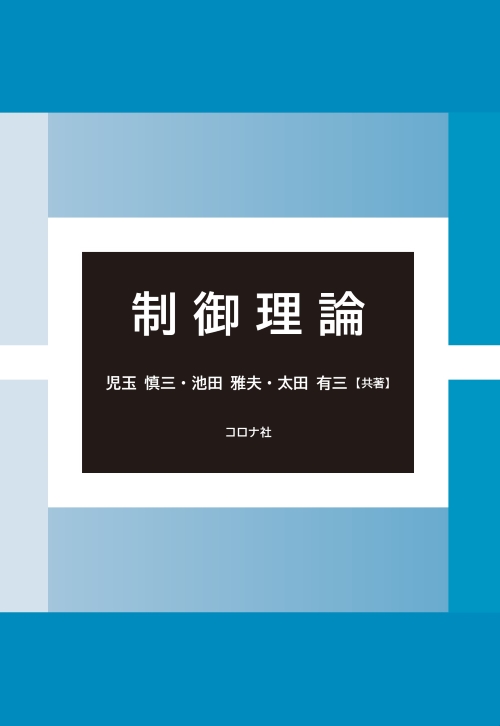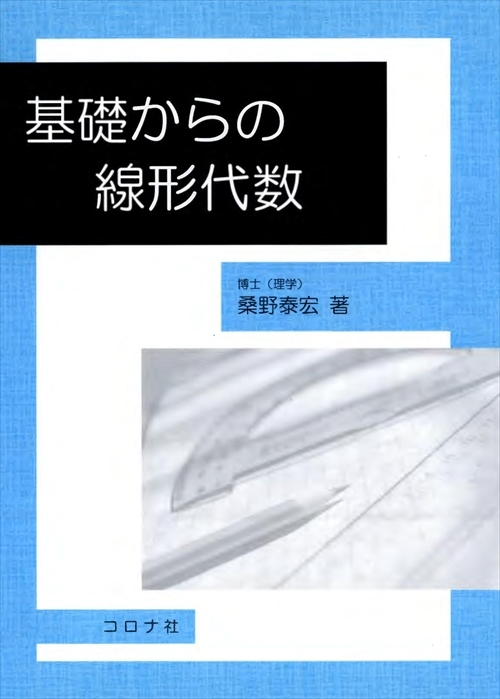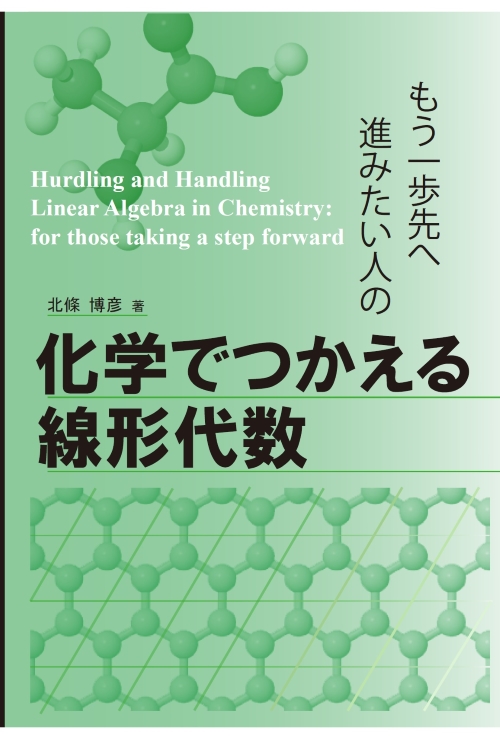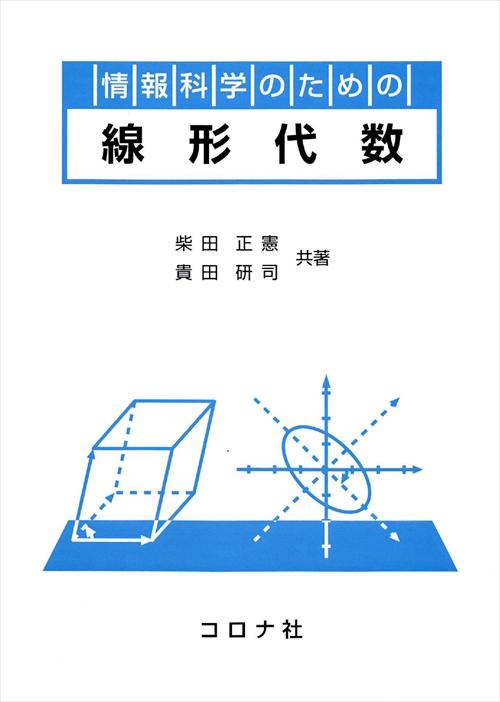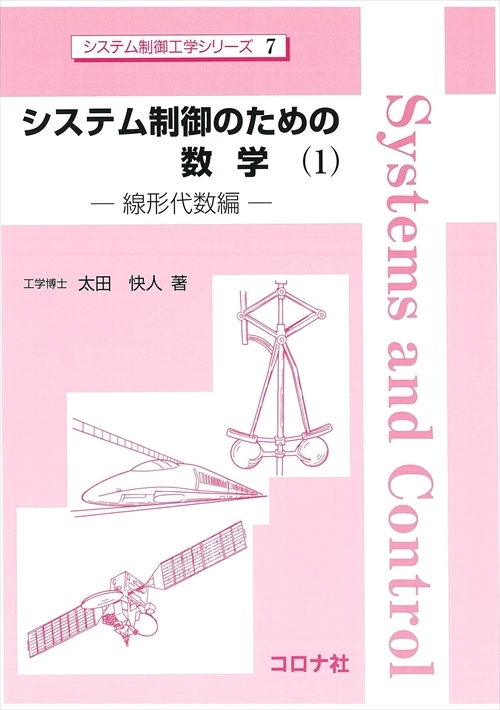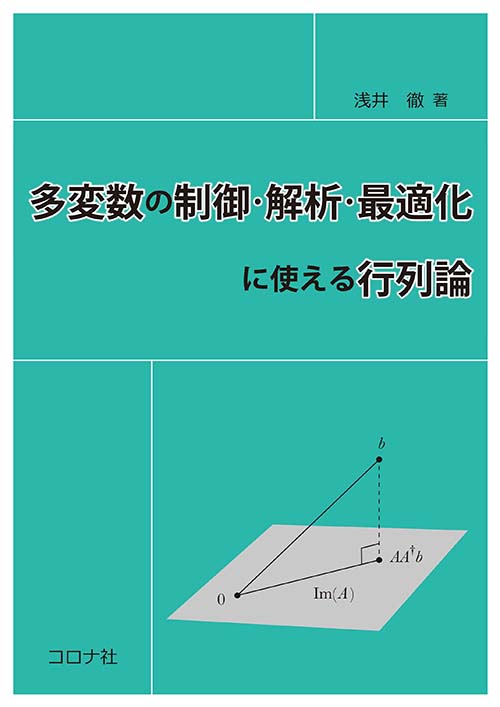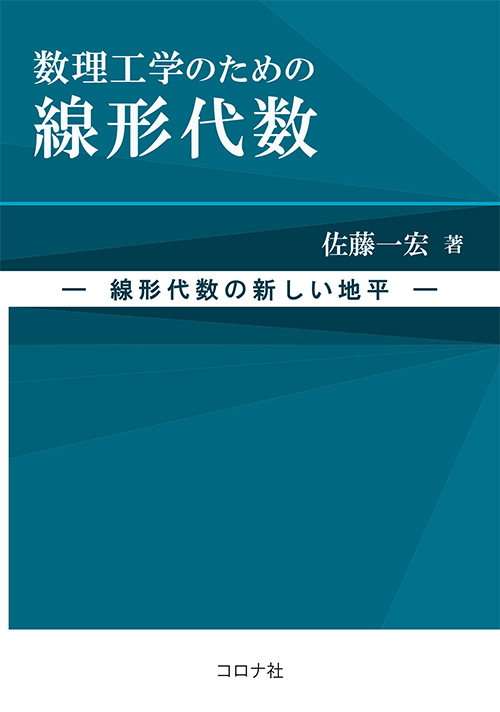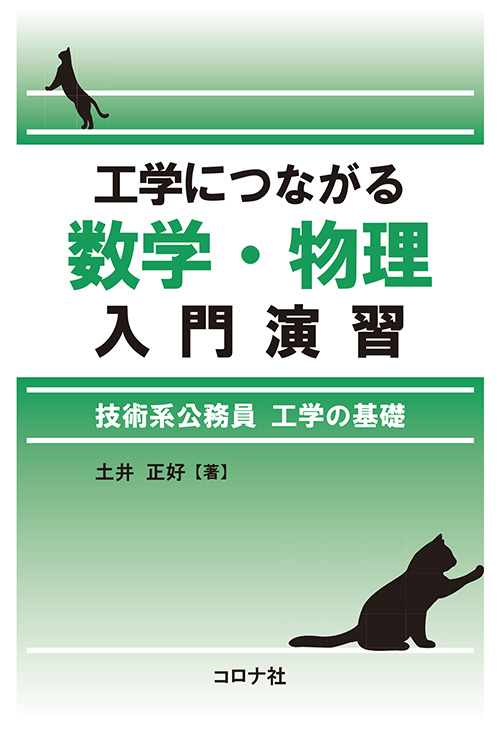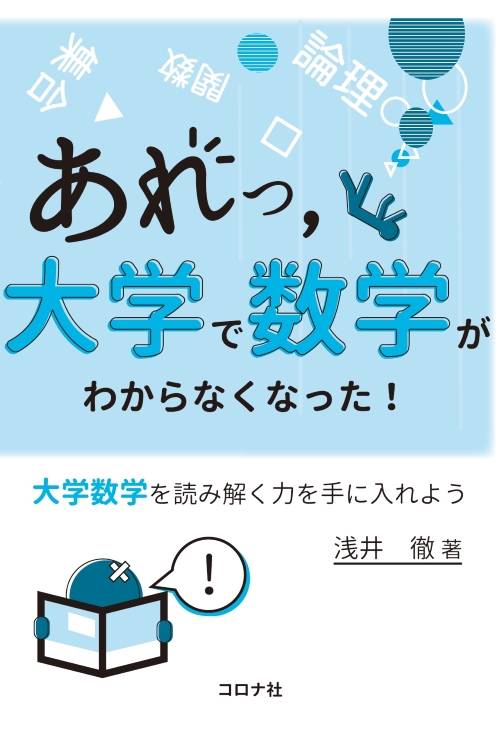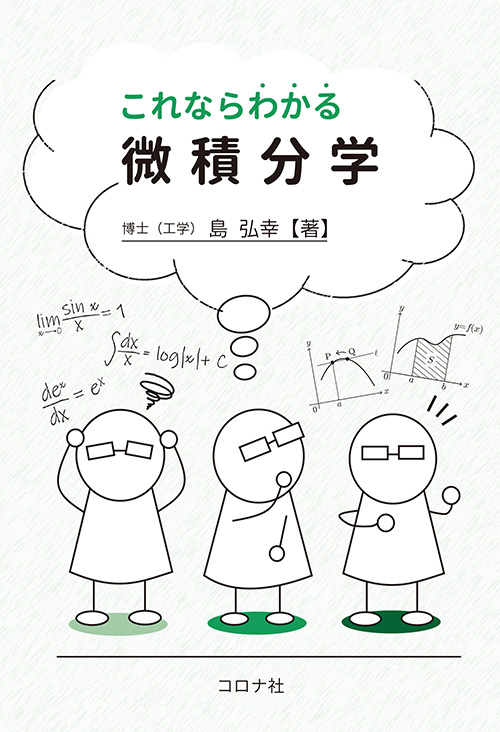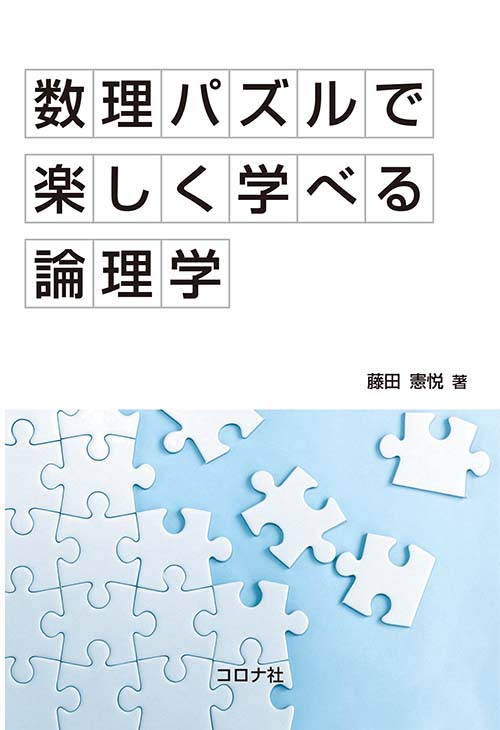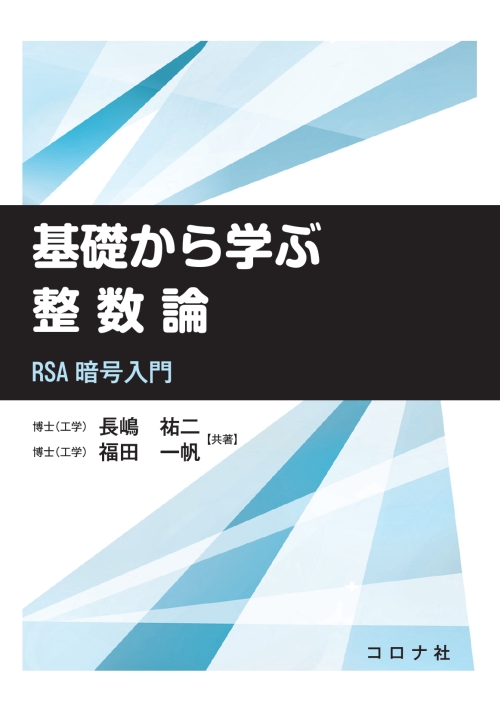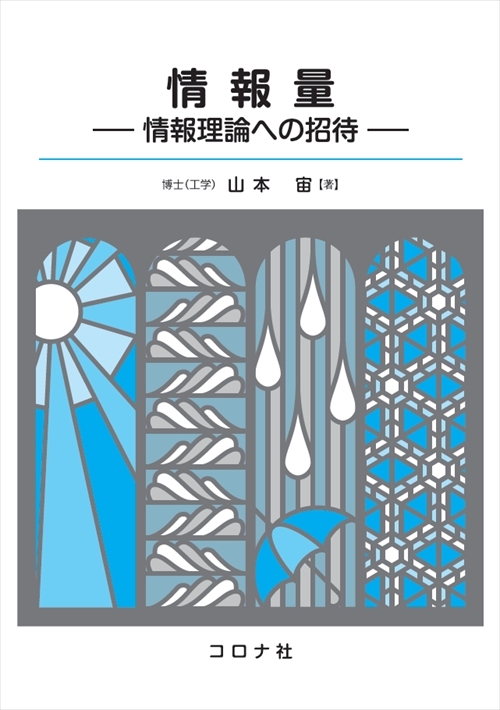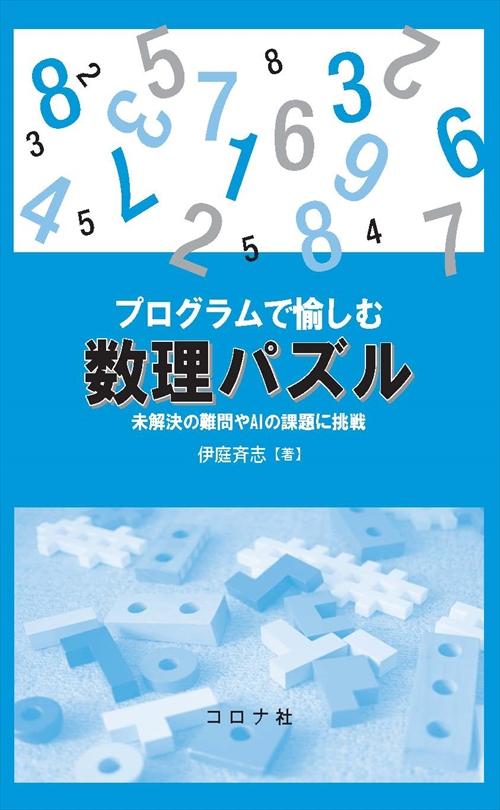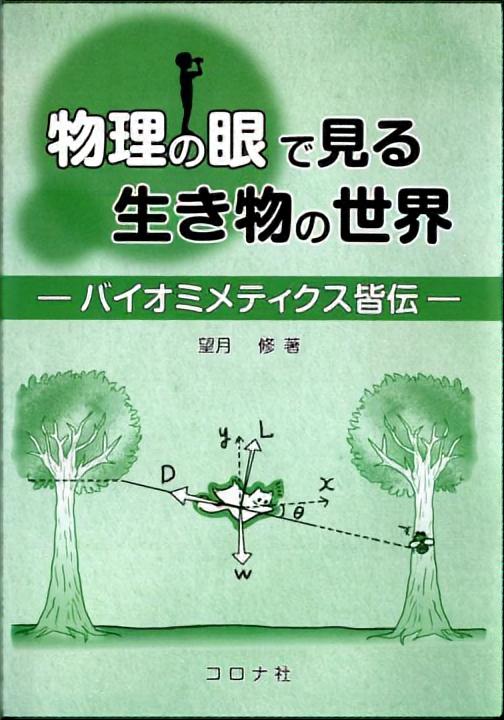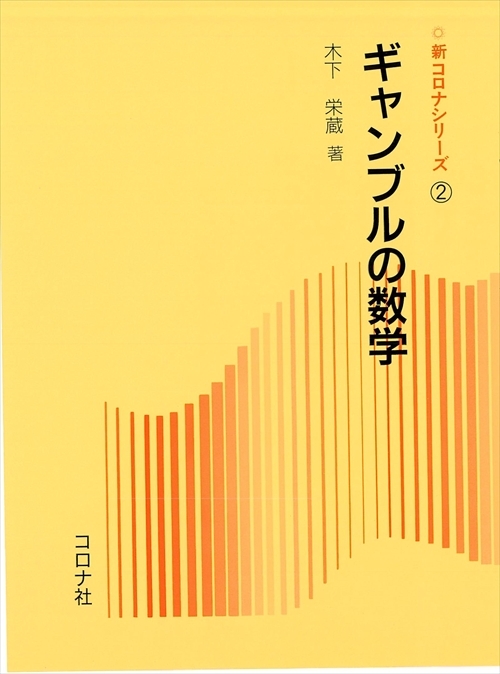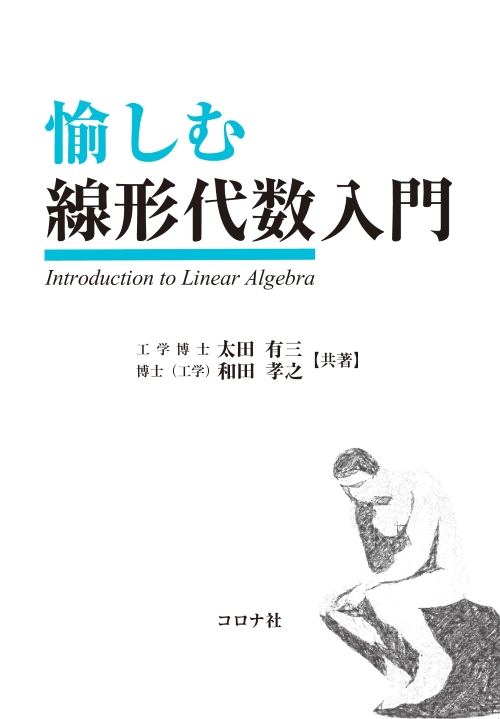
愉しむ線形代数入門
天下り的な定義や定理の記述と証明という説明を避け,それを考える必要性・動機を説明。
- 発行年月日
- 2025/08/28
- 判型
- B5
- ページ数
- 300ページ
- ISBN
- 978-4-339-06134-5
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
【読者対象】
本書は,大学1年生,高専高学年レベルの知識がある学生を主な読者対象としています。また,一度線形代数を学んだ人にももう一度線形代数を愉しんで勉強してもらうことも目指しています。
【書籍の特徴】
行列式のモヤモヤ、晴らします。
多くの線形代数の教科書では、行列式は「そう定義するもの」として登場します。あるいは、満たしてほしい性質を列挙し、その条件を満たす関数として定義されることもあります。しかし、どちらの場合もなぜそのような定義になるのかということは明示されておりません。
本書では、そうした“天下り式”の説明に頼ることなく、初等的なアプローチを用いて連立一次方程式に唯一解が存在する必要十分条件から行列式を自然に導き出しています。行列式以外の概念についても、定義や定理の前にその必要性や動機を丁寧に解説し、納得しながら読み進められる構成を心がけています。
また、個々の問題や例題にとどまらず、それらの相互関係や共通する構造に意識を向けることで、読者が自分の頭で考え、学びを深める力を育むことを重視しています。愉しみながら効率よく学び、「考える線形代数」を身につけてもらう――それが本書の願いです。
独習書として、あるいは定義に疑問を感じて立ち止まったときのリファレンスとしても最適な一冊です。
【各章について】
はじめに1章で記号を準備した後、2章で行列を導入し、3章で連立方程式の消去法を一般化したガウスの消去法を紹介しています。第4章が本書の最も特徴的なコンテンツである行列式について述べ、その後、固有値を導入します。さらに、5章から12章では線形代数の幾何学的な説明も取り入れながら、ベクトル空間や基底等を紹介し、ノルム・ジョルダン標準形まで述べます。最後に13章と14章において線形代数の知識の応用例として,定係数線形微分方程式や定係数線形差分方程式で表される動的システムの安定性と基礎的制御問題を考えています。
【読者へのメッセージ】
本書は、「なぜそうなるのか」を大切にした線形代数の入門書です。定義や定理を押しつけるのではなく、その背景にある考え方や必要性を丁寧にたどります。モヤモヤを抱えたまま先に進まないでください。納得しながら、線形代数を一緒に愉しみましょう。
【本書のキーワード】
線形代数、行列、行列式、ベクトル、ベクトル空間、線形写像、ガウスの消去法、固有値、固有ベクトル、対角化、ジョルダン標準形、疑似逆行列、対称行列、エルミート行列、二次形式、マトリックス平方根、特異値分解、ノルム、現代制御論、システムの安定性
線形代数は,応用分野が広く多くの工学系科目を学ぶ上で必須のものといっても過言ではない。この意味では,基礎からゆっくり時間を掛けて勉強しても十分に元が取れるといってもよい。また,線形代数は,解析学などと異なり極限操作に関する内容が少なく,基礎的概念から諸定理の導出などを丁寧に記述した書物があれば数学科の学生でなくとも十分自習できる。
本書は,大学1年生,高専高学年レベルの知識があれば読み始めることができ,かつ,一度線形代数を学んだ人にももう一度線形代数を愉しんで勉強してもらうことを目指している。「一を聞いて十を知る」という言葉があるが,これは,本質的にAという概念を知れば,類似しているA1,A2, …, An にも応用が利くということである。具体的な例題だけの理解で済まそうとすると,A1, A2, …, An を個別に理解していくが,それらの相互関係,共通部分を意識していないので,An+1には対処できない。これはあまり効率が良いとはいえない。問題P1,P2, …, Pn を理解したとして,新しい問題Pn+1を考えるときに,この問題はいままで考えた問題と関連はないのか,問題Piと関連があるとするとPiを解いたときのアプローチが使えないかなどいろいろ考えながら勉強すると,全体として勉強の効率が良くなる。また,考える力の涵養にも役立つ。このような勉強の仕方は特に新しいものではなく,論語でも『学而不思則罔。思而不学則殆(学ぶだけで考えなければ本当の理解には到達しない。考えるだけで学ばなければ独断に陥る危険がある)』といっている。慣れないと億劫に感ずるかもしれないが,日頃から心がけていると自然にできるようになる。
本書では,愉しんで勉強してもらいながらそのような勉強法の手助けとなることを目指して,天下り的な定義や定理の記述と証明というスタイルを極力避けて,紹介するトピックはそれを考える必要性・動機を説明し,その問題を解いていくための考え方・方法を説明しようと心がけている。例えば,ほとんどの線形代数の本においては,行列式の定義が天下り的に与えられ,その妥当性を次数が2,3の場合の例で示すにとどまっているのに対して,本書では初等的な知識だけを用いて行列式を導出している。さらに,ジョルダン標準形についても,他書籍などで紹介されている単因子など高度な知識を用いずに,本書で説明している知識だけを用いて,ジョルダン標準形を導出している。なお,他のトピックについても本書で説明している知識を引用して導入部分や結果を導くことが多いので,それらをすばやく検索して仮定や結論をしっかり確認できるように,定義・定理・補題・補助定理・例題などについても索引を付けている。
本書の1章から12章は線形代数の部分で,13章,14章は定係数線形微分方程式や定係数線形差分方程式で表される動的システムの安定性と基礎的制御問題への線形代数の知識の応用である。
線形代数で出てくる種々の概念は,図形的・幾何学的に考えると非常にわかりやすいものが多い。しかし,学生諸君にとって,この幾何学的観点は馴染みが薄く,一番基本的な概念であるベクトル空間や部分空間という話になると,とたんに腰が引けてしまうということになりがちである。そこで,線形代数の前半部分ではおもに「計算」を主として代数的観点から,行列の和と積,ガウスの消去法を用いた線形方程式の求解,行列式,固有値と固有ベクトルなどについて述べ,後半部分では幾何学的観点も交えながら,ベクトル空間,線形写像とその行列表現,擬似逆行列,二次形式と対称行列,ノルム,ジョルダン標準形などのトピックを取り上げ
ている。慣れてくると,幾何学的観点からの理論展開の方が代数的観点からのそれよりは直感的にわかりやすい。
13章,14章は,動的システムを対象としており,それ以前の線形代数の部分と少し雰囲気が違うが,通常,学部の現代制御の授業でカバーされる安定解析,可制御性,可観測性,極指定,オブザーバなどの問題が与えられたときに線形代数の部分で学習してきたことを,どのように適用して問題を解いていくかということに焦点を当てて説明している。したがって,本書を現代制御の教科書として利用していただける場合は,制御的観点からなぜこのような問題を考えるかということの紹介を補足をしていただけると効果的である。なお,演習問題の解答はコロナ社のWebページ(p.15参照)でダウンロードできる。
2025年6月
太田有三
和田孝之
1.記号,表記法
1.1 記号一覧
1.2 命題,同値
2.行列,ベクトルに対する演算
2.1 行列とベクトル
2.2 スカラ倍,和,積,線形性
2.3 ブロック行列
2.4 行列,ベクトルの転置
演習問題
3.消去法,行標準形,逆行列
3.1 連立一次方程式の消去法
3.2 消去法の行列表現
3.2.1 準備:行変換
3.2.2 消去法の行列表現
3.3 ガウスの消去法
3.3.1 ガウス・ランクG-rank(A)=nとなる場合
3.3.2 ガウス・ランクG-rank(A)
3.5 逆行列
演習問題
4.行列式
4.1 行列式の導出
4.2 行列式を用いた公式
4.2.1 行列の積の行列式
4.2.2 転置行列AT,共役転置行列AHの行列式
4.2.3 クラーメルの公式
4.3 ブロック行列の行列式と逆行列
演習問題
5.固有値と固有ベクトル,対角化
5.1 固有値と固有ベクトル
5.2 相似変換による対角化
5.3 ケーリー・ハミルトンの定理
演習問題
6.ベクトル空間
6.1 群,環,体
6.2 ベクトル空間,部分空間,基底,次元
6.3 零化空間,値域,行列のランク,次元定理
演習問題
7.行標準形-再論-
7.1 一般化ガウスの消去法,行標準形
7.2 零化空間の基底の求め方(一般解の求め方)
7.3 ランクに関する重要な性質
演習問題
8.基底,線形写像,不変部分空間と行列表現
8.1 基底とベクトル表現
8.2 線形写像と行列表現
8.3 不変部分空間と行列表現
演習問題
9.擬似逆行列
9.1 内積,直交,正規直交基底
9.2 誤差最小かつ大きさ最小の解
9.2.1 rank(A)=n≦mである場合
9.2.2 rank(A)=m≦nである場合
9.2.3 rank(A)=r≦min{m,n}である場合
9.3 最大ランク分解と擬似逆行列
演習問題
10.実対称行列,エルミート行列
10.1 実対称行列,エルミート行列の固有値と対角化
10.2 二次形式,エルミート形式
10.3 マトリックス平方根
10.4 特異値分解,極分解
演習問題
11.ノルム
11.1 ベクトルのノルム
11.2 行列のノルム
11.3 不確かさがある場合の解析
演習問題
12.ジョルダン標準形の導出
12.1 動機的例題
12.2 一般化固有ベクトル
12.3 ジョルダン標準形
演習問題
13.線形時不変システムの解と安定性
13.1 解の公式
13.1.1 離散時間システムの解の公式
13.1.2 連続時間システムの解の公式
13.2 安定性
13.2.1 離散時間システムの安定性
13.2.2 連続時間システムの安定性
13.3 ラプラス変換と伝達関数
13.3.1 ラプラス変換
13.3.2 ラプラス変換を用いた解の計算
13.3.3 伝達関数
演習問題
14.現代制御理論への応用
14.1 可制御性
14.1.1 離散時間システムの可制御性
14.1.2 連続時間システムの可制御性
14.2 可観測性
14.2.1 離散時間システムの可観測性
14.2.2 連続時間システムの可観測性
14.3 極指定
14.3.1 可制御標準形と極指定:1入力系(m=1)の場合
14.3.2 可制御標準形と極指定:多入力系(m≧2)の場合
14.4 オブザーバ
14.4.1 同一次元オブザーバ
14.4.2 最小次元オブザーバ
14.4.3 オブザーバの一般化
14.5 状態空間表現の変換とカルマンの正準形
演習問題
引用・参考文献
索引
読者モニターレビュー【 Yuki 様 (業界・専門分野:機械学習・ロボット工学)】
大学で一度線形代数を学んだものの、どうも腑に落ちないまま単位を取得したという方に、自信を持っておすすめしたい一冊です。
多くの教科書が扱う連立方程式や固有値・固有ベクトルといった基本概念から始まりながらも、その奥にある本質を徹底的に掘り下げています。単なる計算手順の解説に留まらず、数学的思考のプロセスを追体験させてくれます。
特に擬似逆行列の章は印象的です。最小二乗法や線形回帰分析が、いかに線形代数の概念から自然に導かれるかを丁寧に解説しています。また、実対称行列、エルミート行列の章では、推薦システムや画像圧縮といった応用分野で不可欠な特異値分解などの強力なツールを学ぶことができます。
最後に制御論へと続く構成は、線形代数が私たちの世界を記述し、制御するためのパワフルな言語であることを実感させてくれます。線形代数を単なる数学の一学問としてではなく、現実の問題を解くための道具として捉えたい人にとって、非常に価値のある一冊となるでしょう。
読者モニターレビュー【 あめ色玉ねぎ 様 (業界・専門分野:システム工学)】
本書は、定義や定理を単に覚えるのではなく、その背景にある動機や必要性を丁寧に掘り下げ、「なぜそうなるのか」を重視して線形代数を解説している。特に行列式については、天下り的な定義を避け、連立一次方程式の解の存在条件から自然に導出しており、他の教科書とは一線を画す。
前半は計算を中心に、後半は幾何学的視点も取り入れて理論を展開しており、ベクトル空間やジョルダン標準形も直感的に理解できる構成となっている。13章・14章では、制御理論への応用も取り上げ、抽象理論が実問題にどう結びつくかを示している。
索引や例題も充実しており、独習にも適している。線形代数を深く納得しながら学びたいすべての学生に薦めたい良書である。
読者モニターレビュー【 yk 様 (業界・専門分野:臨床医療, 神経科学)】
工学研究者が実用的な側面を重視して著した線形代数の教科書である。線形代数を自信をもって使いこなせるユーザになりたい方にお薦めできる。基礎概念がその導入の必要性とともに解説されており、基本的な定理はほとんど全て網羅されている。例題や演習問題も豊富で、特にジョルダン標準形の導出は丁寧であり、記号の洪水に耐えることさえできれば、試行錯誤しながら遊び感覚で線形代数を身につけることが出来るだろう。さらに、標準的な内容を超えて、類書ではあまり見かけない定理が述べられているのも目新しいし、また行列ノルム=作用素ノルムの導入は初学者の目にはやや抽象的に映るかも知れないが、実用上重要であるのみならず理論的にも関数解析への序章として役立つ。加えて、証明が詳述されているため定理を安心して参照することが出来、辞書的に用いることもできる。
本書の最大の特徴は、ページ数にして約1/3を占める安定性解析および制御理論のコンパクトな定式化である。線形代数の豊かな世界を垣間見せてくれている。惜しむらくは系の具体例が挙げられていないことであるが、そこは読者が各自で興味ある系に適用して遊んでみるのが良いだろう。なお、一部の定理の証明では位相空間論の知識が用いられており、細部まで理解するには実はある程度の数学的素養が要求されることを注意しておこう。
因みに私の専門分野である神経科学でも理論的考察およびデータ解析で線形代数は必須の道具であるが、残念ながら正確に使いこなせている研究者は多くないようである。理工系の学生はもちろんのこと、生物系、医学系の研究者も、線形代数の確かなユーザでありたい方であれば誰でも、教科書として、辞書として、本書をぜひ手に取ってみて欲しい。
読者モニターレビュー【 なつ 様 (業界・専門分野:制御工学)】
本書は、工学系の学問の中でも最も重要な科目の一つである線形代数を丁寧に解説すると同時に、その応用として制御工学を扱った数少ない一冊である。数学と工学を橋渡しする構成となっており、基礎から応用までを通して体系的に学べる点に大きな魅力を感じた。
内容は第1章から第12章までが線形代数、第13章と第14章が制御工学に割かれている。線形代数から制御工学へ自然に接続できるように構成されており、「線形代数の基礎 → ノルム → ジョルダン標準形 → 制御工学」という流れも非常に明快である。まえがきにあるように、本書は「一を聞いて十を知る」ことができるように工夫されており、定義・定理・証明が詳細に記載されているため、初学者でも無理なく読み進められる。
線形代数の章では、特に連立方程式や行列式に多くのページが割かれている。連立方程式の解法については、係数行列が正方行列となる場合とそうでない場合に分けて解説され、加えてアルゴリズムの疑似言語まで掲載されているため、実際にプログラムを組んで解くことも可能である。また、行列式については定義を導出過程から解説しており、理解を一層深める工夫がなされている。さらに、多くの学生が苦手とするベクトル空間についても、具体例を豊富に挙げながら「なぜあるベクトルが特定の空間に属するのか」を解説しており、抽象的な概念を具体的に理解できるよう配慮されている。こうした点からも、本書は大学の授業で教科書として採用されるにふさわしいと感じた。
制御工学の章では、主に現代制御を取り上げており、離散系と連続系の両方の視点から学習できる。基本的には状態空間表現で説明が進むが、途中で伝達関数表現も登場し、現代制御と古典制御の結びつきを理解できる。また、終盤では可制御性・可観測性やオブザーバといった制御工学で重要なテーマを一通り学べる。ただし、「そもそも制御工学とは何か」という導入的な説明や数値シミュレーションは扱われていないため、制御工学を初めて学ぶ人には少々難しく感じられるかもしれない。その場合は、他書で基礎を学んだ上で本書に取り組むことで、数学的な視点から制御工学を整理できるだろう。
全体として、本書は線形代数に関しては初学者にとって非常に分かりやすく、制御工学については中級者以上を対象とした内容になっている。数学的な基礎を固めつつ、その延長線上で制御工学に触れられるため、学習のモチベーションを高めやすい点も魅力的である。学部学生の独学にも役立つだけでなく、大学院進学を目指す人にとっても基礎固めの一冊として十分に活用できるだろう。
総じて、線形代数と制御工学を一貫して学べる数少ない良書であり、本レビューが購入を検討されている方の参考になれば幸いである。
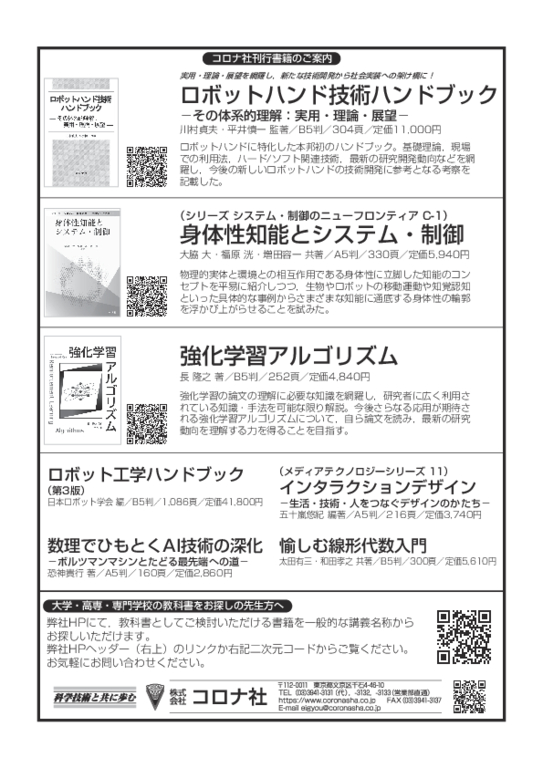
-
掲載日:2025/12/15
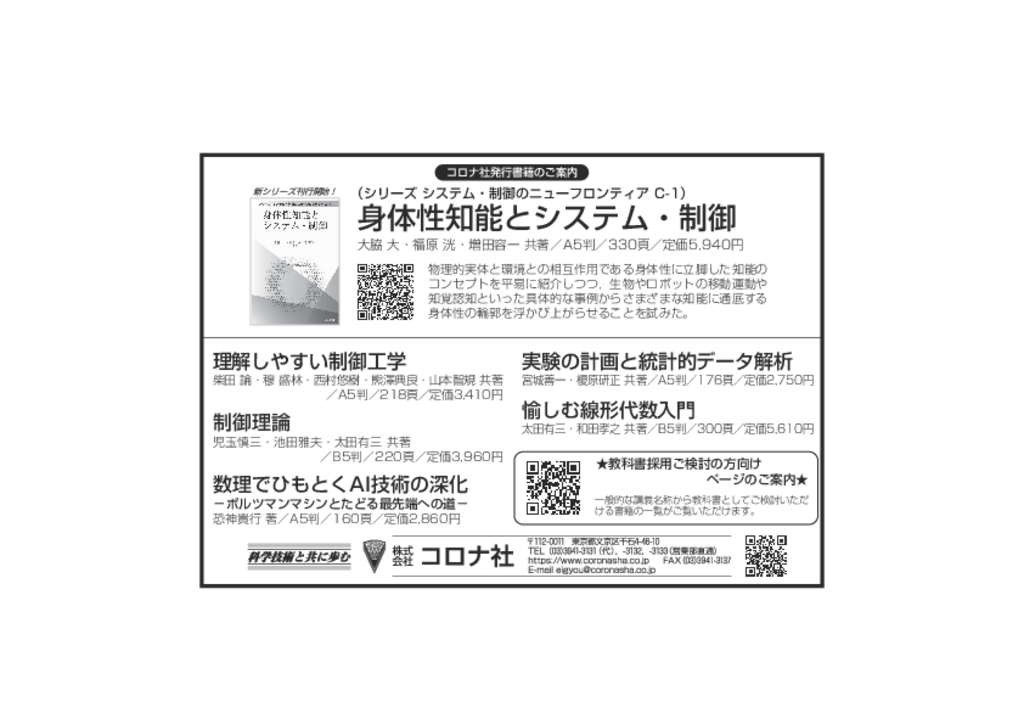
-
掲載日:2025/10/10

-
掲載日:2025/10/01
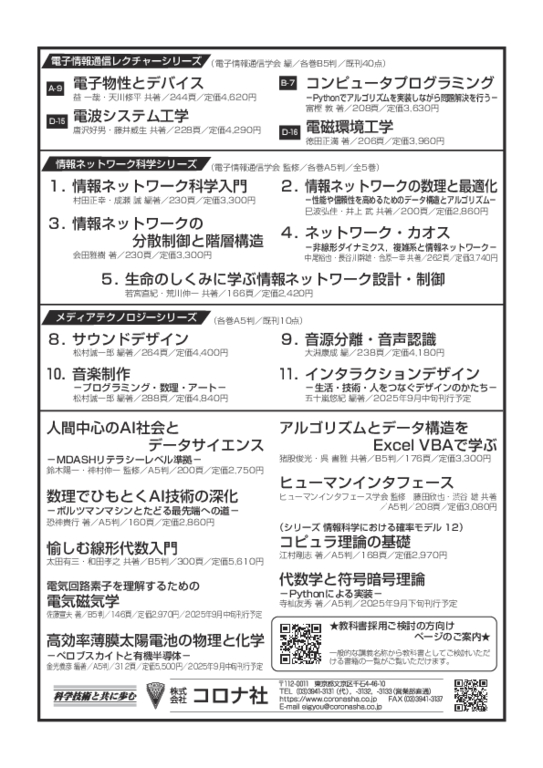
-
掲載日:2025/09/08
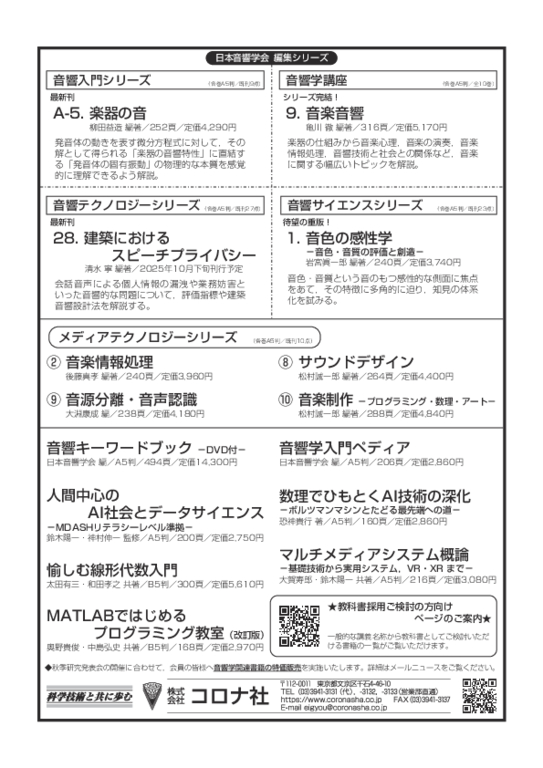
-
掲載日:2025/09/01

-
掲載日:2025/08/12
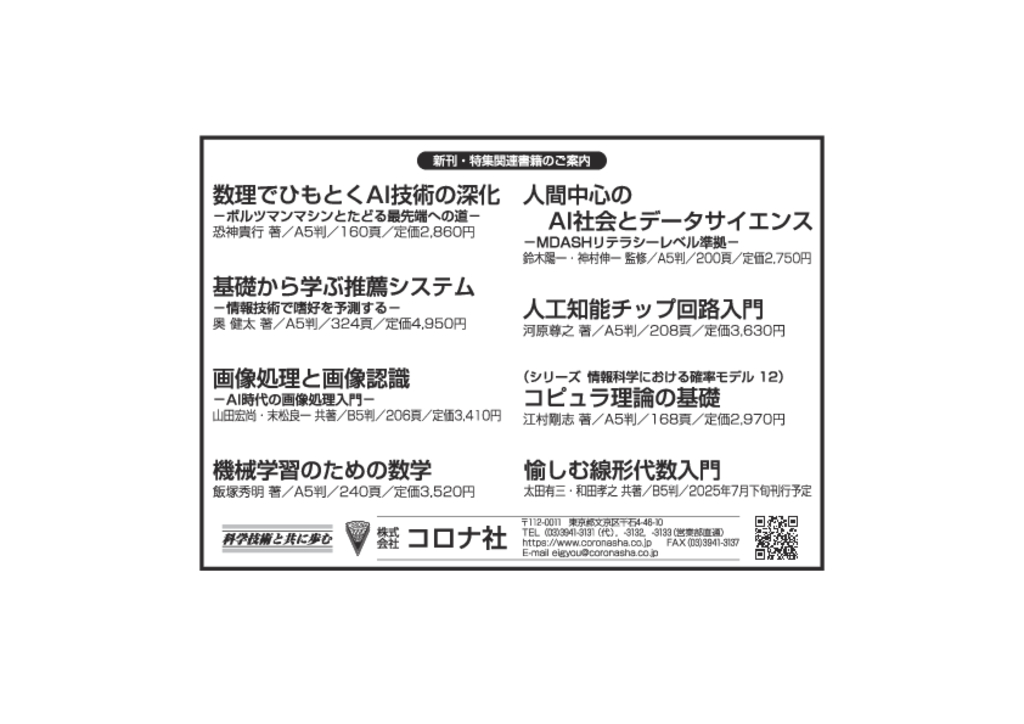
-
掲載日:2025/08/01
関連資料(一般)
- 演習問題の解答