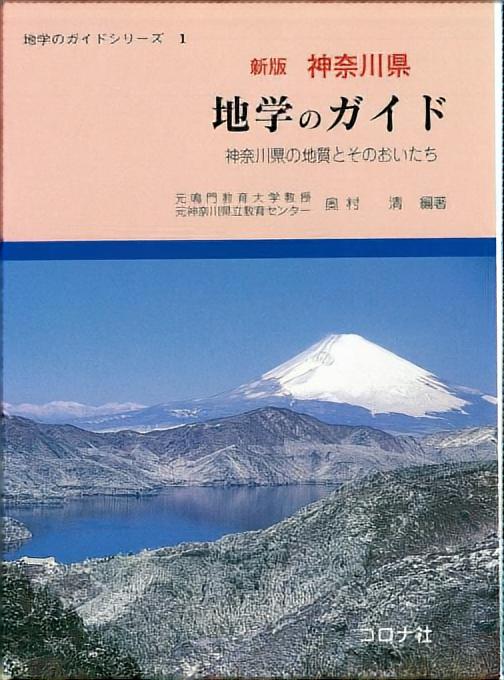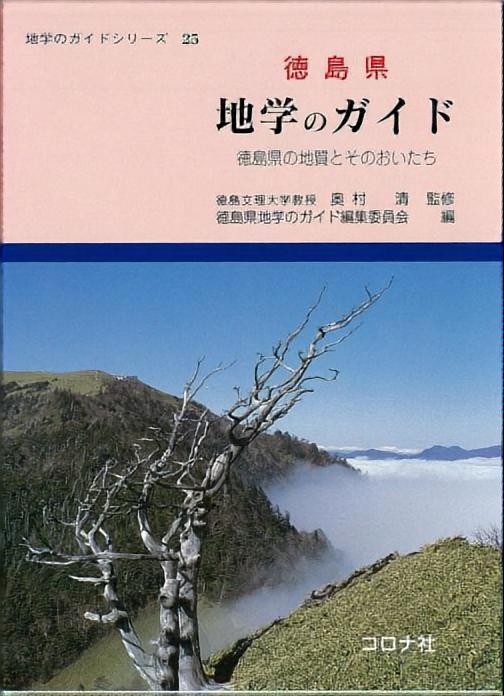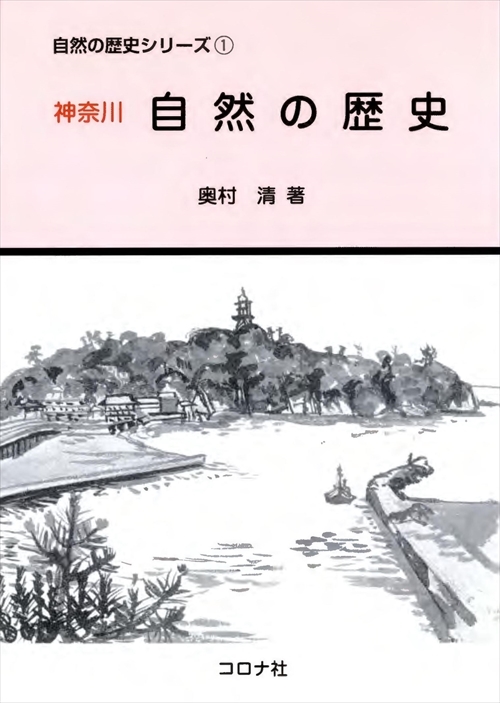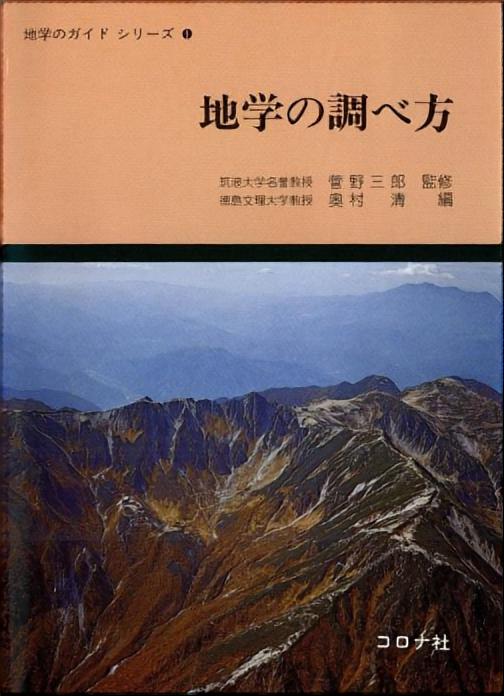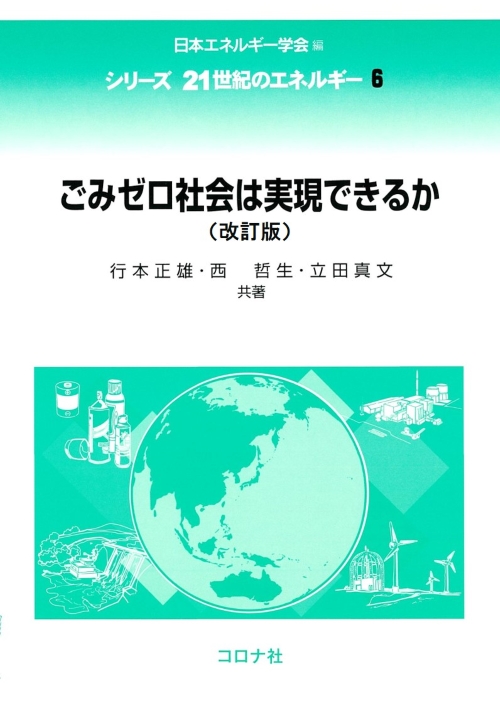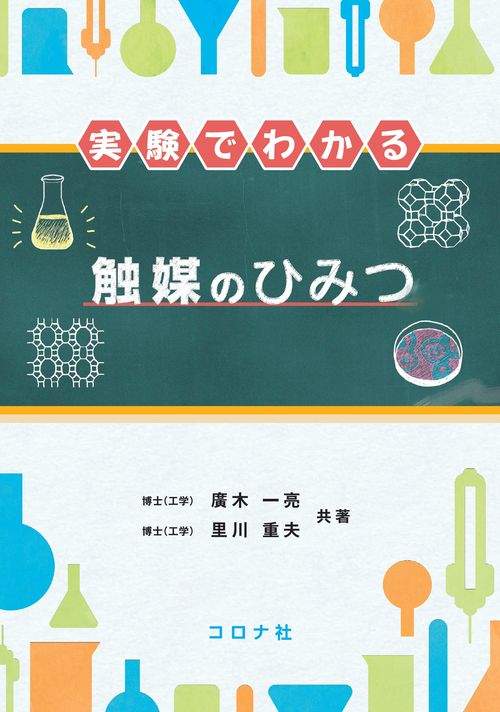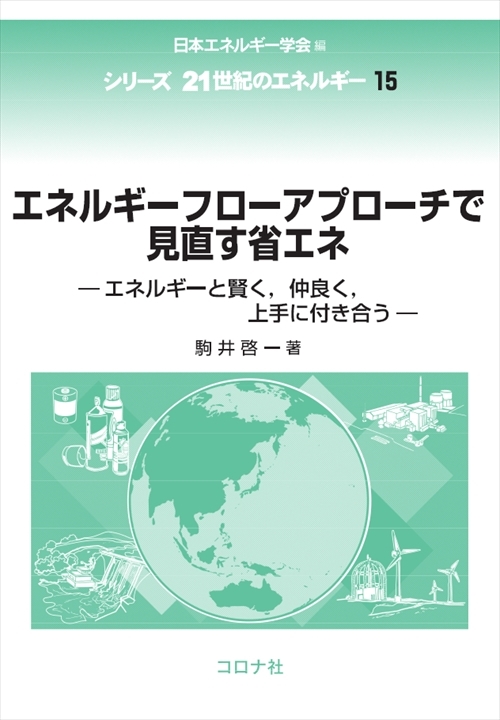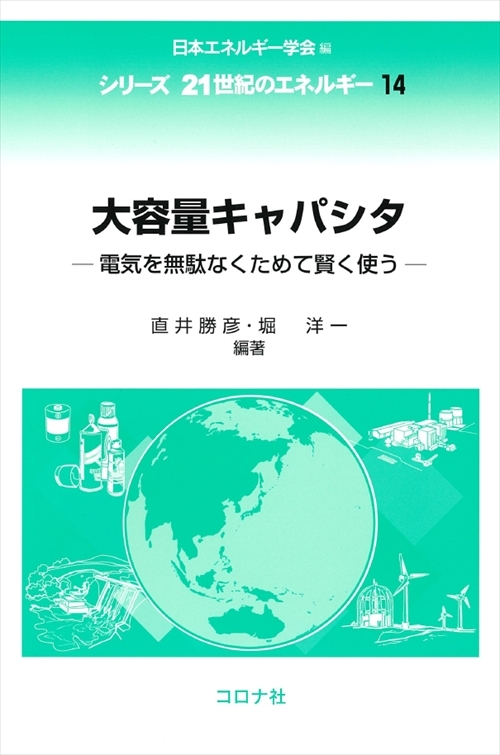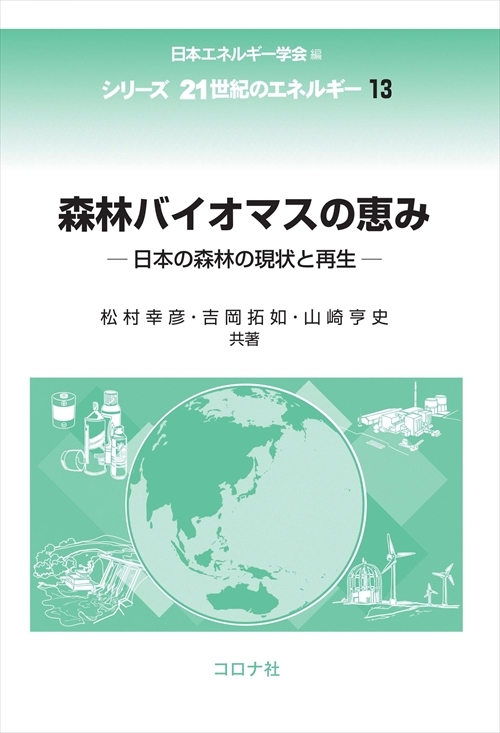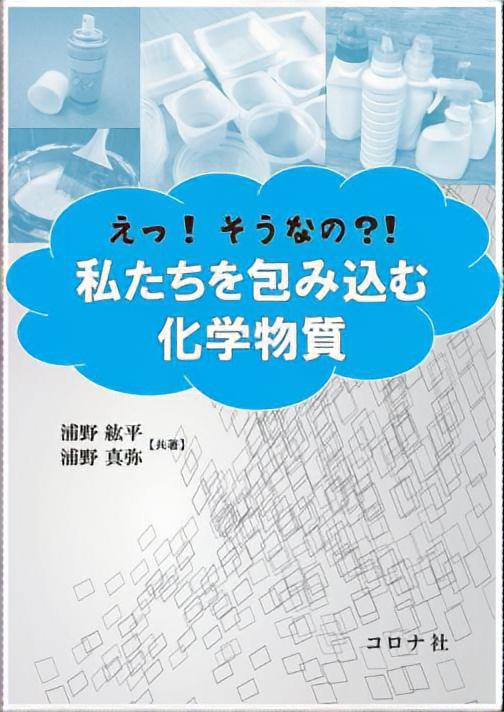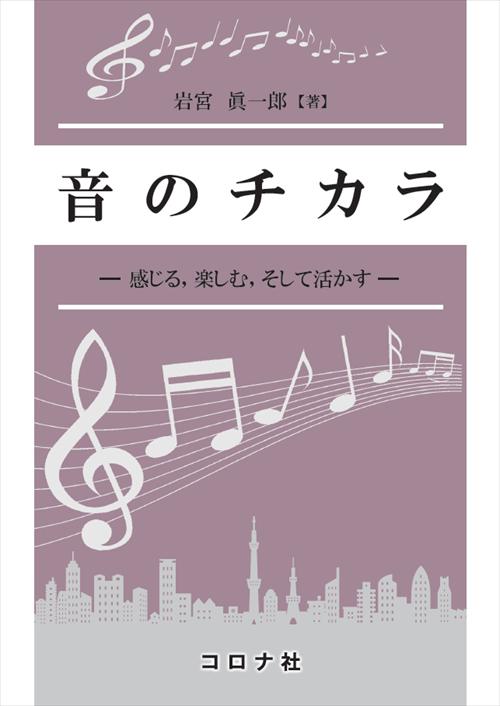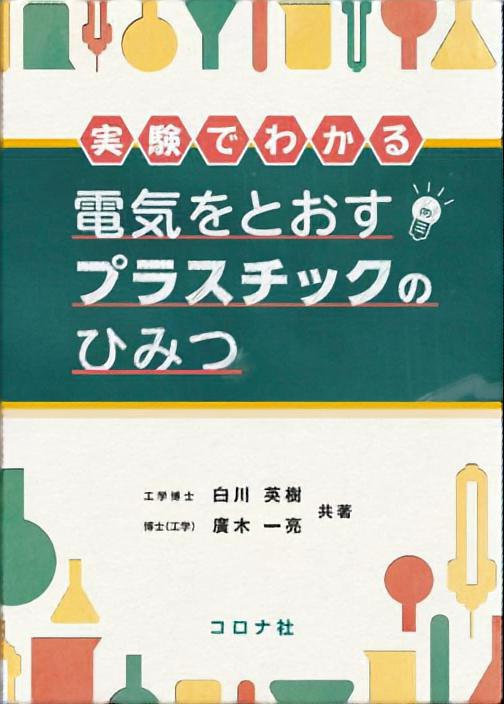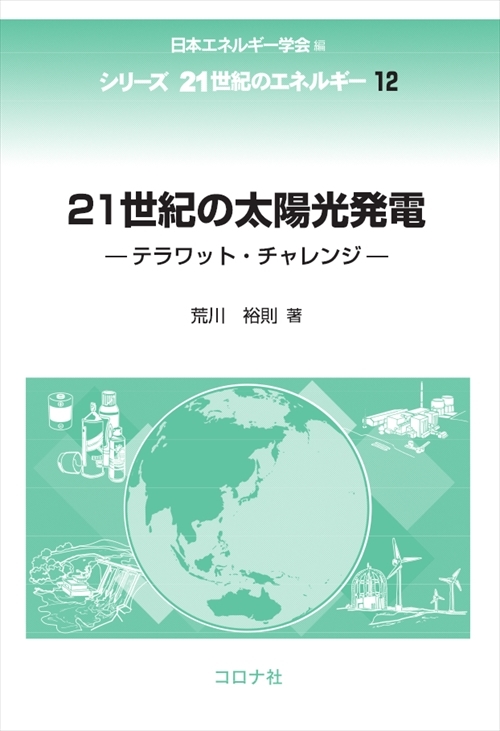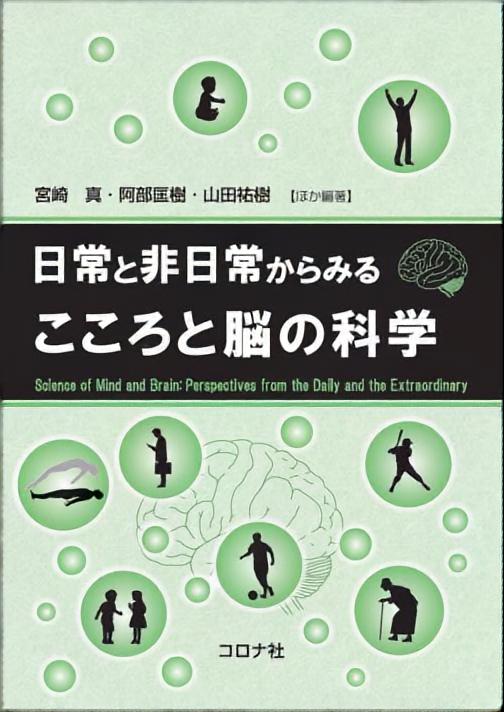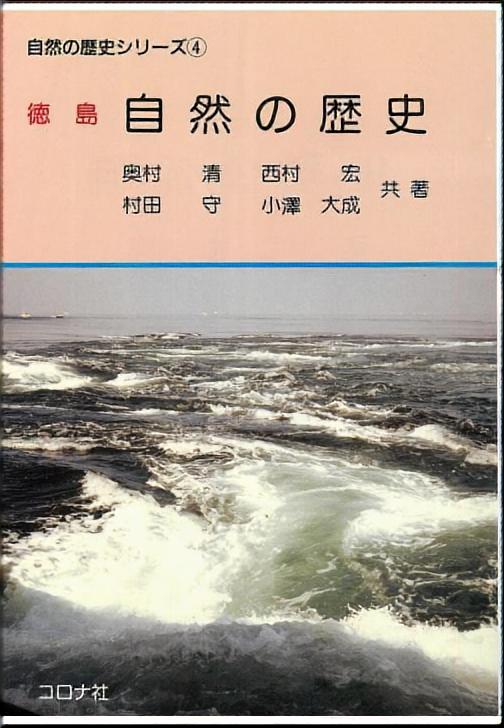
徳島 自然の歴史
吉野川沿いには大活断層中央構造線が通っている。それを境に北にはアンモナイトの化石を含む和泉層群が,南にはプレートに乗って遠い南海からやってきた岩石や地層が見られる。本書ではこのような徳島の自然の歴史を紹介した。
- 発行年月日
- 1998/09/30
- 判型
- B6
- ページ数
- 256ページ
- ISBN
- 978-4-339-07548-9
- 内容紹介
- 目次
吉野川沿いには大活断層中央構造線が通っている。それを境に北にはアンモナイトの化石を含む和泉層群が,南にはプレートに乗って遠い南海からやってきた岩石や地層が見られる。本書ではこのような徳島の自然の歴史を紹介した。
まえがき
I. 県土・四億年の歴史
1 四国の玄関口・徳島
2 三六位の広さ
3 東西に伸びる山並
4 美しい海岸
5 本邦最高気温観測地点
II. 吉野川
1 四国三郎
2 四国山地を横切る吉野川
3 讃岐に向かった吉野川
4 中央構造線に沿って
5 吉野川の三角州の上に立つ徳島平野
III. 徳島平野の地下構造
1 徳島平野
2 徳島平野の地下構造
・最上部礫・砂・泥層 ・上部砂層 ・中部泥層 ・下部砂層 ・基底礫層
3 吉野川と氷期
4 縄文海進
5 徳島平野深部の砂礫層
6 徳島平野地下の化石
IV. 吉野川の海岸段丘・扇状地と新しい地層
・吉野川沿岸の河岸段丘と扇状地 ・三段の河岸段丘 ・扇状地
1 池田の町が発達する河岸段丘
・池田町付近の高・中段段丘 ・低位河岸段丘
2 低・低位段丘面
・なぜ低段丘が高度差を生じたか ・新山は地滑り塊か
3 井沢谷川の扇状地
・扇状地のできた順 ・井沢谷川沿いのもっと古い扇状地 ・本流堆積物と扇状地性堆積物 ・堆積物ができた年代 ・堆積物中の植物化石
4 吉野川南岸の河岸段丘と扇状地
V. 中央構造線
・中央構造線 ・徳島での中央構造線の位置 ・中央構造線はどうしてできたか ・南洋からきた四国の南半分
・付加体 ・プレートを移動させた力ー中央構造線の形成
VI. 阿讃山脈と和泉層群
1 阿讃の山並
2 断層でできた阿讃山脈
3 阿讃山脈の特徴と広がり
4 海底地滑りでできた地層
5 北縁部の地層
6 中軸部の地層の特徴
7 海底地滑りー東から西への海底の流れ
8 堆積盆
9 西から東への隆起
10 褶曲構造
11 化石と年代
VII. 徳島の山中に混ざり込んだ海岸のかけらー緑色岩ー
1 付加体の地質学ー基本的な概念
2 海岸プレートの一生と海洋起源物質
・中央海嶺玄武岩の活動 ・遠洋性堆積物の堆積 ・ホットスポット起源の海山列の形成 ・海台玄武岩の噴出
3 みかぶ緑色岩類ー二億~一億四千万年前の海台の破片?ー
・みかぶ緑色岩類の分布 ・みかぶ緑色岩類を構成する岩石 ・顕微鏡下の特徴
4 みかぶ緑色岩類のできた年代
・化石から見た年代 ・放射性年代
5 みかぶ緑色岩類はどこでできたのかー微量成分化学組成からの考察ー
・みかぶ緑色岩類のNb/Zr ・微量成分の中央海嶺玄武岩規格化パターン
6 年代を考察したみかぶ緑色岩類の形成過程
7 秩父帯北帯の緑色岩ー二億五千年前の海山の破片ー
・神山層群中の緑色岩類 ・緑色岩類の特徴 ・緑色岩類の化学的特徴 ・緑色岩類の放射性年代 ・緑色岩類のた
どってきた歴史
VIII. 鳴門の渦潮
1 観光の名所「渦潮」
2 潮流
3 起潮力
4 潮汐と潮浪
5 淡路島の存在と渦潮
6 大自然の妙「渦潮」
IX. 自然災害の歴史
・自然の恩恵と災害 ・徳島の大地震 ・歴史上最古の大地震 ・安政大地震 ・地震の記録 ・津波の被害 ・前
日の地震の教訓 ・南海地震 ・平成七年兵庫県南部地震 ・忘れたころに・・・
X. 解説編
・ようこそ鳴門教育大学へ
1 岩石と鉱物
・Q1 岩石の種類 ・Q2 堆積岩 ・Q3 石と石コロ ・Q4 火成岩 ・Q5 火砕流 ・Q6 火成岩の化学組成
・Q7 枕状溶岩 ・Q8 変成岩 ・Q9 鉱物ができる
2 プレートの動きと地質
・Q10 地質図を作る ・Q11 地向斜とプレートテクトニクス ・Q12 日本列島の骨組み ・Q13 高校の教科 書が変わる
3 地震と断層
・Q14 二つの地震 ・Q15 断層 ・Q16 徳島の地震 ・Q17 中央構造線
4 地質学の応用
・Q18 温泉 ・Q19 自然災害 ・Q20 上昇する大学の謎
5 解説編の終わりに
・Q21 どんな本を読めばいいですか?
6 解説のあとがき
参考文献