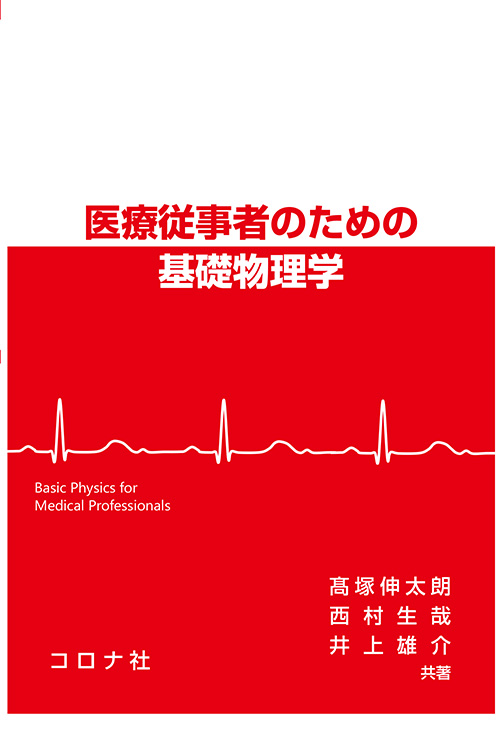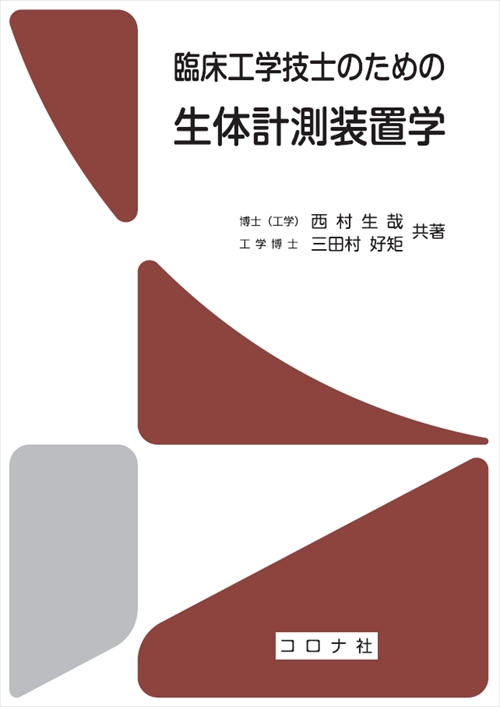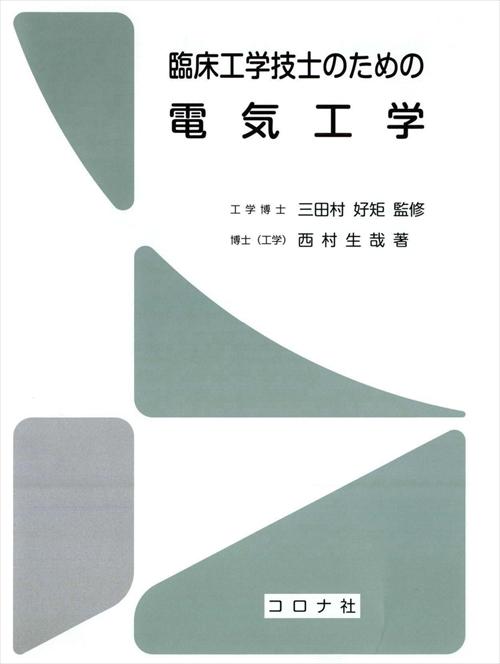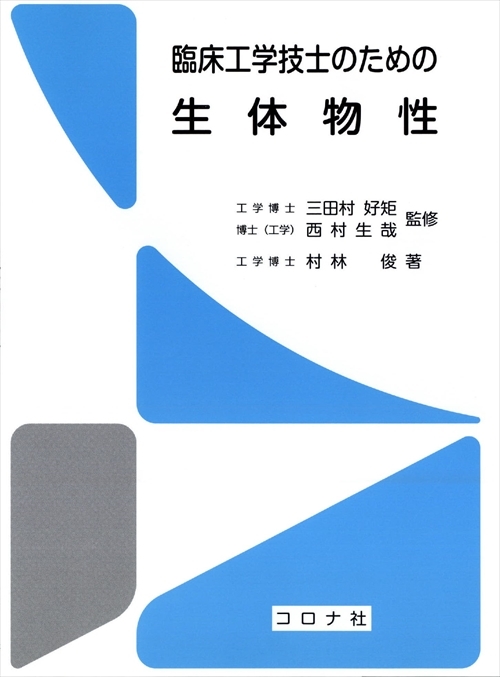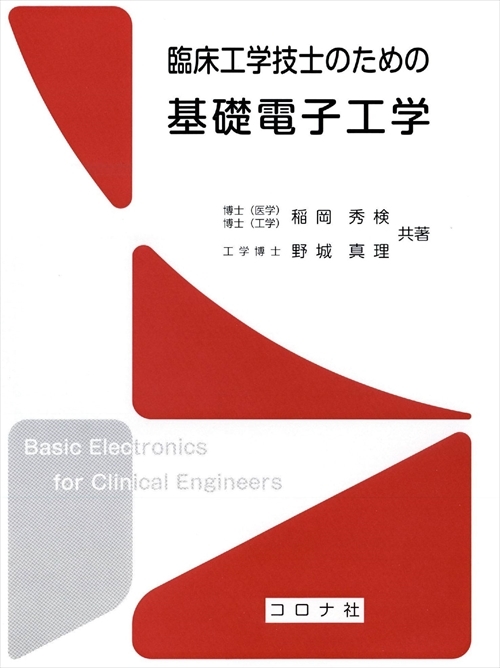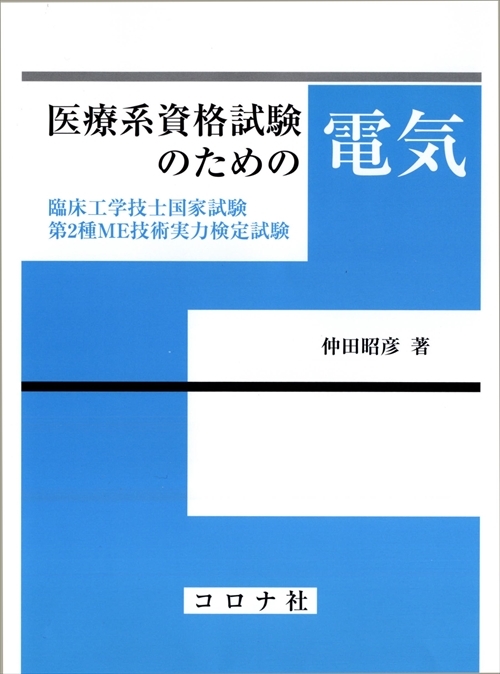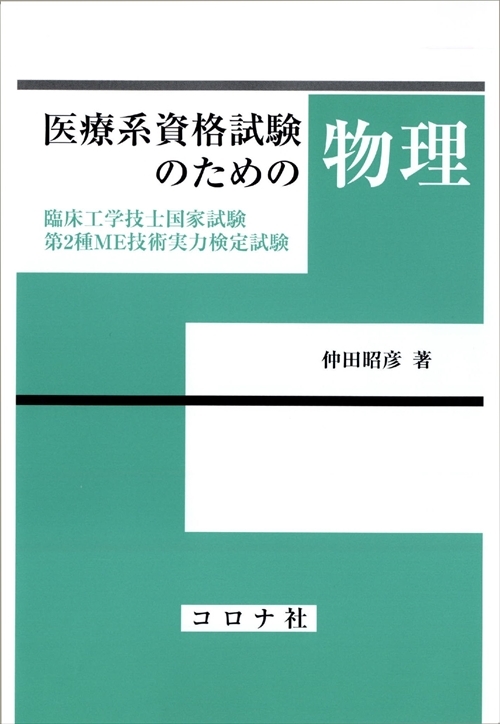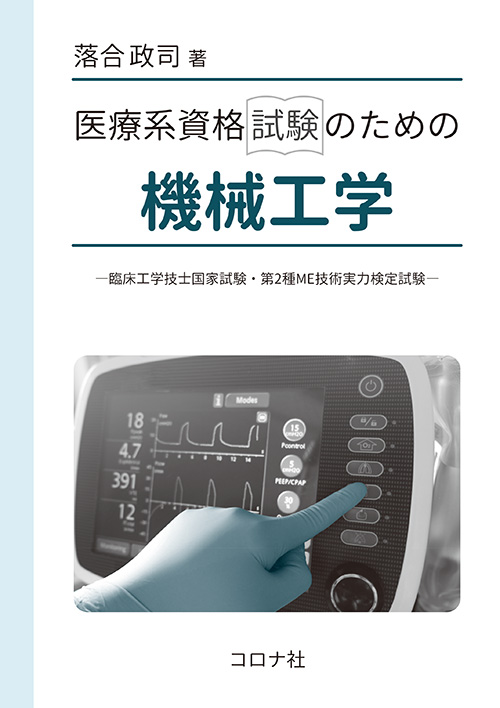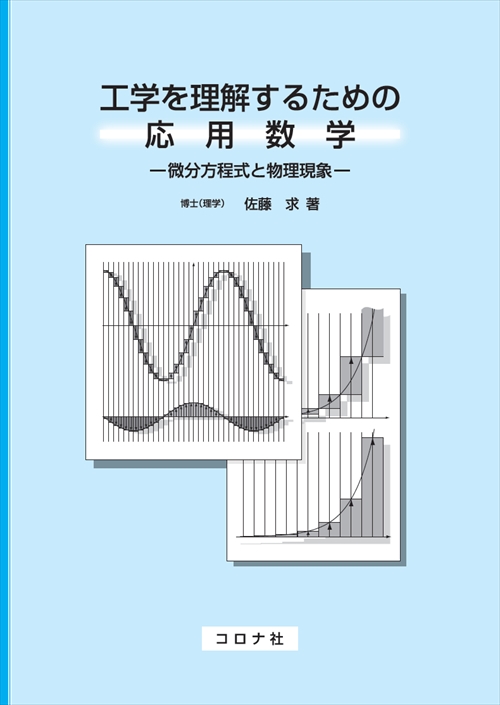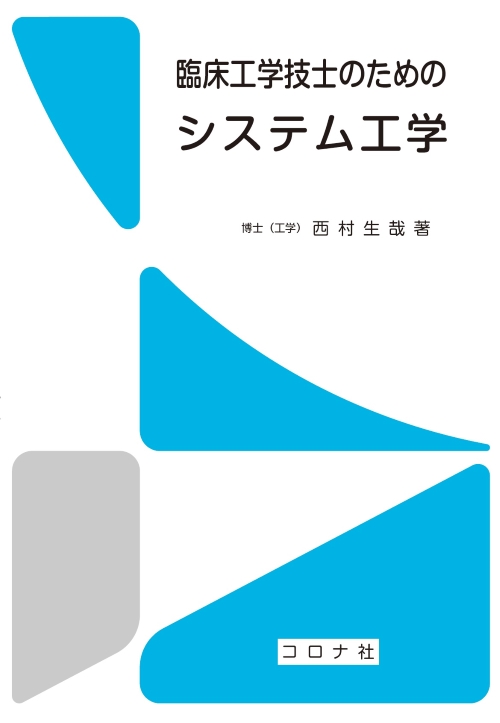
臨床工学技士のための システム工学
ややこしい話はばっさりと切り捨てて、試験に出る内容とその解き方だけに注力した。
- 発行年月日
- 2025/04/11
- 判型
- A5
- ページ数
- 180ページ
- ISBN
- 978-4-339-07282-2
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- 広告掲載情報
【読者対象】
臨床工学技士養成学校(大学・専門学校等)に通う学生、およびその指導教員を対象としている。
【書籍の特徴】
本書のコンセプトは「説明の対象を”ME2種と臨床工学技士の国家試験に必要な内容”に絞り込み、従来の教科書より説明項目を少なくし、その代わり試験に出る項目の理解の助けになる説明と問題を解くためのテクニックをしっかりと解説する」というものである。試験では、過去に出題された問題と類似した問題が多く出される傾向にあるため、本書の半分の分量を使ってME2種と国家試験の過去問と解答を掲載した。必ずや受験に役立つものと思う。また、本書発刊後のME2種・国家試験問題と解答についても、コロナ社Webページの本書の関連資料に掲載を予定している。
【各章について】
第1章 ディジタルデータの表現方法
第2章 信号処理
第3章 論理回路
第4章 制御工学
第5章 変調
第6章 システムの信頼度
第7章 フローチャートとプログラム
第8章 いろいろな用語
付 録 ME2種過去問、国家試験過去問
【著者からのメッセージ】
本書は臨床工学技士を養成する大学・専門学校などの教科書として使用されることを想定しているが、独学で勉強する学生にとっても十分に利用できるように配慮したつもりである。本書がME2種・国家試験合格の一助になれば幸いである。
臨床工学技士養成校で学習する機械工学や電気・電子工学などは,その学問範囲が比較的明確である。それに対してシステム工学というのは,良くいえば広範囲の分野をカバー,悪くいえばいろいろな分野の寄せ集めである。いろいろな分野というのは,例えば論理演算,コンピュータプログラミング,制御工学,通信工学などであり,一貫性はない。要するに機械系や電気・電子系に含まれない工学分野をまとめて,システム工学と名付けているだけである。
寄せ集めといったのは,「第2種ME技術実力検定試験」(以下ME2種と呼ぶ)や「臨床工学技士国家試験」(以下国家試験と呼ぶ)での出題のされ方の話であって,これらの分野そのものは,それぞれ非常に重要な内容を含んでいる。コンピュータプログラミングなどは,小・中学生の必修科目となっているほどである。
多くの分野を含んでいるがゆえに「システム工学」の教科書は,多くの内容を盛り込まなければならない。例えば,制御工学は微分,積分,微分方程式,複素関数,ラプラス変換などを学んだ上で,その応用として理解されるべきものである。そのため,これまでの教科書はそういう数学分野の簡単な説明の後に,伝達関数などの説明を行っている。そうしたい気持ちはわかる。基本の理解をすっ飛ばして伝達関数の性質だけ学んでも意味がない。
しかし勉強する学生にとってみれば,少ないページ数で微分方程式やラプラス変換の説明をされてもまったく理解できないだろう。そのページは死ページとなるだけである。そして,ME2種や国家試験では上述した「それだけ学んでも意味がない」問題しか出ないのである。
そこで,本書はややこしい話はばっさりと切り捨てて,試験に出る内容とその解き方だけに注力した。
これまでの同シリーズのコンセプトは,説明の対象を「ME2種と臨床工学技士の国家試験に必要な内容」に絞り込み,従来の教科書より説明項目を少なくし,その代わり試験に出る項目の理解の助けになる説明と問題を解くためのテクニックをしっかりと解説する,というものであったが,本書でもこのコンセプトを引き継いでいる。
機械工学や電気・電子工学と同様に,システム工学も過去問どうしに強い相関がある。つまり過去問をしっかりとやりこめば,あなたが受験するときに「これ,やったことがある」となる可能性が高いのである。そこで,本書の半分の分量を使ってME2種と国家試験の過去問と解答を掲載した。必ずや受験に役立つものと思う。
本書発刊後のME2種・国家試験問題に関しては,コロナ社のWebページ
(http://www.coronasha.co.jp/)の本書の書籍紹介に掲載する予定である。本書と併せて活用していただきたい。
本書は,臨床工学技士を養成する大学・専門学校などの教科書として使用されることを想定しているが,独学で勉強する学生にとっても十分に利用できるように配慮したつもりである。本書が,ME2種・国家試験合格の一助になれば幸いである。
2025年2月
西村生哉
1.ディジタルデータの表現方法
1.1 10進法,2進法,16進法
1.2 ビットとバイト
2.信号処理
2.1 各種信号処理
2.1.1 移動平均
2.1.2 加算平均
2.1.3 SN比のdB表記
2.1.4 増幅度
2.1.5 微分処理
2.1.6 スプライン補完
2.1.7 自己相関係数
2.2 周波数解析
2.3 A-D変換
2.3.1 サンプリング定理
2.3.2 エイリアシング
3.論理回路
3.1 AND,OR,NOT
3.2 NAND,NOR,XOR
3.3 ブール代数
4.制御工学
4.1 伝達関数とブロック線図
4.2 一次遅れ系の伝達関数と時定数
5.変調
5.1 変調の種類と特徴
5.1.1 アナログ変調
5.1.2 ディジタル変調
5.1.3 パルス変調
5.2 分割多重
6.システムの信頼度
6.1 確率
6.2 機器の信頼度
6.2.1 直列の場合
6.2.2 並列の場合
6.3 検査の信頼度
6.3.1 ダブルチェック(同じ検査を二名で行う)
6.3.2 分担チェック(二人の点検項目が異なりかつたがいに独立している)
6.4 アベイラビリティ
6.5 誤差の蓄積
7.フローチャートとプログラム
7.1 プログラミング言語
7.2 フローチャート
8.いろいろな用語
【不正プログラム関連】
【失敗の原因を探る】
【失敗しないために】
【ネットワーク関連】
【ネットワークトポロジー】
【ファイルフォーマット,さまざまな規格】
【パソコンで使う画像・動画フォーマット】
【画像・動画・音声】
【コンピュータ部品,メモリ】
【コンピュータと人間のインタフェース】
【通信】
【情報セキュリティ】
【ディスプレイ】
【アンテナ】
【その他】
【過去のものとなりつつある技術】
付録
A. 第2種ME技術実力検定試験
A.1 問題
A.2 解答・解説
B. 臨床工学技士国家試験
B.1 問題
B.2 解答・解説
索引
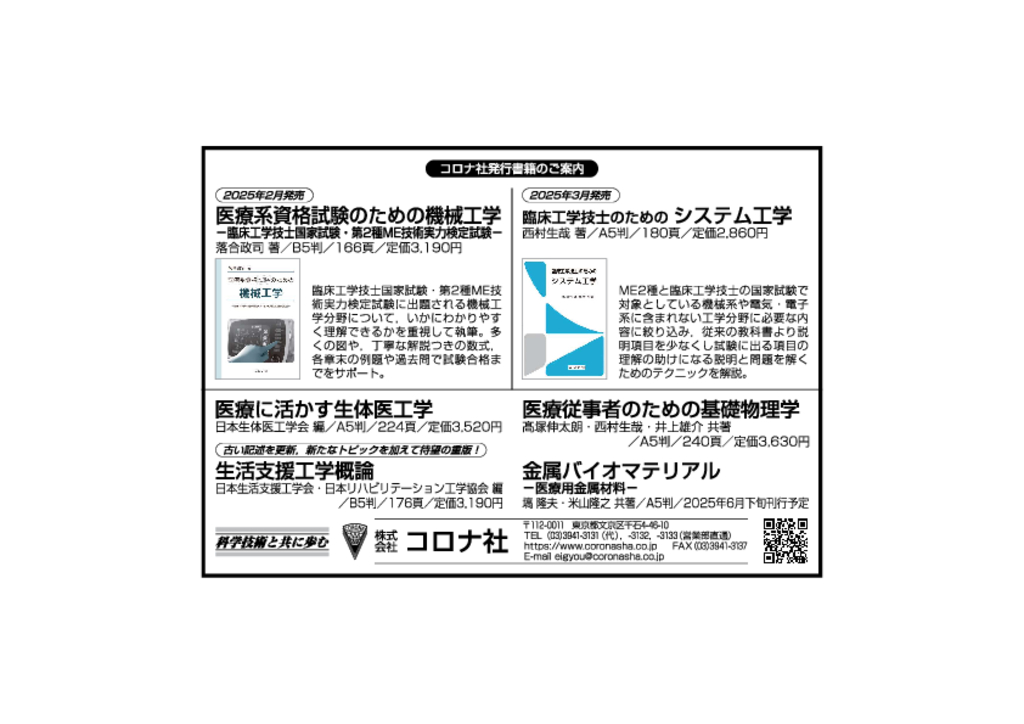
-
掲載日:2025/05/26
関連資料(一般)
- 【臨床工学技士国家試験】過去問題および解答・解説(2025年以降)