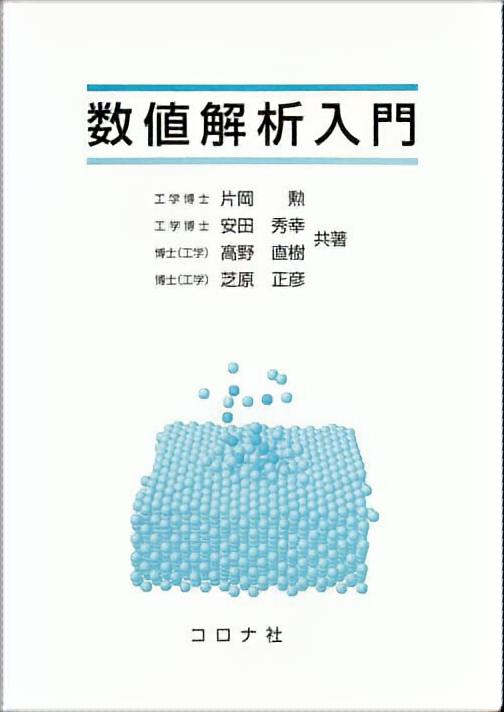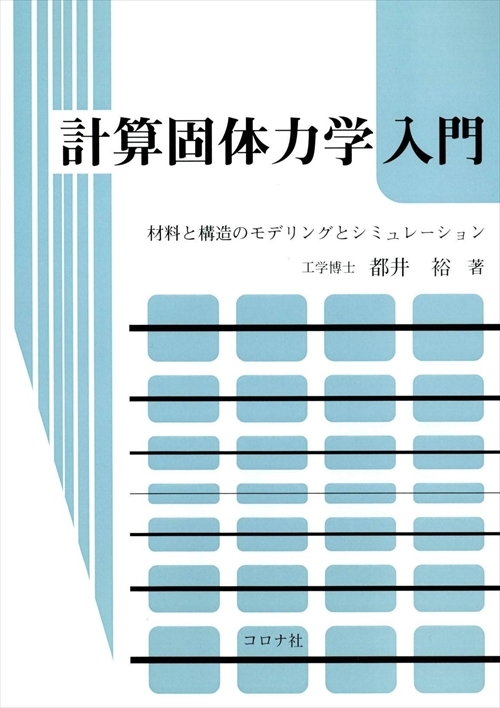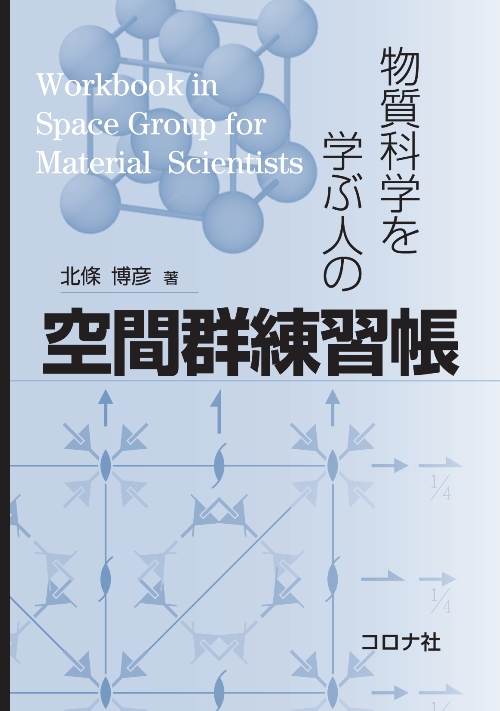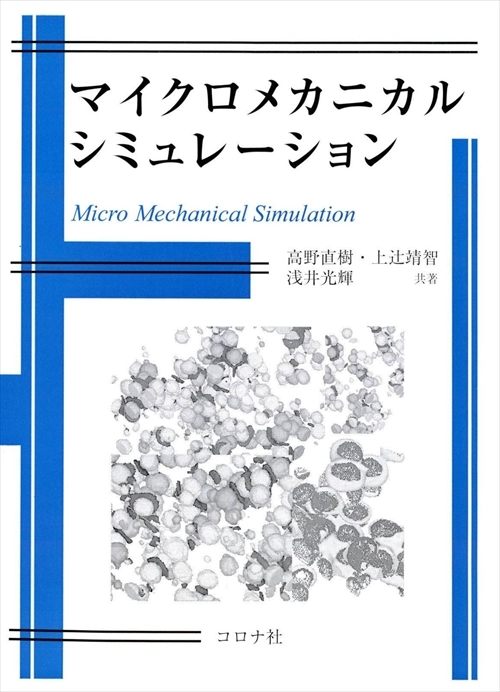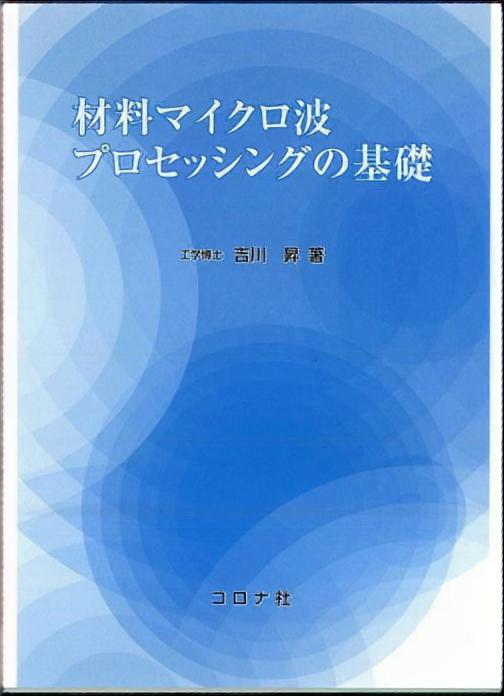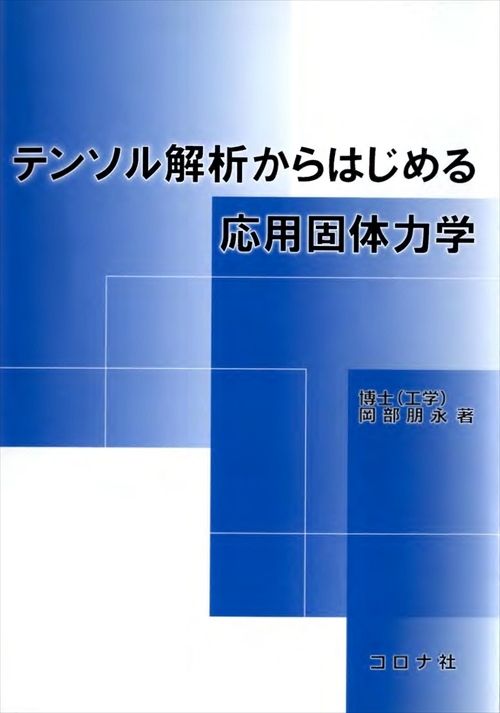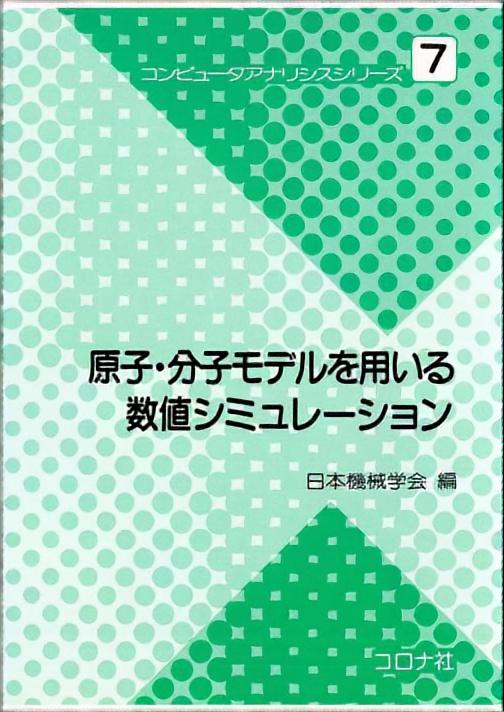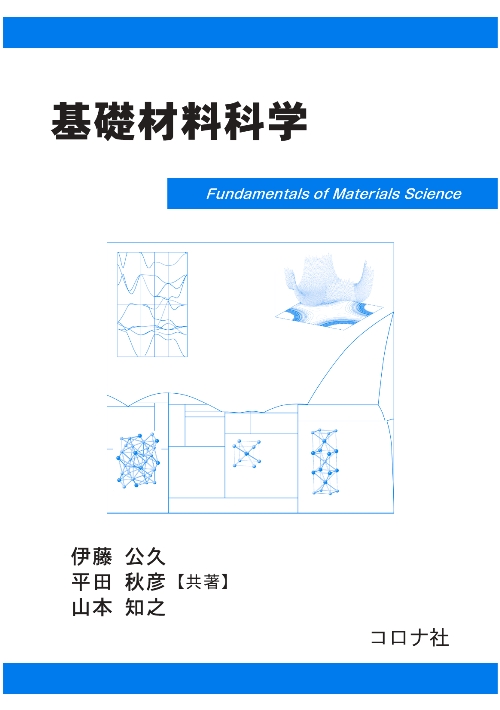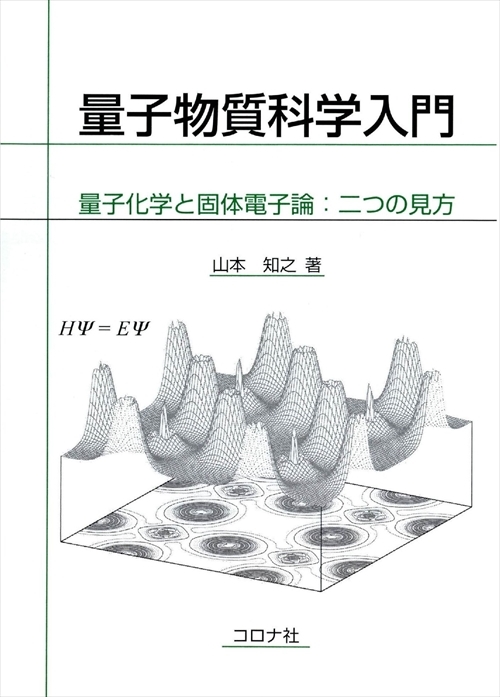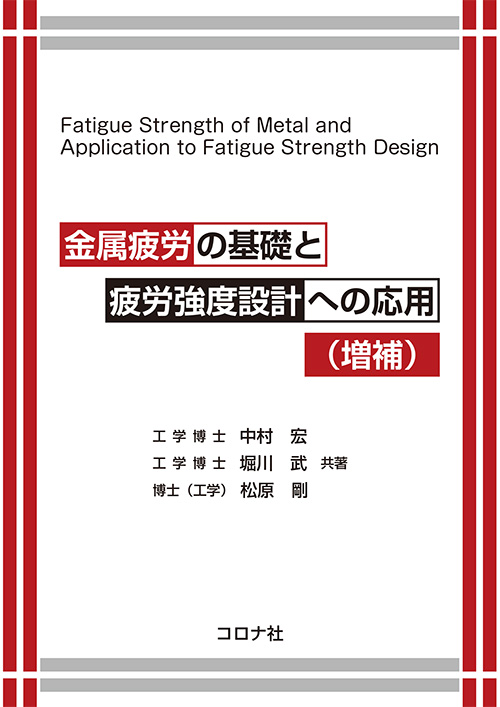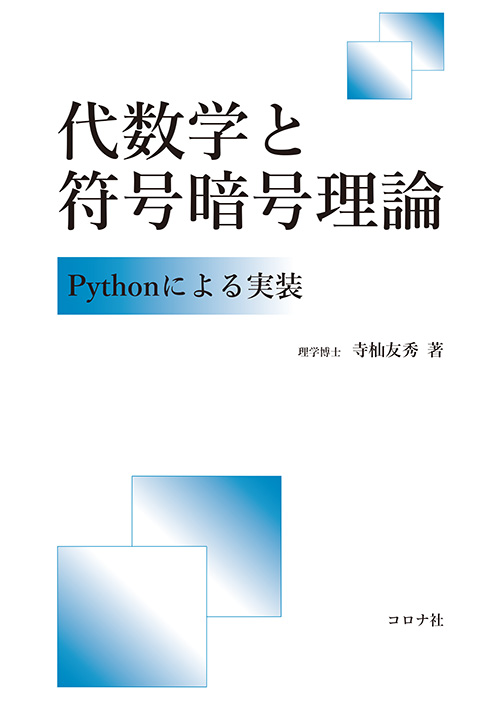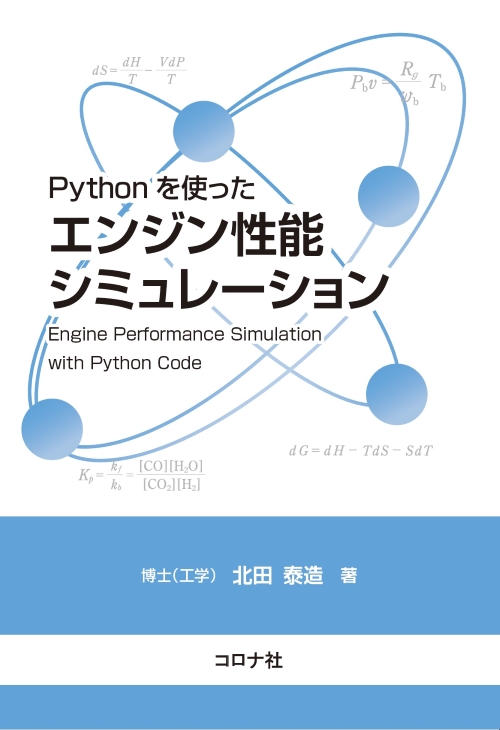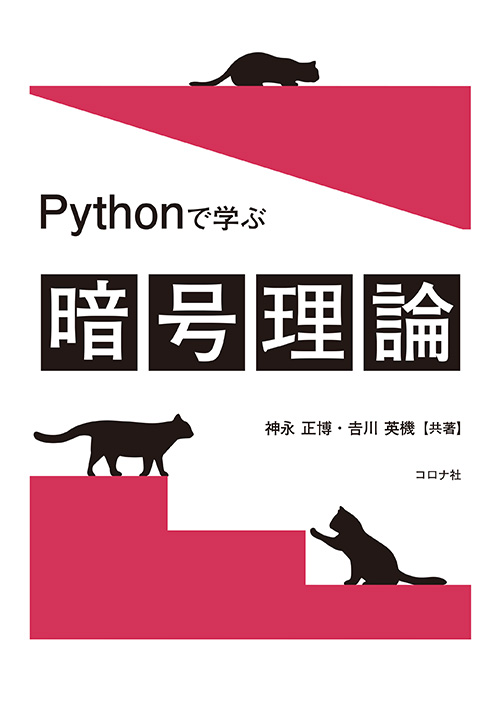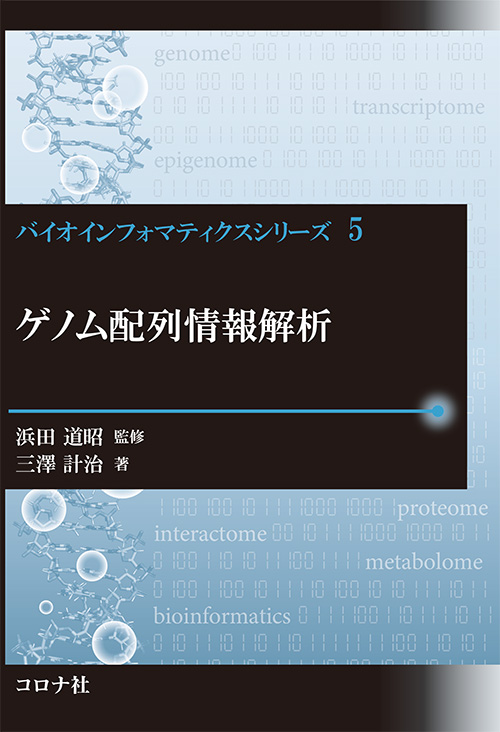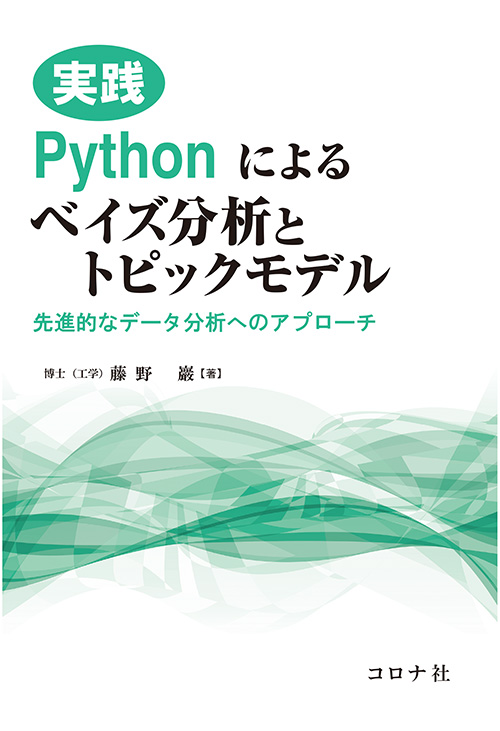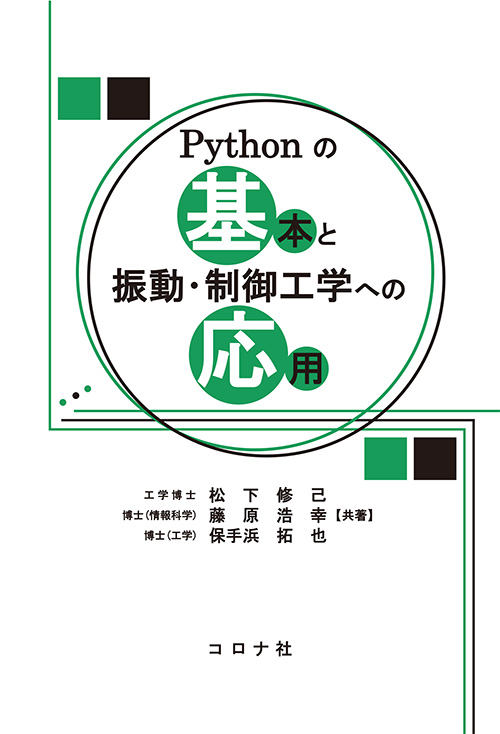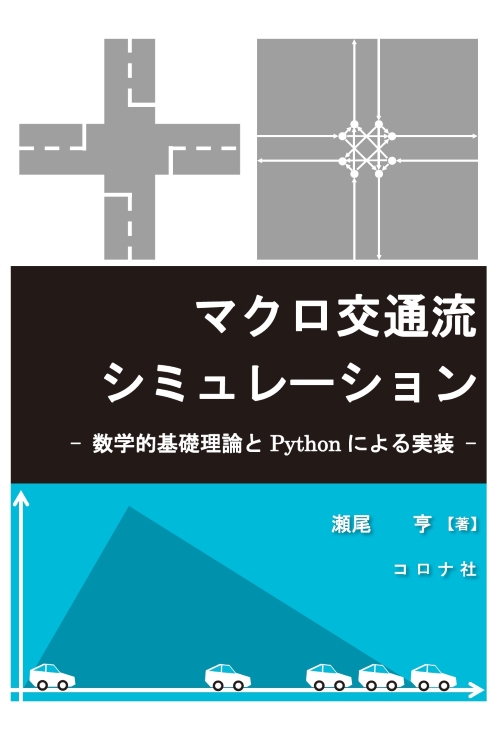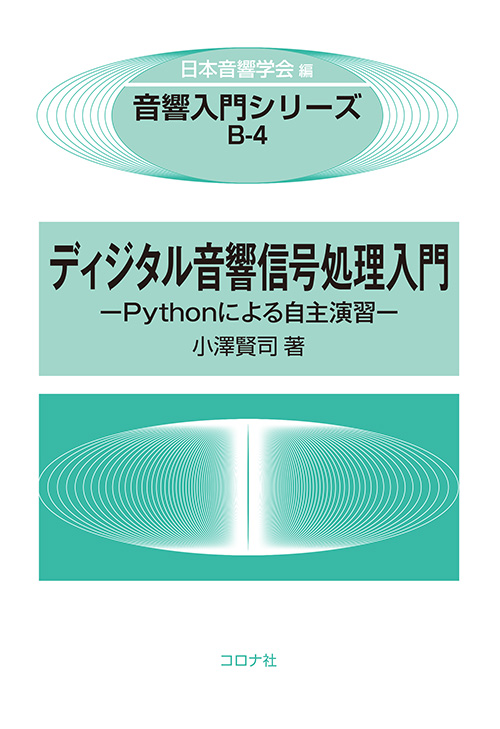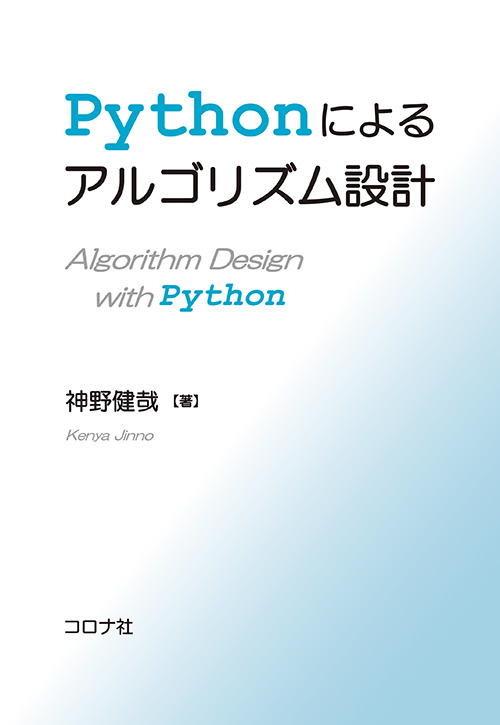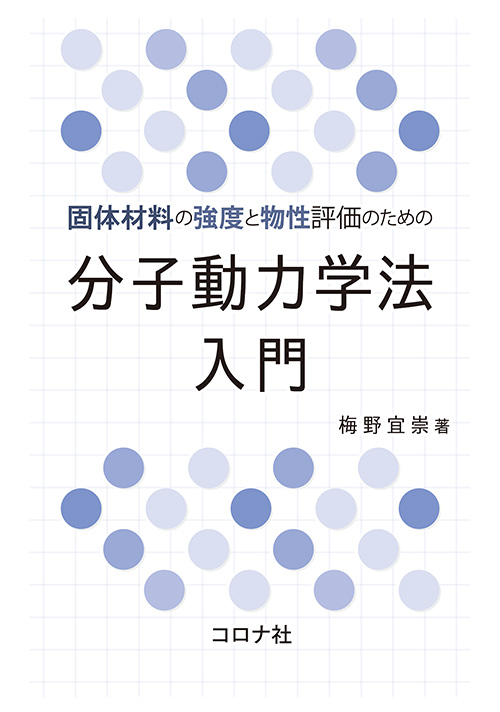
固体材料の強度と物性評価のための 分子動力学法入門
固体を対象とした,原子レベルのシミュレーションをプログラム演習つきで習得する入門編。
- 発行年月日
- 2025/12/12
- 判型
- A5
- ページ数
- 174ページ
- ISBN
- 978-4-339-04699-1
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
【読者対象】
本書は,分子動力学法(MD)を固体材料の強度・物性評価に応用したい学生や若手研究者を主な読者として想定しています。意欲ある学部生や他分野からの読者にも理解できるよう,予備知識がなくても読み進められる構成としています。
【書籍の特徴】
本書は,MDを用いて固体材料の強度や物性を評価するための理論と実践を,初学者にもわかりやすくまとめた入門書です。従来のMD教科書は液体や気体を対象としたものが多く,固体の機械的性質や構造安定性を扱った書籍は限られていました。本書はその空白を埋め,固体の変形・破壊・界面現象を原子レベルで理解したい方に向けて執筆されています。
理論だけでなく,シミュレーション実行に必要な計算手法と実務的知識を丁寧に解説している点も特徴です。周期境界条件や構造緩和,長距離相互作用,応力・エネルギー計算など,固体解析で欠かせない要素を具体例とともに紹介しています。また,なぜその手法が必要なのかという物理的背景の理解を重視し,研究への応用を意識した構成としています。
また,Pythonによる簡易な分子動力学プログラムを作成・実行する演習を用意しており,アルゴリズムの仕組みを実践的に学べます。既存ソフトを「使う」だけでなく,「仕組みを理解し改良する」力を養うことができます。著者のGitHubにプログラム例も公開されています。
さらに,各章の合間に「コーヒーブレイク」と題した小コラムを設け,研究経験やシミュレーションに関する話題を紹介しています。専門書でありながらも肩の力を抜いて読める構成です。最新の機械学習ポテンシャルにも触れ,今後のMD研究の発展を展望しています。理論・実践・展望を一冊で学べる点が,本書の最大の特徴です。
【各章について】
第1章:MDの歴史と基本概念,固体材料研究における位置づけを解説。
第2章:原子に働く力,運動方程式,積分法,温度・圧力制御,構造緩和など基礎理論を整理。
第3章:主要な原子間ポテンシャル(EAM,Tersoff,REBOなど)を紹介し,機械学習ポテンシャルにも触れています。
第4章:表面・界面エネルギー,応力,理想強度などの評価法を示し,強度解析への応用を解説。
第5章:段階的なプログラム演習を通じ,ナノワイヤの変形解析までを実践的に学べます。
第6章:Ewald法やTersoffポテンシャルの導出など,理論を深く理解するための補足を収録。
【読者へのメッセージ】
分子動力学法は,原子の運動を直接「見る」ことができる数少ないシミュレーション手法です。固体の強度や変形のメカニズムを原子レベルで理解することは,未来の材料設計に欠かせない基盤技術となりつつあります。
本書を通じて,MDの理論を「知る」だけでなく「使いこなす」力を身につけ,研究や開発に応用できるようになることを願っています。そして何より,「シミュレーションで物理現象を再現する面白さ」を実感していただければ幸いです。
【本書のキーワード】
分子動力学法,固体材料,強度,変形,破壊,原子間ポテンシャル,機械学習,構造緩和,応力,理想強度,ナノワイヤ,プログラミング,Python
分子動力学法(molecular dynamics;MD)は,原子一つひとつに対する運動方程式を考え,その運動の軌跡を数値計算によって求めるシミュレーション法である。各原子についてのニュートンの運動方程式を解くという,ある意味非常にシンプルな手法であり,もともとは液体における分子の振舞いを再現するためのシミュレーションとして用いられたが,1990年代以降は固体材料の強度問題や物性評価にも積極的に取り入れられるようになった。扱えるモデルのサイズなどに強い制限があるため,当初はよくいえば先進的な取組み,悪くいえば現実離れした役に立たないシミュレーション研究ととらえられた節もあった。しかしながら,その後の計算機能力の飛躍的な進歩に伴い,その有効性が徐々に認められるようになってきたといえる。
地球シミュレータ,京,富岳といったスーパーコンピュータ(スパコン)の名前は,専門家でなくとも耳にするようになり,その存在と発展は広く耳目を集めるようになった。そうした世界トップレベルのスパコンで行われる超大規模計算シミュレーションは,新聞などでもたびたび取り上げられ,世間を驚かせている。一方,研究室レベルで準備できるような中規模な並列計算環境でも,かなりの大規模計算が行えるようになり,一昔前までは考えられなかった計算が可能となってきている。
それでも,工業製品の機械的性能(例えば荷重に対する耐久性など)を直接評価するような,製品開発に直結するようなシミュレーションを分子動力学法で行うことは,いまだに簡単ではないのは事実である。どちらかといえば,開発現場において生じる問題について,そのメカニズム(原子レベルでなにが起こっているのか)をまずは明らかにしたいというような,いわゆるサイエンスの探求のために用いられる手法という側面が強いのが現状である。
しかしながら,原子や分子の動的挙動を直接(シミュレーションであるため,あくまで疑似的にではあるが)観察できるという点は,分子動力学法の大きな強みであり,それによってこそ得られる知見は非常に多いといえる。今後,さらなる計算機能力の向上が見込まれているだけでなく,機械学習・深層学習などを援用した新たな手法の開発も進められるなど,方法論的な進展にも注目すべきものがある。そのため将来的には,より実際的な問題へ適用範囲が広がっていき,工業的にもその重要性が大きく高まっていくものと期待される。現在,FEM(finite element method;有限要素法)を用いた応力解析や熱・流体シミュレーションは,製品設計の現場においても広く使用されており,今や工業製品開発のために欠かせないツールとなっているが,分子動力学法によるシミュレーションがそのような地位を占めるようになる時代が,やがてやってくるかもしれない。
分子動力学法について解説した教科書は,これまでも数多く出版されてきたが,同手法はもともと液体や気体への適用によって発展してきたという背景もあり,液体・気体系に対するシミュレーションを念頭に書かれた本が多い。特に,分子動力学法による固体材料の機械的特性評価を対象として書かれた本はまだ少なく,そのようなシミュレーションに興味のある初学者のための情報は,十分に整理されているとはいえない。
そこで本書では,固体材料の強度や物性評価を行うことを前提として,分子動力学法の基礎理論と基本的手法について解説することを目的とした。このようなシミュレーションに興味のある工学系の大学院生・若手研究者を,読者層の中心として想定している。固体の機械的特性に関する基礎知識があれば,本書の内容は学習しやすいと思われる。ただ,可能なかぎり予備知識は必要ないように,初学者に配慮しながら書いたつもりであるので,意欲のある学部生や,分野外の方にもぜひ手に取っていただければ幸甚である。
第1章では,分子動力学法の歴史を概観するとともに,固体材料の強度・物性評価における位置づけについて述べ,分子動力学法の長所と短所を解説した。また,いったいなんのためにシミュレーションを行うのか,という点はつねに考えていただきたいという思いから,シミュレーションというアプローチに対する考え方についても議論を深めた。
第2章では,分子動力学法の基礎理論について,できるだけ噛み砕きわかりやすく述べた。固体材料に対する変形シミュレーションを行うことを想定して,そのようなケースによく用いられる構造緩和の手法や,大規模系に適した長距離クーロン相互作用の処理など,他書ではあまり触れられない項目についてもカバーした。また第3章では,分子動力学法の肝ともいえる,原子間ポテンシャルについて解説した。固体材料のシミュレーションによく用いられてきたポテンシャルについては,具体的な関数形を示し,一部の有名なものはパラメータも記載した。原子周りの電子分極や電荷移動,化学反応を扱えるような複雑なポテンシャル,さらには最近のトレンドである機械学習ポテンシャルについても紹介したが,複雑になりすぎるものについては関数形の表示は割愛し,コンセプトの解説にとどめた。
第4章では,固体材料に対する強度・物性評価としてよく行われるものを取り上げ,その具体的な方法や注意点について解説した。応力や表面エネルギーといった,一般に(分野を問わず)広く評価される物性値だけでなく,固体の強度問題を議論する際に重要な評価法を紹介している。
本書のもう一つの特色は,第5章において,比較的簡単な分子動力学プログラムを書くための演習を用意したことである。著者の個人的な経験から,シミュレーション手法の概要を理解するために最も手っ取り早い方法は,実際にプログラムを書いてみることであると思われる。第5章では,まず非常に簡単なプログラムを書き,それに少しずつ拡張を加え機能をつけ足していくという形式で,最終的にはナノ材料の変形シミュレーションが行えるプログラムを完成させるようになっている。プログラミングの経験が豊富でない読者でも理解できるようにつとめたつもりなので,ぜひトライしていただきたい。なお,第5章で紹介したプログラムなどは,著者のGitHubリポジトリにて公開している。
また,本題からはやや外れるが,シミュレーションにまつわる四方山話をコーヒーブレイクとしていくつか盛り込んだ。著者の私見がかなり入っている部分もあり,必ずしも共感いただけるとは思っていないが,肩の力を抜いてお読みいただければ幸いである(もちろん,読み飛ばしていただいても支障はない)。
本書の刊行にあたり,株式会社コロナ社の担当者には,企画の段階から貴重なご意見を賜り,原稿について細部までのチェックと適切なご助言をいただいた。また,研究室の若本達哉氏,谷村瞭氏には原稿の試読に加え,第5章のプログラムについて詳細なご指摘をいただいた。皆様のご協力に,心より感謝を申し上げたい。
2025年10月
梅野宜崇
1.分子動力学法とは
1.1 分子動力学法の概要と歴史
1.2 材料強度物性評価における分子動力学法の位置づけ
1.2.1 分子動力学法の長所と短所
1.2.2 モデリングなのか,数値実験なのか
1.3 汎用ソフトウェア
2.分子動力学法の基礎
2.1 原子に働く力とポテンシャル関数
2.2 運動方程式と数値積分
2.2.1 Verlet法
2.2.2 速度Verlet法
2.2.3 Gearの予測子・修正子法
2.3 周期系における計算
2.3.1 周期境界条件
2.3.2 カットオフ距離
2.3.3 bookkeeping(粒子登録)法
2.3.4 領域分割(セルインデックス)法
2.4 アンサンブルと温度・応力制御
2.4.1 速度スケーリング法による温度制御
2.4.2 Nosé-Hoover法による温度制御
2.4.3 圧力(応力)制御法
2.4.4 圧力・温度制御法
2.4.5 拡張系MDにおける仮想質量設定
2.5 構造緩和計算
2.5.1 BFGS法
2.5.2 gloc
2.5.3 FIRE
2.6 ポテンシャル計算に関連する手法
2.6.1 クーロンエネルギーの計算法
2.6.2 カットオフの取扱い
コーヒーブレイク:シミュレーションの「地位」
3.原子間ポテンシャル
3.1 2体間ポテンシャル
3.1.1 Morseポテンシャル
3.1.2 LJポテンシャル
3.1.3 Buckinghamポテンシャル
3.1.4 BMHポテンシャル
3.1.5 2体間ポテンシャルの問題点
3.2 3体間ポテンシャル
3.2.1 SWポテンシャル
3.2.2 Tersoffポテンシャル
3.3 多体ポテンシャル
3.3.1 EAM(原子挿入法)ポテンシャル
3.3.2 MEAMポテンシャル
3.3.3 ADP
3.4 ボンドオーダーポテンシャル(BOP)
3.4.1 EDIP
3.4.2 Brenner(REBO)ポテンシャル
3.5 より複雑なポテンシャル
3.5.1 シェルモデル・ダイポールモデル
3.5.2 電荷移動ポテンシャル・反応力場(ReaxFF)
3.5.3 機械学習ポテンシャル
コーヒーブレイク:機械学習ポテンシャルの商業化
4.分子動力学法による物性評価
4.1 表面・界面のエネルギーと応力
4.1.1 表面・界面エネルギー
4.1.2 表面応力
4.2 バルク部の応力の評価
4.2.1 原子系における応力の定義
4.2.2 ビリアル定理による応力の算出
4.2.3 応力分布の評価法
4.3 理想強度評価と結晶すべり
4.3.1 理想強度
4.3.2 GSF(一般化積層欠陥)エネルギー
4.3.3 結晶すべりの可視化
4.4 構造安定性と臨界荷重の評価
4.4.1 変形解析と構造緩和
4.4.2 不安定平衡の問題
コーヒーブレイク:MDは「異端」?
5.プログラミング演習
5.1 MDコア部分の実装
5.1.1 原子3個の配置
5.1.2 Verlet法の実装
5.1.3 3次元への拡張とエネルギー計算
5.1.4 cfgファイルの書き出しと可視化
5.2 周期境界条件の実装
5.2.1 結晶構造ファイルの作成
5.2.2 結晶モデルの計算
5.2.3 bookkeeping法の実装
5.2.4 温度制御
5.2.5 応力計算
5.2.6 平衡状態の格子定数の計算
5.3 ナノワイヤモデルの引張解析
5.3.1 1次元周期境界の適用
5.3.2 原子構造緩和
5.3.3 準静的引張解析
5.3.4 引張解析の継続
5.3.5 緩和前加熱
5.4 EAMの実装
5.4.1 メッシュデータの利用
5.4.2 メッシュデータの作成
コーヒーブレイク:コードを書くべきか
補遺
A.1 Ewald法の式の導出
A.1.1 式(A.3)の証明
A.1.2 式(A.15)の証明
A.1.3 式(A.19)の証明
A.2 Tersoffポテンシャルにおける力の表式
A.2.1 初期バージョン
A.2.2 bの微分項
A.2.3 ζの微分項
A.2.4 Multicomponentバージョン
A.2.5 カットオフ関数の微分項
引用・参考文献
索引
読者モニターレビュー【 べっちぃー 様(業界・専門分野:半導体工学)】
金属や半導体を含む多様な固体材料を対象に、分子動力学法(MD)を基礎から応用まで体系的に解説しており、大学の入門教材としても社会人のリスキリング教材としても適している。
特に、半導体結晶材料の強度評価や欠陥・破壊挙動の捉え方など、実務の課題に直結しやすい観点で整理されている点が有用である。
さらに、Pythonを用いたシミュレーション例が掲載されているため、理論理解に留まらず手を動かしながら学習を進められ、再現性の高い学びにつながる。
加えて、量子力学と併せて学ぶことで、原子間相互作用や材料物性の背景理解が深まり、より立体的に内容を吸収できると考える。
関連資料(一般)
- 第5章のプログラムなど(GitHub)