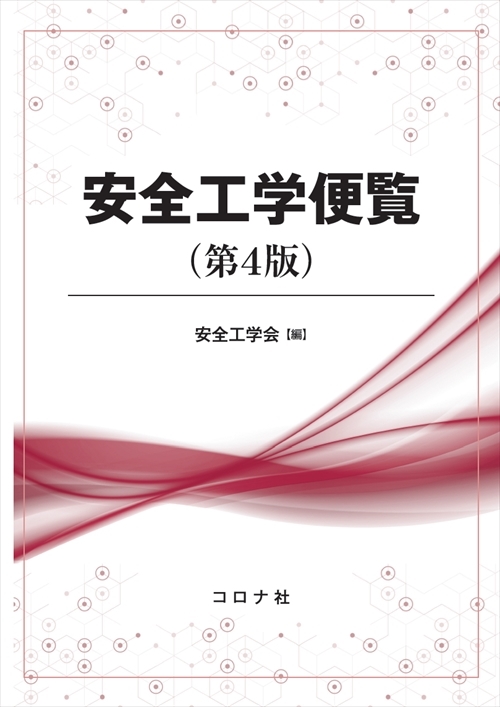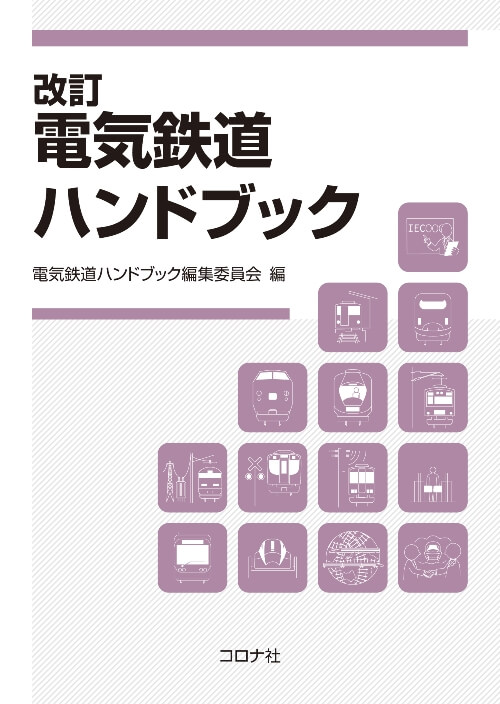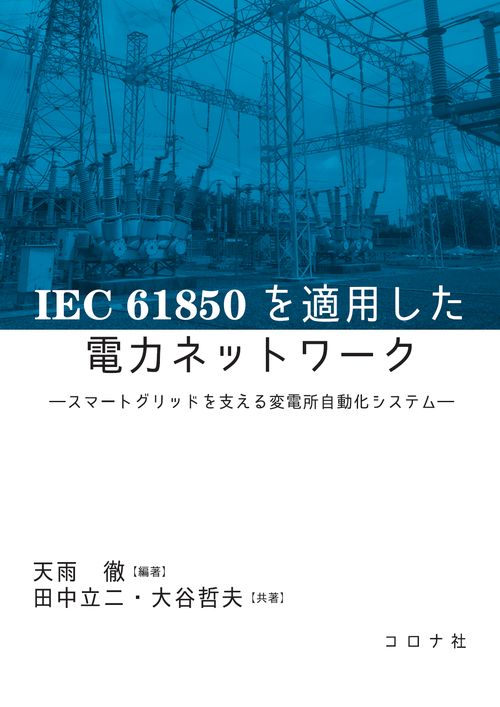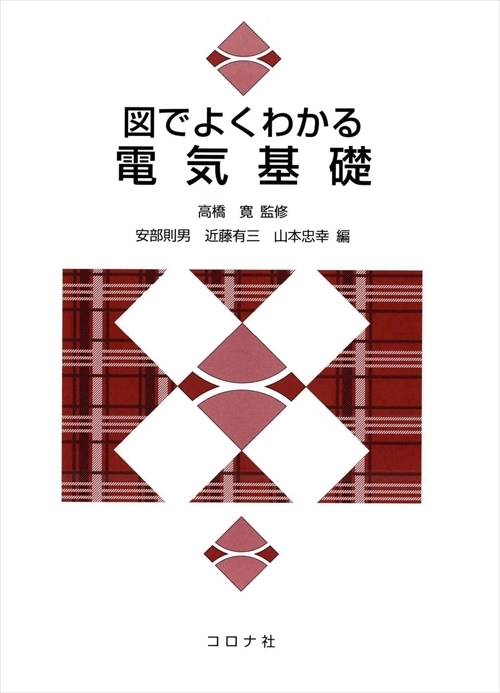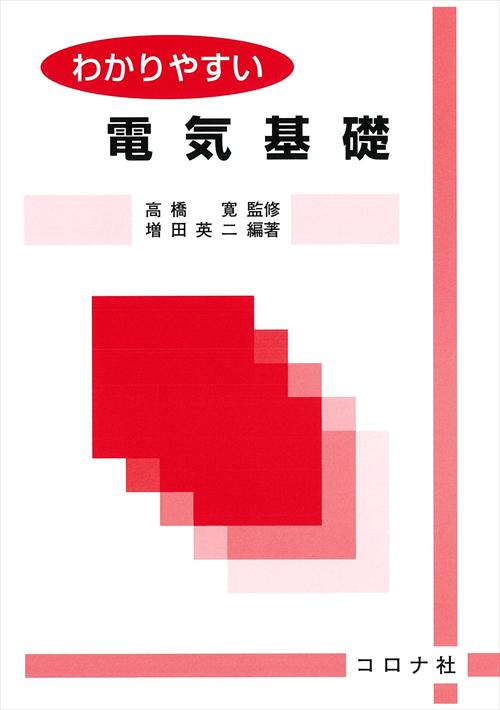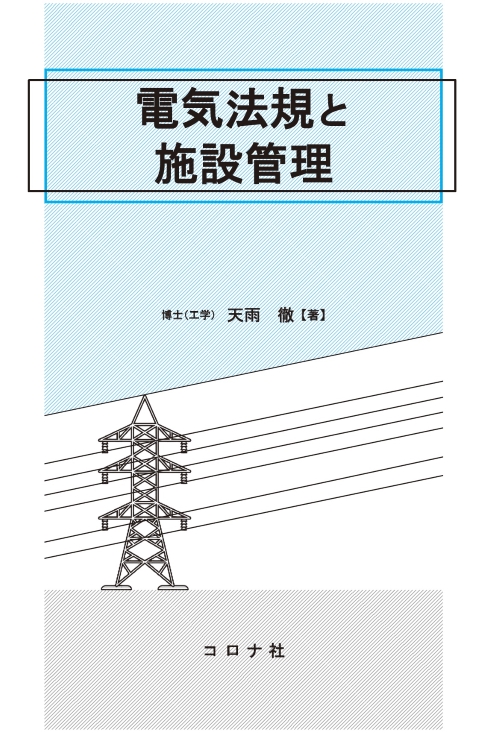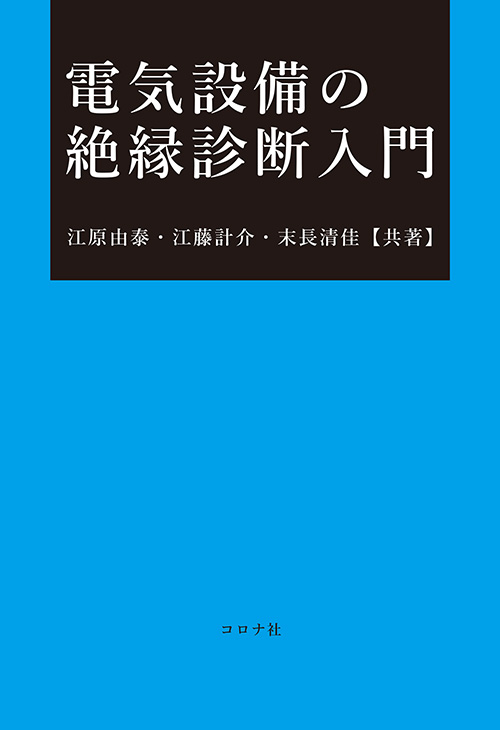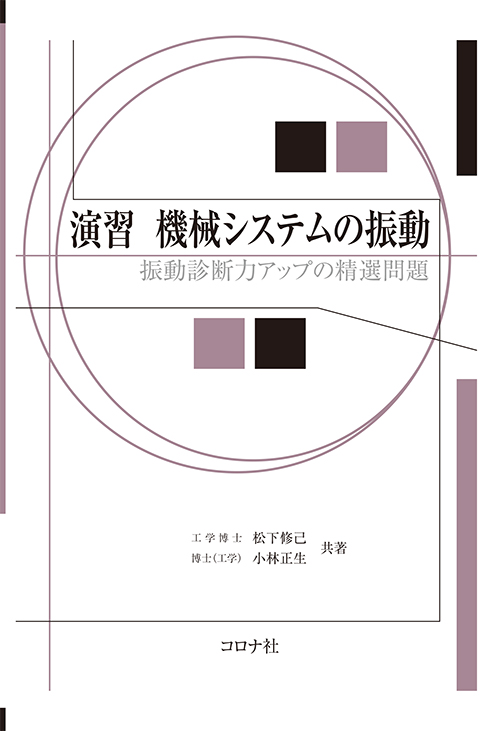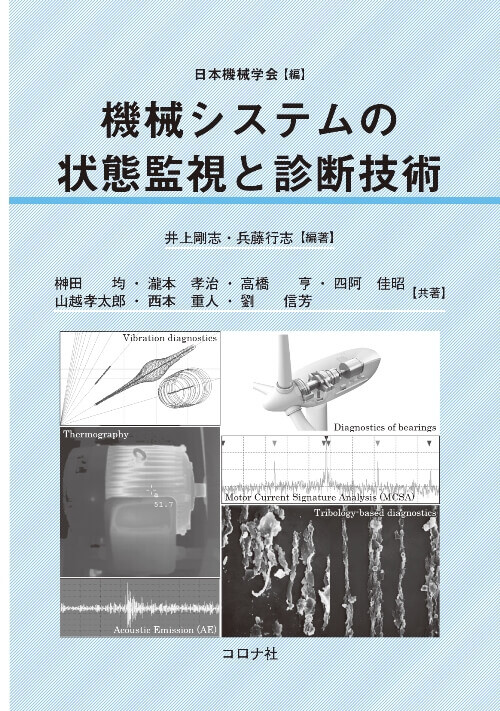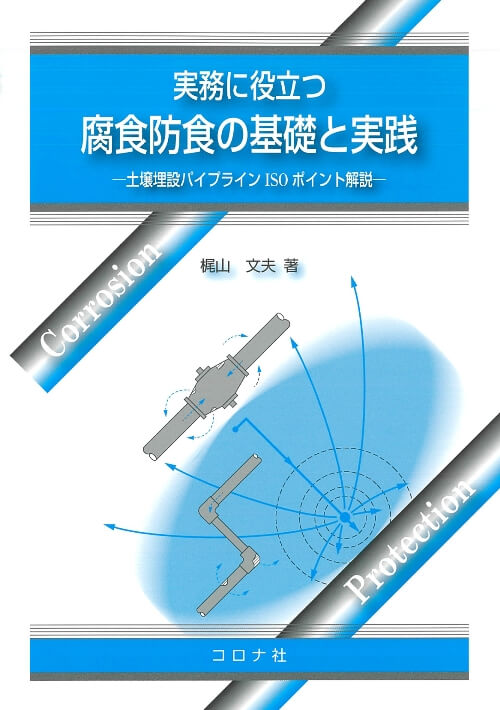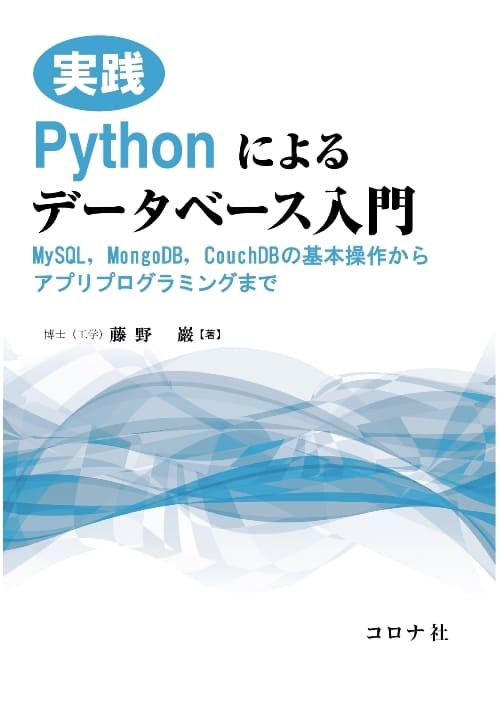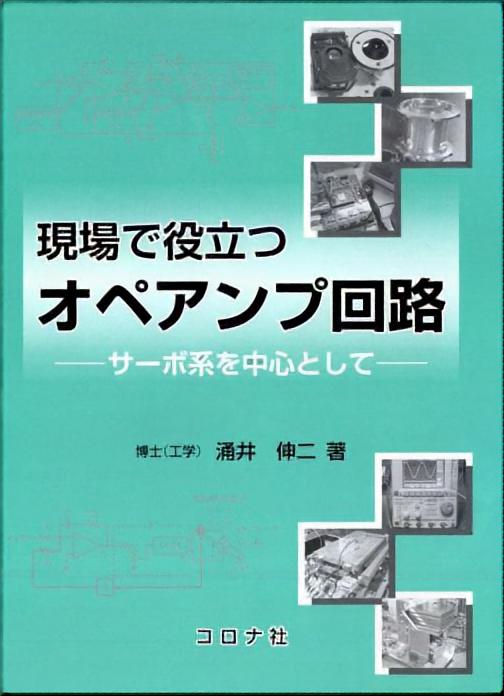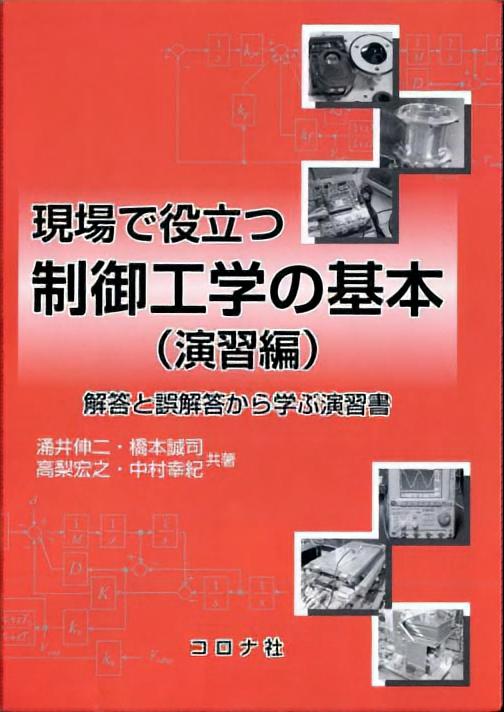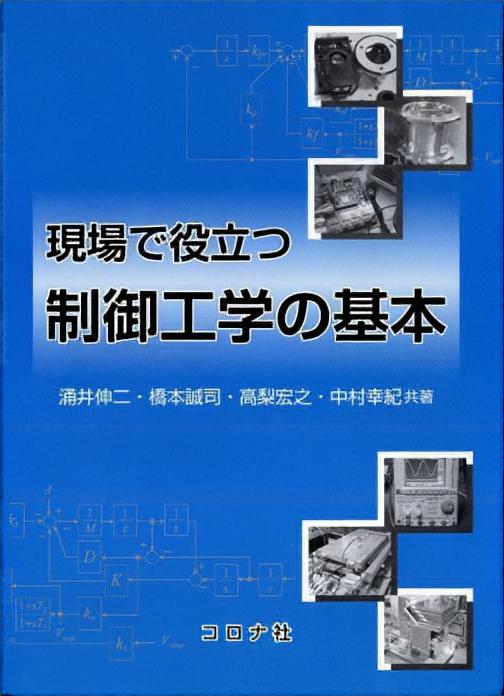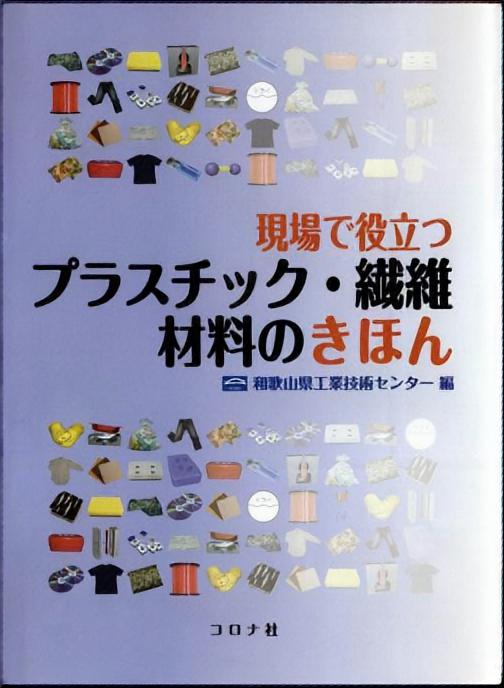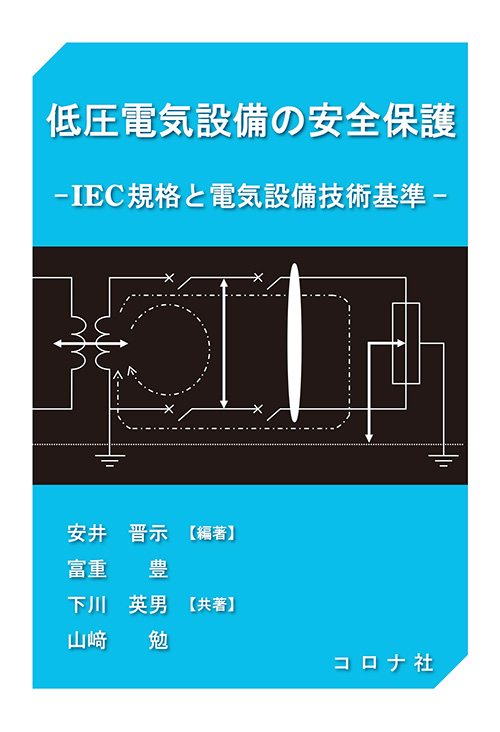
低圧電気設備の安全保護 - IEC規格と電気設備技術基準 -
国内の規格と海外のIEC規格の比較・解説を通して,低圧電気設備の安全保護を学ぶ。
- 発行年月日
- 2022/09/22
- 判型
- A5
- ページ数
- 238ページ
- ISBN
- 978-4-339-00983-5
- 2023年(令和5年)電気設備学会 著作賞
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- 広告掲載情報
本書では,需要場所における低圧電気設備の安全保護のうち,感電保護,過電流保護および過電圧保護に関する規定として,電気設備技術基準(電技)およびその解釈(電技解釈)とIEC 60364 シリーズを対象に,可能な範囲で両規格を比較しながら解説することとした。電気設備に携わる技術者に対して,電気設備における安全保護の基本的な考え方の理解を促すとともに,具体的な保護方法の選定・施工方法を正しく理解できるように,以下に示す視点から平易に解説しようとするものである。
① 故障などが発生する原因とそれによって生じる被害などについて,メカニズムを示すとともに,故障などに対する保護方法の考え方を解説する。
② 電気設備の安全保護に関する基準の技術的根拠,工学的背景を解説する。
③ 電技および電技解釈とIEC 規格とを対比させながら,安全保護の本質的な事項を理解するとともに,国際的な動向の把握の一助とする。
④ 接地系統の種類と,それらの電気的観点における差異を明確にする。
⑤ 安全保護には,故障などが発生しないように事前の対策として行う保護と,それでも発生してしまった故障などによる被害を最小限にするための保護の二つがあることを理解する。
また,設計や施工の実務者が具体的に業務を行う際に役立つように試算例を示し,加えて,電技解釈やIEC 規格の具体的な内容や,それに基づく電気設備の設計方法および計算例などの詳細を,Web 資料に記載した。
【著者からのメッセージ】
電気設備工事は電技とそれを補完する電技解釈などに従って,適切に行わなければなりません。また,海外での電気設備工事においては,その国の基準で行う必要がありますが,多くは国際規格であるIEC規格が活用されています。しかしながら,使用電圧や電気配線の仕組みが国内外で異なることもあり,慣れ親しんだ日本国内の規格とこのIEC規格とを対比させた解説が欲しいところですが,そういった書籍は見当たりませんでした。本書では,低圧(600V以下)の電気設備の安全保護を対象として,電技及び電技解釈とIECの低圧電気設備の安全保護の規格を対比させながら,体系的に理解できるよう解説するとともに,その技術基準の工学的根拠と実際の設計方法までを含めて解説しています。
本書をとおして,電気工事士や電気主任技術者など電気系の資格取得を目指す諸学者,あるいは自治体や企業の電気系技術者,さらには,海外での業務を担当する実務者の方の理解の一助となれば幸いです。
世界的にカーボンニュートラルに向けた実効的な対策が求められる中で,わが国においても風力発電や太陽光発電など自然エネルギーを利用した発電技術の導入が進められており,一般住宅でも太陽光発電設備や蓄電池設備が普及し始めています。また,IoT社会に伴うデータセンターや電気自動車の普及に伴う新しいインフラ設備の増加や,電気設備の老朽化に伴うリニューアル工事など,交流配線に限らず直流配線も含めて多様に電気設備技術者の活躍の場が広がっています。一方で,電気工作物の破損や感電死傷も含めた電気事故件数は横ばい状態であり,なかなかなくならないのが実態です。
そこで筆者らは,電気を扱う技術者が知っておくべき安全保護について,体系的に理解できる解説書の作成を目指しました。電気設備工事は電気設備の技術基準とそれを補完する解釈および内線規程などに従って,適切に行わなければなりません。また,日本の製造業の海外進出に伴い,東南アジア圏内での工場の建設も進んでいます。この際,海外での電気設備工事はその国の基準で行う必要がありますが,多くは国際規格であるIEC規格が活用されています。
しかしながら,使用電圧や電気配線の仕組みが国内外で異なることもあり,慣れ親しんだ日本国内の規格とこのIEC規格とを対比させた解説が欲しいところですが,そういった書籍は見当たりません。
本書では,低圧(600V以下)の電気設備の安全保護を対象として,電気設備の技術基準とIECの低圧電気設備の安全保護の規格を対比させながら,その技術基準の理論的根拠と実際の設計方法までを含めて解説しています。安全保護の各項目では,それぞれの要因が発生するメカニズムと具体的な対策方法について,技術的根拠を示しながらわかりやすく解説するように心がけました。また,設計や施工の実務者が具体的に業務を行う際に役立つように,試算例も示しました。加えて,電気設備の技術基準やIEC規格の具体的な内容,それに基づく電気設備の設計方法および計算例などの詳細を,Web資料に記載しました。実際に業務を行う担当者の方には参考にしていただきたいと思います。
最後に,本書は電気工事士や電気主任技術者など電気系の資格取得を目指す大学・高専の諸学者,あるいは自治体や企業の電気系技術者を念頭において執筆されています。また,海外での業務を担当する実務者の方にも,理解の一助となれば幸いです。
2022年6月
安井 晋示
第Ⅰ編 電気設備と安全保護
1.電気設備と安全保護
1.1 使用方法を誤ると危険な電気
1.2 電気設備の安全性とその方策
1.2.1 電気設備の安全性
1.2.2 電気保安四法
1.3 電気設備に関する国内の技術基準
1.3.1 電技
1.3.2 電技解釈
1.3.3 電技および電技解釈の構成
1.4 電気設備に関する国際的な技術基準
1.4.1 IEC60364シリーズ
1.4.2 IEC61936-1
1.5 電技への国際規格の取り入れと適用
1.5.1 電技への国際規格の取り入れ
1.5.2 IEC規格適用上の留意事項
1.6 低圧電気設備における電技解釈とIEC60364シリーズとの比較
1.6.1 基本的な考え方に差異はない
1.6.2 規定内容に差異がある
1.6.3 本書で扱うおもなIEC規格
第Ⅱ編 感電保護
2.感電の本質と接地の役割
2.1 地絡と感電
2.1.1 地絡および感電とは
2.1.2 感電の発生メカニズム
2.2 感電保護における接地の役割
2.2.1 系統接地
2.2.2 保護接地
2.3 接地系統の種類と接触電圧
2.3.1 接触電圧
2.3.2 接触電圧のまとめ
2.4 主要国の接地系統と配電電圧
3.感電における安全限界
3.1 人体を通過する電流の影響
3.2 心室細動の発生メカニズム
3.2.1 心臓のポンプ機能
3.2.2 心室細動の発生
3.3 人体通過電流の安全限界
3.3.1 IEC規格
3.3.2 低圧地絡保護指針
3.3.3 限界値の比較
3.4 接触電圧の制限
3.4.1 IEC規格における安全電圧
3.4.2 低圧地絡保護指針
3.4.3 電技解釈
4.感電保護の考え方とその対策
4.1 感電保護の種類と体系
4.1.1 IEC規格
4.1.2 電技解釈
4.1.3 電技解釈とIEC規格の差異
4.2 基本保護(直接接触保護)
4.2.1 基礎絶縁の種類
4.2.2 IEC規格の離隔
4.2.3 電技解釈での離隔
4.3 故障保護(間接接触保護)
4.3.1 電源の自動遮断による故障保護
4.3.2 電気的分離
4.3.3 非導電性環境による保護
4.3.4 離隔(電技解釈のみの故障保護)
4.3.5 低抵抗接地による保護(電技解釈のみの故障保護)
4.4 二重絶縁または強化絶縁
4.4.1 二重絶縁
4.4.2 強化絶縁
4.5 低電圧による保護
4.5.1 IEC規格
4.5.2 電技解釈
4.5.3 IEC規格と電技解釈の比較
第Ⅲ編 過電流保護
5.過負荷保護
5.1 配線設備の過負荷保護の原則
5.2 回路の設計電流
5.2.1 IEC規格
5.2.2 電技解釈(幹線)
5.3 配線の許容電流
5.3.1 IEC規格
5.3.2 電技解釈(絶縁電線)
5.3.3 内線規程(ケーブル)
5.3.4 IEC規格と電技解釈,内線規程による許容電流の求め方の相違点
5.4 過負荷保護装置の選定
5.5 分岐回路の過電流保護(電技解釈のみ)
6.短絡保護
6.1 配線の短絡保護の原則
6.2 短絡保護装置の設置
6.2.1 設置位置
6.2.2 移動および省略
6.2.3 省略する場合の注意点
6.2.4 電源側のインピーダンスが大きい場合の注意点
6.3 推定短絡電流
6.3.1 推定短絡電流を求める方法
6.3.2 IEC規格によるトライアングル法則
6.3.3 電技解釈による短絡保護装置の遮断電流
6.4 短絡保護装置の選定
6.4.1 全容量遮断方式
6.4.2 限流遮断方式
6.4.3 カスケード(バックアップ)遮断方式
6.5 配線設備の短絡時許容電流
6.5.1 IEC規格
6.5.2 日本電線工業会規格JCS0168-1
6.5.3 IEC規格とわが国の短絡時許容電流の比較
7.過電流保護の実施
7.1 各施設形態における実施例
7.1.1 系統パターンに応じた過電流保護装置の配置
7.1.2 系統パターン別過電流保護の特徴
7.2 過電流保護装置
7.2.1 中性線の保護―多相系統の中性線の遮断および投入
7.2.2 高調波環境における多相系統の中性線の保護
7.3 過電流保護装置の動作協調
7.3.1 過負荷保護装置の動作協調
7.3.2 全容量遮断における短絡保護装置の動作協調
7.4 過電流保護に関連する法令および規格
第Ⅳ編 過電圧保護
8.高圧側の故障による過電圧
8.1 発生のメカニズム
8.1.1 高圧側の地絡
8.1.2 高低圧混触
8.2 低圧側に発生する過電圧の大きさ
8.2.1 高圧側の地絡
8.2.2 高低圧混触
8.2.3 低圧側発生過電圧の一覧
8.3 過電圧の保護対策
8.3.1 電圧の制限値
8.3.2 IEC規格によるRAの算出
8.3.3 電技解釈によるRBの算出
9.低圧側の故障による過電圧
9.1 中性線欠相による過電圧
9.1.1 発生のメカニズム
9.1.2 保護対策
9.2 多相回路における充電線1線地絡による過電圧
9.2.1 発生のメカニズム
9.2.2 発生する過電圧
9.2.3 保護対策
10.大気現象による過渡過電圧
10.1 雷サージ過電圧の発生メカニズム
10.2 雷サージの種類と雷保護規格
10.2.1 雷サージの種類
10.2.2 雷保護規格
10.3 配電線伝搬雷サージに対する保護対策
10.3.1 過電圧カテゴリとインパルス耐電圧
10.3.2 過渡過電圧抑制のための措置
10.4 直撃雷に対する低圧機器の保護対策
資料A2 接地線および接地極の共用に関する考察
資料A4 IEC規格における漏電遮断器の最大遮断時間の設定
資料A7 接地設備の構成と要求性能
資料C1 過電圧の発生と保護の考え方
引用・参考文献
索引
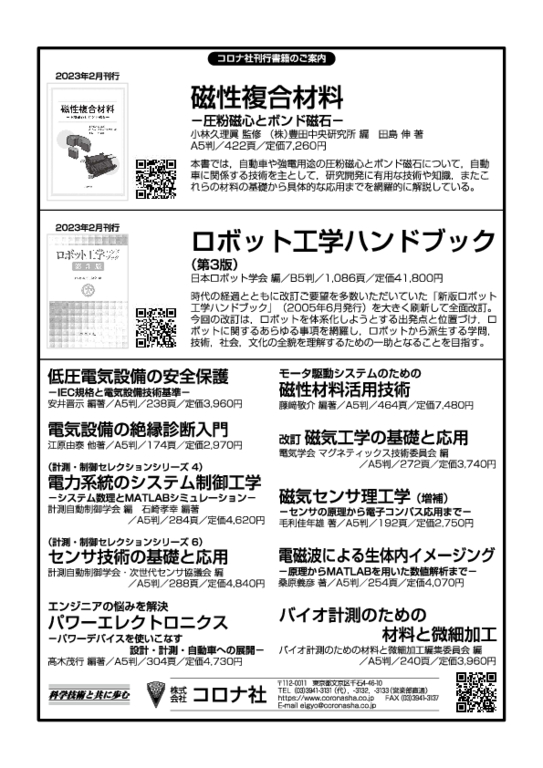
-
掲載日:2023/03/20
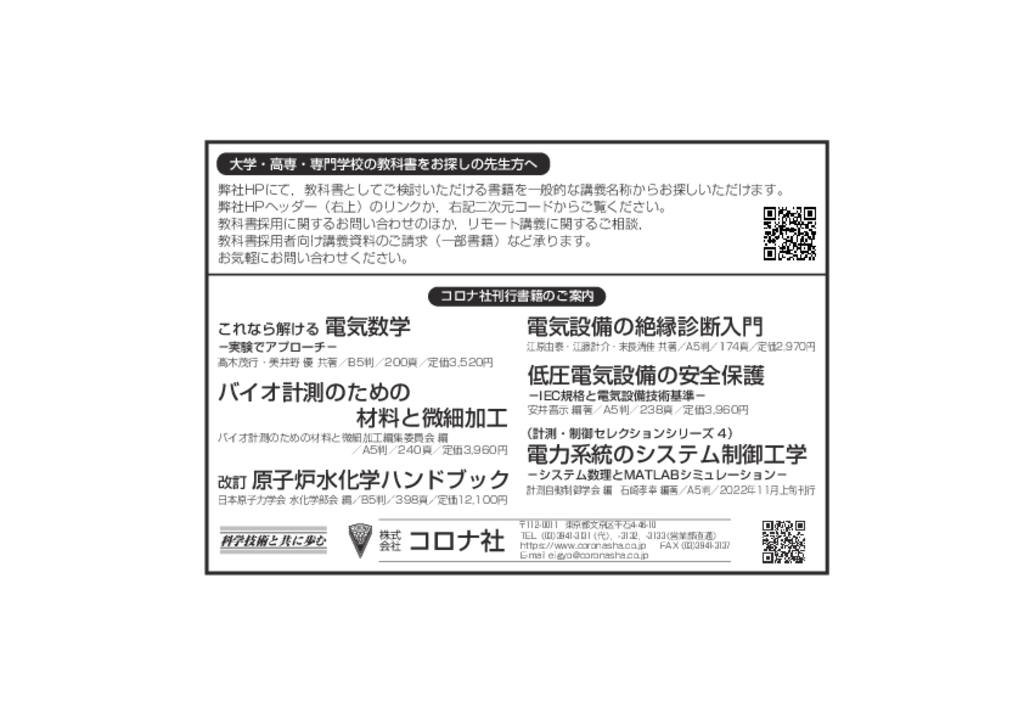
-
掲載日:2022/10/21
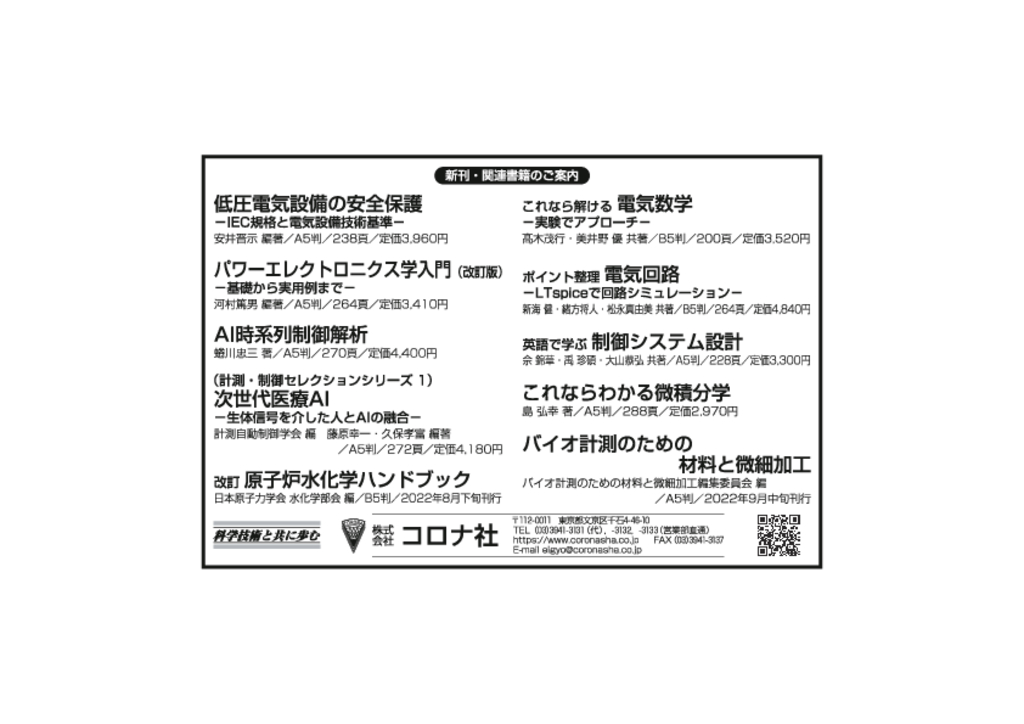
-
掲載日:2022/09/01

-
掲載日:2022/08/31
関連資料(一般)
- Web資料パスワードのヒント
- 資料 A1 わが国における系統接地のはじまり
- 資料 A3 接地系統の種類とその特徴
- 資料 A5 電気機器の感電保護クラス
- 資料 A6 電気機器の保護特級(IP コード)
- 資料 A8 漏電遮断器の普及とその歴史
- 資料 A9 漏電遮断器の形式試験に用いられる試験電流波形と適用条件
- 資料 A10 遮断器における「住宅用」と「産業用」の相違点
- 資料 B1 過電流の発生原因と過電流保護の手段および過電流保護の範囲
- 資料 B2 過電流として扱わない電流
- 資料 B3 幹線設計の手順
- 資料 B4 過電流保護装置
- 資料 B5 多相回路の中性線の過電流
- 資料 B6 幹線分岐配線の短絡時許容電流の試算
- 資料 B7 推定短絡容量の算出方法
- 資料 B8 電圧降下計算
- 資料 B9 過電流保護に関する IEC 規格と電技/電技解釈との対比
- 資料 C2 系統接地(B 種接地)の要求性能
- 資料 C3 過電圧保護装置の選定と施工方法