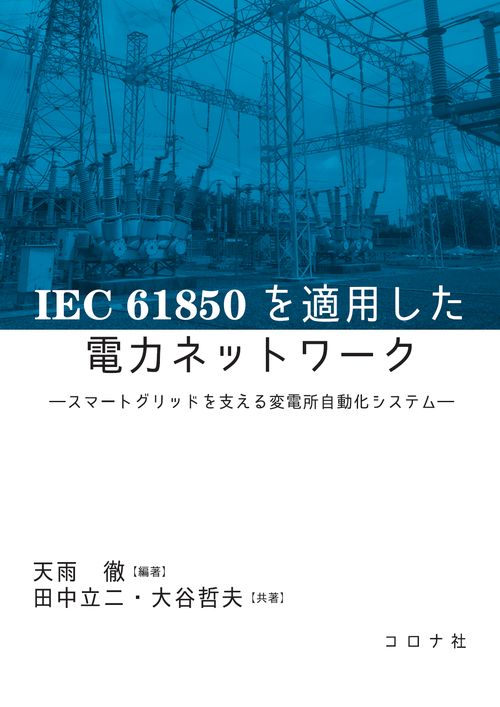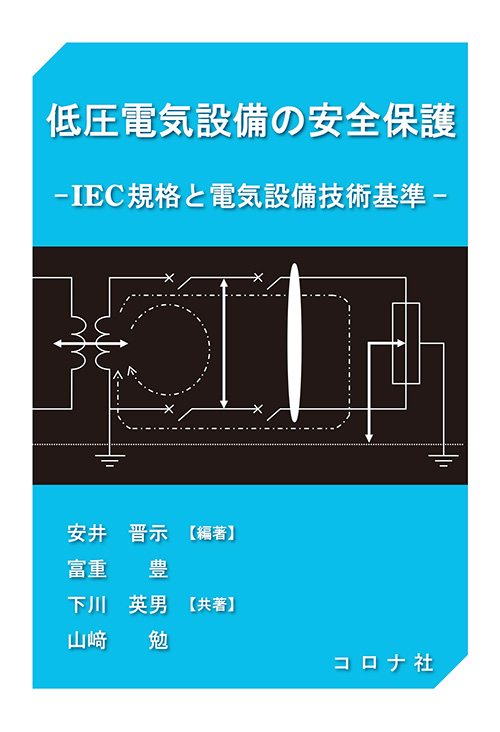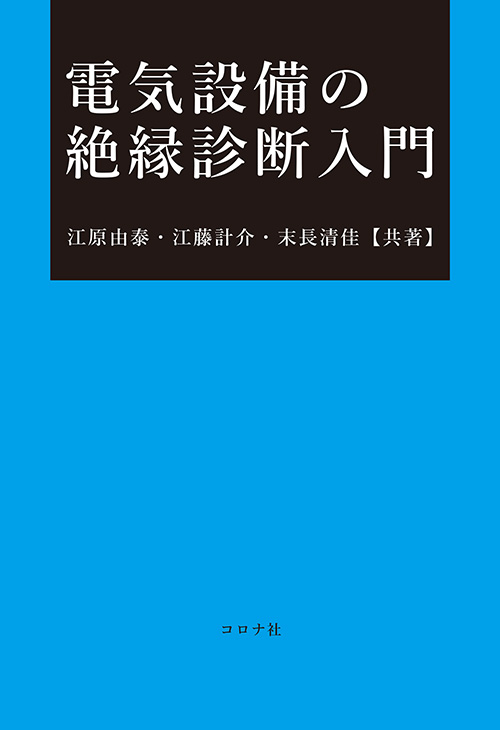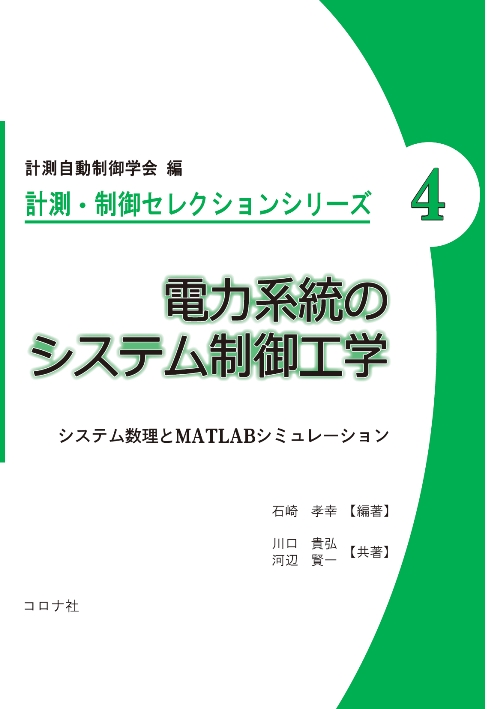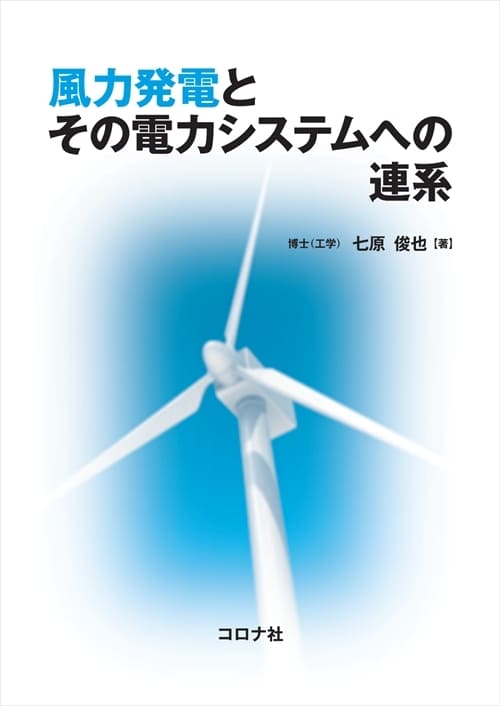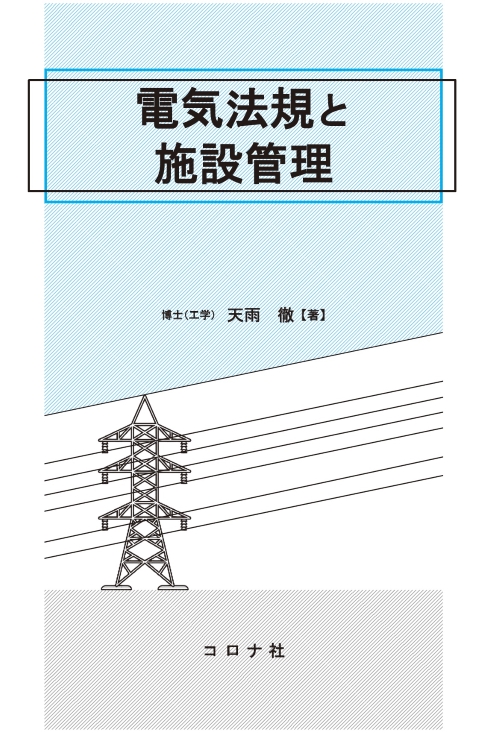
電気法規と施設管理
電気事業法と関連法規を体系的に見据え,実務に十分な知識を習得するための道筋となる1冊
- 発行年月日
- 2025/06/02
- 判型
- A5
- ページ数
- 214ページ
- ISBN
- 978-4-339-00996-5
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
【読者対象】
本書は、「電気法規」を履修する電気工学を学ぶ学部生を主な対象としています。また、電気設備の管理・運用に従事している技術者や、電気設備工事業務に携わる現場のエンジニア、さらには施設の運営管理者にも有益な内容となっています。電気法規の基礎から応用までの内容をしっかりと理解し、現場で実際に直面する問題を解決するための知識を習得したいと考える方々に適しています。
【書籍の特徴】
本書の最大の特徴は、電気法規に関する基本的な理論から、実際の施設管理における応用に至るまで、包括的に解説している点です。法律や規則を理解することが、電気設備の安全な運用と管理にいかに重要であるかを学べます。本書では、法規の解釈だけでなく、どのように実際の施設に適用するかに重点を置き、実務に直結した知識を提供しています。具体的な事例やケーススタディを交えることで、抽象的な法的概念が現場でどのように適用されるかをわかりやすく示しています。加えて、図表やチェックリストも豊富に取り入れており、視覚的に理解しやすい構成となっています。
【各章について】
本書は全9章で構成されており、それぞれが電気法規と施設管理に関する重要なテーマを扱っています。第一章では、電気事業の概要とそれを取り巻く法制度の基本的な枠組みを紹介します。続く章では、電気法規の必要性、歴史的な背景、そして現代の法制度がどのように形成されてきたのかを解説します。次に、設備の設計、施工、運用における法的な留意点を深掘り、現場で実際に適用すべき法規制について詳細に説明します。さらに、施設管理の実際に焦点を当てた章では、電気設備の点検や保守業務を効率的かつ安全に実施するための法的な指針を示します。
【読者へのメッセージ】
本書を通じて、電気法規と施設管理の重要性を実感していただけることを願っています。電気設備の管理は単なる技術的な仕事にとどまらず、法規制に基づく厳格な管理が求められます。特に、電気設備が適切に運用されなければ、安全性が確保できず、事故やトラブルの原因となることもあります。本書では、法規制を遵守しながら、安全で効率的な電気設備管理を実現するための理論と実務の両面に焦点を当てています。現場で直面する法的な問題や課題を解決するための具体的なアプローチを学んでいただき、知識を活かして実際の管理業務に貢献できるようになってください。本書が、皆様の技術者としての成長をサポートし、より安全で効率的な電気設備運用に寄与できることを願っています。
【本書のキーワード】
電気法規、施設管理、電気設備、法規制、規格、施設運営、安全基準、実務応用、技術者のためのガイド、設備点検、法令遵守
電気というものは、わが国だけに留まらず、全地球規模でも人類の社会・経済活動に必要不可欠なエネルギーであることは誰もが認めるところであろう。
しかしながら、人類の社会・経済活動の拡大、高度化に伴い、現代社会は電気をはじめとするエネルギー資源の枯渇問題、そしてそれに関連して地球温暖化問題に直面し、わが国でも、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。エネルギー・産業部門の構造転換、大胆な投資によるイノベーションの創出といった取組みを大きく加速することが必要であるとしている。
これにより電気エネルギーは、さらなる太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入促進、高効率機器の導入促進や排熱回収や未利用エネルギーの活用などの省エネルギー技術開発が進められている。
一方、電気は目に見えないため、われわれが直観的にわかりにくい特性がある。専門的に電気を学んだ人でなければ、電気に関する理解が難しい場合が多い。このため電気法規は単なる法律家には理解できず、電気知識があってはじめて理解できるものである。電気料金はじめ需給契約などの商取引に関しても、電気知識がないと取り扱えない場合がある。
電気技術者は、電気に関する法規や取引契約など自ら関与する機会が多い。そこで電気技術者を目指す学生には、これらの知識を持っていることが要求されている。
他方、大学では、セメスタ制からクォータ制への導入など、カリキュラムの見直しが行われ、従来の教科書では必ずしも十分に対応できるとは言い難い。むしろ昨今では教科書を用いず、プレゼンテーション資料や動画教材を用いて講義を進めることが多い。だからといって教科書が不要ということにもならず、こうした状況だからこそ、一層学びやすい教科書が求められているように思う。
そこでこの教科書は、そのような意図を持って、大学および高専で学ぶ学生を対象に「電気法規と施設管理」をまとめ、簡潔でわかりやすい執筆に留意した。
この教科書は「電気法規と施設管理」であるが、「電気法規」では、電気技術者の常識として必要な電気事業法と関連法規、電気事業の安全、電気設備技術基準といった法律の全体像を理解できるよう心がけた。「施設管理」では、電力需給、電気料金などの概要はじめ、電力系統の運用など、実務に直結する内容とし、最後に、実際の電気事故事例を紹介することで、理論と実践の橋渡しを試みた。
記載内容はいずれも密接に送配電部門に関連が深く、送配電などに関する知識があることを前提に記載されている。よって送配電工学や電力システム工学を学んだうえで本書を勉学することをおすすめする。
この教科書が、電気技術者を目指す学生のために、電気事業法と関連法規を体系的に見据え、将来の実務に十分な知識を習得するための道筋となることを願っている。また、現役の電気技術者にとっても、有益な参考となれば幸いである。
最後に、この教科書完成にあたっては、東京都市大学大学院博士前期課程2年(本書編集当時)の飯田千哉氏、高山大輝氏に多大なる協力をいただいた。心から謝意を表する次第である。また、コロナ社の方々には終始貴重な助言と励ましをいただいた。厚く御礼申し上げる。
2025年4月
天雨 徹
1.電気事業とそれを取り巻く課題と法制度の概要
1.1 電気事業の特性
1.2 電気法規の推移
1.3 電力施設を取り巻く課題と対策
1.4 電気事業者の概要
1.5 電気工作物
1.5.1 一般用電気工作物
1.5.2 事業用電気工作物
1.6 電力システム
1.7 電気工作物の種類と必要な資格
1.8 電気主任技術者
引用・参考文献
2.電気法規の必要性と体系・歴史
2.1 電気事業の推移と現状
2.1.1 初期の電気事業
2.1.2 大電力会社への発展
2.1.3 電気事業の国家管理
2.1.4 電気事業の再編成
2.1.5 電源開発株式会社などの設立
2.1.6 電気事業の広域運営
2.1.7 電源開発の推移
2.2 電気関係法規の体系
2.3 電気事業法の目的と規制対象
2.4 保安規程に関する法律
2.4.1 保安規定の目的
2.4.2 保安規定の内容
2.5 電力自由化前後の電気事業者の種類
2.6 電力システムの変遷
引用・参考文献
3.電気事業法
3.1 電気事業法の概要
3.2 電気事業(「供給規程」から「供給約款」へ)
3.2.1 接続供給
3.2.2 振替供給
3.3 事業の登録,認可,届出
3.3.1 小売電気事業
3.3.2 一般送配電事業
3.3.3 特定送配電事業
3.3.4 発電事業
3.4 電気事業業務
3.4.1 小売電気事業
3.4.2 一般送配電事業
3.4.3 送電事業
3.4.4 特定送配電事業
3.4.5 発電事業
3.5 電気事業規制
3.5.1 広域的運営
3.5.2 公益特権に関する規定
3.6 その他の法律
3.6.1 計量法
3.6.2 電源三法
引用・参考文献
4.電気工作物の保安に関する法規
4.1 電気の保安の考え方
4.2 電気事業法における電気保安体制
4.3 電気工作物の範囲と種類
4.3.1 電気工作物の定義
4.3.2 電気工作物の種類
4.4 事業用工作物の保安体制
4.4.1 自主保安体制―保安規定(電気事業法第42条)
4.4.2 自主保安体制―主任技術者(電気事業法第43条,第44条)
4.5 電気主任技術者資格の取得
4.6 一般用電気工作物の保安体制
4.6.1 使用前自主検査(平成11年の法改正により国から自主へ)
4.6.2 溶接事業者(自主)検査
4.6.3 定期事業者検査(対象は特定電気工作物:おもに発電設備)
4.6.4 自主保安体制―使用前自己確認制度
4.6.5 国の直接的な関与
4.6.6 工事計画の事前届出
4.6.7 許可と届出の範囲(設置工事):国の直接的な関与
4.6.8 使用前検査(特定事業用電気工作物):国の直接的な関与
4.6.9 使用前検査の合格基準
4.6.10 仮合格制度
4.6.11 安全管理審査:国の直接的な関与
4.6.12 立入検査:国の直接的な関与
4.6.13 登録安全管理審査機関:国の直接的な関与
4.6.14 保安に関する報告:国の直接的な関与
4.6.15 電気主任技術者資格の取得
4.6.16 調査業務
4.6.17 技術基準適合命令と立入検査
4.6.18 調査業務の委託と登録調査機関
4.7 電気工事士法
4.7.1 電気工事士法の目的
4.7.2 電気工事の種類と資格
4.7.3 電気工事士でなければできない電気工事の作業
4.7.4 電気工事士でなくても作業できる軽微な工事(電気保安上支障のないもの)
4.7.5 電気工事士免状その他の資格者認定証の交付
4.7.6 第1種電気工事士の講習
4.7.7 電気工事士試験
4.7.8 電気工事士等の義務
4.8 電気用品安全法
4.8.1 電気用品安全法の目的
4.8.2 電気用品の範囲
4.8.3 事業の届出
4.8.4 基準適合義務と記録の保持
4.8.5 特定電気用品の適合性検査
4.8.6 表示の権利とその禁止
4.8.7 販売および使用の規制
4.8.8 危険等防止命令
4.8.9 その他の規制
4.8.10 国内登録検査機関と関連規定
4.8.11 外国登録検査機関
4.8.12 第三者認証制度
4.9 電気工事業法
4.9.1 電気工事業を営む者の登録制度
4.9.2 電気工事業を営む者の通知義務
4.9.3 主任電気工事士の設置義務
4.9.4 電気工事業者の業務規制
5.エネルギー情勢と電気施設管理
5.1 わが国が抱える構造的な課題
5.2 一次エネルギーに占める電力の比率
5.3 資源供給の途絶事例
5.3.1 紛争および政変などによる資源供給の途絶事例
5.3.2 自然災害による資源供給の途絶事例
5.4 電源のベストミックス
5.5 日本のエネルギー供給の課題
5.5.1 エネルギー供給の構造的課題とリスク
5.5.2 日本のエネルギー自給率
5.5.3 石油危機がもたらした影響と対応
5.5.4 電源構成のベストミックス
5.5.5 シェール革命
5.6 電力需給の傾向とエネルギーの多様化
5.7 負荷の種類と特性
5.7.1 日負荷曲線
5.7.2 負荷の種類
5.8 電力需給のバランスと電源開発
5.9 電力供給計画
5.10 長期エネルギー需給見通し
5.11 周波数調整
5.11.1 サービスレベルの維持,向上
5.11.2 電力系統の安定運用
5.12 負荷変動の分類と周波数調整
5.12.1 周波数が維持できないときに生じる問題
5.12.2 周波数異常時のイメージ
5.12.3 負荷変動の分類
5.12.4 負荷変動に対する周波数調整
5.13 予備力発動状況について
引用・参考文献
6.電気設備技術基準(1)―基本事項―
6.1 本章の概要
6.2 電気設備基準の基本
6.3 電気設備技術基準の変遷
6.4 技術基準の種類と規制の内容
6.5 電気工作物による障害防止の基本的な考え方
6.6 基本事項
6.6.1 用語の定義
6.6.2 電圧の区分
6.6.3 電線
6.6.4 電線の接続
6.7 電路の絶縁と絶縁耐力
6.7.1 電路の絶縁の原則
6.7.2 絶縁性能
6.8 接地工事
6.8.1 接地工事の概要
6.8.2 工事方法
6.8.3 接地工事の種類
6.8.4 接地線の種類
引用・参考文献
7.電気設備技術基準(2)―電気工作物―
7.1 本章の概要
7.2 電線路
7.2.1 電線路の種類
7.2.2 架空電線路の施設
7.2.3 地中電線路の施設
7.2.4 サイバーセキュリティの確保
7.3 発電所,変電所等の電気工作物
7.3.1 構内・構外の区分と「さく」「へい」の施設
7.3.2 絶縁油の構外流出防止
7.3.3 発電所の公害の防止等
7.3.4 各機器の保護装置
7.3.5 主機,母線等の施設
7.3.6 圧縮空気装置,ガス絶縁機器の施設
7.3.7 太陽電池発電所等の施設
7.3.8 常時監視をしない発電所等の施設
7.3.9 常時監視をしない変電所の施設
引用・参考文献
8.電気設備技術基準(3)―電気使用場所と国際規格など―
8.1 本章の概要
8.2 電気使用場所の施設
8.2.1 電気使用場所の施設に係る用語の定義
8.2.2 対地電圧の制限
8.2.3 電気機械器具の施設
8.2.4 低圧の配線工事
8.3 国際規格の取入れ
8.3.1 IEC規格とは
8.3.2 IEC 60364とは
8.3.3 日本産業規格(JIS)
8.4 発電設備の電力系統への連系技術要件
8.4.1 連系の基本的な考え方
8.4.2 連系技術要件
引用・参考文献
9.電気事故事例
9.1 電気事故報告について
9.1.1 報告の対象となる事故
9.1.2 電気事故速報(24時間以内)
9.1.3 電気事故詳報(30日以内)
9.2 変圧器のトラブル事例と対策
9.2.1 変圧器のトラブルの原因
9.2.2 変圧器のトラブルへの対策
9.3 配電盤,VCBのトラブル事例と対策
9.3.1 配電盤,VCBのトラブルの原因
9.3.2 配電盤,VCBのトラブルへの対策
9.4 ケーブルのトラブル事例と対策
9.4.1 ケーブルのトラブルの原因
9.4.2 ケーブルのトラブルへの対策
9.5 小動物によるトラブル事例と対策
9.5.1 小動物によるトラブル事例
9.5.2 小動物によるトラブルへの対策
9.6 豪雨,低気圧,台風によるトラブル事例と対策
9.6.1 豪雨,低気圧,台風によるトラブル事例
9.6.2 豪雨,低気圧,台風によるトラブルへの対策
9.7 電気事故の報告対象
引用・参考文献
索引
読者モニターレビュー【ZOOK様(業界・専門分野:建設コンサルタント)】
この「電気法規と施設管理」は電気関連の法規等を説明したテキストであり、また、法律に関連した電気施設の管理を説明した内容となっている。一読してみると個々の法律について分かりやすく丁寧に説明されており、理系特有の法律分野に弱い方にも理解しやすいと感じた次第である。電気事業法を中心とした内容になっており、電気主任技術者や電気工事士といった資格関連の説明や電気工事や施設に関連する電気設備技術基準の説明もきちんとされている。電技解釈の本と合わせて読む事で条文の意味が分かってくると思う。
読者モニターレビュー【 Umehara 様 (業界・専門分野:原子力工学、機械工学)】
本書『電気法規と施設管理』は、広範にわたる電気法規の簡潔な解説と、実務に則した施設管理の解説から構成された一冊です。
法規の文章は難解で、苦手意識を持つ人も少なくないでしょう。しかし本書では、図表や箇条書きにより簡潔かつ分かりやすく示されており、適用ケースによって規定内容が変化する電気法規も、理解がしやすいように書かれています。
施設管理に関する章では、電力会社で勤めた経歴を持つ著者により、実務に直結する知識がまとめられています。
本書の構成のおかげで、これまで漠然とした知識しかなかった私でも、電気設備技術基準の解釈を体系的に把握し、全体像をしっかりと掴むことができました。
さらに、豊富な引用文献から、さまざまな関連書籍へと学びを広げることも可能です。
資格勉強はもちろん、実務に携わる方々の座右の書としても、手元に置いておきたい本書となっています。
読者モニターレビュー【北山 匡史 様 三菱電機(株)(業界・専門分野:電力システム工学)】
本書は、電気事業法、電気工作物の保安とそれに関わる電気主任技術者、電気工事士の資格と役割、電気設備技術基準(電気設備の技術基準の解釈)について体系的に学ぶことを学ぶこと主眼としている。
単なる法規に関する条文解説にとどまらず、電気事業の歴史的変遷、エネルギー情勢や電力需給の動向、電気設備に関する基本事項について簡潔に触れ、法規や施設管理の意義を総合的に理解できる構成となっている点が本書の特徴である。一般的な解説書には見られない視点であり、法規を単なる暗記科目ではなく、実務と結びついた知識として捉える助けとなる。
さらに、電気設備に関するトラブル事例とその対策も取り上げられており、実践的な内容も充実している。安全で効率的な電気設備管理を実現するための意義と実務をバランス良く学べ、法規遵守の重要性を実感できるだろう。
本書は、電気工学を学ぶ大学生・高専生をはじめ、電気主任技術者や電気工事士の資格取得を目指す受験者、現場で設備管理に携わる技術者、施設運営管理者など、電気設備に携わるすべての方にとって、一読に値する一冊である。

-
掲載日:2025/06/01