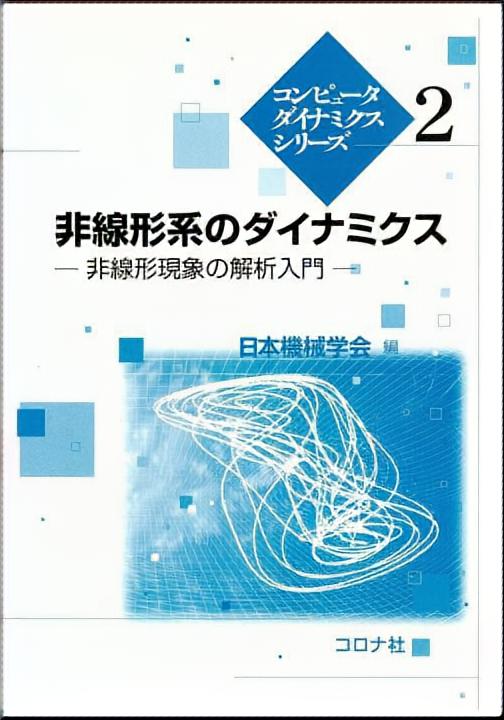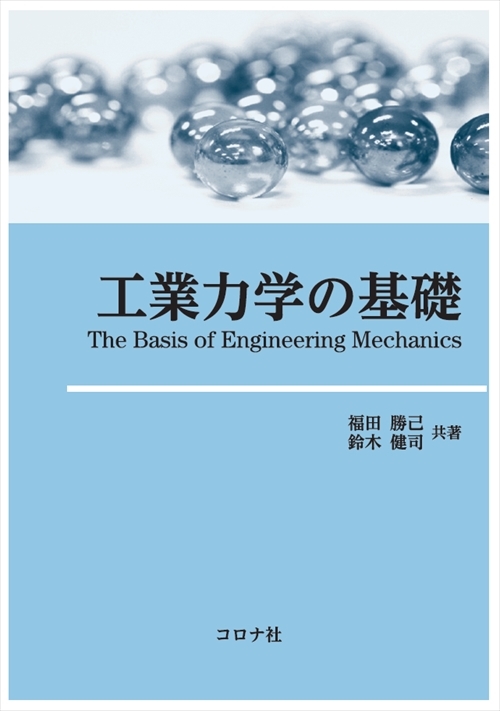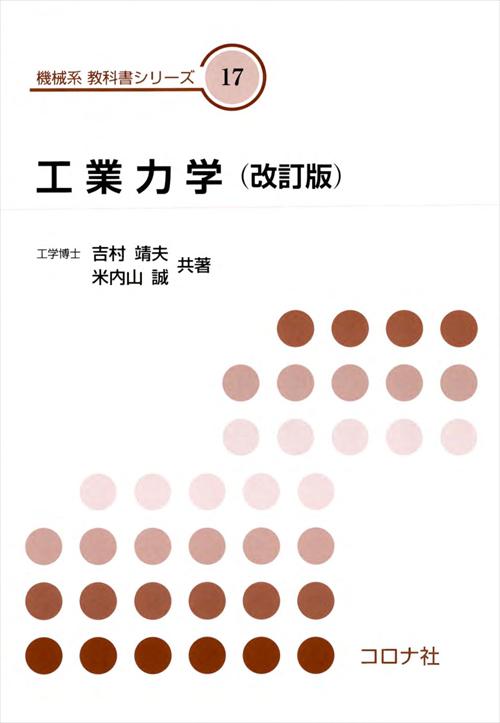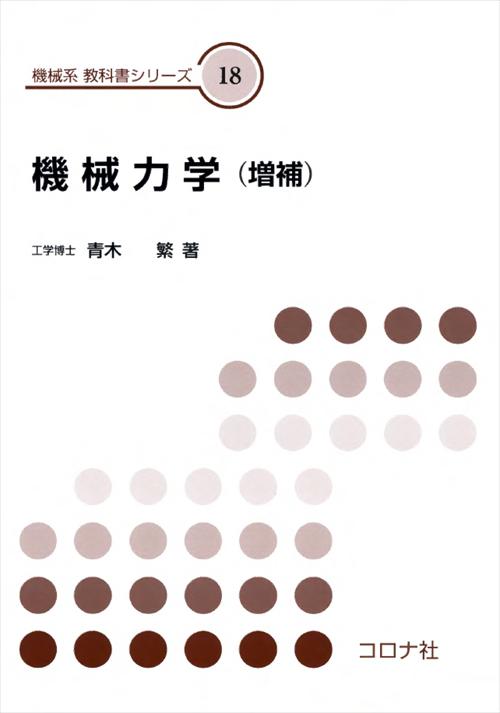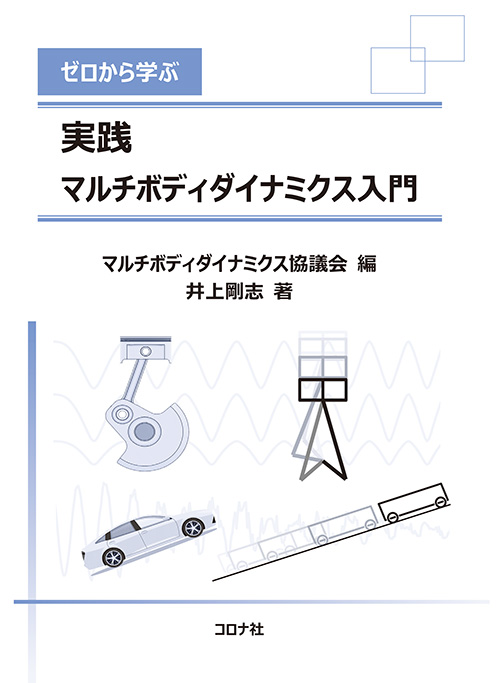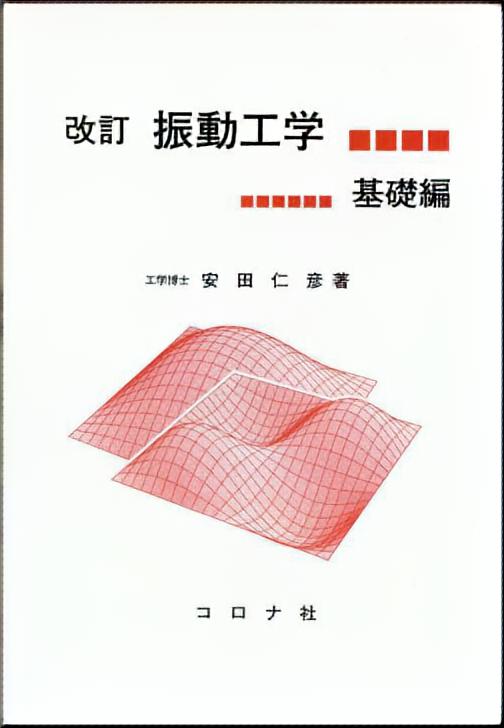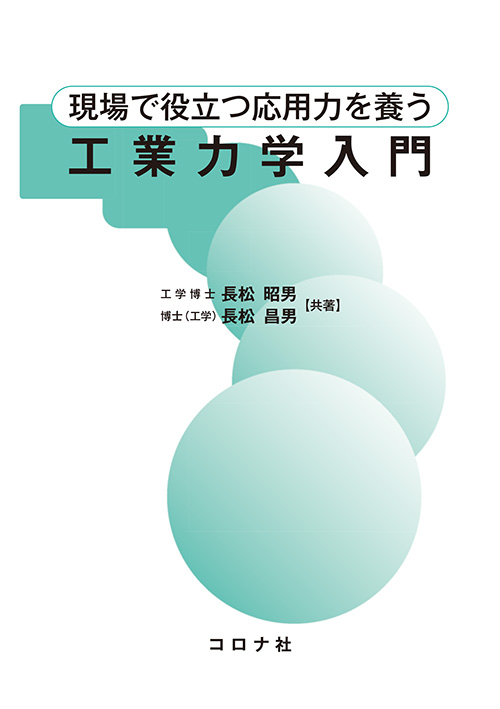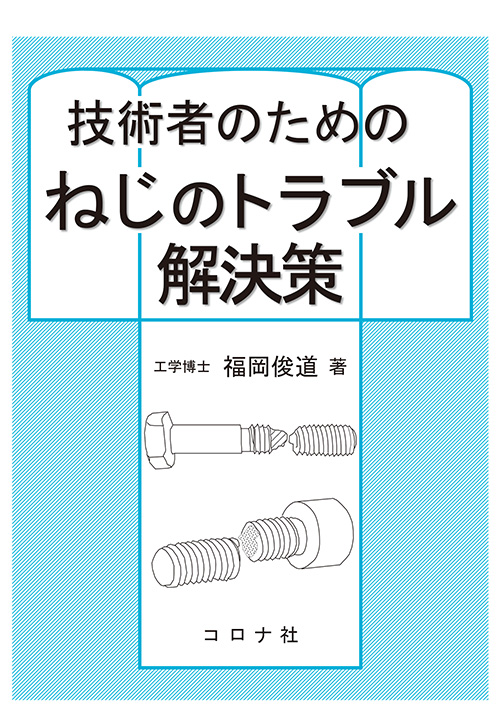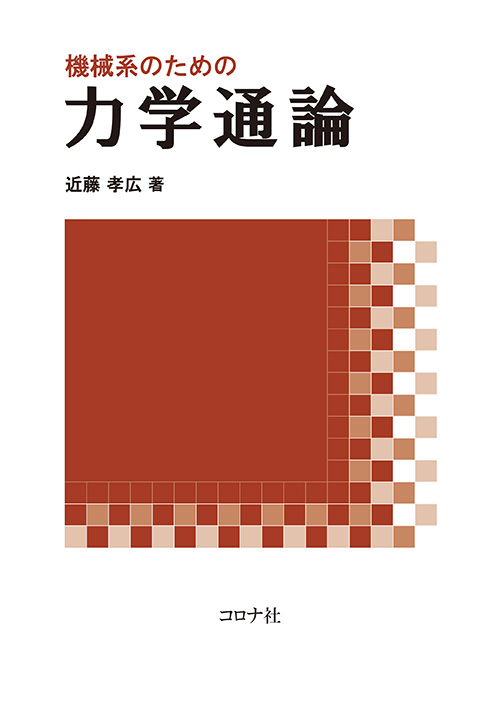
機械系のための力学通論
力学の基礎を,妥協のない水準で網羅する全16章。機械系の学生,教員,技術者に贈る1冊。
- 発行年月日
- 2025/11/05
- 判型
- B5
- ページ数
- 380ページ
- ISBN
- 978-4-339-04696-0
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
『機械系のための力学通論』は,著者が約35年にわたり機械工学を志す学生に行ってきた教育と研究指導の経験に基づき,機械工学の背骨ともいえる動力学(ダイナミクス)の基礎から応用までを,具体的には大学初年度に学ぶ基礎力学(第1章~第11章)から専門科目の機械力学・機械振動学(第12章~第16章)までの内容を,統一的な視点で体系的に論じた教科書または参考書です。読者対象は,機械系の学部生や大学院生をはじめ,若手研究者やエンジニア,さらには力学教育に携わる教員まで幅広く想定しています。
これまでの教育や研究を振り返って痛感するのは,動力学を真に理解して自在に使いこなせるようになることも,それを可能とするように教えることも,決して容易ではないという事実です。教科書の演習問題を解くことができても,実際の機械における複雑な動的現象に直面すると歯が立たないことは少なくありません。その原因の多くは,運動の法則やそこから導かれる種々の関係式を公式として断片的に暗記したにすぎず,それらの物理的意味や適用限界,さらには動力学体系の全体像を十分に理解できていないことにあります。
こうした事態を避けるために,本書では,新たに現れる物理量や関係式について,「なぜそのような定義や展開が必然的で有効なのか」を運動の法則と結びつけて丁寧に説明しました。その過程で必要となる数学的知識も他書を参照せずに理解できるよう配慮し,数式展開は途中経過を省略せずに記述しています。重要な概念については歴史的背景などを補注として添え,論理の流れを追いながら興味を持って力学体系を深く理解できるよう工夫しました。演習問題は基礎的なものから発展的・実践的な題材まで幅広く収録し,すべてに解答を付しています。学習意欲さえあれば自学自習が可能な構成とし,読者が動力学の魅力と威力を実感しながら,基礎力を確実に定着させ,応用力を養うことができるよう意を尽くしたつもりです。
さらに,本書は単なる知識の羅列にとどまらず,読者が自ら考え,現実の問題に対応できる力を養うことを目的としています。そのため,必要に応じて高度な内容にも踏み込みました。少し難しく感じる箇所もあるかもしれませんが,主体的に取り組めば,動的現象を解析する確かな視点を獲得し,将来,研究や技術開発の現場で自信をもって活用できる素地を培うことができるでしょう。
要するに,本書は,著者自身が学生,研究者,教育者として力学に向き合った各段階で,「このような教科書あるいは参考書が手許にあれば」と願った一冊を,著者なりの一貫した視点と統一した表現で具現化したものです。力学は「ものづくり」の根幹にあり,高性能な機械の開発に不可欠な動的現象の理解と解析のための強力な道具です。本書を通じてその奥深さと可能性に触れ,将来の研究や技術開発の座右の書として活用していただければ望外の喜びです。そして願わくは,本書の読者の中から,次の世代に向けた新たな『機械系のための力学通論』を編み出す人材が現れることを期待しています。
本書の特徴
本書は,力学の基礎から応用に至るまでを体系的に学ぶための教科書または参考書として執筆された。主たる読者として想定しているのは,機械系の学部学生,大学院生,若手エンジニア,若手研究者,さらには機械系学生に力学を教授する若手教員である。
材料力学,機械力学,熱力学,流体力学は「機械系四力学」と総称され,機械系学科における必修科目となっている。このことから,力学は機械工学に携わる者にとって不可欠な学問であることが理解される。本書では,特に機械や構造物の動的挙動に焦点を当て,大学初年度で学ぶ一般力学(基礎力学)から専門課程における機械力学や機械振動学に至るまでを,一貫した視点と統一的な表現で解説した。この構成により,読者が動力学に対する理解を段階的に深め,確実に基礎知識を修得できるよう配慮している。
近年,工学教育の現場では,内容の簡易化や直感的な説明の重視といった傾向が強まり,力学教育の質の低下が懸念されている。これは,力学を基盤とする機械工学にとってきわめて深刻な問題である。本書は,次代の機械工学を担う学部学生,大学院生,若手エンジニア,若手研究者が,力学の基礎を確実に修得できることを最優先に考え,内容の水準を妥協することなく,あえて硬質な姿勢を貫いた。特に,理論的背景を明確にしながら基本概念の体系的な理解を促すことを重視している。
その結果,本書は一般的な学部学生向け教科書と比較して,やや高度な内容を含むものとなったかもしれない。しかし,意欲さえあれば,ほかの参考書に頼ることなく自学自習を進められるよう,数学的知識を含め,内容の理解に必要な事項を可能なかぎり自己充足的に記述した。また,重要な概念については丁寧な解説を施し,数式展開の過程を詳細に示すことで,読者が論理の流れを追いながら理解を深められるよう工夫している。さらに,新たな物理量の導入に際しては,単なる定義の提示にとどまらず,その必要性や有用性を運動の法則との関連性を踏まえて説明し,より深い理解を促している。
本書はまた,すでに機械系のメーカーで研究開発や設計に従事しているエンジニアの再学習にも資するよう,実務に不可欠な基礎的事項を厳選して詳述している。さらに,機械系の学生に力学を教授する若手教員の参考となるよう,長年の教育経験に基づき,学生が誤解しやすい点に関する補足説明や,興味を喚起する歴史的背景などを,適宜補注として記載した。
加えて,本書には,従来の教科書や演習書に掲載されている有名な問題だけでなく,機械力学・機械振動学分野の重要な研究テーマを題材とする問題も例題や演習問題として収録した。すべての問題に解答を付し,いくつかの高度な問題には本文で十分に触れられなかった発展的内容の解説を加えている。これらの問題に主体的に取り組むことにより,機械や構造物における動的現象を解明するための強力なツールとしての力学の奥深さと魅力を実感し,実践的応用力を養っていただきたい。
本書が教科書または参考書として広く受け入れられ,機械工学および機械技術の発展に貢献する一助となることを願ってやまない。
執筆の経緯と謝辞
著者は約35年間にわたり,機械系の学生や大学院生に対して力学関係科目の講義を担当してきた。その間,力学教育に熱心に取り組んできたつもりであるが,年を重ねるごとに,力学の基礎的知識が不足している学生が目立つようになった。日本機械学会機械力学・計測制御部門に所属する大学教員からも,同様の懸念を耳にすることが増えてきた。この状況を打開し,教育現場と研究・開発現場との間に広がるギャップを埋めるためには,機械系に必要とされる力学全般の基礎知識を網羅した,やや高度な教科書または参考書が必要であると痛感し,いつかそのような書籍を執筆したいと考えるようになった。その思いを,駆け出しの頃より兄事してきた東京工業大学名誉教授・木村康治先生に語ったところ,執筆を強く勧められたことも,著者にとって大きな励みとなった。
この夢を現実のものとする契機となったのは,2020年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミックである。2020年度末に著者は定年を迎えたが,緊急事態宣言下で最終年度の講義はほぼすべてリモート形式で実施された。慣れないリモート講義の準備に追われ,疲労困憊する中で,A4判で約200頁の講義資料が手元に残された。定年退職後の新たな職務の合間に,出版の目途は立たないまま,さらに約3年かけてこの資料に大幅な加筆修正を施し,ようやく完成に至ったのが本書である。
本書の執筆にあたっては,単著であるがゆえの偏りや誤りを避けるため,新たな章が完成するごとに木村先生に原稿をお送りし,校閲をお願い申し上げた。木村先生は,著者が驚嘆するほどの熱意をもって,原稿の内容はもとより,煩雑な数式に至るまで丹念にご確認くださり,多くの貴重なご意見やご助言を賜った。本書が大きな誤りを免れているとすれば,それはひとえに木村先生の精緻な校閲の賜物であり,浅学菲才の著者が本書を完成させることができたのは,先生の励ましとご支援のおかげである。ここに深甚なる謝意を表する次第である。
また,本書の初稿完成後,出版の可能性を模索する過程で,多くの先生方に原稿をお送りし,ご意見を伺ったところ,ご多用の折にもかかわらず,多くの貴重なご助言を賜った。紙幅の都合により個々のお名前を挙げることは叶わないが,ご支援を賜ったすべての方々に対し心より感謝申し上げる。
最後に,本書の刊行を快諾くださったコロナ社に,重ねて厚く御礼申し上げる。
2025年9月
近藤孝広
1.力学を学ぶ際の心構えと基礎知識
1.1 力学とはどのような学問か
1.2 運動を力学的に理解する手順
1.3 物理量の次元と単位
1.4 物理量の種類
1.5 運動の観測と表現
1.6 等号の意味
1.7 近似法について
2.ベクトルの基本的性質
2.1 ベクトルとは何か
2.2 ベクトルの性質と演算規則
演習問題
3.点の運動の数学的表現法
3.1 点の位置・速度・加速度
3.2 点の運動の成分表示
3.3 微小体積の表し方
演習問題
4.運動の法則
4.1 運動の3法則
4.2 慣性質量と重力質量
4.3 力学でよく現れる運動方程式(微分方程式)の解法
4.4 運動方程式と座標系
演習問題
5.1自由度系の振動
5.1 振動とは何か
5.2 解析モデルと運動方程式
5.3 運動方程式の線形性について
5.4 運動方程式の無次元化と複素化
5.5 自由振動
5.5.1 基本解の導出
5.5.2 0≤ζ<1(0≤c<cc)の場合
5.5.3 ζ>1(c>cc)の場合
5.5.4 ζ=1(c=cc)の場合
5.6 強制振動
5.6.1 特解の導出
5.6.2 振動倍率および位相角の周波数応答
5.6.3 不減衰系の共振点(ζ=0,ν=1)における特解
5.6.4 力伝達率
5.6.5 周波数応答関数
演習問題
6.運動量と力積
6.1 運動量と力積
6.2 運動量保存則
演習問題
7.エネルギーと仕事
7.1 エネルギーと仕事
7.2 保存力
7.3 ポテンシャルエネルギー,力学的エネルギー保存則
7.4 保存力の場での質点の運動
7.5 非保存力
7.6 線形1自由度系の定常強制振動のエネルギー的検討
演習問題
8.角運動量と中心力
8.1 角運動量と角力積
8.2 中心力のみが作用するときの質点の運動
8.3 惑星の運動
8.3.1 ケプラーの法則
8.3.2 ケプラーの法則から万有引力の法則へ
8.3.3 万有引力の法則からケプラーの法則へ
演習問題
9.相対運動
9.1 並進座標系
9.2 2次元回転座標系
9.3 3次元回転座標系
9.4 地球表面上の質点の運動
9.5 オイラー角
演習問題
10.質点系の力学
10.1 質点個別の運動方程式
10.2 重心座標系
10.3 内力の性質
10.4 質点系の全運動量および全角運動量
10.5 質点系の重心の運動
10.6 質点系の原点Oまわりの回転運動
10.7 原点Oまわりの回転と重心Gまわりの回転の分離
10.8 質点系の運動エネルギー
10.9 衝突の取扱い
10.10 質量が変化する物体の運動
演習問題
11.剛体の運動
11.1 剛体とは何か
11.2 さまざまな座標系と角速度ベクトル
11.3 剛体の自由度
11.4 剛体の運動方程式
11.5 慣性テンソル
11.6 平行軸の定理
11.7 薄板の直交軸定理
11.8 慣性主軸および主慣性モーメント
11.9 G系で成分表示した剛体の回転に関する運動方程式
11.10 R′系で成分表示した剛体の回転に関する運動方程式
11.11 剛体の全運動エネルギー
11.12 固定軸まわりの剛体の回転運動
11.13 剛体の平面運動
11.14 対称剛体の運動
11.15 ジャイロ効果
11.16 剛体系の力学
演習問題
12.解析力学の基礎
12.1 仮想仕事の原理(静力学の基本原理)
12.2 ダランベールの原理
12.3 ハミルトンの原理
12.4 ラグランジュの方程式(導出法・その1)
12.5 ラグランジュの方程式(導出法・その2)
12.6 ラグランジュの未定乗数法
演習問題
13.回転機械の力学
13.1 つり合いの一般条件
13.2 剛性ロータのつり合い条件
13.3 剛性ロータのつり合わせ
13.4 つり合い試験器
13.5 ジェフコット・ロータの振れまわり
13.5.1 ジェフコット・ロータ
13.5.2 運動方程式
13.5.3 不つり合いによる強制的な振れまわり
13.5.4 強制的な振れまわりの動的平衡の見地からの解釈
13.5.5 内部減衰による自励的な振れまわり
13.6 基礎支持ばねの異方性の影響
13.7 弾性軸の異方性の影響
13.7.1 自励的な振れまわり
13.7.2 重力の影響による強制的な振れまわり
13.8 ジャイロ効果の影響
13.8.1 運動方程式
13.8.2 基本解および危険速度
13.9 オイルホワールとオイルウィップ
演習問題
14.線形多自由度系の振動
14.1 線形多自由度系の具体例とその特徴
14.2 実モード解析
14.2.1 不減衰自由振動
14.2.2 強制振動
14.3 複素モード解析
14.3.1 複素固有モードの導出
14.3.2 複素固有モードの直交性と正規化
14.3.3 複素モード解析による強制振動解析
14.4 複素モード解析の改良法
14.4.1 複素モード行列の実数化と実モード座標の導入
14.4.2 新型複素モード解析による強制振動解析
14.5 力学的エネルギー保存則に基づく近似解法
14.5.1 レイリー法
14.5.2 レイリー・リッツ法
演習問題
15.連続体の振動
15.1 波動方程式の導出
15.1.1 真直一様断面はりの縦振動
15.1.2 真直丸棒のねじり振動
15.1.3 弦の横振動
15.2 波動方程式の一般解とその性質
15.2.1 一般解(ダランベールの解)の導出
15.2.2 前進波と後退波
15.2.3 境界の影響
15.3 波動方程式の級数解
15.3.1 不減衰自由振動
15.3.2 固有モード関数の直交性
15.3.3 積分定数の決定
15.3.4 一般的な境界条件
15.3.5 不減衰強制振動
15.4 真直一様断面はりの曲げ振動
15.4.1 運動方程式
15.4.2 固有角振動数および固有モード関数
15.4.3 固有モード関数の直交性およびモード解析
15.5 レイリー法およびレイリー・リッツ法
15.5.1 レイリー法
15.5.2 レイリー・リッツ法
演習問題
16.振動制御
16.1 動吸振器
16.1.1 不減衰系の強制振動に対する動吸振器
16.1.2 自由振動および自励振動に対する動吸振器
16.2 能動的振動制御
16.2.1 振動絶縁に対する能動的振動制御
16.2.2 制振に対する能動的振動制御
演習問題
付録:行列の基本的性質
A.1 行列の定義
A.2 行列とベクトル
A.3 行列の演算
A.4 行列の種類
A.5 行列の階数
A.6 行列式
A.7 連立一次方程式
A.8 固有値と固有ベクトル
参考文献
演習問題解答
索引
読者モニターレビュー【 onia 様 (業界・専門分野:振動・音響)】
本書は、動力学を体系的に学べる良書です。導出や解説がとても丁寧であることはもちろん、補注の内容も興味深く、背景理解を深めながら読み進められる点が特に魅力です。
内容は数式で解釈可能な解析的手法に焦点を当て、数値解析手法には踏み込まないですが、動的現象を数理的にモデル化し、解釈する力を養うことができます。
演習問題は振り返りにも最適で、ボリュームも解説も充実しています。
著者により提案された新型複素モード解析手法の紹介は個人的には特に興味深く、改めて手を動かしながら学び、実務での応用も検討してみたいと思いました。
読者モニターレビュー【 上道 茜 様 山口大学工学部 (業界・専門分野:機械工学(熱流体、流体関連振動))】
近藤孝広先生の『機械系のための力学通論』は、まさに力学の「通論」と呼ぶにふさわしい1冊である。本書の前書きどおり、すべての数式展開が詳細かつ丁寧で、学習をサポートしてくれる。本書の構成も非常に周到で、1〜3章で力学を学ぶための準備を行った後、4〜12章で機械系学生が学部1年生で履修する基礎的な力学の内容を網羅している。さらに13章以降では、回転機械の振動、多自由度系・連続体の振動、振動制御といった実用的なテーマを深く掘り下げており、学生だけでなく社会人にとっても有用な内容となっている。高度な内容も含まれるが、重要な概念がしっかりと網羅されており、力学および機械力学を学ぶ上で大きな助けとなるだろう。豊富な例題・演習問題とその解説が極めて丁寧なのも特長だ。随所に散りばめられたコラムも知的好奇心を刺激し、楽しみながら力学を深く学ぶことができる。
読者モニターレビュー【 overload 様 (業界・専門分野::機械工学(特に機械工作))】
近年は大学等の機械系学科として卒業生にはどんな技術的職種や研究分野に進もうとも最低限必要となる機械力学(振動学)の内容をとてもコンパクトかつ平易にまとめたテキストがかなり増えてきているように感じますが、本書は、機械力学(振動学)を技術的な職務や研究でツールとして用いるのに必要な、一般的な大学の講義用教科書を超えた高度なレベルが主に扱われているという意味で、プロフェッショナル志向なテキストといえそうです。
そのような内容のため、学生というよりかは現場の設計開発等で機械力学(振動学)を使いこなす必要のある現場の技術者や、研究の過程でそのようなプロ志向の機械力学(振動学)の素養が必要になってくる大学院生向きの一冊ではありますが、大学学部までに教えきれなかった内容を教授するという意味では、大学院の機械力学(振動学)特論みたいな科目のテキストとしても使えそうです。
あとは専門科目のコマ数や時間配分が比較的恵まれていて教員の各科目における分業が大学ほど徹底していない高専(高等専門学校)では、一人の教員が初歩の力学・工業力学(高専本科2-4年程度)からそれに続く機械力学(振動学)(本科4-5年程度)、さらに続編の(機械)力学特論(専攻科)といった流れで本書を最初から最後まで通読させることも可能かと思います。数式の分量がかなり多めですが、数式展開を丁寧に行っているが故のことで、数学的補足も比較的充実しているので、力学の理解に必要な大学理系一般教養レベルの数学を専門科目と同時並行か、下手したら数学よりも先に専門の力学を履修する必要のある高専の方が本書の有難みは大きいかもしれません。
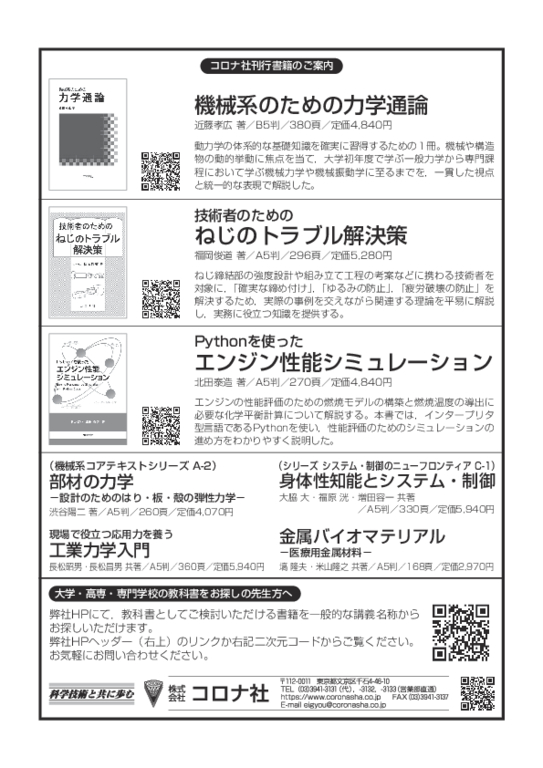
-
掲載日:2025/11/01
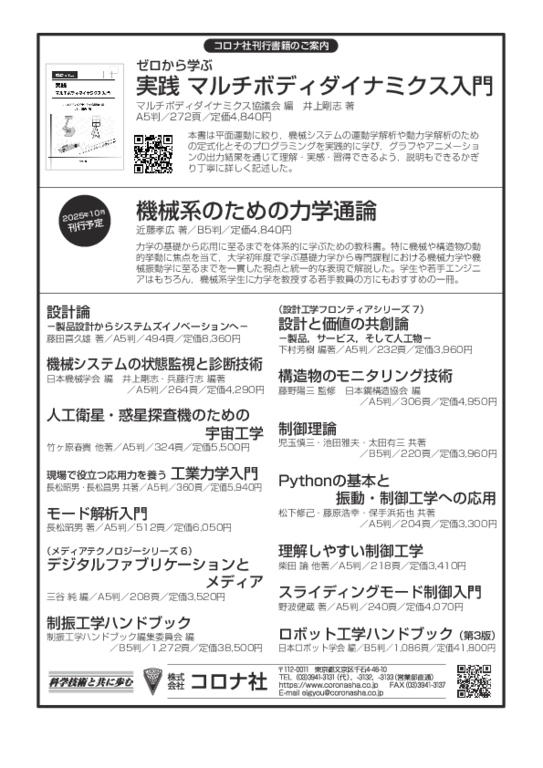
-
掲載日:2025/08/12