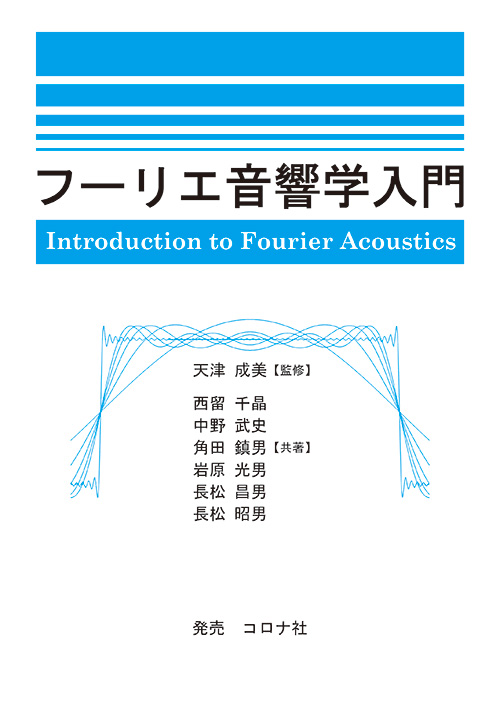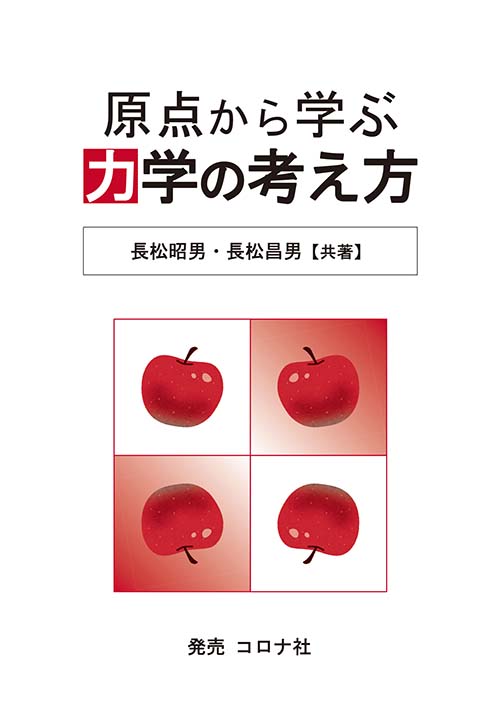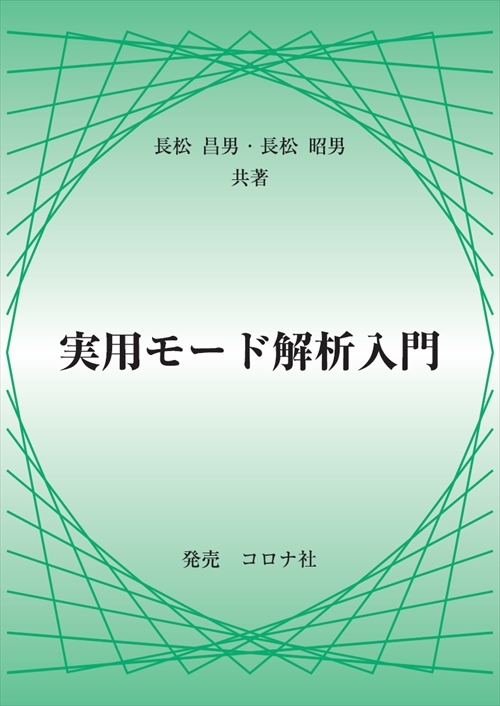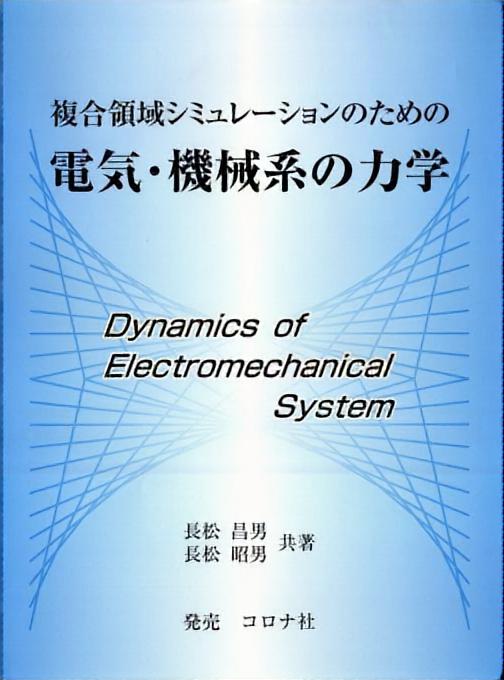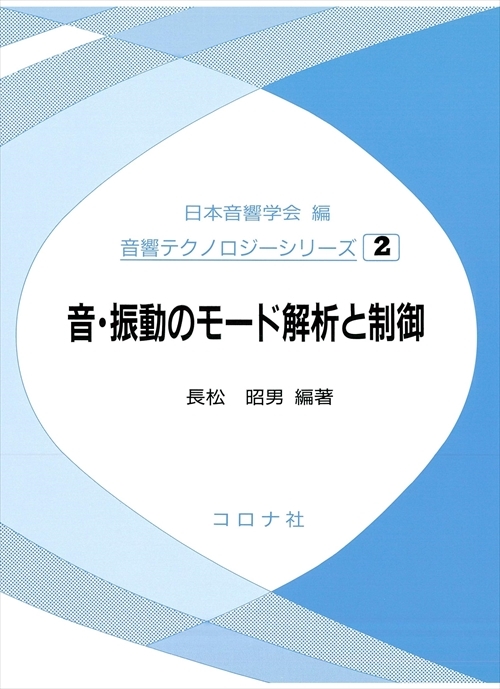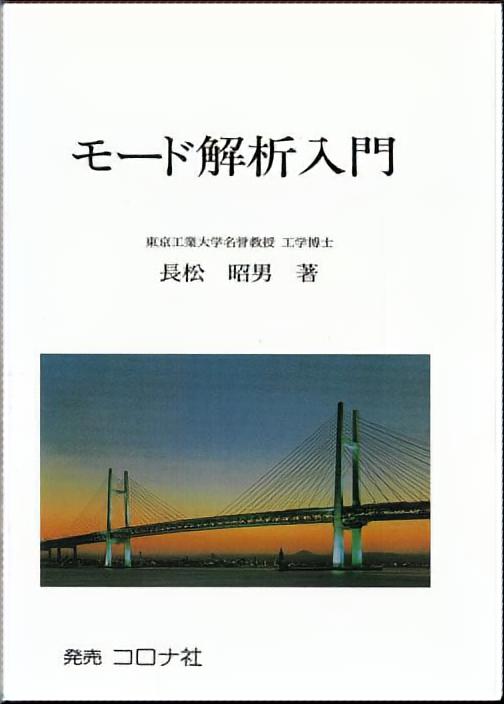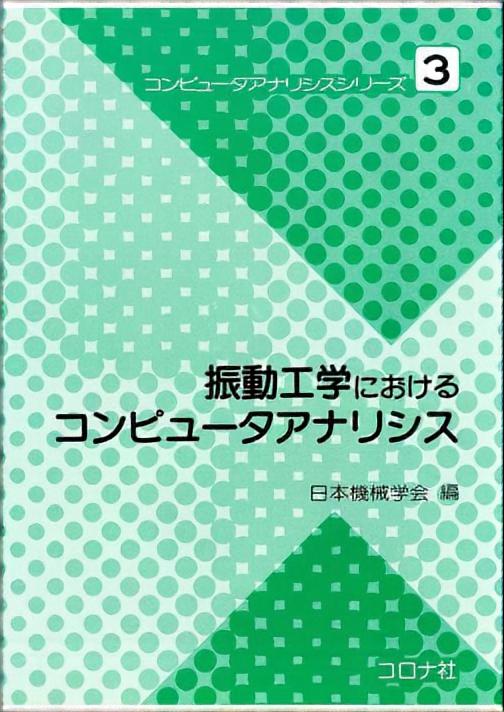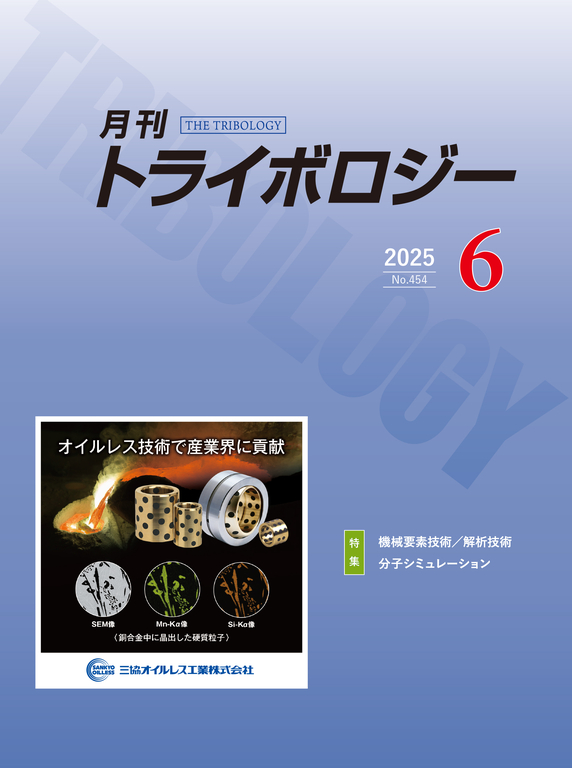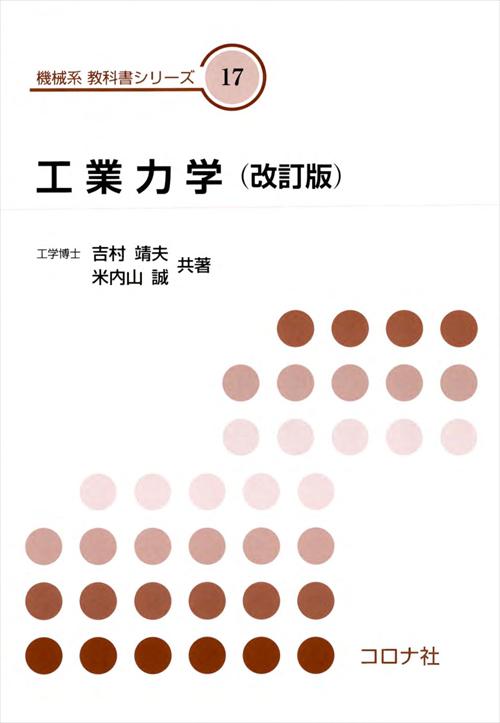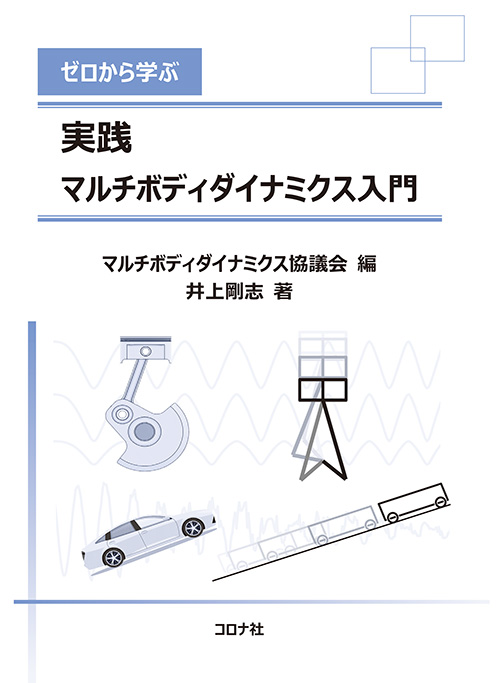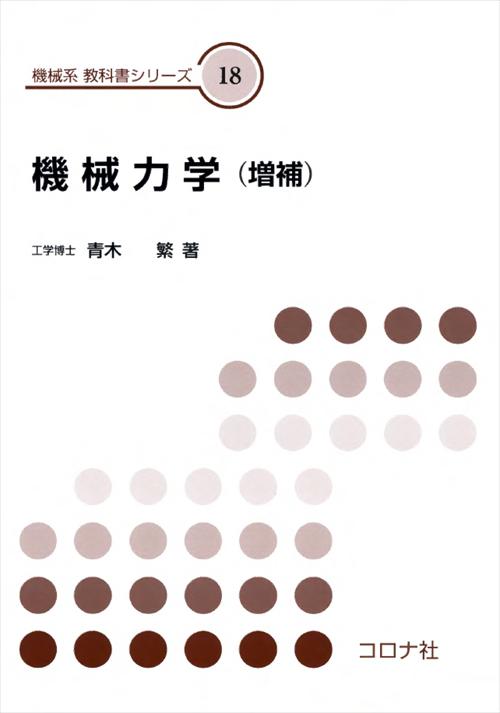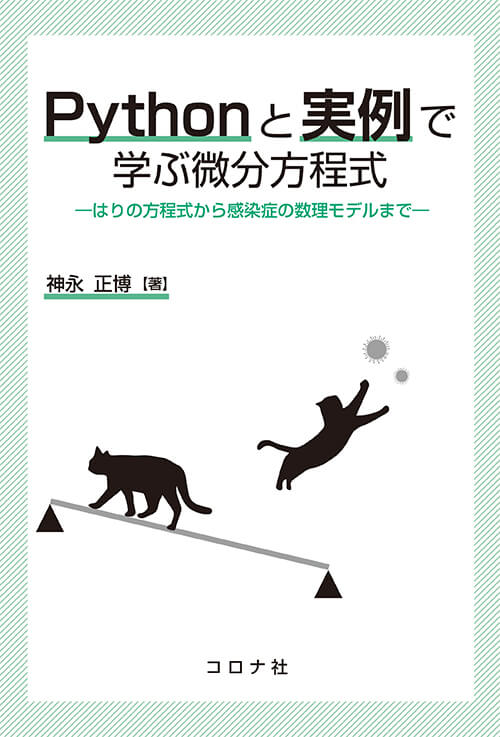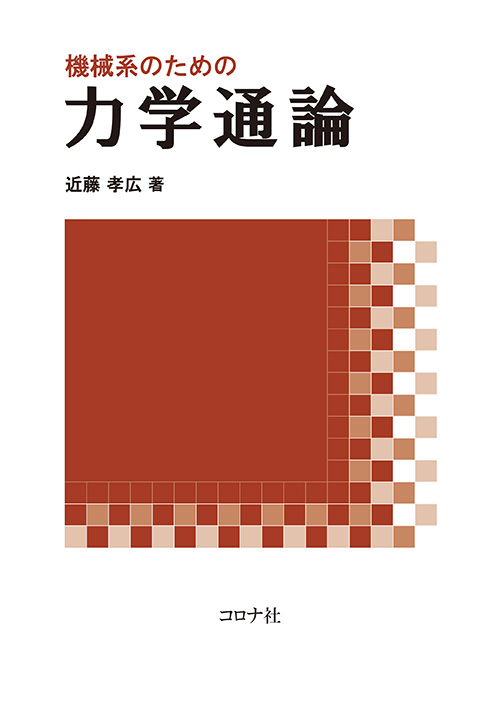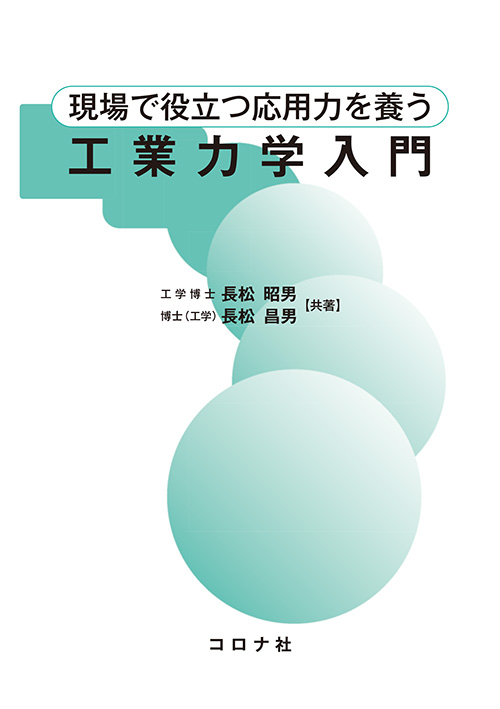
現場で役立つ応用力を養う 工業力学入門
大学,企業内教育の教科書・自習書に最適!181の演習問題・例題と親切な詳細解答付き。
- 発行年月日
- 2025/05/16
- 判型
- A5
- ページ数
- 360ページ
- ISBN
- 978-4-339-04694-6
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 書籍紹介・書評掲載情報
- 広告掲載情報
本書では長年にわたる著者の経験を活かし,現象から本質を見抜く勘と洞察力,複合領域を横断して見通す総合力・水平思考力,ものづくり過程で日々生じる様々なトラブルに対処する能力など,現場で役立つ応用力を養うことを目指す。
初心者が一人前の技術者にまで成長するための最適の近道は,即戦力を養成することである。そのためには,大学受験の際に経験したように,基礎を学ぶと共に力学を応用している身近で簡単な機械・現象のからくりを解明する数多くの演習問題をひたすら解くことから始めるのが最良である。それにより,まず現場で遭遇する問題の題意を理解してそれを適確に表現する図を作成し,次にその図から問題を数式化し,さらにそれを用いて解決策を得る能力を獲得できる。本書の目的はここにあり,181もの演習問題・例題を有し,これらすべてに分かり易い解答を付記してある。
【主要目次】
1.力
2.運動
3.力と運動の関係
4.質点の動力学
5.エネルギー原理
6.運動量と角運動量
7.剛体の動力学
8.振動
本書は,ものづくりを志す学生や若手の技術者・技能者が,初めて工学の味に触れ,固体・流体・熱・電気の力学はもちろん工学全体に共通な基本物理法則を学び,同時に身近にある簡単な種々の機械・装置のからくりを理解することを通して,現象から本質を見抜く勘と洞察力・複合領域を横断して見通す総合力と水平思考力・企業内のものづくり過程で日々生じる様々なトラブルに対処する能力など,現場で役立つ応用力を養うことを目的とする.
筆者が半世紀近くの大学教員の経験を通じて最も苦く感じることは,大学生が在学中に習得すべき必修総単位数が昔と変わらない中で,AD・CAE・FEMの使い方,コンピュータ言語などのソフト・道具・手段に関する授業が増え,その分だけ力学の本質に関する授業数を減らさざるを得なかったため,卒業時の学力低下を招いたことである.
ものづくりに必要なのは,市販のCAEツール・スマートフォン・インターネット等を操作し知識を得る手技ではない.このようなことは実業務中に自然に身に付く.学生・若手社員がまず習得しなければならないのは,市中に溢れる膨大な情報の海から必要なものを選択して拾い出し,正しく組み上げて巧みに使いこなすことを可能にする,工学上の勘・嗅覚・センス・洞察力であり,実製品の開発時に遭遇する諸問題を乗り越えていく能力である.
近年,人工知能が示すように,最新技術はソフトにあるように一見感じる.しかし,優れたソフトは優れたハードに支えられて初めて機能する.例えば,人工知能の中核部品である超LSI作成には0.01μm程度の研磨技術・装置が,それを生かすロボットの精密制御にはμm以下の作動・位置決め技術・装置が不可欠である.そして,ハードの根幹は力学にあり,ものづくりを志す初心者は必ず力学の習得から始めなければならない.
19世紀末にエネルギー保存則が確立し,20世紀初頭に対称性の概念が数学から物理学に導入された.これにより現在,力学の原点がこれら2つにあることが判明している(参考文献18参照).このことは“力学の考え方”としては正しいが,力学をものづくりに応用する技術者は必ず,始祖ニュートン以来の始点である力と運動から力学を学び始めなければならない.“始点から入り原点に至る”.これは力学を教育・学習する際の正しい道筋であり,本書もこれに沿って構成されている.
さて,日本が最も得意とするのは実機・実製品に直結する即戦応用力である.ルネサンス以降西洋で生まれ育った科学技術を明治初期に導入し短期間で消化吸収した日本は,昭和の昔コンピュータが世に生まれる以前に竹製の計算尺と製図板で当時世界最大の戦艦大和・卓越した速度と旋回性能を有する零戦戦闘機・世界初の新幹線を開発し,また前世紀末には自動車技術で世界を制覇した.これらは,往年の日本の技術者がいかに有能で世界最高の実力を有していたかを示している.
前述のように,これに比べ最近の大学卒業時の学生の学力は低下している.しかし日本は,磁気浮上車両・ハイブリッド車を世界に先駆けて生み出すなど,現在でも世界の先端を行く高い技術力を維持している.これは一に,我が国を支える主要企業が洗練された社内教育体制を有し,新入社員・若手技術者を厳しく鍛え上げているためである.約40年間に渡り数多くの企業で社外講師を引き受ける機会に恵まれた筆者は,日本の主要企業が新入社員を世界最高の技術者にまで自力で育成し続けている姿を,目の当たりにしてきた.そこで,筆者のこの貴重
な体験を広く世に残す必要性を痛感し,本書を執筆するに至った.
初心者が一人前の技術者にまで成長するための最適の近道は,現場で役立つ応用力を養成することである.そのためには,大学受験の際に経験したように,基礎を学ぶと共に力学を応用している身近で簡単な機械・装置・現象のからくりを解明する数多くの演習問題をひたすら解くことから始めるのが最良である.それにより,まず現場で遭遇する問題の題意を理解してそれを適確に表現する図を作成し,次にその図から問題を数式化し,さらにそれを用いて解決策を得る能力を獲得できる.本書の目的はここにあり,181もの演習問題・例題を有し,これら
すべてに分かり易い解答を付記してある.
本書は大学や企業内教育の教科書・自習書として適切・有効であることを,筆者は長年の経験に基づき確信し推奨する.また本書は完全解答付き演習問題集としても活用できる.本書をヒントにすれば,物理学・力学の分野を対象にする大学入試・定期試験・企業教育の演習問題の作成に苦労しないであろう.
本書の概要は,下記の通りである.
第1章 力 では,力学を代表する力の概念を紹介する.まず,合成・分解・モーメント・偶力等,力の性質と働きを述べる.次に,物体に作用する力の効果を示す.続いて,懸垂線・静水圧・浮力・固体摩擦等,物体に分布する様々な力の内容を詳説する.
第2章 運動 では,まず,運動する質点・質点系の速度・加速度を定義し,それらの速度を図示するホドグラフと曲率の概念を示す.次に,剛体の並進運動と回転運動の関係から導く瞬間中心とその軌跡を紹介する.また,運動する座標系上をさらに運動する物体の速度と加速度を導き,コリオリの加速度の正体を明らかにする.
第3章 力と運動の関係 では,力から運動への関係を記述し,力学創設の始点となったニュートンの3法則を説明する.また力学の単位系を定義し,国際単位系を紹介する.
第4章 質点の動力学では,落体・放物体・拘束体・荷電粒子・惑星・彗星・人工衛星など様々な物体に作用する力とそれにより生じる運動を数式展開する.
第5章 エネルギー原理 では,全物理学を支配する基本法則であるエネルギー原理を紹介し,力学の原点・根幹をなす力学エネルギー保存則について詳しく説明する.
第6章 運動量と角運動量では,質点の運動量保存則と角運動量保存則を紹介する.
第7章 剛体の動力学 では,剛体の回転運動を決める慣性モーメントと慣性乗積を定義し,慣性楕円体を記述する.次に,剛体運動の解析に用いるオイラー角とオイラーの運動方程式を紹介し,これらを駆使してこまやジャイロの運動を数式展開する.
第8章 振動 では,弾性体の動力学・音響・波動・電磁波・光波・重力波への入口である1自由度系の振動を紹介し,実用上重要な振動絶縁の方法を説明する.
上記各章にはそれぞれ,数多くの例題・演習問題を詳しく分り易い解答と共に付記し,内容を理解しそれを現場で生じる雑多な問題に応用できる実力の養成を可能にしている.
筆者は長年,教育・研究面から吉村卓也首都大学東京教授・御法川学法政大学教授,実用面から天津成美・西留千晶両氏(キャテック株式会社)に様々なご教示・ご協力をいただいていることを記し,深く感謝申し上げる.
なお本書には,著者の力不足から来る不完全さや誤りが存在することを恐れる.読者の皆様からこれらをご指摘・ご教示いただければ,この上ない幸いである.
2025年3月 著者代表 長松昭男
第1章 力
1.1 力の働きと効果
1.1.1 1 点に作用する力
1.1.2 作用点が異なる力の合成
1.1.3 力のモーメント
1.1.4 偶力
[問題1] (1-1) ~ (1-4)
1.2 物体に作用する力
1.2.1 重心(質量の中心)
[問題2] (2-1) ~ (2-4)
1.2.2 拘束された物体に作用する力
1) 接触点・支点に作用する力
[問題3] (3-1) ~ (3-3)
2) 骨組構造
[問題4] (4-1)
[問題5] (5-1) ~ (5-8)
3) 仮想仕事の原理と釣合
[問題6] (6-1) ~ (6-4)
1.2.3 分布する力
1) 分布荷重
[問題7] (7-1) ~ (7-3)
2) 懸垂線
3) 静水圧
[問題8] (8-1) ~ (8-3)
1.2.4 摩擦と力の釣合
[問題9] (9-1) ~ (9-9)
第2章 運動
2.1 質点の運動(速度と加速度)
[問題10] (10-1) ~ (10-6)
2.2 剛体の運動
2.2.1 剛体とは
2.2.2 並進運動と回転運動
2.2.3 平面運動
2.2.4 瞬間中心
[問題11] (11-1) ~ (11-11)
2.2.5 一般運動
2.2.6 相対運動
[問題12] (12-1) ~ (12-9)
第3章 力と運動の関係
3.1 ニュートンの法則
3.2 力学系の単位
3.2.1 MKS 単位系とCGS 単位系
3.2.2 重力単位系
3.2.3 国際単位系(SI)
3.2.4 次元
[問題13] (13-1) ~ (13-6)
第4章 質点の動力学
4.1 質点の運動
vi 目次
4.1.1 落体・放物体の運動
4.1.2 拘束運動
4.1.3 電磁界中の荷電粒子の運動
[問題14] (14-1) ~ (14-19)
4.2 中心力による惑星の運動
[問題15] (15-1) ~ (15-5)
4.3 運動座標系における動力学
[問題16] (16-1) ~ (16-5)
第5章 エネルギー原理
5.1 力学エネルギー保存則
5.2 質点系のエネルギー
5.2.1 重心の運動とエネルギー
5.2.2 仕事率(動力)
[問題17] (17-1) ~ (17-15)
第6章 運動量と角運動量
6.1 質点の運動量と力積
6.2 質点系の運動量と角運動量
6.2.1 運動量の法則とその保存則
6.2.2 角運動量の法則とその保存則
6.2.3 2 体問題
[問題18] (18-1) ~ (18-17)
第7章 剛体の動力学
7.1 剛体の回転運動
目次vii
7.2 慣性モーメントと慣性乗積
[問題19] (19-1) ~ (19-14)
7.3 回転体の反力と釣合せ
7.4 剛体の平面運動
[問題20] (20-1) ~ (20-11)
7.5 剛体の空間運動
7.5.1 オイラー角
7.5.2 オイラーの運動方程式
7.5.3 こまの運動
7.5.4 外力モーメントが0 の運動
7.5.5 ジャイロの運動
[問題21] (21-1) ~ (21-4)
第8章 振動
8.1 自由振動
8.1.1 力学特性
8.1.2 運動方程式と解
8.2 強制振動
8.2.1 不減衰系
8.2.2 粘性減衰系
8.3 振動絶縁
8.3.1 質量から基礎への伝達
8.3.2 基礎から質量への伝達
[問題22] (22-1) ~ (22-14)
参考文献
索引
読者モニターレビュー【 Masa 様(業界・専門分野:機械工学 )】
私が本書を読んだ印象は機械工学分野(材料力学 流体工学 機械設計 機械力学)の各分野に必要な力学に関する知識がまとめられた書籍だと思いました。本書の構成は8章の構成になっており大きく分けると次のような構成になっています。第1章では力学問題を解く基礎的な知識(物理・数学)の記載があり、第2章~第4章では高校物理の内容からステップバイステップで質点系の動力学まで学べるようになっています。また、第5章~第6章でエネルギーや運動量を考える問題にふれ、第7章で剛体の動力学を扱っています。最後の第8章では多自由度の系の基礎となる1自由度系の振動問題を解くことで振動工学の基礎部分を学習できる構成になっています。そのため、本書は高校物理の基礎的な知識を取得していて自分で調べて学習する力があれば、学部1年生でも工業力学の基礎から動力学や振動工学の基礎まで学習ができると思います。ただ、本書は1冊目の工業力学の本としてはハードルが高い書籍なので、初学者に対してはフルカラーで初学者向けの【工業力学 第4版(森北出版)】をサブテキストで使用することをお勧めします。また、本書で取り上げられている問題は機械設計技術者試験や技術士1次試験で出題されるような問題が取り上げられているので資格取得の勉強をしている方にもお勧めします。改善点を挙げると、各機械工学分野の力学に関する知識がまとめられていますが、実務上は業務の一部に力学を使用するため、力学の視点だけでなく機械部品の選定や振動データからの固有振動数の調査方法、リンク系ロボットのトルク計算などの具体的な業務事例にどのように工業力学が使用されるかを説明する項目があってもいいと思いました。私の読書レビューが書籍を検討している方々の参考になれば幸いです。
読者モニターレビュー【 おみにゃ 様(業界・専門分野:制御工学 )】
私は過去に筆者が執筆された「モード解析」(コロナ社)の愛読者なので、本書を非常に楽しく読ませていただいた。本書の内容に関しては、特に高専生や大学1、2年生向けで力学の基礎から剛体の動力学、振動の導入部分までを学ぶことができる。また、これまでに工学系の専門分野を学んでこなかった方々においても、記載されている各式の作り方が丁寧に解説されているために初学者でも安心して学ぶことができる。是非、読書には本書で工業力学の基礎を学んだ上で各専門書を読むことをお勧めしたい。さらに本書のタイトルにあるように現場で役立つ応用力を養うための内容になっている点も大きな特徴である。具体的には練習問題が多数記載されているので、力学の基礎的な知識を理解しながら練習問題を通して実践的なスキルを獲得することが出来る。こうしたスキルの積み重ねが現場における多くの課題を解決する力に繋がるのではないかと考える。個人的には機械式ジャイロに興味があるため、原理の説明から運動方程式の立式までの要点を確認することができたのが非常に勉強になった。是非、本書をお手に取って読んでいただきたい。
読者モニターレビュー【 overload 様(業界・専門分野:機械 )】
レベルや位置付け的には著者の一人による数十年前の前著「工業力学」(養賢堂)を現代の事情、具体的には就活やそれに必要な俗に言うガクチカなどで、工業力学をはじめとする座学の類に昔の学生ほど時間を割く余裕がかなり無くなってきていると思われる現代の学生のために、演習問題の解答についていわゆる行間を読む能力や労力に極力頼らず理解できる程度に詳解を与えている演習主体の教科書、といったところでしょうか。
工業力学はいわゆる機械工学の主要専門科目の四力学(機械力学(振動学)・材料力学・流体力学・熱力学)あるいは機械(要素)設計(法)に進む前段階の基礎的科目として置かれていることがかなり多いようですが、それら科目に進む前段階の入門的科目としての内容、例えば曲げモーメントや噴流に関する力学なども取り扱われており、その点で比較的充実していると思われます。
本書はあくまで演習とその詳解が主体で、公式だとかの理論的な背景の説明は比較的あっさりしている、習うより慣れよの傾向があるので、本書の内容、演習問題の詳説についていけない場合は、例えば「工業力学入門」(森北出版)や「力学キャンパス・ゼミ」(マセマ出版社)などを参照すれば理解が進むものかと思います。
専門科目に与えられている時間数が恵まれている高専などであれば、講義を通して本書を隅々まで通読することも可能かもしれませんが、大半の一般の大学では工業力学に与えられた時間は1年次後期~2年次前期頃に半期・週1時間・2単位程度であることが殆どかと思われるので、その場合は例えば理系一般教養の力学と重複する主に冒頭の基礎的内容や、四力学や要素設計と重複する内容を割愛する、例えば本書終盤の振動などは工業力学習得後に履修することになる機械力学(振動学)などの専門科目の方に回してしまってもよいかもしれません。あるいは理系一般教養の力学や、大学院における例えば(工業・古典)力学特論といった科目のテキストに本書を用いるのもありかもしれません。
一方で、工業力学の科目では終盤におまけ程度に簡単なラグランジュ方程式を用いた力学的問題の解法といった解析力学の初歩・概論的なことを教授していることも少なくないようですが、本書では解析力学は扱われていないので、その点については担当教員が適宜補ってやる必要があるかもしれません。
本書の演習問題は機械設計等の現場における実践的な問題が多いので、大学や高専の専門課程に入りたての若者や初心者にはオーバースペックかもしれませんが、実務者や大学院入試等で演習問題を作成する側の方々にも重宝するのかなとは思います。あるいは機械系以外でも例えば衛星や実験装置等の設計で高度な古典力学の素養が必要になるであろう理学系など非機械系の方々の独習・輪講用書籍として有用かもしれません。
筆者らは従来の伝統的な(特に機械系の)力学教育に対して長年問題提起されてきているようですが、本書はあくまで従来の伝統的な力学教育に沿った内容でありますので、筆者らが例えば「機械の力学」(朝倉書店)などで提唱の新たな(電磁気学等との親和性の高い、理論的対称性の美しさが際立っているような)機械系力学理論の体系の改革に関する続報についても期待したいところです。
amazonレビュー
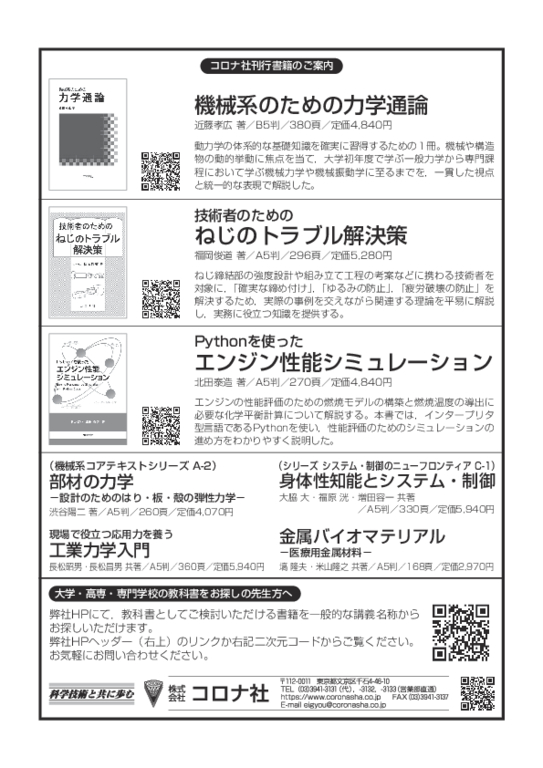
-
掲載日:2025/11/01
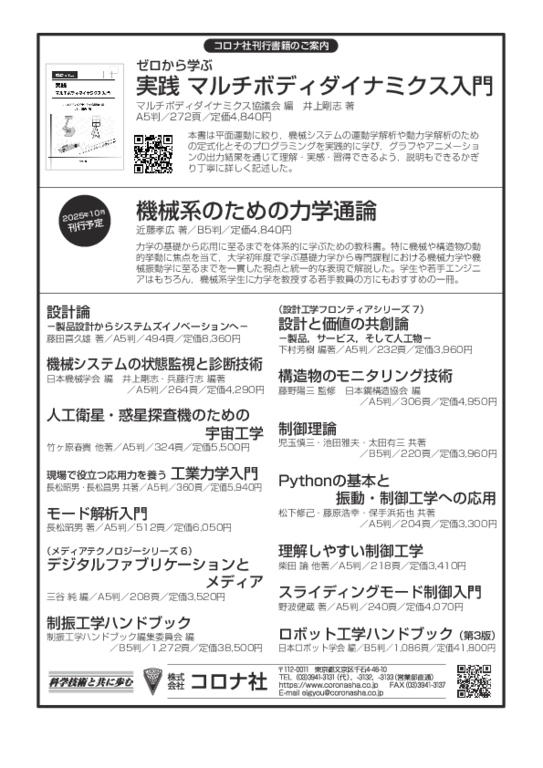
-
掲載日:2025/08/12