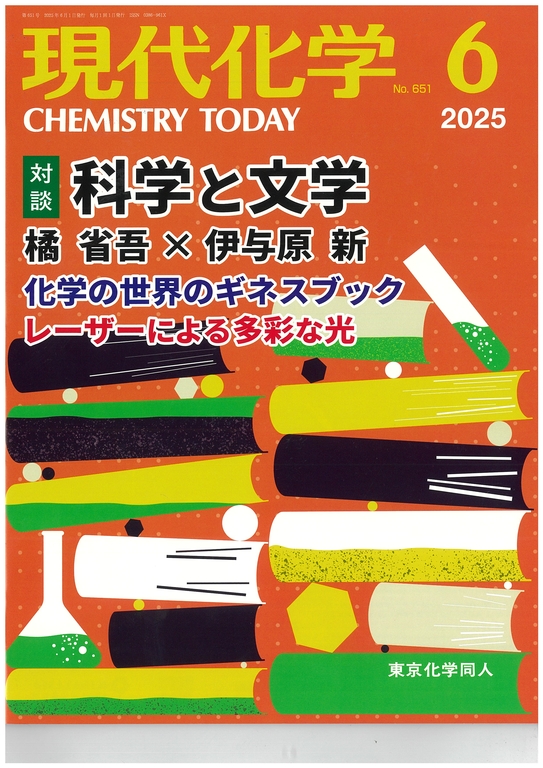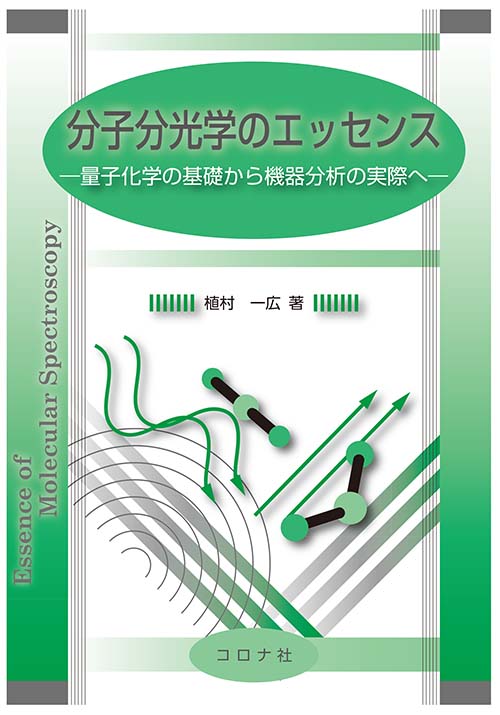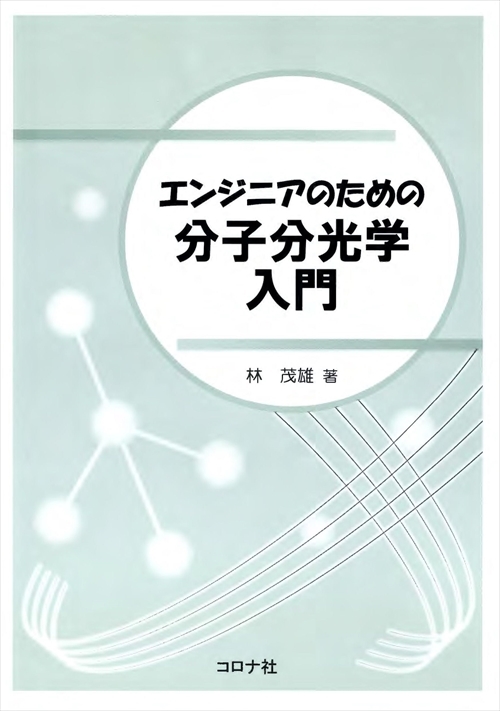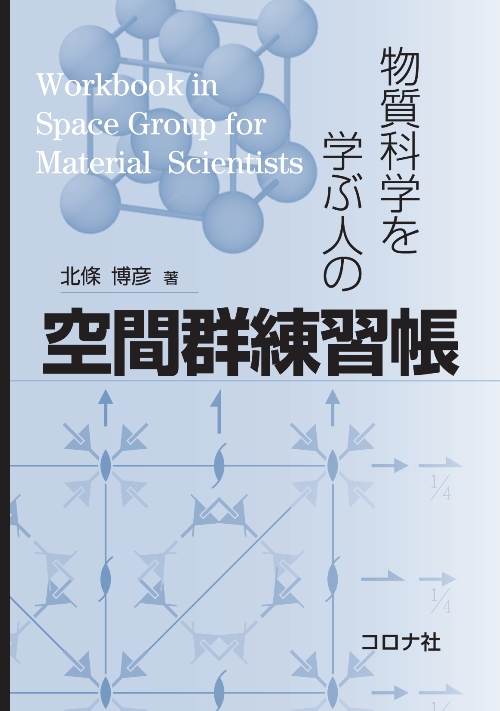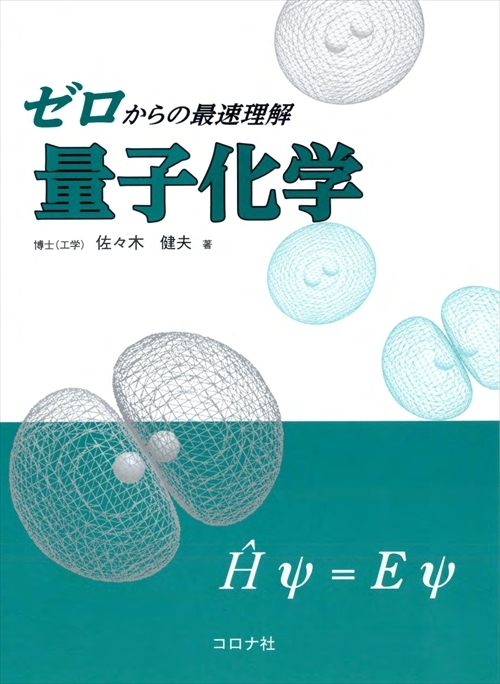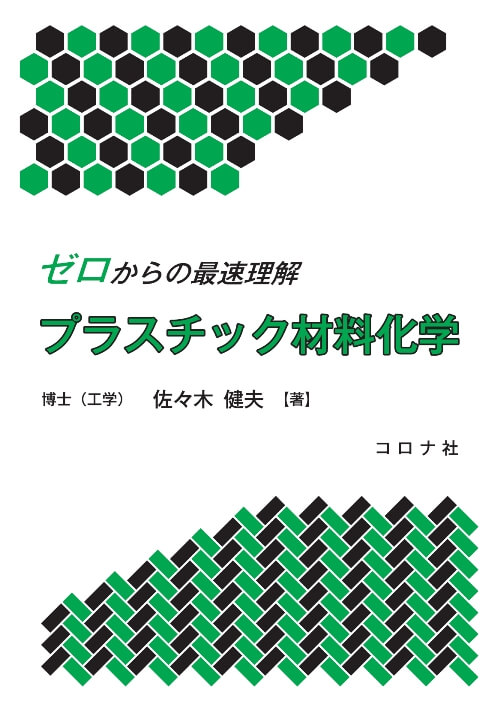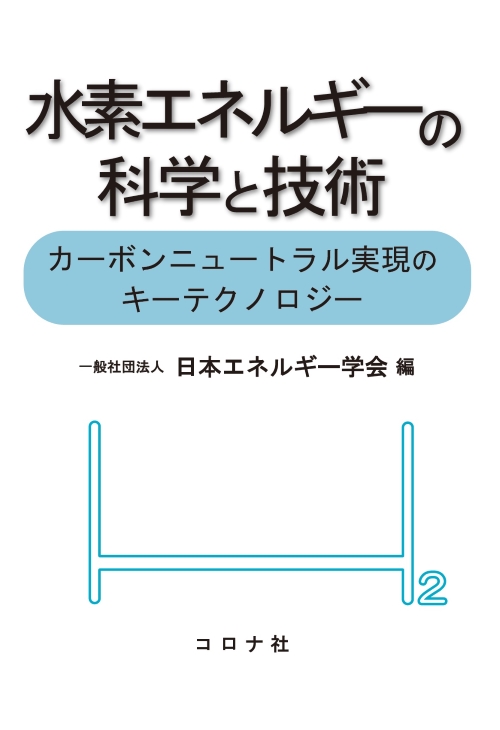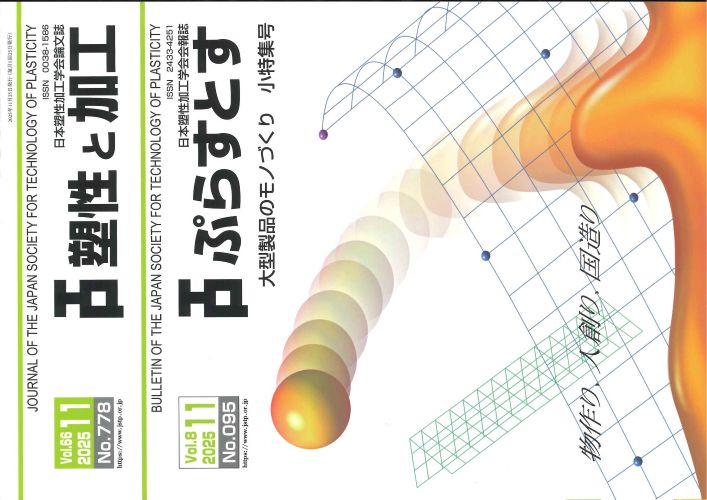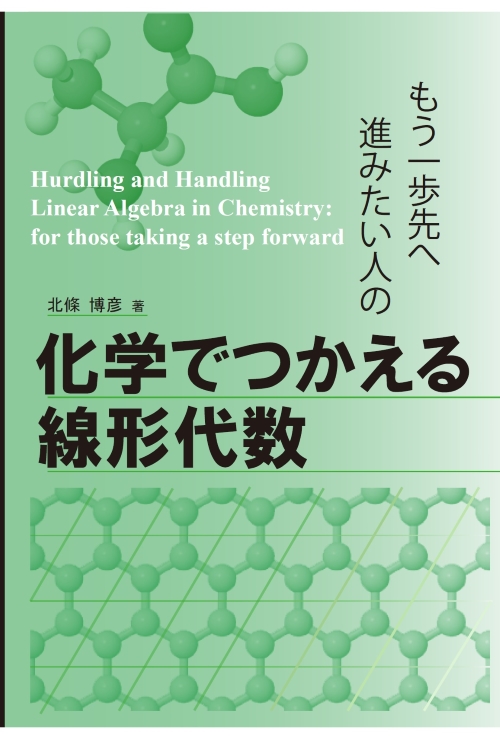分子分光学の基礎
分子分光学の幅広い領域にわたって,初歩から専門への糸口までの手引書
- 発行年月日
- 2025/05/02
- 判型
- A5
- ページ数
- 232ページ
- ISBN
- 978-4-339-06674-6
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 書籍紹介・書評掲載情報
- 広告掲載情報
【書籍の特徴】
本書では分子分光学の幅広い領域を,その原理的な内容を物理化学・量子論の立場から解説している。本書は初歩から専門への糸口までの手引書となるよう意図しており,いわば初歩的な解説書と高度な専門書の間のギャップを埋めるためのものである。分子分光学に関する世界的名著は数多く出版されているが,高度な量子論による取り扱いがなされていたり,内容も豊富であるために初学者にはハードルが高い。本書は学部2~3年生以上の初等量子化学をすでに学習済みの学生が分光学を学習する入門書として,また,この分野に関心をもつ読者が概観を得るための参考書として役立つであろう。
【各章について】
本書は全10章から構成されている。1章は序章であり,「スペクトル」の歴史と,分光学の観測対象に関して説明している。2~4章では分子分光学を学ぶ上で必要な,原子・分子や分子運動の量子論の基礎を解説している。5章では光の特徴および光と分子の相互作用に関して,6章ではマイクロ波分光法によって分子の構造が決定できることを説明している。7章では分子の振動スペクトルから得られる情報に関して,8章ではラマン分光法に関して解説している。9章では電子遷移に関連するスペクトルから得られる情報および励起分子のたどる失活過程に関して取り扱っている。10章では群論の基礎とその分光学への応用に関して解説している。理解の手助けになるよう,各章の章末には数問の演習問題を,その略解を巻末に掲載した。
【著者からのメッセージ】
分子分光学は測定対象や測定手法,また解析の取り扱いも含め,日々進化し続けている分野である。特に,実験手法に関しては,今日においても先駆的な方法が日々開発され,分子分光学はたゆまない進展を続けている。このような広範な分野を1冊の書籍にまとめあげることは困難であり,紙面の都合から取り扱いを断念せざるを得なかった重要な内容や,発展・応用的な内容は数多くある。巻末にはいくつかの詳しい参考図書をあげてあるが,本書をstep stoneとして,ぜひ高度な専門書にも挑戦してもらいたい。
現代科学のほぼすべての分野は「物質」に基盤を置いており,その機能物性や反応性等の性質を分子論的に理解することが必須となっている。現代科学においては,電磁波を用いた計測(分光学的計測)が物質の物性や構造解析の主流として用いられている。分光計測は定量/定性分析の基盤となっており,非常に多くの研究分野で使用されている。現代科学において分光計測をまったく取り入れない研究は稀であるといっても過言ではないだろう。その測定技術や装置も洗練されており,試料をセットしてスイッチを押せば,短時間で非常に簡便にスペクトルの測定ができてしまう。さらに,測定したスペクトルの帰属もオートマチックに行うことが可能となりつつある。しかしながら,観測したスペクトルには分子のどのような性質が反映されているのか,つまり,「一体何を見ているのか」といった測定原理がブラックボックス化しているのも事実である。本書では,分子分光学の原理的側面を基礎的な物理化学・量子論の立場から解説している。特に,マイクロ波分光法,赤外分光法,ラマン分光法,電子遷移などの種々の分光法で得られるスペクトルから分子の幾何学的構造や電子構造がどのように決定されるかを簡単な分子を例に取り扱っている。
本書は分子分光学の幅広い領域にわたって,初歩から専門への糸口までの手引書となるよう意図しており,いわば初歩的な解説書と高度な専門書の間のギャップを埋めるためのものである。分子分光学に関する世界的名著は数多く出版されているが,高度な量子論による取り扱いがなされていたり,内容も豊富であるために初学者にはハードルが高い。本書は学部2~3年生以上の初等量子化学をすでに学習済みの学生が分光学を学習する入門書として,また,この分野に関心をもつ読者が概観を得るための参考書として役立つであろう。
本書は全10章から構成されている。1章は序論であり,「スペクトル」の歴史と,分光学の観測対象に関して説明している。2~4章では分子分光学を学ぶ上で必要な,原子・分子や分子運動の量子論の基礎を解説している。5章では光の特徴および光と分子の相互作用に関して,6章ではマイクロ波分光法によって分子の構造が決定できることを説明している。7章では分子の振動スペクトルから得られる情報に関して,8章ではラマン分光法に関して解説している。9章では電子遷移に関連するスペクトルから得られる情報および励起分子のたどる失活過程に関して取り扱っている。10章では群論の基礎とその分光学への応用に関して解説している。理解の手助けになるよう,各章の章末には数問の演習問題を,その略解を巻末に掲載した。
最後に,分子分光学は測定対象や測定手法,また解析の取り扱いも含め,日々進化し続けている分野である。このような広範な分野を1冊の書籍にまとめあげることは困難であり,紙面の都合から取り扱いを断念せざるを得なかった重要な内容や,発展・応用的な内容は数多くある。巻末にはいくつかの詳しい参考図書をあげてあるが,本書をstep stoneとして,ぜひ高度な専門書にも挑戦してもらいたい。特に,実験手法に関しては,今日においても先駆的な方法が日々開発され,分子分光学はたゆまない進展を続けている。参考図書としてあげたいくつかの書籍には高度な計測技術に関する解説も多くある。
なお,本書は東京理科大学の3~4年生を対象に開講している「分子構造論1」の講義で扱っている内容をまとめたものである。講義資料の間違いの指摘や意見等をくれた多くの履修生に感謝したい。また,本書の刊行に際し,献身的にご協力いただいたコロナ社に感謝の意を申し上げる。
2025年2月
星野翔麻
1.序論 -分光学からわかること-
1.1 スペクトルとは
1.2 孤立分子のエネルギー
1.3 分子運動の自由度
1.4 分子がもつエネルギーの構造
演習問題
2.量子論の基礎
2.1 シュレディンガー方程式
2.2 量子力学的演算子
2.3 波動関数の解釈と条件
2.4 箱の中の粒子モデル
2.5 量子状態の特徴
2.6 波動関数の直交性
演習問題
3.原子・分子の量子論
3.1 水素類似原子の量子論
3.2 水素原子の発光スペクトル
3.3 原子軌道の特徴
3.4 波動関数の空間的広がり
3.5 多電子原子の電子配置
3.6 H_2^+分子の分子軌道
3.7 等核二原子分子の分子軌道
3.8 異核二原子分子の分子軌道
3.9 多原子分子の分子軌道
3.10ヒュッケル近似法
演習問題
4.分子の振動運動と回転運動
4.1 二原子分子のポテンシャルエネルギー曲線
4.2 調和振動子の古典力学的取扱い
4.3 二原子分子のバネモデル
4.4 調和振動子の量子力学的取扱い
4.5 分子の回転運動
演習問題
5.光と分子
5.1 電磁波の特徴
5.2 分子のもつエネルギー準位と電磁波の領域
5.3 吸収と放射の速度論
5.4 ランベルト-ベールの法則
5.5 振動子強度
演習問題
6.回転分光学
6.1 純回転遷移
6.2 回転スペクトルの様相
6.3 遠心力の効果
6.4 多原子分子の回転
演習問題
7.振動分光学
7.1 振動エネルギー準位
7.2 振動遷移の遷移選択律
7.3 同位体効果
7.4 振動の非調和性
7.5 振動-回転スペクトル
7.6 多原子分子の振動
7.7 多原子分子の赤外吸収
演習問題
8.ラマン分光学
8.1 ラマン散乱
8.2 振動ラマン遷移の遷移選択律
8.3 回転ラマン散乱
8.4 振動-回転ラマン遷移
8.5 多原子分子のラマン分光
演習問題
9.電子遷移
9.1 r電子系の電子遷移
9.2 電子遷移の振動構造
9.3 電子遷移の回転構造
9.4 励起分子の動的過程
演習問題
10.分子の対称性と分光学
10.1 対称要素と対称操作
10.2 点群の分類
10.3 対称操作と表現行列
10.4 指標表
10.5 分子運動の対称性
10.6 遷移選択律
演習問題
付録
引用文献
参考図書
演習問題の略解
索引
読者モニターレビュー【 分光屋さん 様 (業界・専門分野:レーザー分光、誘導ラマン散乱顕微鏡)】
本書は分光学、主に気体分子の振動回転分光とラマン分光、π電子系の可視紫外域分光への理解を深めることを目的として書かれた良書です。前半では原子・分子軌道、調和振動子、選択律など分光学で必須となる基礎事項を網羅的に取り扱っており、分光学と量子力学・量子化学の関連性が分かりやすく解説されています。後半では上記の分光法における実践的なスペクトルの帰属、解析方法について解説されています。また演習問題も多数掲載されており、これが概念的な理解だけでなく具体的・実践的な理解をさらに深めるのに役立つと感じました。このように本書は分光の初学者から実際に分光装置を使用するユーザーまで幅広い読者に役立つ内容をコンパクトにまとめており、幅広い読者に役立つことが期待される書籍かと思います。
読者モニターレビュー【 ニホニウム 様 (業界・専門分野:化学(無機化学系))】
本書は、分子分光学をこれから学ぶ方や、研究を始めるにあたって分光学の知識を得たい方におすすめの一冊です。分子の構造や運動に関する情報を得る方法として、マイクロ波分光法、赤外分光法、ラマン分光法、発光分光分析など、さまざまな分光法が挙げられますが、それぞれの分光法で「何を測定できるのか」、「得られるスペクトルが何を意味するのか」を、本書を通じて学ぶことができます。
分子分光学を直接の研究対象としていなくても、分子の同定、構造特性、発光特性の解析などにおいて分光法による測定は広く利用されているため、各分光法の原理を確認する上で役に立つ内容であると感じました。
前半の章では、シュレディンガー方程式や分子軌道法など、量子化学の基本事項が扱われており、基礎を確認しながら分光学の内容を読み進められる構成となっていました。後半の章では、分子の運動や対称性、それらを利用した分光法について、具体的な分子の例やスペクトルの概形などとともに解説されており、数式だけでは理解が難しい部分も視覚的な理解で補いながら学ぶことができました。
読者モニターレビュー【 高橋 新 様 株式会社aratama factory (業界・専門分野:化学、電気電子)】
本書『分子分光学の基礎』は、現代科学において必須の分析手法である分子分光学を、初学者にも理解しやすく体系的にまとめた優れた教科書です。
分光測定装置の高度化により「ブラックボックス化」が進む中、本書は「一体何を見ているのか」という根本的な問いに真摯に向き合っています。量子論の基礎(2-4章)から始まり、マイクロ波、赤外、ラマン分光法、電子遷移(6-9章)まで、各分光法の原理と分子構造決定への応用が丁寧に解説されています。特に、群論の分光学への応用(10章)まで含む構成は、理論と実践の橋渡しとして秀逸です。
著者が「初歩的解説書と高度な専門書の間のギャップを埋める」と述べているように、学部2-3年生が世界的名著に挑戦する前の「step stone」として最適な一冊です。各章末の演習問題と巻末の略解も、自学自習を助ける工夫として評価できます。分光学の本質を理解したい全ての研究者・学生に推薦したい良書です。
amazonレビュー
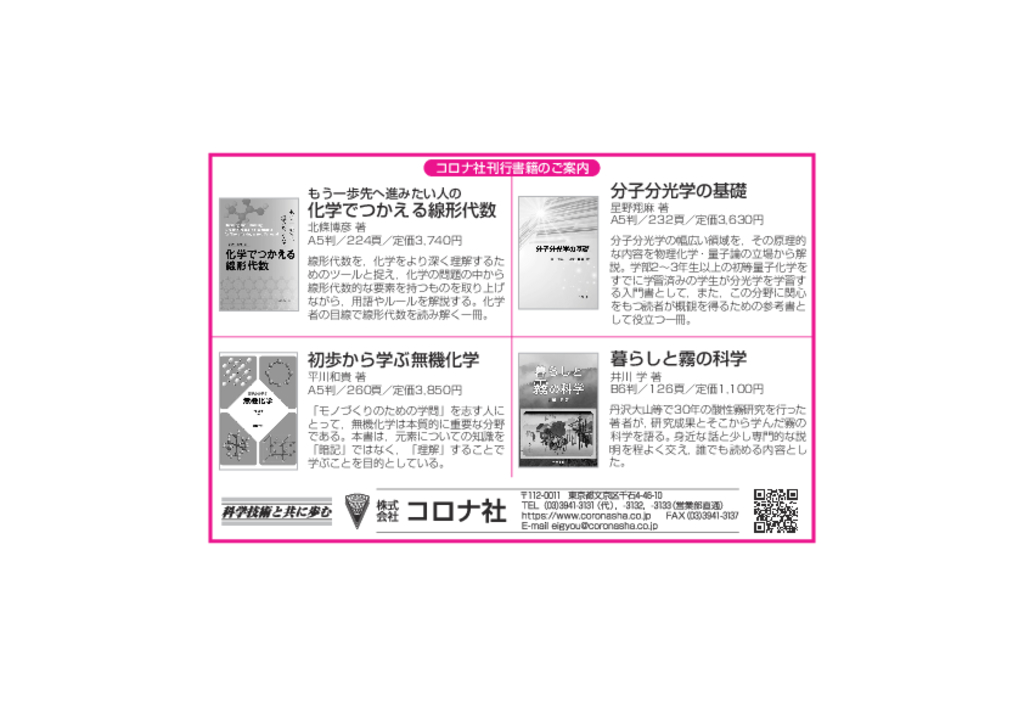
-
掲載日:2025/07/18
-
掲載日:2025/06/01
「化学と工業」2025年6月号 書籍ガイド