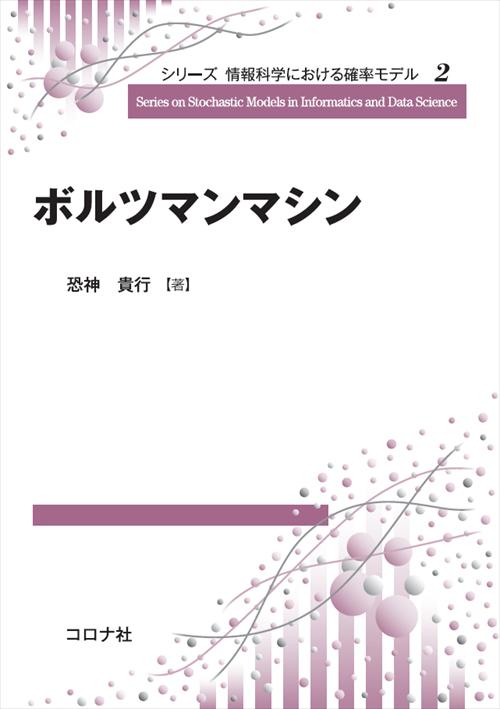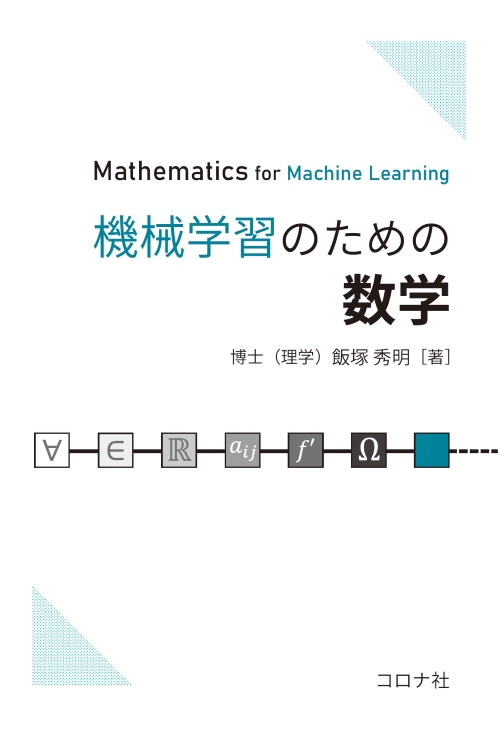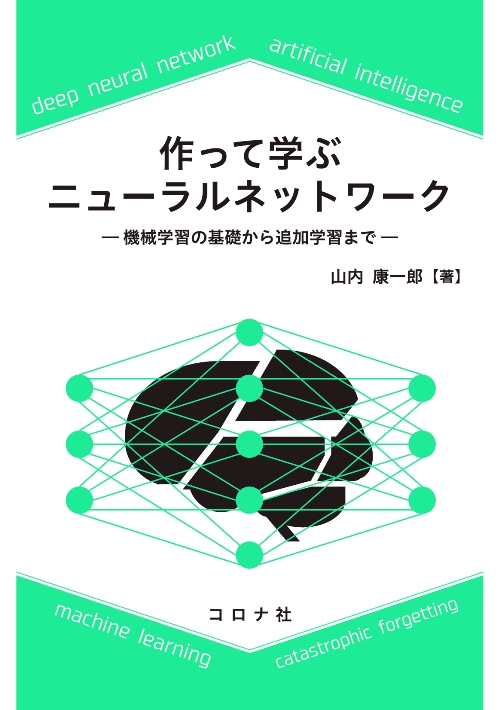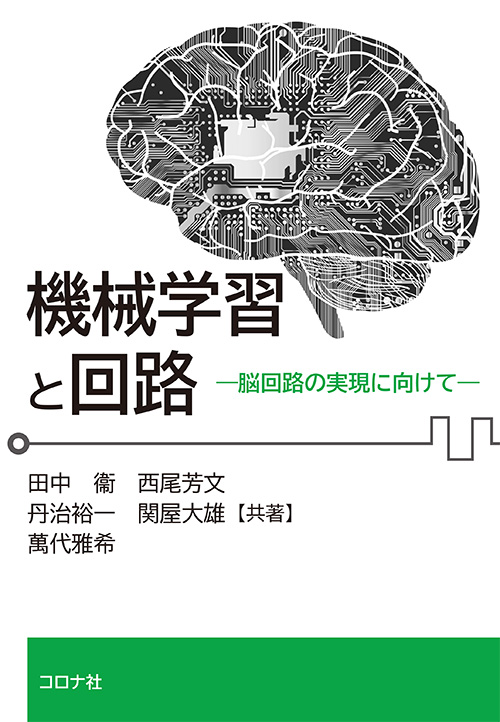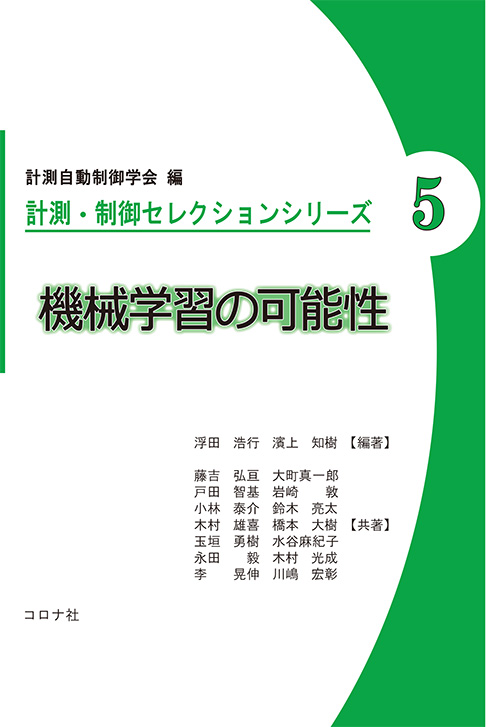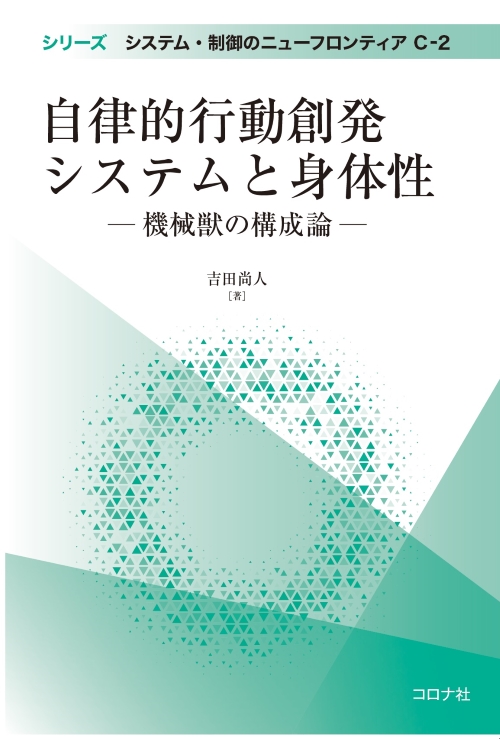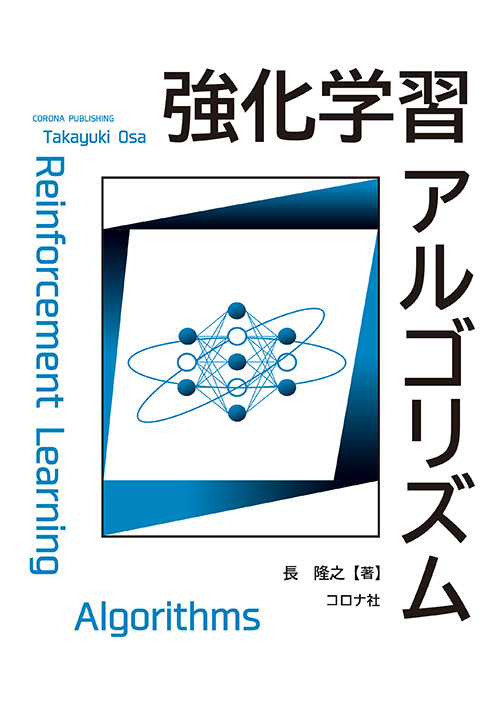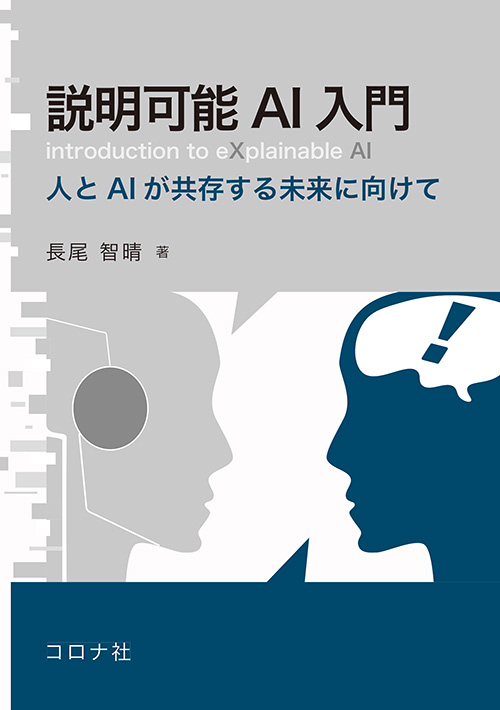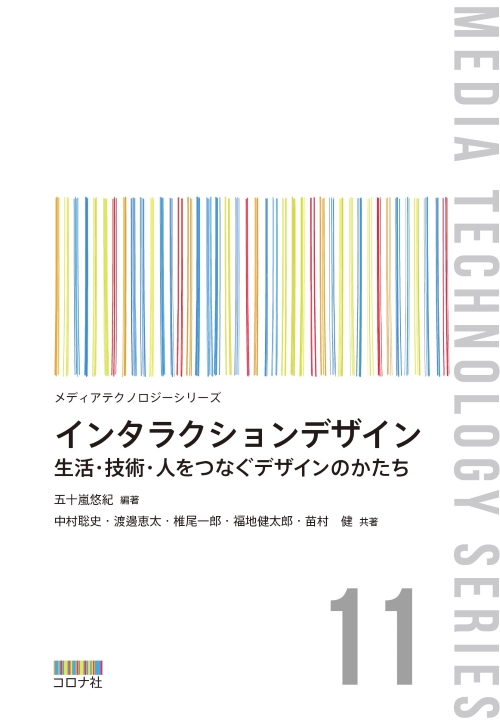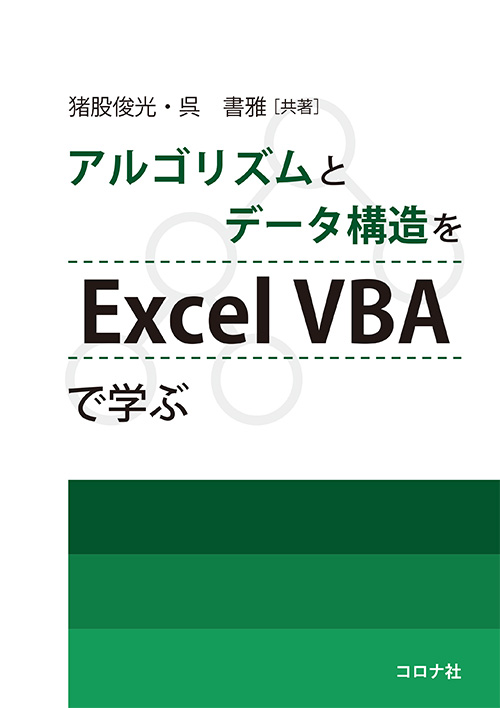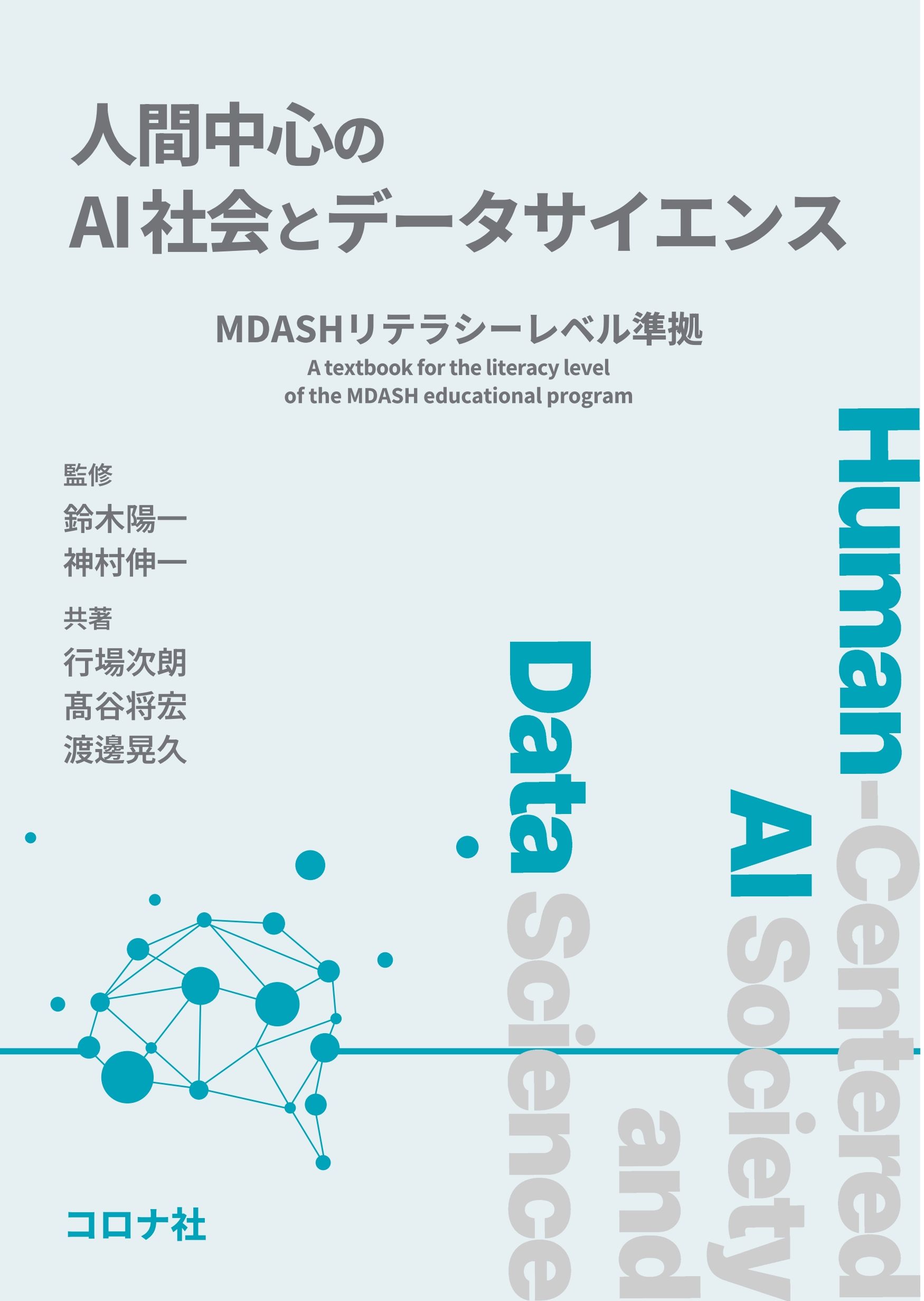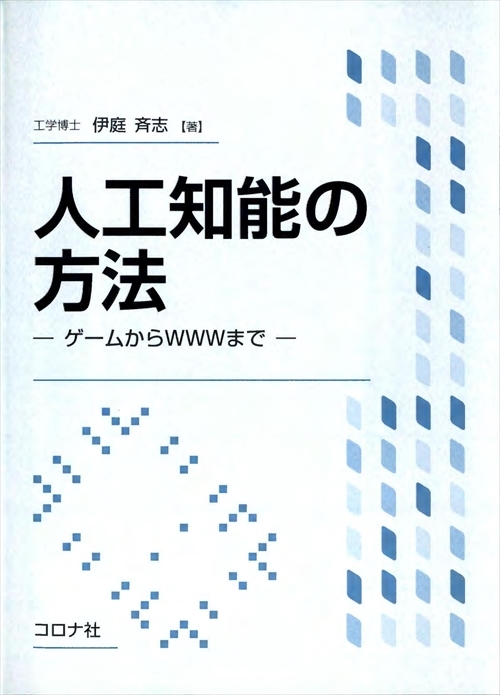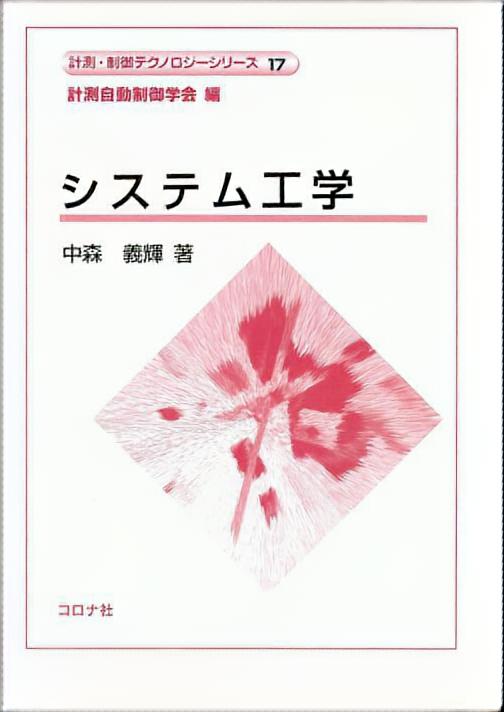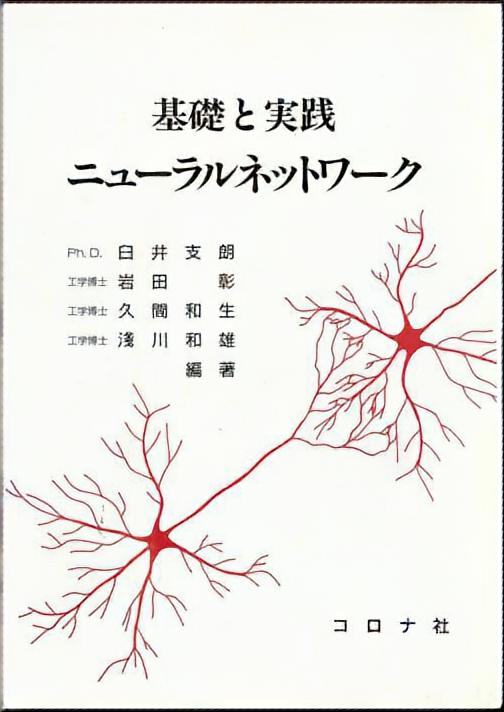数理でひもとくAI技術の深化 - ボルツマンマシンとたどる最先端への道 -
2024年ノーベル物理学賞の主要研究成果ボルツマンマシンと共に,AI技術の最先端へ!
- 発行年月日
- 2025/07/23
- 判型
- A5
- ページ数
- 160ページ
- ISBN
- 978-4-339-02951-2
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 書籍紹介・書評掲載情報
- 広告掲載情報
【読者対象】
本書は、2024年のノーベル物理学賞の対象となったホップフィールドネットワークやボルツマンマシンとは何かを知りたい方、そしてその理解を足がかりに、現代の人工知能技術の最前線に触れたいと考える読者を対象としています。前提となる知識は可能な限り抑えており、理系の大学生程度の数理的素養があれば読み進められるよう配慮しています。一方で、情報科学・人工知能・物理学など各分野の専門家にとっても、新たな視点が得られる内容を目指しています。
【書籍の特徴】
本書の最大の特徴は、ボルツマンマシンを軸として、さまざまな分野についての議論を展開している点にあります。機械学習、統計力学、計算量理論、最適化、量子計算、確率過程など、幅広い分野にまたがる内容を扱いつつ、それぞれの要点を押さえ、共通する構造や相互の関連性が自然に見えてくるように構成されています。
各章は基本的な概念から始まり、場合によっては最先端の研究成果にまで踏み込んだ議論を行います。難解な内容については、あえて一般性を犠牲にし、特別な場合に絞って丁寧に解説することで、直感的な理解を助けます。また、数式なしでは捉えきれない概念は、数式を積極的に用いながら、その背後にある意味や現実との対応関係を日本語で丁寧に説明し、読者の理解を深めることを目指しています。
【各章について】
1章では、ホップフィールドネットワーク、ボルツマンマシン、イジング模型、イジングマシンといった一見異なる概念が、本質的には同じ数理モデルに基づいていることを明らかにします。本書ではこの基本モデルを軸に、全体の議論を組み立てていきます。
2章では、ホップフィールドネットワークによる連想記憶の仕組みを出発点として、現代の大規模言語モデル(たとえば ChatGPT)において中心的役割を果たす注意機構へと議論を発展させます。
3章では、イジング模型を用いて統計力学の基礎から相転移の概念までを解説します。
4章では、イジングマシンを用いた巡回セールスマン問題の解法を起点に、計算量理論の基礎概念を導入し、さらに量子計算の一方式である量子アニーリングにまで議論を広げます。
5章では、ボルツマンマシンによる確率分布の学習の仕組みを出発点に、現代の画像生成AIにおいて重要な役割を担うスコアモデルや拡散モデルへと議論を発展させます。
【読者へのメッセージ】
できるだけ直感的な理解が得られるように説明を工夫しました。これまで分からなかったことが「分かった」「なるほど」と思っていただける箇所があれば幸いです。
【本書のキーワード】
ホップフィールドネットワーク、イジング模型、イジングマシン、ボルツマンマシン、連想記憶、注意機構、相転移、巡回セールスマン問題、量子アニーリング、生成AI、スコアモデル、拡散モデル
2024年,ノーベル物理学賞の受賞者がJohn HopfieldとGeoffrey Hintonに決まったというニュースが飛び込んできた。10月8日のことである。機械学習・人工知能という自分が深くかかわる分野でノーベル賞の受賞者が出たことに大きな驚きを感じたのは,この分野の多くの研究者と同じだろう。
スウェーデン王立科学アカデミーのプレスリリースを読むと,「John Hopfieldは,パターンを保存し再現する方法を使用するネットワークを発明しました。このネットワークのノードはピクセルと思うことができます。ホップフィールドネットワークは…」そして「Geoffrey Hintonは,ホップフィールドネットワークを基盤として,異なる方法を用いる新しいネットワークであるボルツマンマシンを開発しました…」という出だしで受賞理由が説明されており,ホップフィールドネットワークとボルツマンマシンが,受賞理由となる主要な研究成果のキーワードとして強調されている。
2019年に「ボルツマンマシン」を上梓した著者にとって,これは感無量である。少なくとも「なんでそんな本書いたの?」という娘たちの素朴な疑問に対して説明をしやすくなった。前著では,深層学習が注目されるようになる際にボルツマンマシンが果たした役割を力説するとともに,その基礎となる数理も丁寧に解説した。また,「シリーズ情報科学における確率モデル」の一書目であることから,ボルツマンマシンという共通の確率モデルを,生成モデル・判別モデル・時系列モデル,さらには強化学習の行動価値関数モデルとして用いることで,確率モデルの可能性の広さを感じられる構成とした。その内容はいまだ古びることなく,2024年のノーベル物理学賞をきっかけに,より多くの人に読んでいただければ望外の喜びである。
その一方で,前著「ボルツマンマシン」には心残りな点もあった。それは,Amazonのカスタマーレビューにうみねこcafeさんという方が書いてくださった「ヒントン博士の2006年の論文については詳しいですが,ボルツマンマシンが発表された当時の経緯の説明はありません。なのでホップフィールド模型の解説もないので,ホップフィールド模型との違いも含めてボルツマンマシン自体がいまいち分かりません。」というコメントに集約される。これは至極ごもっともなご指摘であり,特に2024年のノーベル物理学賞をきっかけにボルツマンマシンに興味を持たれるかもしれない幅広い読者を考えると,重大な懸念点でもある。
以上が新たに本書を執筆するきっかけである。はじめは,30ページくらいの「第0章」を加えて,前著「ボルツマンマシン」の改訂版を出せないかとコロナ社に相談したが,諸事情を考慮した結果,独立した書籍として出版することになったのが本書である。結果的にこれはとてもよい決定になった。
まず,前著「ボルツマンマシン」と比べて,はるかにボルツマンマシンの広がりが感じられる内容になった。機械学習や人工知能はもちろんのこと,最適化・計算量理論・統計力学・量子力学・確率過程と多岐にわたる話題に触れることになった。これらすべてがボルツマンマシンというレンズを通して見えるのが,本書である。
また,当初はボルツマンマシンに至る歴史的な背景を「第0章」で加筆しようと考えていたが,1冊の書籍でありページ数に余裕があることから,ボルツマンマシンが生まれた後の話題も多く含めることになった。結果,前著「ボルツマンマシン」が出版された後に発表された最新の研究成果も踏まえた内容となっている。特に,「これらのほかにもフィッシャーダイバージェンスの適用範囲を広げる試みがなされている。」と前著第3章を締めくくったフィッシャーダイバージェンス(スコアマッチング)に関する技術はその後大きく発展して,現代の生成AIにおいて主要な役割を果たしている。前著で1.5ページだったスコアマッチングに関する話題は,本書では21ページに拡張された。
上記の変更は,2024年11月6日に第27回情報論的学習理論ワークショップにて行われた,甘利俊一先生によるノーベル物理学賞記念特別講演の影響も強く受けている。2章でも触れるように,Hopfieldがホップフィールドネットワークを提案する10年前に,ホップフィールドネットワークと本質的に同じモデルを提案した方が甘利先生である。すでに本書の執筆が決まっていた著者は,甘利先生の講演から執筆内容のヒントを得ようとしていた。ところが,甘利先生の講演はまったく過去を振り返るものではなく,未来を向いた話しかなかった。結果として,甘利先生ほど未来志向ではないものの,多くの最先端の話題を本書で取り上げることになった。それでも,うみねこcafeさんのご指摘に応えられる内容にもなっているだろう。
最後になりましたが,原稿を丁寧に読み,誤りやわかりにくい点についてコメントや感想をくださった坂井智哉氏に深く感謝いたします。また,各章の冒頭を読んで,どこまでならわかるかを教えてくれた,高校3年生の長女花菜と小学4年生の三女沙菜にもお礼を申し上げます(また挑戦してみてください)。
なお,本書の執筆にあたっては,ChatGPTを随所で活用した。特に,図を作成するためのプログラムはすべてChatGPTで生成し,必要に応じて修正を加えたものである。また,本文の一部についても,ChatGPTを用いて文章をより読みやすく整えた。もちろん,内容に関する責任はすべて著者にある。
2025年5月
恐神貴行
1.はじめに
1.1 異なる目的と共通の数理モデル
1.1.1 ホップフィールドネットワーク
1.1.2 イジング模型
1.1.3 イジングマシン
1.1.4 ボルツマンマシン
1.1.5 注意
1.2 基本モデル
1.2.1 変数
1.2.2 パラメタ
1.2.3 機械学習モデルと物理モデル
1.3 本書の読み方
2.ホップフィールドネットワークと連想記憶
2.1 連想記憶
2.2 甘利・ホップフィールドネットワーク
2.2.1 ホップフィールドネットワークの構造
2.2.2 推論アルゴリズム
2.2.3 学習アルゴリズム
2.3 連想記憶ができる理由
2.3.1 なぜ想起できるのか?
2.3.2 なぜ記憶できるのか?
2.3.3 複数のパターンを記憶できることの確率的考察
2.4 一般化ホップフィールドネットワーク
2.4.1 稠密連想記憶装置
2.4.2 一般化ホップフィールドネットワーク
2.4.3 凹凸手続きの収束
2.5 注意機構
2.6 まとめ
3.イジング模型と相転移
3.1 レンツ・イジング模型
3.2 ボルツマン分布
3.2.1 熱力学第2法則
3.2.2 エントロピー
3.2.3 エントロピーの最大化
3.3 相転移
3.4 スピンの量子的性質
3.4.1 量子状態
3.4.2 パウリ行列とハミルトニアン
3.5 まとめ
4.イジングマシンと最適化
4.1 巡回セールスマン問題
4.1.1 計算量クラス
4.1.2 実用上の困難さ
4.2 イジングマシン
4.2.1 エネルギー関数
4.2.2 組合せ最適化問題に対するアプローチ
4.3 イジングマシンによるモデル化
4.3.1 エネルギー関数の設計
4.3.2 イジングマシンによるモデル化の注意点と限界
4.4 イジングマシンによる最適化
4.4.1 ギブスサンプリング
4.4.2 ギブスサンプリングの収束
4.4.3 シミュレーテッドアニーリング
4.5 量子アニーリング
4.6 まとめ
5.ボルツマンマシンと生成モデル
5.1 ボルツマンマシン
5.1.1 確率分布の学習の指針
5.1.2 勾配法による学習
5.1.3 確率的勾配による学習
5.1.4 ヘブ則との関係
5.2 確率の計算とサンプリング
5.3 スコアマッチングによるスコアモデルの学習
5.3.1 エネルギーモデルとスコアモデル
5.3.2 スコアマッチング
5.3.3 スライススコアマッチング
5.4 スコアモデルからのサンプル生成
5.4.1 ランジュバン動力学サンプリング
5.4.2 条件付き確率分布からのサンプリング
5.5 拡散モデル
5.5.1 拡散過程
5.5.2 時間を反転させた拡散過程
5.5.3 スコアモデルを用いた学習
5.5.4 等式(5.79) の確認
5.6 まとめ
引用・参考文献
索引
読者モニターレビュー【moonbow 様(業界・専門分野:統計科学・バイオインフォマティクス))】
本書は「ボルツマンマシン」という卓越した理論装置を軸に、歴史・数理・応用という三位一体の構成で人工知能の深化を描き出す労作である。2024年、ノーベル物理学賞がジョン・ホップフィールドとジェフリー・ヒントンに授与されたことは、人工知能と統計物理学との深淵な結びつきを世界に知らしめ、新たな知の時代の幕開けを告げた。その新時代の扉を開く鍵こそ、「ボルツマンマシン」に他ならない。
「ボルツマンマシン」は、ホップフィールドネットワークやホップフィールド模型と数理的には同根であり、統計力学、脳神経科学、さらには人工知能の諸分野において独自の発展を遂げてきた。確率的性質を内包するこのモデルは、単なる数理的好奇心にとどまらず、統計的推論やエネルギー最適化の基盤として極めて重要である。
さらに注目すべきは、近年熱狂的な注目を浴びる大規模言語モデル(LLM)や拡散モデルにも、「ボルツマンマシン」の数理が深層に息づいているという事実である。こうした先端技術を真に理解し、創造的に展開するためには、本モデルの本質的な理解が不可欠であろう。
本書は単なる技術解説書ではない。統計、人工知能、深層学習、統計力学、最適化、神経科学といった諸分野を横断し、知のエッセンスを統合する数理的思考の書である。「ボルツマンマシン」に関心を寄せる研究者はもとより、確率モデルにより深い洞察を求める読者、さらには大規模言語モデルや拡散モデルの理論基盤を渇望する技術者にとっても、必携の書といえよう。
読者モニターレビュー【 すず 様 (業界・専門分野:哲学)】
自然言語の文章のような系列データをAIが扱う際には、情報を記憶しそれを適切に利用できる必要がある。従来はニューラルネットワークの構造に再帰的な結合を導入することでデータを逐次的に処理していた(RNN)のに対し、大規模言語モデル(LLM)のアーキテクチャであるTransformerは、注意機構によってデータを並列的に処理している。
以上のようにごく簡単に歴史を整理したとき、注意機構の登場は唐突であるように思われるかもしれない。しかし実は、注意機構は、70年代に登場し発展してきた(甘利・)ホップフィールドネットワークを一般化したものと同一視することができるという。本書第二章は、単純なホップフィールドネットワークの紹介から始まり、それを徐々に一般化していくことで、注意機構を歴史的な文脈に位置づけることを可能にする。
以降の章でも同様に、最先端の話題を単純なモデルを介して扱っている。いずれのモデルの説明においても数式が使われており、また随所に数式の「気持ち」が添えられている。したがって読者は、数理的な正確性を損なうことなく、最先端の話題を直観的に理解することができる。
読者モニターレビュー【 Haruk1y 様(業界・専門分野:機械学習)】
本書の最大の特徴は、ホップフィールドネットワーク、イジング模型、イジングマシン、ボルツマンマシンという一見異なる分野の手法が、実は本質的に同一の数理モデルを基礎としていることを明確に示している点にあります。また、基本のモデルを出発点とした議論の広がりも本書の特徴です。第2章では注意機構まで、第4章では量子アニーリングまで、第5章ではスコアモデルや拡散モデルまでと、現代の機械学習における最先端の話題まで一貫した枠組みで扱われており、分野の歴史的発展を俯瞰できる構成となっています。数式の扱いにも配慮が行き届いており、直感的理解を促すための日本語での説明が併記されています。これにより、数学的な厳密性を保ちながらも、読者の理解を深める工夫が随所に見られます。
基礎的な概念から最先端の応用まで段階的に構成されているため、初学者でも無理なく学習を進めることができる一方で、専門家にとっても新たな視点を得られる深い内容となっていると思います。2024年のノーベル物理学賞受賞により注目が集まっている現在、異なる分野の知見を横断的に学びたい研究者や学生はもちろん、この分野の発展に関心を持つ幅広い読者にとって、極めて価値の高い一冊といえます。
【 yoshiki様(業界・専門分野: Engineering in Medicine )】
本書では、ホップフィールドネットワークから生成AIの拡散モデルまでが一気通貫で解説されています。本書の魅力は、ボルツマンマシンを中心に据え、統計力学・計算量理論・量子計算といった一見別々の領域をまとめて説明し、AI技術に共通する構造をわかりやすく示している点です。
第1章ではホップフィールドネットワークとイジング模型の数理的同型を示し、第2章では連想記憶からTransformerの注意機構へと議論を発展させます。この「古典から現代へ」の橋渡しは丁寧で分かりやすく、読者が無理なく最新の理論へと進めるよう配慮されています。さらに第4章ではイジングマシンを用いた巡回セールスマン問題の実装例を取り上げ、量子アニーリングにも踏み込むため、理論志向の読者にも応用志向の読者にも響く内容となっています。終章に位置付けられたボルツマンマシンと拡散モデルの対比は、生成AIの数理を学びたい方にとって格好のガイドとなるでしょう。
解説では数式を惜しみなく使用しつつも、直感的な理解ができるよう日本語で丁寧に説明しており、微分・積分と確率の基本的な知識があれば大部分を読み進められます。各章末のまとめが要点を端的に再確認させてくれるため、読み進める手が止まりにくいのもありがたいです。
総じて、本書は「ボルツマンマシン=古典的モデル」という固定観念を覆し、AIの現在地と未来像を俯瞰させてくれる稀有な一冊です。2024年にJohn J. Hopfield氏とGeoffrey E. Hinton氏がノーベル物理学賞を共同受賞して注目が高まる今こそ、AIを数理で深く理解したい研究者・エンジニア・学生におすすめです。
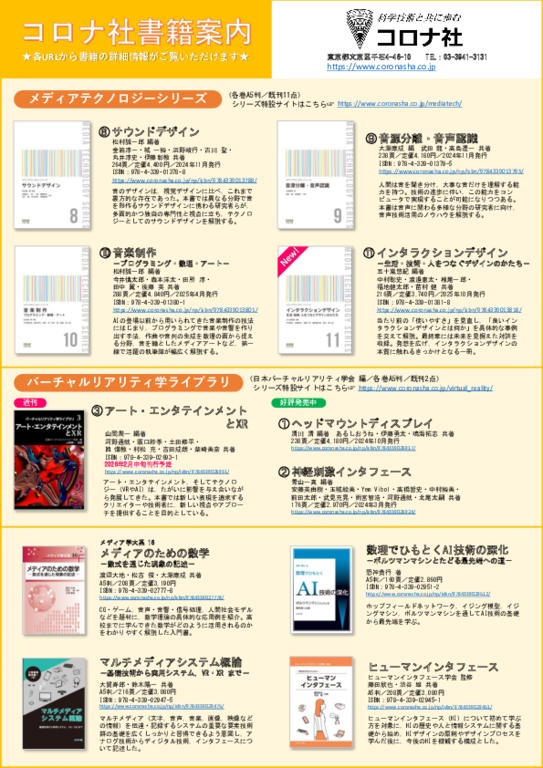
-
掲載日:2025/12/31
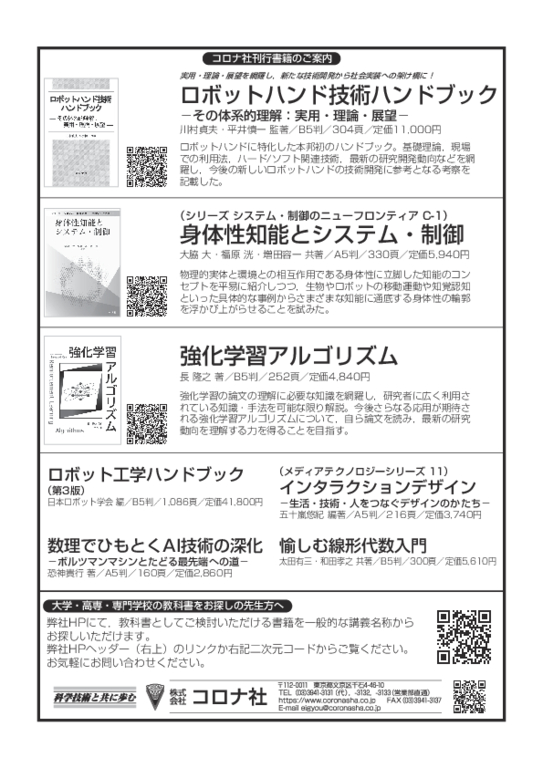
-
掲載日:2025/12/15
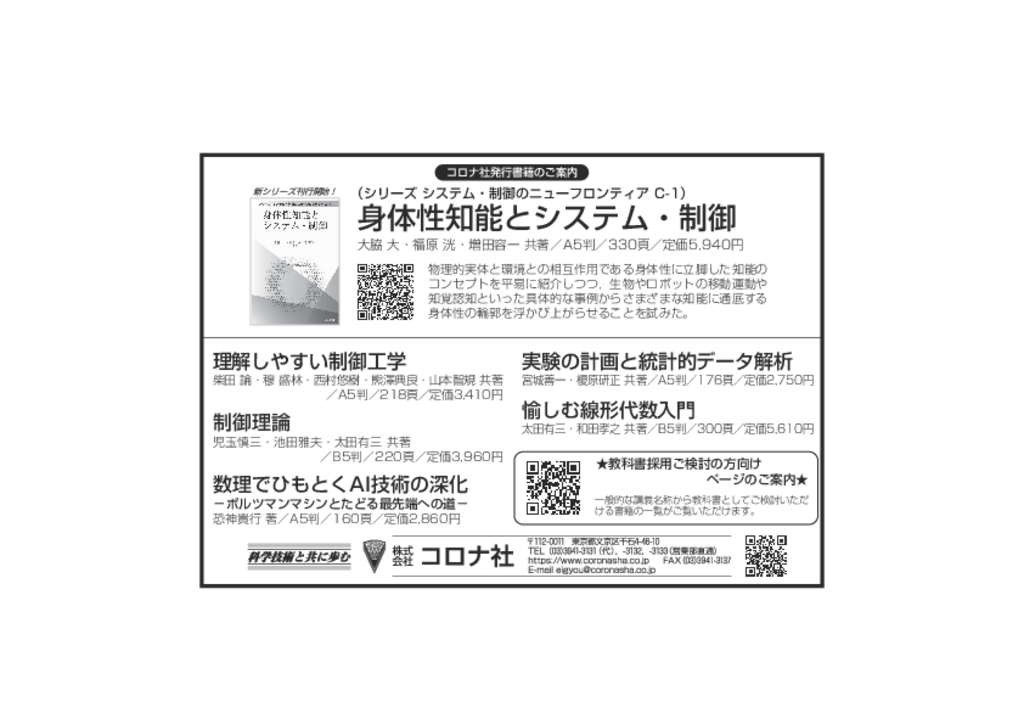
-
掲載日:2025/10/10
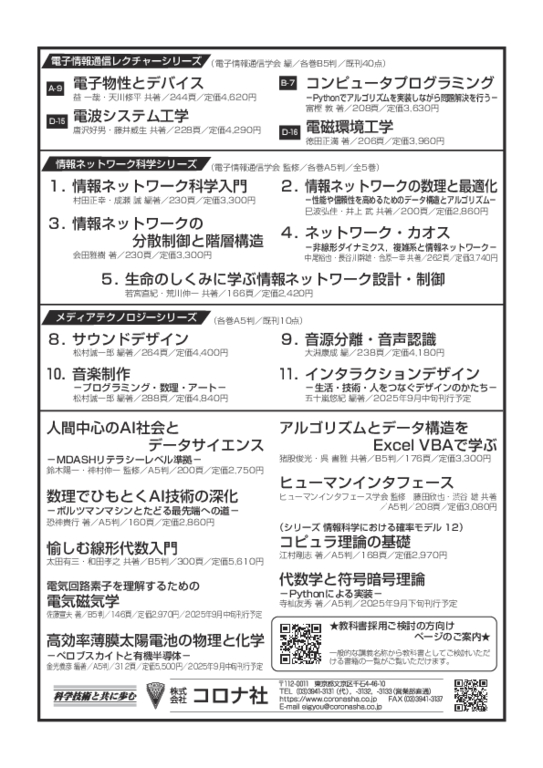
-
掲載日:2025/09/08
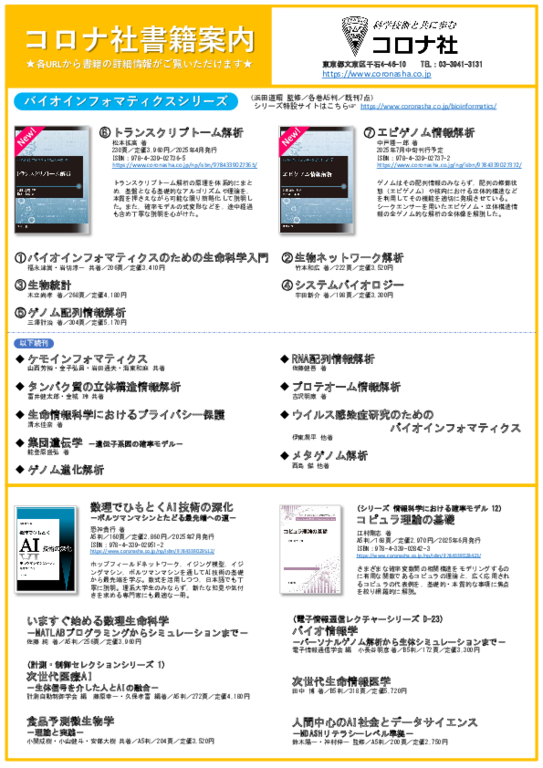
-
掲載日:2025/09/03
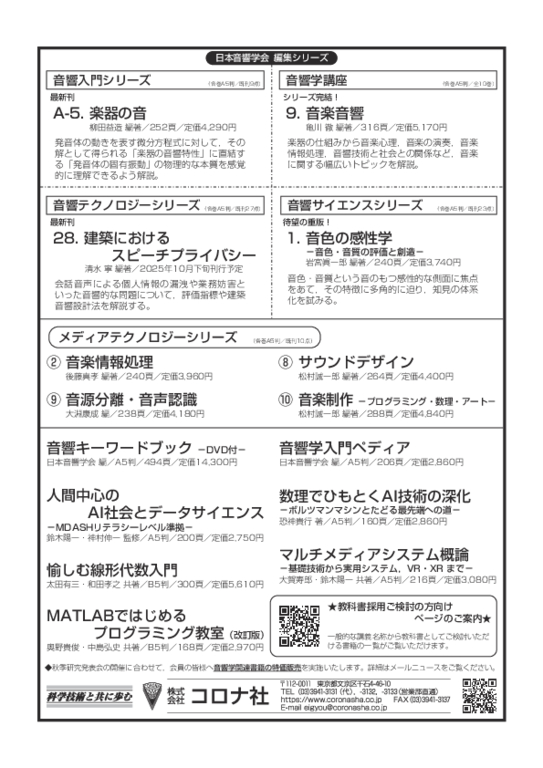
-
掲載日:2025/09/01

-
掲載日:2025/08/12
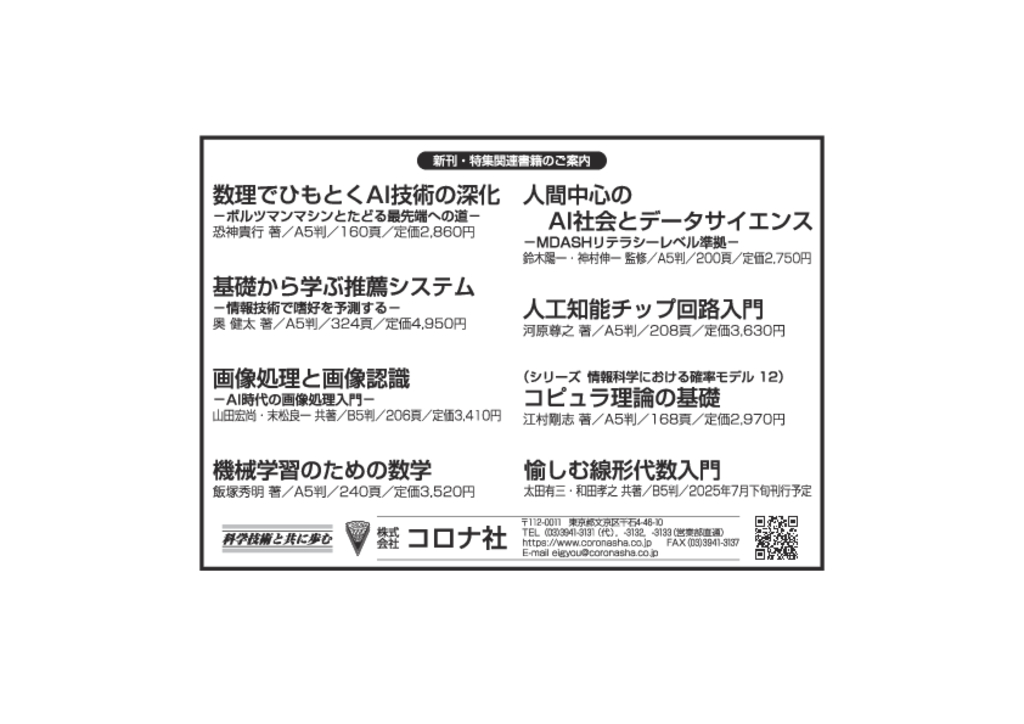
-
掲載日:2025/08/01
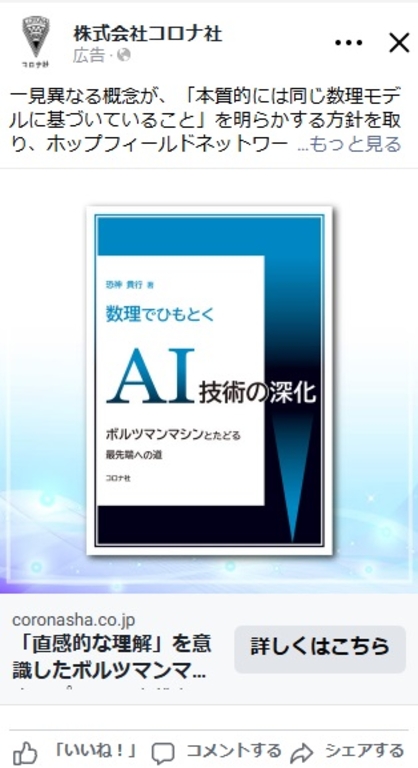
-
掲載日:2025/07/04
facebook広告「数理でひもとくAI技術の深化 - ボルツマンマシンとたどる最先端への道 -」(2025年7月4日)
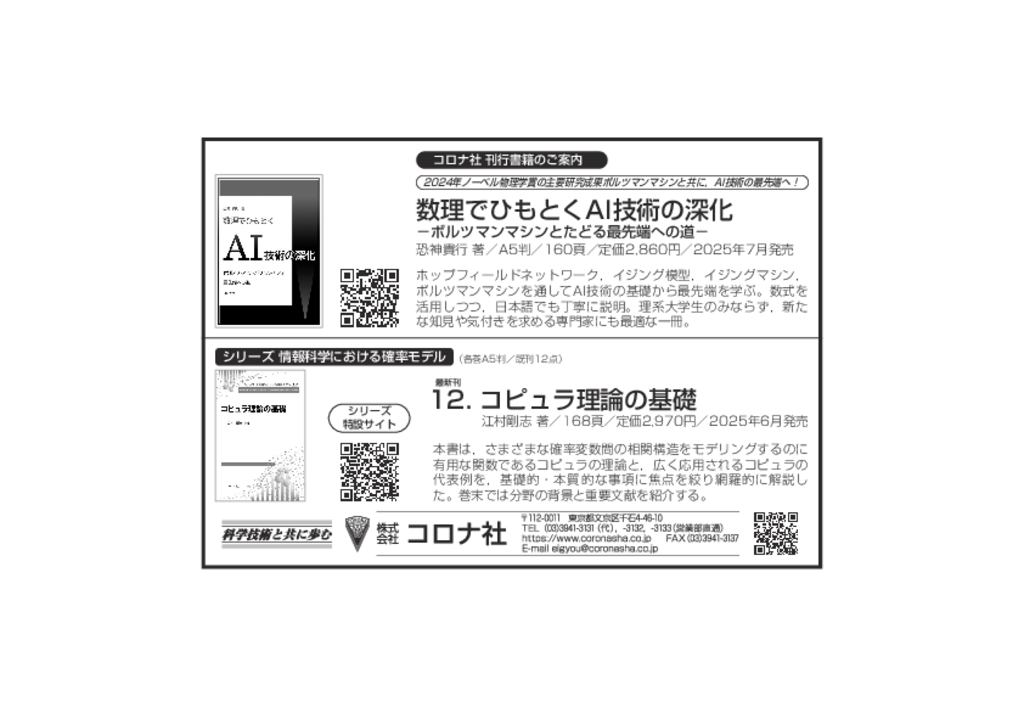
-
掲載日:2025/07/01