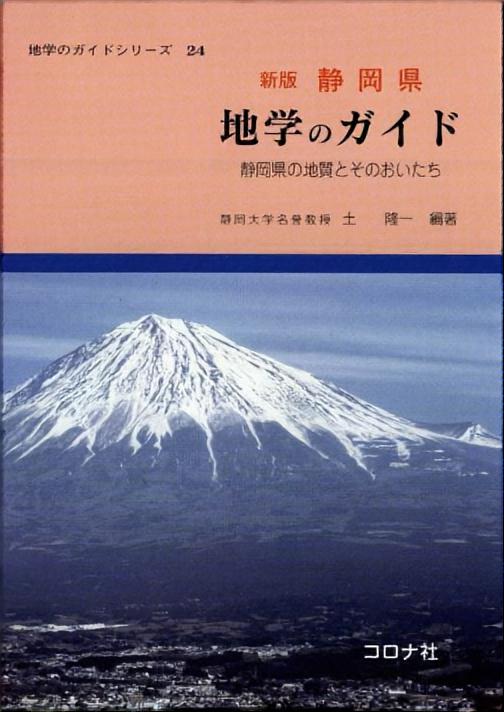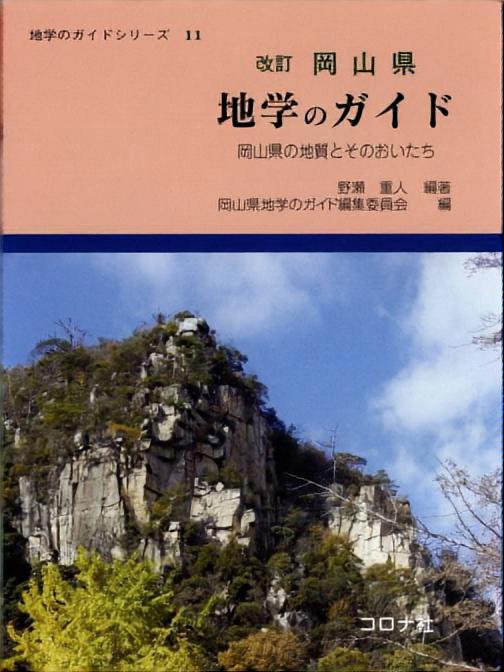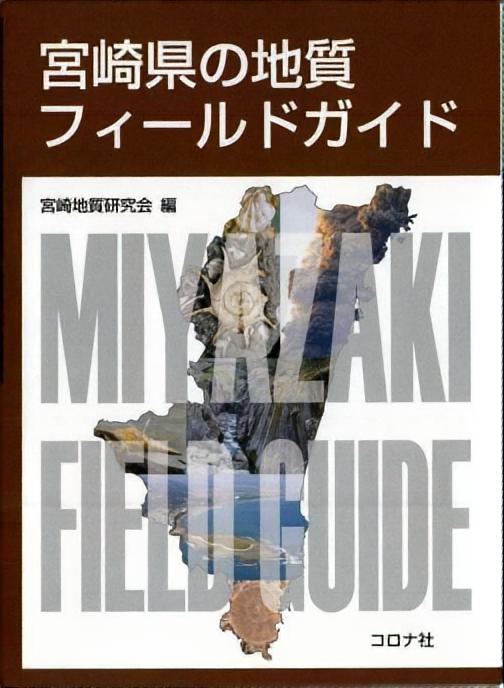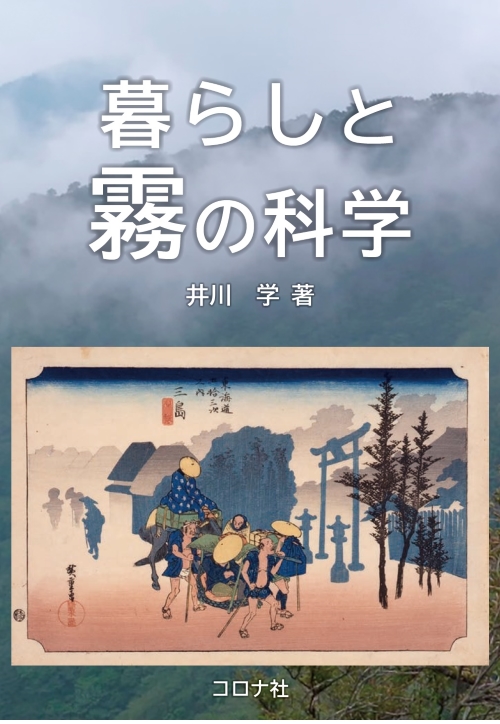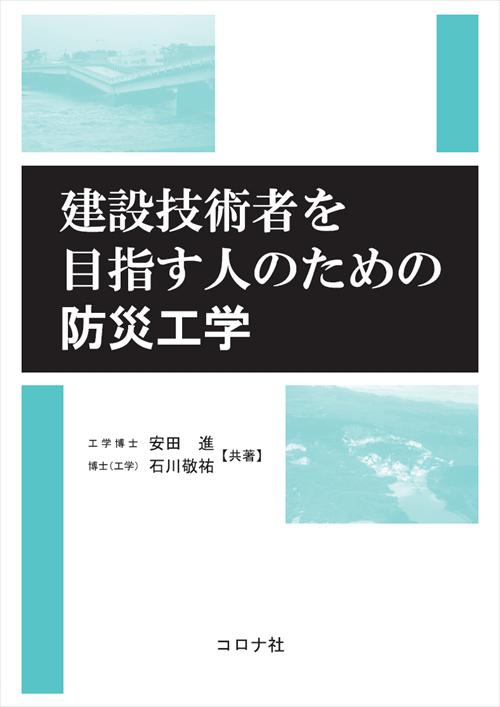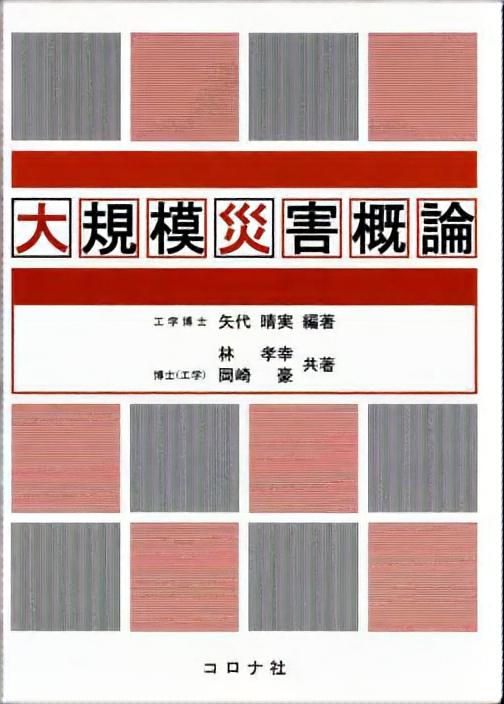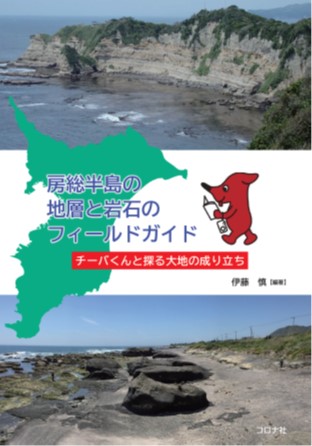
房総半島の地層と岩石のフィールドガイド - チーバくんと探る大地の成り立ち -
地層や岩石の観察を通して,房総半島の魅力を満喫できる,新しいフィールドガイド。
- 発行年月日
- 2025/12/15
- 判型
- B5 フルカラー
- ページ数
- 208ページ
- ISBN
- 978-4-339-06673-9
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
房総半島に分布する地層や岩石は,河川,沿岸,浅海,深海と,様々な堆積環境で形成されたものであり, 国内外をとおして,地層や岩石の宝庫の一つといえます。そのような房総半島の地層や岩石の野外観察をとおして,大地の成り立ちや地球環境史を理解するためのフィールドガイドとしてご活用いただける書籍です。なお3章では,各節の冒頭で見学地点を紹介しています。各地点の情報は,Google Earth 上にて閲覧することが可能です。※「チーバくん」について,千葉県より許諾を得て使用しています(千葉県許諾第B617-1 号)。
【3 章の見学地点,地域】
銚子地域/木下地域/君津-木更津-市原地域/磯根崎-上総湊地域/久留里-養老川-平蔵川-笠森地域/国本層と千葉セクション/小糸川-小櫃川-養老川-太東地域/太東-大原-御宿-勝浦地域/鵜原地域/萩生・竹岡-湊川-養老川地域の黒滝層/三島湖-豊英湖-三石山/鋸山周辺と志駒川地域/鴨川-嶺岡山地-保田・勝山地域/江見海岸周辺地域/南房総の海成段丘 /沼サンゴ層/見物-沖ノ島-大房岬-那古-正木地域/西川名-布良-白浜-白間津-千倉地域/白浜津層と白間津層の生痕化石/千葉市幕張-稲毛付近の昔の海岸線
読者の皆さん,房総半島へようこそ!
房総半島は,四方を海と川に囲まれた自然豊かな大地です。この大地には,山地,丘陵,台地,低地など,さまざまな地形が発達しています。また,房総半島の周辺にはプレート境界が存在しているため,地球の鼓動を身近に感じることができます。房総半島には,さまざまな時代と種類の地層や岩石が分布し,大地が構成されています。このような大地を構成する地層や岩石には,日本列島がアジア大陸東縁部に存在していた時代から,日本海の形成に伴って島弧となり現在に至るまでの,海洋プレートの沈み込みに伴う大地の沈降と隆起や地球環境の変動などの特徴が詳しく記録されています。また,世界で初めて日本の地名が地質時代の名称「チバニアン」として設定された地層も,房総半島に分布しています。さらに,房総半島に分布する地層や岩石は,河川,沿岸,浅海,そして深海と,さまざまな堆積環境で形成されたものです。したがって,このような地層や岩石から,直接観察することのできない地層や岩石の形成過程を詳しく解読することが可能です。このように房総半島は,国内外をとおして,地層や岩石の宝庫の一つといえます。
房総半島は,首都圏にあり,交通のアクセスもよいことから,古くから「巡検」と呼ばれる地層や岩石の見学旅行の対象地域となっています。また,大学や研究所などによる地質学や地球科学の研究対象地域として,多くの方が訪れ,多数の研究成果が国内外で公表されています。このような背景の下,コロナ社から,『千葉県 地学のガイド』(1974),『続千葉県 地学のガイド』(1982),『新・千葉県 地学のガイド』(1993)の3冊のガイドブックが発刊され,巡検や研究,ならびに小・中学校や高等学校での地学教育などに活用されてきました。一方,過去30年間で地質学や地球科学が大きく進歩し,地層や岩石の成因に関する理解や研究方法などに著しい進展が認められます。このような状況から,既刊の3冊の基本的精神を受け継ぎながら,新たなガイドブックの発刊が,コロナ社で計画されました。
本書は,五つの章で構成されています。第1章「房総半島の成り立ち」では,房総半島の地層や岩石ならびに地形の概要とプレート運動との関係,第2章「地層と岩石の観察方法」では,地層,岩石,化石の基本的な研究方法,第3章「地層と岩石のフィールドワーク」では,地層や岩石の野外観察地点と各地点でのおもな観察事項の具体的な解説,第4章「房総半島の資源」では,千葉県が誇る資源の概要,第5章「身近な自然の猛威」では,私達に身近な自然災害の特徴とその保全対策などが,それぞれまとめられています。このように本書は,地層や岩石の野外観察とこれに関連した地質学や地球科学の基礎事項が学べる構成となっています。
本書は,既刊の3冊と同様に,児童・生徒を含めたさまざまな世代や職業の方々はもとより,大学生,大学院生,研究者,技術者の方々に,房総半島の地層や岩石の野外観察をとおして,大地の成り立ちや地球環境史を理解していただくためのフィールドガイドとして作成されました。また,本書は地質学や地球科学の入門書として活用いただくことも可能と考えられます。最後になりますが,コロナ社の方々には,本書の企画段階から出版に至るまで,大変なご尽力とご協力をいただきましたことを,つけ加えさせていただきたいと思います。
読者の皆さん,本書を片手に房総半島の地層や岩石の魅力を満喫してください!
2025年10月
編著者 伊藤 慎
本書を読むにあたって
1.房総半島の成り立ち
1.1 プレート境界と地震活動
1 3枚のプレートが重なる房総半島
2 最近の地震活動
3 過去のおもな地震活動
1.2 古い時代の地層と岩石
1 アジア大陸のへりの時代-付加体の形成
2 日本海の拡大と四国海盆の拡大
3 銚子地域の地層・岩石の形成-ジュラ紀の付加体
4 銚子の白亜紀層
5 白亜紀-古第三紀の付加体
6 房総半島南部の嶺岡帯
7 保田層群
1.3 新しい時代の地層と岩石
1 地質構造の特徴
2 地層や岩石の特徴
3 地層の形成と氷河性海水準変動
1.4 地形の成立
1 下総台地
2 上総丘陵
3 安房丘陵(嶺岡山地を含む)
4 河成段丘・海成段丘および沖積低地
1.5 地下の地質構造
1 測線の設定と位置
2 A-I測線周辺の地表地質
3 反射断面の解釈
4 反射断面の成果と地下の地質構造
1.6 台地と低地の地下地質
1 ボーリング調査
2 低地と台地を構成する地層
3 低地の沖積層
4 台地の下総層群
5 下総層群木下層の谷埋め堆積物
2.地層と岩石の観察方法
2.1 堆積構造と堆積相の観察
1 粒子の移動
2 ベッドフォーム
3 堆積構造
4 堆積相と堆積相解析
5 ワルターの法則
2.2 岩石と鉱物の観察
1 おもな鉱物の種類
2 おもな岩石の種類
3 野外観察
4 偏光顕微鏡による観察
5 電子顕微鏡による観察
2.3 断層と褶曲の観察
1 断層の形成
2 断層露頭の観察
3 断層地形の観察
4 褶曲の形成
5 褶曲露頭の観察
6 褶曲した地層の地表分布の観察
2.4 テフラの観察
1 広域テフラとその意義
2 テフラの記載と対比
3 日本列島の鮮新世-更新世広域テフラ
4 房総半島のテフラ
2.5 微化石の観察
1 微化石の種類
2 微化石の分析
3 微化石の分析からわかること
2.6 貝化石の観察
1 貝化石の産状
2 暖流系種と寒流系種
3 貝類群集と生息環境
4 貝殻に残された痕跡
2.7 無脊椎動物化石の観察
1 刺胞動物門花虫綱イシサンゴ目
2 コケムシ動物門
3 腕足動物門
4 節足動物門甲殻亜門軟甲綱十脚目
5 棘皮動物門ウニ類
2.8 脊椎動物化石の観察
1 骨格や歯について
2 房総半島の脊椎動物化石産地層準
3 板鰓類化石
4 哺乳類化石
5 最後に
2.9 生痕化石の観察
1 生痕化石の識別
2 生痕化石の分類と基準
3 切り合い関係
4 充填物
3.地層と岩石のフィールドワーク
3章の見学地点の参照方法
3.1 銚子地域
A 愛宕山(A1-A2)
B 千騎ヶ岩
C 犬岩
D 黒生
E 海鹿島
F 君ヶ浜
G 犬吠埼
H 酉明浦
I 長崎鼻(I1-I3)
J 宝満
K 夫婦ヶ鼻
L 潮見町
M 名洗
N 屏風ヶ浦(N1-N5)
3.2 木下地域
A 木下万葉公園(A1-A2)
B 石材としての木下貝層(B1-B2)
3.3 君津-木更津-市原地域
A 君津市小糸大谷
B 木更津市真里谷周辺
C 市原市大蔵周辺
D 長柄町刑部
E 市原市瀬又
3.4 磯根崎-上総湊地域
A 磯根崎(A1-A3)-染川河口の右岸(A4)
B 新舞子海岸南端(B1)-上総湊海浜公園北端(B3)
3.5 久留里-養老川-平蔵川-笠森地域
A 川谷(A1-A5)
B 久留里大谷(B1-B2)
C 柿ノ木台(C1-C2)-飯給(C3-C4)-大戸(C5)
D 米原(D1)-平蔵(D2-D4)
E 坂本橋交差点の東
F 野見金山
G 笠森観音(G1-G2)
3.6 国本層と千葉セクション
1 国本層
2 千葉セクション
3 GSSPとテフラ鍵層
3.7 小糸川-小櫃川-養老川-太東地域
A 田倉
B 西日笠
C 二入
D 亀山湖
E 養老渓谷1(E1-E3)
F 養老渓谷2(F1-F3)
G 養老渓谷3(G1-G2)
H 紙敷川(H1-H3)
I いすみ文化とスポーツの森
J 太東港
3.8 太東-大原-御宿-勝浦地域
A 岬町和泉(夫婦岩から南の海岸)
B 大原町
C 三十根(C1)-釣師海岸(C2)
D 田尻海岸
E 八幡岬(E1-E2)
F 石ヶ浦
G 矢の浦
H 部原
3.9 鵜原地域
A 鵜原理想郷(A1-A3)
B 勝浦海中公園(B1-B2)
C 吉尾港(C1-C3)
D ボラの鼻-黒ヶ鼻(D1-D2)
E 砂子ノ浦観音
F 尾名浦
3.10 萩生・竹岡-湊川-養老川地域の黒滝層
A 萩生-竹岡(A1-A5)
B 志駒川(B1-B2)
C 高溝(C1-C2)
D 養老川(D1-D3)
3.11 三島湖-豊英湖-三石山地域
A 三島湖(A1-A3)
B 豊英湖(B1-B4)
C 三石山(C1-C4)
3.12 鋸山周辺と志駒川地域
A 不動岩周辺(A1-A6)
B 明鐘岬周辺(B1-B3)
C 潮吹き隧道出入り口
D 元名
E 鋸山登山自動車道
F 志駒川流域
3.13 鴨川-嶺岡山地-保田・勝山地域
A 太海-鴨川漁港(A1-A3)
B 嶺岡中央林道(B1-B5)
C 大山千枚田(棚田)
D 平久里地域(D1-D2)
E 保田・勝山地域(E1-E2)
3.14 江見海岸周辺地域
A 江見青木-江見吉浦
B 江見漁港
C 江見内遠野-洲貝川河口
3.15 南房総の海成段丘
1 歴史上の地震による海成段丘
2 房総半島南部の沼面群
3 保田低地・岩井低地の海成段丘
4 更新世の海成段丘
3.16 沼サンゴ層
A 館山市西郷
B 館山市沼(B1)-香(B2)-塩見(B3)
3.17 見物-沖ノ島-大房岬-那古-正木地域
A 見物(A1)-波左間(A3)
B 沖ノ島
C 大房岬(C1-C2)-大福寺(崖観音)(C3)
D 那古(D1-D2)-小原(D3)-正木(D4)
3.18 西川名-布良-白浜-白間津-千倉地域
A 西川名(A1)-伊戸(A2)
B 布良(B1)-滝口(B4)
C 野島崎(C1-C3)
D 磯笛公園
E たたみ島(E1-E3)
F 白間津(F1-F3)
G 大川
H 川口
I 平舘
J 安房グリーンライン白浜トンネル北側出入口
3.19 白浜層と白間津層の生痕化石
A 白間津海岸
B 塩浦海岸
3.20 千葉市幕張-稲毛付近の昔の海岸線
A 幕張公園-幕張4丁目交差点(A1-A2)
B 稲毛公園(B1-B3)
C 稲毛陸橋付近
3.21 海岸で打ち上がる化石
A 幕張海岸
B 上総湊-新舞子海岸-磯根崎
4.房総半島の資源
4.1 水溶性天然ガスとヨウ素
1 南関東ガス田
2 水溶性天然ガス田とヨウ素鉱床の発達
3 天然ガスとヨウ素の生産
4 房総半島の天然ガスとヨウ素の利活用
4.2 地下水
1 台地-低地系の地下水
2 丘陵地の地下水
3 沖積低地(平野)の地下水
4 温泉と天然ガスかん水
5 地下水の流れを推定するヒント
4.3 山砂利
1 山砂利とは
2 山砂利の歴史
3 生産工程
4 千葉県の山砂利の使用実績例
5 砂利採取量
5.身近な自然の猛威
5.1 津波堆積物
1 2011年東北地方太平洋沖地震による津波堆積物
2 古津波堆積物
5.2 液状化
1 液状化のしくみと発生の条件
2 液状化による被害
5.3 地すべり
1 嶺岡山地の地すべりと発生場の地形地質
2 反復性のある高田地区の地すべり
3 房総半島の地すべり地形の分布と動きのタイプ
5.4 海岸侵食
1 九十九里浜の成り立ち
2 九十九里浜の現状
付図
索引
読者モニターレビュー【 奈佐原 顕郎 様 筑波大学(業界・専門分野:農学・環境科学)】
チーバくんの首から下(+後頭部)のユニークな地質物語を圧倒的な質と量で語る熱い本である。「千葉の地質ファンよ, ここまで登ってくるがよい」と執筆陣が不敵に微笑む様子が浮かぶ。本書と折り畳み自転車を持って内房線・外房線・久留里線で出かけたい衝動に駆られる。個人的に惹かれたのは大山千枚田が(おそらく)蛇紋岩由来の地すべりであり, それは三浦半島から丹沢, 静岡まで伸びるCIMSBというカッコいい名前の地質帯の一部だと知ったことである。茨城在住の私はこんな素晴らしい本に恵まれた千葉が羨ましくて仕方ない。次はぜひ茨城もお願いします。
amazonレビュー

-
掲載日:2025/12/15

-
掲載日:2025/12/09
房総半島地質巡りへのいざない,新たな出会いの予感!!
ますます千葉県に親しみが湧く書籍登場!
★内容紹介動画公開中★