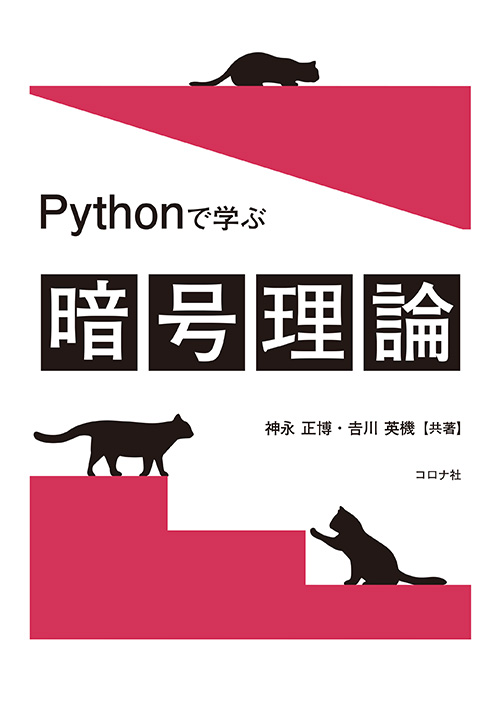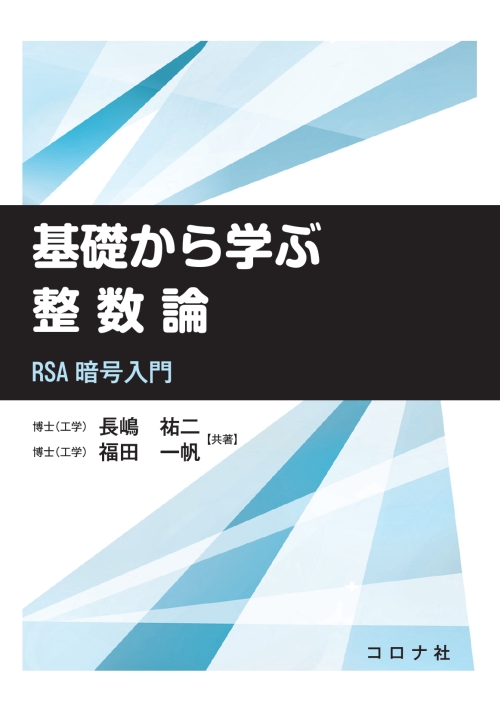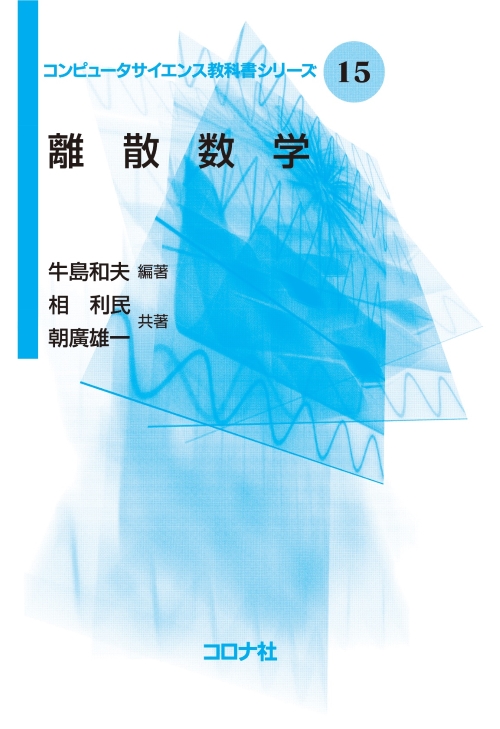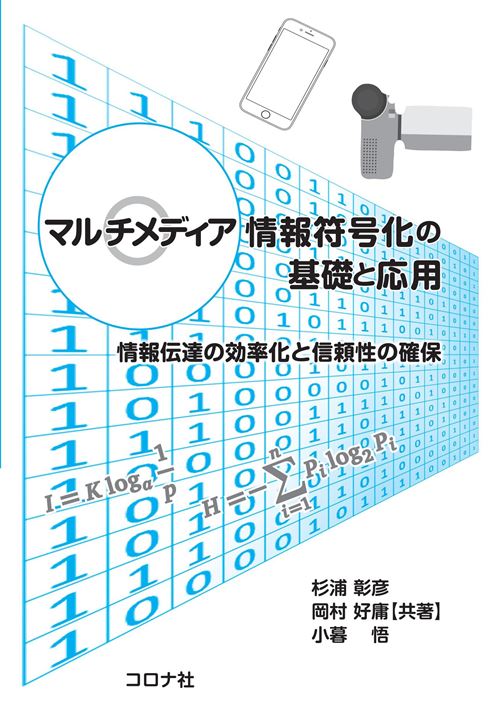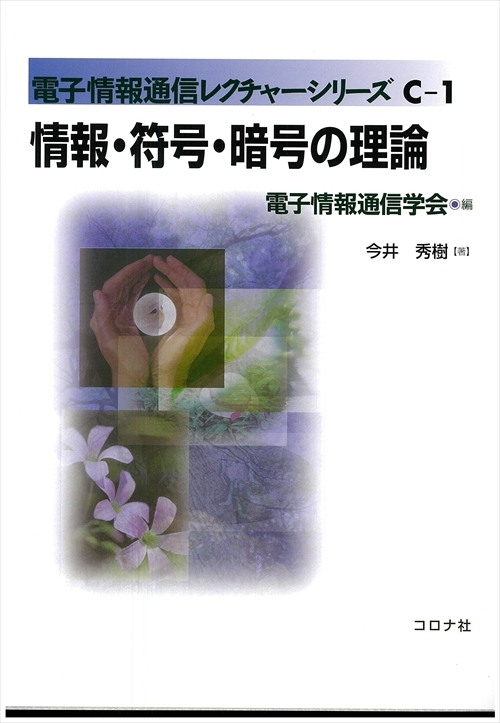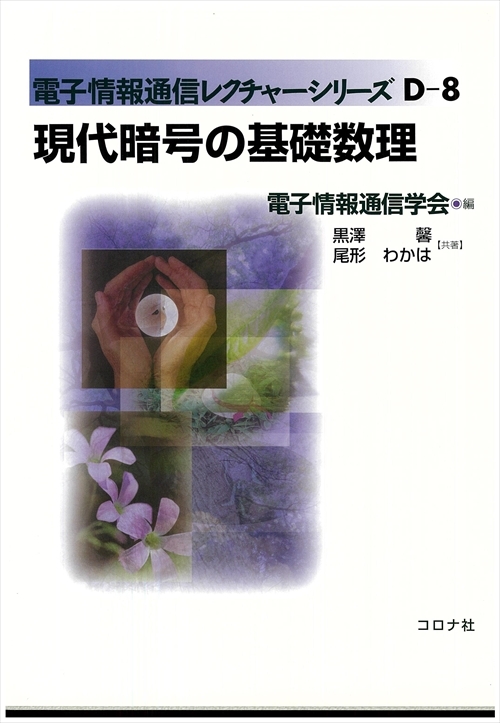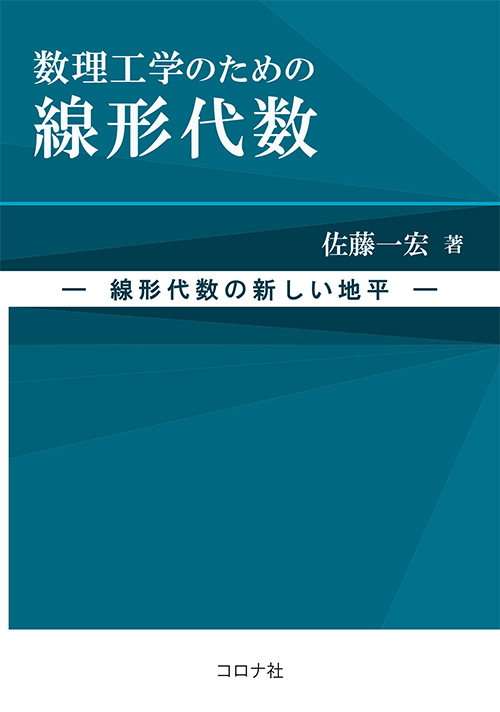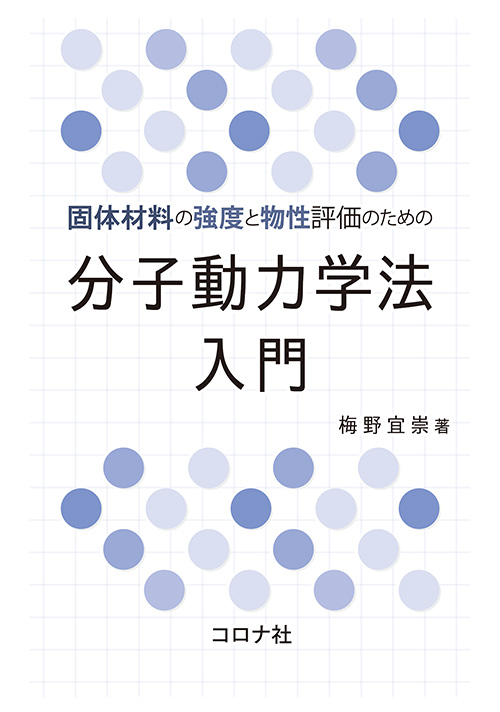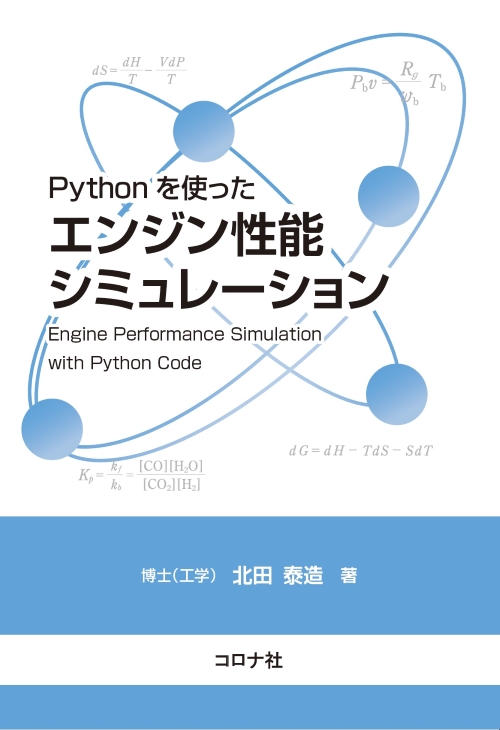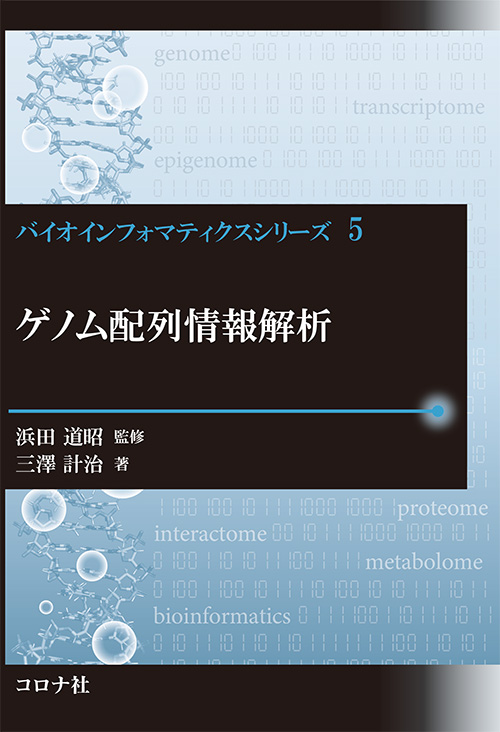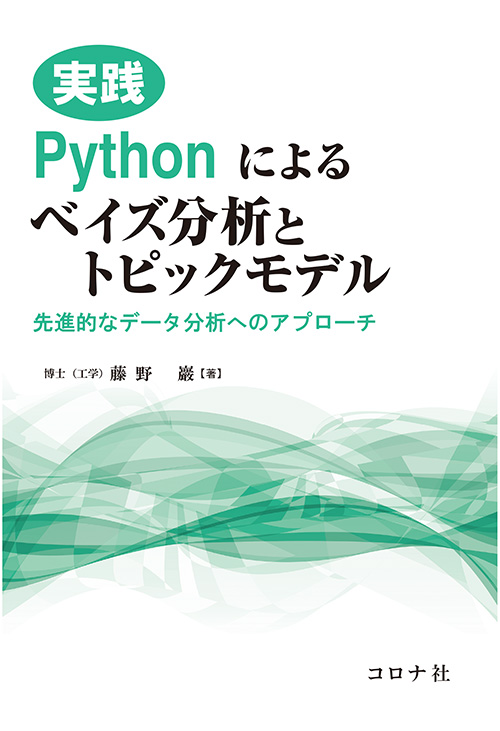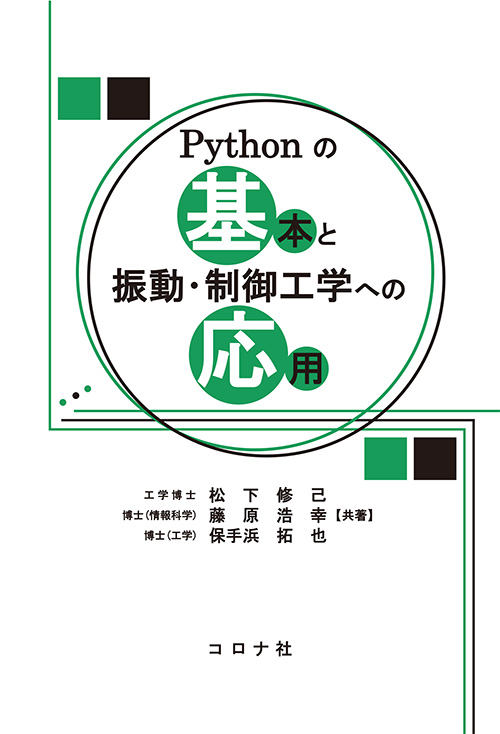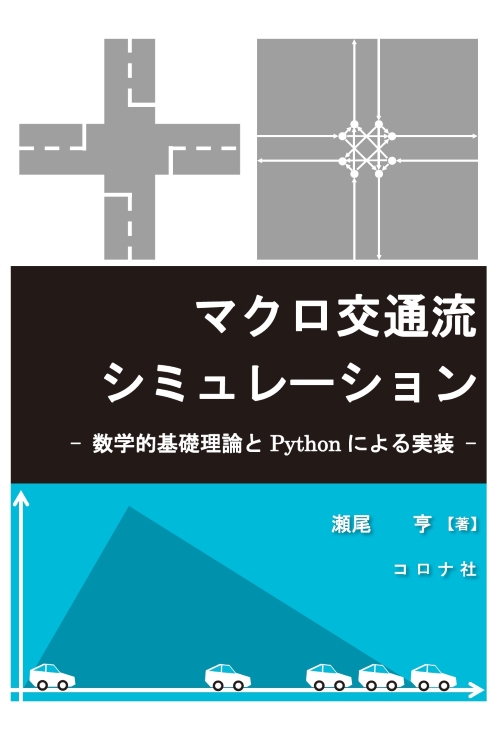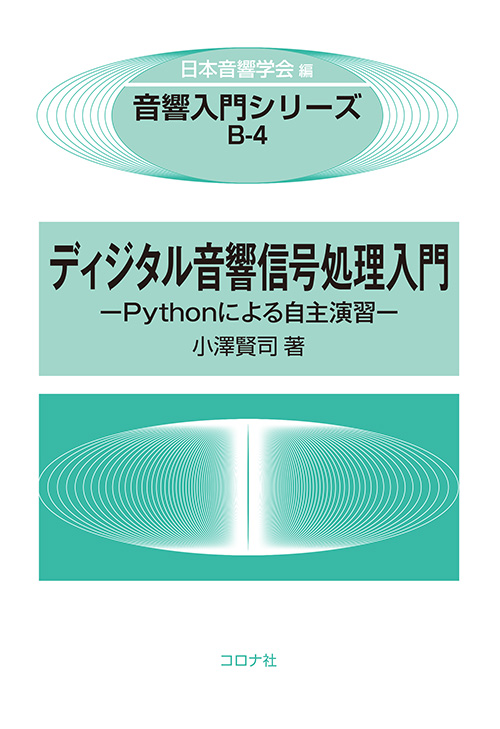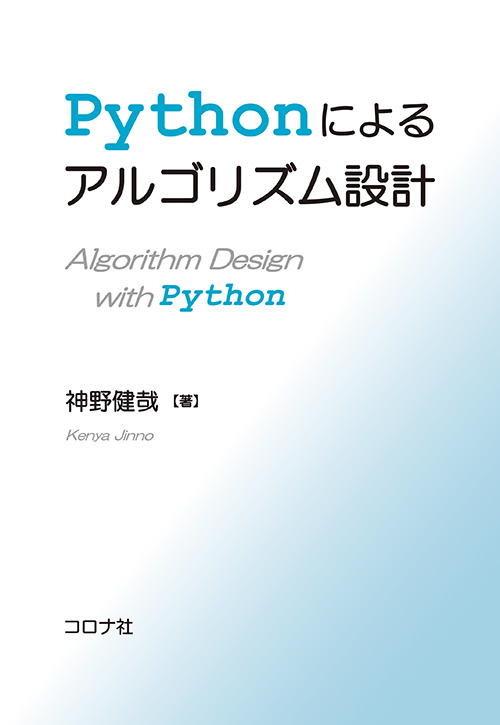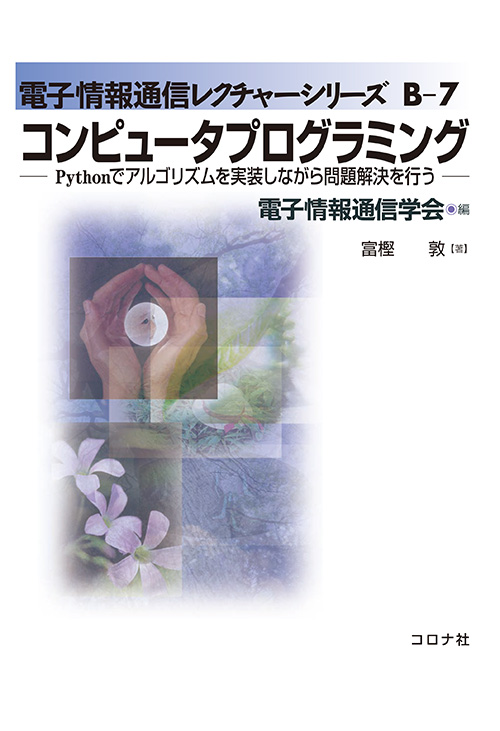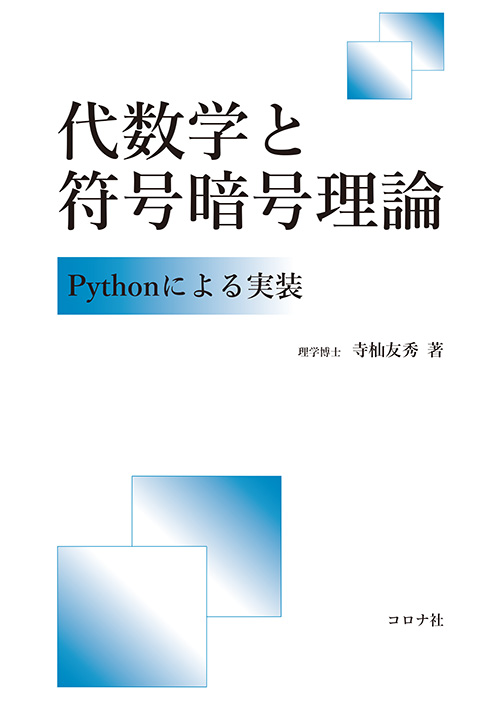
代数学と符号暗号理論 - Pythonによる実装 -
符号・暗号理論の基礎となる初等整数論から始め,Pythonによる演習を入れた。
- 発行年月日
- 2025/10/31
- 判型
- A5
- ページ数
- 202ページ
- ISBN
- 978-4-339-06135-2
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 広告掲載情報
【書籍の紹介】
代数学を学んだことがない読者の方々にも符号理論,暗号理論の根本原理を理解していただけるよう丁寧に,かつ議論が明解になるように心がけて執筆しました。また,変数の扱いが容易であり,扱える整数の大きさにほとんど制限がないPythonによる演習を入れることで,紹介した理論が応用に耐えうるものかどうかを実感していただけるようにしています。
1章「初等整数論」ではその後の2章「暗号理論」,3章「符号理論」で共通に使われる代数的な道具を準備します。環論においてはイデアルを用いた統一的扱いが標準的ですが,後で使う場面を考えて,ユークリッドアルゴリズムおよびそれを拡張した拡張ユークリッドアルゴリズムを議論の中心として説明しました。また符号理論においては素体上の多項式の扱い(例えば割り算アルゴリズムなど)が中心部分を占めているので,これについては詳しく説明しました。
2章で扱う「暗号理論」は伝えたい人にのみ理解でき、第三者にはわからないような形で情報を送るために考えられた理論です。古くは戦争において敵に知られないように作戦をつたえる目的で用いられました。現在ではクレジットカードの番号や、パスワードを送るときに使われています。暗号を解読する理論も研究され、さまざまな種類の暗号があります。
3章に出てくる「符号理論」はあまりおなじみではない方もいらっしゃるかもしれません。復元に使うための情報を送る情報に追加して、送信の途中で情報に傷がついても復元できるようにする理論です。身近な例としては、QRコードにつかわれています。実際にQRコードの一部に小さいロコなどを埋め込んで、その部分を見えなくしても正常に読み込めるものを見かけた人がいるかもしれません。
最後にPythonのプログラミングの基礎と本文中に書ききれなかった定理の証明などを追記しました。
【著者からのメッセージ】
本書は抽象的な定義から始まる代数学の教科書とは異なり、代数学を学んでいない理工学部学生にとってもなじみの深い具体的なものから始まります。よく使われているPythonでプログラミングをしながら読み進めれば理解が深まることと思います。
本書は筆者が法政大学理工学部で代数学を学んだことのない学生を対象とした講義録とゼミで用いた資料が基になっている。本書は代数に関する知識を仮定せず,一般教養の微積分と線型代数の初歩の基礎的知識は仮定するが,線型代数で用いられる言葉は復習の意味も込めて最初から説明した。しかし線型代数に関するいくつかの主要な定理には証明は付けずに説明したので,なぜそのような定理が成り立つかについては,適宜教科書を参照して復習をすることをおすすめする。執筆にあたっては,できるだけ丁寧に,かつ議論が明解になるように心がけた。場合によっては厳密な証明が理解の妨げになることも考慮し,厳密性を省いたところもある。
暗号理論,符号理論は現在も進化をとげており,実際に使用される場面では本書に書かれているものにさらに工夫を加えているものが多いが,根本原理は本書で理解できるものと思っている。
また,ある程度の大きな数を扱わないと,紹介した理論が応用に耐えうるものかどうかを実感しにくい場面も多々あるので,PC上で実際に動くPythonによる演習を入れることとした。Pythonを使う利点としては,変数の扱いが容易である(あいまいな記述も許す)こと,扱える整数の大きさにほとんど制限がないことが挙げられる。これらの点がプログラミング初心者にとってはとっつきやすいだろう。Pythonはいったん機械語に翻訳されてから実行されるので,実行速度は高速である。逆に実際に自分でプログラムを書く立場で考えると,思わぬミスを発見し,修正するのに苦心するところが同時に欠点でもある。またオブジェクト指向型プログラムの書き方をすることも可能であり,いくつかの理論を組み合わせて全体を構成する本書の進め方と合致している面も見逃せないところである。なお,本書で紹介したプログラムはコロナ社の本書書籍詳細ページ(https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339061352/)にて公開している。
本書について,実際に使用して使いにくい点,未熟な点などをご指摘下さった松本圭司氏には,この場をもって感謝の意を述べさせていただきたい。
本書は大きく分けて代数的な準備の部分の「1章初等整数論」とその後に続く「2章暗号理論」と「3章符号理論」である。「初等整数論」ではその後の「暗号理論」,「符号理論」で共通に使われる代数的な道具を準備する。環論においてはイデアルを用いた統一的扱いが標準的であるが,後で使う場面を考えて,ユークリッドアルゴリズムおよびそれを拡張した拡張ユークリッドアルゴリズムを議論の中心として説明した。また符号理論においては素体上の多項式の扱い(例えば割り算アルゴリズムなど)が中心部分を占めているので,これについては詳しく説明した。
2025年8月
寺杣友秀
1.初等整数論
1.1 約数,倍数とユークリッドアルゴリズム
1.1.1 約数,倍数,素数
1.1.2 最大公約数,最小公倍数,素因数分解
1.1.3 整数とユークリッドアルゴリズム
1.1.4 拡張ユークリッドアルゴリズム
1.1.5 演習:拡張ユークリッドアルゴリズム
1.2 剰余系
1.2.1 剰余類の定義
1.2.2 剰余類の計算
1.2.3 中国の補題
1.2.4 105減算
1.3 素体とフェルマーの定理
1.3.1 素体における逆元の計算
1.3.2 演習:素体における逆数
1.3.3 素数に関するフェルマーの定理
1.3.4 素数の積に関するフェルマーの定理
1.4 フェルマーの判定法と素数定理
1.4.1 素数の密度
1.4.2 Nまでの数で最初のk個の素数で割り切れない確率
1.4.3 素数判定
1.4.4 剰余類の高速べき計算
1.4.5 演習:高速べき計算と素数判定
1.5 素体上の多項式
1.5.1 体上の多項式
1.5.2 体上の多項式の割り算アルゴリズム
1.5.3 演習:素体上の多項式
1.5.4 演習:多項式と代入
1.5.5 体と多項式での約数,倍数
1.5.6 多項式のユークリッドアルゴリズム
1.5.7 演習:多項式のユークリッドアルゴリズム
1.5.8 多項式における合同類別
1.6 既約多項式とガロア体
1.6.1 既約多項式と素因子分解の存在
1.6.2 ガロア体
1.6.3 演習:ガロア体
1.6.4 最小多項式
1.6.5 原始根の存在定理
1.6.6 ガロア体のフロベニウス写像
1.6.7 演習:ガロア体を係数とする多項式
2.暗号理論
2.1 暗号理論の概要
2.1.1 暗号化と復号
2.1.2 公開鍵暗号
2.1.3 鍵共有と鍵の配送問題
2.2 RSA 暗号
2.2.1 フェルマーの定理とRSA暗号
2.2.2 現在のRSAの問題と世界記録
2.2.3 演習:RSA暗号,鍵の生成と復号
2.3 ディフィー・ヘルマン鍵共有
2.3.1 離散対数問題
2.3.2 ディフィー・ヘルマン鍵共有のプロトコル
2.3.3 エルガマル暗号
2.3.4 演習:ディフィー・ヘルマン鍵共有とエルガマル暗号
2.4 楕円曲線
2.4.1 楕円曲線の定義
2.4.2 座標を使った楕円曲線の和の計算
2.4.3 素体上の楕円曲線の和の例
2.4.4 演習:有限体上の楕円曲線
2.4.5 楕円曲線上の点の自然数倍の高速計算
2.4.6 演習:楕円曲線の点の高速倍数計算
2.5 楕円曲線暗号
2.5.1 楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有
2.5.2 楕円曲線エルガマル暗号
2.5.3 一般の整数から楕円曲線の点を作る
2.5.4 演習:楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有
2.6 電子署名
2.6.1 電子署名に必要な要件
2.6.2 電子署名の概要
2.6.3 電子署名の準備(ハッシュ)
2.6.4 電子署名の実際
2.6.5 RSA暗号による実装
3.符号理論
3.1 体とベクトル空間
3.1.1 行列の計算
3.1.2 抽象ベクトル空間
3.1.3 部分ベクトル空間と次元
3.2 ベクトル空間と線型写像
3.2.1 線型写像と行列
3.2.2 同型と基底,像と核
3.2.3 行列式
3.2.4 行列式と逆行列,基底
3.3 誤り訂正符号
3.3.1 ブロック符号
3.3.2 ハミング距離
3.3.3 誤り訂正の原理
3.3.4 線型符号と最小ハミング長さ
3.3.5 シングルトン限界
3.3.6 生成行列と組織的符号化
3.3.7 (7,4,3)ハミング符号と誤り訂正
3.3.8 誤り検出とシンドローム行列
3.4 リード・ソロモン符号
3.4.1 符号多項式とリード・ソロモン符号
3.4.2 リード・ソロモン符号の例
3.4.3 リード・ソロモン符号の最小ハミング長さ
3.4.4 リード・ソロモン符号の組織的符号化
3.4.5 演習:リード・ソロモン符号の組織的符号化
3.4.6 (参考)点評価型のリード・ソロモン符号
3.5 リード・ソロモン符号の誤り訂正
3.5.1 シンドローム多項式
3.5.2 変形拡張ユークリッドアルゴリズムと誤り位置多項式
3.5.3 誤り多項式の計算
3.5.4 演習:リード・ソロモン符号の誤り訂正
3.6 巡回符号,BCH符号
3.6.1 巡回符号
3.6.2 BCH符号
3.7 BCH符号の誤り訂正アルゴリズム
3.7.1 シンドローム多項式
3.7.2 誤り位置多項式,誤り多項式の計算
付録A:Pythonによるプログラミング
A.1 Pythonの基本的な使い方
A.1.1 プログラムを始める前の一般的な常識
A.1.2 Spyderのインストール
A.1.3 プログラム環境
A.1.4 言語Pythonについての一般的注意
A.1.5 デバッグについて
A.2 Pythonの文法の基本
A.2.1 変数,リスト,条件分岐
A.2.2 リストの使い方
A.2.3 整数の割り算
A.2.4 インデントと条件分岐if文,else文,elif文
A.2.5 ループを制御するfor文,while文,break文
A.3 関数,クラス,インポート
A.3.1 関数
A.3.2 クラス
A.3.3 演算子オーバロード
A.3.4 データのファイルへの保存
付録B:群論と原始根
B.1 群と巡回群
B.1.1 群の定義
B.1.2 元の位数,同型と巡回群
B.1.3 原始根の存在
B.2 原始根の存在定理
付録C:楕円曲線の和についての結合法則
C.1 射影幾何学と同次多項式のアファイン化
C.2 射影幾何における楕円曲線
C.3 射影幾何における楕円曲線の和
C.4 結合法則について
例題解答
索引
読者モニターレビュー【 にせシャム猫ミミ 様 (業界・専門分野:教育業界)】
本書『代数学と符号暗号理論』は工学的な観点による類書も多い中で,代数幾何学を専門とし,日本数学会理事長も務めた純粋数学者による著作という点で非常に興味をそそられた.暗号理論・符号理論という情報科学の実践的内容について,過度に抽象的になることなく,数学が持つ洗練された記述力によってその本質を簡潔に表現することに成功している稀有な一冊である.
本書は,1. 初等整数論,2. 暗号理論,3. 符号理論の3つの章から構成されている.1冊の中で必要な予備知識を含め,暗号理論と符号理論の双方を同時に学べるという点でも大変魅力的である.
第1章「初等整数論」では,ユークリッドの互除法や剰余系,素体,フェルマーの小定理といった基礎事項が,後の章との関連を意識しつつ,厳密でありながらも平易に解説されている.特に,符号理論への応用を見据えて,素数や有限体(ガロア体),それらを係数とする多項式の性質,剰余演算などについても丁寧に扱われている.また,RSA暗号で実際に利用される形式である「素数の積に関するフェルマーの定理」についてもきちんと証明が示されている点や,高速べき計算といった計算上の工夫にも触れられている点も,初学者にとってありがたい配慮である.
続く第2章「暗号理論」では,RSA暗号やディフィー・ヘルマン鍵共有,さらには楕円曲線暗号まで,現代の暗号技術の基本を一望することができる.内容は,重厚で網羅的な理論展開というよりも,基本事項が簡潔に記述されている構成となっているため非常に読みやすい.また,Pythonコードを通して実際に暗号処理を試せるよう工夫されており,理論を実際に「動かしながら」理解を深めることが可能となっている.
第3章「符号理論」では,誤り訂正符号やリード・ソロモン符号など,情報伝達を支える数理構造が取り上げられる.ベクトル空間や線形写像の基本から始まり,巡回符号やBCH符号のアルゴリズムに至るまでが,代数学的枠組みのもとで体系的に記述されており,有限体という純粋に数学的な対象が現実世界へ応用されている様子を垣間見ることができる.
私個人は数学寄りの背景を持つため,本書のこうした記述に親近感を覚える一方,このような抽象性を含む記述は読者によって評価が分かれる部分かもしれない.しかしながら,抽象的な数学が現実の通信技術にどのように生きているのかを知るうえで,明瞭な記述と併せて例題(解答が巻末に付属している)やPythonコードを通じて「手を動かして」学べる設計になっている本書は格好の入門書であり,ぜひ多くの方に手に取ってほしいと思う.
読者モニターレビュー【 pppp4869 様 (業界・専門分野:セキュリティ研究)】
本書は、初等整数論の基礎から出発し、暗号理論や符号理論へと自然に橋渡しして解説しています。
理論の紹介にとどまらず、Pythonを用いた実装で確かめられる点も大きな特徴です。対象は「代数学を学んだことのない学生」と明示されており、用語の定義や背景が一つひとつ丁寧に説明されています。
読み進めるうちに、私自身、暗号理論の学習で多用していた初等整数論の用語を十分に理解していなかったことを痛感しました。また、Pythonのコードを通じて、学んだ理論や数式をどのようにプログラムへ落とし込むかを具体的に理解できます。
掲載コードにはコメントがない箇所もありますが、行ごとに追いながら数式と照らし合わせ、自分でコメントを付けることで理解をさらに深められるでしょう。
総じて、本書は暗号理論や符号理論に挑戦したい学生はもちろん、基礎となる初等整数論でつまずいた学習者にも自信をもって薦められる一冊です。
読者モニターレビュー【 Manny-Lab 様 (業界・専門分野:機械学習や深層学習を用 いた統計モデリング)】
評者の、本書籍の読後の第一印象は「こう来たか!!」という驚きで、いっぱいでした。
本書の特徴は、まず何においても「数学者が、数学的にしっかりと暗号理論・符号理論を解説した」ことにあります。他の多くの類書では、、情報系の著者が”読者の分かりやすさ”を優先し、実例優先で記述する場合が多いと感じています。その中にあって、本書は、数学者によるしっかりとした記述で、評者としては非常に安心して取り組めました。
記載内容は、少々抽象的な数学的概念を過度に採用しなかったことで、非常にイメージがしやすい内容になっていました。その一方で、少々残念なのは、Pythonコードが、コード掲載に留まった印象を受けたことです。Pythonのコードを、スクラッチで作成し、過度に他のライブラリを使用していない点は、非常に参考になります。
しかしながら、もう少しコード内でのコメントや解説の記載など、一般的なプログラミング系書籍のレベルの記載は欲しいと思いました。もし読者がプログラミングに興味があれば、他のライブラリ(galois, bchlib, reedsolo など)との比較などをすると理解が深まると思います。
本書の内容は、数学などの理論的側面に興味が強い読者には、非常に参考になる書籍と言うことができる、おすすめの書籍です。
読者モニターレビュー【 N/M 様 (業界・専門分野:総合情報学[情報科学])】
本書は,符号理論や暗号理論,そしてこれらを学ぶ上で必要となる基礎的な代数学についての記述がなされている.
本書の大きな特徴としては,代数学,符号理論,暗号理論の各種アルゴリズムを,実際にプログラムとして動作させることのできるPythonでの記述がなされている点である.
私自身,学生時代に情報理論を学んだ際,符号理論の一部として,誤り検出・訂正符号の線形符号や巡回符号について学んだ.その際に,線形符号には他にも,CDやDVDに使われているリード・ソロモン符号,BCH符号も挙げられていたこともあり,本書を大変興味深く拝読させていただいた(これが今回のモニタに応募させていただいた一番の動機でもある).
私自身の理解力不足もあり,数式が意味する所の深い理解はできていないように個人的には痛感したが,少なくとも学生時代に,とある講義で言及された「暗号理論には(難解な)数学が多用されている」という意味合いが本書を通じて感じ取ることができた.
最後に,本書で学んだことが確認できるような演習問題が,もう少しあっても良かったのではないかと個人的には思った次第である.
読者モニターレビュー【 たか 様 (業界・専門分野:制御工学 産業応用 セキュリティ)】
本書は、暗号理論、符号理論、そしてそれらの基礎となる整数論から構成されている。「まえがき」にて、"代数学を学んだことのない学生を対象とした講義録とゼミで用いた資料が基になっている"とあるように、全体を通じて初学者に分かりやすく、お薦めしたい印象を受けた。
その理由として、例題や解説内にて数値例を用いて丁寧に説明が展開されている点とpythonでのサンプルコードが豊富な点が挙げられる。前者については、例えば暗号の章では、RSA暗号や楕円曲線暗号における復号演算のmod演算などにて省略されがちな途中式が丁寧に記述されている。後者についても、pythonでのサンプルコードが多数記載されていることから、実際に手を動かして学びたい人をはじめ、技術者や実験系の学生など各種演算を実装したい人の助けになると思われる。
暗号理論や符号理論は、近年重要視されており、機械学習や制御分野など幅広いジャンルと絡めた研究が盛んに行われている。これらの分野を初めて学ぶ学生から、産業応用へ向け学ぶ技術者まで、幅広い方へ一読頂きたい書籍である。
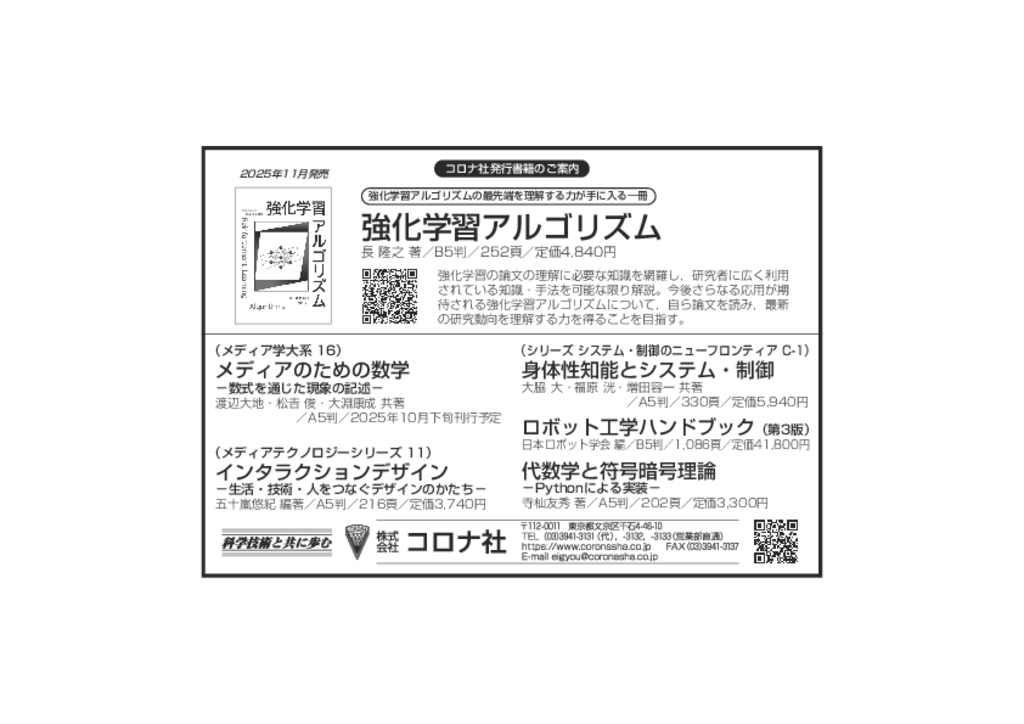
-
掲載日:2025/11/01
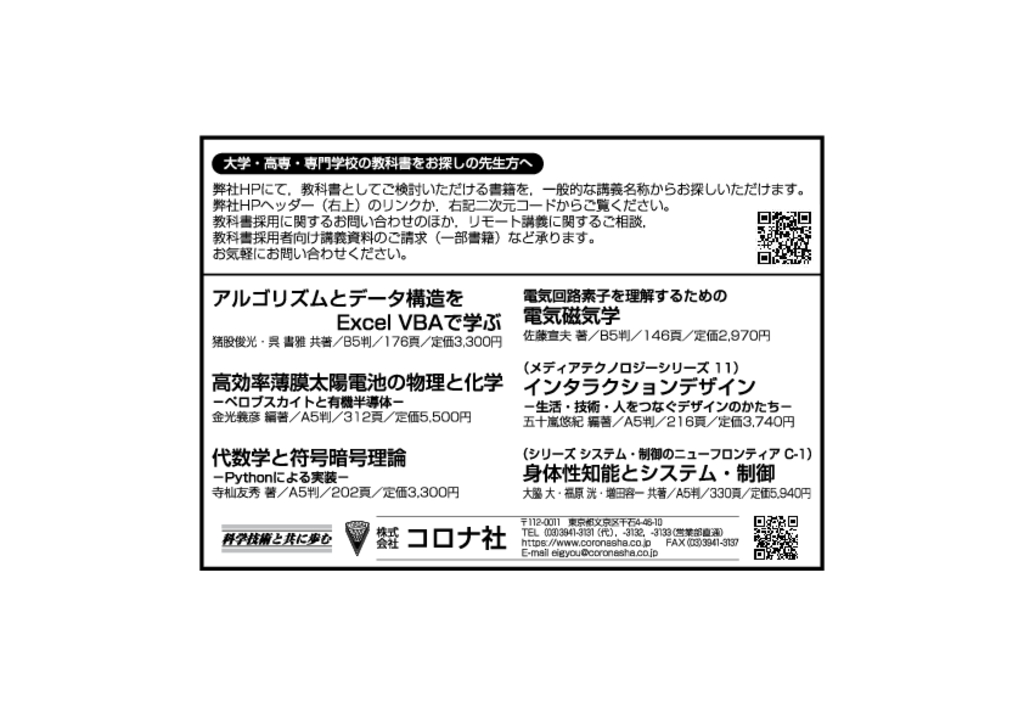
-
掲載日:2025/10/01
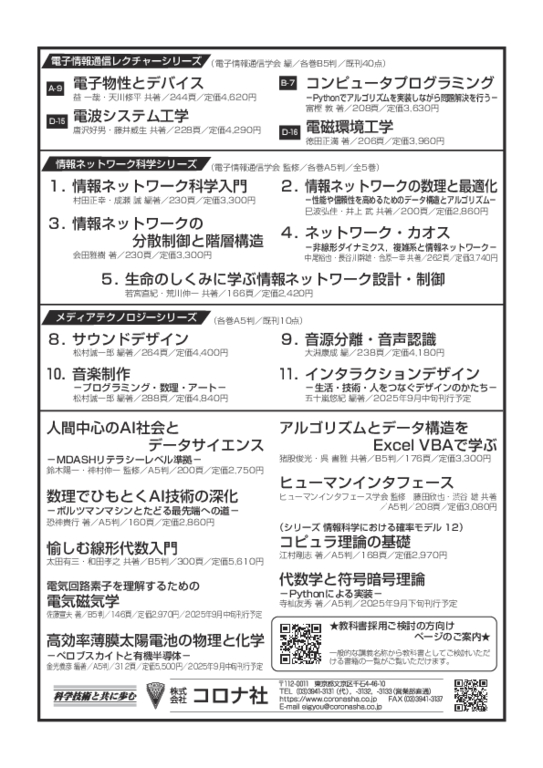
-
掲載日:2025/09/08
関連資料(一般)
- 書籍中のPythonプログラム