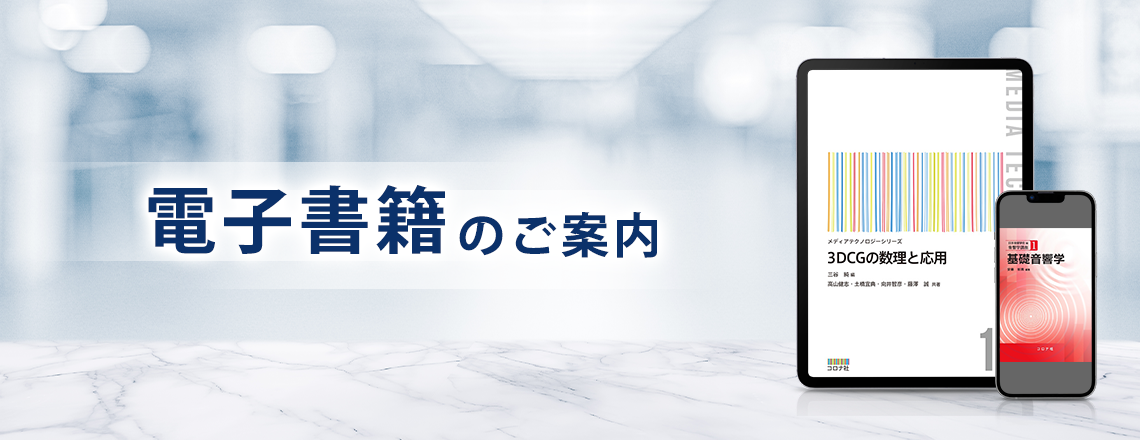12/23
電子書籍のご案内

数学
本書は,国家公務員採用一般職試験で出題された数学と物理の問題を解くことによって,工学分野の基礎力を身につけられる内容である。解答で用いる公式集をはじめ,解答は丁寧な数式展開とし,物理現象のイメージ図も示した。
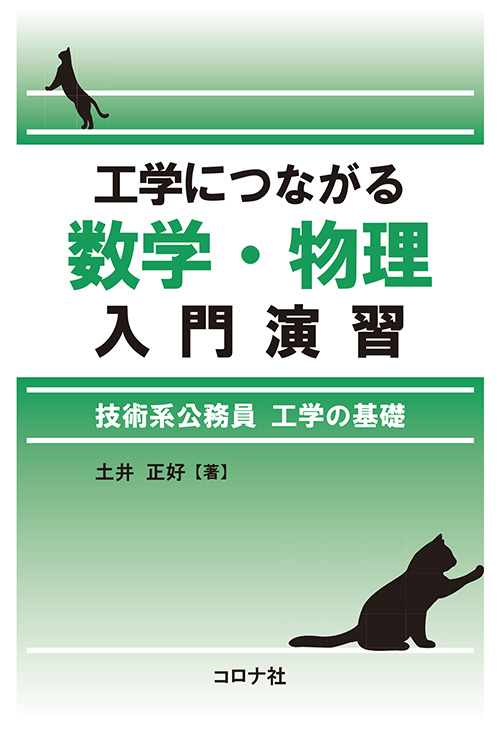
工学につながる数学・物理入門演習
詳細を見る
- 技術系公務員 工学の基礎 -入門レベルの理論経済学を学ぶ上で必要となる数学についてまとめた一冊。数学が苦手な読者でも中学で学んだ知識があれば理解できるように,高校数学から説明して偏微分まで扱う。理解を助けるための例や問題も多く掲載した。
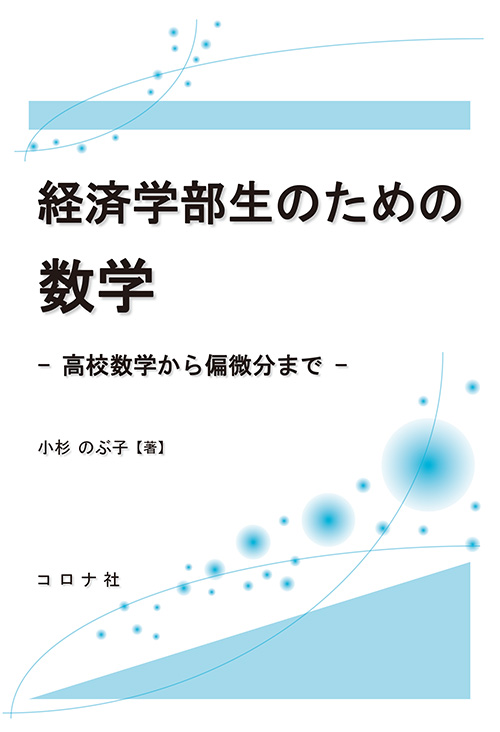
経済学部生のための数学
詳細を見る
- 高校数学から偏微分まで -ベクトル解析では,積分の仕方などを身につけることや,空間的な想像力を養う必要性も意識する必要がある。パズルを解くような感覚が味わえる問題や,現実世界で見られるような設定の問題を多数解くことでベクトル解析を身につける。
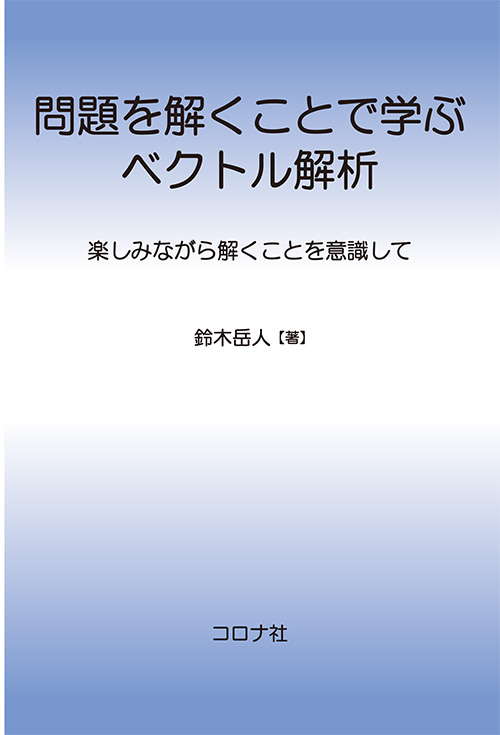
問題を解くことで学ぶベクトル解析
詳細を見る
- 楽しみながら解くことを意識して -得意だったはずの数学が大学で急にわからなくなった!? 命題の文法から,集合・写像に関する記号や語句,大学数学における関数の扱い方,さらに高校と大学の授業の違いまで,大学数学を理解するための「いろは」を詰め込んだ1冊。
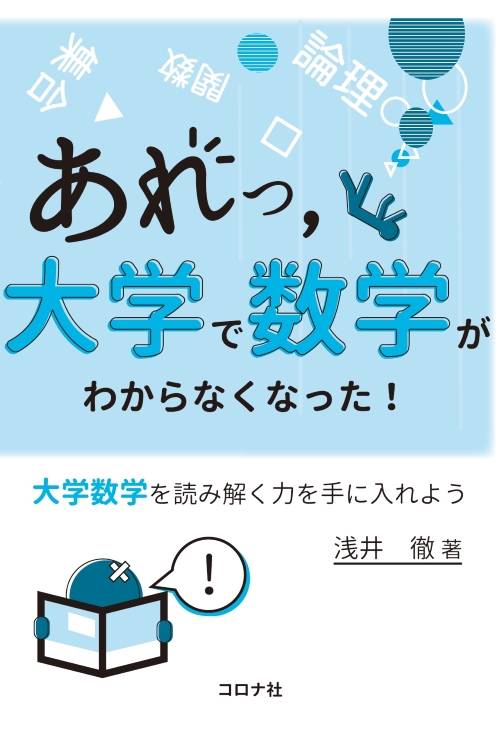
あれっ,大学で数学がわからなくなった!
詳細を見る
- 大学数学を読み解く力を手に入れよう -
理学
メディアコンテンツの制作に携わる人が,前提として身に付けておくべき物理学の基礎をまとめた。物理学の知識を用いて,現実を表面的に観察し,背景にある理論に従って物や人を動かすことで制作物のクオリティを上げることができる。
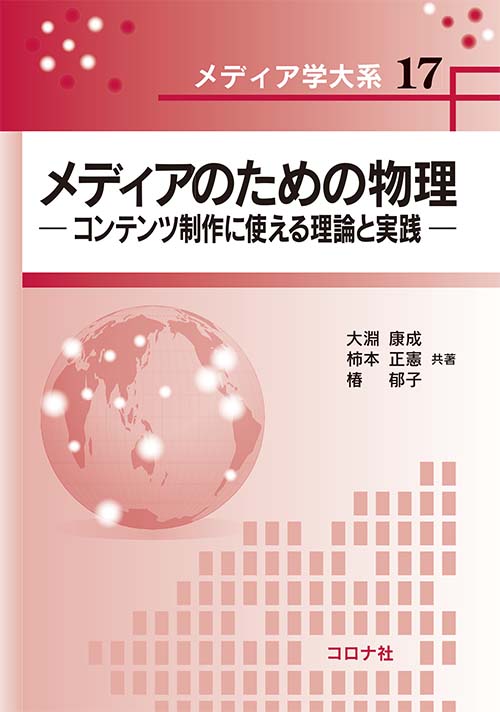
メディア学大系 17
詳細を見る
メディアのための物理
- コンテンツ制作に使える理論と実践 -本書は工学分野を俯瞰する立場で数学的内容を精査し,光学における数学や物理的意味と数学のもつ性質との橋渡しを行うことで,横断的理解を目指した書籍である。数学のレベルは,高校および大学の学部生程度を想定している。
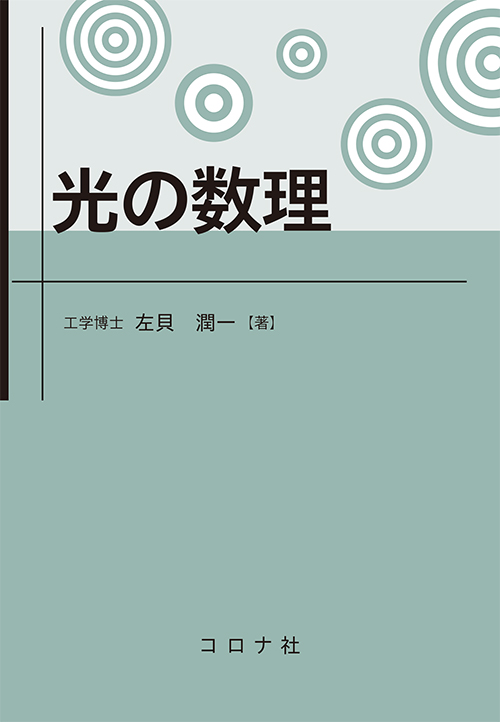
光の数理
詳細を見る本書は,空間データを分析する様々なソフトウェアに組み込まれているクリギングについて,読者が分析対象とする現象に応じた仮定や条件を自ら吟味,設定し,得られた結果の妥当性を判断できるように,その基礎から応用まで解説した。
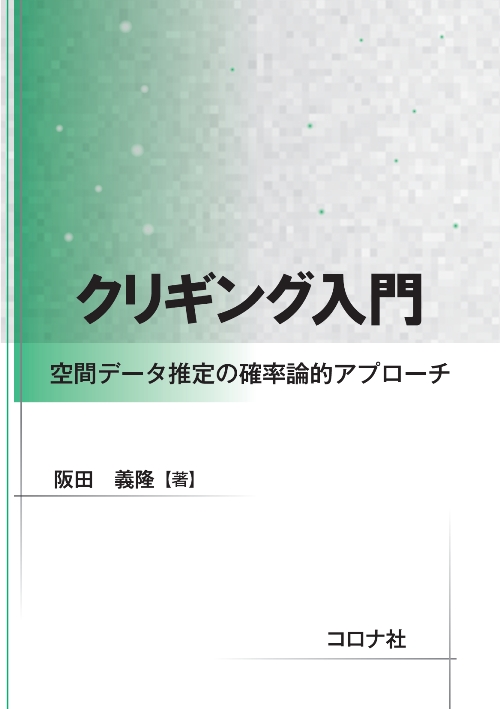
クリギング入門
詳細を見る
- 空間データ推定の確率論的アプローチ -物性研究に必要である良質な結晶試料をつくるための方法として、その適用範囲の広さやコストの低さから多く用いられているフラックス法について、一般的な原理から実用的な実験手順まで体系的に解説した。
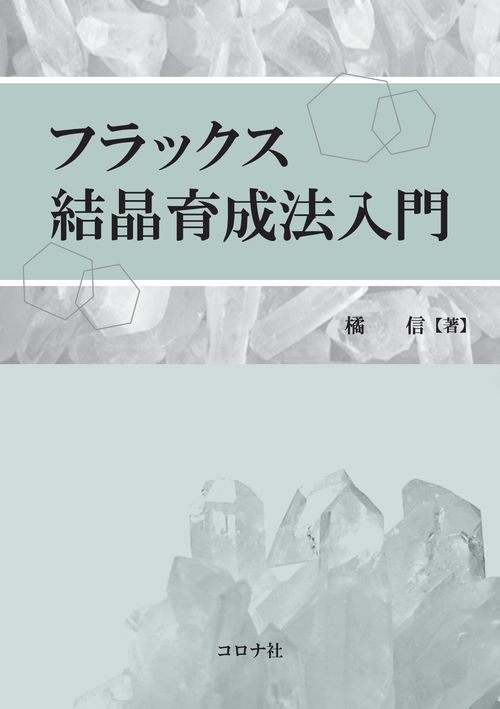
フラックス結晶育成法入門
詳細を見る
情報工学
暗号理論の解説に加え,差分解読法・線形解読法,ハッシュ関数の解析,RSA 暗号に対する攻撃等を体験できる Python プログラムを提供。理論だけでは実感が湧きにくい暗号の仕組みを,プログラムを動かしながら学ぶ。
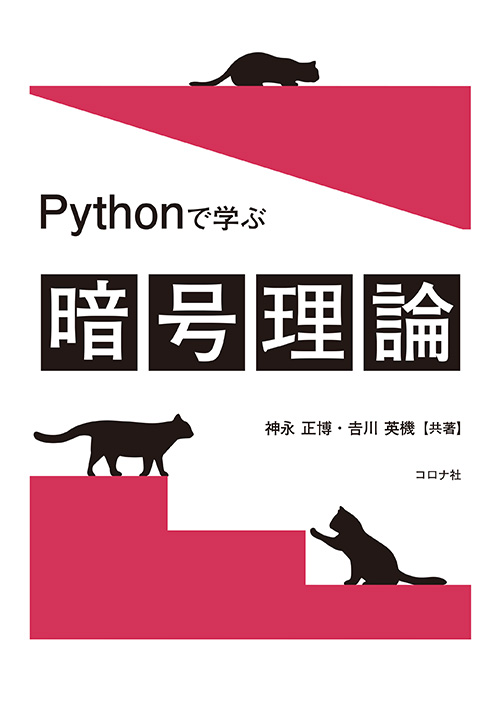
Pythonで学ぶ暗号理論
詳細を見る今後の情報社会を支えるであろう現代の光コンピューティング技術について,基礎から先端技術までを速習する。物理的な側面「光」と情報学的な側面「コンピューティング」を織り交ぜつつ話を進め,研究の最前線になじむことを目指す。
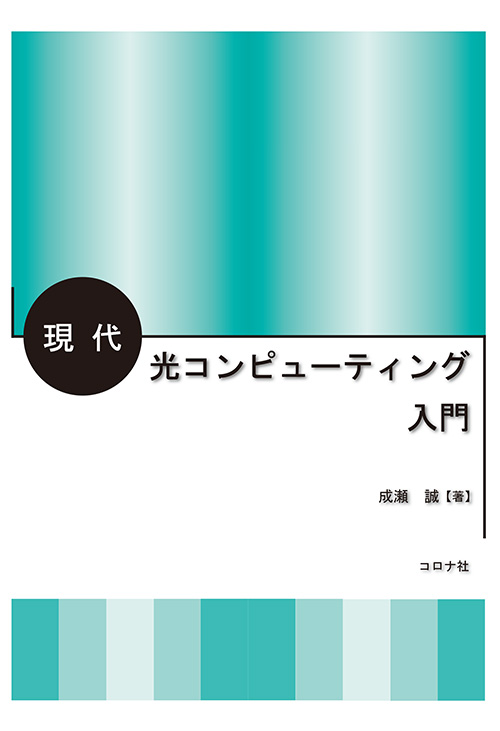
現代光コンピューティング入門
詳細を見るデータサイエンスの土台を築くために欠かせない情報数理に焦点を当て,パターン認識や機械学習の本質を学ぶために必要な内容に絞って丁寧に解説。データサイエンスを学び始める際にはもちろん,基礎を再確認するためにも最適な1冊。
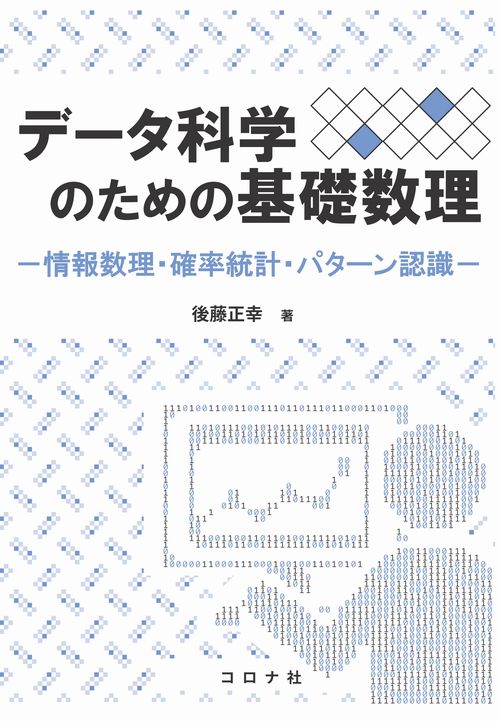
データ科学のための基礎数理
詳細を見る
- 高校数学から偏微分まで -本書は,基礎的な内容のみならず,他の入門書にはあまり書かれていない比較的高度な内容も含む。各章末には情報関連の各種資格試験の過去問題を収録し,本書で学んだ内容がどのような設問として問われるかがわかるようになっている。
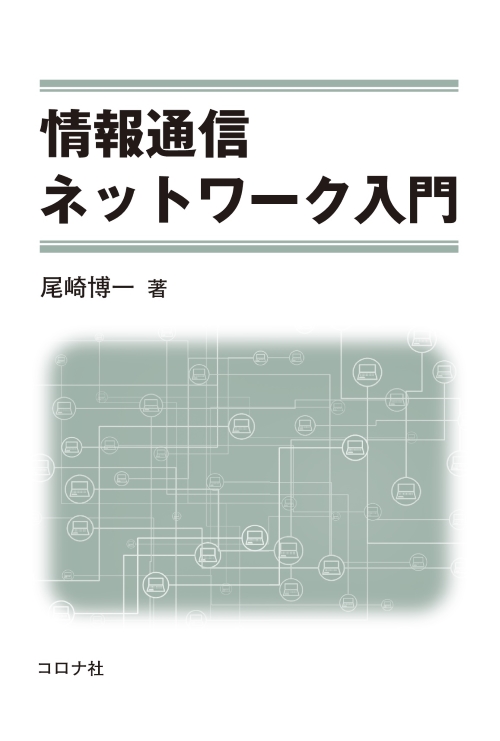
情報通信ネットワーク入門
詳細を見る
マルチメディア
ヘッドマウントディスプレイは,VRやARを実現するための代表的なデバイスである。多種多様なHMDの違い,選択基準,性能や機能の進化,進化に伴う生活や社会の変化など,HMDを網羅的に取り上げた初めての書籍である。
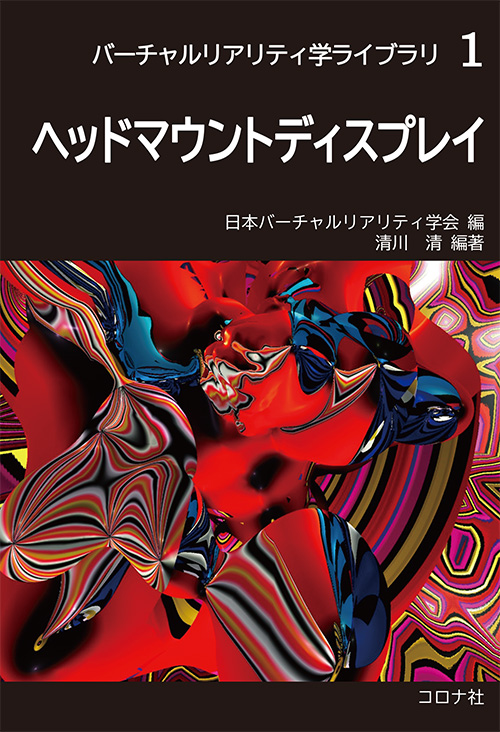
バーチャルリアリティ学ライブラリ 1
詳細を見る
ヘッドマウントディスプレイVRにおいて,感覚提示や感覚変容は非常に重要である。このような感覚を生じさせる仕組みが神経刺激インタフェースである。神経刺激には刺激するための目的がある。どのように研究されてきたのかを1冊で理解できるようまとめた。
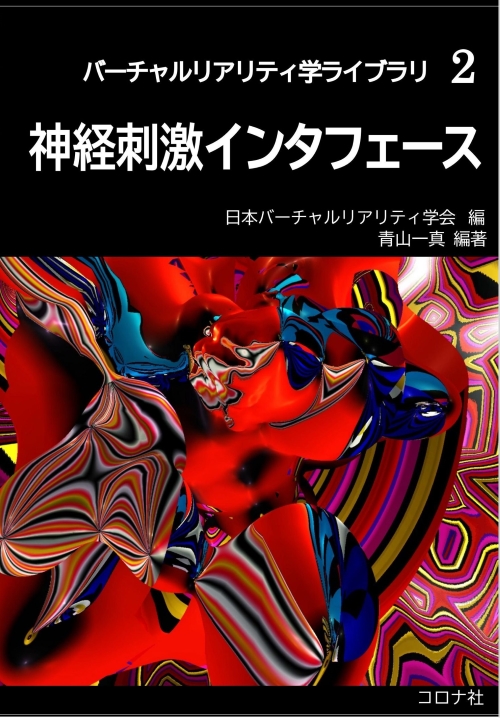
バーチャルリアリティ学ライブラリ 2
詳細を見る
神経刺激インタフェース「デジタルファブリケーション」というデジタルデータをもとに制作を行う技術は製造からメディア,アートまで多岐にわたる領域で革新的な変化をもたらしている。本書では,その起源や技術,背景にある思想や今後の可能性を解説する。
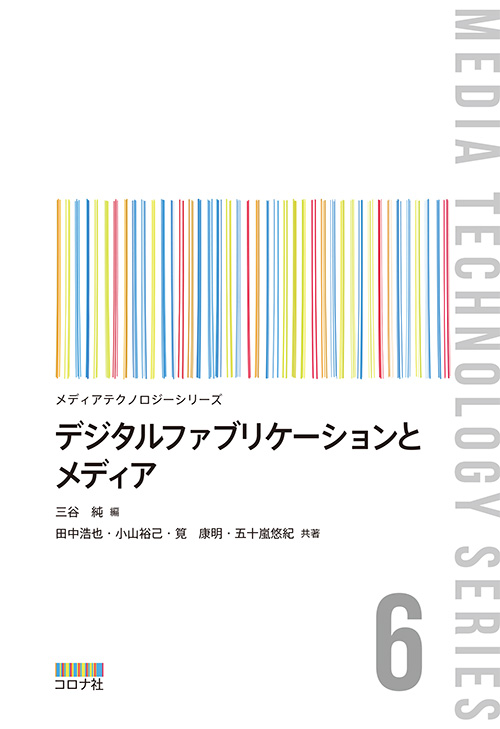
メディアテクノロジーシリーズ 6
詳細を見る
デジタルファブリケーションとメディア今後この分野の研究・開発に取り組む方々の共通基盤となる知見を提供する事に主眼を置き,シリアスゲームの成り立ちから展開,各分野の事例や新たな取組みを整理して論じるとともに,その意義や社会に起こした影響を解説。
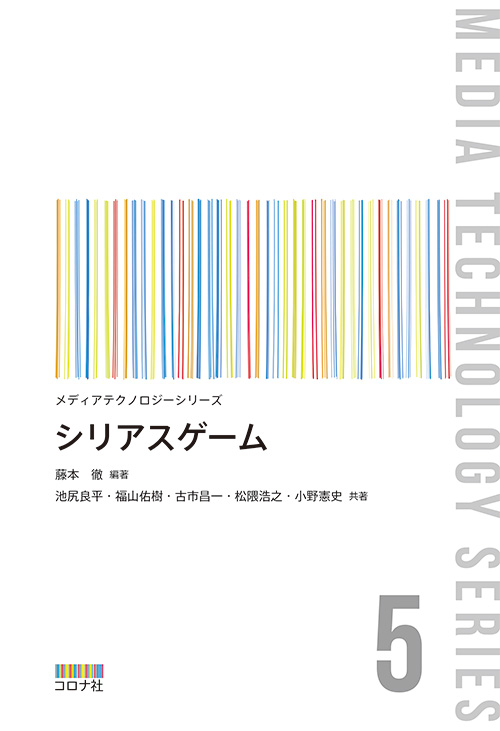
メディアテクノロジーシリーズ 5
詳細を見る
シリアスゲーム
経営・管理工学
本書の目的は,ポストを求めて出現する応募者の中から望ましい人を採用したいとき,利用可能な情報に基づく最適な採用方策を求め,その効果を調べることにある。多種多様な確率モデルが提唱され,興味深い結果が得られる。
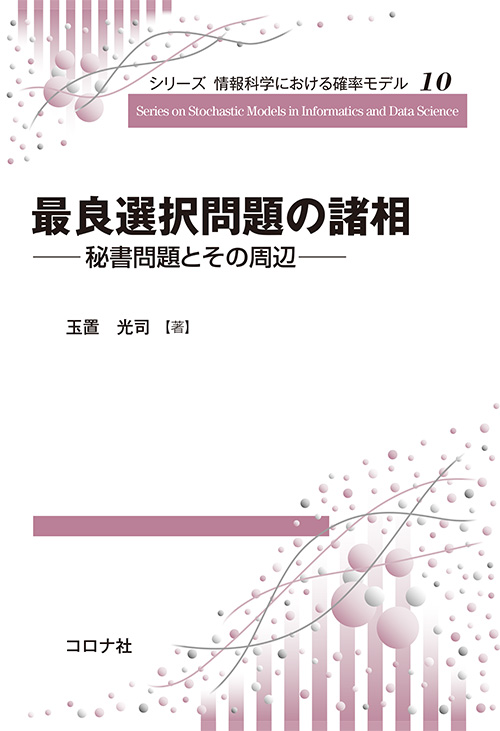
シリーズ 情報科学における確率モデル 10
詳細を見る
最良選択問題の諸相
- 秘書問題とその周辺 -本書は,数理最適化自体の研究について扱っているのではなく,数理最適化に関するこれまでの研究成果とJuliaの既存パッケージを利用して,身近な問題を実際に解くことに興味のある方を読者対象としている。
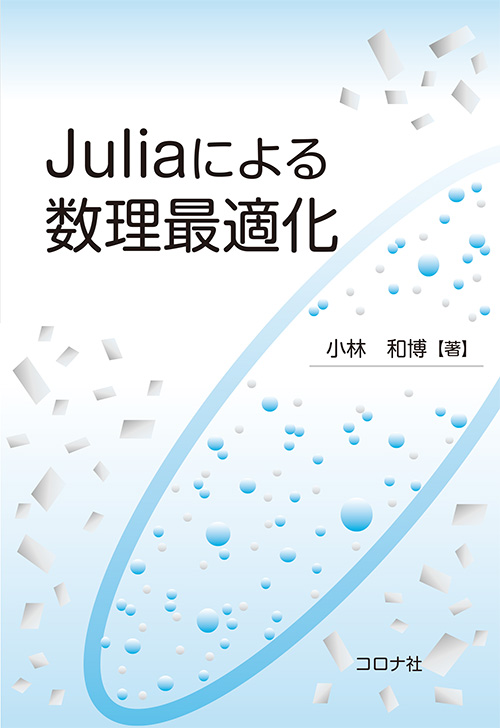
Juliaによる数理最適化
詳細を見る本書は,直接に知ることのできない状態に関する情報を解析するための基本的な方法として用いられるベイズの定理に基づく学習と,それをもとにした部分観測可能なマルコフ決定過程の基本的な結果と応用についてまとめた。
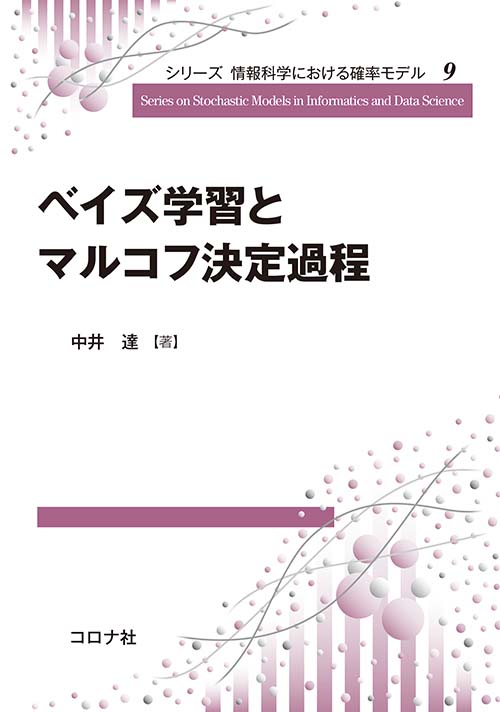
シリーズ 情報科学における確率モデル 9
詳細を見る
ベイズ学習とマルコフ決定過程本書は2人ゲームを念頭に非協力ゲーム理論の基礎から,ゼロ和ゲーム,非ゼロ和ゲーム,無限ゲーム,有限ゲーム,そして発展的なモデルまで,多種多様なバリエーションを示し、不確実性下の意思決定問題に生かせる内容となっている。
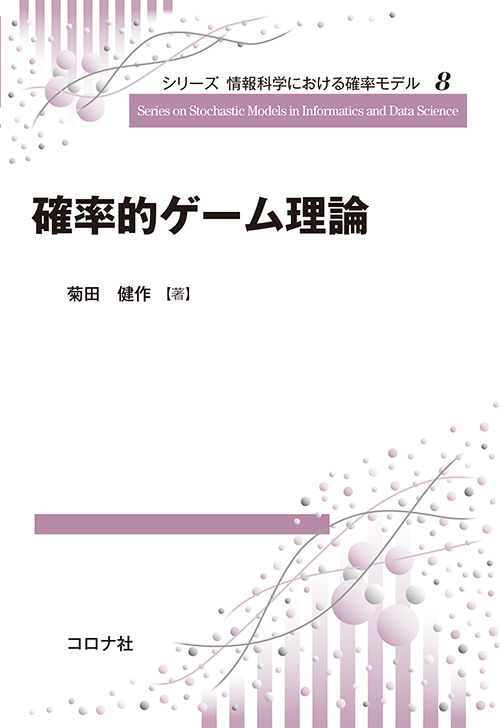
シリーズ 情報科学における確率モデル 8
詳細を見る
確率的ゲーム理論
電気・電子工学
発音体の動きを表す微分方程式,解として得られる「発音体の固有振動」=「楽器の音響特性」の物理的な本質を理解することを目的とした。これは,楽器開発職人が直感的に理解していたことで,高校までの知識で十分理解可能である。
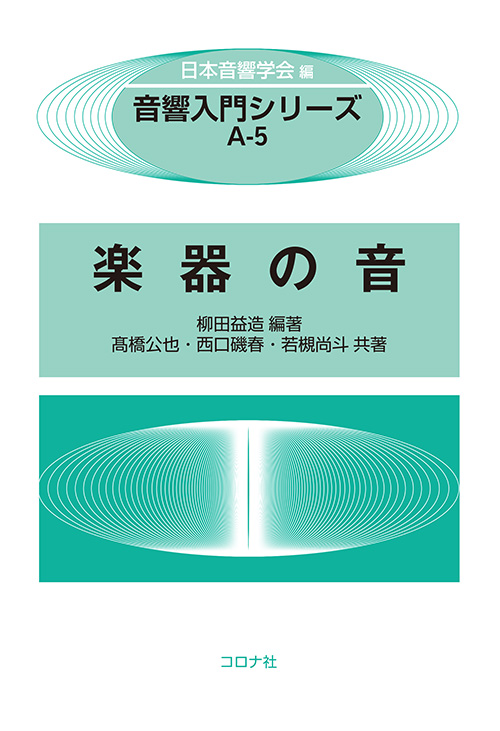
音響入門シリーズ A-5
詳細を見る
楽器の音本書は,平面鏡,レンズ,プリズム,偏光素子,レーザ用素子等の光学素子を,光路制御,結像作用,合・分波,透過率制御,光学系調整法等の機能別に分類・構成し,読者の使用目的に合致した光学素子を探しやすくした実用書である。
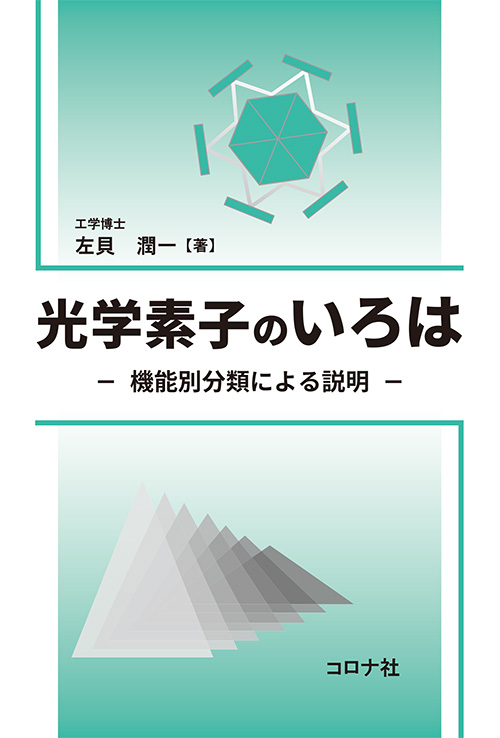
光学素子のいろは
詳細を見る
- 機能別分類による説明 -前半ではスイッチングによる電磁界ノイズ(EMI)の発生原因とその解決法を電磁気学の理論に基づいて説明する。後半では回路技術の視点から,コイルやトランスに関係する発熱要因とその解決法など,実践的な技術について説明する。
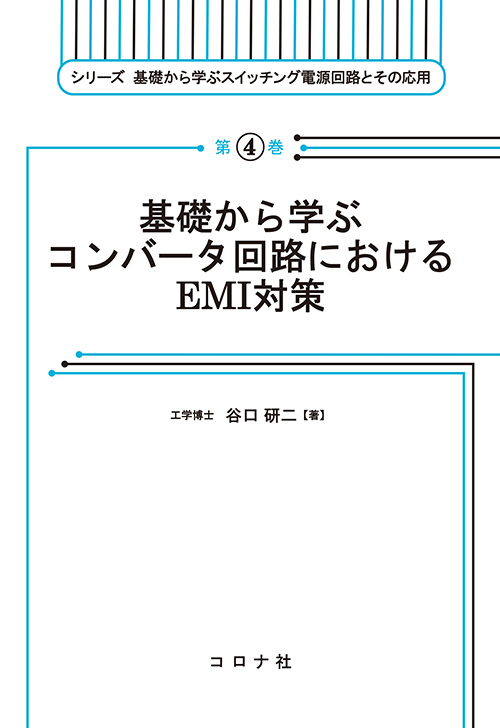
シリーズ 基礎から学ぶスイッチング電源回路とその応用 4
詳細を見る
基礎から学ぶコンバータ回路におけるEMI対策通信の典型的な問題に対する典型的な信号処理手法について解説することで,現在の通信システムで用いられている最先端の信号処理技術を理解するために必要な最低限の知識を,効率的かつ体系的に提供することを目的としている。
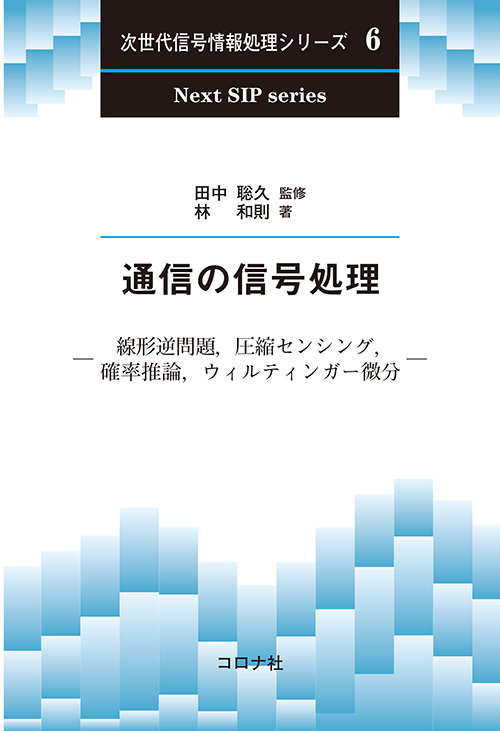
次世代信号情報処理シリーズ 6
詳細を見る
通信の信号処理
- 線形逆問題,圧縮センシング,確率推論,ウィルティンガー微分 -
ME・医学・福祉
人間の意図または意図のために生成した脳活動を脳計測によって読み取り,本人の意図を外部へ伝達する技術であるブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)のタスク・刺激と出力の関係(パラダイム)や信号処理を解説した。
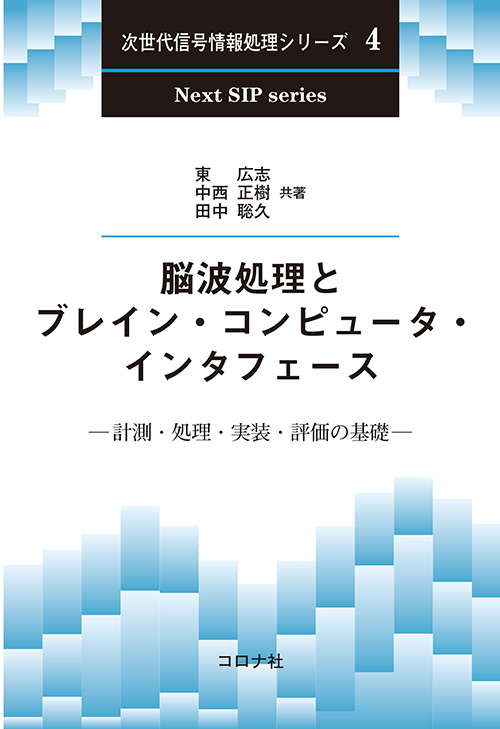
次世代信号情報処理シリーズ 4
詳細を見る
脳波処理とブレイン・コンピュータ・インタフェース- 計測・処理・実装・評価の基礎 -本書では,ミリ波・マイクロ波イメージング技術のシステムを構築するために必要な知識・技術を系統的に解説している。また読者の理解を促すため,画像再構成を行うためのMATLABのプログラムコードを解説,掲載し配布している。
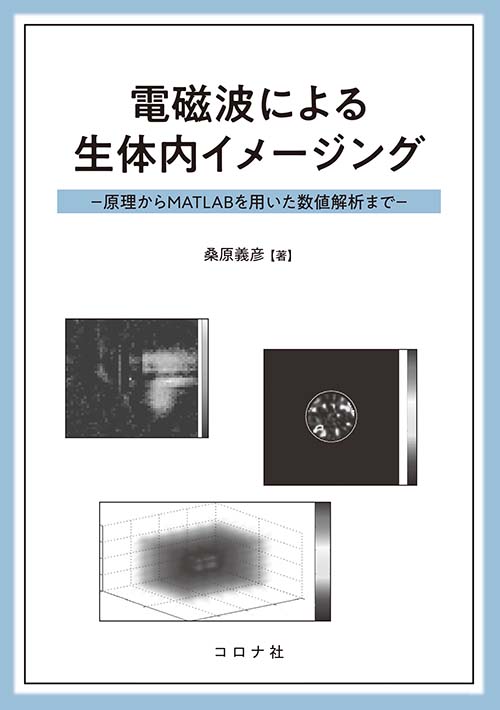
電磁波による生体内イメージング
詳細を見る
- 原理からMATLABを用いた数値解析まで -移植用細胞の効率的培養技術や自動培養技術,非侵襲的細胞品質評価技術を含めたセルプロセッシング工学の基礎から最先端までを解説。増補版では再生医療にも貢献し得る自己組織化をはじめとした新しい基礎技術の解説を加えた。
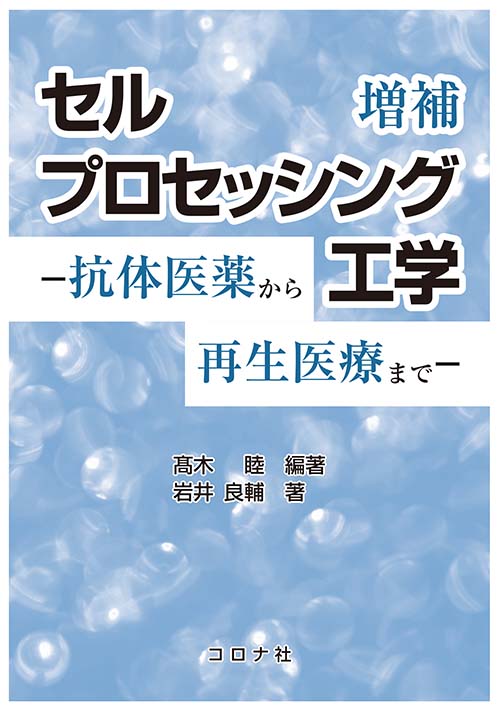
セルプロセッシング工学
詳細を見る
(増補)- 抗体医薬から再生医療まで -医用画像(CTやMRI)以外,特に生体信号を用いたAI技術に焦点を当て,新たな医療AI開発の時代に備えるために必要な事柄を丁寧に解説した。さらに,医療AIに関わる法律や倫理,薬事についても解説を試みた。
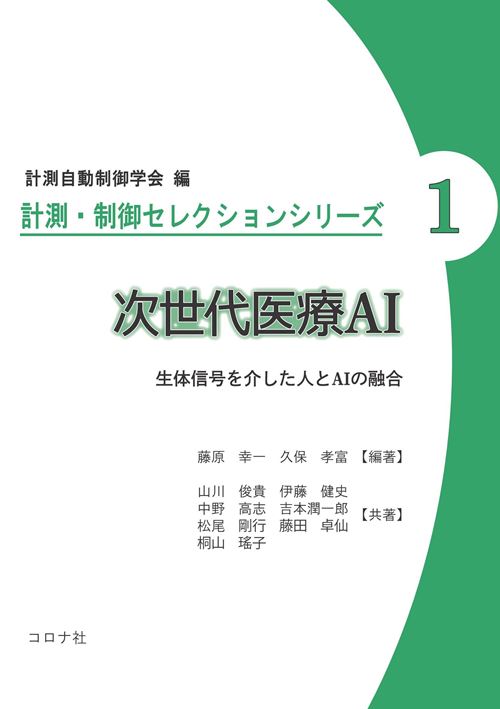
計測・制御セレクションシリーズ 1
詳細を見る
次世代医療AI
- 生体信号を介した人とAIの融合 -
計測・制御
モデルベースドアプローチと異なり,データを直接用いて制御器を設計・更新・調整する方法はデータ駆動制御と呼ばれる。モデリングが困難な状況で操業データを有効に使いコストダウンを実現する方法論を整理・体系化した入門書。
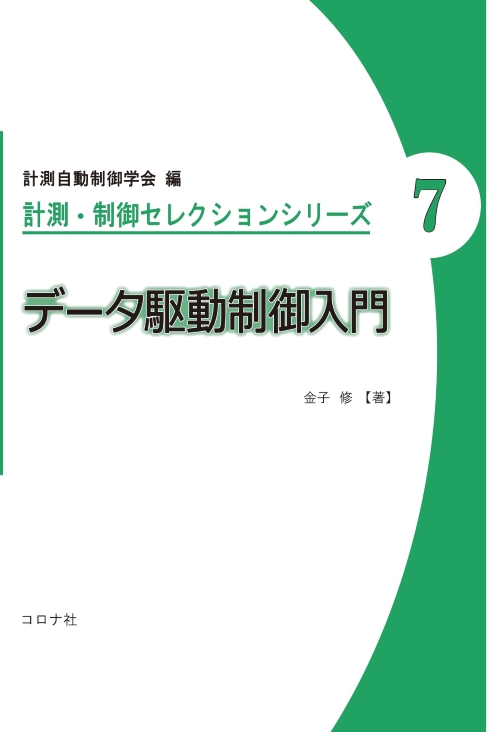
計測・制御セレクションシリーズ 7
詳細を見る
データ駆動制御入門アーム付き自律移動ロボットを例にとり,その構成要素(ハードウェア,ナビゲーション機構,アーム制御機構,機械学習,システムアーキテクチャ)を原理に基づいて学ぶことで,IoT システムの全体像を理解できるよう解説した。
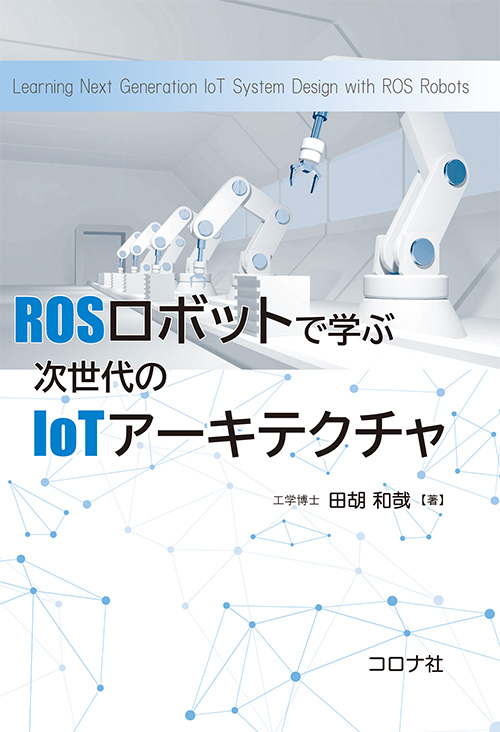
ROSロボットで学ぶ次世代のIoTアーキテクチャ
詳細を見る千差万別ともいわれるセンサ技術を,その広い分野の中で,代表的ニーズがあると考えられる技術に対象を絞り,専門家でない人にもわかりやすいよう,基礎編と応用編にわけて解説している。
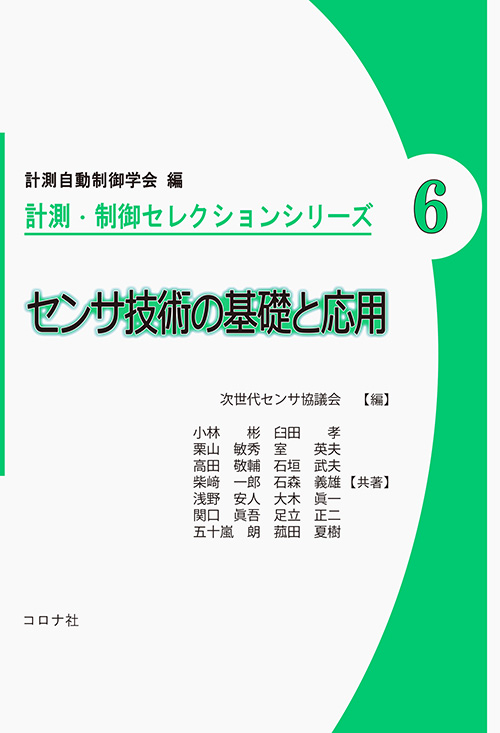
計測・制御セレクションシリーズ 6
詳細を見る
センサ技術の基礎と応用多変量解析や最適化の分野では,行列を用いて考えることが多く,できる限り行列を1つの単位とする行列操作が必要となる。本書では,動機づけを与える疑問を示し,そのうえで議論を進める。内容は実用上で重要なものに絞った。
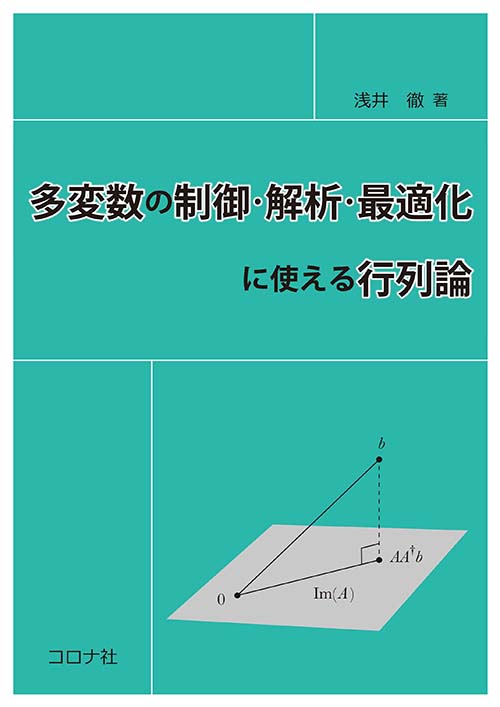
多変数の制御・解析・最適化に使える行列論
詳細を見る
機械工学
ロボティクスには広大な範囲の知識が必要とされます。本書では,ロボットの組立て,制御やセンサ処理のプログラミング,性能評価,ロボコンでの作戦など,ロボットだけに限定して,様々な確率・統計の知識を学ぶことが目的です。
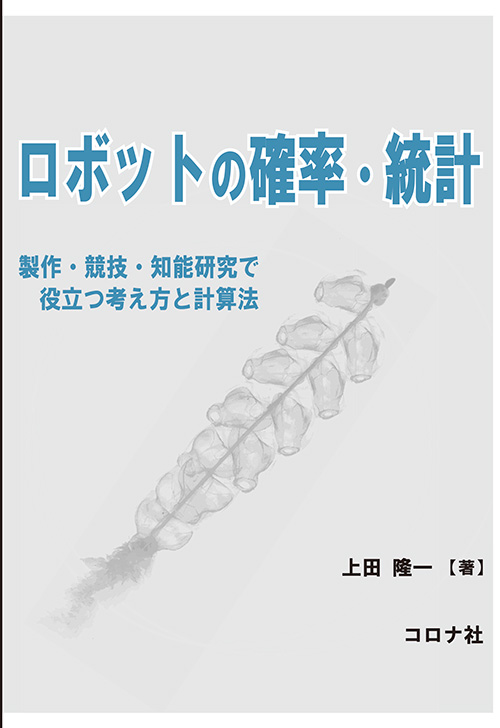
ロボットの確率・統計
詳細を見る
- 製作・競技・知能研究で役立つ考え方と計算法 -不整地移動ロボットを体系的に扱う書籍。各分野で定義がまちまちだった「不整地」の定義と分類を行い,不整地移動ロボットの代表的な移動形態である「車輪型/クローラ型」,「脚型」,「ヘビ型」の機構や力学,制御を広範に解説。
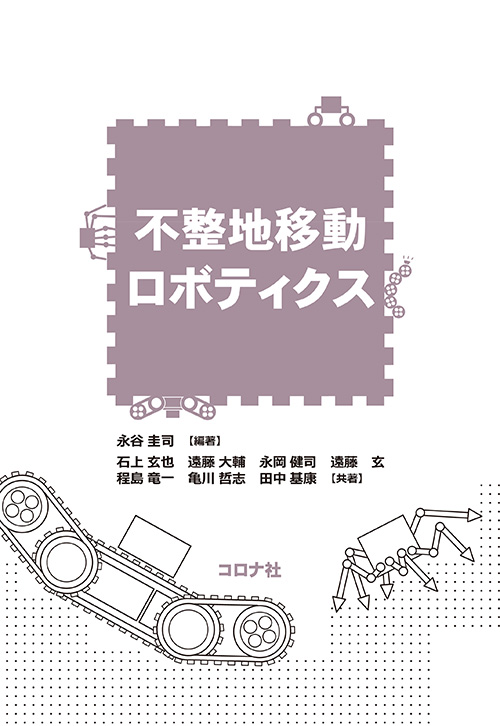
不整地移動ロボティクス
詳細を見る異種接合材において,き裂のような欠陥による応力が無限大となる場合は,通常の応力集中と異なり理解が難しい。本書では,材料組合せをパターンとして表すことで理解の便を図り,実務的な専門書となるように解説した。
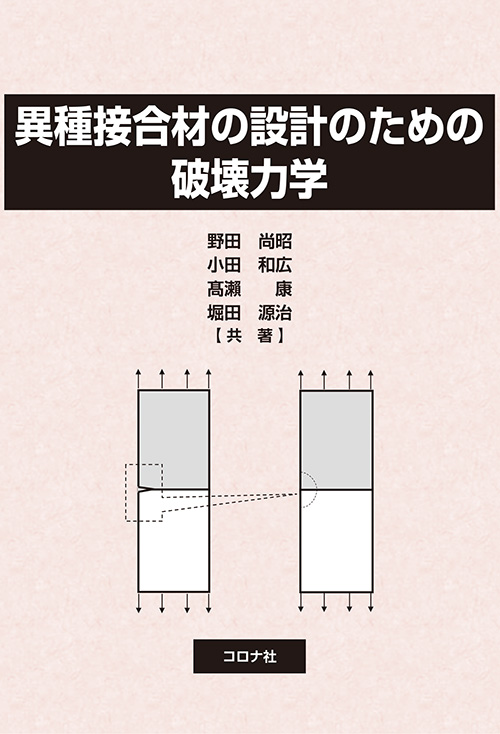
異種接合材の設計のための破壊力学
詳細を見るイノベーティブな製品・サービス・経験を生み出すための「設計工学」指南書。設計対象をシステムととらえ,いわゆる「設計学」や「デザイン学」の分野を横断し,汎用可能な知として議論の展開を行った。設計・デザインに携わる方必携!
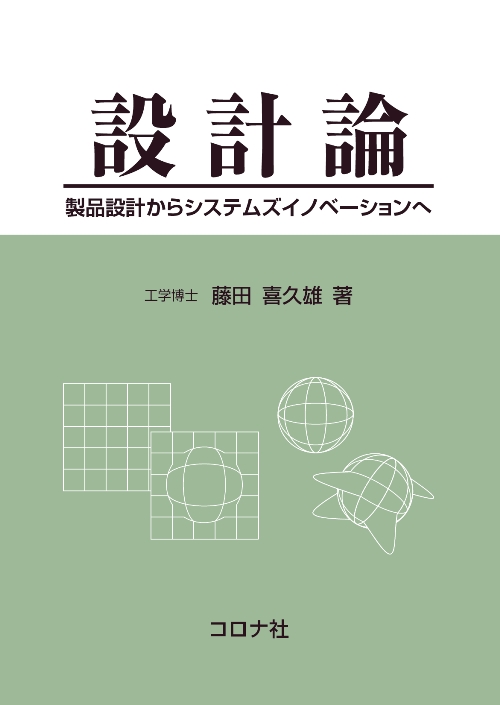
設計論
詳細を見る
- 製品設計からシステムズイノベーションへ -
モビリティ
航空交通管理の成り立ちと現状,システム設計と評価に関わる研究開発,社会実装に至るプロセスと課題を概観して論じる。さまざまな専門分野の読者を想定し,知識の有無に関わらず,航空交通管理分野の体系を学ぶことができる。
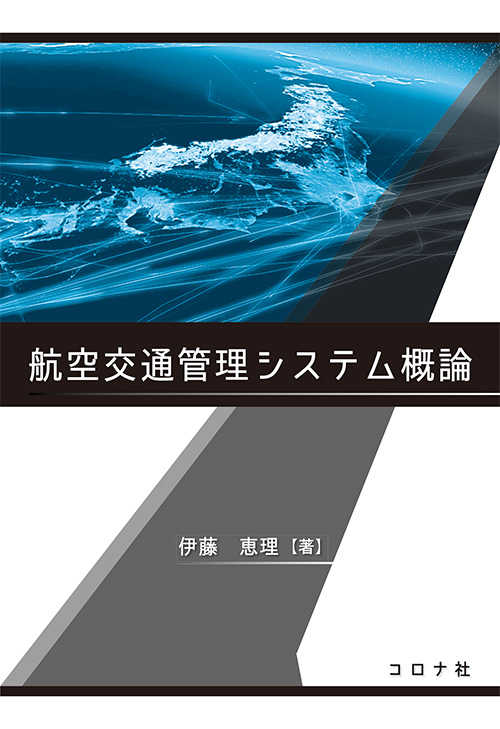
航空交通管理システム概論
詳細を見る製品設計にシミュレーションモデルを用いるモデルベース開発(MBD)について,MATLABを用いて体験的に学習できる良書の改訂版。HILシミュレータなどもWebで提供し,今回の改訂ではスマートMBDについても紹介した。
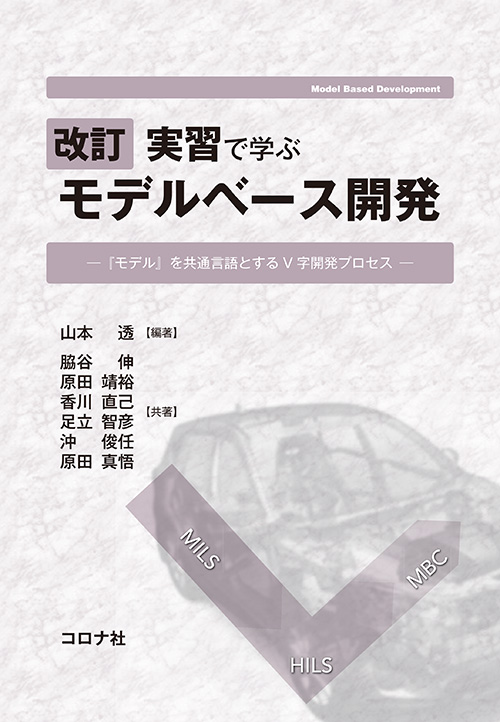
改訂 実習で学ぶ
詳細を見る
モデルベース開発
- 「モデル」を共通言語とするV字開発プロセス -人工衛星と宇宙探査機の設計法について,具体的な多くの例題も紹介しながら,システム構成,構造設計,軌道設計,制御技術について解説。増補では新たに章を追加し,衛星のサブシステムや搭載機器の耐環境性のための検証試験も追加。
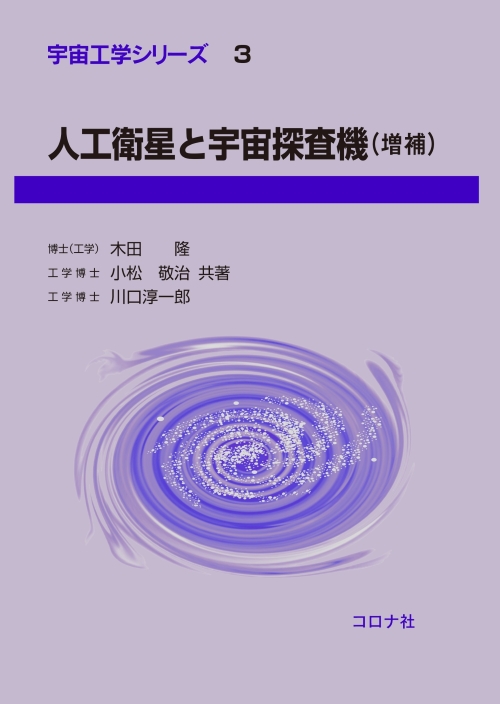
宇宙工学シリーズ 3
詳細を見る
人工衛星と宇宙探査機
(増補)ロボットや自動車が自動走行を行うために不可欠な「自己位置推定」について,その頑健性や信頼度などのさまざまな問題点に対して,枠組みを拡張,もしくは新しい手法を導入し,高性能化することで,それらの問題解決を目指した一冊。
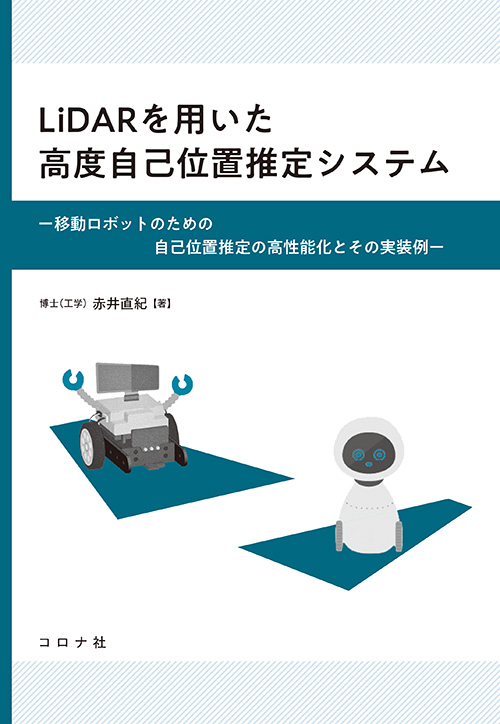
LiDARを用いた高度自己位置推定システム
詳細を見る
- 移動ロボットのための自己位置推定の高性能化とその実装例 -
土木工学
充実した解析手法の説明と,実際のデータを用いた豊富な例題・演習により,土木・交通計画で必須の分析手法である多変量解析の考え方・適用方法を身につける。改訂版では8章の因子分析の内容を再整理し,その説明を充実させた。
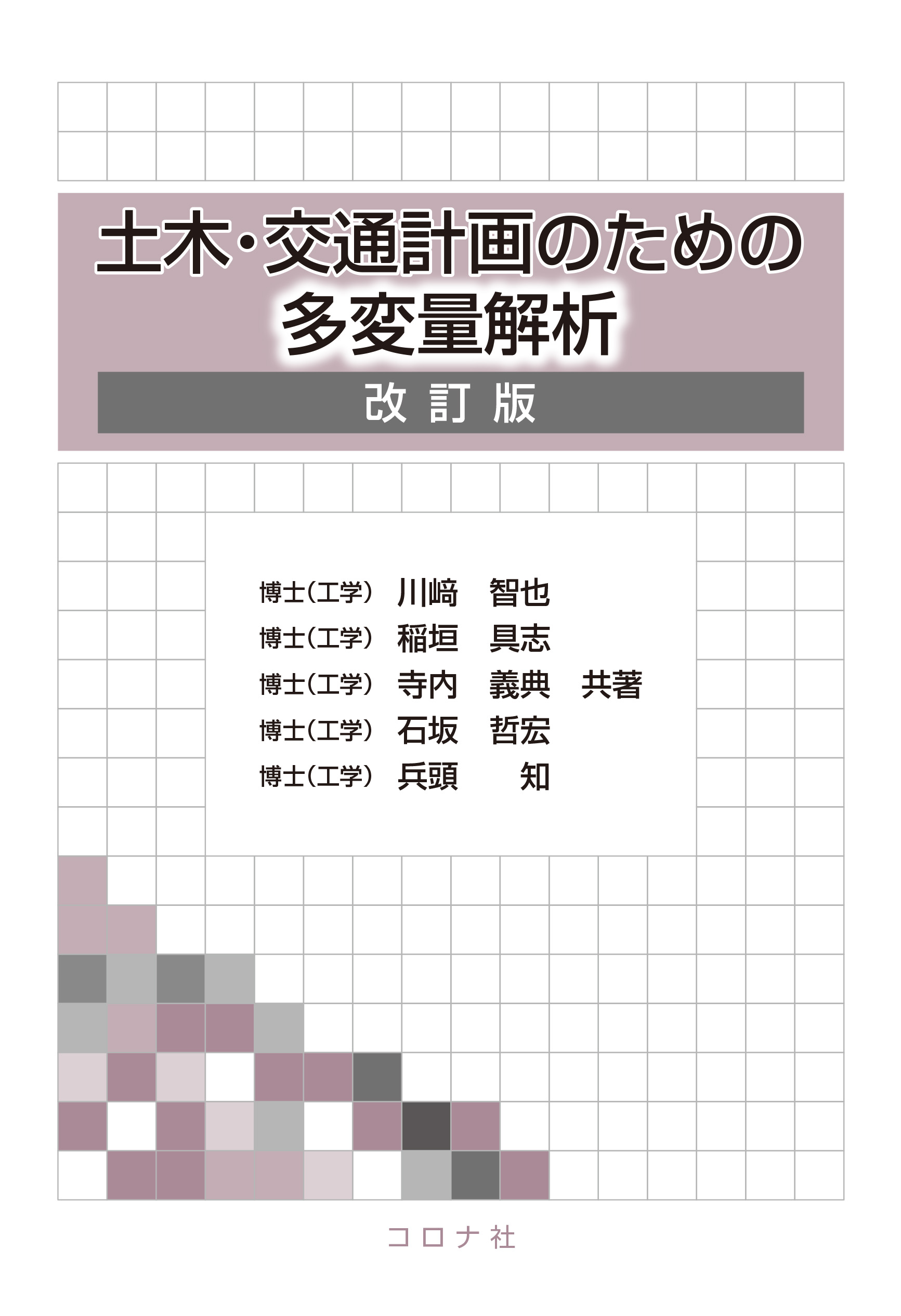
土木・交通計画のための多変量解析
詳細を見る
(改訂版)マクロ交通流シミュレーションの基礎から応用までを解説し,原理原則,数学的理論,それらの実装法を理解する。また,シミュレータの実装を通して,数学的理論をプログラムとして具現化し,実社会の問題解決に役立てる面白さを学ぶ。
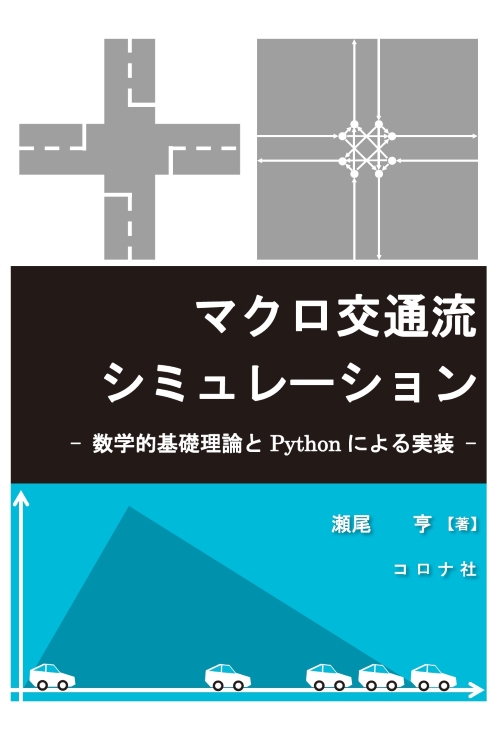
マクロ交通流シミュレーション
詳細を見る
- 数学的基礎理論とPythonによる実装 -繰返し荷重を受ける鋼構造物では,しばしば疲労が問題となる。本書では,特に鋼道路橋の溶接継手を対象として,その基本的な疲労挙動を解説する。また,本書の内容は,鋼道路橋以外の溶接構造物に適用することも可能である。
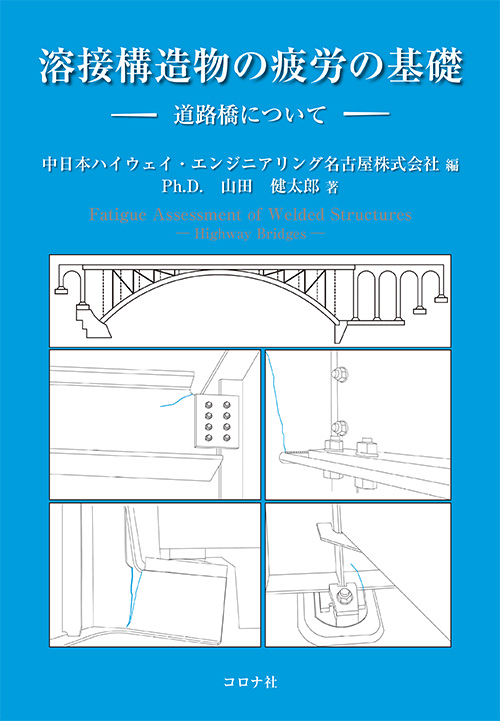
溶接構造物の疲労の基礎
詳細を見る
- 道路橋について -都市マスタープラン,土地利用計画,交通計画,都市施設設計を歴史的な背景含め体系的に整理した都市計画・国土計画の教科書。五訂版ではコンパクトシティ実現化に向けた立地適正化計画を含め,都市計画関連法制度の改正を反映した。
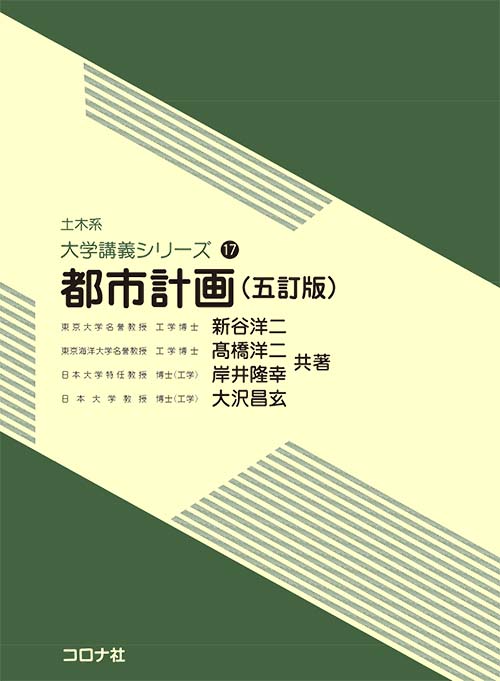
土木系 大学講義シリーズ 17
詳細を見る
都市計画
(五訂版)
建築工学
モニタリング技術の知識は,これまで個々の研究開発者への依存性が高くその習得に多数の研究論文を必要としてきた。本書は土木・建築分野と情報分野の知識を体系的にまとめ,各技術の到達点と課題を大まかに理解できるよう解説した。
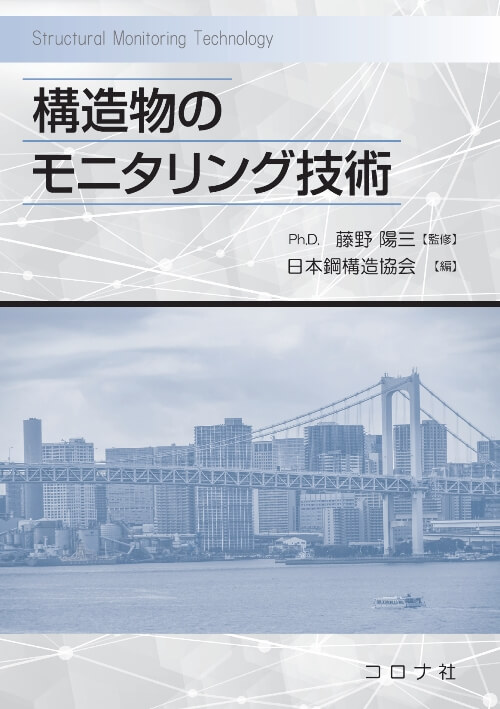
構造物のモニタリング技術
詳細を見る建設技術者を目指す人が最低限必要な防災工学の知識を学べるよう,地域防災計画等でおもな災害対象の、地震災害、風水害、火山災害などの自然災害について,基礎的な知識から災害の予測・対策方法まで具体的な事例を交えて解説した。
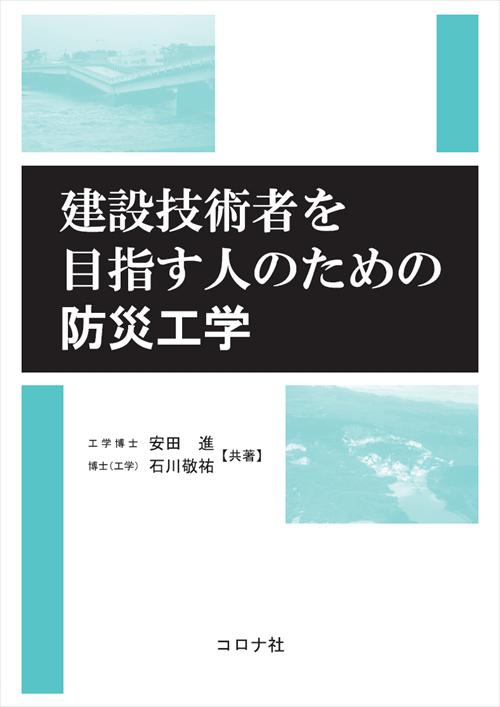
建設技術者を目指す人のための防災工学
詳細を見る本書は,災害対策のための自治体や自主防災組織,企業,学校などの地域防災,および,社会経済への影響が大きい電気,通信,上下水道,道路などのライフライン防護について,具体的な現状と課題を解説した防災対策の教科書である。
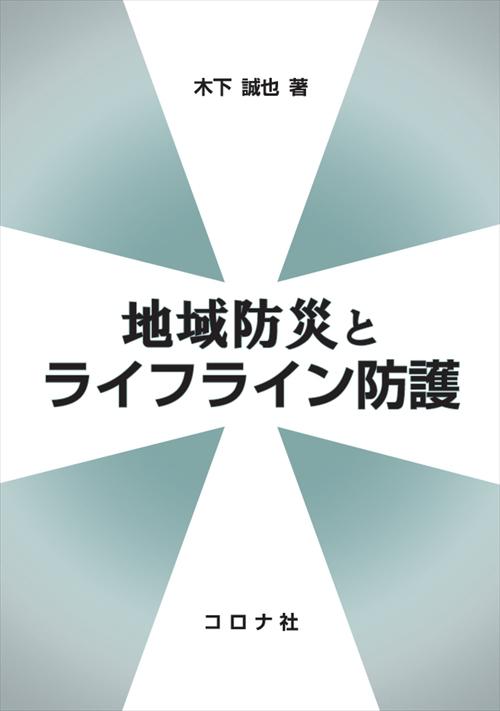
地域防災とライフライン防護
詳細を見る測量学や統計学などの多変量分析などの分野に応用されてきた「一般逆行列」について,本書では,構造工学への応用に焦点を絞り,その理論と有用性について平易に解説した。
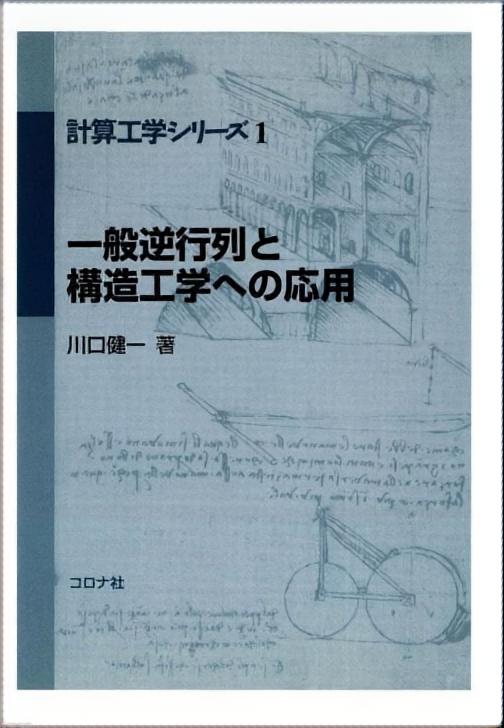
計算工学シリーズ 1
詳細を見る
一般逆行列と構造工学への応用
環境・エネルギー
バイオマス利用の基礎理論と,特にマテリアル利用とエネルギー利用のための実際の技術,生物資源の生産や収穫などに関わる機械作業や乾燥操作,食の安全,環境影響評価,SDGsとの関わりなど,社会実装に至る話題を取り上げた。
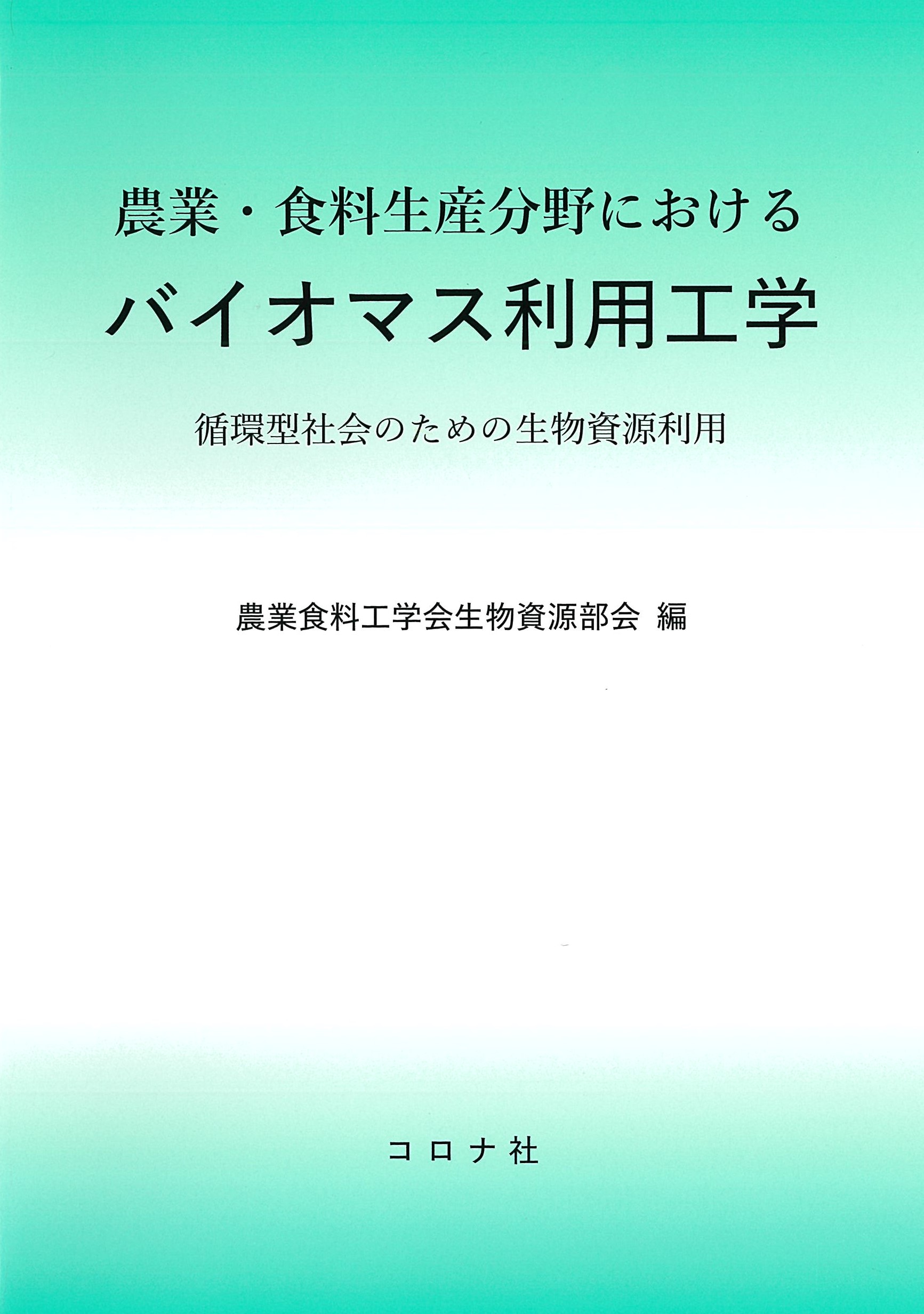
農業・食料生産分野における
詳細を見る
バイオマス利用工学
- 循環型社会のための生物資源利用 -発行から約20年が経過した初版の記載内容を見直しつつ最新の情報へ更新した。さらに基礎編では核分裂生成物の挙動に関する章を,応用編では福島第一原子力発電所の事故を受けた水化学技術に関する章を新たに追加した。
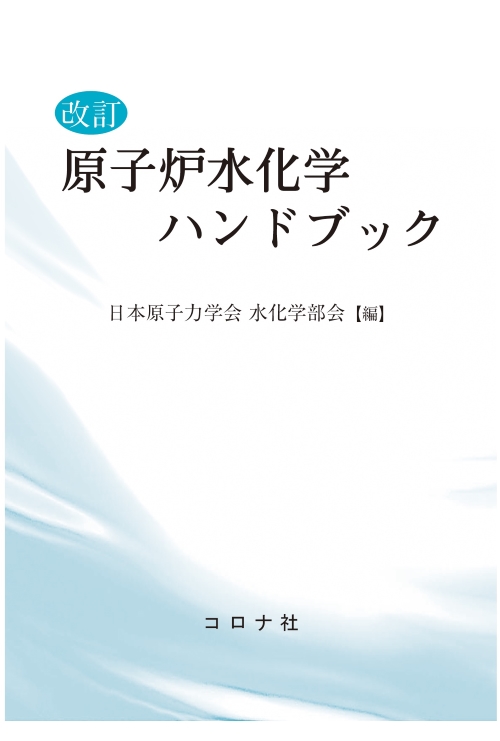
改訂
詳細を見る
原子炉水化学ハンドブック環境問題は喫緊の課題である。今も人類によって自然環境は大きく破壊されつつあるが,科学技術をさらに発展させれば,人類は自然と共生することができるようになるのか。本書では,よい環境とは何か,よい社会とは何かを考えていく。
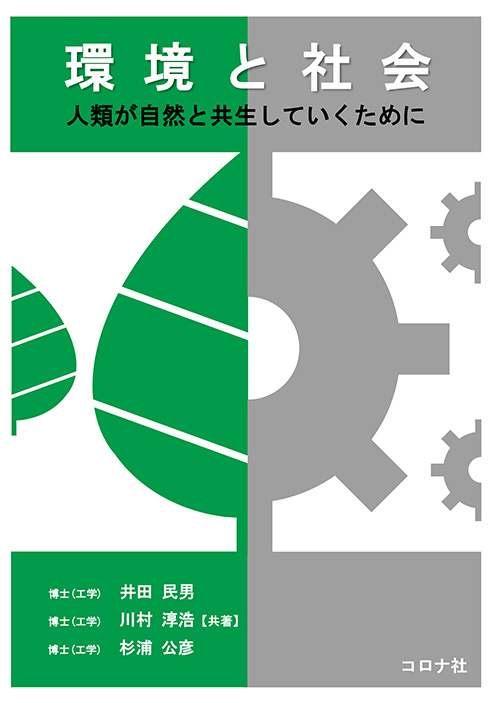
環境と社会
詳細を見る
- 人類が自然と共生していくために -本書では木本系,草本系,農産系,厨芥系,果樹系バイオマス資源の特性を熱・物理学的観点から説明し,さらにバイオコークスの熱エネルギーとしての基本特性や循環型社会実現に向けたバイオコークス開発の意義などについて解説する。
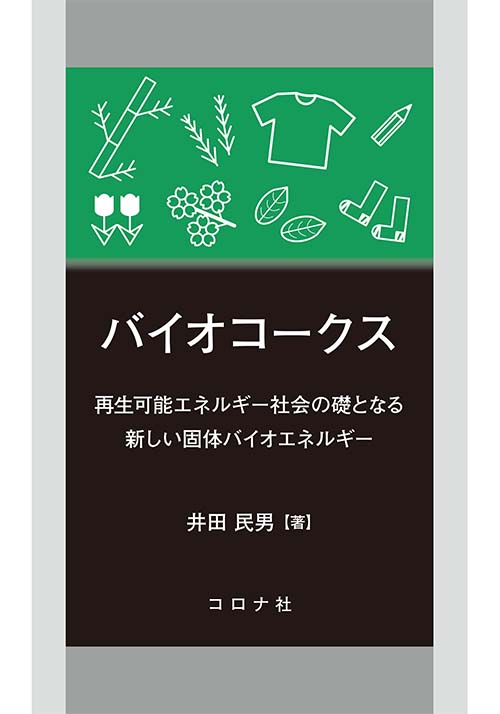
バイオコークス
詳細を見る
- 再生可能エネルギー社会の礎となる新しい固体バイオエネルギー -
化学・化学工学
冷却水系,ボイラー系のような水誘導装置系で多く用いられている腐食抑制剤(腐食インヒビター)について,高分子化合物類を中心に,その作用機構も含めて解説する。また,環境問題の観点から水質と金属腐食の関係についても触れる。
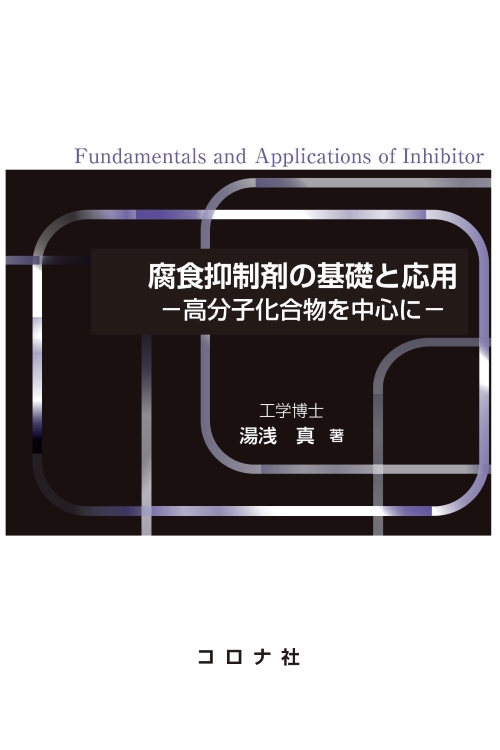
腐食抑制剤の基礎と応用
詳細を見る
- 高分子化合物を中心に -化学系CFDのメジャーソフトAnsys Fluentによる,化学工学の主要科目である移動現象論に焦点を当てた解説本である。流れ,伝熱,物質移動の三つの観点から構成,特に解析解との比較という点に留意した内容である。
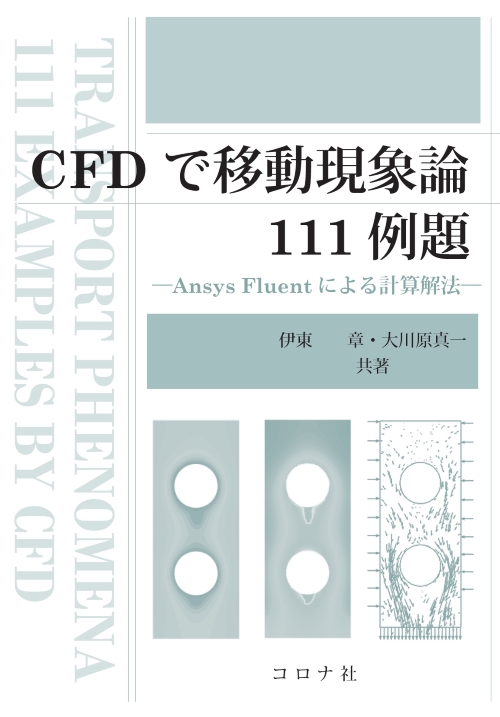
CFDで移動現象論111例題
詳細を見る
- Ansys Fluentによる計算解法 -本書では初めに量子化学を簡単に解説し,その延長として電子スペクトル,続いて振動スペクトル,回転スペクトル,磁気共鳴の順に解説する。この順序は光の波長に対応している。遷移エネルギーと電磁波の波長の関係についても述べる。
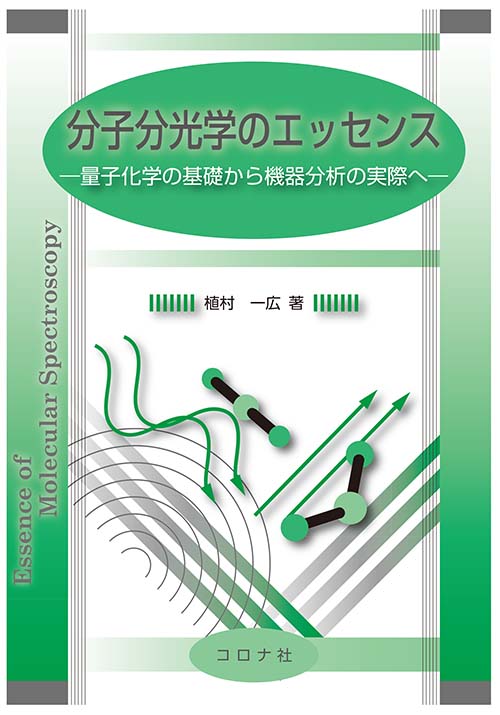
分子分光学のエッセンス
詳細を見る
- 量子化学の基礎から機器分析の実際へ -自然科学を構成する熱力学は,巨視的な平衡状態を対象とする体系的な学問である。本書は,平衡状態として物体の相平衡に注目し,第一法則と第二法則に基づいて熱力学の体系をわかりやすく説明した入門書である。
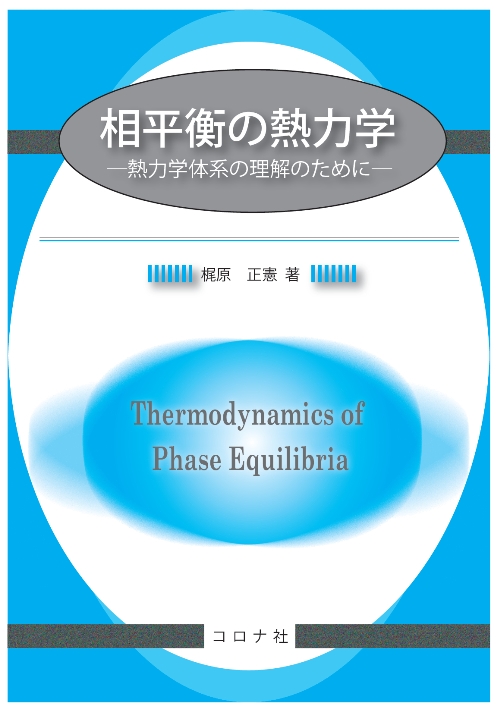
相平衡の熱力学
詳細を見る
- 熱力学体系の理解のために -
生命科学・農学
本書は,未来の医学・医療を「データ駆動型」の医学・医療ととらえ,健康管理・疾病管理・寿命延伸にインパクトが与えるような生命情報の収集方式,およびそれを有効に活用できる医療のあり方,実践体制について解説した。

次世代生命情報医学
詳細を見る本書では,データサイエンスを活用した生命研究をするために必要な,統計科学の基礎を解説する。紹介する解析手法の多くに数式を用いた導出をつけ,読者が各手法の由来を理解したうえで使えるようになることを目指した。
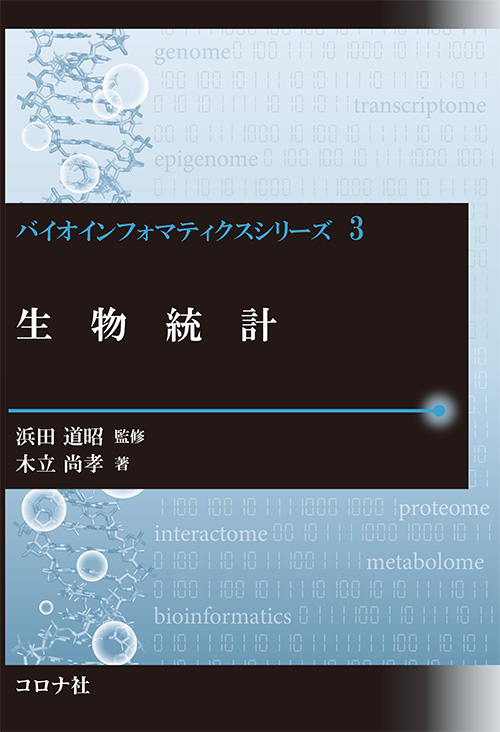
バイオインフォマティクスシリーズ 3
詳細を見る
生物統計プログラミング初学者が数理生命科学の手法を理解,実践することを目的とした入門書。用語の説明を丁寧に行っており,またOctaveでの利用法も説明しているため,MATLABを所有していなくても気軽に学ぶことができる。
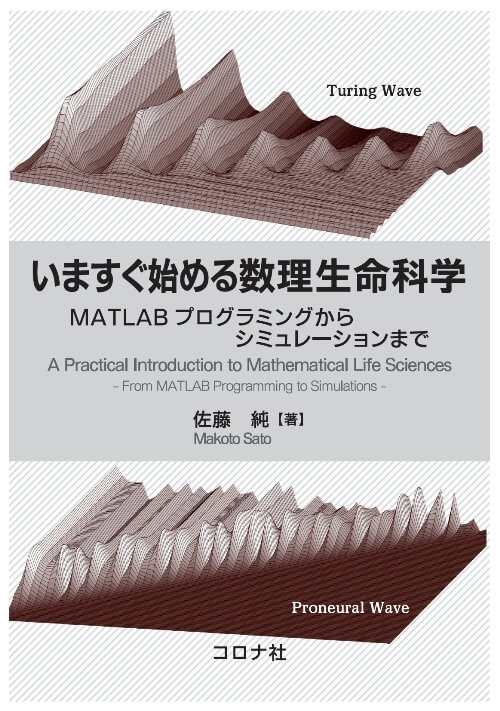
いますぐ始める数理生命科学
詳細を見る
- MATLABプログラミングからシミュレーションまで -農業機械はもとよりセンシング技術や電子制御,自動化ならびにロボット化,ICTの活用さらには環境やエネルギー,ポストハーベスト技術に加えて食料生産・流通に係わる技術分野を体系的にまとめ直し,農業食料工学の知見に資する。
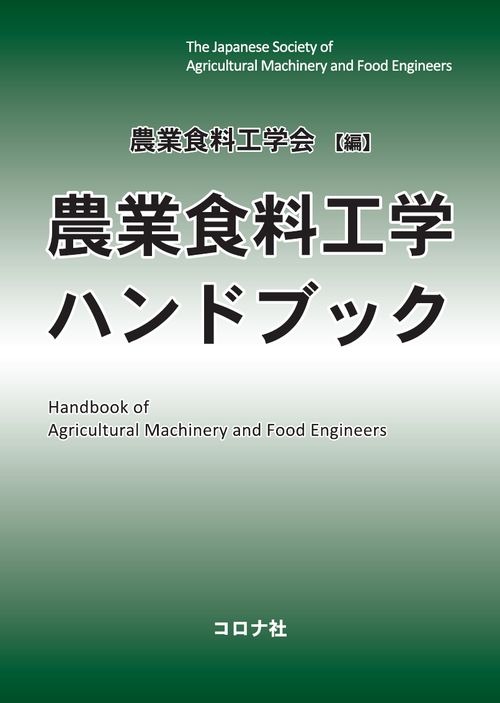
農業食料工学ハンドブック
詳細を見る
人間科学
音楽を聴いたとき,無意識に感動したことはないだろうか。多くの専門家によって感動の理由を説明する試みがなされてきたが,その答えは得られていない。そこで本書では,音楽が脳や身体に与える作用を脳科学と生理学から論じていく。
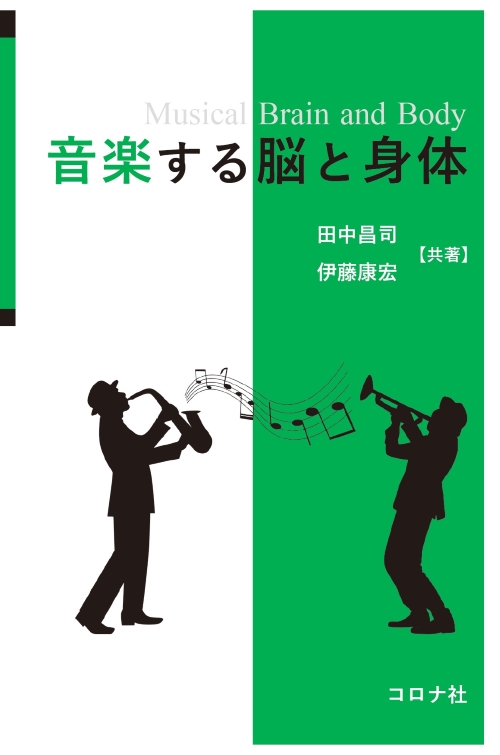
音楽する脳と身体
詳細を見る音楽家を対象に研究・講演などを行ってきた脳科学者が,脳のことをもっと知りたいと考える音大生・音楽家に対し,講義形式でわかりやすく解説した脳科学の入門書。脳科学の基礎事項からはじめ,音楽との関係について詳説する。
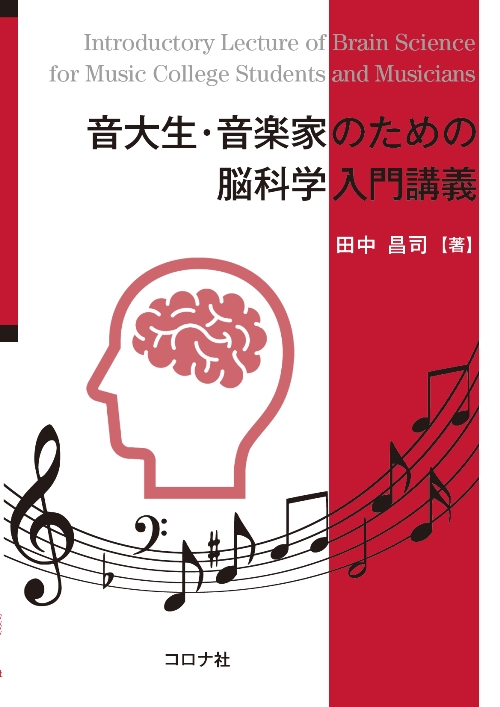
音大生・音楽家のための脳科学入門講義
詳細を見る心理学,脳科学,工学など幅広い分野での感性計測方法を紹介するとともに,筆者ならではのオノマトペ(擬音語・擬態語の総称)やさまざまな自然言語を活用した方法,さらに感性への深層学習適用と応用まで解説する。
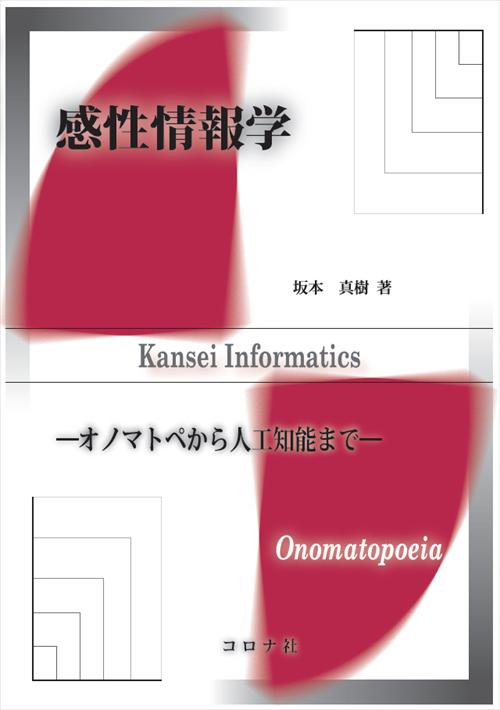
感性情報学
詳細を見る
- オノマトペから人工知能まで -本書は,文理系の大学生がはじめて脳科学および認知科学を学ぶ際の教科書を想定して執筆した。可能な限り図を多く掲載し,初学者でもわかりやすく,かつ教科書としての一定のレベルを保った専門的知識を提供する教科書となっている。
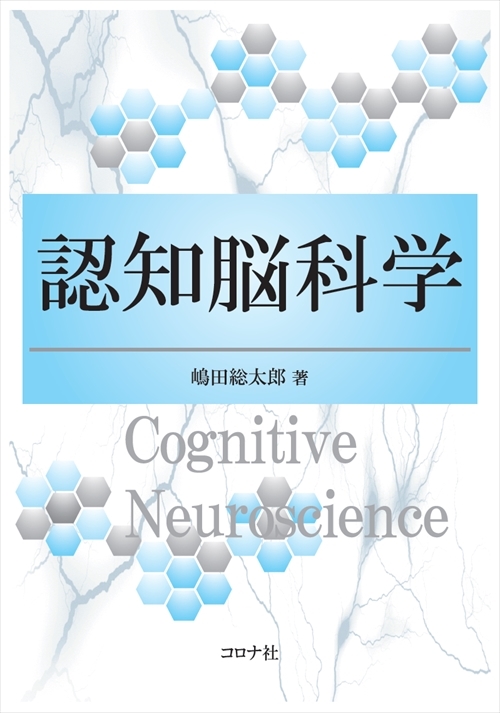
認知脳科学
詳細を見る
生活科学
機能性食品制度の概要にはじまり,栄養の基礎,機能性食品成分と疾病の関わり,機能性食品の課題と今後の動向を安全性と絡めて平易に解説。機能性食品を学ぶ学生,食品開発者はもちろん,一般消費者にも手に取ってほしい一冊。
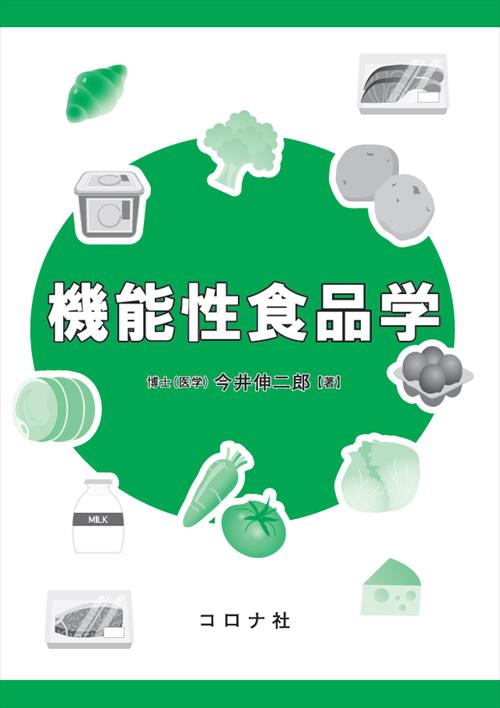
機能性食品学
詳細を見る
科学一般
プレゼンの効率的なやり方・具体的な事例に加えて,基本的な考え方:プレゼンリテラシーを解説する。心理学的背景に基づいて各プレゼン技術の「理由」を示すことにより,読者が良いプレゼンを行うための基礎をしっかり固める。
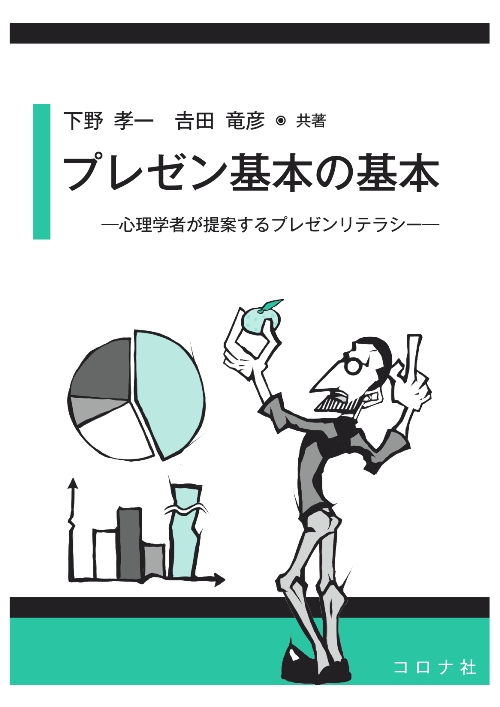
プレゼン基本の基本
詳細を見る
- 心理学者が提案するプレゼンリテラシー -本書は,工学系の大学・高専の学生がわかりやすく論理的な文章を書くための論文作成ガイドブックである。よい例,悪い例,改善例を示し,学生が陥りやすいポイントや技術文書特有の表現などを指摘する。卒論指導をする教員にも最適。
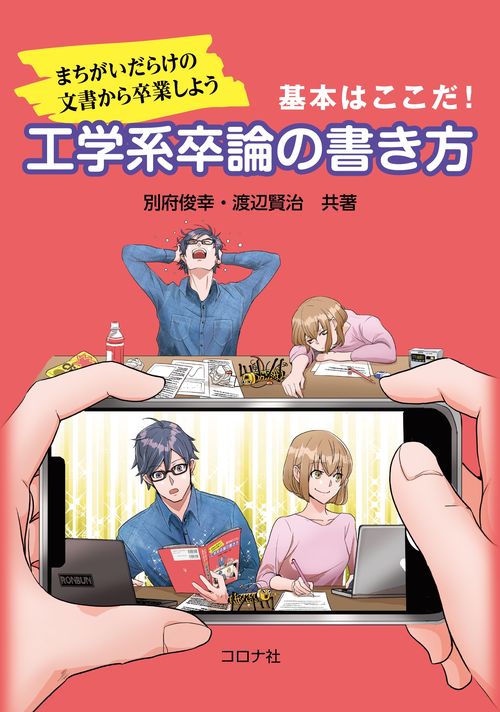
まちがいだらけの文書から卒業しよう-基本はここだ!-
詳細を見る
工学系卒論の書き方本書では「英語表現の上達にはネイティブスピーカーの文章をまねるのが一番」との考えの下,初級~中級・上級レベルまでのさまざまな英語表現を含む例文を多数収録。今よりワンランク上の技術英語を書きたい方の支援ツールとなる。
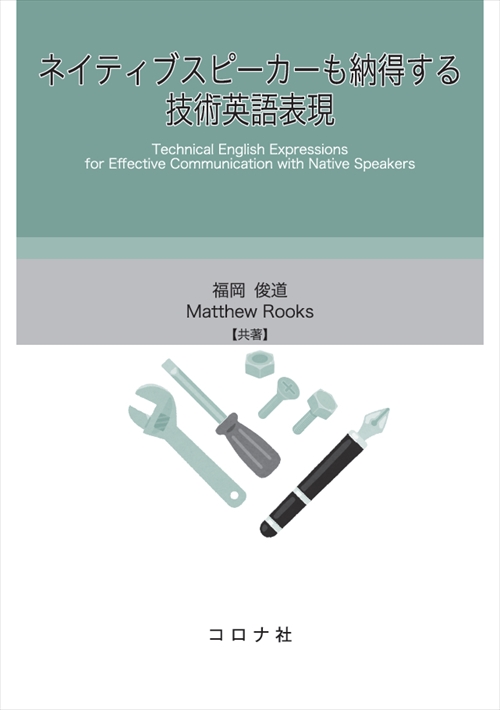
ネイティブスピーカーも納得する技術英語表現
詳細を見る学生達の何気ない会話を取り上げ,次に実際に彼らがおかした失敗,さらに著者自身が若手技術者時代におかした失敗の実例を紹介。「人のふり見て我がふり直せ」というように,擬似失敗体験で実際の場面での失敗防止に役立ててほしい。
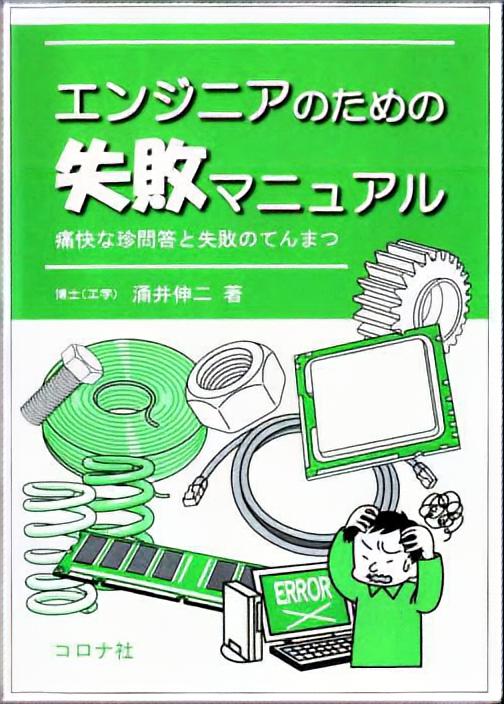
エンジニアのための失敗マニュアル
詳細を見る
- 痛快な珍問答と失敗のてんまつ -
資格試験
「一般計量士 国家試験」の専門科目である「計量に関する基礎知識」「計量器概論及び質量の計量」について第71回(令和2年12月実施)~第73回(令和4年12月実施)の全問題およびその解答,ならびに懇切丁寧な解説を掲載。
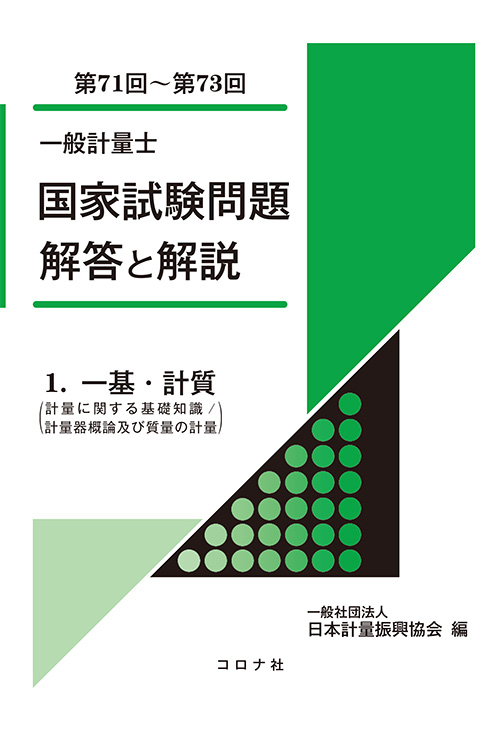
一般計量士
詳細を見る
国家試験問題 解答と解説
- 1.一基・計質(計量に関する基礎知識/計量器概論及び質量の計量)(第71回~第73回) -「環境計量士(濃度関係)国家試験」の専門科目「環境計量に関する基礎知識(化学)」「化学分析概論及び濃度の計量」の第71回(令和2年12月)~第73回(令和4年12月)の全問題とその解答,ならびに懇切丁寧な解説を掲載。
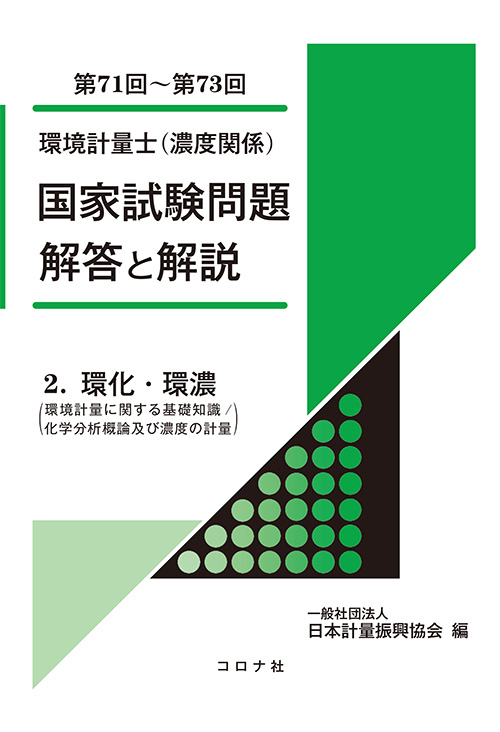
環境計量士(濃度関係)1
詳細を見る
国家試験問題 解答と解説
- 2. 環化・環濃(環境計量に関する基礎知識/化学分析概論及び濃度の計量)(第71回~第73回) -「一般計量士・環境計量士 国家試験」の共通科目である「計量関係法規」および「計量管理概論」について,第71回(令和2年12月実施)~第73回(令和4年12月実施)の全問題およびその解答,ならびに懇切丁寧な解説を掲載。
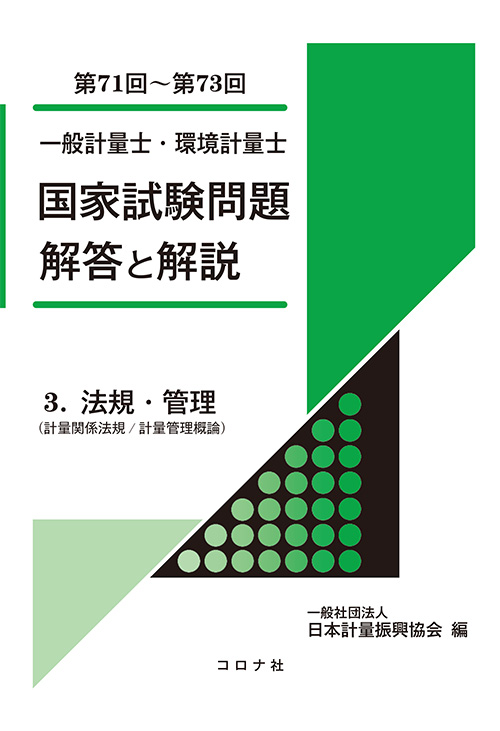
一般計量士・環境計量士
詳細を見る
国家試験問題 解答と解説
- 3. 法規・管理(計量関係法規/計量管理概論)(第71回~第73回) -環境計量士(濃度関係)国家試験の専門科目「環境計量に関する基礎知識(化学)」を分野ごとに体系的に解説。さらに平成24年度から令和4年度までのすべての問題(法規関係の出題を除く)を取り上げて詳細に解説。好評の第3版!
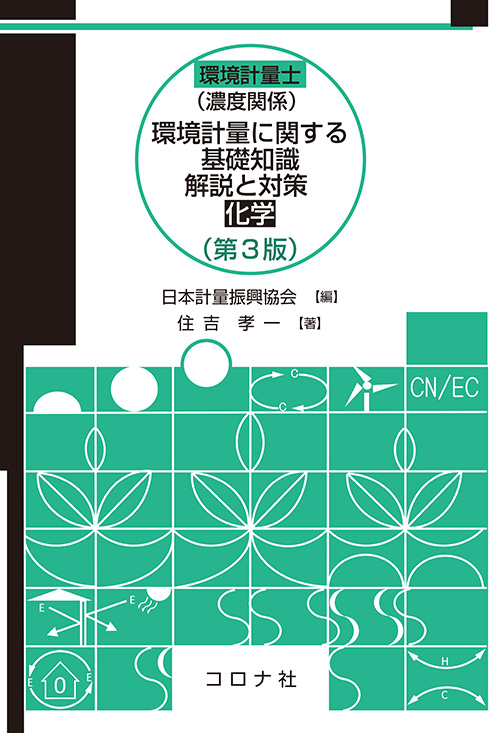
環境計量士(濃度関係)
詳細を見る
環境計量に関する基礎知識 解説と対策 (化学)
(第3版)