レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
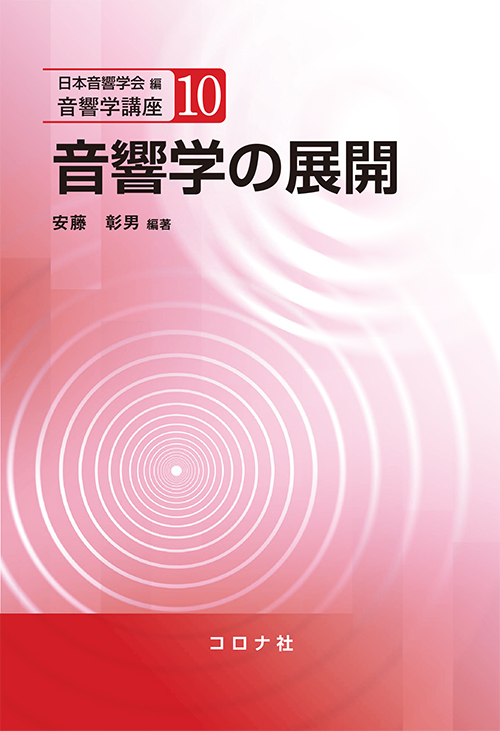
-
音響学講座 10
本書では,音響学における新分野(熱音響,アコースティック・イメージング,音バリアフリー,音のデザイン,音響教育,生物音響)を紹介することで,音響学の諸分野を俯瞰する。音響学の広がりや多様性を感じることのできる一冊。
- 発行年月日
- 2021/09/06
- 定価
- 4,620円(本体4,200円+税)
- ISBN
- 978-4-339-01370-2
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 N/M 様(ご専門:総合情報学(情報科学))】
掲載日:2021/08/26
本書は,音響学講座シリーズ(全10巻)最後の10巻目に位置する書籍で,音響学における新たな分野(熱音響,アコースティック・イメージング,音バリアフリー,音のデザイン,音響教育,生物音響)についての記述がなされている.なお,私自身,音響学に関する基礎知識は全くもっておらず,いきなり音響学の展開という応用から学習するという,少し変わった出会い方で本書をレビューしている.
本書の大きな特徴として,まず目についたのは,私が以前レビューさせていただいた『音響サイエンスシリーズ 22 音声コミュニケーションと障がい者』の時と同様,引用・参考文献の多さにある.各章50〜100近くも和書・洋書の書籍や論文が紹介されている.これだけの多くの引用・参考文献の多いものを情報科学の分野ではあまり目にすることがないため,言及されている内容にもしっかりと裏付けのなされた,本書に対する著者陣の本気度が本シリーズでも伺えた.
今回,私自身,第3章〜第5章を中心にじっくりと読んでみて,感じた点をレビューとして以下に挙げていく.
第3章では,音バリアフリーについて述べてある.音のバリアフリー・ユニバーサルデザインとは何かという考え方から,障がい者・高齢者支援,そして,音声分野,電気音響分野,聴覚分野,騒音・振動,建築音響の各分野での音のバリアフリーとは何かという考え方の解説から,具体的にどのようなバリアフリーの方法があるかなど,最新の研究成果(論文)をベースに数多く紹介されている.この章の参考文献として,私が以前レビューさせていただいた『音響サイエンスシリーズ 22 音声コミュニケーションと障がい者』も一緒に参照すると,理解が深まるようにも感じた.
第4章では,音のデザインについて述べてある.デザインと聞くと,美的センスが必要でアート(芸術)系の専門家が気にすることでは,と思われがちだが,音響学の分野でも音をデザインするとは,どういうことなのかという基本的なことから,音デザインの流れを,実際に使用されている身近な電車の駅構内の到着サイン音を例に,各項目で順番に分かりやすく記述されてある.第4章は,全体的に身の回りの身近な具体例が多く示されているので,読書ペースが比較的遅い私でも,スラスラ読むことができたので,音響学に関する知識がなくても読みやすいように感じた(特に,4.1節と4.2節が読みやすい!).
第5章では,音響教育に述べてある.聴覚訓練・聴能形成を,実際の大学での講義例をベースに解説してあるのでイメージがしやすかった.この章で私自身,一番興味深かったのは,「5.2音響e-Learning」及び,「5.3教育工学的手法の導入」である.本レビュー企画に応募したきっかけの一つでもある「e-Learning」という単語をみかけたので,目次を見たときから興味を抱いていた.なぜ興味があるのかを少し詳しく書くと,学生時代に,eラーニングやブレンディッドラーニング(以下,BL)に関する,選択科目「e-ラーニング概論」を履修していた(しかも2009年当時,日本における研究成果を取り入れた,日本で最初に出版されたブレンディッドラーニングに関する書籍(当時,日本においてはBLの翻訳書が一冊出版されているだけで,それを除く)も書かれた教育工学の専門家の講義)からである.このときは,あくまでも教職科目としてではなく,情報分野の中でも情報システムの一例としての内容だったと記憶している(だが,高等学校の情報B・Cの授業を設計するような課題はあったが・・・).「5.2音響e-Learning」では,このe-Learningを音響学の分野に適応し,シミュレータ教材にはどのようなものがあるかや,それらの教材を作成するにはどういった方法があり,どういった機能が必要になるか,などの概略が分かりやすく記述されている.「5.3教育工学的手法の導入」では,教育工学的手法による効果測定の方法論として,量的研究手法及び,質的研究手法について,それぞれの手法について解説した後,実際の研究事例もあり,理解がしやすかった.先ほど挙げた,選択科目「e-ラーニング概論」でも「学習の種類と学習効果の測定方法」として,習ったような記憶がうっすらあったが,その講義や書籍で割り当てられているページ数が少ないのと,当時の勉強不足もあり,深い意味が理解できていなかったと記憶している.だが本書籍での解説の方が,具体的で分かりやすく記述されていたので,知識の補完(アップデート)ができたように感じた.
最後に,本書は音響学の展開として,いろいろな分野での応用例についての研究成果などが,ある程度分かりやすく記述されてはいるが,少し駆け足気味(概論的)な部分も正直なところ存在するので,興味のある分野については,膨大な引用・参考文献や,音響学講座シリーズの別の書籍などを参考に,本書に挙げられたテーマを深く学ぶことができるだろうと思われる.









