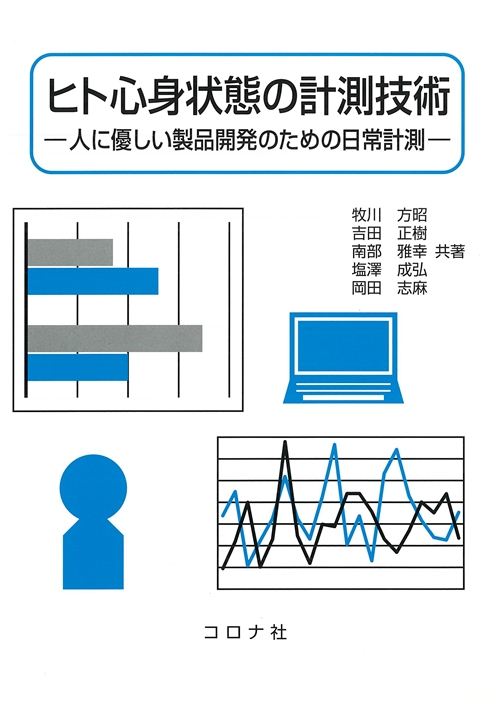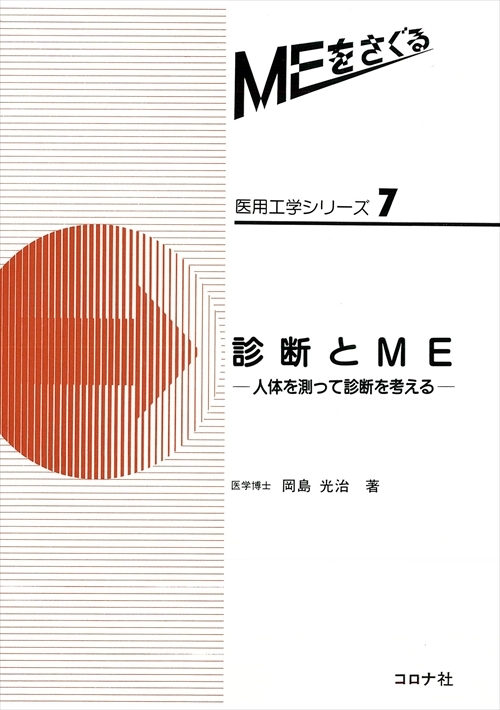
医用工学シリーズ 7
診断とME - 人体を測って診断を考える -
生体計測の意味,計測方法,計測値の処理・解釈,画像診断,患者監視,診断論理,病院情報システムなどについて,数式を一切使わず,しかし決してレベルは落とさずにわかりやすく記述。
- 発行年月日
- 1989/02/25
- 判型
- A5 上製
- ページ数
- 208ページ
- ISBN
- 978-4-339-07026-2
- 内容紹介
- 目次
生体計測の意味,計測方法,計測値の処理・解釈,画像診断,患者監視,診断論理,病院情報システムなどについて,数式を一切使わず,しかし決してレベルは落とさずにわかりやすく記述。
1. はじめに 計測ってなあーに?診断ってなあーに?
1.1 計測はサイエンスのはじまり
──17世紀の天才の教え──
1.2 oldとolderはどちらが年上か
──計画に関する「いろは」のい──
1.3 プロとは知識を数量で把握している人
──学生時代の恩師の教え──
1.4 -,+,■の表現も計測のひとつ
──数量化への努力のあと──
1.5 -(マイナス)は本当にゼロの意味か
──目的に添っての定義──
1.6 問診を客観評価に置き換える
──いろいろの考え方,やり方がある──
1.7 自覚症状の数量表現は可能か
──難しいが,まったくやれないわけではない──
1.8 二値表現しかできないもの
──中間帯がないのが条件──
1.9 何万個もあるものの取扱い
──苦労して数える意味ありや──
1.10 二値表現と数量表現のつながり
──客観化という意味では同じ──
1.11 観測と診断
──その功利性指向──
2. 正常値の概念 その考え方と実例
2.1 正常値とは?健康とは?
──統計よりも実利本位──
2.2 本人や社会に有益か有害か
──要治療と治療不要──
2.3 人並みに働ければ健康者
──作業仮説──
2.4 健康者群の選び方
──厳しさでなく寛容を──
2.5 健康の定義の修飾
──環境が人を変える──
2.6 老化は健康現象か
──万人の定め──
2.7 医療が変える健康の定義
──死ぬべき人が生きられる──
2.8 世の中によって健康度が変わる
──戦争と平和──
2.9 人工臓器をつけた健康者
──ひとつの考え方──
3. 人体の計測 生身を測る
3.1 生体のとらえにくさ
──人間,この不可思議なるもの──
3.2 計測値は変動する
──猫の目と秋の空──
3.3 生体が外へ出す情報をとらえる
──受動的人体計測法──
3.4 五感を助けるME機器
──千里眼や地獄耳──
3.5 生体が発するエレキをつかまえる
──出てくるものは何でも使え──
3.6 増幅器がない時代のME機器
──どうやってつかまえたのか──
3.7 真空管の登場
──医用電子時代のあけぼの──
3.8 電気信号計測は五感を圧倒する
──糸脈診断と心電図──
3.9 生体は磁気も出せば音も出す
──つかまえ方が難しい──
3.10 ぬくもり,動き,圧力を測る
──こんなものまで役立つのか──
3.11 生体に探りを入れる
──能動的人体計測法──
3.12 病院にサイクロトロンが必要になる
──短寿命同位元素への対応──
3.13 人体に電気を与える
──インピーダンス計測と電気刺激法──
3.14 神経を電気で突っつく
──筋肉や脳の検査にもなる──
3.15 体内の分子構成を探る
──形態どころか機能までわかる──
3.16 肺にたまったごみを計測する
──磁気を探る──
3.17 熱や光を生体に与えて測るもの
──使えるものは何でも使え──
3.18 テムズ川の流れは血管の流れに通ずる
──新“海国兵談”ME版──
3.19 検知器(センサ)と変換器(トランスデューサ)
──人体でいえば感覚器──
3.20 何もかも電気に換えて勝負する
──人体と同じやり方──
3.21 センサと生体の接点
──どこまで深入りするか──
3.22 音を電気に換える
──振動がエレキに換わる圧電現象──
3.23 光を電気に換える方法
──人工網膜を胃の中へ──
3.24 温度や圧力も電気に換わる
──いろいろな工夫──
3.25 バイオセンサ
──初耳だ,どんなものだい?──
4. 時間軸情報の描き方と診断 記録曲線の意味と取扱い
4.1 生体のサイクル
──人体のもつ第四の次元──
4.2 血圧の周期性
──秒単位から,年単位,生涯単位まで──
4.3 秒の長さをどうやって決めたのか
──心周期起源の仮説──
4.4 動物の種による心拍周期の違い
──生涯の心拍総数は同じになるか──
4.5 人間は太陽系の生物
──昼夜の生理周期──
4.6 生物時計はちょっぴりへそ曲り
──概日周期──
4.7 人体周期からみた週休制
──バビロニア王の先見か?──
4.8 時差ぼけのおこり方,防ぎ方
──東へ向かうより西へ向かえ──
4.9 性や発情の周期
──猫と人間の理性比べ──
4.10 人生ドラマの序幕からフィナーレまで
──生涯周期──
4.11 時間軸変動のつかまえ方
──周波数分析と標本化定理──
4.12 測定回数は多いほどよいのか
──目的をはっきりしよう──
4.13 早朝起床時の定時観測はどこまで意味があるのか
──その吟味──
4.14 ばらばらの時間軸曲線への対応
──定常性とエルゴード性──
4.15 時間軸曲線はいろいろな周波数の重なり合い
──主役,脇役,そして三枚目,四枚目──
4.16 隠れた周期を見つけ出す
──フーリエ分析とパワースペクトル──
4.17 益鳥を呼び入れ害鳥を追い払う
──瀘波による雑音除去──
4.18 瀘波にまつわる苦心談
──位相ずれをいかに防ぐか──
4.19 知恵を生かした瀘波
──ディジタルフィルタと同期平均加算──
4.20 アナログ信号をディジタル信号へ
──A-D変換とD-A変換──
4.21 分解能の横方向と縦方向
──標本の必要ビット数──
5. 画像情報の作り方と診断 “目に物を見せる”には
5.1 ひと目見ればわかる
──人間の視覚による診断──
5.2 小さいものを大きく見せる
──顕微鏡はME機器の元祖──
5.3 二頭立ての馬車
──形態診断と機能診断の助け合い──
5.4 眼光皮背に徹する
──X線診断──
5.5 死体解剖より前に体内がわかる
──神様への一歩接近──
5.6 影絵から横断図へ
──人体輪切りの奇術:CT──
5.7 よしの髄から体内をのぞく
──内視鏡でどこまでも──
5.8 体の中へ電子の目
──絵が大幅にきれいになる──
5.9 山彦で人体を探る
──超音波は真直ぐ進む──
5.10 超音波診断で何がわかるか
──腹を探られても痛くない──
5.11 血流,血圧,心筋梗塞を音で探る
──最近のトピックス──
5.12 銀粉保存から鉄粉保存へ
──フィルムから磁気媒体への代替り──
5.13 ディジタル画像方式の優位性
──アナログ時計とディジタル時計の差──
5.14 フィルムや記録紙との訣別
──PACSの誕生──
5.15 画像のきめの細かさはどのくらい?
──空間的解像度──
5.16 時間軸曲線も画像へ仲間入り
──医用画像総合システム──
5.17 診療録情報も一緒にしては
──病院情報システムとの統合──
5.18 医用画像の外部貸出し
──個人携帯の医用画像電子手帳,PHD──
5.19 診断画像の保存は必須か
──そうだ!本当にそうか?──
5.20 診断画像は報告書の付録
──専門家と非専門家の立場──
5.21 専門家にとっても画像保存は必須か
──その理由を問いたい──
5.22 画像はなくなってもよい?
──心電図診断の立場──
5.23 他の画像も保存不要にならないのか
──考え方と努力目標──
5.24 やはり画像は残したい
──左脳の判断と右脳の直感──
5.25 画像は脇役,主役は報告書
──本文と挿絵の関係──
5.26 ハイテクノロジーの出現
──倹約の要は減ったが努力は必要──
6. 患者の連続監視 寸時も目を放さない観察
6.1 生死の境目を救う
──診療設備を集中した病室──
6.2 片時も目を放さない診療
──観察・測定頻度の集中──
6.3 機器とスタッフの重装備
──CCUとICU──
6.4 少数病床で短期間回転
──最小経費で最大効果を──
6.5 孔という孔へチューブを入れる
──全身状態の監視と治療──
6.6 生体連続監視の項目
──まず生命徴候(バイタルサイン)を見張る──
6.7 自動監視の効率の悪いもの
──困ったときは人頼み──
6.8 異常が発生しやすい項目に重点を
──CCUとICUのねらいの差──
6.9 一般病棟での集中治療・連続監視
──病院全体のCCU・ICU化──
6.10 連続監視は自動化でやりたい
──人間ではお手上げ──
6.11 誤警報を減らす血の努力
──イソップの教えを生かしたい──
6.12 ボタンひとつで経過が目の前へ
──監視データ保存・表示システム──
6.13 健康なあなたにも心臓モニタ
──携帯形心電図連続監視システム──
6.14 “監視”というからには,その場で処理を
──時計ばかりがコチコチと──
6.15 ちょっと待てば結果がわかる
──心電図実時間処理連続監視システム──
6.16 たまってからやるより,ためる前に処理せよ
──マイコン内蔵方式──
6.17 警告が自動化なら対策も自動化で
──監視・判断・処置のトリプルプレイ──
6.18 先輩に見習う
──ペースメーカや内蔵式除細動器の心電図監視──
6.19 合従連衡で命を救う
──内蔵式CCUへの夢──
6.20 すでに動いている自動化・ICU
──全部がコンピュータ,人間は監督──
6.21 人体の閉回路制御の代行
──ICU・CCUは一種の人工臓器──
6.22 監視という言葉の意味
──もう一度強調しておきたい──
6.23 コンピュータに命を預ける
──どこまで許されるのか──
6.24 外来患者の多項目生体監視
──3時間待ち・3分診察が理想になる──
6.25 多項目監視は外来でもやっている
──運動負荷試験の実例──
7. 診断の論理 病気の見立ての筋道
7.1 診断学の教科書を斬る
──川崎病に例をとる──
7.2 記述のあいまいさ
──肯定と否定の同居──
7.3 前世紀からの診断論理
──疑徴,半確徴および確徴──
7.4 白か黒かの判別方式
──枝分かれの論理──
7.5 問題点解決の工夫
──わずかな差異の取扱い──
7.6 コンピュータでの枝分かれ処理
──真理値表とブール代数──
7.7 黒白ではなく灰色の濃淡で決める判別方式
──確率による手法──
7.8 尤度とベイズの式
──もっともらしさ,確からしさの比較──
7.9 多次元情報空間の考え方
──病気の群在を星雲と見る──
7.10 多次元で見てどこまで確からしいか
──確率密度関数──
7.11 多次元空間方式のメリット
──不自然な区分けをしない──
7.12 パラメータの分布は本当に分離しているのか?
──大きな疑問──
7.13 それでもなお血圧で診断を決めているのは何故?
──簡易性と有用性──
7.14 予後こそ診断の目標
──医学と医療の違い──
7.15 結局はそろばん勘定で診断・治療を決めている
──診断の合目的的性──
7.16 費用と効果のバランス
──どうやって計算するか──
7.17 予後関数を中心とした診断法
──診断名はあえて必要としない──
7.18 病名診断法と予後関数診断法の関係
──成人病医療への新しい取組──
7.19 病気の大区分,小区分,徴分
──診療上の便宜をねらう──
7.20 人工知能による診断法
──コンピュータが人間の頭を代行──
8. 病院・医院の情報システム化 効率と精度の向上を目指して
8.1 患者情報の収集・処理と生体制御
──病院・医院でやっていること──
8.2 医療はすべて情報業なり
──ME学の立場での定義──
8.3 四次産業としての医療
──人類社会の新しい分野──
8.4 患者が来院してから帰途につくまで
──情報の流れ──
8.5 いちばん普及している分野
──医療事務システム──
8.6 検査室全体のコンピュータ管理
──まとめて面倒をみる──
8.7 検査を実施し報告する
──能率向上と精度保証──
8.8 病院から伝票を追放しよう
──部門間連絡システムの導入──
8.9 コンピュータ化部門間連絡の御利益
──間違い防止と診療スムーズ化──
8.10 いつまで残るのか,紙と手書き
──コンピュータ化進展度の判定法──
8.11 自由記載の文章もコンピュータへ
──定型化法やPOMRの活用──
8.12 紙のカルテは結局無くなるのか?
──臨時には有ってもよいし,必要──
8.13 個人面接方式か,見掛けの聖徳太子方式か
──専用と時分割の2方法──
8.14 中央集権と地方分権の得失
──経費と開発所要期間と有用度──
8.15 群雄割拠から幕府ピラミッド体制へ
──時代の流れ──
8.16 みんなで使えば安くなる
──電話線利用の方式──
8.17 小病院・医院のコンピュータ化
──バイクを買うより安くできる──
8.18 電話でお知恵拝借
──他人様のコンピュータが使える──
8.19 医用データベースとネットワーク
──宝島と航海図──
8.20 個人携帯の健康データベース
──ICカードと光カード──
8.21 自動化検診システム
──定期健康診断のコンピュータ化──
8.22 医療のマスプロ流れ作業
──能率向上と精度確保──
8.23 医療のコストベネフィット
──お金を有効に使う診断法──
8.24 胃集団検診は引き合うか
──数千万円で命を拾う──
索引