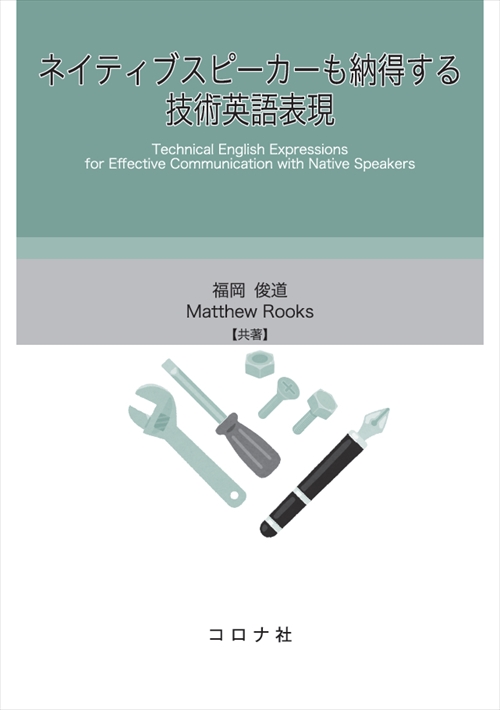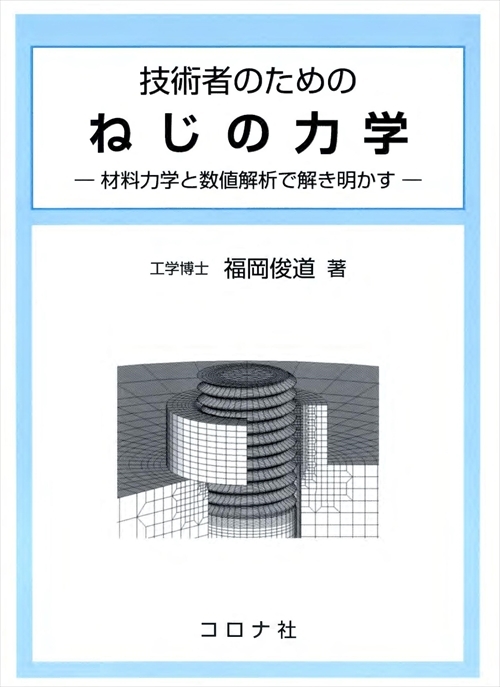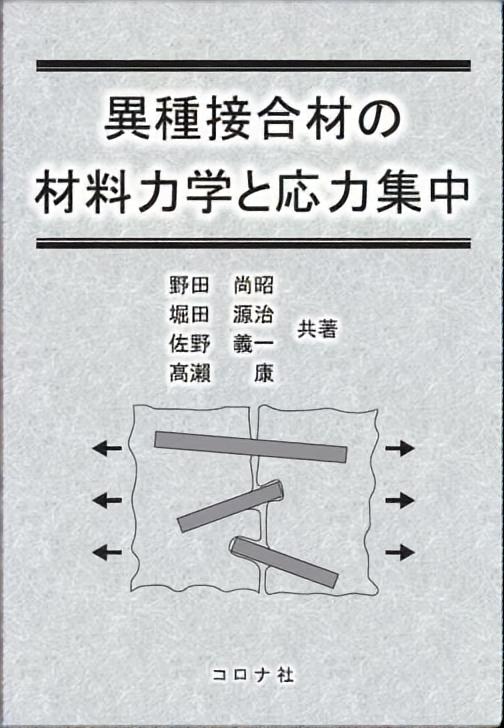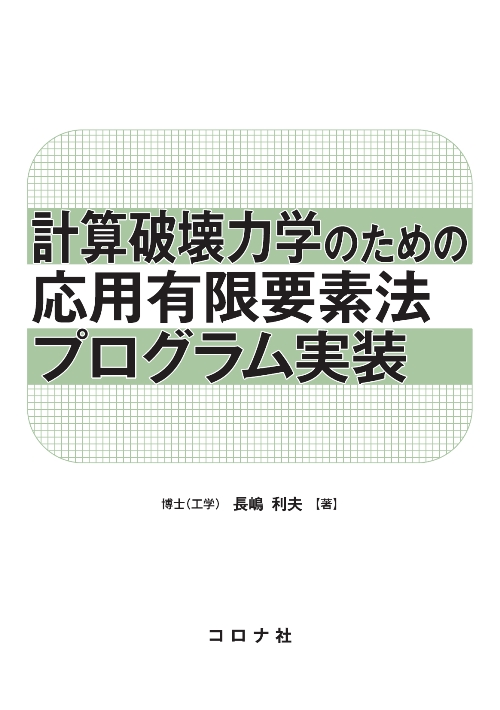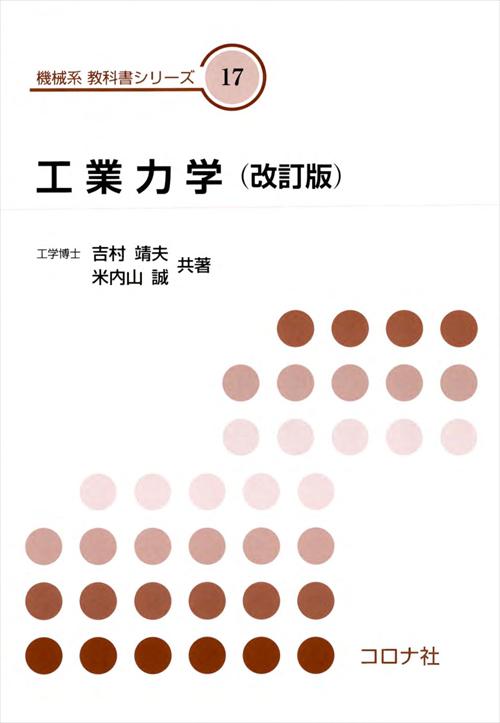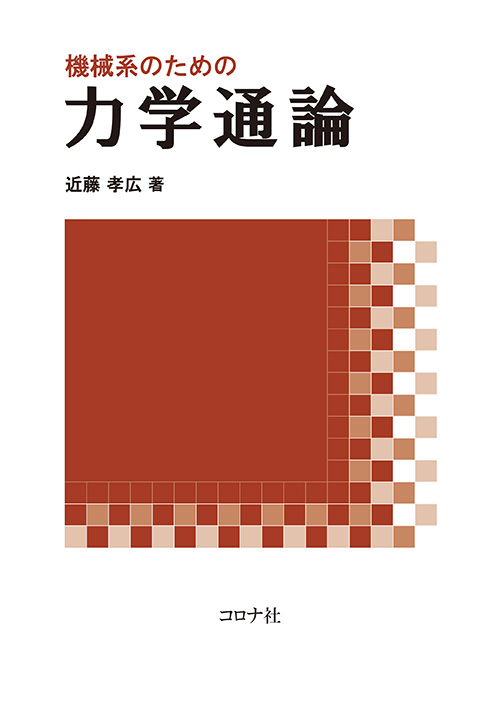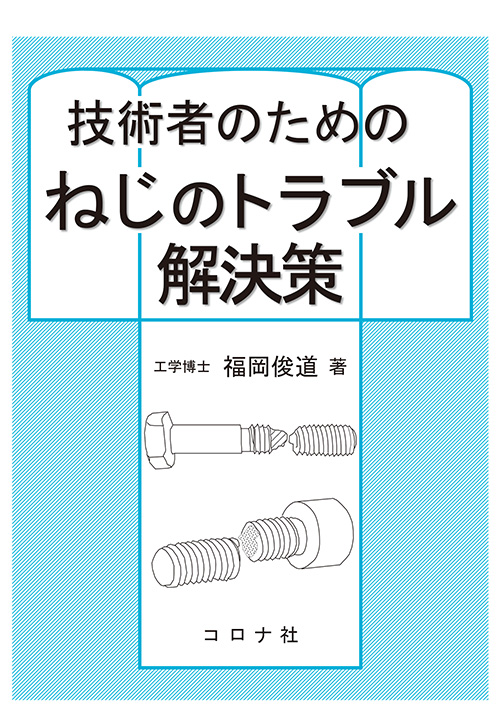
技術者のための ねじのトラブル解決策
ねじの三大難問である「確実な締め付け」,「ゆるみの防止」,「疲労破壊の防止」を解決!
- 発行年月日
- 2025/11/20
- 判型
- A5
- ページ数
- 296ページ
- ISBN
- 978-4-339-04698-4
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- レビュー
- 書籍紹介・書評掲載情報
- 広告掲載情報
【読者対象】
ねじ締結部の強度設計、締結作業の工程設計等の業務を担当し、ねじの三大難問である「確実な締め付け」、「ゆるみの防止」、「疲労破壊の防止」に関連する問題の解決方法、あるいは具体的なヒントを必要としている技術者を対象としています。
【書籍の特徴】
ねじの「ゆるみ」と「疲労破壊」は二者択一的に発生するのではなく、いずれもボルトの軸力不足で発生しているケースが多い。それを具体的な事例を通して説明し、もっとも有効な解決策が「高い精度で締め付ける」であることを、信頼できる研究成果に基づいて平易に解説しています。また、実際に発生したねじのトラブルの事例紹介、技術者が共通して抱く疑問(いわゆるFAQ)に対する回答を通じて、読者各位が対象としている締結部に関する問題の解決策やヒントを提供することを目的としています。
【各章について】
第1章では、他の機械要素との比較を通して、ねじのトラブル解決の難しさを説明しています。第2章では、「確実な締め付け」、「ゆるみの防止」、「疲労破壊の防止」について詳しく解説しています。第3章では、ねじ締結部の設計に必要な基礎事項をまとめています。第4章では、ゆるみと疲労破壊を防ぐための基本である「確実な締め付け」について、トルク法を中心に詳しく解説しています。軸力のばらつきの軽減方法、動力式レンチ/インパクトレンチを使用したときの問題、締結部の検査方法についても解説しています。また、トルク法と回転角法を組み合わせた高精度締め付け方法を紹介し、焼き付きの問題も取り上げています。第5章では、ねじのゆるみを「回転ゆるみ」と「非回転ゆるみ」に分けて解説しています。前者については、有限要素解析によりそのメカニズムを明らかにし、後者については、ボルト軸力低下量の計算方法を説明し、それぞれ具体的な防止策を詳しく説明しています。第6章では、ねじの疲労破壊のメカニズムの説明に続いて、ねじ固有の疲労強度特性、ボルト締め付け線図の問題点を解説し、有限要素解析により求めたねじ谷底の応力振幅に基づいて、具体的な防止策を示しています。最後に、具体的な事故例の解説を通して、理解を深めるように構成されています。4~6章には、読者の理解を深めるために、多数の事例紹介とFAQが関連箇所に配置されています。
【読者へのメッセージ】
ねじの三大難問である「確実な締め付け」、「ゆるみの防止」、「疲労破壊の防止」は、一見独立した問題のように見えますが、実際は三位一体といっても差し支えがないほど密接に関連しています。本書では、その中で一番上流側にある「確実な締め付け」を達成することにより、「ゆるみ」と「疲労破壊」に起因するさまざまなトラブルが防止/解決できることを、多数の事例や具体的な数値を用いて平易に解説しています。
【本書のキーワード】
確実な締め付け、ゆるみの防止、疲労破壊の防止、トルク係数、摩擦係数のばらつき、締結部の剛性、へたり、座面陥没、回転ゆるみ、非回転ゆるみ、熱膨張、界面の離隔、応力振幅
ねじは,あらゆる工業製品の組み立てに使用されていることから,産業の塩と呼ばれている。塩はヒトの生命を維持するために不可欠な物質であるが,普段その存在が意識されることはない。人間生活に深く溶け込んでいるという点で,ねじと塩は似た者同士といえる。一般にねじの存在が意識されるのは,大きな事故やトラブルの原因となったときである。たった1本のねじが壊れただけで,どうしてこんなことになるのか。ずっと昔から使われているのに今さらこんな事故が起きるなんて…そんな非難が飛び交う。
エンジニアリングの分野において,ねじは「機械要素」として分類されている。しかし,歯車や軸受など他の機械要素に比べて,製造されている数は圧倒的に多い。したがって事故率で考えると,母集団が大きいねじは決して危険な機械要素ではない。とはいえ,そんな言い訳はねじに関わる仕事に従事している技術者にとって意味のないことであり,事故やトラブルを零にする,あるいは限りなく零に近づけることが強く求められている。ねじが抱える本質的な問題として,他の機械要素に比べて作用する荷重の種類が多く,さらにそれらが複合的に作用するケースが多い点が挙げられる。同じ寸法・材料・強度のボルトであっても,使用する場所によって引張り,曲げ,せん断,ねじりなど,荷重形態が大きく異なることがある。ある締結部で使用して問題のなかったボルトが,使用箇所が変わった途端にトラブル発生の原因となった事例も多い。
ねじ部品には,JISで規定されたボルト・ナットのように汎用性が高いものから,製品の一部にねじを加工して提供されるケースも多い。わが国のねじ製造業者の数は千を超えるといわれており,さまざまなニーズに応えるために,いろんな形状のねじ部品が日々製造されている。その結果,製品の高性能化の代償として,ねじが関連する事故やトラブルの形態は多様化し,撲滅が困難な状況となっている。
昨今「失敗学」という言葉をよく耳にする。失敗の原因を究明して,同じ過ちをくり返さないための方策を求める新しい研究分野である。ねじに関する二大トラブルは,「ゆるみ」と「疲労破壊」である。産業革命以来発生した膨大なねじのトラブルについて,原因を究明してその防止策を考案し,知識として広く提供する。もしそんなことが実現していれば,ねじに関するトラブルは大幅に減少していたと考えられる。実現できなかった最大の原因は,知識の共有が困難なためである。社会的に問題となった事故やトラブルを除いて,原因の詳細が公表されることはほとんどない。ましてや製造現場のトラブルであれば,ほとんどの場合,社内の取り組みとして対応するため,ノウハウが外に出ることはない。
2015年にコロナ社から発行した拙著『技術者のためのねじの力学』は,著者の予想をはるかに超えてご愛読いただいており,そのことがきっかけとなって,ねじのトラブルに関する相談が以前よりも増えた。それらの中には,比較的簡単に解決策を提供できるものから,こんなことが起こるのかと思われるような事象も少なからずあった。それらの中で一般性のある事象については,その後研究テーマとして取り組んだこともある。以上のような経験を積み重ねた結果から,ねじの二大トラブルである「ゆるみ」と「疲労破壊」は,「確実な締め付け」によってかなり回避できるという結論に至った。
そこで本書では,ねじ締結部の強度設計や組み立て工程の考案などに携わる技術者を対象として,ねじの三大難問である「確実な締め付け」,「ゆるみの防止」,「疲労破壊の防止」を解決するために,実際のトラブル事例を交えながら,関連する理論を平易に解説し,実務に役立つ知識を提供することを目的としている。また本書の特徴として,実際に相談を受けたトラブルなどの中で,一般性のある事象については〈事例研究〉,質問が多い事象についてはFAQ(frequently asked questions)として,関連する節や項で取り上げている。
2025年9月
著者
1.ねじの歴史と役割
2.ねじの三大難問とは?
2.1 三大難問は三位一体?
2.2 確実な締め付け
2.3 ゆるみの防止
2.4 疲労破壊の防止
3.ねじ締結部設計の基礎
3.1 ねじの規格
3.1.1 JIS規格とISO規格
3.1.2 ねじの基準山形
3.1.3 ねじ山のらせんとリード角
3.1.4 ねじの呼び径とピッチ
3.1.5 並目ねじと細目ねじ
3.1.6 ねじの条数
3.1.7 ねじ部品の非相似性
3.1.8 ねじ部品の使い方
3.1.9 ボルト・ナットの形状と座面面積
3.2 締結部の界面と座面面圧
3.2.1 被締結体寸法と界面の面圧分布
3.2.2 ナット座面とボルト頭部座面の面圧
3.3 ねじの剛性
3.3.1 ねじの剛性と締め付け過程の力学特性
3.3.2 一次元ばねモデルによる剛性評価
3.3.3 はめあいねじ部とボルト頭部の等価長さ
3.3.4 被締結体の寸法と剛性
3.3.5 複雑な形状の被締結体の剛性評価
3.3.6 締め付け方法と締結部の力学特性に対する剛性の影響
3.4 ねじ締結部の接触面剛性
3.4.1 表面粗さと接触面剛性
3.4.2 接触面剛性の評価方法
3.4.3 法線方向と接線方向の接触面剛性
3.5 ねじ部品材料の力学特性と熱特性
3.5.1 ねじ部品の材料
3.5.2 炭素鋼系材料の強度と粘り強さ
3.5.3 ステンレス鋼系材料
3.5.4 アルミニウム合金
3.5.5 チタンとチタン合金
3.5.6 非鉄金属製ねじの注意点
3.5.7 各種ねじ部品材料の力学特性と熱特性
4.確実な締め付けへの挑戦
4.1 各種締め付け方法の特徴
4.1.1 トルク法
4.1.2 回転角法
4.1.3 張力法
4.1.4 熱膨張法
4.2 締め付け方法の選択において考慮すべき因子
4.2.1 軸力の大きさとボルトの呼び径・材料・本数
4.2.2 呼び径の大きさと締め付け方法の選択
4.2.3 締結部の寸法と締め付け方法の選択
4.2.4 締結部材料の強度とヤング率
4.2.5 軸力精度と締め付け方法の選択
4.2.6 作業性と締め付けコスト
4.3 トルク法
4.3.1 締め付け原理とトルク-軸力関係式
4.3.2 トルク-軸力関係の簡易式
4.3.3 締め付け過程に及ぼす摩擦係数の影響
4.3.4 トルク係数とねじ面/ナット座面の摩擦係数の測定方法
4.3.5 事例で学ぶ~締め付け関連のトラブルと対策~
4.3.6 平座金の使用による締め付け精度の向上策
4.3.7 ナット座面/ボルト頭部座面の平面度と締め付け精度
4.4 動力式トルクレンチによるボルトの締め付け
4.4.1 動力式トルクレンチの締め付け特性
4.4.2 反トルクによるボルト軸部の接触
4.4.3 ボルト軸部の接触による軸力低下
4.5 インパクトレンチによるボルト締め付け
4.5.1 インパクトレンチの基本的な締め付け特性
4.5.2 締結部剛性と衝撃摩擦係数の影響
4.5.3 締め付け条件,締結部形状と打撃回数の関係
4.6 トルク測定を基準とした締結部の検査方法
4.6.1 代表的な検査方法の概要
4.6.2 各検査方法の特性評価
4.6.3 トルク測定による評価試験
4.7 弾性域回転角法
4.7.1 締め付け原理
4.7.2 適用範囲と締め付け指針
4.8 張力法
4.8.1 締め付け原理と有効張力係数
4.8.2 表面粗さと着座トルクの影響
4.8.3 適用範囲と締め付け指針
4.9 熱膨張法
4.9.1 締め付け原理
4.9.2 簡易解析による温度分布とボルトの伸びの計算
4.9.3 適用範囲と締め付け指針
4.9.4 ボルトヒータを横置きにした締め付け
4.10 トルク係数のリアルタイム計測による高精度ボルト締め付け
4.10.1 締め付け原理
4.10.2 締め付け装置の試作とボルト軸力測定実験
4.10.3 適用範囲の可能性と締め付け指針
4.11 多数ボルトの締め付けと弾性相互作用
4.11.1 ボルトの逐次締め付けと弾性相互作用
4.11.2 締結部形状の影響
4.11.3 管フランジの締め付けとボルト軸力のばらつき
4.12 締め付け最大の難問「ねじの焼き付き」への挑戦
4.12.1 実験による焼き付き現象の検証
4.12.2 焼き付きと真実接触面積,表面粗さ,うねりの関係
5.ねじのゆるみ防止への挑戦
5.1 ゆるみとは何か?
5.2 塑性変形からゆるみへ
5.3 回転ゆるみ ~ねじ部品の戻り回転によるゆるみ~
5.3.1 回転ゆるみが発生しやすい荷重形態
5.3.2 耐ゆるみ性能の評価方法
5.3.3 ユンカー型ゆるみと大型車の車輪脱落事故
5.3.4 ユンカー型ゆるみの発生メカニズム
5.3.5 回転ゆるみの防止策
5.4 非回転ゆるみ ~戻り回転なしに軸力が低下するゆるみ~
5.4.1 非回転ゆるみの発生メカニズム
5.4.2 へたりによる軸力低下量の推定
5.4.3 へたり量の推定
5.4.4 非回転ゆるみの軽減策
5.4.5 熱膨張差によるゆるみ
6.ねじの疲労破壊防止への挑戦
6.1 ねじが壊れるメカニズム
6.1.1 ねじの塑性変形と疲労破壊
6.1.2 回転ゆるみ・非回転ゆるみ・塑性変形から疲労破壊へ
6.1.3 締め付け時のねじの強度
6.2 ねじ部品の応力集中
6.2.1 ねじ山荷重分担率と応力集中
6.2.2 ねじ谷底に沿った応力分布
6.2.3 本体側はめあいねじ部の応力集中
6.3 ねじ固有の疲労強度特性
6.3.1 金属疲労とS-N曲線
6.3.2 ねじの疲労強度に影響する因子
6.3.3 外力の作用形態と応力振幅
6.3.4 被締結体界面の離隔と応力振幅
6.4 ねじの疲労強度の各種評価方法と問題点
6.4.1 ボルト締め付け線図の概要と問題点
6.4.2 軸対称有限要素解析によるボルト締め付け線図の検証
6.4.3 曲げモーメントの作用による界面離隔現象と応力振幅の関係
6.4.4 ねじの疲労強度と応力振幅の推定方法
6.4.5 有限要素法によるねじ部品に発生する応力振幅の解析方法
6.5 有限要素解析によるねじ谷底に沿った応力振幅の評価
6.5.1 ボルト・ナット締結体の応力振幅と疲労破壊
6.5.2 本体側はめあいねじ部の応力振幅と疲労破壊
6.5.3 ねじ谷底まわりの塑性変形の影響
6.6 実機における疲労破壊・疲労強度評価から学ぶ
6.6.1 ジェットコースター車軸のねじ部の疲労破壊
6.6.2 フランジ形軸継手用ボルトの疲労破壊
6.6.3 遠心力が作用するボルト締結体の疲労強度
6.6.4 大型車の車輪脱落事故 ~ゆるみと疲労破壊は表裏一体~
6.7 ねじの疲労強度の向上策
6.7.1 締め付け条件
6.7.2 ねじ部品
6.7.3 締結部形状と外力の作用点
6.7.4 運転時に発生する塑性変形の抑制
6.7.5 回転ゆるみの防止と非回転ゆるみの抑制
あとがき
引用・参考文献
索引
読者モニターレビュー【 製品設計者 様 (業界・専門分野:製造業(輸送機器部品))】
本書は、ねじの基礎的な内容から実務で直面するトラブル対策まで幅広く網羅されており、設計者にとって実用性の高い一冊だと感じました。各章では、図やグラフに加え、FEM解析結果も多用されており、文章だけでは理解しにくい現象も直感的に把握できます。特にグラフは多水準で整理されており、各因子の影響度合いが視覚的に分かりやすい点が印象的でした。全体を通して、著者の長年にわたる研究に基づく知見が随所に感じられ、理論的な裏付けを重視する技術者にとって有益な内容だと思います。
読者モニターレビュー【 忠地 俊明 様 株式会社CPM (業界・専門分野:ねじ商社)】
『技術者のためのねじのトラブル解決策』は、技術書でありながら読み物としても成立した稀有な一冊である。著者があとがきで「書物」という語を用いるように、本書は単なる参考書や解説書ではない。読者がこれまで蓄積してきた知識を呼び起こし、問題に向き合う姿勢を自然と促してくれる点に、その特徴がある。また、ねじを単体要素ではなく「ねじ締結体」として捉え、トラブルの本質を“予張力の破綻”として整理する構造は、設計者のみならず不良・不具合対応に携わる者にとっても極めて実践的な視座を提供する。締付け、緩み防止、疲労破壊という工程に分解しつつ、原理原則の重要性へと立ち返らせる本書は、解析技術が高度化する現代においても揺るがない思考基盤を与えてくれる。ねじ締結の構造理解を深めたい者はもちろん、未然の防止策を設計に込めたい人や、ねじ締結トラブルの低減を願う人まで、ねじを扱うすべての人に強く薦めたい一冊である。
amazonレビュー
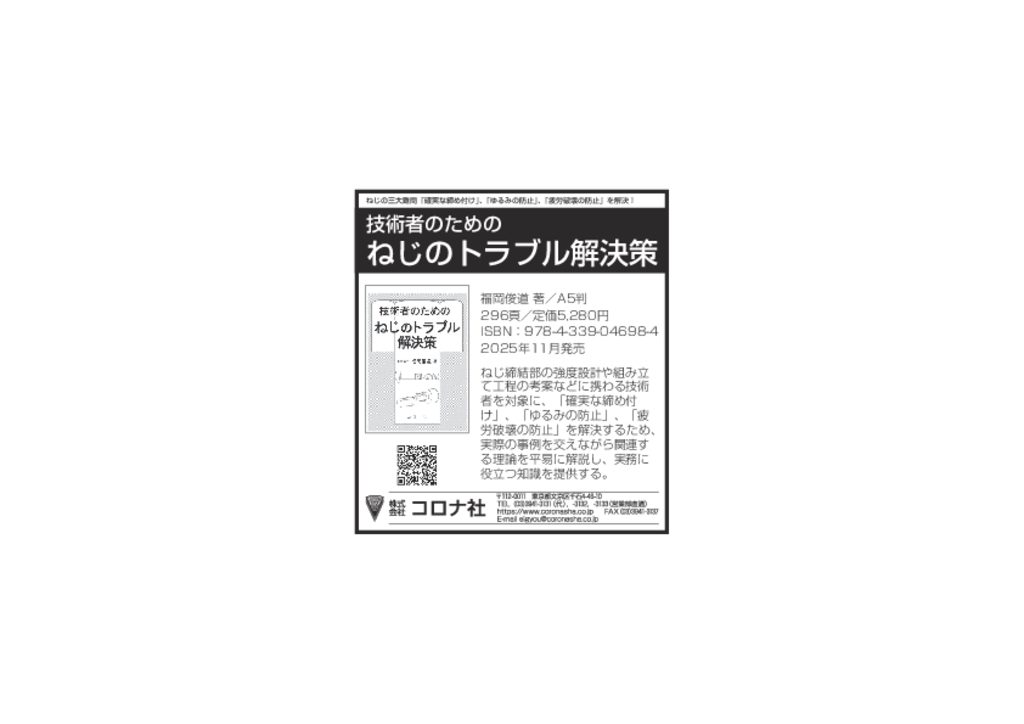
-
掲載日:2025/11/03
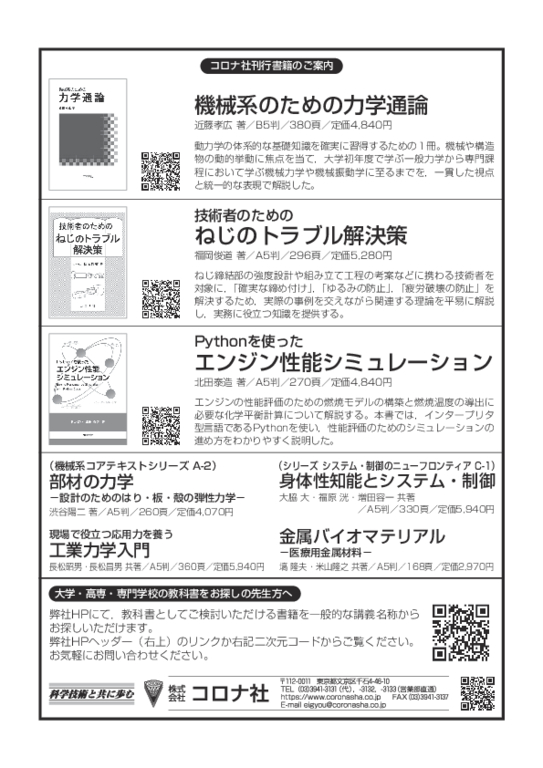
-
掲載日:2025/11/01
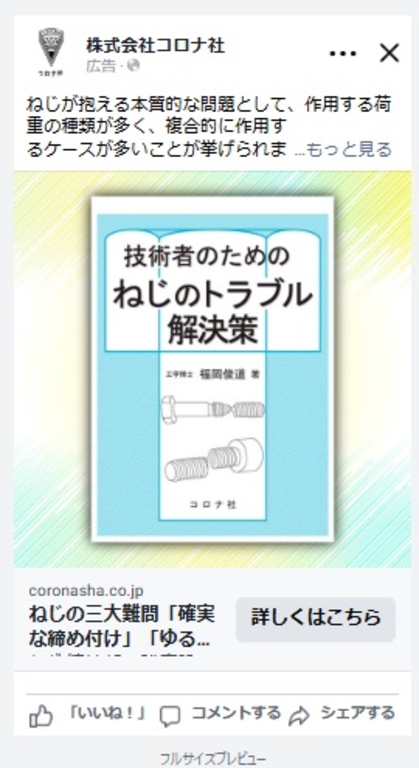
-
掲載日:2025/10/30