レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
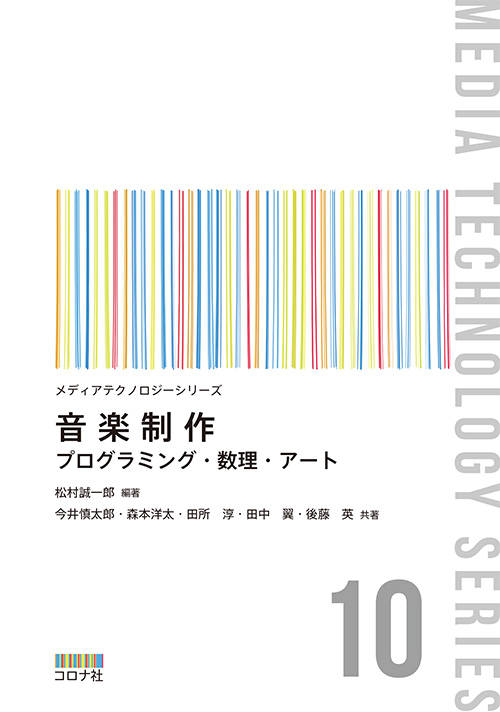
-
AIの登場以前から用いられてきた音楽制作の技法にはじまり,プログラミングで音楽や音響を作り出す手法,作曲や音列の生成を数理の面から捉える分野,音を軸としたメディアアートなど,第一線で活躍の執筆陣が幅広く解説する。
- 発行年月日
- 2025/04/25
- 定価
- 4,840円(本体4,400円+税)
- ISBN
- 978-4-339-01380-1
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 Gg 様(業界・専門分野:録音)】
掲載日:2025/06/03
本書は、電子楽器を初めとするテクノロジーを用いた音楽表現について、わかりやすく、詳細に記された1冊である。
全体的に、この分野では、日本語での書籍や情報が少ないと感じることが多い。その中でも本書はタイトルにある通り、音楽制作を中心にテクノロジーの歴史から、プログラミングの実例、作品例を、日本語で取り上げた良書である。
構成として、初めには音楽用語の解説、テクノロジーを用いた作品や歴史など、時系列順で記載されており、多少の知識があれば、一部だけを読んでも出来る内容となっている。さらに、適宜、図や画像があるためソフトなどの詳細な違いの理解などがしやすい。
ライブエレクトロニクス上演のプロセスや、コードの例、環境構築なども記載されており、座学的要素のみならず、実践に役立つ内容も豊富である。
特に私の場合、セリー音楽のような数学的側面の強い作曲技法について、あまり理解していなかったものの、本書の詳細な解説は、理解に非常に役立った。
DAWやPd、Maxの概念についても丁寧に説明がされており、且つ冗長では無い。簡潔にまとまりながらも、充実した内容であるため、初学者からメディアアーティスト、研究者まで、読者の程度を問わず勧めたい書籍である。特にPdやMaxを初めて扱う学生などには強く勧めたい。
-
読者モニターレビュー【 ミヤザキリョウ 様(業界・専門分野:音楽アート・商業音楽・ソフトウエア開発(アプリ・webなど))】
掲載日:2025/05/16
本書は、Music Tracker、Max、PureData、SuperCollider、TidalCycles などの多様なツールをはじめ、無調音楽の作曲技法(数理的な視点からのアプローチ)、さらにはメディアアートに至るまで、「特定の表現による音楽制作」を主題として取り上げた意欲的な一冊である。
各分野の第一線で活躍する研究者および表現者たちによって執筆されており、内容は極めて前衛的かつ挑戦的である。
本書の特徴として、歴史的背景や代表的な作品例に関する丁寧な解説が随所に盛り込まれており、「技術」と「芸術」という二つの観点から情報が体系的に整理されている点が挙げられる。その結果、専門的な内容でありながらも、読者にとって理解しやすい構成となっている。
ライブコーディングに関する章では、プログラミング言語や開発環境を通して音楽を理論的・構造的に捉え、従来のDAWでは実現が困難であった複雑な処理や即興的な実験が可能となる点が強調されている。環境構築の手順やサンプルコードも豊富に掲載されており、実践的なガイドとしての価値も高い。
取り上げられている各ツールは、それぞれ明確なコンセプトを持ち、Sonic Pi や PureData など、オープンソースかつ無償で利用可能なものも含まれている。読者が興味を持ったものをすぐに試せるよう配慮されており、研究者・実践者双方にとって有益な設計となっている。
個人的に印象深かった一言は、「Show us your screen(スクリーンを見せろ)」というスローガンである。これは制作過程そのものを可視化し、プロセスの価値を共有するという思想を象徴しており、音楽表現における透明性と即興性への新たな視点を提示している。
従来のDAWや楽器による音楽制作に限界を感じている読者にとって、本書で紹介される多様な「表現」の技法は、既存の枠組みを問い直し、創造性を再活性化させる契機となり得るだろう。
音楽制作に対して、より科学的・実験的な姿勢で向き合い、自身の表現世界を深化させたいと考える読者に、強く推奨される一冊である。
-
『DTMステーション』にて対談記事として「音楽制作」を紹介いただきました。
掲載日:2025/05/12
-
読者モニターレビュー【 ルミナス 様(業界・専門分野:音楽、メディア・アート、映像)】
掲載日:2025/04/28
本書は多様なメディアテクノロジーの視点から音楽制作を論じており、著者陣には研究者とクリエイターの双方が名を連ねるため、記述が具体的で非常に興味深い。特に第3章「音響コンポジション」と第6章「メディアアートとミュージックテクノロジー」では、QRコードを通じて実際の音楽作品を視聴できる点が魅力的だ。中でもソニフィケーションの位相空間を視聴覚化した作品『x/y』(3.3.12) は、音の方向や位置を体感的に理解でき、文字情報だけでは得られない発見がある。どの章もテクノロジーが切り拓く音楽の新たな深淵を示し、何度も読み返したくなる一冊である。
-
読者モニターレビュー【 imdkm 様(業界・専門分野:ポピュラー音楽)】
掲載日:2025/04/17
音楽制作をめぐるテクノロジーは音楽のあり方そのものを大きく変化させるものである一方、「新しいテクノロジーが新しい音楽をつくる」という幻想が先走ってしまうこともしばしばあります。また、そうした議論の際にとりあげられるテクノロジーが、端的にいえば楽器産業やソフトウェア産業が売り出す特定のプロダクトにかたよりがちなことも非常に多いと思います。もちろんそうした市場に流通するようなプロダクトの歴史を追うことも興味深いですが、本書は音楽制作に用いられるテクノロジーをより俯瞰的に捉える具体的な事例が豊富に集められています。
個人的な関心からいえば、第一章でデモシーンに出自をもつミュージック・トラッカーについて少なくない紙幅が割かれている点が興味深いものでした。なんらかの音楽的な教育を受けていなくても音楽を制作することができるようになったことはテクノロジーの恩恵の最たるものですが、そこで DAW やワークステーション、グルーヴボックスといったいわば「主流」のソフトウェア/ハードウェアではなく、むしろトラッカーに着目する視点は示唆に富むものでした(私自身が長年のトラッカーユーザーというバイアスもあるかもしれませんが)。
作曲と音響の制作の境界が相対化された20世紀以後の視座を概観しつつ SuperCollider による音響プログラミングを紹介する第三章や、ライヴコーディングの歴史とプログラミング環境の具体的な紹介が簡潔にまとまった第四章(動画で見られるライヴコーディングによるパフォーマンスの具体例が紹介されているのもうれしい)なども、実際の音楽制作にも活かせる具体的な知見が多く、参考になりました。
参考文献等も含め、折をみて参照する書籍になりそうです。
-
読者モニターレビュー【 nasu 様(業界・専門分野:メディアアート(サウンド))】
掲載日:2025/04/15
本書を通して電子音楽の制作ツール各種、具体的な創作手法や発想(黎明期~現代)を網羅的に知ることができます。特に、プログラミング言語やロボット工学を活用してのライブ作品については、さまざま作品例や表現・技術上の課題点まで比較して見ることができます。
制作ツールに初めて触れる場合にも概要を辿りやすく、より素早く各々の興味へ発展させられるかと思います。また自身のように、メディアアート創作に直感的なプロセスを求めるばかりでなく、数理音響やプログラミングによる精緻なサウンド設計に関心を寄せる方にも、広く勧めたい一冊です。
-
ゲームメーカーズ 様による本書プレゼントキャンペーン
掲載日:2025/04/01
詳細はリンク先をご覧ください。
記事題名:音楽制作にまつわるテクノロジーの隆盛や、多彩な音楽表現について論じる書籍『音楽制作 – プログラミング・数理・アート –』、コロナ社より4/8(火)に発売









