レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
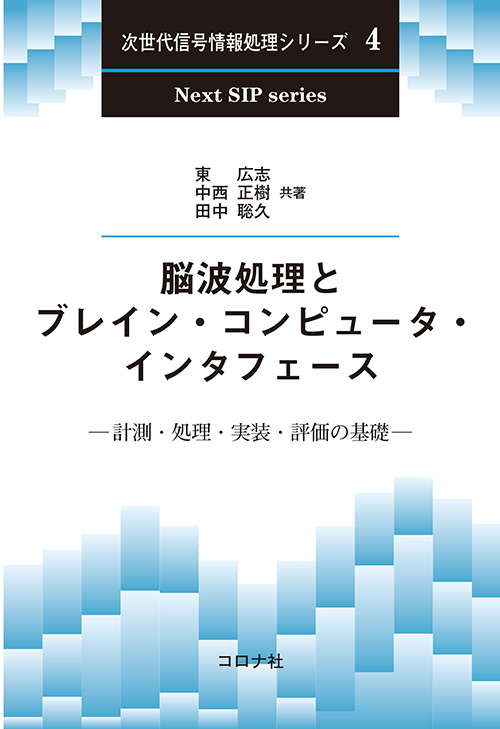
-
脳波処理とブレイン・コンピュータ・インタフェース - 計測・処理・実装・評価の基礎 -
人間の意図または意図のために生成した脳活動を脳計測によって読み取り,本人の意図を外部へ伝達する技術であるブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)のタスク・刺激と出力の関係(パラダイム)や信号処理を解説した。
- 発行年月日
- 2022/10/20
- 定価
- 3,630円(本体3,300円+税)
- ISBN
- 978-4-339-01404-4
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 N/M 様 (ご専門:総合情報学(情報科学) )】
掲載日:2022/10/14
本書は,次世代信号情報処理シリーズ(全17巻)の4巻目に位置する書籍である.本巻では「脳波処理とブレイン・コンピュータ・インタフェース」について,脳科学及び,脳内の信号処理の分野についての記述がなされている.
第1章では,ブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)とブレイン・マシン・インタフェース(BMI)の用語の呼び方の違い(各学問領域における,呼び方の傾向)の話から始まり,用語の定義から紐解かれてゆく.その後,歴史的な背景や,研究対象である"脳"の構造,BCI/BMIの基本構造・分類,脳波を利用することの利点,データを習得した後の処理・信号処理・パターン認識部を実装するために必要なソフトウエアの紹介などについて解説されている.開発環境については,昨今の人工知能技術の流行や,今年2022年4月からの新(教育)課程の高等学校情報科目である『情報Ⅰ・同Ⅱ』の中で扱われているプログラミング言語の一つとしてPythonが挙げられる.このPythonのライブラリであるNumpyやScipy,Scikit-learnなどを用いれば,容易にデータ解析できる点も興味深いのではないだろうか.また,あまり馴染みがないかもしれないが,PsychoPyという心理物理実験のための視覚刺激作成のためのPythonのライブラリも存在しており,Python学習への動機づけや応用としても身近に感じることができるのではないだろうか.
第2章では,BCI/BMIを学ぶ上で必要となる数学的な説明を概論的に解説がなされている.より詳しく知りたい方は,本シリーズの1巻である「信号・データ処理のための行列とベクトル
- 複素数,線形代数,統計学の基礎
-」(https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339014013/)を参考にすると,より理解が深まるだろうと思われる.
第3章では,「脳波計測」,第4章では,「前処理と特徴抽出」について解説された後,第5章では,BCI/BMIの開発において,インタフェースとしての性能を上げるのが目的だが,その開発したBCI/BMIの性能を評価する方法論について解説がなされている.ここまででBCI/BMIの開発における共通の基本的なことが述べられている.
第6章〜第8章では,『事例として取り上げなかった脳波応答の処理・識別や,将来的にBCIにおける有効性が新たに認識されるだろう脳波の応答を処理・認識する際にも,ベースラインとして必ず役に立つ』とまえがきにもある通り,今後研究が進むに連れ必要となってくる最先端技術についても触れられている.なお,これらの章は,それぞれの章が独立した形で記述されている点と,第1章(,第2章の数学的な内容は必要と興味に応じて),第4章〜第5章を一読されていることを前提に記述されている点は少し注意されたい.









