レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
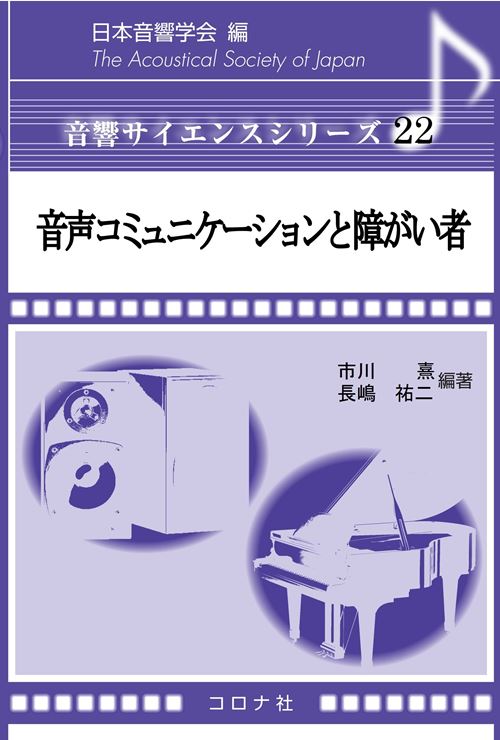
-
音響サイエンスシリーズ 22
コミュニケーション手段として研究が最も進んでいる音声の知見を手掛かりに,手話や指点字などと音声を横断的に分析し,コミュニケーションを支えている重要な機能を明確にする。その上で負担の軽い支援法を実現する手掛かりを示す。
- 発行年月日
- 2021/07/30
- 定価
- 3,740円(本体3,400円+税)
- ISBN
- 978-4-339-01342-9
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
「読売新聞」夕刊READ&LEAD(2021年10月19日)
掲載日:2021/10/19
-
読者モニターレビュー【 ノリ 様(ご専門:情報学・手話言語機械翻訳)】
掲載日:2021/08/06
手話、触手話、指点字、点字を「コミュニケーション方法」の観点から統一的に取り扱っている珍しい本でした。
大まかな障碍特性(難聴・ろう・吃音・手話吃音・弱視・盲・盲ろうなど)をベースにこれらのコミュニケーション方法を取り上げ、丁寧に解説されています。
また、脳損傷ろう者の手話や吃音と手話吃音の類似性や先天全盲ろう児への教育事例など、他書ではあまり見かけないトピックが散りばめられていて、広く勉強になります。
一点、本書執筆時期の兼ね合いもあって手話機械翻訳の話題が既に古くなっている気はしました。
Transformer周りは研究スピードが凄く速いので致し方ない気はします。
深層学習のお気持ちが分かる方で興味があればarXiv(https://arxiv.org/)で「sign language translation」や「sign language generation」と調べてみてください。
-
読者モニターレビュー【 K 様(ご専門:感情認識)】
掲載日:2021/07/26
本書籍では様々な種類の障がいと障がいを持つ方々を助ける技術についての解説・現在の研究の動向についてまとめられています.私は本書籍を通して,音声のみならず,手話や触覚言語など様々なモダリティのことばを介したコミュニケーションとその課題について理解できました.また,取り上げる障がいの対象が広いため,障がいや障がいを持つ方々のコミュニケーションを助けるために求めることを知る最初の書籍として最適ではないかと思います.私はコミュニケーションを助けるための研究に取り組んでいるため,その開発に生かすことができるヒントが多く,非常に勉強になりました.
-
読者モニターレビュー【 N/M 様(ご専門:総合情報学(情報科学))】
掲載日:2021/07/26
本書は,タイトルにもある通り,音響サイエンスシリーズの22冊目の書籍で,音・声に関する学問領域である「音響学」と「音声学」,特にその中でも,障がいという「福祉」の分野についての記述がなされている.
本書の大きな特徴として,まず目についたのは,引用・参考文献の多さにある.各章50〜100近くも和書・洋書の書籍や論文が紹介されている.これだけの多くの引用・参考文献の多いものを情報科学の分野ではあまり目にすることがないため,言及されている内容にもしっかりと裏付けのなされた,著者陣の本書に対する本気度が伺えた.
本書の構成としては,まず第1章で「障がい」の種類や「ことば」に求める条件などを福祉・言語学の立場から詳しく記述されている.第2章以降で,本書のタイトルにもある,「音声コミュニケーションと障がい者」について,これらに関連する各種,用語の定義,歴史的背景,研究成果などの内容が分かりやすく記述されている.
それに加えて,本書が発売される2021年現在,新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の流行もあり,どうやって福祉の分野では支援していくべきかという課題が「あとがき」にも述べられている.
ここで全ての章について述べると,膨大な文書量になるため,個々については挙げないが,その中でも私が気になった部分をいくつか紹介する.
私自身,音響・音声学,福祉の分野に関しては完全に素人なので,情報科学に関連する項目について,「2.2音声合成および音声認識技術の概要とAI技術」では,音声合成・認識技術やAI(人工知能)技術や,音声ディープラーニング(深層学習)などのおなじみに専門用語が出てくるので,情報科学の分野の方には馴染み深いのではないかと思う.「2.3音声技術による支援の例:構音障がい」では,音声技術による支援の例も紹介されていたりと,ICTを用いた障がい者支援のシステムや,アプリケーションを構築しようとする方(特に,本書の守備範囲である音・声に関連するもの)にも,バックグラウンドの知識として,この節だけでなく,本書全体を通して,参考になることも多いのではないと読んでいて思った.
また個人的には,「2.1.5 言語障がい,吃音」,「3.4吃音」についても,大変興味深かった.以前,福山雅治,藤原さくら主演の連続ドラマ「ラヴソング」(フジテレビ系列,2016年4月〜6月期)にて,「吃音」という障がいについて初めて知った(簡単にあらすじを書いておくと,『ある出来事をきっかけにミュージシャンの神代広平(役:福山)は臨床心理士として働きだす.カウンセリングを受けに来た少女・佐野さくら(役:藤原)は吃音症で吃音を気にして周囲の人とうまくコミュニケーションがとれないが,好きな歌を歌う時だけは吃音が出ない.彼女が歌う歌を聞き,その美声と才能に気付いた広平は,さくらの才能を花開かせたいとの思いから諦めかけていた音楽への情熱が湧き上がり,音楽を通じて2人は心を通わせて行く』という内容).本書では,吃音についての研究成果などが分かりやすく記述されてある(本書と直接関係はないが,本書で学んだ後で,連続ドラマの方も視聴すると,吃音という障がいについて,考えるきっかけにもなるとも思った).
最後に,本書は,いろいろな音と障がいについての研究成果などが,ある程度分かりやすく記述されてはいるが,若干,駆け足気味で概論的な部分も存在するので,膨大な引用・参考文献を参考に,興味のある分野については,音響サイエンスシリーズの別の書籍や,関連する他書を読んだりWebページで調べることにより,本書に挙げられたテーマを深く学ぶことができるだろうと思われる.









