レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
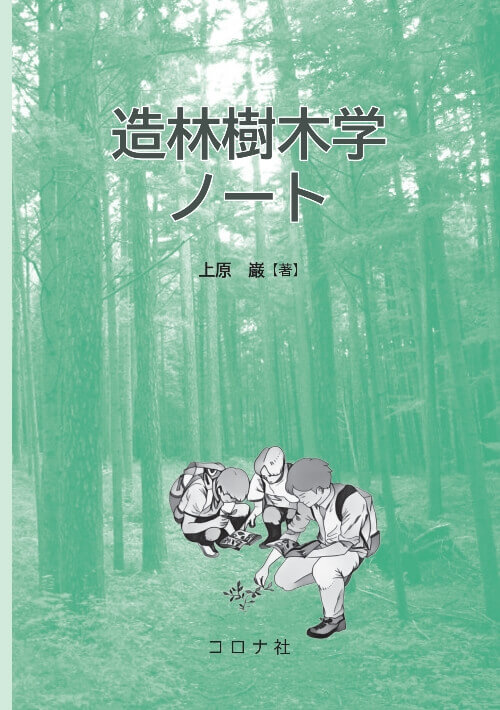
-
「適地適木」という言葉が示すように,各樹木には個性と適地がある。本書は,日本の代表的な造林樹木の特徴、成長特性、そして相性を生かしたこれからの造林,森づくりを行うために必要な知識を得られる一冊である。
- 発行年月日
- 2021/04/12
- 定価
- 2,420円(本体2,200円+税)
- ISBN
- 978-4-339-05276-3
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
amazonレビュー978-4-339-05276-3 造林樹木学ノート
掲載日:2022/02/10
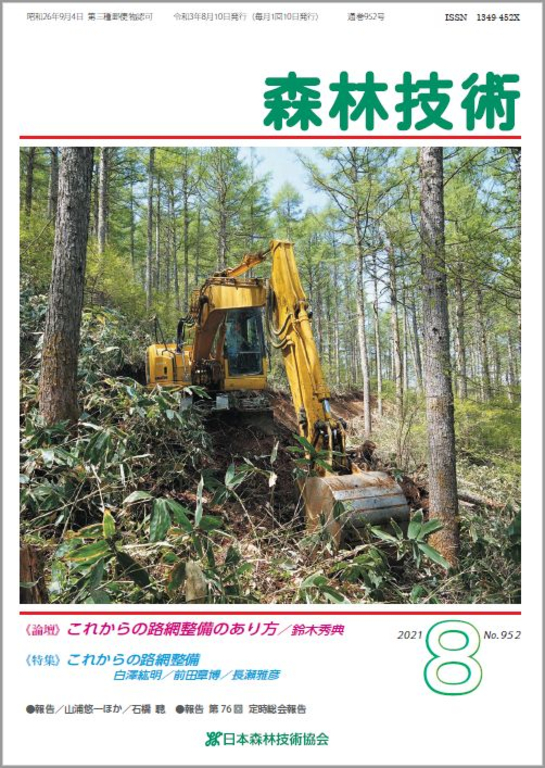
-
「森林技術」No.952(一般社団法人日本森林技術協会 会誌)
掲載日:2021/08/16
「森林技術」No.952内の「本の紹介」にて,東京大学 齋藤暖生先生に書評いただきました。
民族生物学(ethnobiology)という分野がある。民族学・文化人類学から派生した一分野で,身の回りの生物を人々はどのように認識し,つきあっているのかを読み解こうとするものである。本書は『造林樹木学ノート』という名のとおり,造林対象となる樹木の解説に主眼があるが,私は,民族生物学の視点から興味深く読んだ。つまり,日本人が造林という行為をするにあたって,その対象となる樹木の特性をどのように評価し,造林上の工夫を凝らしてきたのか捉え直すことができる書物でもあるからだ。例えば,「なぜスギを植えるのか」と問われたとき,どう答えるだろうか?「スギ材の市場が確立されているから」というのはすぐ思いつく答えの一つだろう。これに対し本書は,スギ材の持つ特性まで掘り下げて解説し,スギが木材として確固たる評価を得ている理由を理解させてくれる。さらに,葉の用途なども紹介し,造林がより有利な営為となるようなヒントも示してくれる。
“人にとっての”という視点から樹木の特性をまとめて解説してくれる書物は,意外と少ない。本書の内容は,造林学を学ぶ人に限らず,森に関わる全ての人にとっての「教養」となるようなものだと思う。ぜひ,さまざまな立場の方に,手にとってもらいたい。ただ,本書での解説につまずきを覚える人もいるかもしれない。というのも,大学の専門課程で学ぶ用語が多く使われているが,その説明があるわけではないからである。用語辞典などを傍らに「教養」を深めてもいいだろうし,わからないままにしていても樹木の特性に関する知識は十分に得られることだろう。
巻末では,樹形と数学の関係など,著者らしい独特の切り口が展開されている。自然に潜む不思議を素直に感じ,知ることの喜びを教えてくれる本でもある。そういう心を忘れずに,森と付き合っていきたいものだ。
(東京大学/齋藤暖生)
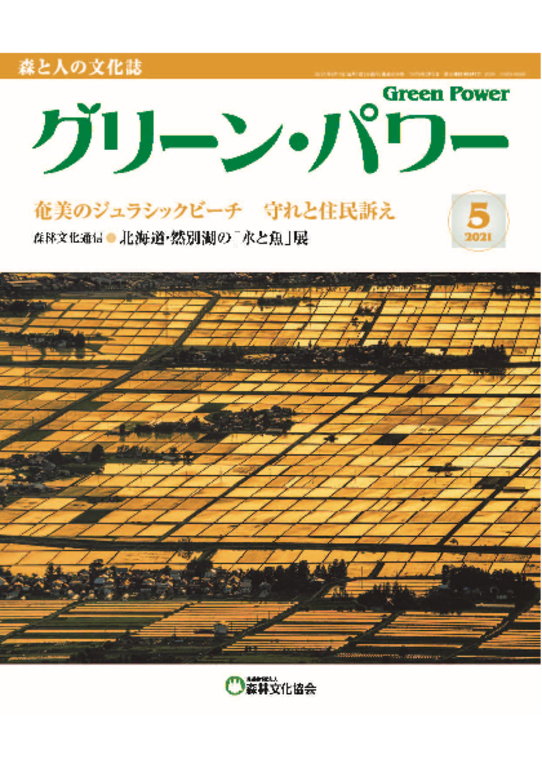
-
「適地適木」の造林に親しむ 『グリーン・パワー』2021年5月号(公益財団法人 森林文化協会)
掲載日:2021/05/01
人間の個性を活かす「適材適所」と同様に、樹木にもその個性を活かす「適地適木」という言葉がある。造林・森づくりでは、各樹木の特性と相性を考えることが基本だ。しかし従来の人工造林では樹木の特性を見ず機械的に、あるいは前例を踏襲する形で林木を植栽することも多い。これからは人工造林だけではなく、自然散布の樹木の「人工更新+天然更新」を合わせる手法が重要になると説く。
本書は、森林科学を学ぶ大学生向けの教科書だが一般の方でも読みやすい。外国語を学ぶ際に単語ノートを増やすように、森林科学のどのテーマにも共通する造林の単語、つまり各樹木の特性を再考し、親しんでもらうのが狙いだ。
日本の代表的な造林樹種であるスギが実は、恐竜の時代から生き残る「未分化の古代樹種」であること、森林を研究する際には数学的な視点が欠かせないことなど、様々なうんちくも楽しめる。 (編集部)
※誌面PDFをこちらからご覧いただけます。









