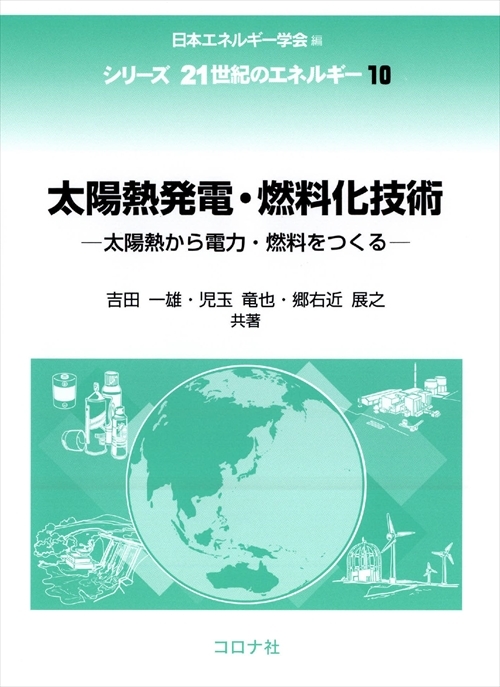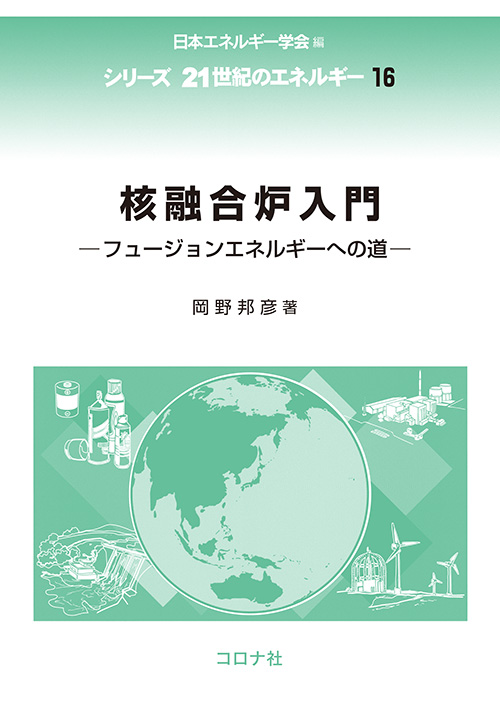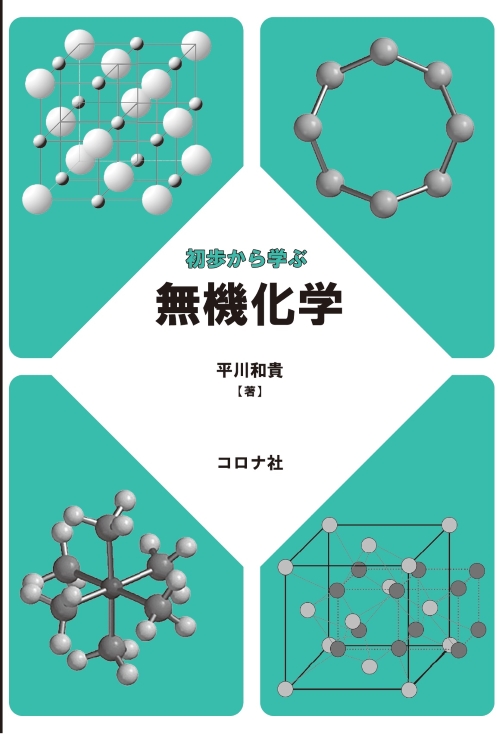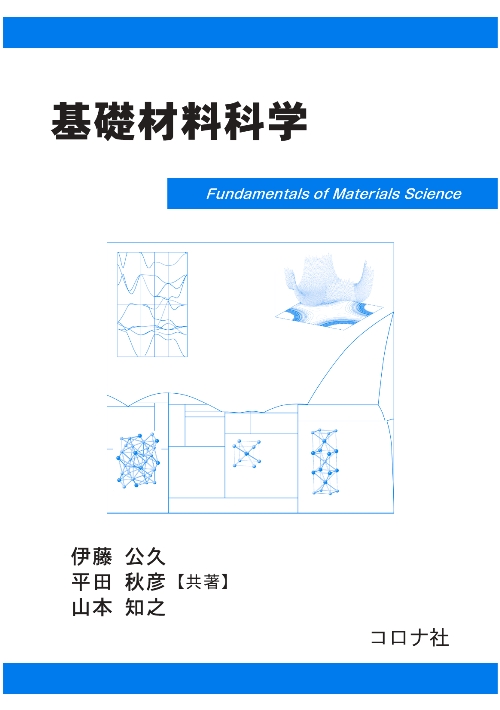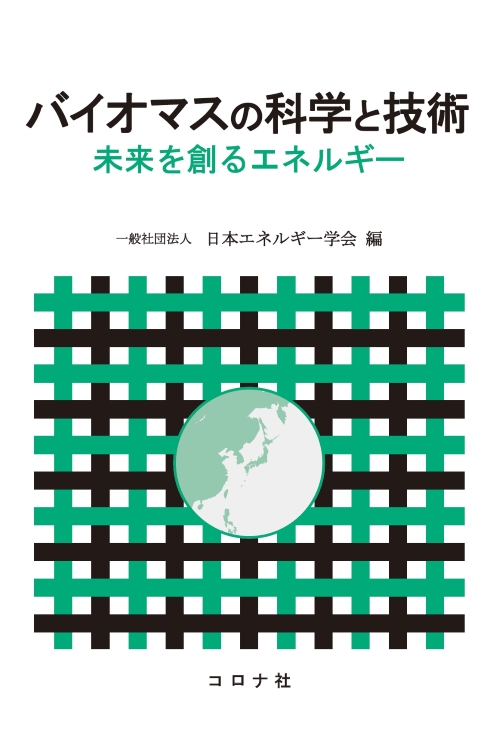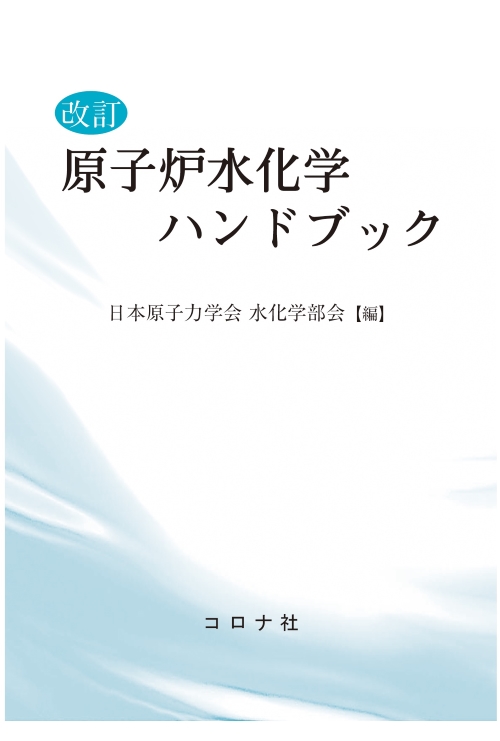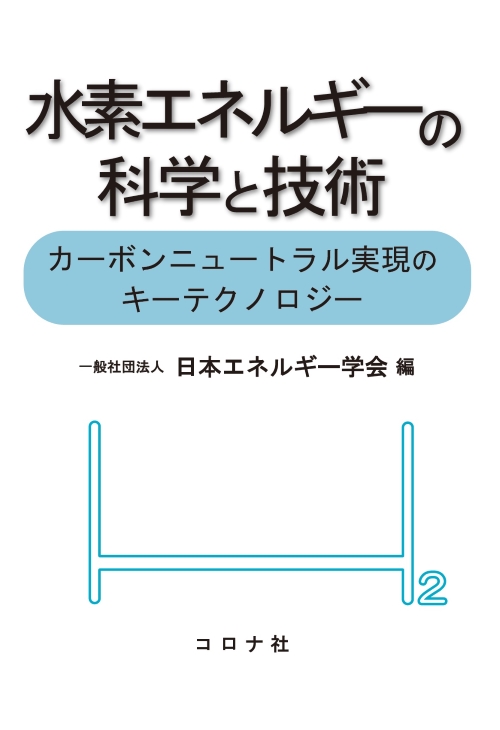
水素エネルギーの科学と技術 - カーボンニュートラル実現のキーテクノロジー -
水素エネルギーが安全かつ経済性をもって利用される社会を実現するために知っておきたい!
- ジャンル
- 発行年月日
- 2026/01/08
- 判型
- A5
- ページ数
- 260ページ
- ISBN
- 978-4-339-06676-0
- 内容紹介
- まえがき
- 目次
- 広告掲載情報
水素の構造から,金属材料中の水素の存在状態,エネルギーとしての水素,水素を含む物質の性能にも触れつつ,水素利用技術や水素製造技術も紹介した。また,水素を原料とする化学物質にも焦点を当て,その経済性の考え方にも触れた。
1970年代に発生したオイルショックを契機に,わが国ではサンシャイン計画と称して,環境問題の抜本的解決に重点が置かれたさまざまな研究開発がスタートした。当時の先進国を中心に水素をエネルギーとして利用する技術に注目が集まり,さまざまな要素技術開発が進められたのもこの時期以降である。わが国では1990年代からWE-NETプロジェクトとして研究開発が加速され,2000年代以降も継続してさまざまな水素エネルギー関連の国家プロジェクトが進められてきた。並行して2003年以降から数年おきに発表されてきたエネルギー基本計画では原子力発電の重要性が謳われてきた。しかし,2011年に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故により,わが国におけるエネルギー政策は大きく方向転換した。すなわち,2014年に発表された第4次エネルギー基本計画には,再エネ電力を重視するとともに水素エネルギーの利用の重要性が記載された。これに呼応したわけではないが,2014年暮れには水素燃料電池自動車が市場投入され,2015年はまさに日本国内において「水素元年」と称される年となった。その後の2018年に出された第5次エネルギー基本計画では,2100年断面でのカーボンニュートラル実現が明記され,水素・アンモニアの導入目標が具体的に記載された。しかし,欧州各国の批判を受け,2020年には「1.5℃目標」に準拠する「2050年カーボンニュートラル実現」を支持するエネルギー政策に方向転換した。本書を編集中の2025年において,再生可能エネルギー主力電源化を支えるグリーン水素のエネルギーとしての利用は既定路線となっている。
このように,わが国では国を挙げて水素エネルギー社会の実現に注力してきており高い技術力を誇る状況にある。しかしながら,学術界における水素エネルギー関連の研究は,さまざまな異なる学術背景を持つ研究集団により,さまざまな観点で研究開発が進められてきた。例えば電気化学分野では電解技術や燃料電池技術,触媒分野では水蒸気改質や光触媒,さらにはアンモニア合成やメタノール合成およびさまざまな炭化水素合成などの研究開発が進められてきた。加えて,材料分野においては水素貯蔵材料や耐水素脆化の構造材料,あるいは膜や吸着材による水素の高純度化技術,低温工学では液化技術や高性能な断熱容器開発,化学工学分野ではさまざまな注目系での最適利用など,それぞれの領域において局所的な最適解が求められてきたのも事実である。もちろん,学会の枠を飛び越えた研究連携は重要視されつつも,その取り組みは限定的であったと言わざるを得ない。
こうした中,本書はそれぞれの分野における専門書ほどの詳細な記述は省きつつ,それでも水素エネルギーの研究開発に,新たにかかわる技術者や研究者,あるいは水素エネルギー技術を専門に学ぶ初学者に対し,学術ミニマムを記した教科書として構成したつもりである(また各節の最後の項(7章は最後の節)では「おわりに」と題して,当該分野の今後の課題や展望について述べた)。そういう意味で,大学における教養レベルの物理学や化学で扱う水素原子および水素分子の構造から,金属材料中の水素の存在状態,熱力学や熱工学あるいは電気化学分野で扱うエネルギーとしての水素の取り扱い,さらには水素キャリアやエネルギーキャリアと称されるさまざまな水素を含む物質の性能にも触れつつ,当然ながら水素利用技術や水素製造技術の基礎的な考え方を盛り込んだ。また,水素を原料として作られるさまざまな化学物質や燃料などにも焦点を当て,その経済性の考え方にも触れた。内容は非常に多岐にわたるが,カーボンニュートラル実現において避けて通ることのできない水素のエネルギー利用が,理工系出身の教養として当たり前のように理解される時代になることを祈りつつ,本書が,「水素エネルギーを安全かつ経済性をもって利用される社会実現」の一助になれば,との思いで編集に携わったことをここに記しておきたい。
2025年11月
編集委員会を代表して
市川貴之
1.水素の基礎
1.1 水素の物性とエネルギーとしての水素
1.1.1 水素とは
1.1.2 水素分子の特徴
1.1.3 水素の化合物
1.1.4 エネルギーとしての水素
1.1.5 おわりに
1.2 金属材料の水素脆化
1.2.1 水素脆化研究の位置付け
1.2.2 水素の吸着から水素脆化破壊まで
1.2.3 水素分析方法
1.2.4 水素脆化破壊における潜伏期
1.2.5 水素脆化感受性評価と破壊形態
1.2.6 水素脆化理論
1.2.7 おわりに
引用・参考文献
2.エネルギーキャリアの概要
2.1 エネルギーキャリアの必要性
2.1.1 素材としての水素とエネルギーとしての水素
2.1.2 各種エネルギーキャリアの特徴
2.1.3 おわりに
2.2 液体水素
2.2.1 液体水素の特徴
2.2.2 水素の液化
2.2.3 液体水素の貯蔵・輸送
2.2.4 液体水素・冷熱の利用
2.2.5 おわりに
2.3 有機ハイドライド
2.3.1 ベンゼン環二重結合の安定性
2.3.2 エネルギーキャリアに用いられる有機ハイドライド
2.3.3 トルエンの水素化によるMCHの合成
2.3.4 メチルシクロヘキサン(MCH)の脱水素反応
2.3.5 おわりに
2.4 アンモニア
2.4.1 アンモニアの歴史とその特性
2.4.2 アンモニアの貯蔵
2.4.3 アンモニアからの水素放出
2.4.4 おわりに
引用・参考文献
3.固体貯蔵
3.1 水素吸蔵合金
3.1.1 水素エネルギーを貯蔵する水素吸蔵合金
3.1.2 水素吸蔵合金の熱力学的特性
3.1.3 水素吸蔵合金の種類
3.1.4 水素吸蔵合金と低圧水素
3.1.5 MHタンクの構成
3.1.6 おわりに
3.2 高圧水素
3.2.1 水素吸蔵合金による水素の高圧化
3.2.2 水素吸蔵合金の水素吸蔵特性
3.2.3 水素吸蔵合金を用いた熱で稼働するケミカルコンプレッサー
3.2.4 水素吸蔵合金を用いたケミカルコンプレッサーの開発の歴史
3.2.5 おわりに
3.3 無機系水素貯蔵材料
3.3.1 軽元素を用いる無機系水素貯蔵材料
3.3.2 無機系水素化物の特徴
3.3.3 水素化物
3.3.4 錯体水素化物
3.3.5 複合系
3.3.6 無機系材料を用いた水素の貯蔵/輸送
3.3.7 おわりに
3.4 吸着材料による水素貯蔵
3.4.1 吸着現象と水素貯蔵
3.4.2 物理吸着による水素吸蔵
3.4.3 吸着水素量の分析方法
3.4.4 さまざまな多孔質材料
3.4.5 液体水素温度における吸着現象
3.4.6 おわりに
引用・参考文献
4.化学変換
4.1 ギ酸
4.1.1 水素キャリアとギ酸
4.1.2 ギ酸の水素キャリアとしての特徴
4.1.3 ギ酸からのガス(水素+二酸化炭素)発生
4.1.4 ギ酸からの高圧ガス(水素+二酸化炭素)発生
4.1.5 高圧水素の精製方法
4.1.6 ギ酸による水素貯蔵
4.1.7 おわりに
4.2 メタネーション
4.2.1 メタネーションとは
4.2.2 メタネーションの課題
4.2.3 構造体触媒反応システムによるメタネーション
4.2.4 原料の高速処理を伴うメタネーション
4.2.5 実プロセス排ガスのそのまま高速処理:オートメタネーション
4.2.6 おわりに
4.3 カーボンリサイクル技術
4.3.1 カーボンリサイクルによる燃料合成の意義
4.3.2 フィッシャー・トロプシュ合成法による炭化水素の製造
4.3.3 メタン合成
4.3.4 メタノール合成および関連反応
4.3.5 おわりに
4.4 アンモニア合成
4.4.1 アンモニア合成法と利用
4.4.2 H-B法によるNH3合成
4.4.3 NH₃合成触媒
4.4.4 NH₃電解合成
4.4.5 おわりに
引用・参考文献
5.水素の製造技術
5.1 水蒸気改質による水素製造
5.1.1 水蒸気改質とは
5.1.2 メタンの水蒸気改質
5.1.3 メタノールの水蒸気改質
5.1.4 エタノールの水蒸気改質
5.1.5 グリセリンの水蒸気改質
5.1.6 おわりに
5.2 熱化学水素製造
5.2.1 熱化学水素製造の原理
5.2.2 熱化学プロセスによるさまざまな水素製造サイクル
5.2.3 高温太陽熱利用型熱化学プロセスによる水素製造サイクル
5.2.4 おわりに
5.3 再エネ電力からの水素製造技術としての水電解
5.3.1 再エネ電力からの水素製造の重要性
5.3.2 水電解の原理と効率
5.3.3 各種水電解技術の概要と課題
5.3.4 水電解の性能解析と低コスト化
5.3.5 おわりに
5.4 圧力スイング吸着法による水素精製
5.4.1 圧力スイング吸着法の原理
5.4.2 水素PSAプロセス
5.4.3 おわりに
5.5 膜分離による水素精製
5.5.1 膜による水素分離
5.5.2 水素生成を伴うプロセス
5.5.3 水素分離膜の種類
5.5.4 無機無孔膜と無機多孔膜
5.5.5 Pd膜およびPd合金膜
5.5.6 アモルファスシリカ膜
5.5.7 ゼオライト膜
5.5.8 おわりに
引用・参考文献
6.水素の利用技術
6.1 燃焼
6.1.1 水素燃焼の概要
6.1.2 燃焼速度と水素の特性
6.1.3 近年の水素燃焼技術の研究開発例
6.1.4 おわりに
6.2 固体高分子形燃料電池
6.2.1 固体高分子形燃料電池の普及状況
6.2.2 PEFCの構造・原理と材料
6.2.3 PEFCの性能と劣化
6.2.4 おわりに
6.3 固体酸化物形燃料電池
6.3.1 固体酸化物形燃料電池の特徴
6.3.2 SOFCの現状と課題,可逆動作セルへの展開
6.3.3 酸化物のH+伝導と酸化物プロトン伝導体燃料電池(PCFC)の開発状況
6.3.4 おわりに
引用・参考文献
7.水素利用の経済性
7.1 ネットゼロカーボンと水素エネルギー
7.2 国内における水素・燃料電池の現在地
7.3 水素利用の将来の姿
7.4 競合技術からみた水素利用の将来
7.5 経済性からみた水素製造の着手例
7.6 おわりに
引用・参考文献
索引
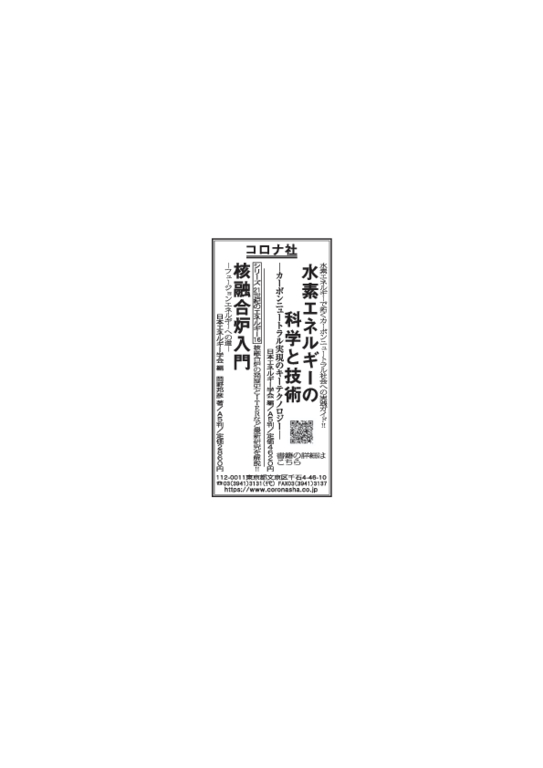
-
掲載日:2026/01/05
関連資料(一般)
- 図6.8のカラー画像