レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
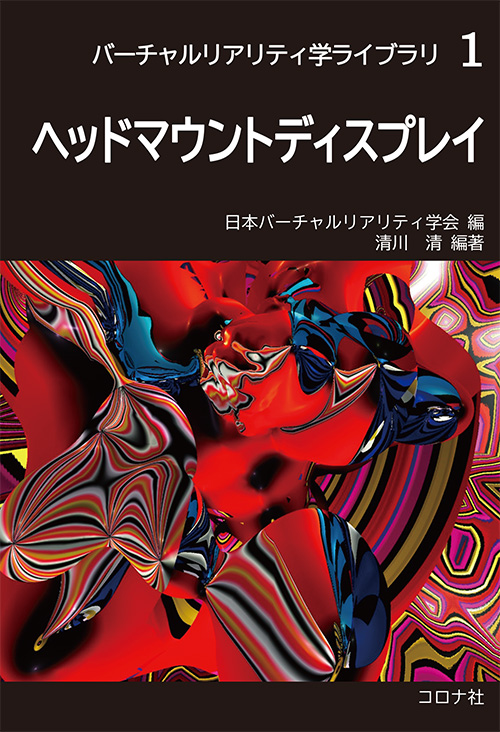
-
ヘッドマウントディスプレイは,VRやARを実現するための代表的なデバイスである。多種多様なHMDの違い,選択基準,性能や機能の進化,進化に伴う生活や社会の変化など,HMDを網羅的に取り上げた初めての書籍である。
- 発行年月日
- 2024/10/07
- 定価
- 4,180円(本体3,800円+税)
- ISBN
- 978-4-339-02691-7
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 N/M 様(業界・専門分野:総合情報学[情報科学])】
掲載日:2024/10/01
本書は「バーチャルリアリティ学ライブラリ」の1巻目に位置する書籍である.本巻では,特に「HMD (Head Mounted Display;ヘッドマウントディスプレイ)」に関連して基礎から最新の研究事例まで幅広い解説がなされている.
まず,本書の特徴としては,まえがきにも記載されているが,『HMDに関する話題を網羅的に取り上げた初めての書籍である』という点である.こういった特定の分野について,網羅的に取り上げた初めての書籍という記述を目にすると,私自身,そういった書籍が出版された時代に出会うことができた,という特別感みたいなものを特に感じる(余談ではあるが,過去のレビューでも挙げたが,学生時代(2009年頃)にも,情報科学技術の応用例として教育工学の分野で何かと話題のブレンディッドラーニングに関する,日本における研究成果を取り入れた,日本で初の書籍にも出会ったことがある).そういったご縁みたいな感情がわき,いつも以上に丁寧に拝読させていただいた.
1章では,ヘッドマウントディスプレイ(以下,HMD)の概要として,HDMの歴史やいろいろなHMDについての記述がなされている.頭部に何かを装着して見え方を変化させようという考え方自体は,大昔からあったようで,虫眼鏡(ルーペ)のような光学レンズや視力の補正用にメガネといったものがそれに該当する.興味深いのは,18世紀にはメガネ屋というものが浮世絵に描かれ,大衆向けの読み物に「掛けた人が見たいものを何でも映し出すメガネ」という,今で言うところのVRやARを連想させるような内容が記載されている点である.
4章〜6章では,HMDに関連するさまざまな最新研究の事例が取り上げられている.個人的に興味深かったのは,5章の視覚の開放として,視力の補正・矯正や,実際に目に関連した疾患などで不自由している方々の視界をシミュレーションするといった単にエンタテイメントの分野だけでなく,医療の分野にまでHMDが活用できる事例には大変興味深いものがあった.
他にも6章のHMDを用いた多感覚情報提示の味覚や食体験の提示をHMDを用いた事例である「おばけジュース」,「メタクッキー」,「拡張満腹感システム」なども興味深かった.特に,「拡張満腹感システム」では,健康面でのダイエット効果にも一役買いそうだなと思った.また,本書にも記述があるが,実際に自身が食べているものがどのようにして身体に取り入れられていくかという大人だけでなく子どもへの食育教育にもHMDの可能性を感じた.
また,あとがきには,電気的な信号に変換して,視神経に刺激を与えることによる可能性も挙げられている.神経刺激による事例を深く知りたい方は,本シリーズの2巻目に位置する書籍である『神経刺激インタフェース』もぜひ読まれることをオススメする(こちらも,拙い文書ではあるが,私がレビューをさせていただいている).
-
読者モニターレビュー【 りん 様(業界・専門分野:IT関係)】
掲載日:2024/10/01
他のVR関連書籍が必須ではなくこれ単体である程度完結しており、また他関連書籍よりも深掘りされている分、HMDの仕組みや開発に関する実用的な知識を得ることができた。
HMDやソフトウェアをを開発する際の問題点や、問題解決の方向性などを具体的に示しており、VR等を使用する際の背景技術から現実空間と仮想空間との差異が開発の問題となるときに、解決策を見出すきっかけにすることができそうだと感じた。
特にコンシューマ向けというよりは業務向けの正確性をある程度求められるようなソリューション開発する際、気をつけるべき基本的な要素を本書を読めば理解できそうだと感じた。
また、ヘッドマウントディスプレイの仕組みや用途、将来こうなっていくであろうという形について本書を読み進めていくうちにイメージが形成され、個人的にワクワクした。
-
ゲームメーカーズ 様による本書プレゼントキャンペーン
掲載日:2024/09/11
詳細はリンク先をご覧くだ。
記事題名:「HMD」にのみフォーカスした解説書籍『ヘッドマウントディスプレイ』、9/19(木)にコロナ社から発売









