レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
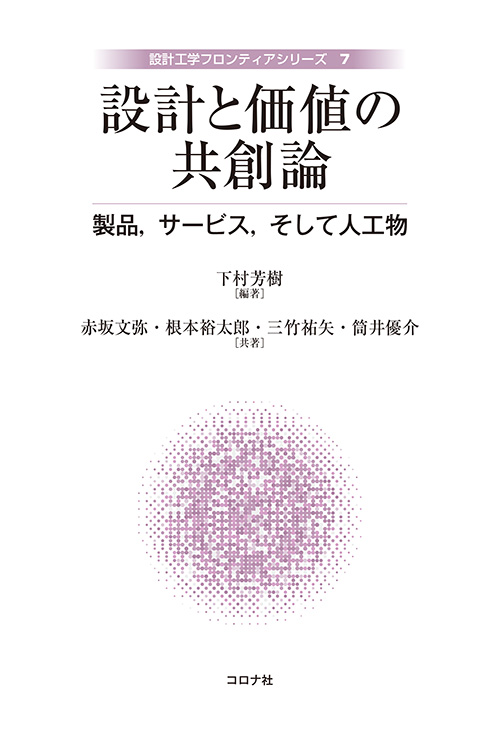
-
本書は,価値の概念を中心に据えつつ,科学・工学・設計の関係と,設計における人の思考の特徴を整理し,関連する既存の設計工学分野における最新の動向に広く言及することにより,理念的設計への架橋とすることを意識した。
- 発行年月日
- 2024/07/22
- 定価
- 3,960円(本体3,600円+税)
- ISBN
- 978-4-339-04707-3
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
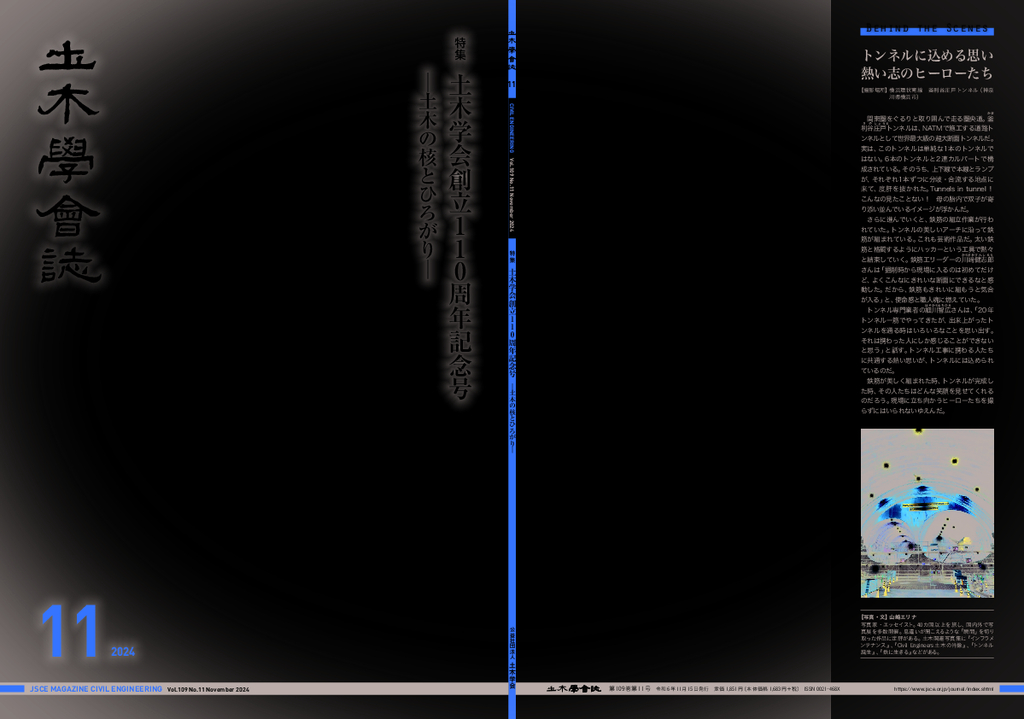
-
「土木学会誌」2024年11月号
掲載日:2024/11/11
「新刊紹介」欄 (p.63) にて掲載いただきました。
【表紙】土木学会誌,2024年,109巻(11号),撮影 山崎エリナ © Japan Society of Civil Engineers
-
【書評】産業技術総合研究所 フェロー 持丸正明 様
掲載日:2024/08/20
企業の方々と話をすると、機能や性能ではなく価値を創り出さなければならない時代なのです、とよく言われる。本書は、そのような価値創出の時代を乗り切らなければならない企業実務家に是非とも読んでいただきたい。そもそも、「価値」とはなんであるのか、その学術的系譜も時代的変遷も実に簡潔明快にまとめられている。「価値」の定義も知らず、ただ創り出せと命じている上司への回答に向け、本書はしっかりとした考え方の基盤を与えてくれる。その上で、「共創」「設計」「イノベーション」という価値創出のためのバズワードも、体系的に整理して位置づけてくれている。もしかすると、実務家の方は本書前半の学術的、体系的な整理が苦手かもしれない。心配せず、その場合は、前半を斜め読みしていきなり第6章あたりから読んでみることをお薦めする。実は、本書後半には、共創やイノベーション、さらに創造性を産み出す方法論が、具体的、網羅的に書き込まれているのである。本書が学術書にとどまらず、実務家にも役立つ手引き書でもあるというのはここである。
さて、もうひとつ、本書の魅力は第9章の「価値と時間軸」にある。VUCAと呼ばれる予測困難な時代において、価値の時間軸をどう描くのか、その答えは読者の皆さんがそれぞれに探すものであるが、本書第9章ではその時代に向けたさまざまな知恵と思いが語られている。製品・サービスの価値がクラスIII型の共創型価値にシフトしてきた頃から、VUCAは始まっていて、下村先生らのチームは誰よりも早くこれに挑んでこられたとも言える。だからこそ、本書第9章には、予見困難な未来の価値に対応できるよう製品・サービスをどう設計しておくべきかの苦労と夢が詰まっているように感じた。
学術書だと思わず、実務書だと思って是非とも手に取っていただきたい。下村先生の講演を聴かれてなんとなく分かった気になっている方々にも強くお薦めする。講演と違って書籍はなんどでもページを戻り、自分が理解できるまで確認できるのだから。
-
【書評】東京大学人工物工学研究センター センター長 高橋浩之 教授
掲載日:2024/08/19
本書「設計と価値の共創論」は人工物工学の系譜をたどりながら、筆者らが取り組んできた共創の視点を織り交ぜ、現代の設計の全体像を俯瞰し、将来の設計の在り方を提示したものであり、野心的な試みをコンパクトにまとめられた貴重な書である。本書ではまず、人類史における人工物の誕生から、その変遷を辿り、サービスなど無形のものも人工物としてとらえ、そのときどきの社会を変革させることにつながったような、人による創造の歴史を示すとともに、人工知能・ロボット・宇宙開発など今後の更なる発展を見据えて、社会との関連を捉えつつ人工物の設計の重要性を説いている。次に、価値について、本書では設計との関連から、哲学の領域にも踏み込み正面からとらえた議論を展開した上で、工学的な価値・価値共創の概念を提示している。一方、設計については、通常用いられている工学設計の考え方と手法から始め、一般設計学の内容を紐解いた上で、設計とabductionによる創造~創造的設計支援まで詳細に論じている。Universal Abduction Studioなどの設計支援システムとLLMによる拡張の可能性については、今後の展開として興味深い。なお、abductionについて、初学者向けにもう少し解説があるとよいと思われる。その後、サービスの価値と設計について議論がなされ、無形性・消滅性などモノとは異なる特性を有するサービスを人工物として捉えた設計論が展開され、ペルソナ・シナリオなどを用いたサービス設計のための方法論が紹介されている。さらに著者らは共創の設計論に踏み込み、人間中心設計・参加型デザインなどを紹介した後に、共創のためのpattern languageやリビングラボなどの具体的な手法を提示している。これらの設計に関する考え方と方法論を踏まえた上で、システムと設計の全体像を示し、製品サービスシステム(PSS)などの具体的な描像を与えるとともに、システムズエンジニアリングなどのアプローチとそれらを適用して作られるシステムの社会に及ぼす影響までを記述している。本書ではまた、価値と時間軸の章を設けて、シナリオプランニングやトランジションマネジメントなどの時間軸マネジメントの手法を示した上で、時間軸を考慮した設計のあり方についての議論を展開している。終章である価値設計のフロンティアにおいては、人工物が人の欲望を満たすように設計されてきたことが現代の邪悪の原因になったと指摘し、プラトニックデザインに向けて規範を持ち込むことがその解決になることを述べ、規範は共感を通じて醸成されると、筆者らの高い精神性を示している。
各国が自国の利益を追求するあまり、対立が深化し、不安定化しつつある昨今においては、ともすれば新たな現代の邪悪を創出しかねない状況であるが、哲学の世界に踏み込んで価値を真摯に論じ、真に優れた設計のあり方を追求した本書自身の価値もまた、30年以上にわたる人工物工学研究の一つの成果を示すものとして大変貴重なものと考えられる。
-
【書評】神戸大学 大学院システム情報学研究科 システム情報学専攻 貝原俊也 教授
掲載日:2024/07/29
設計工学とは、一般に、製品やシステムの設計プロセスを、科学的および技術的な観点から研究し最適化する学問分野として捉えられる。そしてこれらは、どのように創るべきかという科学的問いに関する方法論として位置付けられる。ここで設計の本質は、冒頭の前書きにもあるように、なぜそれを創るのか、また何を創るべきか、という人の思考に根付いた「価値」の概念と深く結びついたものであり、これは工学の範疇を超えていることから、従来の設計工学では積極的に取り扱われてこなかった。しかし、人間中心の社会実現に向け、今や設計において価値を論じることの重要性が認識されるようになっている。このような時代の要請を受け、本書「設計と価値の共創論」は、設計の本質と理想について、価値に対する哲学的な論考を踏まえ総括するという極めて野心的な内容を取り扱っている。このように聞くと難しく思えるかもしれないが、本書では、今後の社会にふさわしい設計を可能とする人材育成を目指し、設計の類型紹介から始まり、人の思考の特徴整理や、現代社会における価値論について、設計の視点から分かりやすく紹介している。またその実用化の例として、サービスの設計や社会システムの観点からの現状と今後の可能性についても示されている。
以上のように、本書は、多くの技術者にとって、今まであまり語られてこなかった設計の本質を理解することができる極めて価値の高い良書である。
-
読者モニターレビュー【 みた 様(業界・専門分野:ウェブ開発)】
掲載日:2024/07/18
本書は幅広い設計手法やその考え方を知りたい人にお勧めします。
1~3章ではモノづくりにおける設計や設計物(プロダクト)の価値がどのように考えられてきたか、工学のみならず歴史・哲学の観点からも多様に論じられています。
4~8章はさまざまな設計開発手法について整理され紹介されています。
9~10章は筆者人らによる今後のものづくりとその価値創造の在り方について1~8章をまとめつつ、提言している内容でした。
私自身は工学系大学出身かつ製造業に従事していたこともあり、設計開発手法に関しては既知の内容が多かった部分はあります。また、その内容に関しても扱われ方がやや古いものもあり、あまり現場をご存知でないのかなと思える記述もありました。
一方で、哲学の観点からものづくりやモノと人とのあり方を論じている本はあまりなく、本書はそういった点から評価できる部分が多々あると思います。
特に、人間とプロダクトがどのように共生してきたのか、そしてプロダクトがどのようにあるべきなのかといった提言部分は、非常に読み応えがありました。
私自身は歴史分野・哲学分野にはめっぽう疎く、非常に興味深く読めました。そうした内容は設計に関わる社会人のみならず、学生さんにとっても、勉強になる点が多いと思います。
-
【書評】村上輝康 様(産業戦略研究所代表)
掲載日:2024/07/08
「価値」を、人の欲望を満たし、人に満ち足りる感情をもたらす効果の概念とし、「設計」を、価値を満たすうえで有用な人工の働きを実現する手段を考察し、それを人工物として実現すること、と定義して、設計論の枠組みの中で、価値を真正面から工学の対象にしようとする野心的な快著である。工学や設計の世界が、主観の入る取組みにならざるを得ないため、可能な限り避けてきた「価値」の議論を、「設計」がもたらしたかもしれない「現代の邪悪」の蔓延が、実学を志向する「設計」に鋭く突き付けている社会からの問に、主著者の下村芳樹(以下、下村)は、半世紀に亘る人工物研究の蓄積を武器に、4人の道連れとともに挑もうとしている。
下村は、幼い頃から、「なぜこれ(人工物)は存在するのか?」「なぜこれは必要なのか?」という根源的な問いを持ちつつ、玩具をつぎつぎにバラバラに分解することで、答えを求めようとしていたそうである。そのようにして感じたモノの存在の意義や必要性に対する「違和感」を、下村は捨て去ることなく育て続け、設計工学、設計学、設計論の研究生活の中に持ち込んでいったという。
本書は筆者には、下村が、その「違和感」から出発して、吉川弘之という日本を代表する設計研究者と出会い、その問いに人工物や設計研究という経路を通じて応えようとした、壮大な人生をかけたオデッセウスの航海記に見える。
その航海においては、今は亡き上田完次とともに価値の変遷をたどり、設計の形態とアブダクションについて小括し、サービスドミナント・ロジックの影響を受けて、共創の設計論を展開する。そして、Geelsから学んで、日本におけるレジームとニッチイノベーションの実存的な共進化に、ランドスケープが後追い的に引きずられていく構造を喝破するが、その航海は、価値と時間軸についてのオリジナルな考察によって最高潮に達し、時間軸設計に対する強い期待をもつに至る。そして、オデッセウスの帰還の最終寄港地となるのは、プラトンに再帰した「理念的設計(プラトニックデザイン)」であり、その実現にむけての、オリジナルなプロセス規範である。
その航海においては、下村が次々に問いを発し続けるが、本書は、その問いに直接応えようとするよりも、それらの問いに対して応えようとした既存の方法論や手法を幅広く渉猟するという方法をとっている。このため本書は、プラトンからカント、ハイデッガーを経て、ウィトゲンシュタイン、パース、吉川まで、ブレインストーミングから、一般設計論を経て、サービス工学、トランシジョンマネジメント、リビングラボまで、設計論の枠組みで価値を研究しようとする時に参照されるべき方法論や手法の、ほとんど全てを尽くして体系化するものともなっている。快著たる所以のひとつである。
実は筆者は、「設計と価値の共創論」という著作を手にして、あるシリアスな問題意識をもってこの著作を読んだ。今、筆者は、第5回の日本サービス大賞の審査活動に入ろうとしているが、本書が、優れた価値の設計をしているサービスイノベーションを探索し評価する際の、新たな羅針盤を与えてくれるのではないか、という実利的な問題意識である。
筆者は、可能な限り科学的に審査をするという意図のもと、それに価値共創のサービスモデルを唯一の拠り所として取り組んでいる。おそらくひとつ上のレイヤーで「価値の共創論」を展開する本書が、強力な実効的な示唆を与えてくれるのではないかと期待したのである。
その期待に対しては、結局、手触り感のある形で筆者を牽引してくれる方法論を獲得することはできなかったが、何故できなかったかを考えることで、本書のアプローチの特徴を理解することともなった。
価値共創のサービスモデルでは、サービスの提供者たる企業と利用者たる顧客という二つのアクターが、知識とスキルの粋を尽くして共創しようとする系の中で価値共創を考えているが、本書においても特に第6章「サービスの価値と設計」以降でこの構図が頻繁に扱われる。
しかしながら、そこには常に「設計者のまなざし」があまりに横溢しており、筆者には、企業と顧客という構図は、設計者と設計対象という構図の中に埋もれてしまっているように思えてならないのである。
本書には、下村の薫陶を受けた、赤坂文弥らの若い研究者も参加している。私には、設計論の研究者というよりもサービス学やサービスデザインの研究者にみえる人たちである。彼らには今後、本書において下村が道筋を創り上げた「設計論における価値研究のフロンティア」を拓いていくとともに、サービス学やサービスデザインにおける「価値」研究に真正面から立ち向かって、最終的には、実務に役立つ方法論を打ち立てて欲しいと思うのは、筆者の我儘があまりに過ぎるであろうか。









