レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
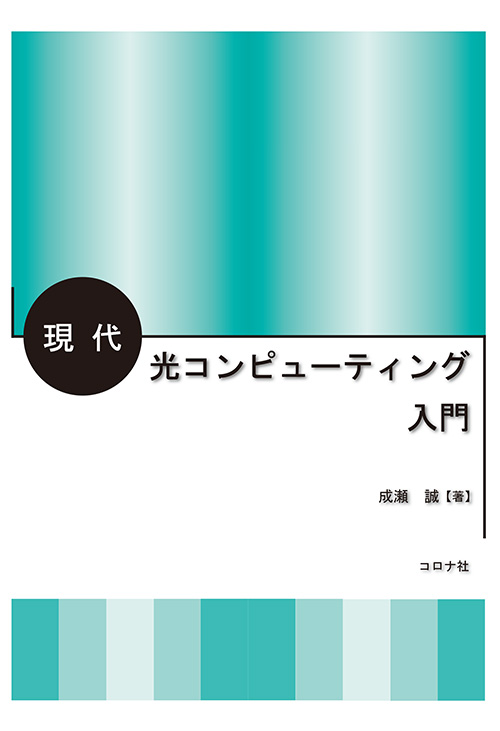
-
今後の情報社会を支えるであろう現代の光コンピューティング技術について,基礎から先端技術までを速習する。物理的な側面「光」と情報学的な側面「コンピューティング」を織り交ぜつつ話を進め,研究の最前線になじむことを目指す。
- 発行年月日
- 2024/05/07
- 定価
- 2,640円(本体2,400円+税)
- ISBN
- 978-4-339-02941-3
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 N/M 様(業界・専門分野:総合情報学[情報科学])】
掲載日:2024/04/22
本書は,物理学(光)と,情報学を合わせた「光コンピューティング」という技術について書かれた入門書である.個人的には,光とコンピュータとの関係でまず思いつくのが,ネットワーク通信において光ファイバを用いている,という理解であったのが正直な感想だった.
本書は,全4章で構成されており,1章では,光コンピューティングを学ぶ上で必要となる光に関する基礎知識が概論的に解説されている.
2章では,コンピューティングの基礎として,従来の技術とアーキテクチャ革新の必要性として,光コンピューティングや量子コンピューティングなどの「物理系の特徴を活かす」という視点が必要になるという議論になり,本書のメインテーマである3章の現代光コンピューティングの話に繋がっている.個人的には,ムーアの法則や,フォンノイマンアーキテクチャ,シャノンの定理,AIなど,情報科学の分野でもおなじみの用語も登場し興味深かった.
3章では,現代光コンピューティングに関する研究例が数多く詳細に紹介されている.個人的には,特に3.4節の強化学習や意思決定,3.5節の粘菌コンピューティングから光コンピューティングについて,AI技術や意思決定,生物の粘菌など,自身の注目している技術と,粘菌コンピューティングという意外性のある研究もされており,大変興味深く拝読させていただいた.
最後の4章では,さらなる発展に向けてということで,これまでの章で述べられてきたことを振り返りつつ,「光の極限性能を生かすフォトニックコンピューティングの創成」という研究プログラムにおける方向性として3つの視座及び,それらに対応した3つの研究柱を設定し,研究に取り組んでいる,という形で締め括られている.









