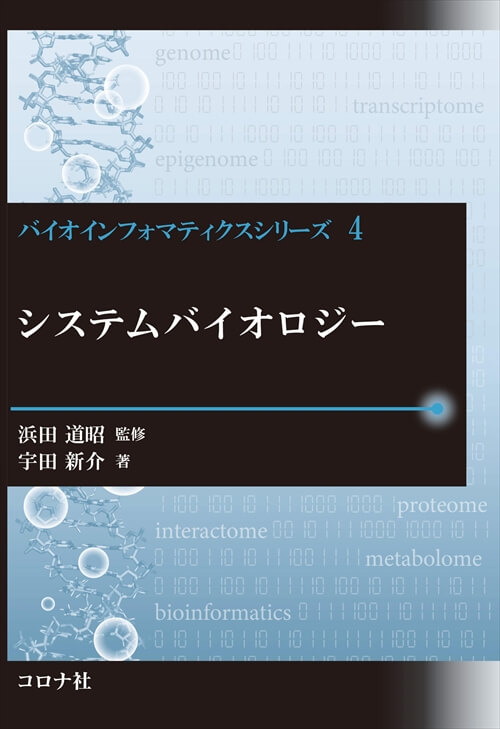レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
- 発行年月日
- 2022/11/17
- 定価
- 3,300円(本体3,000円+税)
- ISBN
- 978-4-339-02734-1
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 EN 様(ご専門:進化生物学・バイオインフォマティクス )】
掲載日:2022/11/14
以前からシステムバイオロジーという概念を知っていたものの、具体的にどのような数理モデルが用いられているか、このような学際的な分野を学ぶために何から学べば良いか分からない状態であった。そのような私にとって、本書は基本的な数理モデルとそのモデルに必要な数学的手法などの一連の学習の道筋を示してくれた。また、本書は実践よりも理論の学習に重きを置いており、腰を据えて読む必要があると感じた。
第1章では、生化学反応をモデル化したいくつかの例を示している。この例は後々の章で何度も参照するため、生化学的経路の図などを手元に置いて、数式と生命現象を紐付けながら各章を読み進めるのが良いと思う。第2〜5章は、常微分方程式、ラプラス変換、フーリエ変換、ベイズ統計などの背景知識を必要とする。これらの章のモデルはある程度、生化学反応の知見が蓄積しているモデル生物を扱う読者に特に有用かもしれない。一方、6章では線形代数を背景知識とした、部分最小2乗回帰モデル等を扱っている。このモデルでは刺激と応答のみからモデルを構築できるため、生化学反応の知見に乏しい生物を扱う読者の研究に活かせるかもしれない。情報理論を応用した細胞の情報伝達に関して述べている第7章では、20世紀のシャノンの情報理論の基礎や比較的最近の1細胞レベルでの解析の参考文献が紹介されており、キャッチアップに役立った。生命をシステムとして分析する研究者だけでなく、生命システムを理解して再構築する合成生物学学者などにも有用な一冊であると思う。
-
読者モニターレビュー【 こんがり@創薬 様(ご専門:創薬研究 )】
掲載日:2022/11/14
システムバイオロジーに関して体系的に学べる書籍は新しいものがなく、新たな参考書の登場を待望していた。
システムバイオロジーは、生命科学系研究者であれば一度は耳にしたことあると思うが、その概念が抽象的でイメージしにくいという人も多いのではないだろうか。本書では、1章でシステムバイオロジーについて「生物システムを数式化すること」と具体的に定義しており、はじめにその曖昧さが排除されることでスムーズに読み進めることができる。 続く2章-4章では、システムバイオロジーの基本となる常微分方程式モデルといった具体的な理論を数式を交えて説明してあり、各モデルの基本的な概念を学ぶことができるし、数式を追うことでその理解はより深まるよう構成されている。個人的には、これまで生化反応を濃度論で考えることが当たり前と思っていたが、4章での確率論で生化学反応をモデル化する考え方は、新たな気付きを得るとともに非常に腑に落ちるもので、今後の研究の参考になった。
5章以降は、実験データからモデルのパラメータを推定する方法について詳細に記載してあり、より実践に近い内容である。概念・知識を学んだだけでは、いざ実践しようとするとどうすれば良いか分からず、行動できないことも多い。その点本書は、知識習得だけで終わらせず、学んだ内容を自分の研究に昇華させることができるよう構成されており、これからシステムバイオロジー研究をはじめたい研究者にとっては最適であろう。
このように、本書は概念・知識の習得から実務までシステムバイオロジーを体系的に学べる良書であり、初学者やこれからシステムバイオロジーをはじめる研究者にとって、常に手の届く場所に置いておきたい書籍である。
-
読者モニターレビュー【 ずみ 様(ご専門:がん免疫治療、ベイジアンネットワーク、予後予測解析 )】
掲載日:2022/11/14
システムバイオロジーというとまずは微分方程式によるモデル化を思いつく人が多いだろう。自分もこの本が届くまではその印象しかなく、実際に本書の前半では簡単な微分方程式の表現から始まりフィードバック機構の表現などが簡潔に、しかし自分のような初学者でも理解できる範疇で記述されている。高校化学で学ぶ微分方程式や化学平衡の理論さえわかれば読めるようになっているのがとても有難い。しかし本書の特徴は後半部分にあると思う。ベイズ法によるパラメータ推定や線形モデルとそのモデル選択手法の解説に限らず、特に類書では取り上げられないような部分最小二乗法についても触れているという点で現代の”データサイエンス"と呼ばれるような手法についても広く解説されている書籍と解釈することもできることから読者層が極めて広い本ではないだろうか。また、最後には情報理論的アプローチについても解説されている。情報をエントロピーを持つものと考えて熱力学的に表現する手法にもつながる内容であり、カバーしている範囲の広さに驚かされた。
-
日本バイオインフォマティクス学会ホームページ
掲載日:2022/06/16