レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
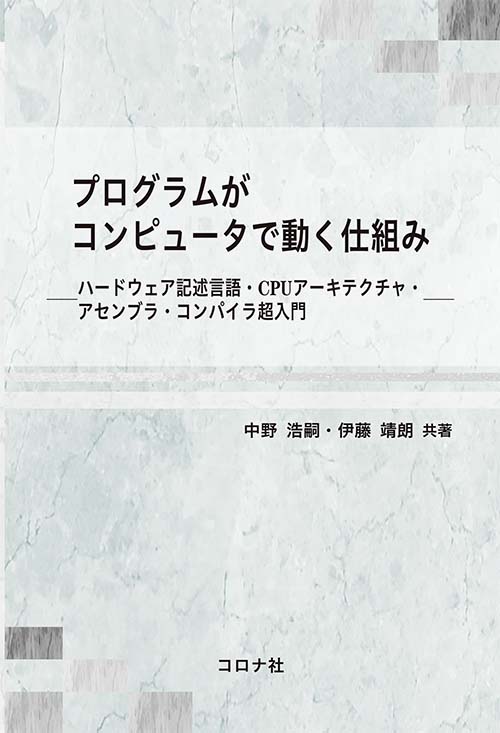
-
プログラムがコンピュータで動く仕組み - ハードウェア記述言語・CPUアーキテクチャ・アセンブラ・コンパイラ超入門 -
本書の目的は,プログラムがどのような仕組みでコンピュータで動作するのかという疑問に簡潔に答えることである.そのためにVerilogを用いて小さなCPUを設計し,それをターゲットとするアセンブラとコンパイラを作成する。
- 発行年月日
- 2021/11/25
- 定価
- 2,860円(本体2,600円+税)
- ISBN
- 978-4-339-02922-2
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
読者モニターレビュー【 diohabara 様(ご専門:プログラム合成)】
掲載日:2021/12/06
プログラムがコンピュータで動く仕組みを学ぶために、CPU、アセンブラ、コンパイラを作る。良い点と悪い点があり、それぞれ話す。
良い点はこの本を読めばどのような流れでプログラムが動いているか分かる点、演習問題があり内容を深く理解できる点だ。字句解析、構文解析を除くと0から実装しており、プログラミング言語を書いた経験がある人ならば本書のサンプルコードを書きながら手順を手元で確認できるだろう。演習問題も付いており、理解を深めたい人にもおすすめである。
悪い点は情報が詰め込まれ過ぎている点、ツールの選定だ。186ページにコンパクトに情報を詰め込んだ負の影響で、箇条書きがあまり使われてなく読む際の認知負荷を大きく感じた。また、選定したツールであるVerilog、Perl、C、Flex、Bisonが現代の若者として多少苦労するのではないかと思った。もっとも、これは杞憂かもしれない。
全体としてよくこの内容を一冊にまとめたと感じた。実際に本書を手に取り、手を動かすことで確認してほしい。
-
読者モニターレビュー【 H. I. 様(ご専門:無線)】
掲載日:2021/11/11
本書は、ソフトウェア開発、アプリケーション開発といった抽象度の高い上位レイヤ設計が流行っている現代において、ハードウェアに近い下位レイヤの重要性を再認識させてくれる書となっている。
1,2章ではハードウェア記述言語であるVerilogを用いた基本的なデジタル回路の設計法を丁寧に説明している。デジタル回路に馴染みのない方でも比較的理解しやすい構成になっている。3,4章では1,2章で設計した複数のデジタル回路を組み合わせて必要最低限の機能を持つCPU (Tiny CPU)を設計している。実際にCPUを設計することでコンピュータの動作原理がイメージできるような構成になっているといえる。
そして、5,6章では簡易なC言語 (Tiny C)で記述したプログラムをアセンブリ言語へと変換し、実際にプログラムがCPU上で動作する仕組みを理解することができる。
最後に、7章ではコンパイラを設計し自動でC言語をアセンブリ言語へと変換する仕組みが丁寧に説明されている。
本書は、アセンブリ言語までは理解しているけど、それが実際にCPU上でどのように処理されているか分からない方にはおススメの書となっている。また、ハードウェアとソフトウェアの関係性を理解する上でも貴重な書である。









