レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
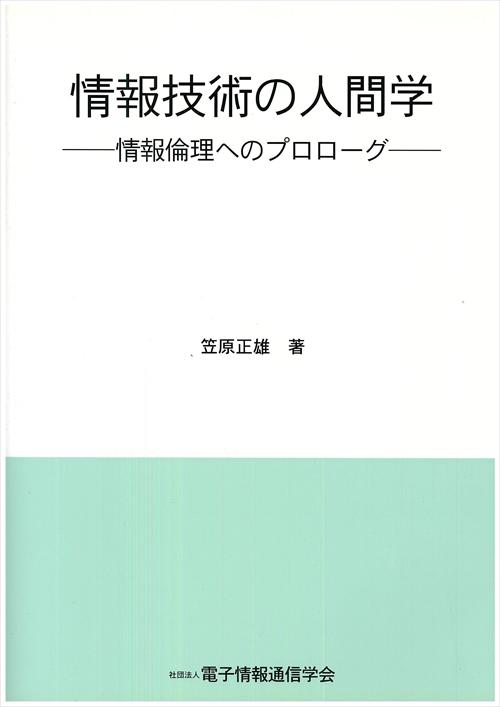
-
一般的なインターネットを背景としたコンピュータ犯罪,著作権侵害などの事例紹介や関連する法律の解説ではなく,よりベーシックな立場に立って,過去一世紀以上の電気系関連学問の発展に軸足を置いて,「情報倫理」を解説した。
- 発行年月日
- 2007/02/20
- 定価
- 2,860円(本体2,600円+税)
- ISBN
- 978-4-88552-219-2
レビュー,書籍紹介・書評掲載情報
-
「電子情報通信学会誌」 2007年11月号
掲載日:2007/12/20
電子情報通信学会誌に、下記の書評が掲載されました。
※当書評文は、電子情報通信学会ならびに書評執筆者の方の許可を得て掲載しております。
近年各方面において「倫理」を守ることの重要性が再確認されている。特に,情報化社会においては,インターネットを使ったコンビュータ犯罪や著作権侵害などが間額となり,それを防ぐために「情報倫理」の教育が子供のうちから必要とされている。
本書はこのような「情報倫理」とは少し異なり,より基本的な立場で技術に対する人間のあり方を述べたもので「情報論理へのプロローグ」となっている。近年目まぐるしく発展した電子情報通信技術には,私たちの生活に恩恵をもたらす光の面があると同時に,犯罪や障害をもたらす彰の面がある。この電子情報通信技術の光と影,及び影への対処法について,本書は豊富な歴史的事実や身近な例を用いて分かりやすく解説する。
本書は三つの部分からなる。 Part 1は「技術と人間」と題し,技術の本質と人間とのかかわり合いを技術史の流れの中で述べている。特こ,ギリシャ時代のプラトンやアリストテレスの技術観に始まり,ドイツ・ルネサンス時代の鉱山学者アグリコラとローマ時代の建築家ウイルトルーウイウスの姿勢を通し,情報技術者には,人間の本質を問う姿勢が必要であることを述べる。
PartⅡは「情報技術の人間学」と題し,ここでは情報技術と人間のかかわり合いを人間の生物学的視点を取り込んで解説している。まず,情報社会を支える情報通信技術について簡単に解説し,情報技術の倫理について言及する。更に,人が乳幼児期こおいていかにコミュニケーション能力を培っていくかを説明し,情報通信技術や最先端IT機器がこの乳幼児のコミュニケーションに影をもたらす可能性があることを述べる。
最後のPartⅢは、「コンテンツ,そして技術」なる題目で,コンテンツの変遷とその社会への影響,コンテンツの保護について述べている。ここでは、P2Pファイル交換ソフトや違法コピーによる著作権侵害の問題や,それを防止する技術も紹介されている。更に、倫理を伴った情報技術が切り開く未来社会の可能性について言及している。
全般的に,歴史上の人物のエピソードや乳幼児の例を取り上げ,多くの人に読みやすく書かれている。学生にもお勧めの一冊である。
(荒川 薫先生 明治大学理工学部情報科学科)
「電子情報通信学会誌」Webページはこちら









